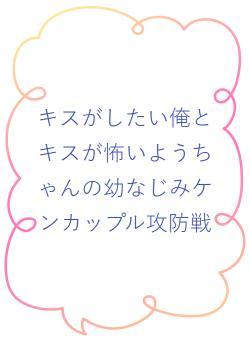体育祭終了後、クラスメイトに打ち上げに誘われた。カラオケにいくと言うのでパスしようとしたが、音無を誘いたいから俺と下野にも来てほしいと女子に懇願されたのだ。真中はいつの間にか帰っていて、一応打ち上げのことをラインしたら、『寝る』と一言返ってきた。
ドリンクバーの機械にグラスを置いてメロンソーダのボタンを押す。シュワッと炭酸の混じったジュースが注がれて、パチパチと小さな気泡が弾ける。ぼんやりとそれを見つめながら、ため息がこぼれた。
どうして急に音無のことを見れなくなったのか。音無を見ていると、胸がドキドキして身体が熱くなる。話しかけられると、鼓動は速さを増し喉が渇いてうまくしゃべれない。
(どうしたもんか……)
「なぁ、おまえもしかしてーー」
右肩をつかまれて声をかけられた。振り向くと、他校の生徒が二人いた。
「やっぱり! 瀬川だ!」
「……だれ?」
「忘れたのかよ! 中学の同級生の顔!」
「……あっ」
(思い出した! いじめをしていた三人の内の一人だ。名前はわからないけど)
「こいつのせいで、俺の友達が不登校になったんだ」
「友達? いじめてたじゃねぇか」
「は? なに言ってんの? ふざけてただけだろ」
こいつの態度から、反省している様子は全くみられない。ふつふつと腹の底から怒りが湧いてくる。
「いじめとおふざけの区別もつかねぇのかよ」
「相変わらずだな。無駄に正義感ふりかざして、ヒーローのつもりかよ。キモいんだよ」
「いじめてる奴の方がよっぽどキモいだろ」
つかまれている右肩をぐっと握りこまれる。奴が右手の拳をぎゅっと握りこんだ。
(殴られる!?)
「はい、そこまで」
音無が間に入り、今にも殴りかかりそうな奴の右手を止めていた。
「その汚い手、離してくれる?」
冷たい目で奴を睨みつけている音無。今まで見たことのない表情に驚いて、身体が硬直する。奴は怯んで、チッと舌打ちをして、もう一人の同じ制服をきた奴と連れ立って去っていった。
「大丈夫?」
「……おぉ、助かった。ありがとな」
「どこかケガしてない? 殴られてない?」
心配そうに顔をのぞきこまれてドキッと心臓が跳ねる。
音無の低く優しい耳なじみのいい声、ふわふわと香るせっけんのようなにおい、まっすぐに俺に向けられる視線。
その全てに身体が反応して頭がふわふわする。
「大げさだな」
これ以上目を合わせていたらおかしくなりそうで、スッと視線を下の方へずらした。
「みんな待ってるから、戻ろ?」
「……わるい。やっぱ俺帰るわ」
「じゃあ、俺も一緒にーー」
「音無はいなきゃいけねーだろ。打ち上げの主役なんだから」
「べつに関係ないよ。俺いなくてもみんな盛り上がってるし」
「ごめん……ちょっと疲れてるから、ひとりにしてほしい」
「……わかった。家についたら連絡して。心配だから」
「過保護か」
「じゃないと、家までついてくよ?」
「わかったから。ちゃんと連絡します」
「うん、よろしい」
カバンを取りに音無と一緒に部屋に戻り、盛り上がっているクラスメイトたちに一言言ってから部屋をあとにした。ちょうど、下野が天城越えを熱唱しているところだった。
せっかく助けてくれたのに、感じの悪い態度を取ってしまった。
「はぁ……」
きっと疲れているからだ。ゆっくり休めば今まで通りにできる。これ以上なにも考えたくなくて、耳にイヤフォンをつけて音楽を再生した。
帰宅後、ベッドに入った途端、泥のように眠ってしまった。翌朝、目覚めてからスマホを確認すると音無からの着信とラインが鬼のように残っていた。
「うわー……忘れてた」
口を尖らせて怒っている音無の顔を想像しておもわず笑ってしまった。
体育祭がおわってからすぐにテスト週間に入った。下野が真中に「家に帰ってもどうせ勉強しないでしょ」と言ったことがきっかけで、四人で学校に居残り、勉強することになった。自習室に行くと既に人がいっぱいで、図書室に行くと意外と人が少なく、四人掛けの机に座って勉強することにした。俺の正面に真中、真中の隣に下野、そして俺の右隣に音無が座っている。問題集を開いた途端、真中は意識を失い机に突っ伏してしまった。下野が呆れて、真中の肩をゆさゆさ揺らすけど反応がない。勉強が嫌すぎて死んでしまったのかもしれない。そんな二人の様子を見ながら音無がフッと口元を緩める。音無が笑っているのを視界の端で捉えてしまい、ドキッと心臓が揺れるのを感じた。そして右半身が緊張で強張っている。
全く勉強に集中できない。音無がサラサラとシャープペンを走らせる音にまで反応してドキドキしている。
「瀬川くん全然進んでないじゃん。一問目で止まってるんだけど」
「数学? 僕がわかるところだったら教えるよ?」
音無と下野に声をかけられて、ごまかすようにノートにぐるぐると円を描く。
「ちょっとトイレ」
この場に居たくなくて、静かに図書室を出る。戸を閉めてからため息を吐いた。ただ隣に座っているだけなのに、身体が熱くなって息が苦しくなる。シャープペンを持っている右手が、音無の左腕に当たっただけで胸の奥をドクッと押される。このままじゃ身体がもたない。一問も解いていないけど、帰ろうかな。ふいに、ガラッと引き戸が開いて真中が出てきた。
「あ、生きてたのか」
「……いや~生死の境をさまよってたみたいなんだよね。尿意のおかげで戻ってこれました」
あくびをしながらだるそうにトイレへ向かう真中。
「あ、この後ラーメン食いにいこうって話になってるんだけど、おまえ来れる?」
「あ、いや、腹の調子悪いからやめとく」
「りょーかい。先に帰るんだろ? 気をつけてな~」
いつも真っ先に帰宅する真中に見送られるとか、なんか変な気分だ。
図書室にカバンを取りに戻り、音無と下野にも体調が悪いと言ってラーメン屋を断って先に帰宅した。帰宅してからも、晩飯を食べている時、風呂に入っている時、ベッドに横になってからもずっと、音無のことが頭から離れない。重症だ。音無から何件もラインがきていたのに、それにも気づかず、ベッドの中でずっと寝返りを打っていた。
そんなこんなで連日寝不足続きの俺。頬杖をついてぼーっと音無を目で追う。窓際で下野となにやら楽し気に話している。
「あっ……」
目が合って、ふいっと顔ごと背けてしまった。今のはさすがに不自然すぎる。ずんずんと誰かが近寄ってくる気配がする。どんっと机に手を置かれて、見上げると、音無が不機嫌極まりない様子でこちらを睨んでいる。
「あのさ、あからさまにーー」
「あー担任に呼ばれてるんだったー」
立ち上がってそそくさと教室を出た。後ろから「こらー無視すんなー」という音無の声が聞こえる。それからも何度か話しかけられたがその度に避けてしまい、さすがに怪しまれているようで、『なんで避けるの?』と音無からラインが来た。
『ごめん』
『謝ってほしいわけじゃないんだけど』
『今、頭の中がごちゃごちゃしてて、落ち着いたら話すから』
『わかった』
これ以降、用事がある時以外、音無から話しかけてくることはなくなった。あんなに何件も来ていたラインもぱたりと止まってしまった。相変わらず俺は音無を目で追っているけれど、目が合うと音無は頬を緩めるくらいで、視線を逸らしても言及しなくなった。
寂しい。
自分から避けておいて、音無に距離を置かれたら寂しいだなんて、自分勝手だ。と自戒しても感情は制御できない。こんなことは初めてだ。会っていない間はずっと音無のことを考えてしまって、勉強が手につかない。仕方がないからベッドに入る。寝てしまう。勉強せずにテストを受ける。この悪循環に陥ってしまい、テストの結果は散々だった。数学は赤点を取ってしまい、補習を受ける羽目になった。
放課後、1時間みっちり補習を受けて、ふらふらと昇降口へ向かう。
つかれた、脳が糖分を欲している。コンビニに寄ってなにか甘いものでも買おう。そう思いながら靴を履き替えていると、生徒玄関の入り口に音無が立っていた。
「おつかれ~」
(えーなんでいるんだよ……)
「瀬川くん、お腹すいてない?」
「すいてるけど」
「よし、パンケーキ食べにいこ!」
「え、今、甘いの食いたくないんだけど(本当はめちゃくちゃ食いたい)」
「この前約束したじゃん。テストおわったらいこーって」
「俺はいいよ。下野や真中といってこいよ」
「誘ったんだけど、真中くんはパスで下野くんは用事があるんだって」
「じゃあ、明日。明日みんなでいこう」
「クーポンの有効期限が今日までなんだよね」
「あー……」
という経緯で、音無とパンケーキを食べに行くことになった。音無と二人きりになるのが久々すぎてどう接したらいいのかわからない。とりあえず道中は音無の話に耳をかたむけて相槌を打っていた。
「わぁ~おいしそう!」
運ばれてきたパンケーキをみて目を輝かせている音無。パンケーキの上にシャインマスカットとレモンのソースがかかっていて、その横にクリームとシロップが添えられている。
「瀬川くんのもおいしそう! 写真撮っていい?」
「おー、どうぞ」
俺の注文したやつは、白桃とバニラアイスがのっていて、音無のと同じようにクリームとシロップが添えられている。うまそうだし映える見た目だけど、そんなに撮らなくてもいいだろと呆れるくらいに写真を撮っている音無。
「おい、今、どさくさに紛れて俺の顔撮っただろ」
「え? 撮ってないよ」
「うそつけ。みせろ」
「撮ってないってば。早く食べないとアイス溶けるよ」
「絶対にあげんなよ! SNSに」
「あげるわけないじゃん。ロックかけて永久保存するんだから」
「やっぱ撮ってんじゃねぇか!」
「もー大きい声出さないでよ。みんな見てるから」
「うっ……」
わくわくしながらパンケーキにナイフを入れて口に運ぶ、おいしさにびっくりして目を瞑る、おいしいねと幸せそうに目を細める。そんな音無をみていると、俺もふわふわと幸せな気持ちになる。寂しさを感じていたなんて忘れるくらいに胸がいっぱいだ。
(よかった。前みたいに、ちゃんと話せてる。ちゃんと笑えてる)
「おまえ、うまそうに食うよな」
「それは、瀬川くんと一緒だからだよ。瀬川くんと一緒に食べるとなんでもおいしく感じるんだよね」
「あー、一人で食うより二人で食った方がうまいってこと?」
「それもあるけど、食べ物だけじゃない。一緒にいると、うれしいし楽しいし幸せなんだ。だから、ずっと一緒にいたいって思っちゃうんだよね」
照れくさそうにふふっと笑い、パンケーキを頬張っている。
かわいい。
「……一緒にいたい、か。なんかわかる気がする」
「うん?」
「俺にとっても、音無は、たぶん……そういう存在、なんだと思う」
「本当に?」
「こんなこと、ウソついてどうすんだよ」
「へへっ、そっか」
噛みしめるように何度も頷いていた。その笑顔がずっと、脳裏から離れない。
ああ、これが恋なんだと自覚してから、ごちゃごちゃと散らかっていた感情が、胸にストンと落ちた。
ドリンクバーの機械にグラスを置いてメロンソーダのボタンを押す。シュワッと炭酸の混じったジュースが注がれて、パチパチと小さな気泡が弾ける。ぼんやりとそれを見つめながら、ため息がこぼれた。
どうして急に音無のことを見れなくなったのか。音無を見ていると、胸がドキドキして身体が熱くなる。話しかけられると、鼓動は速さを増し喉が渇いてうまくしゃべれない。
(どうしたもんか……)
「なぁ、おまえもしかしてーー」
右肩をつかまれて声をかけられた。振り向くと、他校の生徒が二人いた。
「やっぱり! 瀬川だ!」
「……だれ?」
「忘れたのかよ! 中学の同級生の顔!」
「……あっ」
(思い出した! いじめをしていた三人の内の一人だ。名前はわからないけど)
「こいつのせいで、俺の友達が不登校になったんだ」
「友達? いじめてたじゃねぇか」
「は? なに言ってんの? ふざけてただけだろ」
こいつの態度から、反省している様子は全くみられない。ふつふつと腹の底から怒りが湧いてくる。
「いじめとおふざけの区別もつかねぇのかよ」
「相変わらずだな。無駄に正義感ふりかざして、ヒーローのつもりかよ。キモいんだよ」
「いじめてる奴の方がよっぽどキモいだろ」
つかまれている右肩をぐっと握りこまれる。奴が右手の拳をぎゅっと握りこんだ。
(殴られる!?)
「はい、そこまで」
音無が間に入り、今にも殴りかかりそうな奴の右手を止めていた。
「その汚い手、離してくれる?」
冷たい目で奴を睨みつけている音無。今まで見たことのない表情に驚いて、身体が硬直する。奴は怯んで、チッと舌打ちをして、もう一人の同じ制服をきた奴と連れ立って去っていった。
「大丈夫?」
「……おぉ、助かった。ありがとな」
「どこかケガしてない? 殴られてない?」
心配そうに顔をのぞきこまれてドキッと心臓が跳ねる。
音無の低く優しい耳なじみのいい声、ふわふわと香るせっけんのようなにおい、まっすぐに俺に向けられる視線。
その全てに身体が反応して頭がふわふわする。
「大げさだな」
これ以上目を合わせていたらおかしくなりそうで、スッと視線を下の方へずらした。
「みんな待ってるから、戻ろ?」
「……わるい。やっぱ俺帰るわ」
「じゃあ、俺も一緒にーー」
「音無はいなきゃいけねーだろ。打ち上げの主役なんだから」
「べつに関係ないよ。俺いなくてもみんな盛り上がってるし」
「ごめん……ちょっと疲れてるから、ひとりにしてほしい」
「……わかった。家についたら連絡して。心配だから」
「過保護か」
「じゃないと、家までついてくよ?」
「わかったから。ちゃんと連絡します」
「うん、よろしい」
カバンを取りに音無と一緒に部屋に戻り、盛り上がっているクラスメイトたちに一言言ってから部屋をあとにした。ちょうど、下野が天城越えを熱唱しているところだった。
せっかく助けてくれたのに、感じの悪い態度を取ってしまった。
「はぁ……」
きっと疲れているからだ。ゆっくり休めば今まで通りにできる。これ以上なにも考えたくなくて、耳にイヤフォンをつけて音楽を再生した。
帰宅後、ベッドに入った途端、泥のように眠ってしまった。翌朝、目覚めてからスマホを確認すると音無からの着信とラインが鬼のように残っていた。
「うわー……忘れてた」
口を尖らせて怒っている音無の顔を想像しておもわず笑ってしまった。
体育祭がおわってからすぐにテスト週間に入った。下野が真中に「家に帰ってもどうせ勉強しないでしょ」と言ったことがきっかけで、四人で学校に居残り、勉強することになった。自習室に行くと既に人がいっぱいで、図書室に行くと意外と人が少なく、四人掛けの机に座って勉強することにした。俺の正面に真中、真中の隣に下野、そして俺の右隣に音無が座っている。問題集を開いた途端、真中は意識を失い机に突っ伏してしまった。下野が呆れて、真中の肩をゆさゆさ揺らすけど反応がない。勉強が嫌すぎて死んでしまったのかもしれない。そんな二人の様子を見ながら音無がフッと口元を緩める。音無が笑っているのを視界の端で捉えてしまい、ドキッと心臓が揺れるのを感じた。そして右半身が緊張で強張っている。
全く勉強に集中できない。音無がサラサラとシャープペンを走らせる音にまで反応してドキドキしている。
「瀬川くん全然進んでないじゃん。一問目で止まってるんだけど」
「数学? 僕がわかるところだったら教えるよ?」
音無と下野に声をかけられて、ごまかすようにノートにぐるぐると円を描く。
「ちょっとトイレ」
この場に居たくなくて、静かに図書室を出る。戸を閉めてからため息を吐いた。ただ隣に座っているだけなのに、身体が熱くなって息が苦しくなる。シャープペンを持っている右手が、音無の左腕に当たっただけで胸の奥をドクッと押される。このままじゃ身体がもたない。一問も解いていないけど、帰ろうかな。ふいに、ガラッと引き戸が開いて真中が出てきた。
「あ、生きてたのか」
「……いや~生死の境をさまよってたみたいなんだよね。尿意のおかげで戻ってこれました」
あくびをしながらだるそうにトイレへ向かう真中。
「あ、この後ラーメン食いにいこうって話になってるんだけど、おまえ来れる?」
「あ、いや、腹の調子悪いからやめとく」
「りょーかい。先に帰るんだろ? 気をつけてな~」
いつも真っ先に帰宅する真中に見送られるとか、なんか変な気分だ。
図書室にカバンを取りに戻り、音無と下野にも体調が悪いと言ってラーメン屋を断って先に帰宅した。帰宅してからも、晩飯を食べている時、風呂に入っている時、ベッドに横になってからもずっと、音無のことが頭から離れない。重症だ。音無から何件もラインがきていたのに、それにも気づかず、ベッドの中でずっと寝返りを打っていた。
そんなこんなで連日寝不足続きの俺。頬杖をついてぼーっと音無を目で追う。窓際で下野となにやら楽し気に話している。
「あっ……」
目が合って、ふいっと顔ごと背けてしまった。今のはさすがに不自然すぎる。ずんずんと誰かが近寄ってくる気配がする。どんっと机に手を置かれて、見上げると、音無が不機嫌極まりない様子でこちらを睨んでいる。
「あのさ、あからさまにーー」
「あー担任に呼ばれてるんだったー」
立ち上がってそそくさと教室を出た。後ろから「こらー無視すんなー」という音無の声が聞こえる。それからも何度か話しかけられたがその度に避けてしまい、さすがに怪しまれているようで、『なんで避けるの?』と音無からラインが来た。
『ごめん』
『謝ってほしいわけじゃないんだけど』
『今、頭の中がごちゃごちゃしてて、落ち着いたら話すから』
『わかった』
これ以降、用事がある時以外、音無から話しかけてくることはなくなった。あんなに何件も来ていたラインもぱたりと止まってしまった。相変わらず俺は音無を目で追っているけれど、目が合うと音無は頬を緩めるくらいで、視線を逸らしても言及しなくなった。
寂しい。
自分から避けておいて、音無に距離を置かれたら寂しいだなんて、自分勝手だ。と自戒しても感情は制御できない。こんなことは初めてだ。会っていない間はずっと音無のことを考えてしまって、勉強が手につかない。仕方がないからベッドに入る。寝てしまう。勉強せずにテストを受ける。この悪循環に陥ってしまい、テストの結果は散々だった。数学は赤点を取ってしまい、補習を受ける羽目になった。
放課後、1時間みっちり補習を受けて、ふらふらと昇降口へ向かう。
つかれた、脳が糖分を欲している。コンビニに寄ってなにか甘いものでも買おう。そう思いながら靴を履き替えていると、生徒玄関の入り口に音無が立っていた。
「おつかれ~」
(えーなんでいるんだよ……)
「瀬川くん、お腹すいてない?」
「すいてるけど」
「よし、パンケーキ食べにいこ!」
「え、今、甘いの食いたくないんだけど(本当はめちゃくちゃ食いたい)」
「この前約束したじゃん。テストおわったらいこーって」
「俺はいいよ。下野や真中といってこいよ」
「誘ったんだけど、真中くんはパスで下野くんは用事があるんだって」
「じゃあ、明日。明日みんなでいこう」
「クーポンの有効期限が今日までなんだよね」
「あー……」
という経緯で、音無とパンケーキを食べに行くことになった。音無と二人きりになるのが久々すぎてどう接したらいいのかわからない。とりあえず道中は音無の話に耳をかたむけて相槌を打っていた。
「わぁ~おいしそう!」
運ばれてきたパンケーキをみて目を輝かせている音無。パンケーキの上にシャインマスカットとレモンのソースがかかっていて、その横にクリームとシロップが添えられている。
「瀬川くんのもおいしそう! 写真撮っていい?」
「おー、どうぞ」
俺の注文したやつは、白桃とバニラアイスがのっていて、音無のと同じようにクリームとシロップが添えられている。うまそうだし映える見た目だけど、そんなに撮らなくてもいいだろと呆れるくらいに写真を撮っている音無。
「おい、今、どさくさに紛れて俺の顔撮っただろ」
「え? 撮ってないよ」
「うそつけ。みせろ」
「撮ってないってば。早く食べないとアイス溶けるよ」
「絶対にあげんなよ! SNSに」
「あげるわけないじゃん。ロックかけて永久保存するんだから」
「やっぱ撮ってんじゃねぇか!」
「もー大きい声出さないでよ。みんな見てるから」
「うっ……」
わくわくしながらパンケーキにナイフを入れて口に運ぶ、おいしさにびっくりして目を瞑る、おいしいねと幸せそうに目を細める。そんな音無をみていると、俺もふわふわと幸せな気持ちになる。寂しさを感じていたなんて忘れるくらいに胸がいっぱいだ。
(よかった。前みたいに、ちゃんと話せてる。ちゃんと笑えてる)
「おまえ、うまそうに食うよな」
「それは、瀬川くんと一緒だからだよ。瀬川くんと一緒に食べるとなんでもおいしく感じるんだよね」
「あー、一人で食うより二人で食った方がうまいってこと?」
「それもあるけど、食べ物だけじゃない。一緒にいると、うれしいし楽しいし幸せなんだ。だから、ずっと一緒にいたいって思っちゃうんだよね」
照れくさそうにふふっと笑い、パンケーキを頬張っている。
かわいい。
「……一緒にいたい、か。なんかわかる気がする」
「うん?」
「俺にとっても、音無は、たぶん……そういう存在、なんだと思う」
「本当に?」
「こんなこと、ウソついてどうすんだよ」
「へへっ、そっか」
噛みしめるように何度も頷いていた。その笑顔がずっと、脳裏から離れない。
ああ、これが恋なんだと自覚してから、ごちゃごちゃと散らかっていた感情が、胸にストンと落ちた。