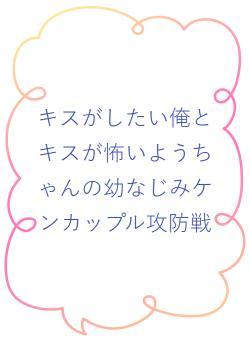夕食後、外のグラウンドに集められたかと思えば、急に肝試し大会が始まった。湖の周りの遊歩道約1キロメートルを二人一組でぐるっと一周するだけなんだけど、陽が落ちた後の薄暗い中でみる湖は不気味で、なにか霊の類が出そうな雰囲気だ。昼間は太陽に反射した水面がキラキラ光ってあんなにキレイだったのに。
ペア決めのクジを引き、下野とペアになった。知ってる奴だから気を使わなくていいものの、
「せ、瀬川くん、よろしくね。僕、こういうの苦手でーー」
突然、カァァーとカラスが大きな声を上げて闇夜に飛び立ち「ギャァァー!」と下野が絶叫して俺に抱きついてきた。不安でしかない。
俺たちの順番が回ってきて下野と一緒に恐る恐る出発する。足元を照らすペンライト所持は許可されたがそれ以外の武器は持っていない。霊の類が現れたらどう対処しようか。後ろにいる下野を守りながら応戦するのは難しいかもしれない。
「ねぇ、あれ、なんかいる……」
「え……怖いこと言うなよ」
ずっと俺の背後に隠れていた下野がなにかに気付いた。その指さす先を追うと、真っ白なワンピースを着た髪の長い女性がこっちをじっとみている。サーッと血の気が引いて、心臓がバクバクと大きく脈動し始めた。
「ひぃぃぃ~~~ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい」
俺の背後に隠れてひたすら謝っている下野。その間に、その女性は音もなく俺たちに近づいてきた。ガクガクと足が震える。逃げなきゃと思っているのに、身体が金縛りにあったみたいに動かない。
(やべー! やられる!?)
「どうぞ。あと半分です。がんばってね!」
なにか小さな包みを手渡し、にっこりと微笑んで道を教えてくれた。目を凝らしてよく見てみると、宿泊施設の職員さんだった。
その後も、風で葉がこすれる音や枝を踏んだ音、虫の鳴き声なんかに下野がいちいち反応して声を上げるものだから恐怖を通り越してイライラが募り「うるせー!」と叫んでしまった。
肝試し大会のせい(ほぼ下野のせい)でどっと疲れてしまい、部屋で休もうかと引き戸を開けると、ぼふんっとなにかが顔面を直撃して足元に落ちた。
「おー、瀬川ごめーん」
部屋を見回すと同部屋の奴らが変な雄たけびを上げて枕を投げまくっていた。いくつもの枕が空中を飛び交う。
(クッソ! どいつもこいつもうるせぇな!)
そして再び、枕が俺の顔面めがけて飛んできた。それをガシッと受け止めておもいっきり投げ返す。
「わっ! 瀬川も参戦してきた!」
次々と容赦なく飛んでくる枕をちぎっては投げちぎっては投げしているうちに体力が尽きてきた。
「静かにしろー消灯時間だー」
廊下から担任の声が響いて、慌ててその辺の布団に潜り込む。誰かが同じ布団に入ってきて、そいつの胸の中に抱きこまれた。
「ちょ、誰だよ!? 苦しいって!」(小声)
「瀬川くん!? 暴れないでよ! 見つかっちゃう!」(小声)
音無だった。背が高いとは思っていたけど、俺を抱き込むくらいには体格差があるってことで、単純にうらやましい。
ギシッと畳を踏む担任の足音が頭上で聞こえた。途端に心臓がバクバクして背中に冷や汗が伝い、緊張で身体が強張る。
くっついている音無の身体からは石けんのいい匂いがして、なんだか頭がふわふわしてきた。
「おとなしく寝てろよー今度暴れたらトイレ掃除させるからなー」
そう言って引き戸を閉め隣の部屋に行ってしまった。担任の頭の中では、罰=トイレ掃除という公式が成り立っているらしい。
「大丈夫?」
掛け布団をガバッと剥いで、心配そうに顔を覗き込んでくる音無。
「顔赤いよ? 熱あるんじゃない?」
額に手を当ててじっとみつめてくる。バランスの取れたアーモンド型の目、スッと通った鼻筋に少し上がった口角。長いまつ毛が影を作り、ミステリアスな雰囲気を醸し出している。
(近くでみたらマジでイケメンだな……)
「瀬川くん?」
音無の呼びかけにハッとしてゆっくりと起き上がる。
「いや~おまえがイケメンすぎて普通に見惚れてた」
「は……?え……??」
みるみるうちに音無の顔が赤くなり、ゆでダコのようになった。
「大丈夫かよ、おまえの方こそ熱あるんじゃね?」
額に手をやると恥ずかしそうに目を伏せてしまった。
(んんっ? なんだこのしおらしい態度は)
いつもなら嫌味の一つや二つぶつけてくるのに、急におとなしくなった。借りてきた猫みたいだ。
「ごめん、トイレいってくる」
ゆっくりと立ち上がりふらふらとした足取りで部屋を出て行った。
「あいつ、大丈夫かな?」と下野に聞いたら「どうだろう……」と苦笑いしていた。ちなみに真中は、枕投げから早々と離脱して布団に入り、今はもう夢の中。マイペースにもほどがある。
翌朝、朝食をおえるとリュックを背負ってグラウンドに集合した。宿泊施設の裏側にある山に登るらしい。山といっても標高五百メートルほどの低山で、登山初心者でも安心して挑戦できる。
「初心者コースと上級者コースだって。どうする?」
初心者コースは距離は長いがなだらかで整備されている登山道、上級者コースは距離は短いが急勾配な山道が続きあまり整備されていない。
「せっかくだから上級者コースにしようぜ」
「ここは安全に、初心者コースがいいと思うんだけど」
「そうだよね。僕、体力に自信ないからみんなの足手まといになっちゃうといけないし」
「早くおわるんならどっちでもいいけど」
「あいつら上級者コースだって」
「絶対無理だろ。肝試しでビビりまくってたしカレー作りも一番遅かったし」
同じグループの四人で登山ルートが載ったパンフレットを眺めていると、違うクラスの奴らがヒソヒソと陰口をたたいていた。
「あぁ!? なんだあいつら!? 言いたいことがあるならはっきり言えよ!」
陰口をたたいていた奴らに大声で反撃していたら、音無と下野に落ち着けと宥められた。
「こうなったら上級者コース一択だろ! 俺たちだってやればできるってみせつけてやろうぜ!」
「「えぇー」」
嫌そうに表情を歪める音無と下野、鼻をほじっている真中。
(こいつら全然やる気ねぇじゃねぇか! 悔しくないのかよ!? バカにされたんだぞ!)
カレー作りが遅かったのは、音無と下野が一生懸命あめ色玉ねぎを炒めていたからだし、真中は米の水分量間違えたけど作業よりも俺のことを優先して声をかけてくれるいい奴だ。肝試しでビビりまくってたのはまぁしかたないとして、一生懸命に取り組んだことをバカにされるのは腹が立つし悔しい。
あまりの悔しさにグッと拳を握りこんで歯を食いしばっていると、音無がスマホをみせてきた。そこには今現在の俺の顔が映っている。自撮りモードになっているらしい。
「瀬川くん、昨日眠れなかったんでしょ? クマ、すごいことになってる」
音無のスマホに映る自分の顔、目の下にくっきりと青黒いクマが広がっている。そのせいで顔色も悪い。
「おとなしく初心者コースにしましょうね~」
「うぐっ、べつにこれくらい大丈夫ーー」
「途中で倒れられたら俺たちが迷惑だからさ」
「瀬川くん、無理しないで?」
「そうそう、適当でいいんだよ。適当で」
確かに、みんなに迷惑をかける可能性があるなら初心者コースにした方がいい。
(でもこのモヤモヤはどう晴らせば……)
「あんな奴ら、相手にしなくていいよ。それにみんなそんなに気にしてないから」
音無が柔らかい笑みを浮かべて俺の肩をポンポン叩いた。
(あ、モヤモヤがスーッと消えていく……)
「わかった。初心者コースにする」
下野が安心したように表情をゆるめてウンウンと頷き、真中は「そうと決まればさっさと行くぞー」と先に行ってしまった。真中の後についていくように俺たちも歩き出した。
「瀬川くんって枕が変わると眠れないタイプ?」
「おー。こう見えて繊細なんだよ」
「いつでもどこでも眠れそうなのにね」
「人をのび太くんみたいに言うな」
「それはのび太くんに失礼だよ」
「あぁ!? おまえはどうなんだよ」
「俺はぐっすり眠れたよ」
「そうか。そりゃあよかったな」
「夢に瀬川くんが出てきてびっくりしたけどね」
「へぇ~どんな夢だよ」
「それは……」
しばらくじっと見つめてきたと思えば、ふふっと笑って「内緒」と口元に人差し指を立てる。
(うわぁー、こんな顔してこんなことされたらそりゃ落ちるわ……)
不覚にもドキッとしてしまった胸をおさえて小さく息を吐いた。
本当に不思議な奴だ。こつの近くにいるとざわめいていた心が落ち着いてふわふわと軽くなる。ウザいし腹が立つ時もあるけど、それもひっくるめて、こいつといる時の自分がけっこう好きだったりする。
そういえば、昨夜は少し様子がおかしかったけど、もう大丈夫なのだろうか。今朝起きたら、顔色も態度もいつもの音無に戻っていた。
「いくら俺がイケメンだからって穴があくほど見つめないでよ」
「昨日のゆでダコはなんだったんだよ。もう大丈夫か?」
「あれは、不意打ちだったから……」
「不意打ち? 誰かになにかされたのか?」
「いや、なんでもないです。大丈夫」
「だったらいいけど。あんま心配かけんなよ?」
「心配……してくれたんだ?」
「まぁ、一応、同じグループだし」
「うん、同じグループだからね」
「それに……友達、だし?」
さっきまで饒舌にはなしていたのに、なぜか急に固まって動かなくなってしまった音無。
(え、まさか引いてる……? 友達だと思ってたの、俺だけ?)
不安になり、「おーい」と音無の目の前でヒラヒラと手を振っていたら、ハッと意識を取り戻した。
「そっか。そうだよね。友達、だもんね」
嚙みしめるように何度も友達友達と呟いている。どういう感情なのか、よくわからない。
「とりあえず、今はそれでいいや」
「は? どういう意味だよ?」
「いや、うん。うれしいよ? うれしいんだけどなんか複雑っていうか」
「ますます意味がわからん」
頭の中に疑問符を浮かべていると、「二人とも早くー」「置いてくぞー」と先を行く下野と真中に急かされて、俺たちは二人の元へ走った。
ペア決めのクジを引き、下野とペアになった。知ってる奴だから気を使わなくていいものの、
「せ、瀬川くん、よろしくね。僕、こういうの苦手でーー」
突然、カァァーとカラスが大きな声を上げて闇夜に飛び立ち「ギャァァー!」と下野が絶叫して俺に抱きついてきた。不安でしかない。
俺たちの順番が回ってきて下野と一緒に恐る恐る出発する。足元を照らすペンライト所持は許可されたがそれ以外の武器は持っていない。霊の類が現れたらどう対処しようか。後ろにいる下野を守りながら応戦するのは難しいかもしれない。
「ねぇ、あれ、なんかいる……」
「え……怖いこと言うなよ」
ずっと俺の背後に隠れていた下野がなにかに気付いた。その指さす先を追うと、真っ白なワンピースを着た髪の長い女性がこっちをじっとみている。サーッと血の気が引いて、心臓がバクバクと大きく脈動し始めた。
「ひぃぃぃ~~~ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい」
俺の背後に隠れてひたすら謝っている下野。その間に、その女性は音もなく俺たちに近づいてきた。ガクガクと足が震える。逃げなきゃと思っているのに、身体が金縛りにあったみたいに動かない。
(やべー! やられる!?)
「どうぞ。あと半分です。がんばってね!」
なにか小さな包みを手渡し、にっこりと微笑んで道を教えてくれた。目を凝らしてよく見てみると、宿泊施設の職員さんだった。
その後も、風で葉がこすれる音や枝を踏んだ音、虫の鳴き声なんかに下野がいちいち反応して声を上げるものだから恐怖を通り越してイライラが募り「うるせー!」と叫んでしまった。
肝試し大会のせい(ほぼ下野のせい)でどっと疲れてしまい、部屋で休もうかと引き戸を開けると、ぼふんっとなにかが顔面を直撃して足元に落ちた。
「おー、瀬川ごめーん」
部屋を見回すと同部屋の奴らが変な雄たけびを上げて枕を投げまくっていた。いくつもの枕が空中を飛び交う。
(クッソ! どいつもこいつもうるせぇな!)
そして再び、枕が俺の顔面めがけて飛んできた。それをガシッと受け止めておもいっきり投げ返す。
「わっ! 瀬川も参戦してきた!」
次々と容赦なく飛んでくる枕をちぎっては投げちぎっては投げしているうちに体力が尽きてきた。
「静かにしろー消灯時間だー」
廊下から担任の声が響いて、慌ててその辺の布団に潜り込む。誰かが同じ布団に入ってきて、そいつの胸の中に抱きこまれた。
「ちょ、誰だよ!? 苦しいって!」(小声)
「瀬川くん!? 暴れないでよ! 見つかっちゃう!」(小声)
音無だった。背が高いとは思っていたけど、俺を抱き込むくらいには体格差があるってことで、単純にうらやましい。
ギシッと畳を踏む担任の足音が頭上で聞こえた。途端に心臓がバクバクして背中に冷や汗が伝い、緊張で身体が強張る。
くっついている音無の身体からは石けんのいい匂いがして、なんだか頭がふわふわしてきた。
「おとなしく寝てろよー今度暴れたらトイレ掃除させるからなー」
そう言って引き戸を閉め隣の部屋に行ってしまった。担任の頭の中では、罰=トイレ掃除という公式が成り立っているらしい。
「大丈夫?」
掛け布団をガバッと剥いで、心配そうに顔を覗き込んでくる音無。
「顔赤いよ? 熱あるんじゃない?」
額に手を当ててじっとみつめてくる。バランスの取れたアーモンド型の目、スッと通った鼻筋に少し上がった口角。長いまつ毛が影を作り、ミステリアスな雰囲気を醸し出している。
(近くでみたらマジでイケメンだな……)
「瀬川くん?」
音無の呼びかけにハッとしてゆっくりと起き上がる。
「いや~おまえがイケメンすぎて普通に見惚れてた」
「は……?え……??」
みるみるうちに音無の顔が赤くなり、ゆでダコのようになった。
「大丈夫かよ、おまえの方こそ熱あるんじゃね?」
額に手をやると恥ずかしそうに目を伏せてしまった。
(んんっ? なんだこのしおらしい態度は)
いつもなら嫌味の一つや二つぶつけてくるのに、急におとなしくなった。借りてきた猫みたいだ。
「ごめん、トイレいってくる」
ゆっくりと立ち上がりふらふらとした足取りで部屋を出て行った。
「あいつ、大丈夫かな?」と下野に聞いたら「どうだろう……」と苦笑いしていた。ちなみに真中は、枕投げから早々と離脱して布団に入り、今はもう夢の中。マイペースにもほどがある。
翌朝、朝食をおえるとリュックを背負ってグラウンドに集合した。宿泊施設の裏側にある山に登るらしい。山といっても標高五百メートルほどの低山で、登山初心者でも安心して挑戦できる。
「初心者コースと上級者コースだって。どうする?」
初心者コースは距離は長いがなだらかで整備されている登山道、上級者コースは距離は短いが急勾配な山道が続きあまり整備されていない。
「せっかくだから上級者コースにしようぜ」
「ここは安全に、初心者コースがいいと思うんだけど」
「そうだよね。僕、体力に自信ないからみんなの足手まといになっちゃうといけないし」
「早くおわるんならどっちでもいいけど」
「あいつら上級者コースだって」
「絶対無理だろ。肝試しでビビりまくってたしカレー作りも一番遅かったし」
同じグループの四人で登山ルートが載ったパンフレットを眺めていると、違うクラスの奴らがヒソヒソと陰口をたたいていた。
「あぁ!? なんだあいつら!? 言いたいことがあるならはっきり言えよ!」
陰口をたたいていた奴らに大声で反撃していたら、音無と下野に落ち着けと宥められた。
「こうなったら上級者コース一択だろ! 俺たちだってやればできるってみせつけてやろうぜ!」
「「えぇー」」
嫌そうに表情を歪める音無と下野、鼻をほじっている真中。
(こいつら全然やる気ねぇじゃねぇか! 悔しくないのかよ!? バカにされたんだぞ!)
カレー作りが遅かったのは、音無と下野が一生懸命あめ色玉ねぎを炒めていたからだし、真中は米の水分量間違えたけど作業よりも俺のことを優先して声をかけてくれるいい奴だ。肝試しでビビりまくってたのはまぁしかたないとして、一生懸命に取り組んだことをバカにされるのは腹が立つし悔しい。
あまりの悔しさにグッと拳を握りこんで歯を食いしばっていると、音無がスマホをみせてきた。そこには今現在の俺の顔が映っている。自撮りモードになっているらしい。
「瀬川くん、昨日眠れなかったんでしょ? クマ、すごいことになってる」
音無のスマホに映る自分の顔、目の下にくっきりと青黒いクマが広がっている。そのせいで顔色も悪い。
「おとなしく初心者コースにしましょうね~」
「うぐっ、べつにこれくらい大丈夫ーー」
「途中で倒れられたら俺たちが迷惑だからさ」
「瀬川くん、無理しないで?」
「そうそう、適当でいいんだよ。適当で」
確かに、みんなに迷惑をかける可能性があるなら初心者コースにした方がいい。
(でもこのモヤモヤはどう晴らせば……)
「あんな奴ら、相手にしなくていいよ。それにみんなそんなに気にしてないから」
音無が柔らかい笑みを浮かべて俺の肩をポンポン叩いた。
(あ、モヤモヤがスーッと消えていく……)
「わかった。初心者コースにする」
下野が安心したように表情をゆるめてウンウンと頷き、真中は「そうと決まればさっさと行くぞー」と先に行ってしまった。真中の後についていくように俺たちも歩き出した。
「瀬川くんって枕が変わると眠れないタイプ?」
「おー。こう見えて繊細なんだよ」
「いつでもどこでも眠れそうなのにね」
「人をのび太くんみたいに言うな」
「それはのび太くんに失礼だよ」
「あぁ!? おまえはどうなんだよ」
「俺はぐっすり眠れたよ」
「そうか。そりゃあよかったな」
「夢に瀬川くんが出てきてびっくりしたけどね」
「へぇ~どんな夢だよ」
「それは……」
しばらくじっと見つめてきたと思えば、ふふっと笑って「内緒」と口元に人差し指を立てる。
(うわぁー、こんな顔してこんなことされたらそりゃ落ちるわ……)
不覚にもドキッとしてしまった胸をおさえて小さく息を吐いた。
本当に不思議な奴だ。こつの近くにいるとざわめいていた心が落ち着いてふわふわと軽くなる。ウザいし腹が立つ時もあるけど、それもひっくるめて、こいつといる時の自分がけっこう好きだったりする。
そういえば、昨夜は少し様子がおかしかったけど、もう大丈夫なのだろうか。今朝起きたら、顔色も態度もいつもの音無に戻っていた。
「いくら俺がイケメンだからって穴があくほど見つめないでよ」
「昨日のゆでダコはなんだったんだよ。もう大丈夫か?」
「あれは、不意打ちだったから……」
「不意打ち? 誰かになにかされたのか?」
「いや、なんでもないです。大丈夫」
「だったらいいけど。あんま心配かけんなよ?」
「心配……してくれたんだ?」
「まぁ、一応、同じグループだし」
「うん、同じグループだからね」
「それに……友達、だし?」
さっきまで饒舌にはなしていたのに、なぜか急に固まって動かなくなってしまった音無。
(え、まさか引いてる……? 友達だと思ってたの、俺だけ?)
不安になり、「おーい」と音無の目の前でヒラヒラと手を振っていたら、ハッと意識を取り戻した。
「そっか。そうだよね。友達、だもんね」
嚙みしめるように何度も友達友達と呟いている。どういう感情なのか、よくわからない。
「とりあえず、今はそれでいいや」
「は? どういう意味だよ?」
「いや、うん。うれしいよ? うれしいんだけどなんか複雑っていうか」
「ますます意味がわからん」
頭の中に疑問符を浮かべていると、「二人とも早くー」「置いてくぞー」と先を行く下野と真中に急かされて、俺たちは二人の元へ走った。