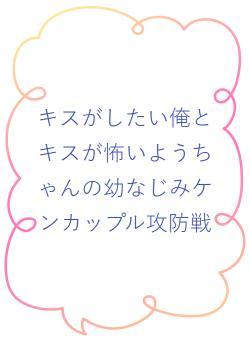四月下旬、高校に入学してから四週間が経とうとしていた。青少年自然の家、湖を眼下に望む豊かな自然に囲まれた山あいに位置した宿泊施設で一泊二日のオリエンテーション合宿が行われている。今はちょうど飯盒炊爨の時間。学校指定のジャージを着用し、四~五人のグループに分かれてカレーを作っている。
そして俺は黙々とにんじんとじゃがいもを切っているところだ。
「わぁ~! いい音だね〜リズムも心地いいし〜」
トントントンと小気味いい音を響かせていると、その様子を隣に立って見つめてくる男が1人。音無理人。俺の手元と顔を交互に見ながら、感嘆の声を上げる。今日もやたら整っている顔面をこれでもかと見せつけてくる。ウザい。
「瀬川くんが料理できるなんて意外だなぁ。今度俺の家まで作りにきてよ」
ビキッ!
血管が浮き上がってきた。このままだと切れそうだ。ぐっと包丁を握り、音無の首元に切先を突き立てる。
「しゃべってねぇで手を動かせ」
「……っ、肉ならもう切れてるよ」
首元に光る包丁の刃先を恐々みながら苦笑いを浮かべ、一口大に切られてトレーに載った鶏肉を指さした。
「できてんならさっさと火ぃ起こして炒めてこいや!」
「玉ねぎがまだ切れてないからさ」
「玉ねぎ!?」
どこからかすすり泣く声が聞こえる。振り向くとすぐ後ろの作業台で下野が涙を流しながら玉ねぎをみじん切りしていた。
「おい、なんでみじん切りなんだよ。カレーだぞ? 串切りでいいんじゃね?」
「あっ、ごめん……弟が玉ねぎ苦手だから我が家ではみじん切りなんだ。それでつい……」
グスグス鼻をすすりながら答える下野の頬は、涙でびしょびしょに濡れていた。
(あぁ~、カレーは家庭によって味が違うもんな。ってか、泣きながら健気にみじん切りしてるのみたらなんかせつなくなってきたわ……)
「なるほど! みじん切りにした玉ねぎをあめ色に炒めるんだね」
「そう、それ! 時間がかかるけどおいしいんだよね!」
音無と下野がキャッキャッと盛り上がっている。この二人、共通点なさそうなのに仲がいい。波長が合うのだろうか。
「瀬川くん! 俺、あめ色玉ねぎの口になってきたよ!」
「んだよ、あめ色玉ねぎの口って……」
「あめ色玉ねぎのカレー、作ってもいいよね!?」
キラキラと瞳を輝かせて懇願するように視線を向けてくる。そしてやたら顔が近い。
「作れよ、勝手に。切っちゃったもんはしかたねぇだろ。ってか、近い離れろ」
音無を引きはがすと、下野と一緒に「わーい! リーダーの許可が下りたー!」とハイタッチをして喜んでいる。
「おらー! 時間ねぇんだからさっさと炒めてこい!」
俺の一声でそそくさと持ち場に戻る二人。他のグループの様子をみると、もう鍋を火にかけており、早いところはルゥを鍋に投入している。
(やべーめっちゃ遅れてる。今日中におわんのか……?)
米炊きを任せた真中の元へ様子を見に行くと、腕を組んでウンウン唸っていた。
「どした?」
「瀬川! ちょうどいいところに……あのさ、水ってどこまで入れればいいの?」
「え? 確か、上の線まで入れるんじゃなかった?」
「りょーかい」
「ちょっと待て。他の奴に確認してーーー」
「いいよ、いいよ。大丈夫」
「お前、適当すぎ。飯盒炊爨は、水加減と火加減が大事なんだからな!」
「まぁ、なんとかなるっしょ」
そう言いながら適当に水を入れて飯盒のフタをしてしまった。
「浸水するまで30分待ちだよな? 楽勝じゃね?」
「アホか。その間に火起こししなきゃだろ。やるぞ」
「えー、休めると思ったのに」
「休んでるヒマねぇよ。ウチのグループただでさえ遅れてんのに」
愚痴る真中を急かし、浸水中の飯盒を持たせてレンガつくりのかまどへと移動する。
「仲間と協力して積極的にコミュニケーションをとりましょう」
「は?」
「今回の合宿のテーマです」
「あぁ」
真中の話に相槌を打ちながら、かまどに新聞紙や落ち葉、木の皮を置いていく。その周りに細い枝を立てかけるように組んで、新聞紙に火をつけた。
「正直、心配だったんだけどさ」
「なにが?」
「瀬川のこと」
「俺!?」
「入学してから俺以外の奴としゃべんないんだもん」
「そうだっけ?」
「そうだよ」
そうっと火に息を吹きかけて酸素を送り込む。細い枝に火が移ったので、少し太目の枝を立てかけようとしたのだが、手が止まった。真中に心配されていたのが意外で聞き入ってしまう。
「このまま友達できないんじゃないかって心配だったけど杞憂だったわ。音無や下野としゃべってんのみて安心した」
「……悪かったな、色々と心配かけて」
「一時期めっちゃ落ちてたもんなぁ~。まぁ、少しづつ元気になってるみたいでよかったよ」
「……ぁりがとう」
励ますようにポンポンと背中に手を添えられて、そこがじんわりとあたたかくなるのを感じた。中学の頃、俺のせいで不登校になった生徒がいた。自分を責め続ける俺に、真中は『お前のせいじゃない。気にするな』と言ってくれた。それでもずっと俺は自分を許せなかったけど、真中は変わらず気さくに接してくれていた。その距離感が心地よくてありがたかった。今もこうしてさりげなく隣にいてくれる。俺は友達に恵まれてるんだ。これ以上心配かけないようにしっかりしないと……
(うっ……鼻の奥がツンとしてきた。やばい、泣きそう……)
目の淵に溜まった涙を落とさないように上を向いたら、顔を覗き込んできた音無と目が合った。
「っ!? お前、いつの間に!? 黙って背後に立つな!」
「いや~声かけづらい雰囲気だったから……で、なんの話?」
ごまかすようにふいっと目をそらしてゴホッと咳払いする。
「なんでもねぇよ」
「あの~火が消えちゃってるみたいなんだけど……」
鍋を手に持った下野が遠慮がちに指摘してくれて、慌てて火起こしを再開した。
ーー1時間後、なんとかカレーが完成し米も炊けた。鍋と飯盒を火からおろし、米の炊け具合を確認するため飯盒のフタを開けた。炊きたてのご飯の香りがふわっと広がる。見た目は特に問題なさそうだ。
「おっ、うまそうじゃん」
真中がしゃもじを使ってご飯をつまみ食いした。
「あっつ! んんっ!? なんか硬いんだけど……」
眉間にシワを寄せる真中。真中からしゃもじを奪い、俺も少し口に入れる。熱くて、ハフハフと口内に空気を入れながら米を噛んでみた。ーーじゃり、と奥歯の上で嫌な音がした。
「……生煮えだ」
同じく味見をした音無と下野も微妙な顔をしている。
「少し水足して炊きなおすか」
「えーまだ食えないの?」
「お前が適当に水入れるからだろ」
「他のグループはもう食い終わって片付けてんだけど」
「うるせー。おとなしく待ってろ」
水を足してフタをして、再び火にかけなおす。
「ごはん、少しわけてもらった」
いつの間にか姿を消していた音無がにこやかに現れた。手に持っている皿には白いごはんが。
「マジか! やったー! やっとカレーが食える!」
「お前ら先に食ってろ」
「瀬川も食えよ。腹へってんだろ?」
「いいから、俺はあとで食う」
音無がもらってきたごはんは2~3人分で、俺たちは4人グループだから明らかに足りない。俺は炊きなおした米をあとで食えればそれでいい。
「瀬川くん、食べてみて」
かまどの火加減をみていたら、音無がそっとカレーがのったスプーンを差しだしてきた。
「え……」
「あ、大丈夫! これ新しいスプーンだから!」
そう言って、にこにことスプーンを口元に持ってくる。
(これって、口開けろってことだよな? なんかめっちゃ恥ずいんですけど!)
スプーンを持っている音無の手ごとがしっとつかみ、そのまま自分の口に運んだ。
「うんまっ!」
玉ねぎの甘みが口の中に広がって味に深みがある。中辛のはずなのに甘い。今まで食べたことない味だ。
「ねっ! うまいよね! よかった~」
「あめ色玉ねぎすげぇな」
「下野くんと交代しながらやってたんだけど、おもったより時間かかっちゃって」
「店に出せるんじゃね?」
「へへっ、これで瀬川くんもあめ色玉ねぎの口になった」
「だから、なんだよ。あめ色玉ねぎの口って」
根気よく玉ねぎを炒めて、時々ヘマをする下野のフォローをして、どこからかごはんを調達してきてくれて。
ふわふわにこにこしてなにを考えてるのか読めない奴だけど、ちゃんと周りをみて動いてくれている。
(なんだよ、けっこういい奴じゃねぇか)
「あっ、また火が消えちゃったみたい」
「げっ!」
ーー30分後、なんとか米が炊き上がり俺はやっとカレーにありつくことができた。他の3人もおかわりをして、炊きなおした米をあっという間にたいらげてしまった。
他のグループは既に片付けを済ませて自由時間を満喫している。俺たちも自由時間確保のため、急いで片付けを済ませた。
自販機で飲み物を買い、適当に散歩でもしようかと話しているうちに音無の姿が消えていた。
「あれ? 音無どこいった?」
「さっき女子に連れていかれた」
「ごはん分けるかわりに自由時間一緒に過ごしてほしいって言われてたんだって」
「えぇ、人身御供じゃねぇか」
「ひとみごくう??」
「生け贄ってことだよ」
「ちょっと様子みてくるわ」
「大丈夫だろ。いつも女子に囲まれてんだから、そういうの慣れてんじゃね?」
「慣れてたとしても、嫌だと思ってるかもしんねぇだろ」
音無を探しに、湖まで続く遊歩道を歩いていると、途中のベンチで音無と女子が座っているのがみえた。
「好きです。つき合ってください」
女子の告白する声が聞こえて、慌てて身を屈める。
「……ごめんね、今は誰ともつき合う気がないから」
「……そうなんだ……理由、きいてもいい?」
「ちゃんと好きになってからつき合いたい。じゃないと、傷つけちゃうから」
「……意外だな。音無くんって来るもの拒まずだから、誰でもいいのかと思ってた」
「……うん、ごめんね」
女子が静かに去っていき、俺もさっさと退散しようとそーっと立ち上がる。
「瀬川くん、盗み聞き?」
声をかけられてびくっと肩が震え、恐る恐る振り返ると、にこやかな笑みを張り付けている音無が手招きしていた。
ため息をついて、どすっと音無の隣に座る。
「……悪かった。聞くつもりはなかったんだけど」
さっき自販機で買ったサイダーを手渡すと「ありがとう」と笑って受け取った。
「……さっきの、来るもの拒まずっていうのは」
「あぁ、中学の頃は断るのが面倒で、告白されたらとりあえずつき合ってたんだけど、長続きしなくてすぐに別れちゃってたから……ちゃんと好きになれなくて相手を傷つけちゃうから、そういうのはやめようと思って」
「ふ〜ん、色々と大変だったんだな」
ペットボトルのフタを開けてスポーツドリンクを喉に流し込んでいると、音無が隣でふふっと笑みをこぼした。
「なんだよ?」
「いや、こういう話すると、羨ましがられたり嫌味を言われたり、からかわれたりするんだけど……瀬川くんは違うんだなと思って」
「……まぁ、受け取り方は人それぞれだけど。さっきの口ぶりからして、音無にとってはしんどいことなのかなって思ったから」
「そっか……やっぱりいいね、瀬川くんは」
「いい?」
「ふふっ、こっちの話」
「??」
なにが『いい』のかよくわからないままスポーツドリンクをごくごくと流し込む。
「それよりさ、俺、炭酸飲めないからそれと交換してよ」
「え、俺も飲めねぇんだけど」
「なんで買ったの……」
「適当だよ。音無の好きなやつわかんなかったから」
「まぁいいや。それ、ちょーだい」
「これ口つけちゃってるしな〜」
「俺はべつに大丈夫だけど」
「そうか?」
もう半分ほど飲んでしまったスポーツドリンクを音無に手渡す。音無はそれを少し口に含み、首をかしげた。
「ん?? なんかこれ甘くない?」
「へ? べつに普通だったけど」
「飲んでみてよ! ちょー甘いから」
促され、俺も少し口に含む。
「……ねっ? 甘いでしょ?」
「……そう言われたら甘い気もするけど」
「いや、異様に甘かったって」
確認のため、もう一口。
「……ん〜? よくわからん」
「えー!」
そして俺は黙々とにんじんとじゃがいもを切っているところだ。
「わぁ~! いい音だね〜リズムも心地いいし〜」
トントントンと小気味いい音を響かせていると、その様子を隣に立って見つめてくる男が1人。音無理人。俺の手元と顔を交互に見ながら、感嘆の声を上げる。今日もやたら整っている顔面をこれでもかと見せつけてくる。ウザい。
「瀬川くんが料理できるなんて意外だなぁ。今度俺の家まで作りにきてよ」
ビキッ!
血管が浮き上がってきた。このままだと切れそうだ。ぐっと包丁を握り、音無の首元に切先を突き立てる。
「しゃべってねぇで手を動かせ」
「……っ、肉ならもう切れてるよ」
首元に光る包丁の刃先を恐々みながら苦笑いを浮かべ、一口大に切られてトレーに載った鶏肉を指さした。
「できてんならさっさと火ぃ起こして炒めてこいや!」
「玉ねぎがまだ切れてないからさ」
「玉ねぎ!?」
どこからかすすり泣く声が聞こえる。振り向くとすぐ後ろの作業台で下野が涙を流しながら玉ねぎをみじん切りしていた。
「おい、なんでみじん切りなんだよ。カレーだぞ? 串切りでいいんじゃね?」
「あっ、ごめん……弟が玉ねぎ苦手だから我が家ではみじん切りなんだ。それでつい……」
グスグス鼻をすすりながら答える下野の頬は、涙でびしょびしょに濡れていた。
(あぁ~、カレーは家庭によって味が違うもんな。ってか、泣きながら健気にみじん切りしてるのみたらなんかせつなくなってきたわ……)
「なるほど! みじん切りにした玉ねぎをあめ色に炒めるんだね」
「そう、それ! 時間がかかるけどおいしいんだよね!」
音無と下野がキャッキャッと盛り上がっている。この二人、共通点なさそうなのに仲がいい。波長が合うのだろうか。
「瀬川くん! 俺、あめ色玉ねぎの口になってきたよ!」
「んだよ、あめ色玉ねぎの口って……」
「あめ色玉ねぎのカレー、作ってもいいよね!?」
キラキラと瞳を輝かせて懇願するように視線を向けてくる。そしてやたら顔が近い。
「作れよ、勝手に。切っちゃったもんはしかたねぇだろ。ってか、近い離れろ」
音無を引きはがすと、下野と一緒に「わーい! リーダーの許可が下りたー!」とハイタッチをして喜んでいる。
「おらー! 時間ねぇんだからさっさと炒めてこい!」
俺の一声でそそくさと持ち場に戻る二人。他のグループの様子をみると、もう鍋を火にかけており、早いところはルゥを鍋に投入している。
(やべーめっちゃ遅れてる。今日中におわんのか……?)
米炊きを任せた真中の元へ様子を見に行くと、腕を組んでウンウン唸っていた。
「どした?」
「瀬川! ちょうどいいところに……あのさ、水ってどこまで入れればいいの?」
「え? 確か、上の線まで入れるんじゃなかった?」
「りょーかい」
「ちょっと待て。他の奴に確認してーーー」
「いいよ、いいよ。大丈夫」
「お前、適当すぎ。飯盒炊爨は、水加減と火加減が大事なんだからな!」
「まぁ、なんとかなるっしょ」
そう言いながら適当に水を入れて飯盒のフタをしてしまった。
「浸水するまで30分待ちだよな? 楽勝じゃね?」
「アホか。その間に火起こししなきゃだろ。やるぞ」
「えー、休めると思ったのに」
「休んでるヒマねぇよ。ウチのグループただでさえ遅れてんのに」
愚痴る真中を急かし、浸水中の飯盒を持たせてレンガつくりのかまどへと移動する。
「仲間と協力して積極的にコミュニケーションをとりましょう」
「は?」
「今回の合宿のテーマです」
「あぁ」
真中の話に相槌を打ちながら、かまどに新聞紙や落ち葉、木の皮を置いていく。その周りに細い枝を立てかけるように組んで、新聞紙に火をつけた。
「正直、心配だったんだけどさ」
「なにが?」
「瀬川のこと」
「俺!?」
「入学してから俺以外の奴としゃべんないんだもん」
「そうだっけ?」
「そうだよ」
そうっと火に息を吹きかけて酸素を送り込む。細い枝に火が移ったので、少し太目の枝を立てかけようとしたのだが、手が止まった。真中に心配されていたのが意外で聞き入ってしまう。
「このまま友達できないんじゃないかって心配だったけど杞憂だったわ。音無や下野としゃべってんのみて安心した」
「……悪かったな、色々と心配かけて」
「一時期めっちゃ落ちてたもんなぁ~。まぁ、少しづつ元気になってるみたいでよかったよ」
「……ぁりがとう」
励ますようにポンポンと背中に手を添えられて、そこがじんわりとあたたかくなるのを感じた。中学の頃、俺のせいで不登校になった生徒がいた。自分を責め続ける俺に、真中は『お前のせいじゃない。気にするな』と言ってくれた。それでもずっと俺は自分を許せなかったけど、真中は変わらず気さくに接してくれていた。その距離感が心地よくてありがたかった。今もこうしてさりげなく隣にいてくれる。俺は友達に恵まれてるんだ。これ以上心配かけないようにしっかりしないと……
(うっ……鼻の奥がツンとしてきた。やばい、泣きそう……)
目の淵に溜まった涙を落とさないように上を向いたら、顔を覗き込んできた音無と目が合った。
「っ!? お前、いつの間に!? 黙って背後に立つな!」
「いや~声かけづらい雰囲気だったから……で、なんの話?」
ごまかすようにふいっと目をそらしてゴホッと咳払いする。
「なんでもねぇよ」
「あの~火が消えちゃってるみたいなんだけど……」
鍋を手に持った下野が遠慮がちに指摘してくれて、慌てて火起こしを再開した。
ーー1時間後、なんとかカレーが完成し米も炊けた。鍋と飯盒を火からおろし、米の炊け具合を確認するため飯盒のフタを開けた。炊きたてのご飯の香りがふわっと広がる。見た目は特に問題なさそうだ。
「おっ、うまそうじゃん」
真中がしゃもじを使ってご飯をつまみ食いした。
「あっつ! んんっ!? なんか硬いんだけど……」
眉間にシワを寄せる真中。真中からしゃもじを奪い、俺も少し口に入れる。熱くて、ハフハフと口内に空気を入れながら米を噛んでみた。ーーじゃり、と奥歯の上で嫌な音がした。
「……生煮えだ」
同じく味見をした音無と下野も微妙な顔をしている。
「少し水足して炊きなおすか」
「えーまだ食えないの?」
「お前が適当に水入れるからだろ」
「他のグループはもう食い終わって片付けてんだけど」
「うるせー。おとなしく待ってろ」
水を足してフタをして、再び火にかけなおす。
「ごはん、少しわけてもらった」
いつの間にか姿を消していた音無がにこやかに現れた。手に持っている皿には白いごはんが。
「マジか! やったー! やっとカレーが食える!」
「お前ら先に食ってろ」
「瀬川も食えよ。腹へってんだろ?」
「いいから、俺はあとで食う」
音無がもらってきたごはんは2~3人分で、俺たちは4人グループだから明らかに足りない。俺は炊きなおした米をあとで食えればそれでいい。
「瀬川くん、食べてみて」
かまどの火加減をみていたら、音無がそっとカレーがのったスプーンを差しだしてきた。
「え……」
「あ、大丈夫! これ新しいスプーンだから!」
そう言って、にこにことスプーンを口元に持ってくる。
(これって、口開けろってことだよな? なんかめっちゃ恥ずいんですけど!)
スプーンを持っている音無の手ごとがしっとつかみ、そのまま自分の口に運んだ。
「うんまっ!」
玉ねぎの甘みが口の中に広がって味に深みがある。中辛のはずなのに甘い。今まで食べたことない味だ。
「ねっ! うまいよね! よかった~」
「あめ色玉ねぎすげぇな」
「下野くんと交代しながらやってたんだけど、おもったより時間かかっちゃって」
「店に出せるんじゃね?」
「へへっ、これで瀬川くんもあめ色玉ねぎの口になった」
「だから、なんだよ。あめ色玉ねぎの口って」
根気よく玉ねぎを炒めて、時々ヘマをする下野のフォローをして、どこからかごはんを調達してきてくれて。
ふわふわにこにこしてなにを考えてるのか読めない奴だけど、ちゃんと周りをみて動いてくれている。
(なんだよ、けっこういい奴じゃねぇか)
「あっ、また火が消えちゃったみたい」
「げっ!」
ーー30分後、なんとか米が炊き上がり俺はやっとカレーにありつくことができた。他の3人もおかわりをして、炊きなおした米をあっという間にたいらげてしまった。
他のグループは既に片付けを済ませて自由時間を満喫している。俺たちも自由時間確保のため、急いで片付けを済ませた。
自販機で飲み物を買い、適当に散歩でもしようかと話しているうちに音無の姿が消えていた。
「あれ? 音無どこいった?」
「さっき女子に連れていかれた」
「ごはん分けるかわりに自由時間一緒に過ごしてほしいって言われてたんだって」
「えぇ、人身御供じゃねぇか」
「ひとみごくう??」
「生け贄ってことだよ」
「ちょっと様子みてくるわ」
「大丈夫だろ。いつも女子に囲まれてんだから、そういうの慣れてんじゃね?」
「慣れてたとしても、嫌だと思ってるかもしんねぇだろ」
音無を探しに、湖まで続く遊歩道を歩いていると、途中のベンチで音無と女子が座っているのがみえた。
「好きです。つき合ってください」
女子の告白する声が聞こえて、慌てて身を屈める。
「……ごめんね、今は誰ともつき合う気がないから」
「……そうなんだ……理由、きいてもいい?」
「ちゃんと好きになってからつき合いたい。じゃないと、傷つけちゃうから」
「……意外だな。音無くんって来るもの拒まずだから、誰でもいいのかと思ってた」
「……うん、ごめんね」
女子が静かに去っていき、俺もさっさと退散しようとそーっと立ち上がる。
「瀬川くん、盗み聞き?」
声をかけられてびくっと肩が震え、恐る恐る振り返ると、にこやかな笑みを張り付けている音無が手招きしていた。
ため息をついて、どすっと音無の隣に座る。
「……悪かった。聞くつもりはなかったんだけど」
さっき自販機で買ったサイダーを手渡すと「ありがとう」と笑って受け取った。
「……さっきの、来るもの拒まずっていうのは」
「あぁ、中学の頃は断るのが面倒で、告白されたらとりあえずつき合ってたんだけど、長続きしなくてすぐに別れちゃってたから……ちゃんと好きになれなくて相手を傷つけちゃうから、そういうのはやめようと思って」
「ふ〜ん、色々と大変だったんだな」
ペットボトルのフタを開けてスポーツドリンクを喉に流し込んでいると、音無が隣でふふっと笑みをこぼした。
「なんだよ?」
「いや、こういう話すると、羨ましがられたり嫌味を言われたり、からかわれたりするんだけど……瀬川くんは違うんだなと思って」
「……まぁ、受け取り方は人それぞれだけど。さっきの口ぶりからして、音無にとってはしんどいことなのかなって思ったから」
「そっか……やっぱりいいね、瀬川くんは」
「いい?」
「ふふっ、こっちの話」
「??」
なにが『いい』のかよくわからないままスポーツドリンクをごくごくと流し込む。
「それよりさ、俺、炭酸飲めないからそれと交換してよ」
「え、俺も飲めねぇんだけど」
「なんで買ったの……」
「適当だよ。音無の好きなやつわかんなかったから」
「まぁいいや。それ、ちょーだい」
「これ口つけちゃってるしな〜」
「俺はべつに大丈夫だけど」
「そうか?」
もう半分ほど飲んでしまったスポーツドリンクを音無に手渡す。音無はそれを少し口に含み、首をかしげた。
「ん?? なんかこれ甘くない?」
「へ? べつに普通だったけど」
「飲んでみてよ! ちょー甘いから」
促され、俺も少し口に含む。
「……ねっ? 甘いでしょ?」
「……そう言われたら甘い気もするけど」
「いや、異様に甘かったって」
確認のため、もう一口。
「……ん〜? よくわからん」
「えー!」