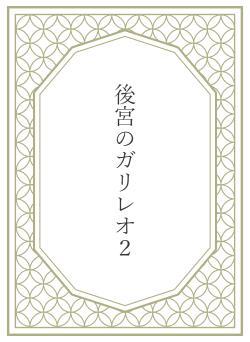「……そうか。白蓮妃の願いが、皇太后の蘇り……」
「そうと決まったわけではありません。すべてはあの女官の推測だと、本人もそう言っております」
恩雲に呼び出され、すべてを説明した冥焔は深く揖礼を捧げた。
しばしの沈黙が房を包み込む。恩雲は長椅子にゆったりと腰かけたまま、指先で玉佩を弄んでいた。その瞳は冥焔を通り越し、遠くを見つめている。
「彼女は、皇太后の女官だった。そしてお前を知っていたということなんだな」
「おそらく。でなければ……」
冥焔は言葉を呑み込んだ。
冥焔が冥焔ではなかったとき、白蓮妃と直接の面識はなかったはずだ。しかし、同じ宮城内で生活していればおのずとその存在を感じることもあったのだろう。白蓮妃が皇太后のお気に入りだったのなら、なおのこと。
「冥焔」
恩雲が気づかわしげに声をあげたので、冥焔は「大丈夫だ」と首を横に振った。
白蓮妃に傷を抉られ、目の前が真っ暗になった。しかし、そこから救い上げてくれた者がいる。
(救われたと、思いたくはないがな)
あの小憎らしい、生意気な、だらしのない、目つきも口も悪い、そして不敬極まりない女官のことを考えると、なぜか自分が自分でないような気持ちになる。どうしてここまで心を乱されるのかと悩み、そして延々と考え続けてしまう事実も、甚だ不本意なのである。
冥焔の表情をじっと見ていた恩雲は、なにを思ったのだろうか、にやりと笑った。
「しかし、あの女官。麗麗は想定以上に使えたねえ。いち女官にしておくのはもったいない。そう思わないか」
「大家?」
突然、なにを言い出すのだろう。
「白蓮妃の死で上級妃がひとつ空いたというのもある。そのまま不在というのもなんだし、あの麗麗とやらを入れてみるのはおもしろいだろうなあ」
「おやめください!」
ぎょっと目をむいた冥焔は、慌てて口を開いた。
「あの女官は、ひとつのことにしか興味が向きません。そそっかしいですし、察するのも苦手です。房もものすごいありさまですし、口も悪いですし、ひとりでふらふらと夜出歩くのですよ。あんな者を妃だなんて!」
恩雲はからからと笑った。
「冥焔。ずいぶんとあの麗麗とやらを気に入ったんだね」
冥焔はそれこそ全力で拳を握りしめ否定する。
「気に入ってなどおりません!」
「ではなぜ、名で呼ばない」
皇帝の問いに、冥焔は咄嗟に黙り込んだ。
(名を呼ばない……?)
恩雲は、さらに畳みかけるように言葉を重ねる。
「深入りしないようにと、線を引くのは結構だ。けれど、そう思う時点ですでに深入りしているものだと、なぜ気づかないのかな」
(大家は、なにを言っているのだ)
深入りとはなんだ。線を引くとはどういうことだ。確かに、自分はあの女官の名を呼んだことはないが、しかし……。
だめだ、と冥焔はこめかみを押さえた。考え始めたら、またよくわからない感情が湧き上がってくる。この、焦りとも取れるような、妙な感覚はなんなのだろう。
「……わたくしには、わかりかねます」
冥焔の言葉に、皇帝は呆れたように息をついた。
「とはいえ、あの子をこのまま無位無冠というわけにもいかない。それだけあの麗麗には世話になった」
うーん、と天を仰いだ恩雲は、子どものような笑顔になった。
「では、こういうのはどうかな」
そして耳打ちされた冥焔は、再び目をむくこととなる。
「本気ですか」
「本気だとも」
恩雲は砕けた顔でかかと笑い続けた。
「お願いしますね、哥哥」
冥焔はじろりと恩雲をにらんだ。
「哥哥は、おやめください、大家」
「そうと決まったわけではありません。すべてはあの女官の推測だと、本人もそう言っております」
恩雲に呼び出され、すべてを説明した冥焔は深く揖礼を捧げた。
しばしの沈黙が房を包み込む。恩雲は長椅子にゆったりと腰かけたまま、指先で玉佩を弄んでいた。その瞳は冥焔を通り越し、遠くを見つめている。
「彼女は、皇太后の女官だった。そしてお前を知っていたということなんだな」
「おそらく。でなければ……」
冥焔は言葉を呑み込んだ。
冥焔が冥焔ではなかったとき、白蓮妃と直接の面識はなかったはずだ。しかし、同じ宮城内で生活していればおのずとその存在を感じることもあったのだろう。白蓮妃が皇太后のお気に入りだったのなら、なおのこと。
「冥焔」
恩雲が気づかわしげに声をあげたので、冥焔は「大丈夫だ」と首を横に振った。
白蓮妃に傷を抉られ、目の前が真っ暗になった。しかし、そこから救い上げてくれた者がいる。
(救われたと、思いたくはないがな)
あの小憎らしい、生意気な、だらしのない、目つきも口も悪い、そして不敬極まりない女官のことを考えると、なぜか自分が自分でないような気持ちになる。どうしてここまで心を乱されるのかと悩み、そして延々と考え続けてしまう事実も、甚だ不本意なのである。
冥焔の表情をじっと見ていた恩雲は、なにを思ったのだろうか、にやりと笑った。
「しかし、あの女官。麗麗は想定以上に使えたねえ。いち女官にしておくのはもったいない。そう思わないか」
「大家?」
突然、なにを言い出すのだろう。
「白蓮妃の死で上級妃がひとつ空いたというのもある。そのまま不在というのもなんだし、あの麗麗とやらを入れてみるのはおもしろいだろうなあ」
「おやめください!」
ぎょっと目をむいた冥焔は、慌てて口を開いた。
「あの女官は、ひとつのことにしか興味が向きません。そそっかしいですし、察するのも苦手です。房もものすごいありさまですし、口も悪いですし、ひとりでふらふらと夜出歩くのですよ。あんな者を妃だなんて!」
恩雲はからからと笑った。
「冥焔。ずいぶんとあの麗麗とやらを気に入ったんだね」
冥焔はそれこそ全力で拳を握りしめ否定する。
「気に入ってなどおりません!」
「ではなぜ、名で呼ばない」
皇帝の問いに、冥焔は咄嗟に黙り込んだ。
(名を呼ばない……?)
恩雲は、さらに畳みかけるように言葉を重ねる。
「深入りしないようにと、線を引くのは結構だ。けれど、そう思う時点ですでに深入りしているものだと、なぜ気づかないのかな」
(大家は、なにを言っているのだ)
深入りとはなんだ。線を引くとはどういうことだ。確かに、自分はあの女官の名を呼んだことはないが、しかし……。
だめだ、と冥焔はこめかみを押さえた。考え始めたら、またよくわからない感情が湧き上がってくる。この、焦りとも取れるような、妙な感覚はなんなのだろう。
「……わたくしには、わかりかねます」
冥焔の言葉に、皇帝は呆れたように息をついた。
「とはいえ、あの子をこのまま無位無冠というわけにもいかない。それだけあの麗麗には世話になった」
うーん、と天を仰いだ恩雲は、子どものような笑顔になった。
「では、こういうのはどうかな」
そして耳打ちされた冥焔は、再び目をむくこととなる。
「本気ですか」
「本気だとも」
恩雲は砕けた顔でかかと笑い続けた。
「お願いしますね、哥哥」
冥焔はじろりと恩雲をにらんだ。
「哥哥は、おやめください、大家」