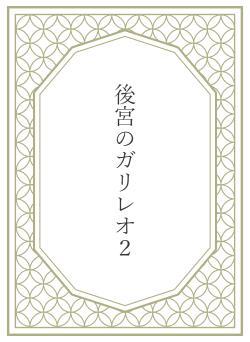「おい! 起きろ! 起きろ、女官!」
ぐえっと腹部を強く押されて、同時に苦い液体が喉元からせり上がる。
麗麗ははっと目を開けた。視界いっぱいに広がったのは、冥焔の顔だ。その顔がやけに近い。というか、これ、腕に抱かれてはいやしないか。
「めい……え……」
「しゃべるな!」
あろうことか、冥焔は麗麗の口の中に指を突っ込んだ。そのまま麗麗の体を下に向け、ぐいぐいと喉の奥を押してくる。
生理的な反応で、思わずえずいた。と同時に、公共の電波では虹色で表現されるような、つまり、お見せできないものがおろろろと口からまろび出た。
冥焔がほっと息をつくのが耳元で聞こえる。
「水だ。口をゆすげ」
休むことなく水袋を口の中に突っ込まれる。うっと飲みそうになるところをこらえて水を口に含むと、うえっともう一度吐き出した。
同じことを何度か繰り返して、ようやく解放された。いなや、体を抱え上げられる。なにをするのだと思うものの、体が言うことを聞かない。おとなしく運ばれていると、房の長椅子へとそっと横たえられた。
胃はちくちくするし、喉は焼けたように痛い。視界が回り、じっとしているだけでも気持ち悪い。
冥焔は相変わらずの仏頂面で、麗麗を見下ろしていた。
「気分はどうだ」
「……最悪です」
そこでようやく、麗麗は自分の置かれている状況に目が行った。
「私、生きてるんですね……」
声ががらがらだ。
「そこの、吐き痕はお前か」
「……たぶ、ん」
茶を口に含んで、すぐに吐き出した。その痕が床にしっかり残っている。
「毒が回る前に大方吐き出したというところか。上出来だ」
そこで、麗麗ははたと気づく。
「冥焔様は、なぜ、ここに」
ようやく周りの状況がわかってきた。
ここは白蓮妃の房である。毒を飲まされた麗麗はその場に放置されていたらしい。灯りの入っていない房は薄暗く、今が朝なのか夜なのか、それすらもわからない。
「今、いつですか。星送りの儀は……? 白蓮妃は、どこへ……」
「一気にしゃべるな」
冥焔は、恐ろしいほど真剣な顔をしている。
「白蓮妃が、先日の歩揺の出所だったのだ」
「歩揺……って、あの、毒の!?」
「そうだ。端的に話すぞ。今朝、手のものから報告があった」
そうして冥焔が語った内容によると、怪異でおびえた妃や女官に歩揺を渡していたのは白蓮妃であることが判明したという。『身を守るために常に身につけているように』と言葉を添えて。そして、『決して人に言わぬように』と、『言えば効力を失う』と告げていたのだそうだ。
親しい者に贈るときにも、『決して出所を教えてはいけない』と念を押していたらしい。
(あの、謁見……!)
麗麗は目を見開いた。
白蓮妃の房の前に並んでいた人たちは、房から出るときになにかを大切そうに握りしめていた。それが、毒の歩揺だったのだ。
「大家が白蓮妃を捕らえよと密命を下された」
「密命……」
「ああ。星送りの儀は、今夜だ。ただでさえ予言騒動で不穏な空気にもかかわらず、白蓮妃の捕縛が公となれば、再び混乱が起こる。それで、手のものと急ぎ月魄宮へと出向き……」
冥焔はそこで一度言葉を句切った。眉間に深いしわを刻み込み、険しい息を吐く。
「……肝が冷えたぞ」
「へっ」
「来てみたら、白蓮妃は房に籠もり、人払いをしているという。そして、いつもちょろちょろしているお前がどこにも見当たらない。大家の命を持って無理やり乗り込んでみたら、白蓮妃の姿は見えず」
冥焔はそこでようやく、麗麗の顔を正面から見た。
「お前が、ここでぶっ倒れていたというわけだ」
恐ろしいほど真剣な表情だった。見れば、額にはうっすらと汗をかき、深衣はぐちゃぐちゃに乱れている。いや、それよりも……。
「冥焔様……?」
なぜ、そんな目をするのだろう。まるで置いていかれるのを恐れている子どものような目だ。初めて見る表情に、麗麗は胸が騒ぐ。
冥焔は視線を断ち切るように、さっと顔を背けてしまう。
「刻がない。このまましばらく休め。俺は、行く」
「……行く?」
「白蓮妃をすぐに押さえなくては」
「ちょっ……冥焔様!」
麗麗はそのまま踵を返そうとした冥焔の袖をつかんだ。
「押さえるって、白蓮妃を捕まえるってことですよね!? だったら、私も行きます」
「馬鹿な」
振り返った黒々とした瞳が、麗麗を鋭く射貫いた。
「毒を食らい、ろくに動けず歩くのもままならないくせに、なにを言う」
「でも!」
「だめだ」
ぐっと麗麗は唇を嚙んだ。
あのときと似ている。歩揺の毒性を確かめるために冥焔が獄へ行くと言った際、興味本位でついていこうとした麗麗を、冥焔が厳しい言葉で止めたのだ。
冥焔の言うことは正しい。今だってそうだ。自分が行ったところでただの足手まといにしかならないだろう。けれど、しかし。
「冥焔様。私を連れていってください」
「離せ。邪魔だ」
突き放すような言葉とともに、冥焔は麗麗の手を振り払う。踵を返し、房の外へと足を向ける。
(行かせるものか!)
麗麗は歯を食いしばり、叫んだ。
「白蓮様は私を生かしました!」
冥焔は驚いたように足を止めた。
「ふたりきりでした。誰もいませんでした。殺そうとしたのなら、刃物でもなんでも使えたんです。そもそも、叫ぶだけでよかった。女官が紛れ込んだ、命を狙われたとでも騒げば、私を簡単に処刑できた。でも、白蓮様は毒を使ったんです!」
言葉があふれて止まらない。喉の痛みも忘れて、麗麗は叫んだ。
「確実に殺すつもりなら、すぐにわからぬように毒を盛ればよかったはずです。遅効性の毒なら吐き出す心配もなく、私は房を去ったあとに死んでいたでしょう。でも、あの方は即効性の毒を使った。しかも、わざと刺激の強いものを混ぜて、私が吐き出せるように仕向けたのです。致死量に達しないよう、加減までして──!」
話しながら、麗麗は自分がこれほど熱くなっている理由がわからなかった。
自分に毒を盛った相手だ。いつもの麗麗なら面倒事には関わりたくないと、冥焔の指示に従っていただろう。けれど、今は引けない。
「私は、白蓮様の意を知らなければなりません。なぜ毒を盛ったのか、毒を盛ったにもかかわらず、なぜ私を生かしたのか……なぜ……」
なんとしても自分の耳で、白蓮妃の申し開きを聞きたかった。
無性に泣きたくなって、泣いてたまるかと服の裾をつかんで耐える。
「お願いします、冥焔様。白蓮様に会わせてください。お願いします……っ」
耐えきれなかった涙が、ひと粒麗麗の頰を伝った。
ややあって、重いため息が聞こえた。
「白蓮妃は処刑される。減刑などもってのほかだ」
「……わかってます」
歩揺の出所が白蓮妃だと冥焔は明言した。皇帝の命が出ているということは、裏も取れているのだろう。彼女を待つのはどんなに低く見積もっても極刑だ。
「それでも会いたいというのか」
「はい」
きっぱりと宣言する。心に迷いはなかった。白蓮妃に会いたい、会って理由を聞きたい。
冥焔はうなずくと、麗麗の体を長椅子からすくい上げた。
「後悔するなよ」
「……ありがとうございます」
聞き遂げてもらえたのだ。安堵して、麗麗は宦官の腕に体を預けた。
外に出ると、すでに昼を回っているようだった。星送りの儀の準備のためか、宮の周辺にはほとんど人がいない。人気のない宮は異様な雰囲気である。
白蓮妃を押さえると言っていたのでどうするのかと思ったが、冥焔は心当たりがあるようだ。抱え上げた麗麗の体重など気にする様子もなく、さくさくと宮から出ていってしまう。
冥焔は足を東へと向けた。後宮の東側には、麗麗は行ったことがない。
「お前と先日の夜に話したあと、一連の怪異についてしかるべき調査を行った」
冥焔はぽつりと言葉を落とした。
「はい」
「泣き声は、やはり風穴だ。訴え出た妃の宮の近くに竹林があって、その竹のひとつに細い穴が開いていたのだ。明らかに人の手が入った穴だった」
「……はい」
「赤子の声が聞こえる件。あれは、お前の言う通り獣で間違いない。床下からは糞が見つかった。それと同時に……床下に餌が撒いてあったのも、見つけたぞ」
この話は、どこに向かっているのだろう。
「水が赤くなった件。お前の推測通り、赤さびだと判明した。しかし、水路に異変はなく、代わりに古い鉄器具が沈められていた。そして」
冥焔はひとつ息を吸って、重々しく吐いた。
「妃や女官が訴えを起こす前、これらのすべての場所を、白蓮妃の女官が訪れていた事実を確認した」
「それって、つまり……」
「一連の怪異についても、白蓮妃が意図的に起こしていた可能性が高い。……お前の、ガリレオとやらの信念に従ってみた結果、これらのことが明らかになったのだ」
まるで託宣を告げるかのような声色で冥焔はきっぱりと言い切った。
麗麗は顎に手を添えて考えた。
人の手で怪異が作られていた。とすると、もしや。
「あの、明林の──呪いの房も、もしかして……」
「瑛琳妃の、亡くなった女官か」
硬質な声が、麗麗の真上から降ってくる。
「はい。中央には、魔除けとして窓を塞ぐ風習はありません。けれど、もし影響力のある人が、『魔をよけるために』と助言したのだとしたら……」
瑛琳妃や今残っている三女官は、〝女官たちにせがまれて〟窓を塞いだのだと言っていた。その女官はおびえていたそうだ。おそらく、救いを求めて白蓮妃と繋がったのだろう。そして、窓を塞ぐようにと助言を受けた。
その結果、首を絞められたという事件に繋がったのだとしたら、やはりこれも作られた怪異になりはしないか。
麗麗の言葉に、冥焔はうなずく。
「白蓮妃だろうな、おそらくは」
「やはり、そうですか」
それからしばらくは、無言だった。さくさくと冥焔は歩を進める。麗麗もおとなしくその腕に抱かれたまま、どれほど歩いたのだろうか。
視線の先に、石造りの門が見えてくる。あれは……。
「廟……」
廟は、霊を祀る場所だ。東側ということは、おそらく祖先を祀るためのもの。
門の前で足を止め、冥焔は麗麗を地面へと下ろした。
「歩けるか」
「はい」
ややよろけはするが、大丈夫そうだ。
「では俺の後ろにつけ。油断するな」
冥焔はそう言うと、門に向き直った。
「俺の考えが正しければ、白蓮妃はここにいる」
両開きの扉が静かに、ため息をつくかのようにゆっくりと開いて、ふたりを飲み込み口を閉じる。
中は灯りが焚かれていた。貴人の白い襦裙が、揺らめく炎に照らされぬるりと光る。
まるで闇に咲く一輪の花のような後ろ姿だ。一心に祈りを捧げているように見える。麗麗と冥焔に気づかないはずはないが、しかし、顔を上げようともしない。
「なにか御用?」
涼やかな声である。
「言い逃れができると思わないでいただきたい」
冥焔が一歩前に進み出るも、白蓮妃は変わらず後ろを向いたままだ。
「白蓮妃。あなたのすべての行いは、大家の耳にも届いている。おとなしく一緒に来てもらおう」
長い沈黙のあと、白蓮妃はふっとかすかに笑ったようだった。
「断らせていただくわ」
その言葉とともに、ゆっくりと白蓮妃は振り返った。まるで着ている白い襦裙が闇に溶けて流れ出すかのような、緩慢な動きだ。
紅く縁どられた唇が目に留まる。口布が外されているのだ、と麗麗はそのとき初めて気づいた。凄まじいまでの美貌が、炎の赤に照らされている。魔性の笑みがふたりを捕らえて弧を描く。
冥焔は一歩も譲らず、貴人から目を離さない。
「断れるとお思いか」
それから冥焔が語ったのは、麗麗が白蓮妃の宮で耳にしたのと同じ真実だった。
一連の怪異の裏に、白蓮妃の女官がいたこと。
怪異を恐れる者たちに、毒のある歩揺を配っていたこと。
しかし、それらすべてを聞いても、白蓮は顔色ひとつ変えなかった。
「……なるほど」
赤い唇が蠱惑的に弧を描く。
「では、聞かせていただきましょう。なぜ私がそのようなことを?」
美しい毒の花がささやくように、白蓮妃は嫣然と微笑む。
冥焔は一歩、白蓮妃へと近づく。足音が廟の石床に、乾いた音を刻んだ。
「……あなたが、あの方──亡き皇太后の女官だからだ」
(え!?)
ぎょっとして、麗麗は思わず冥焔を仰ぎ見る。冥焔は視線を逸らさず、にらみつけるように白蓮妃を見つめている。
「皇太后亡きあと、後宮が解体された際、皇太后付きの女官たちは後宮を出たと記録されている。その中にはもちろん、あなたもいたはずだ」
白蓮妃は微動だにしない。ただ静かに冥焔を見つめるその瞳は、底なしの深さをたたえている。
「しかし、あなたは自分を売ったのだ。皇太后の女官であった事実を公にし、上級妃としての教養や振る舞いをすでに習得していると、娘を欲しがる官吏に主張した。そして名を変え、官吏の親戚として入内した」
「証拠は」
白蓮妃は、あくまで優雅に、微笑を崩さぬまま問う。
「娼館だ」
冥焔の声は低く、静かだった。
「官吏──あなたの生家とされている氏が、妓女を身請けしたという記録があった。妓女の念書と、白蓮妃、あなたの筆跡が一致している」
「…………」
無言のまま、白蓮妃は冥焔を見つめている。笑みの形は崩れていない。
「そしてもうひとつ。例の皇太后の女官と、身請けされた妓女の特徴だ。どちらも鋭い歯──虎牙の持ち主であり、その左側のみが欠けていると記録がある。……白蓮妃。もしあなたが否定するのであれば、口を開けて見せてはくれないか」
白蓮妃は微笑んだまま、ただじっと冥焔を凝視していた。炎の光に照らされたその美貌は、もはや人のものではない。
「さらに言うならば、あなたが今ここにいることが答えだ」
冥焔は、最後の言葉を落とすように告げた。
「この廟は、亡き貴人を祀る廟。その中には皇太后も含まれている」
炎がまた、ゆらりと揺れた。
「皇太后の女官は、誰もが忠実だった。あなたは皇太后の〝呪い〟を実行しようとしたのではないか。〝後宮に住まう女すべての死を願う〟……その呪いを真実にするために」
廟の中は静まり返っている。
ふ、と貴人の口元から小さく吐息が漏れた。その吐息はやがて声を伴い笑い声へと成長する。口元で、鋭い歯がきらりと光った。左側が欠けた虎牙をむき出して、白蓮妃は大笑する。おかしくて仕方がないというように。そして、ふうと息をつき、目尻にたまった涙をぬぐった。
「認めましょう。確かに私は、皇太后様の女官だった者。けれど、それと今回の件になんの関係があるの?」
「なんだと?」
冥焔が気色ばむ。白蓮妃はいっそ朗らかと言えるような声色で告げた。
「私は後宮での暮らしが忘れられなかったのよ。どうせなら女官ではなく、妃として、思う存分贅沢をして暮らしたかった。そのために、官吏と取引をしたにすぎないわ。それのどこが悪いのかしら。皆やっていることでしょう」
「……白蓮妃」
冥焔の咎めるような声は、白蓮妃には一切届かない。楽しそうに、朗々と話し続ける。
「怪異の裏に私の女官がいたと言ったわね。けれど、それが偶然でないとなぜ言い切れるの? 確かに私は不安を訴える者たちに、歩揺を渡したわ。しかし、それは女官を介して渡していただけ。私本人の意志で毒を入れたのだという証はあるのかしら」
白蓮妃はそこでふと口を閉じ、ややあって、もう一度開いた。
「私がやったという証を、見せなさい」
白蓮妃は微動だにせず、ただ冥焔をまっすぐに見つめている。その瞳には、動揺もおびえも見当たらない。圧倒的勝者の余裕すら漂わせていた。
冥焔は口を閉ざしている。先ほどまであれほど白蓮妃を追い詰めていたはずなのに、言葉を返せないのだ。
麗麗にはわかっていた。今までの話に物的証拠は存在せず、すべてが状況証拠のみだ。
確かに、後宮では証拠など不要である。皇帝の命令ひとつですべてが決まる。しかし、白蓮妃はそれを許さぬと言っている。
「できるわけがないわね、お前には」
白蓮妃は唇の端に酷薄な笑みを刻んだ。
「滑稽ね、冥焔。……いえ、別の名があったわね。その名を、今ここで呼んでみようかしら。そこの麗麗にでも聞かせてやりなさい。お前の本当の名を」
「……!」
冥焔の顔色が変わった。
「お前が……いいえ、お前たちが今、必死に隠している事実を、私が知らぬとでもお思いかしら」
「なんのことか、わからぬな」
冥焔の瞳に宿るのは怒りではない。焦りだ。
白蓮妃は容赦しない。まるで獲物の急所を知り尽くしているかのように、愉悦の笑みを浮かべながらさらに刃をねじ込んだ。
「冥焔。お前はあのときから一向に変わらない。だから〝天意〟を失ったのよ」
こつん、と絹の沓が石畳を鳴らす。
「風にも天にも背を向け、己に都合のいいものだけを天意と呼び、聞きたいことしか聞かず、見たいものしか見ず、あげく、ひとたび目を背けたものには二度と目を向けようともしない。それが、お前の〝天意〟」
吐き捨てるような、侮蔑に満ちた言葉が廟にじわりと響いて溶ける。
「だからあんなことになったのよ。すべては、お前のせい。お前が全部を壊したの。皇太后様も──」
「やめろ!」
冥焔の顔が、はっきりとゆがんだ。手が小さく震え、唇は引きつっている。
「やめろ……っ」
冥焔は叫んだ。それは怒鳴り声ではない。叫ぶことで、なにかを押しとどめようとする、必死の悲鳴だ。
その瞬間、麗麗はすべてを悟った。
冥焔と白蓮妃の因縁や、一連の思わせぶりな会話も、彼女にとってはどうでもいい。けれど、宦官・冥焔という男が〝崩壊〟していくさまは見たくなかった。
あれほど偉そうに、堂々としていた宦官の顔色は、青を通り越して白い。手は衝撃に打ち震え、視線は揺れ、今にも崩れ落ちそうなほどの衝撃を受けている。
そして、それこそが白蓮妃の狙いなのだ。
(……むかつく)
彼女の一挙手一投足が、宦官の心を抉る。冥焔が絶対に触れてほしくない過去を容赦なく引きずり出して、嬲っている。執拗に、冷酷に、迷いなく。
(むかつくっ……!)
麗麗の心の中に灯もった炎が、勢いよく燃え上がった。
(白蓮様は、冥焔様を傷つけたいだけなんだ)
喉が熱い。拳が震え、爪が手のひらに食い込んだ。その痛みで意識がはっきりとした。
(黙ってなんていられるわけ、ない)
どんな理由があろうとも、触れられたくない過去はある。その傷を無理やり抉られているさまを見るのは、たとえ鬼上司とてまっぴらごめんだ。
「お待ちください!」
心の火に従って、麗麗は声を張り上げていた。廟に響いた声は、自分でも驚くほど大きい。うわんっと反響する声に、冥焔も白蓮妃も同時にこちらを振り向いた。
ふーっと鼻息も荒く、麗麗は仁王立ちになった。頭の先から爪の先まで怒気ではちきれそうだ。
(……証拠がないなら、作ればいい)
麗麗は、憤怒に任せて口を開いた。
「証ならあります」
「……あら」
白蓮妃がことりと首をかしげた。表情が抜け落ちた顔は麗麗を捕らえ、その唇だけが不自然につり上がる。
「聞かせてもらいましょうか」
「是」
冥焔の視線を感じる。こちらを案じているのがわかる。麗麗は大丈夫だと言うように、口の端に笑みを浮かべてみせた。
「……白蓮妃がお持ちの薬棚には札が貼ってありましたね。その中には毒物もあったと存じます。あれを使ったのではないですか」
「まさか、雌黄を持っていただけで、証? あれは顔料として使っているの。絵を描くのが好きなのよ」
麗麗は負けるかと笑みを深くする。
「いえ。白蓮様は絵をお描きにはなりません。確かに雌黄は顔料ではありますが、もし絵をお描きになるのだとしたら、他の色もなければ不自然です。そうですね。例えば青金石、辰砂、孔雀石……。あの房にはありませんね」
頭の中で、生前よく読んでいた『鉱物辞典』を反芻しながら、つらつらと並べてみせる。鉱石の中には、絵の具の材料になるものもある。しかし、あの薬棚には雌黄以外の名はなかったはずだ。
「雌黄一色を使っているのよ」
「雌黄は、黄色。禁色です。主上以外、誰も使えない色ですね。鉱石として鑑賞するだけならいざ知らず、黄のみで絵を描くだなんて不敬にあたります。白蓮様のお立場なら、当然わきまえていらっしゃるはず」
白蓮妃はなにも答えない。ただ、わずかに顎を上げたまま、麗麗をにらみ返していた。
「白蓮様」
麗麗はそこで、一度言葉を句切る。
「なぜ、白蓮様は雌黄が証拠だという前提で、話されているのでしょう」
「……なんですって?」
「私たちは、歩揺に毒が含まれていたということしかお話していないはずなのに」
「!」
白蓮妃の指先がわずかに動いた。冥焔の、息を呑む音が耳に届く。
「毒の話のあとに、お前が薬棚の話をしたからよ。それで察しただけ」
「でも、あの薬棚には、他に毒になるようなものもありましたよね。大黄とか、治葛も」
麗麗の反論に、冥焔がぎょっとした顔で声をあげた。
「治葛だと……!? 猛毒ではないか」
「はい。でも、治葛は下薬──治療薬でもあるんです。熱を下げたり、咳を止めたり。だから、薬棚にあってもおかしくはないんです」
ちらりと冥焔を見やり、麗麗はにこりともせず言葉を重ねた。
「冥焔様が今、毒だと連想されたように、普通は治葛と聞けば毒を思い浮かべる。それなのに、白蓮様は雌黄をご自身で持ち出された。それはつまり、最初から雌黄が自分にとって致命的だと、よくご存じだったということです」
白蓮妃は、表情のそげ落ちた顔で麗麗を見据えている。
「言い逃れはできません、白蓮様」
声が、廟に響き渡る。
「これにて、証明完了です」
廟の中に、静寂が満ちる。
白蓮妃はなにも言わない。ただ、静かに麗麗を見つめ続ける。その沈黙は永遠にも思えるほど長く、張り詰めている。
けれど、それはおそらく一瞬のことだったのかもしれない。ふ、と赤く色づいた唇が開かれた。
「慈悲などかけず、殺しておけばよかった」
乾いた笑みが浮かぶ。
「よく回る口に、その知識。あまりにも危険だと感じたわ。だからこそ、儀式が始まる前にお前を始末しなければと思ったのに。……お前を惜しんだ自分が憎い。お前とあの人を会わせたかった。叶うことなら三人で、一緒に話をしたかった……。ほんの少しの慈悲と希望を持ったのが、私の敗因ね」
それはあきらめの笑みであり、皮肉の笑みであり、どこか安堵にも似た、壊れた微笑だった。
白蓮妃は居住まいを正す。
「すべて、私がやったことよ」
涼やかな瞳は穏やかな色を浮かべ、引き結ばれた唇は梅花のように艶やかだ。姿勢を正し、凜としたまなざしを向ける白蓮妃は、とても麗しかった。
ぽつり、ぽつりと口を開く。
変わり者として、いじめられていた。皇太后に引き立てられ、側仕えになった。皇太后だけが自分の味方だった。そして──。
「皇太后様は、自死なさった……そう世間は信じているらしいわね」
白蓮妃は薄く笑い、冥焔に視線を向けた。
「けれど、私は騙されない。あの方は処刑されたのよ」
きっぱりと言い切ると、白蓮妃は麗麗に目を向ける。
「麗麗、お前は、蘇りの証があれば信じると言ったわね」
(……なんで?)
麗麗の額を冷たい汗が伝う。どうして、そんな穏やかな表情で、声でいられるのだろう。このあと彼女を待っているのは極刑だというのに、なぜ。
「では検証をしましょう。鬼求代が成功するか、否か。お前の目で確かめなさい」
(鬼求代……!?)
確か、死者が蘇るために生きている者を身代わりにしなければならないという律のことだ。なぜ、今その話が出てくるのだろう。
白蓮妃は微笑むと、結い上げた髪に挿していた歩揺をひとつ、引き抜いた。
「冥焔。お前たちの〝天意〟では、私は裁けない」
ぞわっと、麗麗の背中を嫌な予感が駆け上る。
(待って、まさか)
「今夜は星送りの儀。亡き者の魂を慰める夜。私は、あの方をこの手で迎えに行きましょう」
白蓮妃は唇に言葉を乗せる。
「──此生无憾」
「やめろ!」
弾かれたように、冥焔が床を蹴った。一歩遅れて麗麗も後を追う。白蓮妃まで数歩の距離、だがしかし、その数歩が絶望的に遠かった。
歩揺が揺れる。炎に照らされ、ぬらぬらと光っている。
妃は歩揺を両手で握り、鋭い切っ先を喉元に向けた。そして、不気味に輝く光が流星のように──妃の喉を貫いた。
「あっ……」
嫌な音がした。前のめりで倒れる妃を、冥焔が受け止める。
「びゃ……白蓮様!」
「大丈夫だ、ぎりぎり骨で止まった! 侍医を……っ」
そう叫ぶ冥焔の唇に、白蓮妃の白い指がすっと添えられた。まるで黙れと言うかのように。
喉をついたせいで、気道も傷ついたのだろうか。かすれた声で、白蓮は笑う。
「ざんねん、ね」
「まさか、歩揺に毒を……!?」
体を痙攣させた白蓮を前に、冥焔の顔が青ざめる。駆け寄った麗麗も、どうすればいいのかわからない。
胃に入った毒ならば吐かせればいいが、血から入った毒は一切の猶予なく体内を駆け巡る。
「白蓮様……!」
差し伸べた麗麗の手を、白蓮が握った。
紅を掃いた唇が、うっすらと開く。なにかを言おうとしていることに気づき、麗麗は急いで白蓮妃の口元に耳を寄せた。
「検証……を……お願い……ね」
(なに言ってんの……!)
身を切られるほどの痛みが麗麗の心を襲った。
喉の奥が熱いのに、体の中心が冷えている。泣きたいのか怒りたいのか、麗麗にはわからない。ただ激しい感情が体中を駆け巡り、声にならない叫びとなって麗麗の口から迸る。
この世界に来て、麗麗は特に不満もなく暮らしていたと思っていた。けれど、それは勘違いだったのだ。
白蓮妃は、唯一麗麗と同じ熱を持つ仲間だった。言葉を交わすたびに、心が沸き立った。たった二回の邂逅だったけれど、それで十分だ。
師であり、友であり、そして、同胞だった。
やがて白蓮妃の体の痙攣が止まる。ぐにゃりと投げ出された手足からは、血の色が消えている。
死にゆく妃の顔は、ぞっとするほど美しかった。
「……終わりだ」
冥焔の声は低く、かすれていた。その表情にやりきれなさと痛ましさをにじませながら、事切れた白蓮妃をそっと床に横たえる。
「女官。行くぞ。大家に報告を──」
「いえ、まだです」
麗麗は手の甲で涙を乱暴にぬぐった。泣いている暇はない。白蓮妃は取り返しのつかないことを始めようとしていると気づいたのだ。
「冥焔様。白蓮様は……鬼求代を検証しようとしています!」
「なんだって?」
冥焔は目を見張った。
もはや一刻の猶予もない。急がなければ、と麗麗は足を廟の戸へ向ける。
「あの予言です。『流れ星が墜ち、天の刑罰が下される』。これは、星送りの儀でたくさんの人が死ぬということですよね?」
「そうだ。しかし、白蓮妃は今、ここで死んだぞ。これ以上なにも起きるはずが──」
「天灯です……!」
「はっ?」
「白蓮様は、天灯を自ら作っていらっしゃいました。そこに、もし毒が仕掛けられているのだとしたら……!」
冥焔の顔色が変わった。
「行くぞ、女官!」
「はい!」
来た道を急いで駆け下り、廟の門を出た瞬間──。
「しまった、もう始まっていたか!」
西の空に天高く、おびただしい量の天灯が舞い上がっている。
「急ぎましょう……!」
ぐえっと腹部を強く押されて、同時に苦い液体が喉元からせり上がる。
麗麗ははっと目を開けた。視界いっぱいに広がったのは、冥焔の顔だ。その顔がやけに近い。というか、これ、腕に抱かれてはいやしないか。
「めい……え……」
「しゃべるな!」
あろうことか、冥焔は麗麗の口の中に指を突っ込んだ。そのまま麗麗の体を下に向け、ぐいぐいと喉の奥を押してくる。
生理的な反応で、思わずえずいた。と同時に、公共の電波では虹色で表現されるような、つまり、お見せできないものがおろろろと口からまろび出た。
冥焔がほっと息をつくのが耳元で聞こえる。
「水だ。口をゆすげ」
休むことなく水袋を口の中に突っ込まれる。うっと飲みそうになるところをこらえて水を口に含むと、うえっともう一度吐き出した。
同じことを何度か繰り返して、ようやく解放された。いなや、体を抱え上げられる。なにをするのだと思うものの、体が言うことを聞かない。おとなしく運ばれていると、房の長椅子へとそっと横たえられた。
胃はちくちくするし、喉は焼けたように痛い。視界が回り、じっとしているだけでも気持ち悪い。
冥焔は相変わらずの仏頂面で、麗麗を見下ろしていた。
「気分はどうだ」
「……最悪です」
そこでようやく、麗麗は自分の置かれている状況に目が行った。
「私、生きてるんですね……」
声ががらがらだ。
「そこの、吐き痕はお前か」
「……たぶ、ん」
茶を口に含んで、すぐに吐き出した。その痕が床にしっかり残っている。
「毒が回る前に大方吐き出したというところか。上出来だ」
そこで、麗麗ははたと気づく。
「冥焔様は、なぜ、ここに」
ようやく周りの状況がわかってきた。
ここは白蓮妃の房である。毒を飲まされた麗麗はその場に放置されていたらしい。灯りの入っていない房は薄暗く、今が朝なのか夜なのか、それすらもわからない。
「今、いつですか。星送りの儀は……? 白蓮妃は、どこへ……」
「一気にしゃべるな」
冥焔は、恐ろしいほど真剣な顔をしている。
「白蓮妃が、先日の歩揺の出所だったのだ」
「歩揺……って、あの、毒の!?」
「そうだ。端的に話すぞ。今朝、手のものから報告があった」
そうして冥焔が語った内容によると、怪異でおびえた妃や女官に歩揺を渡していたのは白蓮妃であることが判明したという。『身を守るために常に身につけているように』と言葉を添えて。そして、『決して人に言わぬように』と、『言えば効力を失う』と告げていたのだそうだ。
親しい者に贈るときにも、『決して出所を教えてはいけない』と念を押していたらしい。
(あの、謁見……!)
麗麗は目を見開いた。
白蓮妃の房の前に並んでいた人たちは、房から出るときになにかを大切そうに握りしめていた。それが、毒の歩揺だったのだ。
「大家が白蓮妃を捕らえよと密命を下された」
「密命……」
「ああ。星送りの儀は、今夜だ。ただでさえ予言騒動で不穏な空気にもかかわらず、白蓮妃の捕縛が公となれば、再び混乱が起こる。それで、手のものと急ぎ月魄宮へと出向き……」
冥焔はそこで一度言葉を句切った。眉間に深いしわを刻み込み、険しい息を吐く。
「……肝が冷えたぞ」
「へっ」
「来てみたら、白蓮妃は房に籠もり、人払いをしているという。そして、いつもちょろちょろしているお前がどこにも見当たらない。大家の命を持って無理やり乗り込んでみたら、白蓮妃の姿は見えず」
冥焔はそこでようやく、麗麗の顔を正面から見た。
「お前が、ここでぶっ倒れていたというわけだ」
恐ろしいほど真剣な表情だった。見れば、額にはうっすらと汗をかき、深衣はぐちゃぐちゃに乱れている。いや、それよりも……。
「冥焔様……?」
なぜ、そんな目をするのだろう。まるで置いていかれるのを恐れている子どものような目だ。初めて見る表情に、麗麗は胸が騒ぐ。
冥焔は視線を断ち切るように、さっと顔を背けてしまう。
「刻がない。このまましばらく休め。俺は、行く」
「……行く?」
「白蓮妃をすぐに押さえなくては」
「ちょっ……冥焔様!」
麗麗はそのまま踵を返そうとした冥焔の袖をつかんだ。
「押さえるって、白蓮妃を捕まえるってことですよね!? だったら、私も行きます」
「馬鹿な」
振り返った黒々とした瞳が、麗麗を鋭く射貫いた。
「毒を食らい、ろくに動けず歩くのもままならないくせに、なにを言う」
「でも!」
「だめだ」
ぐっと麗麗は唇を嚙んだ。
あのときと似ている。歩揺の毒性を確かめるために冥焔が獄へ行くと言った際、興味本位でついていこうとした麗麗を、冥焔が厳しい言葉で止めたのだ。
冥焔の言うことは正しい。今だってそうだ。自分が行ったところでただの足手まといにしかならないだろう。けれど、しかし。
「冥焔様。私を連れていってください」
「離せ。邪魔だ」
突き放すような言葉とともに、冥焔は麗麗の手を振り払う。踵を返し、房の外へと足を向ける。
(行かせるものか!)
麗麗は歯を食いしばり、叫んだ。
「白蓮様は私を生かしました!」
冥焔は驚いたように足を止めた。
「ふたりきりでした。誰もいませんでした。殺そうとしたのなら、刃物でもなんでも使えたんです。そもそも、叫ぶだけでよかった。女官が紛れ込んだ、命を狙われたとでも騒げば、私を簡単に処刑できた。でも、白蓮様は毒を使ったんです!」
言葉があふれて止まらない。喉の痛みも忘れて、麗麗は叫んだ。
「確実に殺すつもりなら、すぐにわからぬように毒を盛ればよかったはずです。遅効性の毒なら吐き出す心配もなく、私は房を去ったあとに死んでいたでしょう。でも、あの方は即効性の毒を使った。しかも、わざと刺激の強いものを混ぜて、私が吐き出せるように仕向けたのです。致死量に達しないよう、加減までして──!」
話しながら、麗麗は自分がこれほど熱くなっている理由がわからなかった。
自分に毒を盛った相手だ。いつもの麗麗なら面倒事には関わりたくないと、冥焔の指示に従っていただろう。けれど、今は引けない。
「私は、白蓮様の意を知らなければなりません。なぜ毒を盛ったのか、毒を盛ったにもかかわらず、なぜ私を生かしたのか……なぜ……」
なんとしても自分の耳で、白蓮妃の申し開きを聞きたかった。
無性に泣きたくなって、泣いてたまるかと服の裾をつかんで耐える。
「お願いします、冥焔様。白蓮様に会わせてください。お願いします……っ」
耐えきれなかった涙が、ひと粒麗麗の頰を伝った。
ややあって、重いため息が聞こえた。
「白蓮妃は処刑される。減刑などもってのほかだ」
「……わかってます」
歩揺の出所が白蓮妃だと冥焔は明言した。皇帝の命が出ているということは、裏も取れているのだろう。彼女を待つのはどんなに低く見積もっても極刑だ。
「それでも会いたいというのか」
「はい」
きっぱりと宣言する。心に迷いはなかった。白蓮妃に会いたい、会って理由を聞きたい。
冥焔はうなずくと、麗麗の体を長椅子からすくい上げた。
「後悔するなよ」
「……ありがとうございます」
聞き遂げてもらえたのだ。安堵して、麗麗は宦官の腕に体を預けた。
外に出ると、すでに昼を回っているようだった。星送りの儀の準備のためか、宮の周辺にはほとんど人がいない。人気のない宮は異様な雰囲気である。
白蓮妃を押さえると言っていたのでどうするのかと思ったが、冥焔は心当たりがあるようだ。抱え上げた麗麗の体重など気にする様子もなく、さくさくと宮から出ていってしまう。
冥焔は足を東へと向けた。後宮の東側には、麗麗は行ったことがない。
「お前と先日の夜に話したあと、一連の怪異についてしかるべき調査を行った」
冥焔はぽつりと言葉を落とした。
「はい」
「泣き声は、やはり風穴だ。訴え出た妃の宮の近くに竹林があって、その竹のひとつに細い穴が開いていたのだ。明らかに人の手が入った穴だった」
「……はい」
「赤子の声が聞こえる件。あれは、お前の言う通り獣で間違いない。床下からは糞が見つかった。それと同時に……床下に餌が撒いてあったのも、見つけたぞ」
この話は、どこに向かっているのだろう。
「水が赤くなった件。お前の推測通り、赤さびだと判明した。しかし、水路に異変はなく、代わりに古い鉄器具が沈められていた。そして」
冥焔はひとつ息を吸って、重々しく吐いた。
「妃や女官が訴えを起こす前、これらのすべての場所を、白蓮妃の女官が訪れていた事実を確認した」
「それって、つまり……」
「一連の怪異についても、白蓮妃が意図的に起こしていた可能性が高い。……お前の、ガリレオとやらの信念に従ってみた結果、これらのことが明らかになったのだ」
まるで託宣を告げるかのような声色で冥焔はきっぱりと言い切った。
麗麗は顎に手を添えて考えた。
人の手で怪異が作られていた。とすると、もしや。
「あの、明林の──呪いの房も、もしかして……」
「瑛琳妃の、亡くなった女官か」
硬質な声が、麗麗の真上から降ってくる。
「はい。中央には、魔除けとして窓を塞ぐ風習はありません。けれど、もし影響力のある人が、『魔をよけるために』と助言したのだとしたら……」
瑛琳妃や今残っている三女官は、〝女官たちにせがまれて〟窓を塞いだのだと言っていた。その女官はおびえていたそうだ。おそらく、救いを求めて白蓮妃と繋がったのだろう。そして、窓を塞ぐようにと助言を受けた。
その結果、首を絞められたという事件に繋がったのだとしたら、やはりこれも作られた怪異になりはしないか。
麗麗の言葉に、冥焔はうなずく。
「白蓮妃だろうな、おそらくは」
「やはり、そうですか」
それからしばらくは、無言だった。さくさくと冥焔は歩を進める。麗麗もおとなしくその腕に抱かれたまま、どれほど歩いたのだろうか。
視線の先に、石造りの門が見えてくる。あれは……。
「廟……」
廟は、霊を祀る場所だ。東側ということは、おそらく祖先を祀るためのもの。
門の前で足を止め、冥焔は麗麗を地面へと下ろした。
「歩けるか」
「はい」
ややよろけはするが、大丈夫そうだ。
「では俺の後ろにつけ。油断するな」
冥焔はそう言うと、門に向き直った。
「俺の考えが正しければ、白蓮妃はここにいる」
両開きの扉が静かに、ため息をつくかのようにゆっくりと開いて、ふたりを飲み込み口を閉じる。
中は灯りが焚かれていた。貴人の白い襦裙が、揺らめく炎に照らされぬるりと光る。
まるで闇に咲く一輪の花のような後ろ姿だ。一心に祈りを捧げているように見える。麗麗と冥焔に気づかないはずはないが、しかし、顔を上げようともしない。
「なにか御用?」
涼やかな声である。
「言い逃れができると思わないでいただきたい」
冥焔が一歩前に進み出るも、白蓮妃は変わらず後ろを向いたままだ。
「白蓮妃。あなたのすべての行いは、大家の耳にも届いている。おとなしく一緒に来てもらおう」
長い沈黙のあと、白蓮妃はふっとかすかに笑ったようだった。
「断らせていただくわ」
その言葉とともに、ゆっくりと白蓮妃は振り返った。まるで着ている白い襦裙が闇に溶けて流れ出すかのような、緩慢な動きだ。
紅く縁どられた唇が目に留まる。口布が外されているのだ、と麗麗はそのとき初めて気づいた。凄まじいまでの美貌が、炎の赤に照らされている。魔性の笑みがふたりを捕らえて弧を描く。
冥焔は一歩も譲らず、貴人から目を離さない。
「断れるとお思いか」
それから冥焔が語ったのは、麗麗が白蓮妃の宮で耳にしたのと同じ真実だった。
一連の怪異の裏に、白蓮妃の女官がいたこと。
怪異を恐れる者たちに、毒のある歩揺を配っていたこと。
しかし、それらすべてを聞いても、白蓮は顔色ひとつ変えなかった。
「……なるほど」
赤い唇が蠱惑的に弧を描く。
「では、聞かせていただきましょう。なぜ私がそのようなことを?」
美しい毒の花がささやくように、白蓮妃は嫣然と微笑む。
冥焔は一歩、白蓮妃へと近づく。足音が廟の石床に、乾いた音を刻んだ。
「……あなたが、あの方──亡き皇太后の女官だからだ」
(え!?)
ぎょっとして、麗麗は思わず冥焔を仰ぎ見る。冥焔は視線を逸らさず、にらみつけるように白蓮妃を見つめている。
「皇太后亡きあと、後宮が解体された際、皇太后付きの女官たちは後宮を出たと記録されている。その中にはもちろん、あなたもいたはずだ」
白蓮妃は微動だにしない。ただ静かに冥焔を見つめるその瞳は、底なしの深さをたたえている。
「しかし、あなたは自分を売ったのだ。皇太后の女官であった事実を公にし、上級妃としての教養や振る舞いをすでに習得していると、娘を欲しがる官吏に主張した。そして名を変え、官吏の親戚として入内した」
「証拠は」
白蓮妃は、あくまで優雅に、微笑を崩さぬまま問う。
「娼館だ」
冥焔の声は低く、静かだった。
「官吏──あなたの生家とされている氏が、妓女を身請けしたという記録があった。妓女の念書と、白蓮妃、あなたの筆跡が一致している」
「…………」
無言のまま、白蓮妃は冥焔を見つめている。笑みの形は崩れていない。
「そしてもうひとつ。例の皇太后の女官と、身請けされた妓女の特徴だ。どちらも鋭い歯──虎牙の持ち主であり、その左側のみが欠けていると記録がある。……白蓮妃。もしあなたが否定するのであれば、口を開けて見せてはくれないか」
白蓮妃は微笑んだまま、ただじっと冥焔を凝視していた。炎の光に照らされたその美貌は、もはや人のものではない。
「さらに言うならば、あなたが今ここにいることが答えだ」
冥焔は、最後の言葉を落とすように告げた。
「この廟は、亡き貴人を祀る廟。その中には皇太后も含まれている」
炎がまた、ゆらりと揺れた。
「皇太后の女官は、誰もが忠実だった。あなたは皇太后の〝呪い〟を実行しようとしたのではないか。〝後宮に住まう女すべての死を願う〟……その呪いを真実にするために」
廟の中は静まり返っている。
ふ、と貴人の口元から小さく吐息が漏れた。その吐息はやがて声を伴い笑い声へと成長する。口元で、鋭い歯がきらりと光った。左側が欠けた虎牙をむき出して、白蓮妃は大笑する。おかしくて仕方がないというように。そして、ふうと息をつき、目尻にたまった涙をぬぐった。
「認めましょう。確かに私は、皇太后様の女官だった者。けれど、それと今回の件になんの関係があるの?」
「なんだと?」
冥焔が気色ばむ。白蓮妃はいっそ朗らかと言えるような声色で告げた。
「私は後宮での暮らしが忘れられなかったのよ。どうせなら女官ではなく、妃として、思う存分贅沢をして暮らしたかった。そのために、官吏と取引をしたにすぎないわ。それのどこが悪いのかしら。皆やっていることでしょう」
「……白蓮妃」
冥焔の咎めるような声は、白蓮妃には一切届かない。楽しそうに、朗々と話し続ける。
「怪異の裏に私の女官がいたと言ったわね。けれど、それが偶然でないとなぜ言い切れるの? 確かに私は不安を訴える者たちに、歩揺を渡したわ。しかし、それは女官を介して渡していただけ。私本人の意志で毒を入れたのだという証はあるのかしら」
白蓮妃はそこでふと口を閉じ、ややあって、もう一度開いた。
「私がやったという証を、見せなさい」
白蓮妃は微動だにせず、ただ冥焔をまっすぐに見つめている。その瞳には、動揺もおびえも見当たらない。圧倒的勝者の余裕すら漂わせていた。
冥焔は口を閉ざしている。先ほどまであれほど白蓮妃を追い詰めていたはずなのに、言葉を返せないのだ。
麗麗にはわかっていた。今までの話に物的証拠は存在せず、すべてが状況証拠のみだ。
確かに、後宮では証拠など不要である。皇帝の命令ひとつですべてが決まる。しかし、白蓮妃はそれを許さぬと言っている。
「できるわけがないわね、お前には」
白蓮妃は唇の端に酷薄な笑みを刻んだ。
「滑稽ね、冥焔。……いえ、別の名があったわね。その名を、今ここで呼んでみようかしら。そこの麗麗にでも聞かせてやりなさい。お前の本当の名を」
「……!」
冥焔の顔色が変わった。
「お前が……いいえ、お前たちが今、必死に隠している事実を、私が知らぬとでもお思いかしら」
「なんのことか、わからぬな」
冥焔の瞳に宿るのは怒りではない。焦りだ。
白蓮妃は容赦しない。まるで獲物の急所を知り尽くしているかのように、愉悦の笑みを浮かべながらさらに刃をねじ込んだ。
「冥焔。お前はあのときから一向に変わらない。だから〝天意〟を失ったのよ」
こつん、と絹の沓が石畳を鳴らす。
「風にも天にも背を向け、己に都合のいいものだけを天意と呼び、聞きたいことしか聞かず、見たいものしか見ず、あげく、ひとたび目を背けたものには二度と目を向けようともしない。それが、お前の〝天意〟」
吐き捨てるような、侮蔑に満ちた言葉が廟にじわりと響いて溶ける。
「だからあんなことになったのよ。すべては、お前のせい。お前が全部を壊したの。皇太后様も──」
「やめろ!」
冥焔の顔が、はっきりとゆがんだ。手が小さく震え、唇は引きつっている。
「やめろ……っ」
冥焔は叫んだ。それは怒鳴り声ではない。叫ぶことで、なにかを押しとどめようとする、必死の悲鳴だ。
その瞬間、麗麗はすべてを悟った。
冥焔と白蓮妃の因縁や、一連の思わせぶりな会話も、彼女にとってはどうでもいい。けれど、宦官・冥焔という男が〝崩壊〟していくさまは見たくなかった。
あれほど偉そうに、堂々としていた宦官の顔色は、青を通り越して白い。手は衝撃に打ち震え、視線は揺れ、今にも崩れ落ちそうなほどの衝撃を受けている。
そして、それこそが白蓮妃の狙いなのだ。
(……むかつく)
彼女の一挙手一投足が、宦官の心を抉る。冥焔が絶対に触れてほしくない過去を容赦なく引きずり出して、嬲っている。執拗に、冷酷に、迷いなく。
(むかつくっ……!)
麗麗の心の中に灯もった炎が、勢いよく燃え上がった。
(白蓮様は、冥焔様を傷つけたいだけなんだ)
喉が熱い。拳が震え、爪が手のひらに食い込んだ。その痛みで意識がはっきりとした。
(黙ってなんていられるわけ、ない)
どんな理由があろうとも、触れられたくない過去はある。その傷を無理やり抉られているさまを見るのは、たとえ鬼上司とてまっぴらごめんだ。
「お待ちください!」
心の火に従って、麗麗は声を張り上げていた。廟に響いた声は、自分でも驚くほど大きい。うわんっと反響する声に、冥焔も白蓮妃も同時にこちらを振り向いた。
ふーっと鼻息も荒く、麗麗は仁王立ちになった。頭の先から爪の先まで怒気ではちきれそうだ。
(……証拠がないなら、作ればいい)
麗麗は、憤怒に任せて口を開いた。
「証ならあります」
「……あら」
白蓮妃がことりと首をかしげた。表情が抜け落ちた顔は麗麗を捕らえ、その唇だけが不自然につり上がる。
「聞かせてもらいましょうか」
「是」
冥焔の視線を感じる。こちらを案じているのがわかる。麗麗は大丈夫だと言うように、口の端に笑みを浮かべてみせた。
「……白蓮妃がお持ちの薬棚には札が貼ってありましたね。その中には毒物もあったと存じます。あれを使ったのではないですか」
「まさか、雌黄を持っていただけで、証? あれは顔料として使っているの。絵を描くのが好きなのよ」
麗麗は負けるかと笑みを深くする。
「いえ。白蓮様は絵をお描きにはなりません。確かに雌黄は顔料ではありますが、もし絵をお描きになるのだとしたら、他の色もなければ不自然です。そうですね。例えば青金石、辰砂、孔雀石……。あの房にはありませんね」
頭の中で、生前よく読んでいた『鉱物辞典』を反芻しながら、つらつらと並べてみせる。鉱石の中には、絵の具の材料になるものもある。しかし、あの薬棚には雌黄以外の名はなかったはずだ。
「雌黄一色を使っているのよ」
「雌黄は、黄色。禁色です。主上以外、誰も使えない色ですね。鉱石として鑑賞するだけならいざ知らず、黄のみで絵を描くだなんて不敬にあたります。白蓮様のお立場なら、当然わきまえていらっしゃるはず」
白蓮妃はなにも答えない。ただ、わずかに顎を上げたまま、麗麗をにらみ返していた。
「白蓮様」
麗麗はそこで、一度言葉を句切る。
「なぜ、白蓮様は雌黄が証拠だという前提で、話されているのでしょう」
「……なんですって?」
「私たちは、歩揺に毒が含まれていたということしかお話していないはずなのに」
「!」
白蓮妃の指先がわずかに動いた。冥焔の、息を呑む音が耳に届く。
「毒の話のあとに、お前が薬棚の話をしたからよ。それで察しただけ」
「でも、あの薬棚には、他に毒になるようなものもありましたよね。大黄とか、治葛も」
麗麗の反論に、冥焔がぎょっとした顔で声をあげた。
「治葛だと……!? 猛毒ではないか」
「はい。でも、治葛は下薬──治療薬でもあるんです。熱を下げたり、咳を止めたり。だから、薬棚にあってもおかしくはないんです」
ちらりと冥焔を見やり、麗麗はにこりともせず言葉を重ねた。
「冥焔様が今、毒だと連想されたように、普通は治葛と聞けば毒を思い浮かべる。それなのに、白蓮様は雌黄をご自身で持ち出された。それはつまり、最初から雌黄が自分にとって致命的だと、よくご存じだったということです」
白蓮妃は、表情のそげ落ちた顔で麗麗を見据えている。
「言い逃れはできません、白蓮様」
声が、廟に響き渡る。
「これにて、証明完了です」
廟の中に、静寂が満ちる。
白蓮妃はなにも言わない。ただ、静かに麗麗を見つめ続ける。その沈黙は永遠にも思えるほど長く、張り詰めている。
けれど、それはおそらく一瞬のことだったのかもしれない。ふ、と赤く色づいた唇が開かれた。
「慈悲などかけず、殺しておけばよかった」
乾いた笑みが浮かぶ。
「よく回る口に、その知識。あまりにも危険だと感じたわ。だからこそ、儀式が始まる前にお前を始末しなければと思ったのに。……お前を惜しんだ自分が憎い。お前とあの人を会わせたかった。叶うことなら三人で、一緒に話をしたかった……。ほんの少しの慈悲と希望を持ったのが、私の敗因ね」
それはあきらめの笑みであり、皮肉の笑みであり、どこか安堵にも似た、壊れた微笑だった。
白蓮妃は居住まいを正す。
「すべて、私がやったことよ」
涼やかな瞳は穏やかな色を浮かべ、引き結ばれた唇は梅花のように艶やかだ。姿勢を正し、凜としたまなざしを向ける白蓮妃は、とても麗しかった。
ぽつり、ぽつりと口を開く。
変わり者として、いじめられていた。皇太后に引き立てられ、側仕えになった。皇太后だけが自分の味方だった。そして──。
「皇太后様は、自死なさった……そう世間は信じているらしいわね」
白蓮妃は薄く笑い、冥焔に視線を向けた。
「けれど、私は騙されない。あの方は処刑されたのよ」
きっぱりと言い切ると、白蓮妃は麗麗に目を向ける。
「麗麗、お前は、蘇りの証があれば信じると言ったわね」
(……なんで?)
麗麗の額を冷たい汗が伝う。どうして、そんな穏やかな表情で、声でいられるのだろう。このあと彼女を待っているのは極刑だというのに、なぜ。
「では検証をしましょう。鬼求代が成功するか、否か。お前の目で確かめなさい」
(鬼求代……!?)
確か、死者が蘇るために生きている者を身代わりにしなければならないという律のことだ。なぜ、今その話が出てくるのだろう。
白蓮妃は微笑むと、結い上げた髪に挿していた歩揺をひとつ、引き抜いた。
「冥焔。お前たちの〝天意〟では、私は裁けない」
ぞわっと、麗麗の背中を嫌な予感が駆け上る。
(待って、まさか)
「今夜は星送りの儀。亡き者の魂を慰める夜。私は、あの方をこの手で迎えに行きましょう」
白蓮妃は唇に言葉を乗せる。
「──此生无憾」
「やめろ!」
弾かれたように、冥焔が床を蹴った。一歩遅れて麗麗も後を追う。白蓮妃まで数歩の距離、だがしかし、その数歩が絶望的に遠かった。
歩揺が揺れる。炎に照らされ、ぬらぬらと光っている。
妃は歩揺を両手で握り、鋭い切っ先を喉元に向けた。そして、不気味に輝く光が流星のように──妃の喉を貫いた。
「あっ……」
嫌な音がした。前のめりで倒れる妃を、冥焔が受け止める。
「びゃ……白蓮様!」
「大丈夫だ、ぎりぎり骨で止まった! 侍医を……っ」
そう叫ぶ冥焔の唇に、白蓮妃の白い指がすっと添えられた。まるで黙れと言うかのように。
喉をついたせいで、気道も傷ついたのだろうか。かすれた声で、白蓮は笑う。
「ざんねん、ね」
「まさか、歩揺に毒を……!?」
体を痙攣させた白蓮を前に、冥焔の顔が青ざめる。駆け寄った麗麗も、どうすればいいのかわからない。
胃に入った毒ならば吐かせればいいが、血から入った毒は一切の猶予なく体内を駆け巡る。
「白蓮様……!」
差し伸べた麗麗の手を、白蓮が握った。
紅を掃いた唇が、うっすらと開く。なにかを言おうとしていることに気づき、麗麗は急いで白蓮妃の口元に耳を寄せた。
「検証……を……お願い……ね」
(なに言ってんの……!)
身を切られるほどの痛みが麗麗の心を襲った。
喉の奥が熱いのに、体の中心が冷えている。泣きたいのか怒りたいのか、麗麗にはわからない。ただ激しい感情が体中を駆け巡り、声にならない叫びとなって麗麗の口から迸る。
この世界に来て、麗麗は特に不満もなく暮らしていたと思っていた。けれど、それは勘違いだったのだ。
白蓮妃は、唯一麗麗と同じ熱を持つ仲間だった。言葉を交わすたびに、心が沸き立った。たった二回の邂逅だったけれど、それで十分だ。
師であり、友であり、そして、同胞だった。
やがて白蓮妃の体の痙攣が止まる。ぐにゃりと投げ出された手足からは、血の色が消えている。
死にゆく妃の顔は、ぞっとするほど美しかった。
「……終わりだ」
冥焔の声は低く、かすれていた。その表情にやりきれなさと痛ましさをにじませながら、事切れた白蓮妃をそっと床に横たえる。
「女官。行くぞ。大家に報告を──」
「いえ、まだです」
麗麗は手の甲で涙を乱暴にぬぐった。泣いている暇はない。白蓮妃は取り返しのつかないことを始めようとしていると気づいたのだ。
「冥焔様。白蓮様は……鬼求代を検証しようとしています!」
「なんだって?」
冥焔は目を見張った。
もはや一刻の猶予もない。急がなければ、と麗麗は足を廟の戸へ向ける。
「あの予言です。『流れ星が墜ち、天の刑罰が下される』。これは、星送りの儀でたくさんの人が死ぬということですよね?」
「そうだ。しかし、白蓮妃は今、ここで死んだぞ。これ以上なにも起きるはずが──」
「天灯です……!」
「はっ?」
「白蓮様は、天灯を自ら作っていらっしゃいました。そこに、もし毒が仕掛けられているのだとしたら……!」
冥焔の顔色が変わった。
「行くぞ、女官!」
「はい!」
来た道を急いで駆け下り、廟の門を出た瞬間──。
「しまった、もう始まっていたか!」
西の空に天高く、おびただしい量の天灯が舞い上がっている。
「急ぎましょう……!」