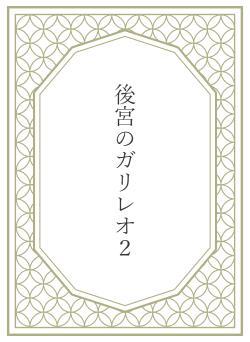「冥焔様」
「なんだ」
「疲れました」
「そうか」
「……おなかもすきました」
「そうか」
冥焔はどこ吹く風で、麗麗の前をのしのしと歩いている。
もう昼だ。今日は朝からずっとこの背中を追いかけているので、もういい加減休憩したい。そう暗に伝えたかったのだが、冥焔はまったく取り合ってくれない。
「冥焔様」
「だから、なんだ」
「察してください。休憩したいって言ってるんですよ!」
冥焔は驚いたように振り向いて目をぱちくりさせた。
「なら、はっきりそう言え」
「……今度からそうします」
察せないなら、言うしかない。けれどこの宦官、こんな調子で本当に大丈夫なのか。
(空気が読めないにもほどがある)
自分の空気の読めなさはえいやと棚に上げておく。悪口とは、そういうものである。
大混乱の百茗の宴が終わってから、半月が経った。麗麗は今日も今日とて冥焔と共に各妃嬪の宮を回っていた。
というのも、あの百茗の宴での出来事以来、怪異を訴える者が急増したのである。
こうして歩いているだけでも、そこかしこでひそひそと噂話が飛び交っているのがわかる。普段であれば冥焔が歩くだけであちこちで黄色い悲鳴があがっていたが、今は女官たちもそれどころではないようだ。
無理もない。後宮に住む妃嬪のほとんどが参加した宴で、あんな不気味な事件が起こったら、不安になるのもむべなるかな。
そのため、皇帝からの緊急要請で、麗麗は一時、女官業務を離れることになった。冥焔と共に怪異の調査に本腰を入れよとのお達しである。寝起きには今まで通り深藍宮を使うが、業務はまったくの別だ。
『麗麗がいないと、寂しいな』
そう言って瑛琳妃は快く送り出してくれた。皇帝の命であることはおそらく知っているだろう。にもかかわらず、詮索してこない。本当によくできた方だ。
他の三女官は好奇心で目がきらきらしていたけれど、詳細を尋ねてくる者はいない。瑛琳妃から『詮索するな』ときつく命じられているのかもしれなかった。同僚に恵まれるという事実が大変ありがたく感じる。
察しの悪い冥焔をつつきにつついてようやく休憩となった麗麗は、深藍宮へと戻った。冥焔はその場から離れた。直前に別の宦官からなにやら耳打ちされていたので、なにか用でも入ったのだろう。
冥焔は人使いが荒い。それだけではなく、今は焦っているようにも見えた。しかし、それを汲むほど麗麗は優しくないのだ。
(説明されていないのに、こちらが汲み取るのもなんか癪だしさ)
疲れた体を引きずるようにして宮に入ると、厨へと向かった。昼を大きく回っているが、まだ食事は残っているだろうか。
「あら、麗麗。遅かったじゃない」
厨に続く扉を開けると、花里が朗らかな笑顔で鍋を磨いている。
「あの……なんでもいいので、なにか食べるもの、ありますか」
「あるわよ。ほら、そこ」
見ると、卓子の上に籠に入った包子が盛られている。麗麗の目が輝いた。
「ありがとうございます……っ!」
「お礼はあとで娘娘に言いなさい。『麗麗はがんばっているから、いつでも食べられるものを用意しておいて』と頼まれているのよ」
「瑛琳様が?」
「ええ。蒸し直すわ。少し待っててね」
そう言いながら花里は包子を籠ごと沸騰した湯の上にかけてくれる。
しみじみとありがたさが胸に広がる。
(なんだろうなあ、この実家感)
蒸し直された包子に、そぎ落とした干し肉を酒で煮たものと、甘辛く味付けした青菜を挟み、かぶりついた。じゅわっと口いっぱいに幸せが広がる。
(うっ……まぁ……!)
ちょっと濃いめの味が疲れた体に染み渡るようだ。
「麗麗はすぐ顔に出るわね」
花里が嬉しそうにふふふと笑った。
「あっ! ずるい。麗麗がおやつ食べてる!」
ひょこっと入り口から顔を出した雪梅が、すーっと近寄ってきた。
「ねえ、ちょっとわけてよ」
「だめです」
「けちね!」
「私の食事です」
ちぇーっとふてくされながら、雪梅が長椅子に体を投げ出すように座った。
「雪梅はずいぶん早かったわね。洗い物は終わったの?」
花里の言葉に、雪梅は大きく伸びをしながら応える。
「終わったわよ。今はどこもかしこも嫌~な空気が漂ってるから。ちんたら仕事してる女官もいないし、洗い場、空いてたわ」
「……そう」
花里が頰に手を添えてため息をつく。ぱたぱたと元気な足音が聞こえてきた。
「あーっ! 麗麗がおやつ食べてる!」
今度は香鈴だ。目を輝かせながら厨に入ると、物欲しそうな顔で麗麗にすりよった。
「ねえ麗麗?」
「だめです」
しゅん、とうなだれる香鈴に、花里はころころと笑った。
「香鈴もお仕事完了?」
雪梅が洗い物や掃除、文の代筆など宮の維持に努めているのとは対照的に、香鈴は茶会の準備やお出かけ準備、服や化粧品の調達、贈答品の選定など、主に外交関係を担当している。
「うん。瑛琳様もちょっと休むって房にいるよ」
ぐでーっと同じく長椅子に体を投げ出して、香鈴は息をついた。
「こんな空気じゃ茶会もやらないだろうし、しばらくは暇になりそう。やることなくてつまんないよ」
「そーんなにお暇なら、私の仕事、半分あげるわよ」
雪梅が恨みがましい視線を向けた。香鈴はまったく気にするそぶりを見せず、にぱっと笑ってみせる。
「いいよ」
「……あんたって、嫌みが通じないわよね」
みんながそろっていて、仕事も一段落ついたのなら、ということで花里がお茶を入れてくれる。長案を囲んで、しばし休憩時間だ。
茶請けの麻花をつまみながら、雪梅は首を振った。
「それにしても、この嫌ーな空気。なんとかならないかしら。気が滅入っちゃうわ」
「しょうがないよ。あんな予言聞いたら、みんな怖がっちゃうって」
「そうよね。あれだけはっきりとおっしゃっていたら、不安にもなるわよね」
ふーっと三女官のため息が重なり、麗麗はおそるおそる口を開いた。
「あのう、結局、あの宴で白蓮様が言っていたことって、なんだったんでしょう」
「えっ」
空気がまた、ぴしっと固まる。
「もしかして、麗麗、わかってなかったの!?」
「はい」
ごまかしても仕方ないので、こくりとうなずいた。
麗麗が今理解している点は三つだ。突然白蓮妃が立ち上がって意味不明な発言をしたこと、それがやたら不穏な気配だったこと、そしてそのあと、麗麗の仕事──つまり、怪異を訴える人が爆増したこと。ただそれだけだった。
「あんた……ほんっと、ちょっとは勉強しなさいよ」
「すみません」
じっとりとした視線を向けてくる雪梅に、麗麗は素直に謝っておく。
「しょうがないわね。あのとき白蓮妃が言っていたことはね」
雪梅は、白蓮妃が諳んじた詩を要約してくれた。
風が泣き、月が沈み、魂がさまよう。
死者の叫びが響き、深い悲嘆の果てに冥府に至る。
この世の恨みは夜ごとに深まり、宮は怪で満ちあふれる。
流れ星が墜ち、天の刑罰が下される。
これだけ聞いても、正直さっぱりだ。首をかしげている麗麗に、雪梅はしょうがないといった風情で説明を始めた。
「つまり、〝死者が怒っている〟って言ってるのよ」
「怒っている、ですか」
「そう。それで、〝後宮に怪しい出来事がたくさん起こる〟らしくてね。〝星が墜ちて、天が罰を与えるだろう〟って、予言よ」
雪梅はここで声をひそめた。
「この、星が墜ちて、天が罰を与える、って話なんだけど。これが、『星送りの儀』のことを指していて、儀式の日に、たくさんの人が死ぬんじゃないかって噂されてるの」
星送りの儀。聞いたような聞いていないような……と、首をかしげた麗麗の顔を見て、雪梅は呆れたように息をついた。
「言っとくけど、説明したからね」
「ごめんなさい」
「いいわよ。麗麗はこういうの覚えるのが苦手なんだって、さすがにわかってきたから。あのね、星送りの儀っていう儀式がもうすぐあるのよ。ちょうどあと七日後ね」
「儀式、ですか」
「そうだよ」
口を挟んだのは、香鈴だ。
「月のない夜にね、天灯を星に見立てて夜空に飛ばすの。すごく綺麗なんだって」
うっとりとした顔で頰に手を当てている。
「後宮中から、灯りが夜空に向かって飛んでいくんだよ。中央の名物になってるらしくって、宮城のみんなはもちろんだけど、城下の人たちも楽しみにしてるんだって!」
(へえ~!)
麗麗の目が輝く。つまり、ランタンフェスティバルというやつか。
「それは楽しみですね」
「そうなのよ。ほら、後宮の人員ってほとんどが入れ替わってるって前に教えたでしょ。だから今回の星送りの儀は、私たち含め、初めて儀式に参加する人が多くて。すごく、すご~く楽しみにしてたのよ! それなのに……っ」
雪梅は悔しそうに顔をゆがめると、麻花を口いっぱい頰張ってむしゃむしゃと食べ始めた。
(喉に詰まりそう)
案の定、ぐっと変な音がした。これはお茶のおかわりがいると判断したのだろう、花里が苦笑いしながらもう一度湯を沸かし始める。
雪梅はなんとか口の中のものを飲み下したようで、涙目になりながらさらに管を巻く。
「あんな予言されたら、楽しめるものも楽しめなくなっちゃうわよ!」
「それなんですけど」
麗麗は疑問に思っていたことを口に出す。
「なぜみんな、白蓮様の予言を信じているのでしょう。ああいう場であんな不穏な発言をしたら、通常であれば獄行きなのでは?」
後宮で不穏な噂を故意に流すのは律で禁止されているはずだ。
「白蓮様は特別なのよ」
雪梅はぶーたれた表情のまま続ける。
「あの方は、仙女様だから」
徳妃・白蓮。仙女の生まれ変わりだと噂される妃である。
それは見た目の麗しさ、たおやかさももちろんであるが、それ以上に、彼女はよく〝こういうこと〟があるのだそうだ。
「すごいのよ。天気とかをね、ぴたりと当てちゃうの」
「占いもするんだよ。えっとね、相性とか、手相とか!」
「ときどきね、ああやって意識を失うのよ。仙術を使って先に起こる出来事を予見するんだって。一部の女官や宦官の間ではものすごく有名なのよ」
「宮に行列ができてるときあるもんねぇ」
雪梅と香鈴の言葉に、麗麗は首をかしげた。
「行列? なんのために」
「もちろん、白蓮様の託宣を受けるために、だよ!」
香鈴が鼻息も荒くそう告げる。うなずいたのは雪梅だ。
「白蓮妃にはものすごい数の熱狂的支持者がいるって思ってもらったほうがいいわ。あの方に話を聞いてもらうだけで病が治るだとか、恐ろしいことが起こらないだとか、そりゃもういろいろ言われてるんだから」
(うわあ)
思わずげんなりしてしまった。また顔に出てしまっていたのか、雪梅がくすっと笑みをこぼした。
「ほんと、わかりやすいわね。私、麗麗のそういうところ好きだわ」
「……お褒めにあずかりどうも。でも、ちょっと気になるんですけど、皆のおびえ方は異常ではありませんか。もともと白蓮妃が〝そういう人〟だったのだとしても、全員が信じきっているわけではないのでしょう? ここ最近の後宮の空気は、少しいきすぎなのではないですか」
麗麗の問いに、雪梅はちらっと厨の入り口に目を向けてから声をひそめた。
「いい? これ、外で言っちゃだめよ。……皇太后様の一件があるからよ」
皇太后というと、確か絞鬼の事件のときに冥焔が言葉を濁していた……。
(首をくくって死んだっていう人か)
「皇太后様はね、羅帝がお亡くなりになって、龍帝が登極されたときにはすでにご様子がおかしかったようなのよ」
「と、言いますと」
「それこそ幽鬼みたいなありさまで。……怪しげな術を習得しようとしていたんですって」
「怪しげな術?」
そうそう、と雪梅の言葉を香鈴が受け継ぐ。
「永遠の若さを手に入れようとなさっていたんだって。いろんな丸薬を飲んだり、香を焚いたりしたんだけれど、結局願いは叶わなくて。それで、絶望して……」
香鈴が自分の首をきゅっと絞める動作をした。
「香鈴」
花里にたしなめられて、香鈴はぷくっとむくれた顔をする。
「まあ、そういう噂があるのよ」
花里も頰に手を当ててため息をつく。
「ふたりの話に付け足すと、皇太后様は呪いをかけたのだと言われているわ。お亡くなりになる寸前に、後宮に住まう女すべての死を願った、と」
「女すべての死、ですか」
規模が大きい呪いだ、と妙に感心してしまう。一方で、納得もした。
『死者が怒っている。天が罰を与えるだろう』とは、皇太后の呪いを指しているということか。そしてその呪いのせいで、星送りの儀でたくさんの人が死ぬと白蓮妃は予言した。
最悪だ。だからこんなに一気に怪異が増えたのだ、と麗麗は麻花をくわえたまま天井を仰いだ。
そんなことを言われたら、誰だって気にする。気にする人が増えれば不安も増すし、枯れ尾花だって立派な幽鬼に様変わりだ。
しかし、この三女官は一切おびえていないように思える。後宮の空気を嫌だとは感じているようだが、それ以下でも以上でもないといった風情である。
「皆さんは、あまり信じていらっしゃらないのですね」
麗麗の言葉に、三女官はそろって顔を見合わせ苦笑いをした。
「私たちはね、明林のときにひどい目に遭ったでしょう。こりてるのよ」
「そうそう。呪いだのなんだの噂されてさ! 許せないわ。病気だったのに、あんな扱いされて」
「明林はねえ、すっごくいい子だったんだよ。それなのに、あんなに怖がられて、ひどいよ。あの子が呪いなんてするはずないのに!」
「だから、皇太后様の話も、よく知りもしないのにあれこれ勝手に想像して怖がるのって、おかしいと思うわ。私たちは、だけどね」
麗麗はそこに、女官たちの絆の強さ、思慮深さを見た。明林──呪いの房事件で亡くなった女官が散々に噂されていたのを憤り、悔しく感じていたのだろう。だから、皇太后の呪いの件も、一歩引いた姿勢で見ているのだ。
「でもね、私たちみたいなのは少数派よ」
雪梅が肩をすくめた。
「麗麗。あんたも気をつけなさい。白蓮様を仙女だって崇め奉ってる人は相当多いと思っていいわ。皇太后様の呪いの件もみんなが怖がっているのは間違いないんだから、あまり変な発言をして注目を浴びると面倒なことになるわよ」
「面倒なことですか」
確かに、白蓮妃の支持者がわんさかいるような状況で、『あの人、怪しいんで信じないほうがいいですよ』なんて言ったらどうなるか、想像しただけで恐ろしい。皇太后の呪いの件は言うに及ばずだ。
しかし、雪梅は麗麗の考えとまったく別のことを口走った。
「ただでさえ、冥焔様の件で、あんた今大変なんだから」
「へっ」
なんでそこであの宦官の名が出てくるのだ。
香鈴がにまっと笑い、じりじりと麗麗ににじりよる。
「知ってる? 今ねえ、白蓮様の予言の裏でひそかにささやかれている噂」
「いえ」
「んふふ、それはね。麗麗と冥焔様が好い関係って話だよ」
「はあ!?」
香鈴はにこにこしながら、麗麗の腕に自分の腕を絡ませた。
「こないだの百茗の宴のときに、ふたりきりで手を握り合ってたんでしょ?」
しまった、と麗麗は苦い顔をする。
(あれだ。あのときの腹痛)
突然、冥焔が腹痛になった。そのときに巾で汗を拭こうと手を伸ばし、その手をつかまれた。
あれを『手を握り合った』と表現するのはややおかしいが、当たらずといえども遠からずだ。周りに人はいなかったはずだが、さすが後宮。どこに目があるかわからない。
雪梅も目にからかいの色を浮かべながら、麗麗を肘でえいえいとつつく。
「すんご~く甘い雰囲気だった、あれはそういう関係だって、もっぱらの噂になってんのよ、あんたたち」
心底やめてほしい。自分と冥焔は、有り体に言うと上司と部下だ。しかも冥焔のあの様子。どこをどう切り取ったら、甘い雰囲気に見えるのだろう。
「あらあら、そうだったの」
頭を抱えた麗麗の前では花里が頰をぱっと赤らめ、嬉しそうに手を叩いた。
「仲がいいのは知っていたけど、もうそんな関係になったのねぇ」
「なってません」
「だめよ、おおっぴらにそういう関係だってわかるようなことをしたら。うるさい人たちに目をつけられてしまうわ」
「違います」
「ああいうのはこっそりと。そうねえ、夜の院子、木陰の下とかでやるのがいいのよ。次からそうなさい。なんなら、私が娘娘にそれとなく事情を説明して、夜に抜け出すお手伝いを──」
「いりません!」
知らなかった。いや、注目されているのは気づいていた。冥焔と歩いているだけでほいほい嫌がらせされるので、自分に向けられているのが嫉妬心だいうこともなんとなく理解していた。
でもそれは、冥焔のような人気者がちんちくりんの自分をかまっている事実が気に食わないからだ、と思っていたのに。
(好い関係……)
あの冥焔と、恋人関係である。そんな噂になっていたなんてあんまりではないか。
肩をがっくりと落とす。
(これから、あの宦官の半径一メートル以内に入らないようにしよう)
話を聞きたがる三女官を適当にかわしながら、麗麗は深く心に刻み込んだ。
「なんだ」
「疲れました」
「そうか」
「……おなかもすきました」
「そうか」
冥焔はどこ吹く風で、麗麗の前をのしのしと歩いている。
もう昼だ。今日は朝からずっとこの背中を追いかけているので、もういい加減休憩したい。そう暗に伝えたかったのだが、冥焔はまったく取り合ってくれない。
「冥焔様」
「だから、なんだ」
「察してください。休憩したいって言ってるんですよ!」
冥焔は驚いたように振り向いて目をぱちくりさせた。
「なら、はっきりそう言え」
「……今度からそうします」
察せないなら、言うしかない。けれどこの宦官、こんな調子で本当に大丈夫なのか。
(空気が読めないにもほどがある)
自分の空気の読めなさはえいやと棚に上げておく。悪口とは、そういうものである。
大混乱の百茗の宴が終わってから、半月が経った。麗麗は今日も今日とて冥焔と共に各妃嬪の宮を回っていた。
というのも、あの百茗の宴での出来事以来、怪異を訴える者が急増したのである。
こうして歩いているだけでも、そこかしこでひそひそと噂話が飛び交っているのがわかる。普段であれば冥焔が歩くだけであちこちで黄色い悲鳴があがっていたが、今は女官たちもそれどころではないようだ。
無理もない。後宮に住む妃嬪のほとんどが参加した宴で、あんな不気味な事件が起こったら、不安になるのもむべなるかな。
そのため、皇帝からの緊急要請で、麗麗は一時、女官業務を離れることになった。冥焔と共に怪異の調査に本腰を入れよとのお達しである。寝起きには今まで通り深藍宮を使うが、業務はまったくの別だ。
『麗麗がいないと、寂しいな』
そう言って瑛琳妃は快く送り出してくれた。皇帝の命であることはおそらく知っているだろう。にもかかわらず、詮索してこない。本当によくできた方だ。
他の三女官は好奇心で目がきらきらしていたけれど、詳細を尋ねてくる者はいない。瑛琳妃から『詮索するな』ときつく命じられているのかもしれなかった。同僚に恵まれるという事実が大変ありがたく感じる。
察しの悪い冥焔をつつきにつついてようやく休憩となった麗麗は、深藍宮へと戻った。冥焔はその場から離れた。直前に別の宦官からなにやら耳打ちされていたので、なにか用でも入ったのだろう。
冥焔は人使いが荒い。それだけではなく、今は焦っているようにも見えた。しかし、それを汲むほど麗麗は優しくないのだ。
(説明されていないのに、こちらが汲み取るのもなんか癪だしさ)
疲れた体を引きずるようにして宮に入ると、厨へと向かった。昼を大きく回っているが、まだ食事は残っているだろうか。
「あら、麗麗。遅かったじゃない」
厨に続く扉を開けると、花里が朗らかな笑顔で鍋を磨いている。
「あの……なんでもいいので、なにか食べるもの、ありますか」
「あるわよ。ほら、そこ」
見ると、卓子の上に籠に入った包子が盛られている。麗麗の目が輝いた。
「ありがとうございます……っ!」
「お礼はあとで娘娘に言いなさい。『麗麗はがんばっているから、いつでも食べられるものを用意しておいて』と頼まれているのよ」
「瑛琳様が?」
「ええ。蒸し直すわ。少し待っててね」
そう言いながら花里は包子を籠ごと沸騰した湯の上にかけてくれる。
しみじみとありがたさが胸に広がる。
(なんだろうなあ、この実家感)
蒸し直された包子に、そぎ落とした干し肉を酒で煮たものと、甘辛く味付けした青菜を挟み、かぶりついた。じゅわっと口いっぱいに幸せが広がる。
(うっ……まぁ……!)
ちょっと濃いめの味が疲れた体に染み渡るようだ。
「麗麗はすぐ顔に出るわね」
花里が嬉しそうにふふふと笑った。
「あっ! ずるい。麗麗がおやつ食べてる!」
ひょこっと入り口から顔を出した雪梅が、すーっと近寄ってきた。
「ねえ、ちょっとわけてよ」
「だめです」
「けちね!」
「私の食事です」
ちぇーっとふてくされながら、雪梅が長椅子に体を投げ出すように座った。
「雪梅はずいぶん早かったわね。洗い物は終わったの?」
花里の言葉に、雪梅は大きく伸びをしながら応える。
「終わったわよ。今はどこもかしこも嫌~な空気が漂ってるから。ちんたら仕事してる女官もいないし、洗い場、空いてたわ」
「……そう」
花里が頰に手を添えてため息をつく。ぱたぱたと元気な足音が聞こえてきた。
「あーっ! 麗麗がおやつ食べてる!」
今度は香鈴だ。目を輝かせながら厨に入ると、物欲しそうな顔で麗麗にすりよった。
「ねえ麗麗?」
「だめです」
しゅん、とうなだれる香鈴に、花里はころころと笑った。
「香鈴もお仕事完了?」
雪梅が洗い物や掃除、文の代筆など宮の維持に努めているのとは対照的に、香鈴は茶会の準備やお出かけ準備、服や化粧品の調達、贈答品の選定など、主に外交関係を担当している。
「うん。瑛琳様もちょっと休むって房にいるよ」
ぐでーっと同じく長椅子に体を投げ出して、香鈴は息をついた。
「こんな空気じゃ茶会もやらないだろうし、しばらくは暇になりそう。やることなくてつまんないよ」
「そーんなにお暇なら、私の仕事、半分あげるわよ」
雪梅が恨みがましい視線を向けた。香鈴はまったく気にするそぶりを見せず、にぱっと笑ってみせる。
「いいよ」
「……あんたって、嫌みが通じないわよね」
みんながそろっていて、仕事も一段落ついたのなら、ということで花里がお茶を入れてくれる。長案を囲んで、しばし休憩時間だ。
茶請けの麻花をつまみながら、雪梅は首を振った。
「それにしても、この嫌ーな空気。なんとかならないかしら。気が滅入っちゃうわ」
「しょうがないよ。あんな予言聞いたら、みんな怖がっちゃうって」
「そうよね。あれだけはっきりとおっしゃっていたら、不安にもなるわよね」
ふーっと三女官のため息が重なり、麗麗はおそるおそる口を開いた。
「あのう、結局、あの宴で白蓮様が言っていたことって、なんだったんでしょう」
「えっ」
空気がまた、ぴしっと固まる。
「もしかして、麗麗、わかってなかったの!?」
「はい」
ごまかしても仕方ないので、こくりとうなずいた。
麗麗が今理解している点は三つだ。突然白蓮妃が立ち上がって意味不明な発言をしたこと、それがやたら不穏な気配だったこと、そしてそのあと、麗麗の仕事──つまり、怪異を訴える人が爆増したこと。ただそれだけだった。
「あんた……ほんっと、ちょっとは勉強しなさいよ」
「すみません」
じっとりとした視線を向けてくる雪梅に、麗麗は素直に謝っておく。
「しょうがないわね。あのとき白蓮妃が言っていたことはね」
雪梅は、白蓮妃が諳んじた詩を要約してくれた。
風が泣き、月が沈み、魂がさまよう。
死者の叫びが響き、深い悲嘆の果てに冥府に至る。
この世の恨みは夜ごとに深まり、宮は怪で満ちあふれる。
流れ星が墜ち、天の刑罰が下される。
これだけ聞いても、正直さっぱりだ。首をかしげている麗麗に、雪梅はしょうがないといった風情で説明を始めた。
「つまり、〝死者が怒っている〟って言ってるのよ」
「怒っている、ですか」
「そう。それで、〝後宮に怪しい出来事がたくさん起こる〟らしくてね。〝星が墜ちて、天が罰を与えるだろう〟って、予言よ」
雪梅はここで声をひそめた。
「この、星が墜ちて、天が罰を与える、って話なんだけど。これが、『星送りの儀』のことを指していて、儀式の日に、たくさんの人が死ぬんじゃないかって噂されてるの」
星送りの儀。聞いたような聞いていないような……と、首をかしげた麗麗の顔を見て、雪梅は呆れたように息をついた。
「言っとくけど、説明したからね」
「ごめんなさい」
「いいわよ。麗麗はこういうの覚えるのが苦手なんだって、さすがにわかってきたから。あのね、星送りの儀っていう儀式がもうすぐあるのよ。ちょうどあと七日後ね」
「儀式、ですか」
「そうだよ」
口を挟んだのは、香鈴だ。
「月のない夜にね、天灯を星に見立てて夜空に飛ばすの。すごく綺麗なんだって」
うっとりとした顔で頰に手を当てている。
「後宮中から、灯りが夜空に向かって飛んでいくんだよ。中央の名物になってるらしくって、宮城のみんなはもちろんだけど、城下の人たちも楽しみにしてるんだって!」
(へえ~!)
麗麗の目が輝く。つまり、ランタンフェスティバルというやつか。
「それは楽しみですね」
「そうなのよ。ほら、後宮の人員ってほとんどが入れ替わってるって前に教えたでしょ。だから今回の星送りの儀は、私たち含め、初めて儀式に参加する人が多くて。すごく、すご~く楽しみにしてたのよ! それなのに……っ」
雪梅は悔しそうに顔をゆがめると、麻花を口いっぱい頰張ってむしゃむしゃと食べ始めた。
(喉に詰まりそう)
案の定、ぐっと変な音がした。これはお茶のおかわりがいると判断したのだろう、花里が苦笑いしながらもう一度湯を沸かし始める。
雪梅はなんとか口の中のものを飲み下したようで、涙目になりながらさらに管を巻く。
「あんな予言されたら、楽しめるものも楽しめなくなっちゃうわよ!」
「それなんですけど」
麗麗は疑問に思っていたことを口に出す。
「なぜみんな、白蓮様の予言を信じているのでしょう。ああいう場であんな不穏な発言をしたら、通常であれば獄行きなのでは?」
後宮で不穏な噂を故意に流すのは律で禁止されているはずだ。
「白蓮様は特別なのよ」
雪梅はぶーたれた表情のまま続ける。
「あの方は、仙女様だから」
徳妃・白蓮。仙女の生まれ変わりだと噂される妃である。
それは見た目の麗しさ、たおやかさももちろんであるが、それ以上に、彼女はよく〝こういうこと〟があるのだそうだ。
「すごいのよ。天気とかをね、ぴたりと当てちゃうの」
「占いもするんだよ。えっとね、相性とか、手相とか!」
「ときどきね、ああやって意識を失うのよ。仙術を使って先に起こる出来事を予見するんだって。一部の女官や宦官の間ではものすごく有名なのよ」
「宮に行列ができてるときあるもんねぇ」
雪梅と香鈴の言葉に、麗麗は首をかしげた。
「行列? なんのために」
「もちろん、白蓮様の託宣を受けるために、だよ!」
香鈴が鼻息も荒くそう告げる。うなずいたのは雪梅だ。
「白蓮妃にはものすごい数の熱狂的支持者がいるって思ってもらったほうがいいわ。あの方に話を聞いてもらうだけで病が治るだとか、恐ろしいことが起こらないだとか、そりゃもういろいろ言われてるんだから」
(うわあ)
思わずげんなりしてしまった。また顔に出てしまっていたのか、雪梅がくすっと笑みをこぼした。
「ほんと、わかりやすいわね。私、麗麗のそういうところ好きだわ」
「……お褒めにあずかりどうも。でも、ちょっと気になるんですけど、皆のおびえ方は異常ではありませんか。もともと白蓮妃が〝そういう人〟だったのだとしても、全員が信じきっているわけではないのでしょう? ここ最近の後宮の空気は、少しいきすぎなのではないですか」
麗麗の問いに、雪梅はちらっと厨の入り口に目を向けてから声をひそめた。
「いい? これ、外で言っちゃだめよ。……皇太后様の一件があるからよ」
皇太后というと、確か絞鬼の事件のときに冥焔が言葉を濁していた……。
(首をくくって死んだっていう人か)
「皇太后様はね、羅帝がお亡くなりになって、龍帝が登極されたときにはすでにご様子がおかしかったようなのよ」
「と、言いますと」
「それこそ幽鬼みたいなありさまで。……怪しげな術を習得しようとしていたんですって」
「怪しげな術?」
そうそう、と雪梅の言葉を香鈴が受け継ぐ。
「永遠の若さを手に入れようとなさっていたんだって。いろんな丸薬を飲んだり、香を焚いたりしたんだけれど、結局願いは叶わなくて。それで、絶望して……」
香鈴が自分の首をきゅっと絞める動作をした。
「香鈴」
花里にたしなめられて、香鈴はぷくっとむくれた顔をする。
「まあ、そういう噂があるのよ」
花里も頰に手を当ててため息をつく。
「ふたりの話に付け足すと、皇太后様は呪いをかけたのだと言われているわ。お亡くなりになる寸前に、後宮に住まう女すべての死を願った、と」
「女すべての死、ですか」
規模が大きい呪いだ、と妙に感心してしまう。一方で、納得もした。
『死者が怒っている。天が罰を与えるだろう』とは、皇太后の呪いを指しているということか。そしてその呪いのせいで、星送りの儀でたくさんの人が死ぬと白蓮妃は予言した。
最悪だ。だからこんなに一気に怪異が増えたのだ、と麗麗は麻花をくわえたまま天井を仰いだ。
そんなことを言われたら、誰だって気にする。気にする人が増えれば不安も増すし、枯れ尾花だって立派な幽鬼に様変わりだ。
しかし、この三女官は一切おびえていないように思える。後宮の空気を嫌だとは感じているようだが、それ以下でも以上でもないといった風情である。
「皆さんは、あまり信じていらっしゃらないのですね」
麗麗の言葉に、三女官はそろって顔を見合わせ苦笑いをした。
「私たちはね、明林のときにひどい目に遭ったでしょう。こりてるのよ」
「そうそう。呪いだのなんだの噂されてさ! 許せないわ。病気だったのに、あんな扱いされて」
「明林はねえ、すっごくいい子だったんだよ。それなのに、あんなに怖がられて、ひどいよ。あの子が呪いなんてするはずないのに!」
「だから、皇太后様の話も、よく知りもしないのにあれこれ勝手に想像して怖がるのって、おかしいと思うわ。私たちは、だけどね」
麗麗はそこに、女官たちの絆の強さ、思慮深さを見た。明林──呪いの房事件で亡くなった女官が散々に噂されていたのを憤り、悔しく感じていたのだろう。だから、皇太后の呪いの件も、一歩引いた姿勢で見ているのだ。
「でもね、私たちみたいなのは少数派よ」
雪梅が肩をすくめた。
「麗麗。あんたも気をつけなさい。白蓮様を仙女だって崇め奉ってる人は相当多いと思っていいわ。皇太后様の呪いの件もみんなが怖がっているのは間違いないんだから、あまり変な発言をして注目を浴びると面倒なことになるわよ」
「面倒なことですか」
確かに、白蓮妃の支持者がわんさかいるような状況で、『あの人、怪しいんで信じないほうがいいですよ』なんて言ったらどうなるか、想像しただけで恐ろしい。皇太后の呪いの件は言うに及ばずだ。
しかし、雪梅は麗麗の考えとまったく別のことを口走った。
「ただでさえ、冥焔様の件で、あんた今大変なんだから」
「へっ」
なんでそこであの宦官の名が出てくるのだ。
香鈴がにまっと笑い、じりじりと麗麗ににじりよる。
「知ってる? 今ねえ、白蓮様の予言の裏でひそかにささやかれている噂」
「いえ」
「んふふ、それはね。麗麗と冥焔様が好い関係って話だよ」
「はあ!?」
香鈴はにこにこしながら、麗麗の腕に自分の腕を絡ませた。
「こないだの百茗の宴のときに、ふたりきりで手を握り合ってたんでしょ?」
しまった、と麗麗は苦い顔をする。
(あれだ。あのときの腹痛)
突然、冥焔が腹痛になった。そのときに巾で汗を拭こうと手を伸ばし、その手をつかまれた。
あれを『手を握り合った』と表現するのはややおかしいが、当たらずといえども遠からずだ。周りに人はいなかったはずだが、さすが後宮。どこに目があるかわからない。
雪梅も目にからかいの色を浮かべながら、麗麗を肘でえいえいとつつく。
「すんご~く甘い雰囲気だった、あれはそういう関係だって、もっぱらの噂になってんのよ、あんたたち」
心底やめてほしい。自分と冥焔は、有り体に言うと上司と部下だ。しかも冥焔のあの様子。どこをどう切り取ったら、甘い雰囲気に見えるのだろう。
「あらあら、そうだったの」
頭を抱えた麗麗の前では花里が頰をぱっと赤らめ、嬉しそうに手を叩いた。
「仲がいいのは知っていたけど、もうそんな関係になったのねぇ」
「なってません」
「だめよ、おおっぴらにそういう関係だってわかるようなことをしたら。うるさい人たちに目をつけられてしまうわ」
「違います」
「ああいうのはこっそりと。そうねえ、夜の院子、木陰の下とかでやるのがいいのよ。次からそうなさい。なんなら、私が娘娘にそれとなく事情を説明して、夜に抜け出すお手伝いを──」
「いりません!」
知らなかった。いや、注目されているのは気づいていた。冥焔と歩いているだけでほいほい嫌がらせされるので、自分に向けられているのが嫉妬心だいうこともなんとなく理解していた。
でもそれは、冥焔のような人気者がちんちくりんの自分をかまっている事実が気に食わないからだ、と思っていたのに。
(好い関係……)
あの冥焔と、恋人関係である。そんな噂になっていたなんてあんまりではないか。
肩をがっくりと落とす。
(これから、あの宦官の半径一メートル以内に入らないようにしよう)
話を聞きたがる三女官を適当にかわしながら、麗麗は深く心に刻み込んだ。