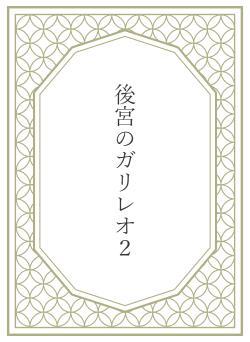頭痛がひどい。
冥焔はこめかみに指を置き、軽く押すとふうっと息をついた。墨壺が乾かないように蓋をし、筆を置く。書に書きつけられた墨がゆっくりと乾くさまを見ながら、その内容に思いを馳せた。
そこには、怪異が起こった時期と、内容がつぶさに記載されている。
ここ数日、怪異を訴える妃嬪が増えた。明らかに、百茗の宴での予言が原因である。
「冥焔様」
入室の言葉とともに房の入り口に顔を出した手のものが、控えめに冥焔に声をかけた。
「手が空きますでしょうか。大家がお呼びです」
「すぐに向かう」
手のものに筆と書の処理を任せ、房を出た。
外は晴れている。冬が近いからか、空は青く、そして遠い。風はすでに冷たく、身を切るような寒さである。
恩雲は院子の亭子にいた。すでに人払いはしてあるようで、他には誰の姿もない。
「さすがに、不用心ではないですか」
進められるがままに座卓に腰を下ろすと、冥焔は眉にしわを寄せた。
「こうした院子の一角のほうが、見晴らしがいいでしょう。下手に房に籠もっているより、よほど用心になる」
確かに、院子には植木もあるが、どれも皆、綺麗に剪定されており見晴らしがきく。こっそり誰かが近づくこともできないし、ましてや盗み聞きなどできないだろう。
床に広げられた緋毛氈の上には、器に盛られた胡餅や乾果。いそいそと手を伸ばす恩雲を押さえて、冥焔は自分の指先で乾果をつまんだ。口に含み、違和がないことを確認する。
「別に、かまわないのに」
「立場をお考えください。万が一、毒でも盛ってあったらどうするのです」
「大丈夫。これは手のものが用意してくれたやつだから」
「馬鹿ですか。いくら身内だからといって、油断してはいけません。特に、今のようなときには、なにが起こるかわからないのですから」
ため息をついて、冥焔は改めて恩雲の顔を見た。
「それで。例の予言の件ですか」
「ああ。お前からの報告にもあった通り、この数日で異変を訴える妃嬪が急増している」
「はい」
「あの女官を、瑛琳妃の元から外そうと思う」
そう言いながら、恩雲は今度こそ乾果をつまんで口に含んだ。
冥焔は目を閉じる。次に皇帝が告げるであろう言葉は、わかっている。
「白蓮妃を、調べろと」
「ああ」
冥焔は一瞬、目に暗い光を浮かべた。
「白蓮妃の予言を信じていらっしゃるのですか」
その問いには答えずに、恩雲は乾果を嚙み下した。
「例の儀式まで、あと八日」
そして、そのまま視線を空に漂わせた。
「何事もなければ、それでよい。しかし、なにかあってからでは遅すぎる」
「はい」
ふたりの間を、冷たい風が吹き抜けていく。
「魂霊は惑う、か……」
恩雲の呟きは、風に乗って空へと溶ける。
「まだ、この世が忘れられないのだろうか。あのお方は」
その言葉に、冥焔も同じく空を見上げた。
青空は澄み渡っている。冥焔が最後に見た皇太后の瞳のように、寒々しい青が広がっている。
冥焔はこめかみに指を置き、軽く押すとふうっと息をついた。墨壺が乾かないように蓋をし、筆を置く。書に書きつけられた墨がゆっくりと乾くさまを見ながら、その内容に思いを馳せた。
そこには、怪異が起こった時期と、内容がつぶさに記載されている。
ここ数日、怪異を訴える妃嬪が増えた。明らかに、百茗の宴での予言が原因である。
「冥焔様」
入室の言葉とともに房の入り口に顔を出した手のものが、控えめに冥焔に声をかけた。
「手が空きますでしょうか。大家がお呼びです」
「すぐに向かう」
手のものに筆と書の処理を任せ、房を出た。
外は晴れている。冬が近いからか、空は青く、そして遠い。風はすでに冷たく、身を切るような寒さである。
恩雲は院子の亭子にいた。すでに人払いはしてあるようで、他には誰の姿もない。
「さすがに、不用心ではないですか」
進められるがままに座卓に腰を下ろすと、冥焔は眉にしわを寄せた。
「こうした院子の一角のほうが、見晴らしがいいでしょう。下手に房に籠もっているより、よほど用心になる」
確かに、院子には植木もあるが、どれも皆、綺麗に剪定されており見晴らしがきく。こっそり誰かが近づくこともできないし、ましてや盗み聞きなどできないだろう。
床に広げられた緋毛氈の上には、器に盛られた胡餅や乾果。いそいそと手を伸ばす恩雲を押さえて、冥焔は自分の指先で乾果をつまんだ。口に含み、違和がないことを確認する。
「別に、かまわないのに」
「立場をお考えください。万が一、毒でも盛ってあったらどうするのです」
「大丈夫。これは手のものが用意してくれたやつだから」
「馬鹿ですか。いくら身内だからといって、油断してはいけません。特に、今のようなときには、なにが起こるかわからないのですから」
ため息をついて、冥焔は改めて恩雲の顔を見た。
「それで。例の予言の件ですか」
「ああ。お前からの報告にもあった通り、この数日で異変を訴える妃嬪が急増している」
「はい」
「あの女官を、瑛琳妃の元から外そうと思う」
そう言いながら、恩雲は今度こそ乾果をつまんで口に含んだ。
冥焔は目を閉じる。次に皇帝が告げるであろう言葉は、わかっている。
「白蓮妃を、調べろと」
「ああ」
冥焔は一瞬、目に暗い光を浮かべた。
「白蓮妃の予言を信じていらっしゃるのですか」
その問いには答えずに、恩雲は乾果を嚙み下した。
「例の儀式まで、あと八日」
そして、そのまま視線を空に漂わせた。
「何事もなければ、それでよい。しかし、なにかあってからでは遅すぎる」
「はい」
ふたりの間を、冷たい風が吹き抜けていく。
「魂霊は惑う、か……」
恩雲の呟きは、風に乗って空へと溶ける。
「まだ、この世が忘れられないのだろうか。あのお方は」
その言葉に、冥焔も同じく空を見上げた。
青空は澄み渡っている。冥焔が最後に見た皇太后の瞳のように、寒々しい青が広がっている。