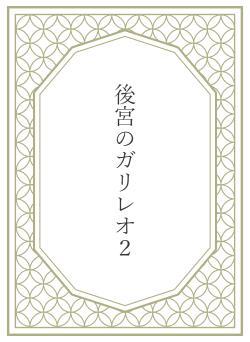「歩揺の出所がわからない、だって?」
冥焔の報告に、皇帝・恩雲は片眉を上げた。
「調べさせてはいるのですが、これが一筋縄ではいかないのです」
冥焔はこめかみを押さえ、ふーっと重い息をつく。
房は人払いをしており、皇帝とふたりきりだ。ことがことだけに、あまり大事にしたくない。毒物を知らずに持ち歩いていたとなれば、大混乱に陥る。それだけは避けねばならない。
歩揺の一件は、冥焔の下についている義理も口も堅い配下──手のものが文字通り手を回している。歩揺の回収と、それをどこから入手したのかという調査である。優秀な者ばかりだが、それでもかなり手こずっている。
「女官仲間からもらった、という話が一番多いのです。不安がっていたら、『心を落ち着かせるのにいいよ』ともらった、と。なまじ歩揺の出来がいいので、皆が喜んで受け取ったとか。しかし、誰からもらったのだという大本に話を聞いても、その人物は別の女官から受け取っているのですよ」
「へえ」
「意中の宦官からもらったのだという妃たちもおりますし」
すると、恩雲の目がきらっと輝く。
「その妃たちの一覧は」
「作成しております」
冥焔の言葉に、恩雲は満足そうにうなずいた。
後宮では、宦官と妃がねんごろな関係になるのはよくあることだ。皇帝がすべての妃を平等に扱えない以上、起こりうる。だからそれを格別に咎めはしない。だが、おおっぴらにいちゃつくとなると、話は変わってくる。皇帝の威信に関わるからだ。
そして、度の過ぎた愛情は時としてよからぬ方向へと向かっていく。それを防ぐためにも、誰と誰がどのような関係であるのか、ある程度把握しておくほうが都合がいい。
「仲のいい恋人たちを監視するのは、気が進まないけど。仕方がないよねえ」
「大家、仕方がないですまされては困ります」
「ま、それはいったん横に置いておこう。今は歩揺のほうが問題だ」
否はない。冥焔は咳払いをし、話を続けた。
「後宮にいる妃嬪、女官は上級、下級合わせれば千人を超えます。宦官も含めると、辿るのは容易ではありません。なるべく早く特定させ、大本をたたけるようにいたします」
「時間がかかりそうだね」
「不甲斐ない報告で大変申し訳ございません」
恩雲は長椅子にもたれかかるようにして息をついた。
「絞鬼が出た、ねえ……。まあ、みんなが不安になるのもしょうがないよね。あんなことがあったから」
冥焔は目を伏せた。胸の奥がじくりと痛む。
「すべて終わったことです。それに、死者はなにもできません」
「うん、そうだね」
恩雲は、えいやと長椅子から体を起こした。
「そういえば冥焔。あの可愛い女官はどうしてる?」
「どうしてる、とは?」
「今回も素晴らしい活躍をしてくれたのだから、褒美をやるのが礼儀だろう。まさか、なにも渡してないなんてことはないだろうね」
きらきらと目を輝かせる恩雲に、そうだ、と冥焔は手を打った。
「大家、その件でご報告なのですが」
「うんうん」
恩雲が身を乗り出して話を聞く。
「院子の石榴をひとつほど、もぎました」
「……うん? 石榴?」
「わたくしが手折ったので、彼女はお咎めなしでお願いいたします」
「待って、話がわからん」
「ですから、石榴を手折って、あの女官にあげたのです。わたくしがしたことですので、お許しください」
「……えっ、まさか、石榴を渡したのか、彼女に? 褒美として?」
恩雲はぎょっと目をむいた。なにをそれほどまでに驚いているのか、冥焔にはわからない。
正確には褒美ではなかった。ただ、なんとなくそうしてやりたくなったから石榴をもいで渡したのだ。だが、褒美という意味では褒美になるだろう。だから報告しただけなのだが、いったいその行為のどこに、驚く点があったのだろう。
黙っている冥焔を見て、恩雲は一度口を開き、なにかを言いかけ、また閉じる。そして長い長いため息とともに言葉を吐き出した。
「そうか、冥焔はあの女官を好いていたのだな」
「はあっ!?」
目をひんむいた冥焔である。恩雲はうんうんとしたり顔でうなずき、なんとも言えない笑みを浮かべてみせた。
「だが何事にも順番というものがある。まずは思いを伝え、気持ちが通じ合ってからでないと、受け入れてもらえないのではないか?」
「大家、なにを言っているのです!?」
「石榴を渡したのだろう? それはつまり、俺の子を産め、ということではないか」
(今、なにを聞いた?)
冥焔の頭の中を、恩雲の言葉がぐるぐると回る。
(子を産め? 俺の子を……?)
石榴は子孫繁栄の象徴である縁起物だ。その実を採って異性に渡すこと、これすなわち遠回しの告白──自分の子を産んでほしい、という意味になるのだ。
当然、冥焔は知らなかった。女官の反応を思い返す限り、あの女官も知らないだろう。どうかそのまま知らないままでいてほしい。というか気づくな、頼むから。
あまりのことに固まってしまった冥焔に、恩雲はからからと笑う。
「いいじゃないか。あの女官は見目もいい。気性はやや難しそうだが、そういう点でもお前と相性がよさそうだ」
「大家……」
はあ、と冥焔はため息をつく。
「わたくしは宦官ですよ」
「今は、だろう」
「おやめなさい!」
思わず声を荒らげた。
「……大家。わたくしはあなたの僕です。それ以上でも、以下でもありません。いいですね」
細い糸をぴんと張り詰めたかのような緊張が、ふたりの間に走った。
緊張を破ったのは恩雲だ。あきらめたように首を振ると、目元に揶揄の笑みを浮かべてみせる。
「にしても、冥焔って実は馬鹿でしょ」
恩雲の言葉に、冥焔はむっと唇を引き結んだ。
「馬鹿とはなんですか、馬鹿とは」
「大馬鹿でしょうが。功ある者に褒美を与えるなら、もっとちゃんとしたものを贈りなさい。それこそ歩揺とか、櫛とか、いろいろあるでしょうが」
「歩揺や、櫛、ですか……」
あの女官に飾り物を贈っている自分を想像して、冥焔はうっと言葉に詰まった。黙ってしまった冥焔の様子を見て、やれやれと恩雲は肩をすくめた。
「いいね、冥焔。次にその女官に会ったら、必ずちゃんとした褒美をやりなさい。これは命令だ。いいな」
それだけ言うと、恩雲は立ち上がる。冥焔の肩にぽんっと手を置いて。
「それとも、佩玉を用意させようか?」
佩玉は、腰に身につける大切な飾りだ。それを贈ることは求婚を意味する。
「冗談はおやめください」
冥焔の呆れたような声に恩雲はからからと笑い、その場をあとにした。
残された冥焔は頭を抱える。
命じられたからには、褒美を渡さねばならぬ。だがいったい、なにを渡せばいい?
生まれてこの方、女性に贈り物などしたことがない。どんな表情で、どのような口上をもってして、そしてなにを贈ればいいのか一向にわからず、途方に暮れてしまう。
歩揺の出所を突き止めるよりも、こちらの問題のほうが難航しそうだ。
冥焔は深いため息をついた。
冥焔の報告に、皇帝・恩雲は片眉を上げた。
「調べさせてはいるのですが、これが一筋縄ではいかないのです」
冥焔はこめかみを押さえ、ふーっと重い息をつく。
房は人払いをしており、皇帝とふたりきりだ。ことがことだけに、あまり大事にしたくない。毒物を知らずに持ち歩いていたとなれば、大混乱に陥る。それだけは避けねばならない。
歩揺の一件は、冥焔の下についている義理も口も堅い配下──手のものが文字通り手を回している。歩揺の回収と、それをどこから入手したのかという調査である。優秀な者ばかりだが、それでもかなり手こずっている。
「女官仲間からもらった、という話が一番多いのです。不安がっていたら、『心を落ち着かせるのにいいよ』ともらった、と。なまじ歩揺の出来がいいので、皆が喜んで受け取ったとか。しかし、誰からもらったのだという大本に話を聞いても、その人物は別の女官から受け取っているのですよ」
「へえ」
「意中の宦官からもらったのだという妃たちもおりますし」
すると、恩雲の目がきらっと輝く。
「その妃たちの一覧は」
「作成しております」
冥焔の言葉に、恩雲は満足そうにうなずいた。
後宮では、宦官と妃がねんごろな関係になるのはよくあることだ。皇帝がすべての妃を平等に扱えない以上、起こりうる。だからそれを格別に咎めはしない。だが、おおっぴらにいちゃつくとなると、話は変わってくる。皇帝の威信に関わるからだ。
そして、度の過ぎた愛情は時としてよからぬ方向へと向かっていく。それを防ぐためにも、誰と誰がどのような関係であるのか、ある程度把握しておくほうが都合がいい。
「仲のいい恋人たちを監視するのは、気が進まないけど。仕方がないよねえ」
「大家、仕方がないですまされては困ります」
「ま、それはいったん横に置いておこう。今は歩揺のほうが問題だ」
否はない。冥焔は咳払いをし、話を続けた。
「後宮にいる妃嬪、女官は上級、下級合わせれば千人を超えます。宦官も含めると、辿るのは容易ではありません。なるべく早く特定させ、大本をたたけるようにいたします」
「時間がかかりそうだね」
「不甲斐ない報告で大変申し訳ございません」
恩雲は長椅子にもたれかかるようにして息をついた。
「絞鬼が出た、ねえ……。まあ、みんなが不安になるのもしょうがないよね。あんなことがあったから」
冥焔は目を伏せた。胸の奥がじくりと痛む。
「すべて終わったことです。それに、死者はなにもできません」
「うん、そうだね」
恩雲は、えいやと長椅子から体を起こした。
「そういえば冥焔。あの可愛い女官はどうしてる?」
「どうしてる、とは?」
「今回も素晴らしい活躍をしてくれたのだから、褒美をやるのが礼儀だろう。まさか、なにも渡してないなんてことはないだろうね」
きらきらと目を輝かせる恩雲に、そうだ、と冥焔は手を打った。
「大家、その件でご報告なのですが」
「うんうん」
恩雲が身を乗り出して話を聞く。
「院子の石榴をひとつほど、もぎました」
「……うん? 石榴?」
「わたくしが手折ったので、彼女はお咎めなしでお願いいたします」
「待って、話がわからん」
「ですから、石榴を手折って、あの女官にあげたのです。わたくしがしたことですので、お許しください」
「……えっ、まさか、石榴を渡したのか、彼女に? 褒美として?」
恩雲はぎょっと目をむいた。なにをそれほどまでに驚いているのか、冥焔にはわからない。
正確には褒美ではなかった。ただ、なんとなくそうしてやりたくなったから石榴をもいで渡したのだ。だが、褒美という意味では褒美になるだろう。だから報告しただけなのだが、いったいその行為のどこに、驚く点があったのだろう。
黙っている冥焔を見て、恩雲は一度口を開き、なにかを言いかけ、また閉じる。そして長い長いため息とともに言葉を吐き出した。
「そうか、冥焔はあの女官を好いていたのだな」
「はあっ!?」
目をひんむいた冥焔である。恩雲はうんうんとしたり顔でうなずき、なんとも言えない笑みを浮かべてみせた。
「だが何事にも順番というものがある。まずは思いを伝え、気持ちが通じ合ってからでないと、受け入れてもらえないのではないか?」
「大家、なにを言っているのです!?」
「石榴を渡したのだろう? それはつまり、俺の子を産め、ということではないか」
(今、なにを聞いた?)
冥焔の頭の中を、恩雲の言葉がぐるぐると回る。
(子を産め? 俺の子を……?)
石榴は子孫繁栄の象徴である縁起物だ。その実を採って異性に渡すこと、これすなわち遠回しの告白──自分の子を産んでほしい、という意味になるのだ。
当然、冥焔は知らなかった。女官の反応を思い返す限り、あの女官も知らないだろう。どうかそのまま知らないままでいてほしい。というか気づくな、頼むから。
あまりのことに固まってしまった冥焔に、恩雲はからからと笑う。
「いいじゃないか。あの女官は見目もいい。気性はやや難しそうだが、そういう点でもお前と相性がよさそうだ」
「大家……」
はあ、と冥焔はため息をつく。
「わたくしは宦官ですよ」
「今は、だろう」
「おやめなさい!」
思わず声を荒らげた。
「……大家。わたくしはあなたの僕です。それ以上でも、以下でもありません。いいですね」
細い糸をぴんと張り詰めたかのような緊張が、ふたりの間に走った。
緊張を破ったのは恩雲だ。あきらめたように首を振ると、目元に揶揄の笑みを浮かべてみせる。
「にしても、冥焔って実は馬鹿でしょ」
恩雲の言葉に、冥焔はむっと唇を引き結んだ。
「馬鹿とはなんですか、馬鹿とは」
「大馬鹿でしょうが。功ある者に褒美を与えるなら、もっとちゃんとしたものを贈りなさい。それこそ歩揺とか、櫛とか、いろいろあるでしょうが」
「歩揺や、櫛、ですか……」
あの女官に飾り物を贈っている自分を想像して、冥焔はうっと言葉に詰まった。黙ってしまった冥焔の様子を見て、やれやれと恩雲は肩をすくめた。
「いいね、冥焔。次にその女官に会ったら、必ずちゃんとした褒美をやりなさい。これは命令だ。いいな」
それだけ言うと、恩雲は立ち上がる。冥焔の肩にぽんっと手を置いて。
「それとも、佩玉を用意させようか?」
佩玉は、腰に身につける大切な飾りだ。それを贈ることは求婚を意味する。
「冗談はおやめください」
冥焔の呆れたような声に恩雲はからからと笑い、その場をあとにした。
残された冥焔は頭を抱える。
命じられたからには、褒美を渡さねばならぬ。だがいったい、なにを渡せばいい?
生まれてこの方、女性に贈り物などしたことがない。どんな表情で、どのような口上をもってして、そしてなにを贈ればいいのか一向にわからず、途方に暮れてしまう。
歩揺の出所を突き止めるよりも、こちらの問題のほうが難航しそうだ。
冥焔は深いため息をついた。