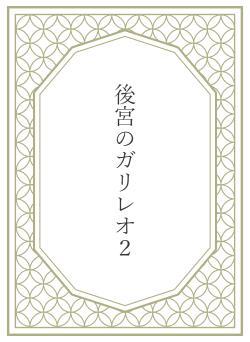「これは隙間風です。このように壁に少しだけ穴が空いた状態で、そこを風が勢いよく通り抜けることによって、泣き声のような音が出るんですよ」
麗麗の説明を聞いて、妃は青ざめた顔をほんの少しだけゆるめた。
「ほ、本当ですか? 呪いではないのですね」
「はい」
断言すると、妃は顔を覆って泣き始める。
「よ、よかった……! もう本当に怖かったんです。わたくし、呪われて死ぬのではないかと」
「大丈夫ですよ、死にませんから」
(あーしんどい)
麗麗はちらっと後ろにいる冥焔に視線を向けた。
(さっさと仕事してくんないかな)
その思いが通じたようで、冥焔は一歩進み出る。妃は圧倒されたように息を呑み、青かった顔はみるみる赤くなっていく。
「この女官の言う通り、呪いなど存在しません。世迷い言に惑わされることなく、自らの勤めを果たしていただきますよう、お願い申し上げます」
「は、はい……!」
妃はおびえた様子はどこへやら。顔をほわっと赤らめ、とろんとした顔の乙女に様変わりしていた。
(美形ってすごいな)
皇帝から妙な厳命を受けて数日がたった。仕方なく麗麗は冥焔と行動を共にし、怪異の調査と解決に当たっているというわけだ。
初めはおとなしく、相手の顔を立ててしおらしく(当社比)していた麗麗だったが、そのうち馬鹿らしくなった。
この冥焔という宦官は、人使いがとにかく荒い。こっちの事情もおかまいなしに現れては、事情説明もほどほどに、あれよあれよと現場に連れていかれるのである。しかも、やたら偉そうだ。
礼儀がなっていない人に、礼儀を通す義理はない。多少の意趣返しは許してもらいたい。ということで、麗麗は気を遣うのを早々にやめた。
それにしても恐ろしいのは、その怪異の物量だった。あっちでもこっちでも幽鬼やら呪いやらがわんさかで、さすがの麗麗も少々食傷気味になっていた。
妃の宮を出て、麗麗は伸びをする。
「にしても、呪いだのなんだの、なんなんですかねこの量は。どっから湧いてくるんだ。温泉か」
冥焔はむっとしたように顔をしかめた。
「文句を言うな。大家の命だぞ」
わかっている。でも愚痴くらい許してほしい。
「おい、女官。さっきのあれだが」
「どれです」
「俺が最後に妃に声をかけるという、あれだ。あれは必要なのか?」
「当たり前です」
麗麗はふんすと鼻息を荒くした。
「冥焔様は私ひとりに怪異の解決を押しつけようとなさっていますが」
図星だったのだろう、ぴくっと冥焔の眉がはねた。
「それだと本当の解決にはなりません。相手の不安を取り除いて差し上げて、ようやく問題が解決するのです」
おびえた妃たちは、麗麗の話の半分くらいが理解できていればいいほうだと思っている。なにしろ麗麗は女官であるし、身分が低い。そんなやつがしゃしゃり出て、『はいこれで証明しました』なんて言ったところで誰が安心するだろう。
この宦官が後宮の人気者なのは間違いないし、どうやら地位も高いらしい。そういった立場の者が声をかけて、ようやく混乱が収まるというものだ。それに。
「冥焔様は大変お顔がよろしいので、思った以上に効果があります。ご自身の強みを活かしていただきたいと存じます」
「意味がわからぬ」
「自分だけ楽をしようとしないでくださいってことですよ」
麗麗の説明を聞いて、妃は青ざめた顔をほんの少しだけゆるめた。
「ほ、本当ですか? 呪いではないのですね」
「はい」
断言すると、妃は顔を覆って泣き始める。
「よ、よかった……! もう本当に怖かったんです。わたくし、呪われて死ぬのではないかと」
「大丈夫ですよ、死にませんから」
(あーしんどい)
麗麗はちらっと後ろにいる冥焔に視線を向けた。
(さっさと仕事してくんないかな)
その思いが通じたようで、冥焔は一歩進み出る。妃は圧倒されたように息を呑み、青かった顔はみるみる赤くなっていく。
「この女官の言う通り、呪いなど存在しません。世迷い言に惑わされることなく、自らの勤めを果たしていただきますよう、お願い申し上げます」
「は、はい……!」
妃はおびえた様子はどこへやら。顔をほわっと赤らめ、とろんとした顔の乙女に様変わりしていた。
(美形ってすごいな)
皇帝から妙な厳命を受けて数日がたった。仕方なく麗麗は冥焔と行動を共にし、怪異の調査と解決に当たっているというわけだ。
初めはおとなしく、相手の顔を立ててしおらしく(当社比)していた麗麗だったが、そのうち馬鹿らしくなった。
この冥焔という宦官は、人使いがとにかく荒い。こっちの事情もおかまいなしに現れては、事情説明もほどほどに、あれよあれよと現場に連れていかれるのである。しかも、やたら偉そうだ。
礼儀がなっていない人に、礼儀を通す義理はない。多少の意趣返しは許してもらいたい。ということで、麗麗は気を遣うのを早々にやめた。
それにしても恐ろしいのは、その怪異の物量だった。あっちでもこっちでも幽鬼やら呪いやらがわんさかで、さすがの麗麗も少々食傷気味になっていた。
妃の宮を出て、麗麗は伸びをする。
「にしても、呪いだのなんだの、なんなんですかねこの量は。どっから湧いてくるんだ。温泉か」
冥焔はむっとしたように顔をしかめた。
「文句を言うな。大家の命だぞ」
わかっている。でも愚痴くらい許してほしい。
「おい、女官。さっきのあれだが」
「どれです」
「俺が最後に妃に声をかけるという、あれだ。あれは必要なのか?」
「当たり前です」
麗麗はふんすと鼻息を荒くした。
「冥焔様は私ひとりに怪異の解決を押しつけようとなさっていますが」
図星だったのだろう、ぴくっと冥焔の眉がはねた。
「それだと本当の解決にはなりません。相手の不安を取り除いて差し上げて、ようやく問題が解決するのです」
おびえた妃たちは、麗麗の話の半分くらいが理解できていればいいほうだと思っている。なにしろ麗麗は女官であるし、身分が低い。そんなやつがしゃしゃり出て、『はいこれで証明しました』なんて言ったところで誰が安心するだろう。
この宦官が後宮の人気者なのは間違いないし、どうやら地位も高いらしい。そういった立場の者が声をかけて、ようやく混乱が収まるというものだ。それに。
「冥焔様は大変お顔がよろしいので、思った以上に効果があります。ご自身の強みを活かしていただきたいと存じます」
「意味がわからぬ」
「自分だけ楽をしようとしないでくださいってことですよ」