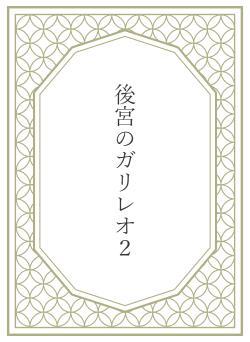「大家」
不本意、いや不愉快である。
例の女官が房を辞したあと、冥焔は皇帝・恩雲とふたりきりでその場に残っていた。
本来なら自身もあの女官と共に退出し、見張りの宦官にあとを頼むと伝えるべきである。しかし、どうしても黙ってはいられなかったのだ。
「どういうおつもりですか」
「そう怖い顔をするな、冥焔」
恩雲はにこっと微笑み、椅子の手すりに肘をつき、手の甲で頭を支えた。そうしてくだけた姿勢で座っていると、若々しい顔がよりいっそう年相応に見える。
皇帝はまだ十七歳。自分よりも三つ年下だというのを踏まえても、やはりこうしたほんの少しの所作や、好奇心に輝く黒い瞳に、少年らしさがにじみ出てしまう。ゆえに、普段であれば『みっともないからおやめください』と叱る冥焔だが、今回はさすがに呆れて言葉にならない。
「本気ですか? あの女官と、わたくしが、ふたりで?」
「本気だとも」
「なぜ」
「そりゃあ、さっき言った通りだよ。いち女官がなんの後ろ盾もなしに、あっちの宮やこっちの宮に行ったり来たりできないでしょう。彼女が不安に思うのも無理はない」
なにを言っているんだ、と冥焔は苦い顔をした。
「だからこそ、瑛琳妃のお付きにという話ではなかったのですか」
あの女官の後ろ盾には、有力な人物が必要だ。それは冥焔とてわかっていることである。
いち女官の命は軽い。しかもあの気性だ。どう見ても世渡り下手だし、それはこの後宮では文字通り命取りとなる。あのぽんぽん回る口は、どこで怒りを買うかわかったものではない。皇帝や冥焔が見ていないところで勝手に処刑されていたら困るのだ。
そんな中で後ろ盾に手を上げてくれたのは、瑛琳妃だ。どうやらあの呪いの房を解決した女官に恩義を感じているようで、うちの女官に、と皇帝に頼んでくれたらしい。
上級妃の女官という肩書きがあれば、多少言動がおかしくても、怒りを買ったとしても、なんとかなることが多い。少なくとも今の下級女官という立場よりは安心である。
「そうなんだけどね。あれはすごいな。あそこまで感情が顔に出るのはいっそ才能だね」
恩雲はおもしろくて仕方ないという顔をして、顎を撫でた。
「見たか? あの女官の顔。お前とお近づきになりたくて『一緒に』と進言したんじゃない。意趣返しだ。理不尽だからお前も協力しろ、と言いたかったんだろうな。豪胆な子だね」
「わかっていて、大家はわたくしに協力しろと仰せで?」
「もちろんだとも!」
体を起こし、恩雲は胸を張る。
「あの娘はとんでもないね。瑛琳でもかばいきれないなにかが起こる やもしれない。そうなったときに、冥焔。お前が必要でしょう」
冥焔は深いため息をつく。
「なれば、大家がひとことお声をかければよろしいではありませんか。あの女官にはかまうなと。それですむお話だと存じますが」
冥焔の言葉に、恩雲はやれやれと首を振った。
「もっとよく考えて。わたしがかばったらそれはそれでことでしょう。お前は、あの娘が後宮の闇に引き裂かれるのが見たいわけではないよね?」
ぐっと冥焔は言葉を呑んだ。
その通りだ。皇帝に目をかけられたとわかったなら、どんな魔の手があの女官に伸びるのかわかったものじゃない。
(だからこそ、一度後宮を空にしたというのに)
徹底的に粛正したつもりだったが、後宮に闇は凝ったままだ。それどころか闇はさらに深まり、その闇から噴き出るように怪異があふれ、はびこっている。
(いったいなにが起きているんだ……)
ひやひやとした嫌な予感が、冥焔の背筋を撫でる。
呪い。幽鬼。魔物。妖魔。その他怪しげな事象を、以前の冥焔は馬鹿馬鹿しいと感じていた。そんなものにうつつを抜かしているなど、万死に値する。だが。
(もう俺は繰り返さない)
怪異はだめだ。絶対に、放置してはいけない。早急に解決しなければ、また取り返しのつかないことになる。
あの女官を見つけたときはしめたものと思ったのだ。
怪異が怪異ではないという事実を証明できる唯一の駒を手放してなるものか。だからこそ、皇帝の勅命という形で縛ろうとした。
出世を喜ばない者はいない。ゆえに問題ないと判断した。しかし、あの女官にはそれが理不尽に感じられたということか。
「冥焔」
皇帝の柔らかな声が冥焔の耳に落ちる。
「わたしは、あなたがあの女官とやり合っているのが楽しくて仕方ないんです。冷酷無比、謹厳実直のあなたが、いきいきとした顔を見せるのが、嬉しいんですよ」
「大家」
むっと冥焔は顔をしかめる。
「敬語はおやめください」
不本意、いや不愉快である。
例の女官が房を辞したあと、冥焔は皇帝・恩雲とふたりきりでその場に残っていた。
本来なら自身もあの女官と共に退出し、見張りの宦官にあとを頼むと伝えるべきである。しかし、どうしても黙ってはいられなかったのだ。
「どういうおつもりですか」
「そう怖い顔をするな、冥焔」
恩雲はにこっと微笑み、椅子の手すりに肘をつき、手の甲で頭を支えた。そうしてくだけた姿勢で座っていると、若々しい顔がよりいっそう年相応に見える。
皇帝はまだ十七歳。自分よりも三つ年下だというのを踏まえても、やはりこうしたほんの少しの所作や、好奇心に輝く黒い瞳に、少年らしさがにじみ出てしまう。ゆえに、普段であれば『みっともないからおやめください』と叱る冥焔だが、今回はさすがに呆れて言葉にならない。
「本気ですか? あの女官と、わたくしが、ふたりで?」
「本気だとも」
「なぜ」
「そりゃあ、さっき言った通りだよ。いち女官がなんの後ろ盾もなしに、あっちの宮やこっちの宮に行ったり来たりできないでしょう。彼女が不安に思うのも無理はない」
なにを言っているんだ、と冥焔は苦い顔をした。
「だからこそ、瑛琳妃のお付きにという話ではなかったのですか」
あの女官の後ろ盾には、有力な人物が必要だ。それは冥焔とてわかっていることである。
いち女官の命は軽い。しかもあの気性だ。どう見ても世渡り下手だし、それはこの後宮では文字通り命取りとなる。あのぽんぽん回る口は、どこで怒りを買うかわかったものではない。皇帝や冥焔が見ていないところで勝手に処刑されていたら困るのだ。
そんな中で後ろ盾に手を上げてくれたのは、瑛琳妃だ。どうやらあの呪いの房を解決した女官に恩義を感じているようで、うちの女官に、と皇帝に頼んでくれたらしい。
上級妃の女官という肩書きがあれば、多少言動がおかしくても、怒りを買ったとしても、なんとかなることが多い。少なくとも今の下級女官という立場よりは安心である。
「そうなんだけどね。あれはすごいな。あそこまで感情が顔に出るのはいっそ才能だね」
恩雲はおもしろくて仕方ないという顔をして、顎を撫でた。
「見たか? あの女官の顔。お前とお近づきになりたくて『一緒に』と進言したんじゃない。意趣返しだ。理不尽だからお前も協力しろ、と言いたかったんだろうな。豪胆な子だね」
「わかっていて、大家はわたくしに協力しろと仰せで?」
「もちろんだとも!」
体を起こし、恩雲は胸を張る。
「あの娘はとんでもないね。瑛琳でもかばいきれないなにかが起こる やもしれない。そうなったときに、冥焔。お前が必要でしょう」
冥焔は深いため息をつく。
「なれば、大家がひとことお声をかければよろしいではありませんか。あの女官にはかまうなと。それですむお話だと存じますが」
冥焔の言葉に、恩雲はやれやれと首を振った。
「もっとよく考えて。わたしがかばったらそれはそれでことでしょう。お前は、あの娘が後宮の闇に引き裂かれるのが見たいわけではないよね?」
ぐっと冥焔は言葉を呑んだ。
その通りだ。皇帝に目をかけられたとわかったなら、どんな魔の手があの女官に伸びるのかわかったものじゃない。
(だからこそ、一度後宮を空にしたというのに)
徹底的に粛正したつもりだったが、後宮に闇は凝ったままだ。それどころか闇はさらに深まり、その闇から噴き出るように怪異があふれ、はびこっている。
(いったいなにが起きているんだ……)
ひやひやとした嫌な予感が、冥焔の背筋を撫でる。
呪い。幽鬼。魔物。妖魔。その他怪しげな事象を、以前の冥焔は馬鹿馬鹿しいと感じていた。そんなものにうつつを抜かしているなど、万死に値する。だが。
(もう俺は繰り返さない)
怪異はだめだ。絶対に、放置してはいけない。早急に解決しなければ、また取り返しのつかないことになる。
あの女官を見つけたときはしめたものと思ったのだ。
怪異が怪異ではないという事実を証明できる唯一の駒を手放してなるものか。だからこそ、皇帝の勅命という形で縛ろうとした。
出世を喜ばない者はいない。ゆえに問題ないと判断した。しかし、あの女官にはそれが理不尽に感じられたということか。
「冥焔」
皇帝の柔らかな声が冥焔の耳に落ちる。
「わたしは、あなたがあの女官とやり合っているのが楽しくて仕方ないんです。冷酷無比、謹厳実直のあなたが、いきいきとした顔を見せるのが、嬉しいんですよ」
「大家」
むっと冥焔は顔をしかめる。
「敬語はおやめください」