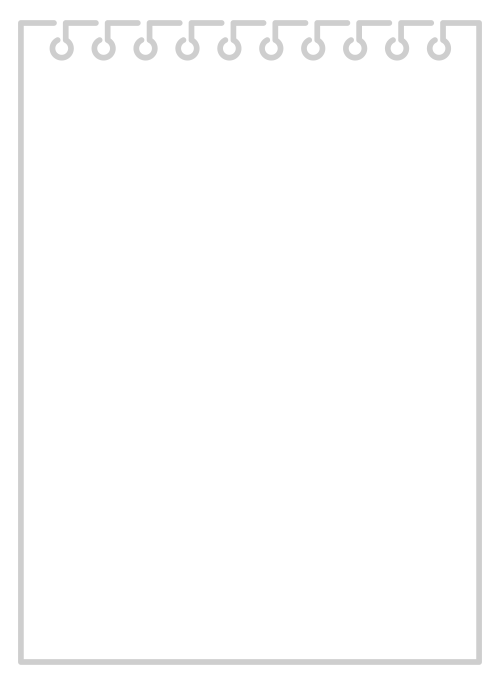どれぐらい眠っていたのだろう。
相変わらず、体の痛みは残っている。でも先ほどよりはほんの少しだけ、マシになったような気もしないでもない。
瞼を開ける。数秒。
ぼやけた視界。白い天井が明るく映る。徐々にハッキリと開ける視界。綺麗で白いと思っていた天井は、割と年季が入っていた。
「――――真村くん」
少し驚いた。
誰も居ないと思っていたから。
ベッドに横たわる俺の左側に、綺麗な黒髪をした少女。その顔には見覚えがあった。
「なん、で?」
すごく久しぶりに声を出した気がする。自分でも分かるほど、掠れて痛々しい声だった。
それでも、彼女、酒井凪沙は不快な顔をしない。それどころか、すごく安心したように優しく微笑んでみせた。
「声出すの、つらい?」
つらくはないが、出したいとも思わない。ほんのわずかに動く首を縦に振ると、彼女は「うん」と相槌を打った。
「よかった。本当に、本当に……」
彼女の手が、俺の左手に伸びる。
こうして誰かに手を握られたのは、すごく久々な気がする。そしてそれは、すごく暖かくて心が溶けていくような錯覚を覚えた。
視線で彼女を見ると、俯いていた。泣いているのだろうか。小さくて細い肩が揺れている。
あぁ、そういえば。
さっきもこんなことあったっけ。さっきがいつ頃だったかは分からないけど、こうして酒井に手を握られていた。
その時からずっと、俺の側に居たのかな。だとしたら、なんでそこまでして?
――――私は、あなたの恋人なの。
不思議なモノだ。
そんな事実は一切無いのに、嘘でもこんな可愛い子にそう言われると心が躍る。人間、というか男というのは、ひどく単純で馬鹿な生き物なのかもしれない。その証拠は、俺だ。
そもそもの話。
何故、彼女は俺にそんな《《嘘》》を吐いたのだろうか。純粋に揶揄っているのだろうか。……いや、彼女の表情を見る限りそんな感じはしない。まさに、俺の為に涙を流してくれている。
「覚えてる? 私のことも、これまでのことも」
そう言われて、記憶をたぐり寄せてみる。
名前は覚えている。真村真嗣。そしてこの子は、クラスメイトの酒井凪沙。俺たちは夏ヶ丘高校に通う高校二年生だ。
あぁ、そうそう。今は夏休みで、その帰り道に車に撥ねられたんだっけ。
衝撃の瞬間のことは、正直あまり思い出したくない。今こうして、病院のベッドに横になっていて、意識もある。助かったのだから、それで良い。
「真村くん?」
彼女の問いかけに返答するのを忘れていた。
首を縦に振るだけで、酒井には伝わるはず。そうだと分かっていたのに。
「覚えてる」
酒井は、少し驚いていた。
覚えていないと思っていたのだろうか。でも、少しだけ、ほんの少しだけ口角が上がった。
「よかった」
その一言には、すごく沢山の想いが込められているような。本当にこの子は俺に《《好意》》を寄せてくれている。確信なんてモノは無かったけれど、そんな気がして、すごく気分が良くなった。
そこでようやく、頭が包帯でぐるぐる巻きにされていることに気づいた。さっきからの脳を締め付けるような圧迫感は、これが原因だったのか。それとも、純粋に俺の記憶が傷ついているだけの痛みなのか。よくわからない。
「さっきまで藤村先生も居たの。でも、目が覚めたって分かったら学校に戻っちゃった」
担任の名前を聞いて、妙に体が強張った。色々と学校にも、酒井にも迷惑をかけたようだ。それもそうだ。夏休み中の事故。しかも補習帰りとなれば、学校側の監督責任が問われかねない。そういう意味でも、俺が目を覚ましたのは良かったのだろう。
ずっと彼女は、俺の手を握ってくれている。恥ずかしさは感じない。むしろ安心感でまた眠ってしまいそうだ。
そうだ。この子は俺の恋人なのだ。俺は知らないが、彼女がそう言うのだから、きっとそう。
「退院したら、何したい?」
酒井凪沙の優しさ。その海に浸かり切ってしまったせいか、特になんとも思っていなかったクラスメイトが、非常に可愛く見える。
あまり声を出して欲しくないのは本音だろうが、こうして問いかけてくるあたり、俺と会話したい気持ちを抑えきれないらしい。可愛い奴だ。
「だったら」
「だったら?」
「とりあえず」
「とりあえず?」
「君とチューしたい」
「ほぉ、なるほど」
飲み込んだかのように思えた態度。奥歯で言葉を噛み砕いているが、それが異物だと気づいたらしく。
「ちゅ、ちゅ、チュー!?」
病室に似合わない声で吐き出した。
恋人同士にとって、チューなんてのは挨拶にすぎない。本音を言えば、こんな可愛い子を捕まえるなんてことは、この先ないだろう。だからもっと先までシタイ。
あからさまに狼狽えたくせに、俺の表情を見た途端に、キリッと顔を作り直している。
「そ、そういうのは……まだ」
すっかり、忘れていた。
きっと彼女は俺を揶揄っているだけだ。酒井凪沙というクラスメイトの性格を、俺はよく知っている。
可愛くて、人気者で、お調子者で。すごくポジティブな子。俺が事故で落ち込んでいると思ったのだろう。だからこうやって「恋人」だなんて嘘を吐く。
根幹にあるのは、俺に元気を出して欲しいという想い。それも彼女なりの優しさであることは分かる。が、生憎俺はそんな嘘は嫌いだ。
恋人だなんて、誰も救われない嘘。でも、一度それに乗っかってしまったのは事実だ。
……いや、もう。
一度死にかけたのだから。
俺に、失うモノは何一つ無い。
「ほ、ほ、ほら。まだしばらく入院みたいだから」
「退院したら」
「えっ?」
「退院したら、いい?」
だから俺は、意地でも君とキスしてやる。