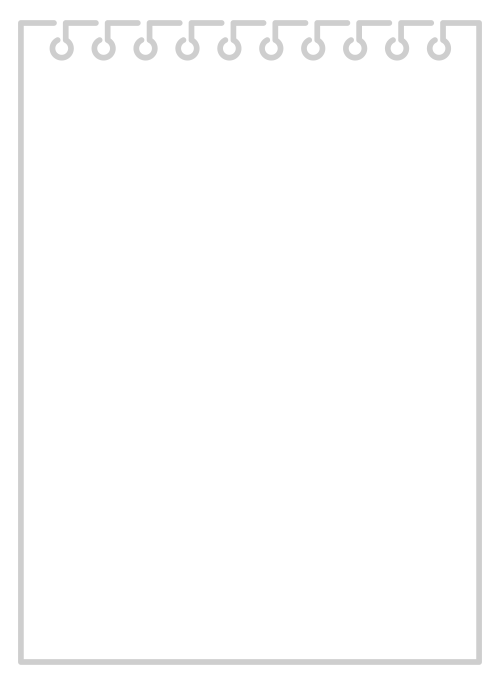深い。とても深い。
暗闇ではない。うっすらと橙色に染まった視界。やけに反響する機械音。それは単調で憂鬱になる。
深い。何故か分からない。直感的にそう感じてしまっただけ。根拠なんて一切存在しない。
眠っている時の感じではない。現にこうして、辺りを見渡すだけの意識が残っている。でも不思議と、眠っている時よりも体が軽くてとても心地が良い。
記憶もしっかりある。
真村真嗣。高校二年。今この場で頭をフル回転させているのは紛れもなく俺本人。とりあえずは一安心だが、疑問は尽きない。そもそも、何故俺はこんな場所に居る? ここは俺が知っている現実世界なのだろうか。
記憶を遡ろうとすると、猛烈に頭が痛む。一旦やめて、もう一度試みる。……やっぱりダメだ。痛い。
それでも、断片的に脳裏に浮かぶピース。それをパズルのように組み合わせていけば、きっと俺が欲しい情報は手に入るはず。
だけど、出来なかった。
理性ではない、俺の本能がそれを拒否した。何を思ってか「それを知る必要はない」と強く言われているような気がして。
直前まで、誰かと一緒に居た。
ふと蘇る記憶。髪の長い彼女と。
いや、確か後ろで結ってたような、そうじゃないような。いずれにしても、すごく可愛らしい子と一緒に居た気がする。
恋人とかじゃない。それは断言できた。切ないというか、純粋に悲しかったりする。でも今はどうでも良いや。この心地の良い空間で、永遠に過ごせるのなら、それで。
――――じ
一瞬だ。ほんの一瞬だけ、頭を殴られた。
振り返る。誰も居ない。殴られたような錯覚だったのか。にしても痛い。
前を見る。果てしなく広がっている橙色の世界。俺以外に誰も居ない。この果てはどうなっているのだろう。勇者であれば、きっと足を進めるだろうが、生憎俺はそんなんじゃない。ただここに立ち尽くすだけ。
――――しんじ
俺の名前だ。頭の痛みはない。
誰かが俺を呼んでいる。無機質な声。男か女かも分からない。
まるで、空から声が降ってくるような感覚だった。傘でも差さないとそれを一身に浴びることになる。べっとりと体に纏わりつく無機質声がすごく気持ち悪い。
――――真嗣っ!
声が変わった。女性の声。
力強さの中に、どこか落ち着きのある声。相変わらず空から声が降ってくるが、纏わりつくような気持ち悪さはない。むしろ今度はとても心地良い。本能的に、俺の好きな声だった。
痛む頭の中に、天秤が出てくる。
心地の良い空間に一人で居るのか。それとも、この声を信じるべきか。
前者だ。圧倒的に。いくら後者の声が好きだとしても、この空間に敵うほどではない。
でも、一人。これから先もずっと、いずれ自分が真村真嗣であること忘れてしまっても。たった一人で存在し続けなければならない。
なんというか、それは寂しい。
でも、声を信じてしまったら、《《また》》きっと辛いことに埋もれる人生に逆戻りするだろう。
なんだろうか。
この拭えない違和感は。このままだと俺は、もう二度とこの場から出ることが出来ない確信があった。すなわちそれは、俺の。
――――生きたいなぁ。
あぁ、そうか。
俺は、死にかけているんだ。
世界が光り輝く。眩しい。
あれだけ心地良かった体の節々に走る痛み。そして感じる、手のひらのぬくもり。
誰かに手を握られている。気のせいじゃない。これは確かだ。痛む全身の中で、そこだけ痛くない。あの世界のように心地が良い。
「――――真村、くん」
聞き覚えのある声。落ち着いていて、とても優しい声。
覚醒していく頭。そこで初めて、瞼が固まり切っていることに気付いた。
瞬間接着剤でくっついているように、力を入れても視界が開けない。
「私が、分かる?」
ぼんやりしていて、よく分からない。
《《彼女》》がそう言うのなら、瞼が開いているのだろう。久々に開いたからか、曇りガラスのように濁った視界。声の主が誰かなんて分からなかった。だから、答えを躊躇う。そもそも、喉を開く力も残っていなかった。
手のひら。手の甲。しっかりと、優しく包み込まれていて感覚が過敏になっているよう。
時折、冷たい何かがポツリと当たる。泣いているのだろうか。こんな俺の為に、彼女は涙を流してくれているのだろうか。
そんなことを考える。自分の状況はイマイチ理解出来ていないが、俺は何かしらの事故で搬送されたのは直感で理解出来た。
せっかく瞼が開いたのに、痛みと疲れで猛烈に眠い。今すぐにでもそうしたいが、何というか、彼女のことが気になって一生懸命視線を動かしてみる。
「ふふっ」
あ、笑った。
さっきまで泣いていたのに、微笑んだ。
よく見えないけど、きっとすごく綺麗で可愛い子なんだろうな。上品さの中にクシャッとした愛嬌。こんな子が俺の手を握ってくれているなんて。その状況がまず奇跡だ。
「私は、あなたの恋人よ」
そんなわけねぇよ。
心の中で盛大にツッコんで、また眠りに落ちてしまった。