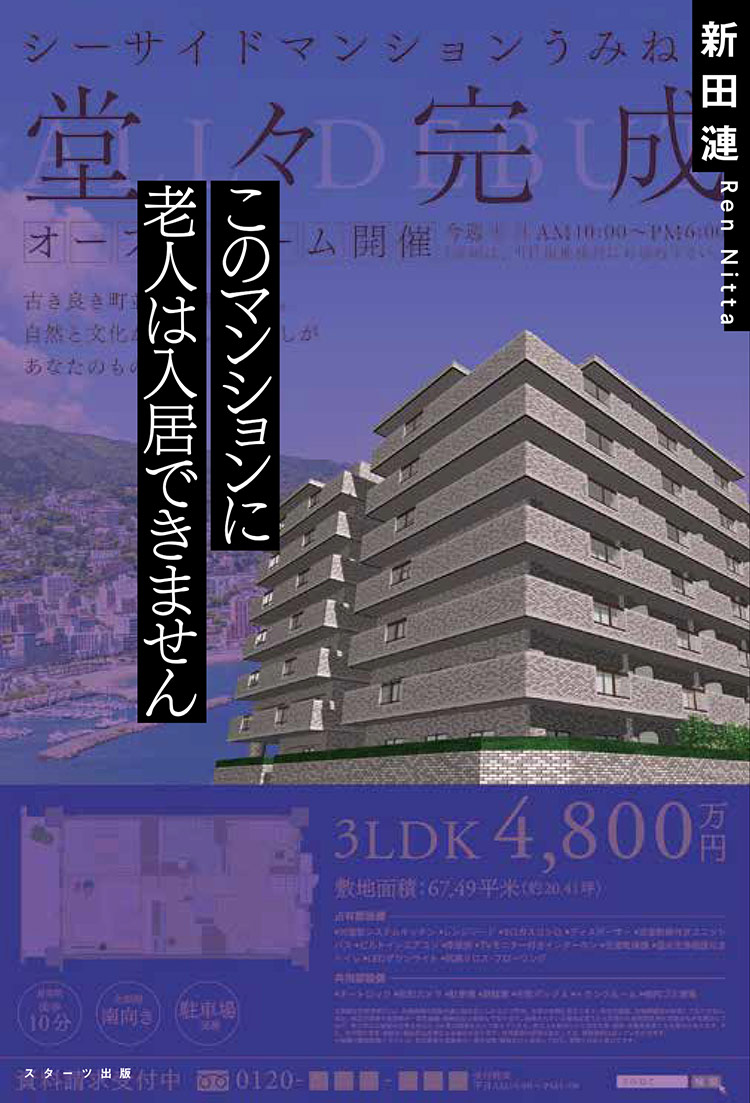願いはどのように叶えられ、僕はなにを失ったのか。
その答えを確かめるには、もう一度鳥居をくぐり、元の時代に戻って岬の生存を確かめる必要がある。けれど、大切ななにかを失うのだとしたら、次はどんな代償を支払わなくちゃいけないのだろう。
思わぬリスクが発覚したせいで、鳥居を使う心理的なハードルがさらに上がってしまった。そして今、鳥居探しにもうひとつの壁が立ちふさがっている。
「はい、赤上荘です。お盆の宿泊についてですね。大変申し訳ありませんが、すでに予約がいっぱいでして――」
赤上荘で働き始めて二週間が経ち、夏休みシーズンに突入したことにより、時間が捻出しづらくなったのだ。この時代には当然ながらネット予約がないので、予約の問い合わせはすべて電話でかかってくる。赤上荘で一番仕事が少ないのは僕だから、自ずと電話番の役割が定まってしまった。
とはいえ、僕としても裏方作業はありがたい。表に出てしまうと、どうしても岬と同い年くらいの女の子が目に入ってしまうからだ。この前は熱中症ということにして誤魔化せたけれど、何度もそれで押し通せるとは思えなかった。
昼休憩の時間になり母屋に向かうと、額に汗を滲ませた美羽もやってきた。愛想のいい美羽は主にチェックインやチェックアウト等、お客さんと接する業務を担当している。本日の宿泊客がやってくる十五時までが休憩時間だ。
「お疲れっ、そろそろお仕事にも慣れてきた?」
美羽は冷蔵庫から麦茶を取り出し、コップに注ぎ差し出してくれた。
僕はお礼を言いながら受け取り、一気に飲み干す。
「……大浴場の掃除をしても、筋肉痛にはならなくなったかな」
「あはは。アレ結構しんどいでしょ。千晴くんはひょろひょろだもんね」
「これでもすこし筋肉がついたと思う」
「まだぜんぜんですなあ。ほら」
美羽はそう言いながら、僕の二の腕を掴んでくる。くすぐったさと気恥ずかしさが同時に押し寄せて、僕は思わず情けない声を出してしまう。
「ちょっ、やめて」
「いひひ、よいではないかあ」
美羽の追撃を必死に避けていると、いつの間にか恵子さんが笑顔で傍に立っていた。
「やっぱり若い子は元気ねえ」
「そりゃあね、夏休みだし。いくらでも働けちゃうよ」
「じゃあ、おつかいでも頼んじゃおうかな。ちょっとお醤油を切らしちゃって」
墓穴を掘った美羽は「べぁっ」と変な声を出したが、渋々といった様子で頷く。
僕のシャツの袖を、しっかりと引っぱりながら。
「ねえ美羽、この手はなにを意味してるの」
「ついてきてねってこと。あと、お醤油持ってね。そのための筋肉だよね」
どうやら僕もせっせと墓穴を掘っていたらしい。まだ美羽との付き合いは短いけれど、ここから逃れる術はない。おつかいに付き添うしかなさそうだ。そう観念し、美羽と一緒に母屋の外に出る。生ぬるい潮風が頬を撫でた。いくら現代より気温が低いとはいえ、午後になると項垂れてしまうほどには暑くなる。
僕と美羽はできるだけ日陰を選ぶようにして、じぐざぐの軌道で歩いていく。
「そういえば、千晴くんはまだムラマツ商店には行ったことないよね?」
僕は頷く。食事は用意してもらえるし、着替えも保さんの服を借りている。そもそもこの時代で使えるお金を持っていないので、買い物という選択肢すら頭になかった。
「ムラマツ商店はね、なんでもあるんだよ。食料品に駄菓子、ポッキーにお煎餅。そしてなんと、私が好きなホームランバーまで!」
「それってぜんぶ食料品に含まれると思う」
「まあまあ。とにもかくにも、この島の人にとっては欠かせない場所なんだよ。だから千晴くんも、ムラマツ商店デビューを経てようやく島民になれるね」
「なるほど。通過儀礼みたいなものなんだ」
「そうそう。千晴くんの日頃の働きに免じて、特別に認めてあげようではないか」
「ははあ、ありがたき幸せ」
やけに仰々しい言葉遣いで美羽がふざけるので、僕もへりくだりながら感謝を述べる。そんなくだらないやり取りを楽しんでしまう自分に驚く。僕がどれだけ罪悪感を抱きながら斜に構えようとも、いつの間にか美羽のペースに巻き込まれてしまうのだ。
「ムラマツ商店はここの坂道をのぼったところにあるんだけれど、てっぺんからの景色がまた格別なんだよね。土庄の町並みと瀬戸内海が見渡せて、すごいから!」
美羽は軽やかな足取りで坂道をのぼり、くるりと振り返る。
僕も倣うようにして振り返ると、たしかに絶景だった。
空と海が混ざり合う景色自体は、元の時代とさほど変わらない。小豆島は、昔ながらの風景が残り続けているのだと改めて気がついた。
「いい景色だね、本当に」
それでも心の底からそう思えたのは、心理的要因が大きいのだろう。両親やクラスメイトの視線を浴びなくていいのは、僕が予想していたよりも負担が減るらしい。
「でしょ。この辺りで食べるホームランバーが一番おいしいんだから」
ご機嫌な美羽と並んで歩いていると、やがてムラマツ商店らしき建物が見えた。
店舗の入り口には赤い琺瑯看板が取り付けられていて、軒先にはアイスが入ったショーケースが鎮座している。トリコロールカラーの庇には風鈴がぶら下がっており、まるでジオラマで再現した駄菓子屋がそのまま大きくなったみたいだ。
「おばあちゃん、いるー?」
美羽が元気よく店の奥に声をかけると、居住スペースとおぼしき畳の部屋から、背中が曲がったお婆さんが現れた。
「あら美羽ちゃん。ちょっと久しぶりね」
「半年ぶりくらいかな? 私に会えなくて寂しかったでしょ」
「そうねえ。夜も眠れないくらいよ」
本心なのか冗談なのかわからないが、二人は仲がいいらしい。お婆さんは慈愛に満ちた瞳で美羽を眺めたのち、僕のほうをゆっくりと見やった。
「そっちの男の子は、はじめましてだね」
「はい。多々良千晴です」
「そうかいそうかい。いい名前だね」
僕とお婆さんが会話をしている間に、美羽はすでに大きな醤油の容器を右手で担いでいる。
「このお醤油と、あとホームランバーふたつ欲しいな」
「はいよ。ありがとうね」
美羽はポケットから小銭を出し、机の上に並べて置く。しめて二百円。醤油は小豆島の特産品とはいえ、現代では考えられないくらい安かった。
「醤油、僕が持つよ」
ビニール袋がないようなので、担ぐようにして持つしかない。すこし重いけれど、これくらいなら大丈夫だろう。
「ありがとう。その代わり、アイスは私が持ってあげるね。感謝したまえ」
「……ありがたき幸せです。で、どこで食べるの?」
「近くに石段があるから、そこで食べよ。この時間はちょうど木陰で涼しいよ」
美羽が店を出ようとした瞬間、小学生くらいの男女が元気よくやってきた。黒いシャツを着た男の子と、白いブラウスの女の子。どちらも岬と同い年くらいだろう。
『――ねえ、お兄ちゃん』
いつもの幻聴。僕はできるだけ女の子を視界に入れないようにして、足早に店を出る。背中を冷たい汗が伝う。蝉の声が耳の奥で反響する。蒸し暑い空気で肺が満たされていく。
「……千晴くん、大丈夫?」
「うん。ちょっと目眩がしただけ」
咄嗟に誤魔化すと、美羽は目を伏せながら「そっか」と呟いた。
その声は、どこか残念そうな響きを帯びていた。
会話が止まり、足音だけが響く。
夏の空気が滲んでいく。
「千晴くんってさ――」
二秒ほど間を置いて、美羽が振り向く。
「ちいさな女の子が苦手なの?」
質問が僕の胸を切り開いていく。どう答えるべきか迷った時間が、もはや正解だと伝えているようなものだった。僕の様子を見て、美羽は薄々察していたのかもしれない。それがさっきの出来事で確信に変わったのだろう。
美羽はふうと息を吐き、あくまでも軽い調子で言葉を続ける。
「どうして家出したのかも含めてさ、まだ千晴くんのことぜんぜん知らないんだよね」
「えっと、それは」
僕は妹を事故で失い、五十年後の未来から来た。
なんて伝えたところで、言葉だけでは信じてもらえるはずがない。
「無理にとは言わないけれど、教えてくれたら嬉しいな」
でも、恩人である美羽になにも伝えないのは不誠実じゃないだろうか。僕がいつまでこの時代に留まるのか定かじゃないけれど、できるだけ良好な関係を築いておきたい。人付き合いが上手じゃない僕にとっては、それがせめてもの恩返しに繋がるだろうから。
「実はさ」
いつの間にか石段に辿り着いていた。木陰が伸び、潮風が路地を通り抜けていく。美羽は細い腕を伸ばし、僕にホームランバーを手渡してくれる。
僕たちは石段に並んで腰掛け、ほとんど同時にホームランバーをかじる。
「半年くらい前に、妹が事故で亡くなったんだ」
咀嚼せずに放った言葉は石段を転がり落ちていく。冷たさだけが残った唇で、僕はタイムスリップしたことを伏せつつ自身の罪を白状する。
「妹の岬はまだ七歳だったのに、車に轢かれそうになった僕の代わりに死んだ。ちいさな身体で僕に体当たりしたんだ。僕がよそ見をしていなきゃ、岬はまだ生きていた。僕と違って、岬は明るくて愛される存在だった。それなのに、なにもない僕なんかを守ったんだ」
言葉と一緒に、あの日の記憶が溢れ出す。
生きている意味なんてないのに、どうして僕が生き残ったのだろう。
「本当なら僕が死ぬはずだった――いや、僕が死ねばよかったんだ」
そこまで言い切ると、世界から切り離されたように静寂が広がった。
「その日から、ちいさな女の子を見たら岬の幻聴が聞こえるようになった。だからさっきみたいに、ときどき具合が悪くなるんだ」
ひとつ、またひとつと足元に水滴が落ちていく。ホームランバーが溶けるにしては早い。手元を見ると、まださきほどの形を保っている。
じゃあ、この雫は。
疑問が浮上するのと同時に、視界が白く滲んだ。
僕はいつの間にか、涙を流していたのだ。
慌てて目元を拭う。こんなの、まるで僕が被害者みたいじゃないか。
被害者は岬であって、僕は加害者となにも変わらないんだ。
だから、僕に泣く資格なんて。
「ごめん、今のは忘れ――」
なんとか笑顔を取り繕い、美羽のほうを向く。
そこで僕は、言葉を失ってしまった。
美羽が、僕よりも泣いていたからだ。
「……そんなの、辛すぎるよ」
嗚咽交じりの声。
美羽は何度も指で涙を拭いながら、くしゃくしゃになった顔で僕を見る。
「……そうだね。岬は辛かったと思う」
「岬ちゃんもだけど、千晴くんもだよ!」
あまりにも大きな声だったので、思わず肩が跳ねてしまう。そのまま呆気にとられていると、美羽が距離を詰めてきた。
潤んだ瞳が眼前に迫ったせいで、僕はすこしだけ仰け反ってしまう。
「千晴くんはずっと自分を責め続けてきたんだよね。そんな生き方、あんまりすぎるよ。千晴くんはなにも悪くない。岬ちゃんだって、千晴くんには笑っててほしいはずだよ。だからさ――」
そう言って、美羽は両手で僕の頬を挟む。ホームランバーが落下する。
「僕が死ねばよかったなんて、絶対に言わないで」
まるで母親が子どもを叱るみたいに真剣な表情。
もし相手が美羽じゃなかったら、きっと反発していた。
僕が抱えた罪悪感や苦しみを知りもしないくせにと声を荒らげて、激情をぶつけていた。
けれど、なぜかそんな気にはなれなかった。美羽の言葉は僕を中途半端に慮るものではなかったし、偽善者が快感を得るための綺麗事にも聞こえなかった。
「……わがった」
頬が潰されているせいで、妙な発音になる。
無言の間が生まれる。
僕と美羽はしばし視線を交錯させ、やがて二人同時に吹き出してしまう。
「あはは、なに言ってるの」
美羽は心底おかしそうに笑いながら、ようやく解放してくれた。
「僕のせいじゃないでしょ」
「千晴ふんのへいだよ」
美羽がタコのような顔をして、さきほどの僕の発音を真似してくる。それがなんだか無性におかしくて、僕はお腹を抱えて笑ってしまった。
こんなにも、感情を表に出したのはいつぶりだろうか。
「千晴くんがそんなに笑ってるの、初めて見たかも」
「……そうだね。自分でも久しぶりだなって」
「笑ってるほうがいいよ。私と一緒のときは、ずっと笑顔でいてね」
「それはそれで不気味じゃないかな」
「そう? 最高だって。私、死ぬときは絶対に笑顔でいたいもん」
お婆さんになり、病室のベッドで家族に囲まれる美羽を想像する。五十年後の美羽がどうなっているかはわからないけれど、彼女には明るい最期がとてもよく似合うだろう。
「きっと叶うよ、それ」
心からの言葉を告げると、美羽はなんだか複雑な感情を誤魔化すように白い歯をこぼした。それは僕が初めて見る表情だったので、妙な違和感を覚えた。
「ありがとね。あ、アイス落ちちゃってる!」
けれど、すぐにいつもの雰囲気に戻っていた。
そのまま美羽は名残惜しそうに足元を見て、すこしだけ唇を尖らせる。
「それにしても交通戦争を思い出すなあ。小豆島も観光バスとかタクシーが多いから、千晴くんの過去だって他人事じゃないんだよね。ちいさい子も増えてきたし」
「交通戦争って?」
耳馴染みのない言葉だったので、思わず聞き返す。しかし、すぐに自分がミスを犯したと悟ってしまう。赤上荘のテレビの一件を思い出す。
この時代における僕の疑問は、一般常識であるケースが大半だ。
「ほら、自動車事故の死者が、日露戦争の死者を上回る勢いで増えたってやつ。昔よくテレビでやってたのに……本当に知らない?」
案の定、美羽は両眉を上げて覗き込んでくる。
どうやって誤魔化そうかと悩んでいると、美羽はさも冗談めいた様子で僕の秘密へ迫ってくる。
「千晴くんはやっぱり変わってるよね。浮世離れしてるというか……ここにいるのに、どこにもいない気がする」
まっすぐな美羽の視線が、初めて痛いと感じてしまった。
その答えを確かめるには、もう一度鳥居をくぐり、元の時代に戻って岬の生存を確かめる必要がある。けれど、大切ななにかを失うのだとしたら、次はどんな代償を支払わなくちゃいけないのだろう。
思わぬリスクが発覚したせいで、鳥居を使う心理的なハードルがさらに上がってしまった。そして今、鳥居探しにもうひとつの壁が立ちふさがっている。
「はい、赤上荘です。お盆の宿泊についてですね。大変申し訳ありませんが、すでに予約がいっぱいでして――」
赤上荘で働き始めて二週間が経ち、夏休みシーズンに突入したことにより、時間が捻出しづらくなったのだ。この時代には当然ながらネット予約がないので、予約の問い合わせはすべて電話でかかってくる。赤上荘で一番仕事が少ないのは僕だから、自ずと電話番の役割が定まってしまった。
とはいえ、僕としても裏方作業はありがたい。表に出てしまうと、どうしても岬と同い年くらいの女の子が目に入ってしまうからだ。この前は熱中症ということにして誤魔化せたけれど、何度もそれで押し通せるとは思えなかった。
昼休憩の時間になり母屋に向かうと、額に汗を滲ませた美羽もやってきた。愛想のいい美羽は主にチェックインやチェックアウト等、お客さんと接する業務を担当している。本日の宿泊客がやってくる十五時までが休憩時間だ。
「お疲れっ、そろそろお仕事にも慣れてきた?」
美羽は冷蔵庫から麦茶を取り出し、コップに注ぎ差し出してくれた。
僕はお礼を言いながら受け取り、一気に飲み干す。
「……大浴場の掃除をしても、筋肉痛にはならなくなったかな」
「あはは。アレ結構しんどいでしょ。千晴くんはひょろひょろだもんね」
「これでもすこし筋肉がついたと思う」
「まだぜんぜんですなあ。ほら」
美羽はそう言いながら、僕の二の腕を掴んでくる。くすぐったさと気恥ずかしさが同時に押し寄せて、僕は思わず情けない声を出してしまう。
「ちょっ、やめて」
「いひひ、よいではないかあ」
美羽の追撃を必死に避けていると、いつの間にか恵子さんが笑顔で傍に立っていた。
「やっぱり若い子は元気ねえ」
「そりゃあね、夏休みだし。いくらでも働けちゃうよ」
「じゃあ、おつかいでも頼んじゃおうかな。ちょっとお醤油を切らしちゃって」
墓穴を掘った美羽は「べぁっ」と変な声を出したが、渋々といった様子で頷く。
僕のシャツの袖を、しっかりと引っぱりながら。
「ねえ美羽、この手はなにを意味してるの」
「ついてきてねってこと。あと、お醤油持ってね。そのための筋肉だよね」
どうやら僕もせっせと墓穴を掘っていたらしい。まだ美羽との付き合いは短いけれど、ここから逃れる術はない。おつかいに付き添うしかなさそうだ。そう観念し、美羽と一緒に母屋の外に出る。生ぬるい潮風が頬を撫でた。いくら現代より気温が低いとはいえ、午後になると項垂れてしまうほどには暑くなる。
僕と美羽はできるだけ日陰を選ぶようにして、じぐざぐの軌道で歩いていく。
「そういえば、千晴くんはまだムラマツ商店には行ったことないよね?」
僕は頷く。食事は用意してもらえるし、着替えも保さんの服を借りている。そもそもこの時代で使えるお金を持っていないので、買い物という選択肢すら頭になかった。
「ムラマツ商店はね、なんでもあるんだよ。食料品に駄菓子、ポッキーにお煎餅。そしてなんと、私が好きなホームランバーまで!」
「それってぜんぶ食料品に含まれると思う」
「まあまあ。とにもかくにも、この島の人にとっては欠かせない場所なんだよ。だから千晴くんも、ムラマツ商店デビューを経てようやく島民になれるね」
「なるほど。通過儀礼みたいなものなんだ」
「そうそう。千晴くんの日頃の働きに免じて、特別に認めてあげようではないか」
「ははあ、ありがたき幸せ」
やけに仰々しい言葉遣いで美羽がふざけるので、僕もへりくだりながら感謝を述べる。そんなくだらないやり取りを楽しんでしまう自分に驚く。僕がどれだけ罪悪感を抱きながら斜に構えようとも、いつの間にか美羽のペースに巻き込まれてしまうのだ。
「ムラマツ商店はここの坂道をのぼったところにあるんだけれど、てっぺんからの景色がまた格別なんだよね。土庄の町並みと瀬戸内海が見渡せて、すごいから!」
美羽は軽やかな足取りで坂道をのぼり、くるりと振り返る。
僕も倣うようにして振り返ると、たしかに絶景だった。
空と海が混ざり合う景色自体は、元の時代とさほど変わらない。小豆島は、昔ながらの風景が残り続けているのだと改めて気がついた。
「いい景色だね、本当に」
それでも心の底からそう思えたのは、心理的要因が大きいのだろう。両親やクラスメイトの視線を浴びなくていいのは、僕が予想していたよりも負担が減るらしい。
「でしょ。この辺りで食べるホームランバーが一番おいしいんだから」
ご機嫌な美羽と並んで歩いていると、やがてムラマツ商店らしき建物が見えた。
店舗の入り口には赤い琺瑯看板が取り付けられていて、軒先にはアイスが入ったショーケースが鎮座している。トリコロールカラーの庇には風鈴がぶら下がっており、まるでジオラマで再現した駄菓子屋がそのまま大きくなったみたいだ。
「おばあちゃん、いるー?」
美羽が元気よく店の奥に声をかけると、居住スペースとおぼしき畳の部屋から、背中が曲がったお婆さんが現れた。
「あら美羽ちゃん。ちょっと久しぶりね」
「半年ぶりくらいかな? 私に会えなくて寂しかったでしょ」
「そうねえ。夜も眠れないくらいよ」
本心なのか冗談なのかわからないが、二人は仲がいいらしい。お婆さんは慈愛に満ちた瞳で美羽を眺めたのち、僕のほうをゆっくりと見やった。
「そっちの男の子は、はじめましてだね」
「はい。多々良千晴です」
「そうかいそうかい。いい名前だね」
僕とお婆さんが会話をしている間に、美羽はすでに大きな醤油の容器を右手で担いでいる。
「このお醤油と、あとホームランバーふたつ欲しいな」
「はいよ。ありがとうね」
美羽はポケットから小銭を出し、机の上に並べて置く。しめて二百円。醤油は小豆島の特産品とはいえ、現代では考えられないくらい安かった。
「醤油、僕が持つよ」
ビニール袋がないようなので、担ぐようにして持つしかない。すこし重いけれど、これくらいなら大丈夫だろう。
「ありがとう。その代わり、アイスは私が持ってあげるね。感謝したまえ」
「……ありがたき幸せです。で、どこで食べるの?」
「近くに石段があるから、そこで食べよ。この時間はちょうど木陰で涼しいよ」
美羽が店を出ようとした瞬間、小学生くらいの男女が元気よくやってきた。黒いシャツを着た男の子と、白いブラウスの女の子。どちらも岬と同い年くらいだろう。
『――ねえ、お兄ちゃん』
いつもの幻聴。僕はできるだけ女の子を視界に入れないようにして、足早に店を出る。背中を冷たい汗が伝う。蝉の声が耳の奥で反響する。蒸し暑い空気で肺が満たされていく。
「……千晴くん、大丈夫?」
「うん。ちょっと目眩がしただけ」
咄嗟に誤魔化すと、美羽は目を伏せながら「そっか」と呟いた。
その声は、どこか残念そうな響きを帯びていた。
会話が止まり、足音だけが響く。
夏の空気が滲んでいく。
「千晴くんってさ――」
二秒ほど間を置いて、美羽が振り向く。
「ちいさな女の子が苦手なの?」
質問が僕の胸を切り開いていく。どう答えるべきか迷った時間が、もはや正解だと伝えているようなものだった。僕の様子を見て、美羽は薄々察していたのかもしれない。それがさっきの出来事で確信に変わったのだろう。
美羽はふうと息を吐き、あくまでも軽い調子で言葉を続ける。
「どうして家出したのかも含めてさ、まだ千晴くんのことぜんぜん知らないんだよね」
「えっと、それは」
僕は妹を事故で失い、五十年後の未来から来た。
なんて伝えたところで、言葉だけでは信じてもらえるはずがない。
「無理にとは言わないけれど、教えてくれたら嬉しいな」
でも、恩人である美羽になにも伝えないのは不誠実じゃないだろうか。僕がいつまでこの時代に留まるのか定かじゃないけれど、できるだけ良好な関係を築いておきたい。人付き合いが上手じゃない僕にとっては、それがせめてもの恩返しに繋がるだろうから。
「実はさ」
いつの間にか石段に辿り着いていた。木陰が伸び、潮風が路地を通り抜けていく。美羽は細い腕を伸ばし、僕にホームランバーを手渡してくれる。
僕たちは石段に並んで腰掛け、ほとんど同時にホームランバーをかじる。
「半年くらい前に、妹が事故で亡くなったんだ」
咀嚼せずに放った言葉は石段を転がり落ちていく。冷たさだけが残った唇で、僕はタイムスリップしたことを伏せつつ自身の罪を白状する。
「妹の岬はまだ七歳だったのに、車に轢かれそうになった僕の代わりに死んだ。ちいさな身体で僕に体当たりしたんだ。僕がよそ見をしていなきゃ、岬はまだ生きていた。僕と違って、岬は明るくて愛される存在だった。それなのに、なにもない僕なんかを守ったんだ」
言葉と一緒に、あの日の記憶が溢れ出す。
生きている意味なんてないのに、どうして僕が生き残ったのだろう。
「本当なら僕が死ぬはずだった――いや、僕が死ねばよかったんだ」
そこまで言い切ると、世界から切り離されたように静寂が広がった。
「その日から、ちいさな女の子を見たら岬の幻聴が聞こえるようになった。だからさっきみたいに、ときどき具合が悪くなるんだ」
ひとつ、またひとつと足元に水滴が落ちていく。ホームランバーが溶けるにしては早い。手元を見ると、まださきほどの形を保っている。
じゃあ、この雫は。
疑問が浮上するのと同時に、視界が白く滲んだ。
僕はいつの間にか、涙を流していたのだ。
慌てて目元を拭う。こんなの、まるで僕が被害者みたいじゃないか。
被害者は岬であって、僕は加害者となにも変わらないんだ。
だから、僕に泣く資格なんて。
「ごめん、今のは忘れ――」
なんとか笑顔を取り繕い、美羽のほうを向く。
そこで僕は、言葉を失ってしまった。
美羽が、僕よりも泣いていたからだ。
「……そんなの、辛すぎるよ」
嗚咽交じりの声。
美羽は何度も指で涙を拭いながら、くしゃくしゃになった顔で僕を見る。
「……そうだね。岬は辛かったと思う」
「岬ちゃんもだけど、千晴くんもだよ!」
あまりにも大きな声だったので、思わず肩が跳ねてしまう。そのまま呆気にとられていると、美羽が距離を詰めてきた。
潤んだ瞳が眼前に迫ったせいで、僕はすこしだけ仰け反ってしまう。
「千晴くんはずっと自分を責め続けてきたんだよね。そんな生き方、あんまりすぎるよ。千晴くんはなにも悪くない。岬ちゃんだって、千晴くんには笑っててほしいはずだよ。だからさ――」
そう言って、美羽は両手で僕の頬を挟む。ホームランバーが落下する。
「僕が死ねばよかったなんて、絶対に言わないで」
まるで母親が子どもを叱るみたいに真剣な表情。
もし相手が美羽じゃなかったら、きっと反発していた。
僕が抱えた罪悪感や苦しみを知りもしないくせにと声を荒らげて、激情をぶつけていた。
けれど、なぜかそんな気にはなれなかった。美羽の言葉は僕を中途半端に慮るものではなかったし、偽善者が快感を得るための綺麗事にも聞こえなかった。
「……わがった」
頬が潰されているせいで、妙な発音になる。
無言の間が生まれる。
僕と美羽はしばし視線を交錯させ、やがて二人同時に吹き出してしまう。
「あはは、なに言ってるの」
美羽は心底おかしそうに笑いながら、ようやく解放してくれた。
「僕のせいじゃないでしょ」
「千晴ふんのへいだよ」
美羽がタコのような顔をして、さきほどの僕の発音を真似してくる。それがなんだか無性におかしくて、僕はお腹を抱えて笑ってしまった。
こんなにも、感情を表に出したのはいつぶりだろうか。
「千晴くんがそんなに笑ってるの、初めて見たかも」
「……そうだね。自分でも久しぶりだなって」
「笑ってるほうがいいよ。私と一緒のときは、ずっと笑顔でいてね」
「それはそれで不気味じゃないかな」
「そう? 最高だって。私、死ぬときは絶対に笑顔でいたいもん」
お婆さんになり、病室のベッドで家族に囲まれる美羽を想像する。五十年後の美羽がどうなっているかはわからないけれど、彼女には明るい最期がとてもよく似合うだろう。
「きっと叶うよ、それ」
心からの言葉を告げると、美羽はなんだか複雑な感情を誤魔化すように白い歯をこぼした。それは僕が初めて見る表情だったので、妙な違和感を覚えた。
「ありがとね。あ、アイス落ちちゃってる!」
けれど、すぐにいつもの雰囲気に戻っていた。
そのまま美羽は名残惜しそうに足元を見て、すこしだけ唇を尖らせる。
「それにしても交通戦争を思い出すなあ。小豆島も観光バスとかタクシーが多いから、千晴くんの過去だって他人事じゃないんだよね。ちいさい子も増えてきたし」
「交通戦争って?」
耳馴染みのない言葉だったので、思わず聞き返す。しかし、すぐに自分がミスを犯したと悟ってしまう。赤上荘のテレビの一件を思い出す。
この時代における僕の疑問は、一般常識であるケースが大半だ。
「ほら、自動車事故の死者が、日露戦争の死者を上回る勢いで増えたってやつ。昔よくテレビでやってたのに……本当に知らない?」
案の定、美羽は両眉を上げて覗き込んでくる。
どうやって誤魔化そうかと悩んでいると、美羽はさも冗談めいた様子で僕の秘密へ迫ってくる。
「千晴くんはやっぱり変わってるよね。浮世離れしてるというか……ここにいるのに、どこにもいない気がする」
まっすぐな美羽の視線が、初めて痛いと感じてしまった。