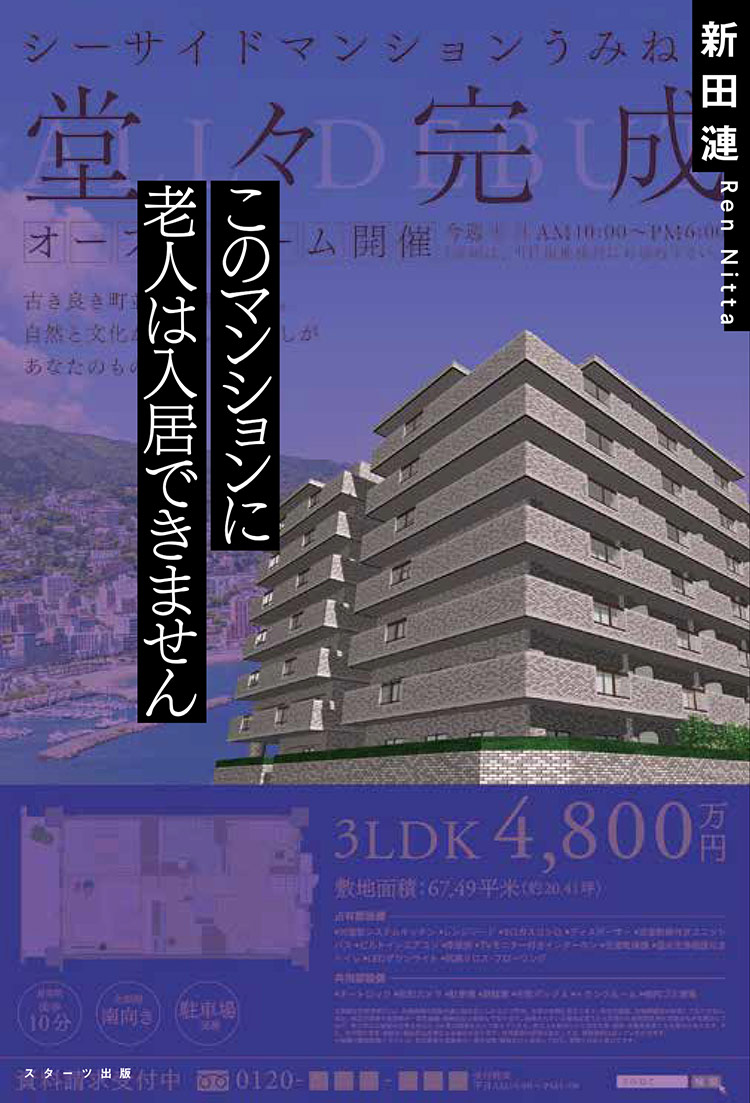朝食後、僕は美羽と一緒に近くの海岸通りを訪れていた。日差しの下を歩くと、いかに周囲の景色が様変わりしているのかがよくわかる。元の時代ではドラッグストアだった場所には、要塞のようなホテルが聳え立っている。砂浜には棕櫚の木がたくさん植えられていて、今の小豆島よりもどこか南国の雰囲気が漂っていた。
「あのリゾートホテルはなに?」
「銀波園だよ。コマーシャルでもたくさん流れてるから有名だと思ってた。もしかして千晴くんって、瀬戸内の人でもないの?」
僕は曖昧な笑みで頷きつつ、内心で驚いていた。銀波園は今も地名として残っているけれど、こんなに大きなリゾート施設が元になっていたとは。
砂浜から銀波園に近づくにつれ、観光客が増えていく。たくさんのざわめき。バスターミナルとおぼしき場所には数え切れないほどの観光バスが止まっている。いくつものツアーが組まれているのだろう。あちこちに咲く黄色いハマボウの花の華やかさも相まって、なんだか今の小豆島より活気に溢れている気がした。
「今は大きなホテルがたくさんできたから、ウチも若干厳しくなったんだよね。まあ、民宿でしか味わえない接客を武器に頑張るしかないんだけど」
美羽は力強い声でそう説明してくれた。
どうやら五十年前の小豆島はリゾート地として定番の場所らしく、夏休みになるとこうして大勢の観光客が訪れるみたいだ。しかし、その大半は大型リゾートホテルに流れてしまうとのこと。今の小豆島も決して観光客が少ないわけじゃないけれど、なんだか別の場所の話を聞いているみたいだった。
「さて、次はどこに行こっか。バスに乗って寒霞渓でも行く?」
寒霞渓は僕がいた時代でも有名な観光地なので、首を横に振った。
「それより町並みを見て回りたいかも」
「いいねえ。お散歩がてら、馴染みの喫茶店に連れてってあげようではないかっ」
美羽のプランに同意し、僕たちはゆっくりと散歩することになった。
この時代の町並みはどこか雑然としている。それはきっと、民家や個人商店の間に、居酒屋やスナックといった夜の店舗が挟まれているからだ。元の時代にもスナックは何軒かあるけれど、ここまで多くないので違和感が拭えなかった。時代が変われば、生活だけでなく遊び方も変わるのだろうか。
「休みの日はどこで遊んでるの?」
興味本位で質問すると、美羽はすこし上を向きながら考える素振りをする。
「んー、今から行く喫茶店が多いかな。たまにフェリーで高松まで出ることもあるよ。まあ、お小遣いだけじゃ頻繁には行けないけどさ」
「アルバイト代は?」
「それが出ないんだよねえ。友達にも『貰えばいいのに』って言われるけど、なんだか申し訳なくって」
美羽は眉を下げ、困ったように笑う。普段の働きぶりはまだそこまで知らないけれど、すこしくらい給料を貰ってもバチは当たらないはずなのに。
「いい子なんだね、美羽は」
率直な感想を口にすると、美羽は「びぁっ」と変な声を漏らしながら立ち止まった。
「びっくりするから、いきなり褒めるの禁止っ!」
そして視線を泳がせながら、両手でぱたぱたと頬を仰ぐ。
なんだか変な空気になってしまったので、僕は次の言葉を探せないでいた。
「も、もうすぐ喫茶店だよ」
美羽がぎこちなく歩き出したので、僕はすこし後ろをついていく。
今日の美羽は制服ではなく、格子模様の白いワンピースを着ている。長い裾がひらりと揺れるたびに、僕は実家のカーテンを思い出してしまう。口にするのは失礼だと弁えているので、心の奥底に秘めておく。
この時代では、僕の感覚のほうがおかしいのだから。
やがて前方に、赤い庇が目を引く建物が現れた。どうやらあそこが喫茶店らしく、入り口には『輪舞』と書かれた小さな看板が立てかけられている。看板の主張は控えめで、気づかずに通り過ぎる人も大勢いるかもしれない。けれど、そんな外観的特徴を差し引いても見覚えのない店構えだった。
つまり、ここも五十年後にはなくなっている。
「可愛いお客さんが来たよー」
美羽は勝手知ったる様子で扉を開けた。店内は冷房が効いており、心地よい冷風が身体を撫でていく。この時代はもうエアコンが普及しているんだなと思いながら見渡すと、なんだか大きくて茶色い機器が壁に張り付いていた。まさか、あれがエアコンなのだろうか。
「らっしゃいま……って、なんだ。美羽か」
店の奥から聞こえてきた明るい声が、なげやりな態度に変化していく。
見ると、緑色のエプロンをつけた女性が立っていた。ややカールが強い茶色のショートヘアに、耳元から覗くイヤリング。そして極めつけは咥えタバコ。
喫茶店の店員にしては、風貌が尖りすぎている。
「んー、あれー。お客さんにそんな態度でいいのかな」
「アイス珈琲で五時間も粘るような客、これくらいで十分だよ」
エプロンをつけた女性は悪態をつきながら、こちらへ視線を流す。
どうやら、ようやく僕の存在に気がついたらしい。
「……そっちは誰。初めて見る顔だな」
「千晴くん。夏休みの間だけウチで働くことになった家出少年なんだよね」
「大丈夫なの、それ」
エプロンをつけた女性は僕へ近寄り、鋭い眼光で凝視してくる。
「まあ、変な気を起こすようには見えないか」
そして、なにやら安心された。
僕はなんとか笑顔を作り、当たり障りのない挨拶を口にする。
「よ、よろしく。多々良千晴です」
「ん、私は松風裕子。裕子でいいよ」
「裕子ちゃんは私と同じクラスだから、千晴くんとも同い年だよ」
美羽の説明を受け、僕は衝撃を隠せないでいた。
「えっと、裕子……って僕たちと同い年なの?」
「あはは。大人っぽいよね」
「いや、そこじゃなくて普通にタバコを吸ってるけど」
未成年喫煙をやんわり指摘すると、美羽たちは不思議そうに顔を見合わせた。
「タバコなんて珍しいものじゃないだろ」
「ね。私は一回も吸ったことがないけど」
どうやらこの時代は、元の時代より未成年の喫煙に対して寛容らしい。いちいち驚いていられないけれど、カルチャーショックは拭えなかった。
そんなことより、注文は?」
裕子は灰皿にタバコを擦りながら、メニュー表を片手で渡してくれた。両端がぼろぼろになった紙に、手書きでさまざまな料理名が記載されている。
「私はアイス珈琲のシロップたっぷりで。千晴くんは?」
「じゃあコーラで」
「うい。ちょい待っててね」
裕子は雑な返事を残し、暖簾の奥へと消えていく。
僕は立ち尽くしたまま、囁くようにして美羽へ質問をする。
「美羽って、もしかして不良なの?」
「ううん。私は真面目だし、裕子ちゃんだって暴走族じゃないから不良じゃないよ」
冗談を言っている様子ではないので、本気で裕子を普通の女の子だと認識しているらしい。不良の定義にやや相違はあるけれど、美羽は人を見る目は確かだと豪語していた。それを信じるなら、裕子も決して悪い子じゃないのだろう。たぶん。
「はい、お待たせ」
すぐに裕子が戻ってきた。グラスに入ったアイス珈琲と、瓶入りのコーラが卓上に置かれる。このテーブルに座れという合図なのだろう。僕と美羽が座ると、当然のように裕子は美羽の隣に座った。
「……で、千晴はなんで家出したの」
そして、単刀直入すぎる質問が飛んでくる。
返答に迷ってしまう。適当な理由を選ぼうとしたけれど、美羽もまた興味津々といった表情だ。あまり大きな嘘をつくと、後々面倒になる気がした。
「一言でいえば家庭の問題、かな」
近からず、遠からず。両親とうまくいっていないのは嘘じゃないし、この時代にやってきた理由を辿れば岬に行き着くので、広い意味で捉えれば家庭の問題だ。
僕の言葉を聞いた裕子は、切れ長の二重でじっとこちらを見つめている。
「なるほどね。見たところガリ勉っぽいし、親が厳しいカンジか」
「まあ、そんなところ」
僕が頷くと、裕子はエプロンのポケットからポッキーの箱を取り出し、こちらに向けてきた。
「食べるか?」
どうしてこのタイミングなんだろう。
「……ありがとう、いただくよ」
困惑しながらも箱からポッキーを一本取り出し、口に運ぶ。味は現代のものとそんなに変わらないようで、普通においしかった。裕子は相変わらず僕をじっと見ているけれど、その目つきはさっきよりも柔らかい。事態を飲み込めないまま咀嚼していると、美羽が「よかったね」と声をかけてきた。
「裕子からお菓子が貰えたってことは、もう二人は友達だよ」
「……へえ、そうなんだ」
知らない間に、謎の通過儀礼を経たらしい。
「うん。本当ならタバコを一本渡すんだって」
ヤンキー漫画すぎるだろうと思ったけれど、怖いので口を噤む。
「千晴は吸わないみたいだし、なにより今は美羽がいるし」
「いやー、いつも気を遣ってもらって悪いねえ」
美羽が裕子の肩を小突く。美羽はタバコを一度も吸ったことがないと言っていたし、よほど煙が苦手なのかもしれない。僕もあまり好きではないので、気持ちはわかる。
二人のやり取りを眺めながらコーラを飲んでいると、裕子の視線が不意に戻ってきた。心の底を見透かすような眼光。思わず目を背けたくなる。僕はいてもたってもいられなくなり、適当な質問を裕子にぶつける。
「裕子って、将来はこのお店を継ぐの」
「なんで?」
「いや、なんとなく」
「……別にいいだろ、未来のことなんてさ」
裕子はポッキーを咥え、やや乱暴にへし折る。
その行為に、不機嫌さが垣間見えた気がした。
なにか気に障ることを聞いてしまったのだろうか。
そう考えていると、店内にベルの音が鳴り響いた。入り口の扉が開かれたらしい。
「いらっしゃい。何名サマですか」
裕子はゆっくりと立ち上がり、残りのポッキーを指で押し込んでいく。
「三人です」
男性の低い声。女性が微笑むような声。
「すずしいね」
そして、岬とよく似た声。
振り返ると、七歳くらいの女の子が店に入ってくるところだった。
裕子は家族連れを僕たちから離れた席に案内する。距離は五メートルほど。
けれど、僕の精神をかき乱すには十分すぎる近さだった。
「なに食べる?」
「あたし、パフェが食べたい!」
メニューを覗き込みながら、女の子は弾むように笑う。揺れる黒髪が岬の面影と重なっていく。岬が生きていたら、七度目の夏を迎えていた。僕が注意を怠らなければ、岬の人生は続いていた。
「千晴くん?」
眼球の奥から痛みが滲み出す。
だんだんと鼓動が速くなり、呼吸が荒くなる。
「――ねえ、千晴くん!」
美羽の声。
いつの間にか、肩を掴まれていた。
「大丈夫? すごく顔色が悪いよ」
美羽の瞳が不安そうに揺れる。
僕は誤魔化そうとしたけれど、頬が引き攣ってうまく笑えなかったかもしれない。
あの事故以来、岬と同い年くらいの女の子を見るたびに気分が悪くなる。罪悪感という言葉では片付けられないくらいの激情が、身体の奥から血管を伝って溢れ出すのだ。
「……ごめん、ちょっと気分が悪くなっただけ。もう大丈夫だから」
「ぜんぜんそうは見えないよ。部屋に戻る?」
「ううん、すこし休めばよくなると思う」
本当はここにいたほうが辛いけれど、美羽に無用な心配はかけたくなかった。
それに、この痛みは僕にとって必要なものだ。
この時代に来てから、ふとした瞬間に僕は笑ってしまう。僕の罪を知っている人間がいないから、あの視線が向けられないから、無意識に楽しんでしまう。
岬の人生を奪った分際で。生きる価値もない存在なのに。
僕がこの時代に来た理由はわからない。
けれど、岬を差し置いて楽しむ権利なんて、僕にはありやしないのだ。
「……もう大丈夫」
自分に言い聞かせるように呟く。
もう大丈夫だ。しっかりと、自分の罪を思い出したから。
目を擦り、顔を上げると、さっきよりも店内が白く霞がかっていた。
「あのリゾートホテルはなに?」
「銀波園だよ。コマーシャルでもたくさん流れてるから有名だと思ってた。もしかして千晴くんって、瀬戸内の人でもないの?」
僕は曖昧な笑みで頷きつつ、内心で驚いていた。銀波園は今も地名として残っているけれど、こんなに大きなリゾート施設が元になっていたとは。
砂浜から銀波園に近づくにつれ、観光客が増えていく。たくさんのざわめき。バスターミナルとおぼしき場所には数え切れないほどの観光バスが止まっている。いくつものツアーが組まれているのだろう。あちこちに咲く黄色いハマボウの花の華やかさも相まって、なんだか今の小豆島より活気に溢れている気がした。
「今は大きなホテルがたくさんできたから、ウチも若干厳しくなったんだよね。まあ、民宿でしか味わえない接客を武器に頑張るしかないんだけど」
美羽は力強い声でそう説明してくれた。
どうやら五十年前の小豆島はリゾート地として定番の場所らしく、夏休みになるとこうして大勢の観光客が訪れるみたいだ。しかし、その大半は大型リゾートホテルに流れてしまうとのこと。今の小豆島も決して観光客が少ないわけじゃないけれど、なんだか別の場所の話を聞いているみたいだった。
「さて、次はどこに行こっか。バスに乗って寒霞渓でも行く?」
寒霞渓は僕がいた時代でも有名な観光地なので、首を横に振った。
「それより町並みを見て回りたいかも」
「いいねえ。お散歩がてら、馴染みの喫茶店に連れてってあげようではないかっ」
美羽のプランに同意し、僕たちはゆっくりと散歩することになった。
この時代の町並みはどこか雑然としている。それはきっと、民家や個人商店の間に、居酒屋やスナックといった夜の店舗が挟まれているからだ。元の時代にもスナックは何軒かあるけれど、ここまで多くないので違和感が拭えなかった。時代が変われば、生活だけでなく遊び方も変わるのだろうか。
「休みの日はどこで遊んでるの?」
興味本位で質問すると、美羽はすこし上を向きながら考える素振りをする。
「んー、今から行く喫茶店が多いかな。たまにフェリーで高松まで出ることもあるよ。まあ、お小遣いだけじゃ頻繁には行けないけどさ」
「アルバイト代は?」
「それが出ないんだよねえ。友達にも『貰えばいいのに』って言われるけど、なんだか申し訳なくって」
美羽は眉を下げ、困ったように笑う。普段の働きぶりはまだそこまで知らないけれど、すこしくらい給料を貰ってもバチは当たらないはずなのに。
「いい子なんだね、美羽は」
率直な感想を口にすると、美羽は「びぁっ」と変な声を漏らしながら立ち止まった。
「びっくりするから、いきなり褒めるの禁止っ!」
そして視線を泳がせながら、両手でぱたぱたと頬を仰ぐ。
なんだか変な空気になってしまったので、僕は次の言葉を探せないでいた。
「も、もうすぐ喫茶店だよ」
美羽がぎこちなく歩き出したので、僕はすこし後ろをついていく。
今日の美羽は制服ではなく、格子模様の白いワンピースを着ている。長い裾がひらりと揺れるたびに、僕は実家のカーテンを思い出してしまう。口にするのは失礼だと弁えているので、心の奥底に秘めておく。
この時代では、僕の感覚のほうがおかしいのだから。
やがて前方に、赤い庇が目を引く建物が現れた。どうやらあそこが喫茶店らしく、入り口には『輪舞』と書かれた小さな看板が立てかけられている。看板の主張は控えめで、気づかずに通り過ぎる人も大勢いるかもしれない。けれど、そんな外観的特徴を差し引いても見覚えのない店構えだった。
つまり、ここも五十年後にはなくなっている。
「可愛いお客さんが来たよー」
美羽は勝手知ったる様子で扉を開けた。店内は冷房が効いており、心地よい冷風が身体を撫でていく。この時代はもうエアコンが普及しているんだなと思いながら見渡すと、なんだか大きくて茶色い機器が壁に張り付いていた。まさか、あれがエアコンなのだろうか。
「らっしゃいま……って、なんだ。美羽か」
店の奥から聞こえてきた明るい声が、なげやりな態度に変化していく。
見ると、緑色のエプロンをつけた女性が立っていた。ややカールが強い茶色のショートヘアに、耳元から覗くイヤリング。そして極めつけは咥えタバコ。
喫茶店の店員にしては、風貌が尖りすぎている。
「んー、あれー。お客さんにそんな態度でいいのかな」
「アイス珈琲で五時間も粘るような客、これくらいで十分だよ」
エプロンをつけた女性は悪態をつきながら、こちらへ視線を流す。
どうやら、ようやく僕の存在に気がついたらしい。
「……そっちは誰。初めて見る顔だな」
「千晴くん。夏休みの間だけウチで働くことになった家出少年なんだよね」
「大丈夫なの、それ」
エプロンをつけた女性は僕へ近寄り、鋭い眼光で凝視してくる。
「まあ、変な気を起こすようには見えないか」
そして、なにやら安心された。
僕はなんとか笑顔を作り、当たり障りのない挨拶を口にする。
「よ、よろしく。多々良千晴です」
「ん、私は松風裕子。裕子でいいよ」
「裕子ちゃんは私と同じクラスだから、千晴くんとも同い年だよ」
美羽の説明を受け、僕は衝撃を隠せないでいた。
「えっと、裕子……って僕たちと同い年なの?」
「あはは。大人っぽいよね」
「いや、そこじゃなくて普通にタバコを吸ってるけど」
未成年喫煙をやんわり指摘すると、美羽たちは不思議そうに顔を見合わせた。
「タバコなんて珍しいものじゃないだろ」
「ね。私は一回も吸ったことがないけど」
どうやらこの時代は、元の時代より未成年の喫煙に対して寛容らしい。いちいち驚いていられないけれど、カルチャーショックは拭えなかった。
そんなことより、注文は?」
裕子は灰皿にタバコを擦りながら、メニュー表を片手で渡してくれた。両端がぼろぼろになった紙に、手書きでさまざまな料理名が記載されている。
「私はアイス珈琲のシロップたっぷりで。千晴くんは?」
「じゃあコーラで」
「うい。ちょい待っててね」
裕子は雑な返事を残し、暖簾の奥へと消えていく。
僕は立ち尽くしたまま、囁くようにして美羽へ質問をする。
「美羽って、もしかして不良なの?」
「ううん。私は真面目だし、裕子ちゃんだって暴走族じゃないから不良じゃないよ」
冗談を言っている様子ではないので、本気で裕子を普通の女の子だと認識しているらしい。不良の定義にやや相違はあるけれど、美羽は人を見る目は確かだと豪語していた。それを信じるなら、裕子も決して悪い子じゃないのだろう。たぶん。
「はい、お待たせ」
すぐに裕子が戻ってきた。グラスに入ったアイス珈琲と、瓶入りのコーラが卓上に置かれる。このテーブルに座れという合図なのだろう。僕と美羽が座ると、当然のように裕子は美羽の隣に座った。
「……で、千晴はなんで家出したの」
そして、単刀直入すぎる質問が飛んでくる。
返答に迷ってしまう。適当な理由を選ぼうとしたけれど、美羽もまた興味津々といった表情だ。あまり大きな嘘をつくと、後々面倒になる気がした。
「一言でいえば家庭の問題、かな」
近からず、遠からず。両親とうまくいっていないのは嘘じゃないし、この時代にやってきた理由を辿れば岬に行き着くので、広い意味で捉えれば家庭の問題だ。
僕の言葉を聞いた裕子は、切れ長の二重でじっとこちらを見つめている。
「なるほどね。見たところガリ勉っぽいし、親が厳しいカンジか」
「まあ、そんなところ」
僕が頷くと、裕子はエプロンのポケットからポッキーの箱を取り出し、こちらに向けてきた。
「食べるか?」
どうしてこのタイミングなんだろう。
「……ありがとう、いただくよ」
困惑しながらも箱からポッキーを一本取り出し、口に運ぶ。味は現代のものとそんなに変わらないようで、普通においしかった。裕子は相変わらず僕をじっと見ているけれど、その目つきはさっきよりも柔らかい。事態を飲み込めないまま咀嚼していると、美羽が「よかったね」と声をかけてきた。
「裕子からお菓子が貰えたってことは、もう二人は友達だよ」
「……へえ、そうなんだ」
知らない間に、謎の通過儀礼を経たらしい。
「うん。本当ならタバコを一本渡すんだって」
ヤンキー漫画すぎるだろうと思ったけれど、怖いので口を噤む。
「千晴は吸わないみたいだし、なにより今は美羽がいるし」
「いやー、いつも気を遣ってもらって悪いねえ」
美羽が裕子の肩を小突く。美羽はタバコを一度も吸ったことがないと言っていたし、よほど煙が苦手なのかもしれない。僕もあまり好きではないので、気持ちはわかる。
二人のやり取りを眺めながらコーラを飲んでいると、裕子の視線が不意に戻ってきた。心の底を見透かすような眼光。思わず目を背けたくなる。僕はいてもたってもいられなくなり、適当な質問を裕子にぶつける。
「裕子って、将来はこのお店を継ぐの」
「なんで?」
「いや、なんとなく」
「……別にいいだろ、未来のことなんてさ」
裕子はポッキーを咥え、やや乱暴にへし折る。
その行為に、不機嫌さが垣間見えた気がした。
なにか気に障ることを聞いてしまったのだろうか。
そう考えていると、店内にベルの音が鳴り響いた。入り口の扉が開かれたらしい。
「いらっしゃい。何名サマですか」
裕子はゆっくりと立ち上がり、残りのポッキーを指で押し込んでいく。
「三人です」
男性の低い声。女性が微笑むような声。
「すずしいね」
そして、岬とよく似た声。
振り返ると、七歳くらいの女の子が店に入ってくるところだった。
裕子は家族連れを僕たちから離れた席に案内する。距離は五メートルほど。
けれど、僕の精神をかき乱すには十分すぎる近さだった。
「なに食べる?」
「あたし、パフェが食べたい!」
メニューを覗き込みながら、女の子は弾むように笑う。揺れる黒髪が岬の面影と重なっていく。岬が生きていたら、七度目の夏を迎えていた。僕が注意を怠らなければ、岬の人生は続いていた。
「千晴くん?」
眼球の奥から痛みが滲み出す。
だんだんと鼓動が速くなり、呼吸が荒くなる。
「――ねえ、千晴くん!」
美羽の声。
いつの間にか、肩を掴まれていた。
「大丈夫? すごく顔色が悪いよ」
美羽の瞳が不安そうに揺れる。
僕は誤魔化そうとしたけれど、頬が引き攣ってうまく笑えなかったかもしれない。
あの事故以来、岬と同い年くらいの女の子を見るたびに気分が悪くなる。罪悪感という言葉では片付けられないくらいの激情が、身体の奥から血管を伝って溢れ出すのだ。
「……ごめん、ちょっと気分が悪くなっただけ。もう大丈夫だから」
「ぜんぜんそうは見えないよ。部屋に戻る?」
「ううん、すこし休めばよくなると思う」
本当はここにいたほうが辛いけれど、美羽に無用な心配はかけたくなかった。
それに、この痛みは僕にとって必要なものだ。
この時代に来てから、ふとした瞬間に僕は笑ってしまう。僕の罪を知っている人間がいないから、あの視線が向けられないから、無意識に楽しんでしまう。
岬の人生を奪った分際で。生きる価値もない存在なのに。
僕がこの時代に来た理由はわからない。
けれど、岬を差し置いて楽しむ権利なんて、僕にはありやしないのだ。
「……もう大丈夫」
自分に言い聞かせるように呟く。
もう大丈夫だ。しっかりと、自分の罪を思い出したから。
目を擦り、顔を上げると、さっきよりも店内が白く霞がかっていた。