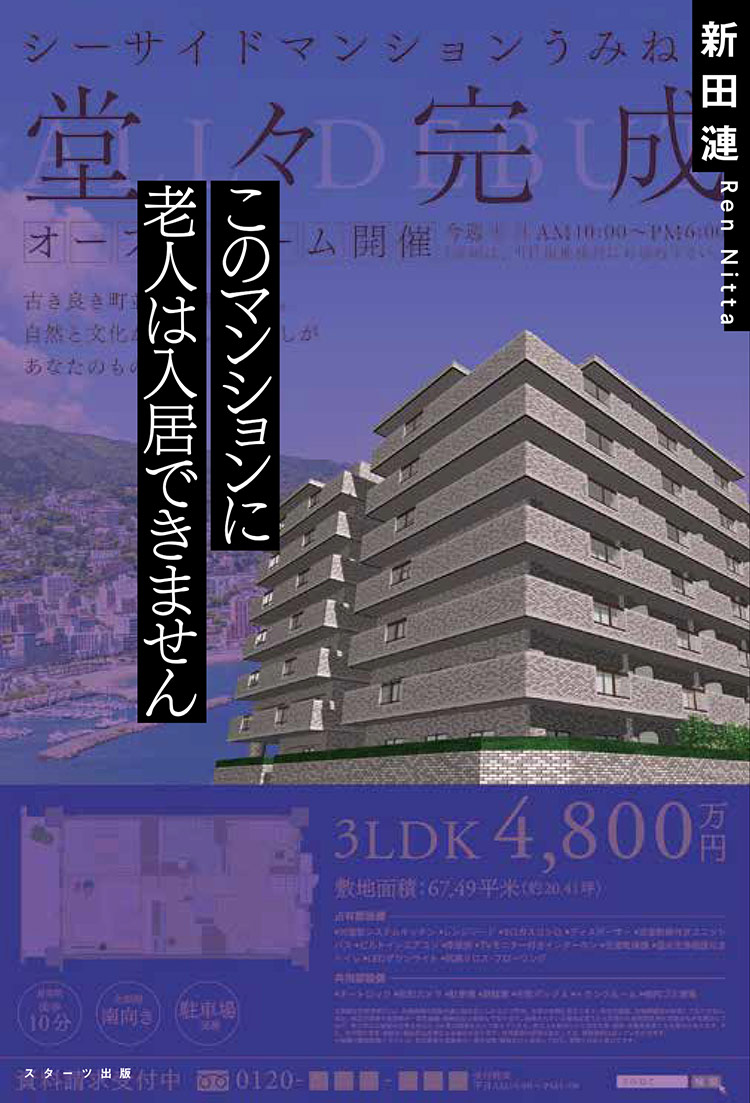五十年前に飛ばされて、知らない女の子に助けられる。そんな非日常が押し寄せて、疲れていたにもかかわらず、昨夜もあまり寝付けなかった。
鈍い頭痛に苛まれながら、布団を畳んで部屋の隅に寄せる。畳から漂うい草の匂いに、木目が特徴的な格天井。僕の部屋とまったく違うこの環境は、タイムスリップが現実である証拠だった。
今の僕はこの時代にとってイレギュラーな存在であり、長居するのが得策とは思えない。どこかキリのいいタイミングで、元の時代に戻るべきだろう。
けれど、僕は『岬が助かる未来が訪れてほしい』と願ったのであって『五十年前に行きたい』とは願っていないのだ。仮に『元の時代に帰りたい』と願ったところでうまくいくとも思えない。最悪の場合、もっと昔に飛ばされてしまう恐れもある。法則性を見つけるまでは迂闊に行動できそうになかった。
しばらくは、ここでお世話になるしかなさそうだ。
不幸中の幸いというべきか、僕は赤上荘でアルバイトすることになった。
本来結ぶはずのさまざまな雇用契約は『美羽の友達』という肩書きによりすべて省略され、たいした面接もなく明日からの勤務が決定している。身分を証明できない僕としてもありがたい話だけれど、やっぱり不用心すぎて心配になってしまう。もし僕が本当に犯罪者だったら、いったいどうするつもりなのだろう。
そんなことを考えながら、スクールバッグに隠していたスマホに手を伸ばす。
電波はない。当然ながらWi‐Fiも飛んでいないので、たいした機能は使えない。
それでも、これを見せればタイムスリップの証明になるだろう。まだ美羽たちに事情を明かしてはいないけれど、いつか使うときが来るかもしれない。モバイルバッテリーや筆箱と一緒に、しばらくはスクールバックの中で眠らせておこう。
整理を終えて立ち上がり、背筋を伸ばしてからカーテンを開く。
眼下に広がる瀬戸内海は穏やかで、あちこちが白く輝いている。視界を遮るものが少ないおかげか、僕がいた時代よりも海が大きく映った。こころなしか、空を舞う海鳥ものびのびと飛んでいるような気がした。
身支度を軽く整えて一階に下りると、玄関で美羽が接客をしている最中だった。
「ウチの景色、とてもよかったでしょう。へへ、銀波園さんには負けてられませんから。絶対、また来てくださいね。お二人の顔、覚えましたからね!」
美羽は細い腕で力こぶを作りながら、お客さんらしき若い男女と会話している。やや砕けた口調ながらも、失礼な印象を与えないのは美羽の強みなのだろう。
若い男女は満足気に微笑みながら、ボストンバッグを肩に提げて去っていった。美羽は男女の姿が見えなくなるまで、全力で手を振り続けていた。
「おはよう千晴くん、よく眠れた?」
お客さんを送り終えた美羽が、カウンターの中から笑顔で問いかけてきた。僕はすこし悩みながらも首肯する。実際のところ眠気は残っているけれど、アピールしたって仕方ない。
「それなら良かった。もうちょっとで私も中休みだから、一緒に朝ごはん食べよっか。おいしいもの、ご馳走するよ!」
美羽は両手で米を握るジェスチャーをする。おにぎりの確定演出だった。
「……楽しみにしておくよ。それより、僕が働くのは明日からでいいの? 今日からでも構わないのに」
「今日は観光地の勉強をしてもらわなくっちゃ。お客さんにもよく聞かれるからね」
「ああ、なるほど」
それは必要だと思った。昨日だって、見慣れた場所が様変わりしていて面食らったほどだ。五十年後の小豆島で暮らしていたからこそ先入観が邪魔をして、お客さんに間違った案内をしてしまうかもしれない。
「じゃあ、お言葉に甘えて観光地を巡ってくるよ」
「え、一人で行くみたいな言い方してる」
「もしかして、美羽もついてきてくれるの?」
「当たり前でしょ。バスガイドさんみたいに愉快に楽しく案内しちゃうから」
美羽の申し出はシンプルにありがたかった。僕だけではこの時代の常識がわからず、第三者に迷惑をかけてしまう可能性もあるからだ。
「ということで、千晴くんは先に家で待ってて。中休みになったら私も行くね」
「わかった」
美羽にそう答えてから、母屋へと向かった。
瀬戸内海から吹く潮風は柔らかく、制服のシャツを優しく揺らす。降り注ぐ日差しも皮膚を突き刺すようなものではなく、どことなく丸みを帯びている気がした。
まだ家族と仲がよかった頃、両親は夏になるたびに幼い頃の記憶を語ってくれた。
駄菓子屋で買ったアイスを神社の石段で食べたことや、窓から吹き込む潮風を頼りに昼寝した話は清涼感で溢れ、どこか作り話めいていた。
けれど、こうして体感するとあの話が嘘じゃないと納得できてしまう。
現代の夏とは、別の季節みたいだ。
穏やかな気持ちで歩いていると、観光客とおぼしき家族連れとすれ違った。
四十代くらいの夫婦と、赤い花柄のワンピースを着た七歳くらいの女の子。
楽しげに笑う声が、僕の鼓膜を容赦なく突き刺す。
『――お兄ちゃん』
岬の声がする。
これは幻聴だ。そうわかっているはずなのに、半ば無意識に辺りを見渡してしまう。
昨日の影が、どこかで僕を見張っているかもしれない。
呼吸が荒くなり、全身から汗が噴き出してくる。僕の様子がよほどおかしかったのか、さきほどの家族連れが訝しげな顔でこちらを見ている。僕は気まずさを誤魔化すようにして、足早に母屋へと駆け込んだ。
居間のソファには、美羽の母親である恵子さんが座っていた。どうやら朝食を摂り終えたところらしい。
「どうしたの、顔色が悪いわよ」
そして開口一番、異変を見抜かれてしまう。僕は取り繕うように笑って頬を掻く。
「あ、えっと。なんでもないです。ちょっと低血圧なので」
「あら、民宿の仕事は朝早いから頑張ってね」
恵子さんは白い歯を覗かせながら、からかうように言う。
「あはは。わかりました」
僕が愛想笑いに終始したせいで、会話が止まってしまう。
壁時計の秒針の音が鳴り響く。思い返せば、知らない大人と雑談する機会なんて久しぶりなのだ。正解がわからなかった。
「……あの、本当にお世話になっていいんですか。自分で言うのもなんですが、素性もわからないような奴ですよ」
だから、気まずさを埋めるために質問してみる。とはいえ、昨夜から引っかかっていた。この時代はきっと他人との距離感が近い。それでも僕を住み込みで働かせてくれるのは寛容すぎるだろう。
「まあねえ。二人は恋人でもなさそうだし、友達にも見えなかったから迷ったわ」
恵子さんは顎に手を当て、言葉を選ぶようにして言った。
「じゃあ、どうしてですか」
「美羽の願い事だもの。娘が楽しい生活を送れるようにするのは、親の役目ってやつよ。だから千晴くんは赤上荘にたくさん貢献しつつ、美羽を楽しませてあげてね」
冗談めいた口調だったけれど、たしかな重圧が両肩にのしかかる。
美羽は僕との会話が楽しいと言ってくれたけれど、手応えはない。僕との会話で楽しめる感性の持ち主なら、鏡と会話しても愉快になれると思う。
「自信はありませんが、できるだけ頑張ります」
そう宣言したタイミングで、玄関から元気な足音が聞こえてくる。
「朝のチェックアウト終わったよ!」
「お疲れ様。朝ごはん用意してるから、千晴くんと一緒に食べちゃって」
「あー、そうなんだ。ありがとう」
美羽はお礼を口にしつつも、眉を下げながら意味ありげな視線をこちらに向けてくる。私のおにぎりが食べられなくて残念だったねと言いたげだった。
テーブルに用意してもらった朝食は、健康的な献立だった。脂が乗った鮭の塩焼きに、緑が鮮やかなほうれん草のお浸し。ちょうどいい量のごはんと味噌汁。見ているだけで唾液が溢れそうになる。
「いただきまーす」
美羽が勢いよく両手を合わせたので、僕も手を合わせ、お浸しに箸を伸ばす。しゃきっとした食感がほどよく残っていて、味がしっかりと染み込んでいる。塩辛さを感じないのは、細かくまぶされた白胡麻のおかげだろうか。
「……おいしい」
感想が、感嘆と一緒に漏れる。
朝食を摂らずに学校へ行く日がほとんどだったのに、恵子さんが用意してくれた料理はどれも優しく胃に馴染んでいく。ずっと前から、この献立で朝が始まっているような感覚だった。
「へへー、おいしいでしょ。お母さんの料理は島で一番だからね」
「なんだか喜んでいいのかわからない評価だわ。せめて瀬戸内で一番にしてよ」
二人の会話に耳を傾けながら、味噌汁を一口。合わせ味噌と出汁の風味が、まろやかに舌の上で溶けていく。ふしめんと呼ばれる素麺の切れ端が入っているので、食べ応えも満点だった。
いつの間にか窓が開けられており、網戸から涼しい夏風が吹き込んでくる。カーテンレールに結ばれた風鈴が転がるようにひとつ鳴った。
「さっきより顔色がよくなってるわね」
恵子さんは僕を見て、安心したように頬を綻ばせる。
「はい。かなり楽になりました」
「それならよかった。明日から気合い入れて頑張ってね。寝坊しないようにね」
僕は頷く。低血圧は嘘だし、朝も苦手ではない。けれど、取り乱した理由を説明するには僕の素性から話さなくちゃいけない。この生活に慣れるまでは、伝えるべきじゃないだろう。理由は保身だけじゃない。僕が未来から来たと知れば、きっといろいろなことが気になってしまうはずだから。
たとえば、五十年後も赤上荘は続いているのかとか。
美羽が民宿を継がなかったのか、それとも別の土地に移住しているのか。なんにせよ、赤上荘だけでなく母屋さえ現存していないのだ。僕は味噌汁をもう一口すすりながら、改めて不思議な体験をしているなと実感した。
鈍い頭痛に苛まれながら、布団を畳んで部屋の隅に寄せる。畳から漂うい草の匂いに、木目が特徴的な格天井。僕の部屋とまったく違うこの環境は、タイムスリップが現実である証拠だった。
今の僕はこの時代にとってイレギュラーな存在であり、長居するのが得策とは思えない。どこかキリのいいタイミングで、元の時代に戻るべきだろう。
けれど、僕は『岬が助かる未来が訪れてほしい』と願ったのであって『五十年前に行きたい』とは願っていないのだ。仮に『元の時代に帰りたい』と願ったところでうまくいくとも思えない。最悪の場合、もっと昔に飛ばされてしまう恐れもある。法則性を見つけるまでは迂闊に行動できそうになかった。
しばらくは、ここでお世話になるしかなさそうだ。
不幸中の幸いというべきか、僕は赤上荘でアルバイトすることになった。
本来結ぶはずのさまざまな雇用契約は『美羽の友達』という肩書きによりすべて省略され、たいした面接もなく明日からの勤務が決定している。身分を証明できない僕としてもありがたい話だけれど、やっぱり不用心すぎて心配になってしまう。もし僕が本当に犯罪者だったら、いったいどうするつもりなのだろう。
そんなことを考えながら、スクールバッグに隠していたスマホに手を伸ばす。
電波はない。当然ながらWi‐Fiも飛んでいないので、たいした機能は使えない。
それでも、これを見せればタイムスリップの証明になるだろう。まだ美羽たちに事情を明かしてはいないけれど、いつか使うときが来るかもしれない。モバイルバッテリーや筆箱と一緒に、しばらくはスクールバックの中で眠らせておこう。
整理を終えて立ち上がり、背筋を伸ばしてからカーテンを開く。
眼下に広がる瀬戸内海は穏やかで、あちこちが白く輝いている。視界を遮るものが少ないおかげか、僕がいた時代よりも海が大きく映った。こころなしか、空を舞う海鳥ものびのびと飛んでいるような気がした。
身支度を軽く整えて一階に下りると、玄関で美羽が接客をしている最中だった。
「ウチの景色、とてもよかったでしょう。へへ、銀波園さんには負けてられませんから。絶対、また来てくださいね。お二人の顔、覚えましたからね!」
美羽は細い腕で力こぶを作りながら、お客さんらしき若い男女と会話している。やや砕けた口調ながらも、失礼な印象を与えないのは美羽の強みなのだろう。
若い男女は満足気に微笑みながら、ボストンバッグを肩に提げて去っていった。美羽は男女の姿が見えなくなるまで、全力で手を振り続けていた。
「おはよう千晴くん、よく眠れた?」
お客さんを送り終えた美羽が、カウンターの中から笑顔で問いかけてきた。僕はすこし悩みながらも首肯する。実際のところ眠気は残っているけれど、アピールしたって仕方ない。
「それなら良かった。もうちょっとで私も中休みだから、一緒に朝ごはん食べよっか。おいしいもの、ご馳走するよ!」
美羽は両手で米を握るジェスチャーをする。おにぎりの確定演出だった。
「……楽しみにしておくよ。それより、僕が働くのは明日からでいいの? 今日からでも構わないのに」
「今日は観光地の勉強をしてもらわなくっちゃ。お客さんにもよく聞かれるからね」
「ああ、なるほど」
それは必要だと思った。昨日だって、見慣れた場所が様変わりしていて面食らったほどだ。五十年後の小豆島で暮らしていたからこそ先入観が邪魔をして、お客さんに間違った案内をしてしまうかもしれない。
「じゃあ、お言葉に甘えて観光地を巡ってくるよ」
「え、一人で行くみたいな言い方してる」
「もしかして、美羽もついてきてくれるの?」
「当たり前でしょ。バスガイドさんみたいに愉快に楽しく案内しちゃうから」
美羽の申し出はシンプルにありがたかった。僕だけではこの時代の常識がわからず、第三者に迷惑をかけてしまう可能性もあるからだ。
「ということで、千晴くんは先に家で待ってて。中休みになったら私も行くね」
「わかった」
美羽にそう答えてから、母屋へと向かった。
瀬戸内海から吹く潮風は柔らかく、制服のシャツを優しく揺らす。降り注ぐ日差しも皮膚を突き刺すようなものではなく、どことなく丸みを帯びている気がした。
まだ家族と仲がよかった頃、両親は夏になるたびに幼い頃の記憶を語ってくれた。
駄菓子屋で買ったアイスを神社の石段で食べたことや、窓から吹き込む潮風を頼りに昼寝した話は清涼感で溢れ、どこか作り話めいていた。
けれど、こうして体感するとあの話が嘘じゃないと納得できてしまう。
現代の夏とは、別の季節みたいだ。
穏やかな気持ちで歩いていると、観光客とおぼしき家族連れとすれ違った。
四十代くらいの夫婦と、赤い花柄のワンピースを着た七歳くらいの女の子。
楽しげに笑う声が、僕の鼓膜を容赦なく突き刺す。
『――お兄ちゃん』
岬の声がする。
これは幻聴だ。そうわかっているはずなのに、半ば無意識に辺りを見渡してしまう。
昨日の影が、どこかで僕を見張っているかもしれない。
呼吸が荒くなり、全身から汗が噴き出してくる。僕の様子がよほどおかしかったのか、さきほどの家族連れが訝しげな顔でこちらを見ている。僕は気まずさを誤魔化すようにして、足早に母屋へと駆け込んだ。
居間のソファには、美羽の母親である恵子さんが座っていた。どうやら朝食を摂り終えたところらしい。
「どうしたの、顔色が悪いわよ」
そして開口一番、異変を見抜かれてしまう。僕は取り繕うように笑って頬を掻く。
「あ、えっと。なんでもないです。ちょっと低血圧なので」
「あら、民宿の仕事は朝早いから頑張ってね」
恵子さんは白い歯を覗かせながら、からかうように言う。
「あはは。わかりました」
僕が愛想笑いに終始したせいで、会話が止まってしまう。
壁時計の秒針の音が鳴り響く。思い返せば、知らない大人と雑談する機会なんて久しぶりなのだ。正解がわからなかった。
「……あの、本当にお世話になっていいんですか。自分で言うのもなんですが、素性もわからないような奴ですよ」
だから、気まずさを埋めるために質問してみる。とはいえ、昨夜から引っかかっていた。この時代はきっと他人との距離感が近い。それでも僕を住み込みで働かせてくれるのは寛容すぎるだろう。
「まあねえ。二人は恋人でもなさそうだし、友達にも見えなかったから迷ったわ」
恵子さんは顎に手を当て、言葉を選ぶようにして言った。
「じゃあ、どうしてですか」
「美羽の願い事だもの。娘が楽しい生活を送れるようにするのは、親の役目ってやつよ。だから千晴くんは赤上荘にたくさん貢献しつつ、美羽を楽しませてあげてね」
冗談めいた口調だったけれど、たしかな重圧が両肩にのしかかる。
美羽は僕との会話が楽しいと言ってくれたけれど、手応えはない。僕との会話で楽しめる感性の持ち主なら、鏡と会話しても愉快になれると思う。
「自信はありませんが、できるだけ頑張ります」
そう宣言したタイミングで、玄関から元気な足音が聞こえてくる。
「朝のチェックアウト終わったよ!」
「お疲れ様。朝ごはん用意してるから、千晴くんと一緒に食べちゃって」
「あー、そうなんだ。ありがとう」
美羽はお礼を口にしつつも、眉を下げながら意味ありげな視線をこちらに向けてくる。私のおにぎりが食べられなくて残念だったねと言いたげだった。
テーブルに用意してもらった朝食は、健康的な献立だった。脂が乗った鮭の塩焼きに、緑が鮮やかなほうれん草のお浸し。ちょうどいい量のごはんと味噌汁。見ているだけで唾液が溢れそうになる。
「いただきまーす」
美羽が勢いよく両手を合わせたので、僕も手を合わせ、お浸しに箸を伸ばす。しゃきっとした食感がほどよく残っていて、味がしっかりと染み込んでいる。塩辛さを感じないのは、細かくまぶされた白胡麻のおかげだろうか。
「……おいしい」
感想が、感嘆と一緒に漏れる。
朝食を摂らずに学校へ行く日がほとんどだったのに、恵子さんが用意してくれた料理はどれも優しく胃に馴染んでいく。ずっと前から、この献立で朝が始まっているような感覚だった。
「へへー、おいしいでしょ。お母さんの料理は島で一番だからね」
「なんだか喜んでいいのかわからない評価だわ。せめて瀬戸内で一番にしてよ」
二人の会話に耳を傾けながら、味噌汁を一口。合わせ味噌と出汁の風味が、まろやかに舌の上で溶けていく。ふしめんと呼ばれる素麺の切れ端が入っているので、食べ応えも満点だった。
いつの間にか窓が開けられており、網戸から涼しい夏風が吹き込んでくる。カーテンレールに結ばれた風鈴が転がるようにひとつ鳴った。
「さっきより顔色がよくなってるわね」
恵子さんは僕を見て、安心したように頬を綻ばせる。
「はい。かなり楽になりました」
「それならよかった。明日から気合い入れて頑張ってね。寝坊しないようにね」
僕は頷く。低血圧は嘘だし、朝も苦手ではない。けれど、取り乱した理由を説明するには僕の素性から話さなくちゃいけない。この生活に慣れるまでは、伝えるべきじゃないだろう。理由は保身だけじゃない。僕が未来から来たと知れば、きっといろいろなことが気になってしまうはずだから。
たとえば、五十年後も赤上荘は続いているのかとか。
美羽が民宿を継がなかったのか、それとも別の土地に移住しているのか。なんにせよ、赤上荘だけでなく母屋さえ現存していないのだ。僕は味噌汁をもう一口すすりながら、改めて不思議な体験をしているなと実感した。