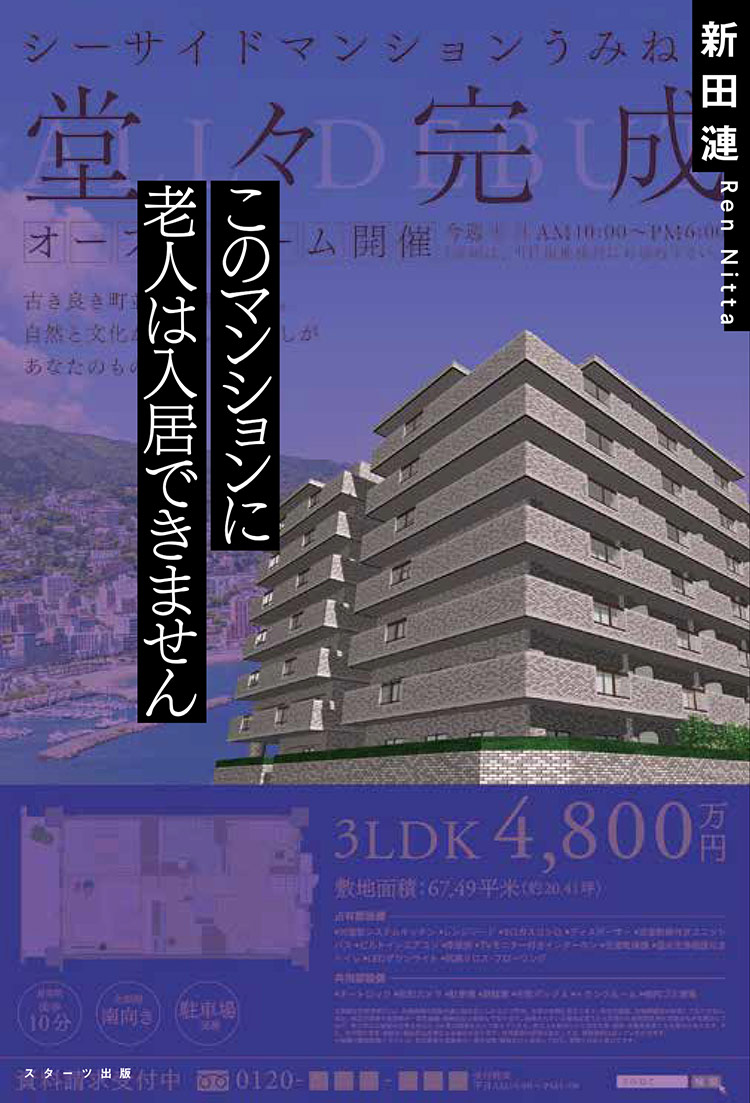美羽の案内で辿り着いたのは、土庄港の近くに建つ『赤上荘』という民宿だった。
白壁が特徴的な二階建ての建物は全体的に凹凸がなく、入り口や窓がなければ大きな豆腐が横たわっているように見える。各部屋の窓からは、一切の明かりが漏れ出していなかった。
「き、今日は平日だからお客さんが少ないけど、土日は賑わってるから。本当だよ?」
僕が言わんとしていたことを察したのか、美羽は弁解しながら赤上荘の隣にある木造の平屋へ歩いていく。こちらが住居スペースらしい。玉砂利が敷き詰められた駐車場を横切り、玄関へと向かう。造り自体は古民家に分類される建物だけれど、当然ながらこの時代ではまだ新築だ。
「たっだいまー!」
美羽は元気よく玄関扉を開く。普段から施錠されていないのか、鍵を取り出す素振りはなかった。僕は戸惑いながらも追従して、美羽に倣うようにしてスニーカーを脱ぐ。アディダスはこの時代にあるのだろうか、なんて考えていたら、美羽が居間に向かって大きな声で呼びかけた。
「お父さんお母さん、民宿のほうに友達泊めてもいいよね?」
友達という言葉にむず痒さを覚えるが、さっき出会った家出少年と紹介するのは話がややこしくなると判断したのだろう。
僕は頑張って「友達です」といった雰囲気を醸し出しながら、美羽の両親に挨拶することにした。
居間を覗き込むと、母親とおぼしき女性が鶯色のソファでくつろいでいた。
「あら、友達って男の子だったの」
美羽に似て、二重瞼が印象的な女性だった。
美羽の母親はゆっくりと立ち上がり、ボリュームがあるミディアムヘアを揺らしながらこちらに近づいてくる。
「えっと、多々良千晴と申します」
「千晴くんね。親御さんの許可はもらってる?」
「あ、はい。一応……」
「わかったわ。あとは美羽に案内してもらってね」
美羽の母親はにっと笑ってから、ふたたびソファへと戻っていく。
こちらが拍子抜けするくらい、あっさりとしたやり取りだった。
「ね、なんにも問題なかったでしょ」
美羽が小声で囁くように言う。
「優しい人なんだね」
「でしょー? 大好きな自慢のお母さん」
誇らしげに笑う美羽を直視できなかった。
僕と同年代なのに、どうしてここまで両親という存在を肯定できるのだろう。
「じゃ、部屋に案内するからついてきて」
上機嫌で歩き出す美羽を追い、外に出て、そのまま民宿の入り口をくぐる。
受付の壁には『小豆島』と書かれたペナントや提灯が飾られており、それらに囲まれるようにして大きな男性が座っていた。
「おかえり。美羽、そっちはお客さんかい?」
この人が美羽の父親だろう。美羽にはあまり似ておらず、全体的な造りが大ぶりだった。たくましい髭も相まって武骨な印象を受けたけれど、口調自体は柔らかい。
美羽はカウンターに近づき、「じゃーん」と言いながら僕を紹介するような手つきをする。
「ううん、友達だよ。空いてる部屋に泊めてあげたくって」
「お、男の子をかい……?」
「一緒に寝るわけじゃないし、いいでしょ?」
「……それならいいけど」
美羽の父親が、値踏みするような視線を僕に向ける。年頃の娘が男子をいきなり家に連れてきたら、いろいろと勘ぐってしまうのは無理もない。
心象を悪くしないよう、できるだけ丁寧に挨拶したほうがいいかもしれない。
「た、多々良千晴と申します。いきなり押しかけてしまい、すみません」
「まあ、今日はお客さんもあまりいないから別に構わないよ。ゆっくりしていってね」
「ありがとうございます」
美羽の父親はいくらか警戒心を解いてくれたようで、髭の隙間から笑顔を覗かせてくれた。
僕は深々と頭を下げてから、美羽の案内で階段を上がる。
「ありがとう」
そして、美羽にもお礼を告げる。
「気にしないで、困ったときはお互い様だし。それに、千晴くんがまたこの島に来たときに泊まってくれたら、ウチの儲けにも繋がるからね」
美羽は指で小銭の形を作りながら、ひひひと悪魔のように笑ってみせる。
「そうだね、次に来たときはお客さんとしてしっかりお金を払うよ」
「うんうん。友達割で安くなると思うから」
美羽はスキップするような足取りで二階へ到達し、廊下へ進んでいく。
僕は楽しげに弾む背中を見ながら、残酷な現実について考えてしまう。
土庄港周辺は昔ながらの住宅も残っているが、島の玄関口だけあってすこしずつ変化している。赤上荘が建っていた場所も例外じゃなく、今はセブン‐イレブンが建っていたはずだ。大人になった美羽が別の場所で民宿を営んでいる可能性もあるけれど、この建物が現存しないのは確かだった。
「ほら、この部屋使って」
美羽が案内してくれたのは、二階の一番奥の部屋。襖で仕切られた六畳の和室だった。背の低いテーブルの上には、お茶菓子とお茶碗。そして青い花柄のポットが置かれている。なんだか祖母の家を訪れたような、懐かしい匂いがした。
「ごめんね、一番狭い部屋になっちゃうけど」
「ううん。あんまり広いと落ち着かないからちょうどいいよ」
僕はスクールバックを置いて、ゆっくりと深呼吸した。
い草の香りが鼻腔を満たしていき、すこしだけ落ち着きを取り戻す。
ひとまず、これからどうすべきかを考えたかった。
「そっかそっか、それならよかったよ」
しかし、美羽は畳にちょこんと腰を下ろし、居座る気満々のオーラを放っていた。
「えっと……戻らないの?」
僕の問いかけに、美羽は勢いよく首肯する。
まだ話し足りないといわんばかりの表情だった。
「せっかくなんだし、テレビでも観ながらお話しでもしようよ!」
「一応聞くけど、僕に拒否権ってあったりするのかな」
「ないない。タダで泊めてるんだから、人権があると思っちゃダメだよ」
「そこまで剥奪されるんだ」
美羽は楽しげに笑いながら、部屋の隅にあったテレビらしきものに四つん這いで近づいていく。それがテレビだと確信できなかったのは、用途不明のボタンやツマミがたくさんついていたからだった。
「この部屋だけは普通のテレビだから、百円玉がいらないよ。ラッキーだね」
百円玉が必要なテレビとは、いったいどういうことだろう。僕の疑問をよそに、美羽は慣れた様子でテレビの右下にあるツマミのようなものを引っぱる。
でも、画面にはなにも映らない。十秒ほど待っても応答はなかった。
「壊れてるんじゃない?」
僕が呟くと、美羽はぎゅるりと振り返り、目を丸くした。
「千晴くん家のテレビって、すぐに点くの?」
どうやら僕は迂闊な発言をしてしまったらしい。
昔のテレビはきっと、起動するまで時間がかかるのだろう。
言い訳を探している間に、画面にゆっくりと色が広がっていく。
「まあ、これよりはちょっとだけ早いかな」
「いいないいな。家にあるテレビもあんまり新しくないからなあ」
美羽は身体を左右に揺らしながら、テレビに視線を戻した。
画面に映し出された男性は、家のリビングでくつろぎながら妻らしき女性と軽妙な会話を繰り広げている。ホームドラマだろうか。
「千晴くんはさ、もしかして親と喧嘩中なの?」
ふと、美羽が問いかけてくる。視線はテレビに向けられたままだった。僕はどう答えるべきか迷った。両親とは、喧嘩らしいやり取りすらしていないからだ。
「……美羽の家族みたいに仲はよくないかな。家にいても、ずっと息苦しいよ」
最後にちゃんと会話したのは、いつだろう。
帰宅後、母は決まってリビングのソファに座っていた。時間になると夕食の準備をするために立ち上がり、調理が終わるとふたたびソファに戻る。夕日を浴びる背中からは生気を感じられず、まるでプログラミングされたロボットのようだった。
岬を失ってからの母は、ただ生きているだけだ。それは父も同様で、ただでさえ細い身体がさらに小さくなった気がした。
僕がそうさせてしまったのだ。
「そっか。だったら、明日も明後日も帰りたくないんだ。でも家出少年クン、当面の生活費は持ってるのかな?」
からかうように美羽が言う。
財布には二万円ほど入っていた。この時代は今よりも物価が安いはずだ。
節約すれば、二週間くらいは凌げるかもしれない。
いや、駄目だ。
ここまで計算して、現代の紙幣は使えないことに気がついた。デザインが違いすぎるので、偽札扱いされるのがオチだろう。間違いなく警察沙汰だ。
「あんまり持ってないんでしょ」
僕の沈黙を肯定と捉えた美羽は、いつの間にかこちらを向いていた。大きな瞳は蛍光灯の明かりを吸い込んで、僕を心配するように揺れている。
「……ほとんどないけど、なんとかするよ」
「どうやって」
「アルバイト、とか」
反射的にそう言ってみたものの、平成生まれの僕の身分証は使えそうにない。そもそもアルバイトなんてしたことがないし、この時代の僕は学生とも言い切れない。
とてつもなく無力で、無価値な存在だった。
「千晴くんって、やっぱりアレだなあ」
美羽は僕に近寄り、初めて会ったときのように顔を覗き込んでくる。
「アレ?」
「民宿に泊まる人ってさ、楽しい理由で旅をする人ばかりじゃないんだよね。傷心旅行で来てくれる人もたくさんいるし、最期の思い出を残そうとしてる人だっている。千晴くんからも、そんな雰囲気が漂ってるなーって」
その声はどこまでも真剣で、僕を心の底から案じているようだった。
事実、僕から幸せそうなオーラが出ているとは考えにくい。
岬が生きていた頃から、暗い人間である自覚はあった。
「だから僕を連れてきたの?」
「だって、あのまま放っておいたら海に飛び込みそうだったもん」
「……美羽はお人好しだね」
「民宿のお仕事はね、お節介なくらいがちょうどいいんだよ」
美羽は力こぶを作るような仕草をしてから、勢いよく立ち上がる。
「あとね、私と出会った人はみんな笑顔にするって決めてるの」
「それは仕事の心構え?」
「ううん。人として。だから千晴くんには、笑って帰ってもらわなきゃ困るな」
美羽は満面の笑みを浮かべつつ、僕の肩をびしびしと叩く。
志としては立派だけれど、僕には眩しすぎた。
「じゃあ、ドラマも終わったしそろそろ行こっか」
「どこに?」
「ごはんだよ、晩ごはん。私もう、お腹ぺこぺこ」
嘆く美羽を見て、僕は初めて自分の空腹に気がついた。そういえば、昼休みにスティックパンをかじってからコーラしか口にしていない。
「今日は私がご馳走したげるから、任せておいて」
大股で美羽が部屋を出ていくので、僕は大人しくついていく。民宿の娘だけあって、料理はお手の物なのだろうか。
僕と美羽はふたたび住居スペースへ戻り、台所へと向かう。美羽の母親は部屋に戻ったのか、居間の電気は消されていた。美羽が電気のスイッチを入れ直すと、ばちっと弾けたような音が鳴る。テレビと同様に、照明が灯るのも時間がかかった。
「さてさて」
美羽はハミングしながら引き戸を開き、包丁とまな板を取り出す。
そしてくるりと振り向いて、自信たっぷりな表情をひとつ。
「おにぎりでいいかな」
「え、おにぎり?」
予想外の提案に、思わず目を瞬かせてしまう。
「うん。みなさまご存じのおにぎり」
「……包丁とまな板を出した意味はなに?」
「料理は期待感を演出するべしって、この前テレビで言ってたから!」
「期待外れになったら元も子もないよ」
僕のツッコミを受け、美羽は白い歯を見せて愉快そうに笑う。
「まあまあ、私のおにぎりはおいしいって評判だからさ。そこで座って待っててよ」
僕は頷いて、大人しくテーブルに着く。美羽は大きな炊飯器にしゃもじを突っ込んで、懐かしい曲の鼻歌を口ずさみながら奮闘している。
「千晴くんお腹すいてるよね? おっきくしちゃってもいい?」
「ありがとう。でも僕、そんなに食べないタイプなんだ」
「そうなんだ。もう握っちゃったから頑張って食べてね」
なんのための質問だったのだろう。どうやら美羽は、こちらの意見を聞いたうえで自分の意見を通してくるタイプらしい。
強引だなと呆れてしまうが、不思議と不快ではなかった。
やがて美羽は、宣言どおり大きなおにぎりがのったお皿を持ってきてくれた。どう見ても僕の顔より大きい。絶対に食べきれない量だけど、出された食事を残すのも気が引ける。立ち向かうしかなかった。
心の中で覚悟を決めていると、美羽はぱんと両手を叩いた。
「じゃ、食べながらお話しよっか」
「話?」
僕は両手を合わせながら聞き返す。
「うん。これからのこと。しばらく家には帰る気ないんだよね?」
おにぎりを頬張りながら、僕は曖昧に頷いた。
ちょうどよい塩味が舌の上に広がり、じんわりと疲れをほぐしてくれる。
「そっか。見かけによらず頑固者だね」
「いろいろと事情があるんだよ」
「事情はあっても、お金はぜんぜんないと」
「まあ、そうなるね」
僕がそう答えると、対面に座った美羽はおにぎりを一口かじり「そっかそっか」と大きく頷いた。そして、仰々しく腕を組む。慣れない仕草なのだろう。どうにもおさまりが悪いらしく、何度も左右の腕を組み直している。
「千晴くんって、地元でアルバイトとかやってた?」
「いや、とくには……」
「人とかかわるのって好き?」
「苦手かも。一人でいるのが好きだから」
「まあ、そのへんはどうにでもなるよ。土日も入れるよね?」
「待って。もしかして、なにかの面接が始まってる?」
「当たり。よかったらさ、ウチで住み込みのアルバイトしてみない?」
美羽はぱちんと指を鳴らす。
「……えっと、僕がこの民宿で?」
「そ。もうすぐ夏休みで忙しくなるからさ、家出少年の手も借りたいって感じなんだよ。ね、お願い。時給もうんと弾むから。たぶんだけど!」
今度はこちらが腕を組む番だった。僕はきっと愛想が悪い。というよりも、楽しいときも表情があまり変わらないらしい。どう好意的に捉えても接客業に向かないタイプだろう。とはいえ、接客以外にもやることはあるはずだ。
「民宿のアルバイトって、具体的になにをするの」
「お布団運んだり、畳んだり……お客さんと愉快に楽しくお話ししたり!」
「布団の上げ下げはできるけど、会話するなんて自信がないよ」
僕が素直に白状すると、美羽は不思議そうに首を傾げた。
「そうかな。お話しするの得意そうなのに」
そんなことを言われたことがなかったので、本気で戸惑ってしまった。岬が亡くなってからは、誰かと会話らしい会話をした記憶すらない。岬が生きていた頃だって友達はいなかったので、会話に対しては苦手意識しかない。
「どうしてそう思ったの?」
だから、本心からの問いかけが口から漏れ出す。
けれど美羽は僕の声色なんて気にも留めないといわんばかりに、白い歯を覗かせた。
「だって今、すっごく楽しいもん」
毒気を抜かれるとはこういう状態だろう。
美羽の返答があまりにも予想外だったからか、僕も笑ってしまった。
「あ、初めて笑った」
「……そりゃね。やっぱり美羽は、人を見る目がないってよく言われない?」
「ないない。人を見る目だけは確かだから」
美羽は根拠のない自信とともに胸を張る。その仕草がだんだん愉快に思えてきたので、僕はふっと肩の力を抜いて天井を見上げた。蛍光灯から垂れ下がった紐が、ゆらゆらと揺れている。
どのみち、現状を把握して帰る手段を見つけるまで、選択肢は他にないのだ。
「期待に応えられるかわからないけど、頑張ってみるよ」
「やった! じゃあ、そのおにぎりを食べたら各部屋の案内しちゃうね。あ、お父さんにも伝えなくちゃ」
なんだか忙しない女の子だなと苦笑いしつつも、どこか居心地のよさを感じてしまう。僕と正反対すぎて、なにもかもが新鮮だからかもしれない。
残ったおにぎりを口に運ぶ。
塩味はさきほどよりも丸くなっていて、優しく舌の上で溶けていった。
白壁が特徴的な二階建ての建物は全体的に凹凸がなく、入り口や窓がなければ大きな豆腐が横たわっているように見える。各部屋の窓からは、一切の明かりが漏れ出していなかった。
「き、今日は平日だからお客さんが少ないけど、土日は賑わってるから。本当だよ?」
僕が言わんとしていたことを察したのか、美羽は弁解しながら赤上荘の隣にある木造の平屋へ歩いていく。こちらが住居スペースらしい。玉砂利が敷き詰められた駐車場を横切り、玄関へと向かう。造り自体は古民家に分類される建物だけれど、当然ながらこの時代ではまだ新築だ。
「たっだいまー!」
美羽は元気よく玄関扉を開く。普段から施錠されていないのか、鍵を取り出す素振りはなかった。僕は戸惑いながらも追従して、美羽に倣うようにしてスニーカーを脱ぐ。アディダスはこの時代にあるのだろうか、なんて考えていたら、美羽が居間に向かって大きな声で呼びかけた。
「お父さんお母さん、民宿のほうに友達泊めてもいいよね?」
友達という言葉にむず痒さを覚えるが、さっき出会った家出少年と紹介するのは話がややこしくなると判断したのだろう。
僕は頑張って「友達です」といった雰囲気を醸し出しながら、美羽の両親に挨拶することにした。
居間を覗き込むと、母親とおぼしき女性が鶯色のソファでくつろいでいた。
「あら、友達って男の子だったの」
美羽に似て、二重瞼が印象的な女性だった。
美羽の母親はゆっくりと立ち上がり、ボリュームがあるミディアムヘアを揺らしながらこちらに近づいてくる。
「えっと、多々良千晴と申します」
「千晴くんね。親御さんの許可はもらってる?」
「あ、はい。一応……」
「わかったわ。あとは美羽に案内してもらってね」
美羽の母親はにっと笑ってから、ふたたびソファへと戻っていく。
こちらが拍子抜けするくらい、あっさりとしたやり取りだった。
「ね、なんにも問題なかったでしょ」
美羽が小声で囁くように言う。
「優しい人なんだね」
「でしょー? 大好きな自慢のお母さん」
誇らしげに笑う美羽を直視できなかった。
僕と同年代なのに、どうしてここまで両親という存在を肯定できるのだろう。
「じゃ、部屋に案内するからついてきて」
上機嫌で歩き出す美羽を追い、外に出て、そのまま民宿の入り口をくぐる。
受付の壁には『小豆島』と書かれたペナントや提灯が飾られており、それらに囲まれるようにして大きな男性が座っていた。
「おかえり。美羽、そっちはお客さんかい?」
この人が美羽の父親だろう。美羽にはあまり似ておらず、全体的な造りが大ぶりだった。たくましい髭も相まって武骨な印象を受けたけれど、口調自体は柔らかい。
美羽はカウンターに近づき、「じゃーん」と言いながら僕を紹介するような手つきをする。
「ううん、友達だよ。空いてる部屋に泊めてあげたくって」
「お、男の子をかい……?」
「一緒に寝るわけじゃないし、いいでしょ?」
「……それならいいけど」
美羽の父親が、値踏みするような視線を僕に向ける。年頃の娘が男子をいきなり家に連れてきたら、いろいろと勘ぐってしまうのは無理もない。
心象を悪くしないよう、できるだけ丁寧に挨拶したほうがいいかもしれない。
「た、多々良千晴と申します。いきなり押しかけてしまい、すみません」
「まあ、今日はお客さんもあまりいないから別に構わないよ。ゆっくりしていってね」
「ありがとうございます」
美羽の父親はいくらか警戒心を解いてくれたようで、髭の隙間から笑顔を覗かせてくれた。
僕は深々と頭を下げてから、美羽の案内で階段を上がる。
「ありがとう」
そして、美羽にもお礼を告げる。
「気にしないで、困ったときはお互い様だし。それに、千晴くんがまたこの島に来たときに泊まってくれたら、ウチの儲けにも繋がるからね」
美羽は指で小銭の形を作りながら、ひひひと悪魔のように笑ってみせる。
「そうだね、次に来たときはお客さんとしてしっかりお金を払うよ」
「うんうん。友達割で安くなると思うから」
美羽はスキップするような足取りで二階へ到達し、廊下へ進んでいく。
僕は楽しげに弾む背中を見ながら、残酷な現実について考えてしまう。
土庄港周辺は昔ながらの住宅も残っているが、島の玄関口だけあってすこしずつ変化している。赤上荘が建っていた場所も例外じゃなく、今はセブン‐イレブンが建っていたはずだ。大人になった美羽が別の場所で民宿を営んでいる可能性もあるけれど、この建物が現存しないのは確かだった。
「ほら、この部屋使って」
美羽が案内してくれたのは、二階の一番奥の部屋。襖で仕切られた六畳の和室だった。背の低いテーブルの上には、お茶菓子とお茶碗。そして青い花柄のポットが置かれている。なんだか祖母の家を訪れたような、懐かしい匂いがした。
「ごめんね、一番狭い部屋になっちゃうけど」
「ううん。あんまり広いと落ち着かないからちょうどいいよ」
僕はスクールバックを置いて、ゆっくりと深呼吸した。
い草の香りが鼻腔を満たしていき、すこしだけ落ち着きを取り戻す。
ひとまず、これからどうすべきかを考えたかった。
「そっかそっか、それならよかったよ」
しかし、美羽は畳にちょこんと腰を下ろし、居座る気満々のオーラを放っていた。
「えっと……戻らないの?」
僕の問いかけに、美羽は勢いよく首肯する。
まだ話し足りないといわんばかりの表情だった。
「せっかくなんだし、テレビでも観ながらお話しでもしようよ!」
「一応聞くけど、僕に拒否権ってあったりするのかな」
「ないない。タダで泊めてるんだから、人権があると思っちゃダメだよ」
「そこまで剥奪されるんだ」
美羽は楽しげに笑いながら、部屋の隅にあったテレビらしきものに四つん這いで近づいていく。それがテレビだと確信できなかったのは、用途不明のボタンやツマミがたくさんついていたからだった。
「この部屋だけは普通のテレビだから、百円玉がいらないよ。ラッキーだね」
百円玉が必要なテレビとは、いったいどういうことだろう。僕の疑問をよそに、美羽は慣れた様子でテレビの右下にあるツマミのようなものを引っぱる。
でも、画面にはなにも映らない。十秒ほど待っても応答はなかった。
「壊れてるんじゃない?」
僕が呟くと、美羽はぎゅるりと振り返り、目を丸くした。
「千晴くん家のテレビって、すぐに点くの?」
どうやら僕は迂闊な発言をしてしまったらしい。
昔のテレビはきっと、起動するまで時間がかかるのだろう。
言い訳を探している間に、画面にゆっくりと色が広がっていく。
「まあ、これよりはちょっとだけ早いかな」
「いいないいな。家にあるテレビもあんまり新しくないからなあ」
美羽は身体を左右に揺らしながら、テレビに視線を戻した。
画面に映し出された男性は、家のリビングでくつろぎながら妻らしき女性と軽妙な会話を繰り広げている。ホームドラマだろうか。
「千晴くんはさ、もしかして親と喧嘩中なの?」
ふと、美羽が問いかけてくる。視線はテレビに向けられたままだった。僕はどう答えるべきか迷った。両親とは、喧嘩らしいやり取りすらしていないからだ。
「……美羽の家族みたいに仲はよくないかな。家にいても、ずっと息苦しいよ」
最後にちゃんと会話したのは、いつだろう。
帰宅後、母は決まってリビングのソファに座っていた。時間になると夕食の準備をするために立ち上がり、調理が終わるとふたたびソファに戻る。夕日を浴びる背中からは生気を感じられず、まるでプログラミングされたロボットのようだった。
岬を失ってからの母は、ただ生きているだけだ。それは父も同様で、ただでさえ細い身体がさらに小さくなった気がした。
僕がそうさせてしまったのだ。
「そっか。だったら、明日も明後日も帰りたくないんだ。でも家出少年クン、当面の生活費は持ってるのかな?」
からかうように美羽が言う。
財布には二万円ほど入っていた。この時代は今よりも物価が安いはずだ。
節約すれば、二週間くらいは凌げるかもしれない。
いや、駄目だ。
ここまで計算して、現代の紙幣は使えないことに気がついた。デザインが違いすぎるので、偽札扱いされるのがオチだろう。間違いなく警察沙汰だ。
「あんまり持ってないんでしょ」
僕の沈黙を肯定と捉えた美羽は、いつの間にかこちらを向いていた。大きな瞳は蛍光灯の明かりを吸い込んで、僕を心配するように揺れている。
「……ほとんどないけど、なんとかするよ」
「どうやって」
「アルバイト、とか」
反射的にそう言ってみたものの、平成生まれの僕の身分証は使えそうにない。そもそもアルバイトなんてしたことがないし、この時代の僕は学生とも言い切れない。
とてつもなく無力で、無価値な存在だった。
「千晴くんって、やっぱりアレだなあ」
美羽は僕に近寄り、初めて会ったときのように顔を覗き込んでくる。
「アレ?」
「民宿に泊まる人ってさ、楽しい理由で旅をする人ばかりじゃないんだよね。傷心旅行で来てくれる人もたくさんいるし、最期の思い出を残そうとしてる人だっている。千晴くんからも、そんな雰囲気が漂ってるなーって」
その声はどこまでも真剣で、僕を心の底から案じているようだった。
事実、僕から幸せそうなオーラが出ているとは考えにくい。
岬が生きていた頃から、暗い人間である自覚はあった。
「だから僕を連れてきたの?」
「だって、あのまま放っておいたら海に飛び込みそうだったもん」
「……美羽はお人好しだね」
「民宿のお仕事はね、お節介なくらいがちょうどいいんだよ」
美羽は力こぶを作るような仕草をしてから、勢いよく立ち上がる。
「あとね、私と出会った人はみんな笑顔にするって決めてるの」
「それは仕事の心構え?」
「ううん。人として。だから千晴くんには、笑って帰ってもらわなきゃ困るな」
美羽は満面の笑みを浮かべつつ、僕の肩をびしびしと叩く。
志としては立派だけれど、僕には眩しすぎた。
「じゃあ、ドラマも終わったしそろそろ行こっか」
「どこに?」
「ごはんだよ、晩ごはん。私もう、お腹ぺこぺこ」
嘆く美羽を見て、僕は初めて自分の空腹に気がついた。そういえば、昼休みにスティックパンをかじってからコーラしか口にしていない。
「今日は私がご馳走したげるから、任せておいて」
大股で美羽が部屋を出ていくので、僕は大人しくついていく。民宿の娘だけあって、料理はお手の物なのだろうか。
僕と美羽はふたたび住居スペースへ戻り、台所へと向かう。美羽の母親は部屋に戻ったのか、居間の電気は消されていた。美羽が電気のスイッチを入れ直すと、ばちっと弾けたような音が鳴る。テレビと同様に、照明が灯るのも時間がかかった。
「さてさて」
美羽はハミングしながら引き戸を開き、包丁とまな板を取り出す。
そしてくるりと振り向いて、自信たっぷりな表情をひとつ。
「おにぎりでいいかな」
「え、おにぎり?」
予想外の提案に、思わず目を瞬かせてしまう。
「うん。みなさまご存じのおにぎり」
「……包丁とまな板を出した意味はなに?」
「料理は期待感を演出するべしって、この前テレビで言ってたから!」
「期待外れになったら元も子もないよ」
僕のツッコミを受け、美羽は白い歯を見せて愉快そうに笑う。
「まあまあ、私のおにぎりはおいしいって評判だからさ。そこで座って待っててよ」
僕は頷いて、大人しくテーブルに着く。美羽は大きな炊飯器にしゃもじを突っ込んで、懐かしい曲の鼻歌を口ずさみながら奮闘している。
「千晴くんお腹すいてるよね? おっきくしちゃってもいい?」
「ありがとう。でも僕、そんなに食べないタイプなんだ」
「そうなんだ。もう握っちゃったから頑張って食べてね」
なんのための質問だったのだろう。どうやら美羽は、こちらの意見を聞いたうえで自分の意見を通してくるタイプらしい。
強引だなと呆れてしまうが、不思議と不快ではなかった。
やがて美羽は、宣言どおり大きなおにぎりがのったお皿を持ってきてくれた。どう見ても僕の顔より大きい。絶対に食べきれない量だけど、出された食事を残すのも気が引ける。立ち向かうしかなかった。
心の中で覚悟を決めていると、美羽はぱんと両手を叩いた。
「じゃ、食べながらお話しよっか」
「話?」
僕は両手を合わせながら聞き返す。
「うん。これからのこと。しばらく家には帰る気ないんだよね?」
おにぎりを頬張りながら、僕は曖昧に頷いた。
ちょうどよい塩味が舌の上に広がり、じんわりと疲れをほぐしてくれる。
「そっか。見かけによらず頑固者だね」
「いろいろと事情があるんだよ」
「事情はあっても、お金はぜんぜんないと」
「まあ、そうなるね」
僕がそう答えると、対面に座った美羽はおにぎりを一口かじり「そっかそっか」と大きく頷いた。そして、仰々しく腕を組む。慣れない仕草なのだろう。どうにもおさまりが悪いらしく、何度も左右の腕を組み直している。
「千晴くんって、地元でアルバイトとかやってた?」
「いや、とくには……」
「人とかかわるのって好き?」
「苦手かも。一人でいるのが好きだから」
「まあ、そのへんはどうにでもなるよ。土日も入れるよね?」
「待って。もしかして、なにかの面接が始まってる?」
「当たり。よかったらさ、ウチで住み込みのアルバイトしてみない?」
美羽はぱちんと指を鳴らす。
「……えっと、僕がこの民宿で?」
「そ。もうすぐ夏休みで忙しくなるからさ、家出少年の手も借りたいって感じなんだよ。ね、お願い。時給もうんと弾むから。たぶんだけど!」
今度はこちらが腕を組む番だった。僕はきっと愛想が悪い。というよりも、楽しいときも表情があまり変わらないらしい。どう好意的に捉えても接客業に向かないタイプだろう。とはいえ、接客以外にもやることはあるはずだ。
「民宿のアルバイトって、具体的になにをするの」
「お布団運んだり、畳んだり……お客さんと愉快に楽しくお話ししたり!」
「布団の上げ下げはできるけど、会話するなんて自信がないよ」
僕が素直に白状すると、美羽は不思議そうに首を傾げた。
「そうかな。お話しするの得意そうなのに」
そんなことを言われたことがなかったので、本気で戸惑ってしまった。岬が亡くなってからは、誰かと会話らしい会話をした記憶すらない。岬が生きていた頃だって友達はいなかったので、会話に対しては苦手意識しかない。
「どうしてそう思ったの?」
だから、本心からの問いかけが口から漏れ出す。
けれど美羽は僕の声色なんて気にも留めないといわんばかりに、白い歯を覗かせた。
「だって今、すっごく楽しいもん」
毒気を抜かれるとはこういう状態だろう。
美羽の返答があまりにも予想外だったからか、僕も笑ってしまった。
「あ、初めて笑った」
「……そりゃね。やっぱり美羽は、人を見る目がないってよく言われない?」
「ないない。人を見る目だけは確かだから」
美羽は根拠のない自信とともに胸を張る。その仕草がだんだん愉快に思えてきたので、僕はふっと肩の力を抜いて天井を見上げた。蛍光灯から垂れ下がった紐が、ゆらゆらと揺れている。
どのみち、現状を把握して帰る手段を見つけるまで、選択肢は他にないのだ。
「期待に応えられるかわからないけど、頑張ってみるよ」
「やった! じゃあ、そのおにぎりを食べたら各部屋の案内しちゃうね。あ、お父さんにも伝えなくちゃ」
なんだか忙しない女の子だなと苦笑いしつつも、どこか居心地のよさを感じてしまう。僕と正反対すぎて、なにもかもが新鮮だからかもしれない。
残ったおにぎりを口に運ぶ。
塩味はさきほどよりも丸くなっていて、優しく舌の上で溶けていった。