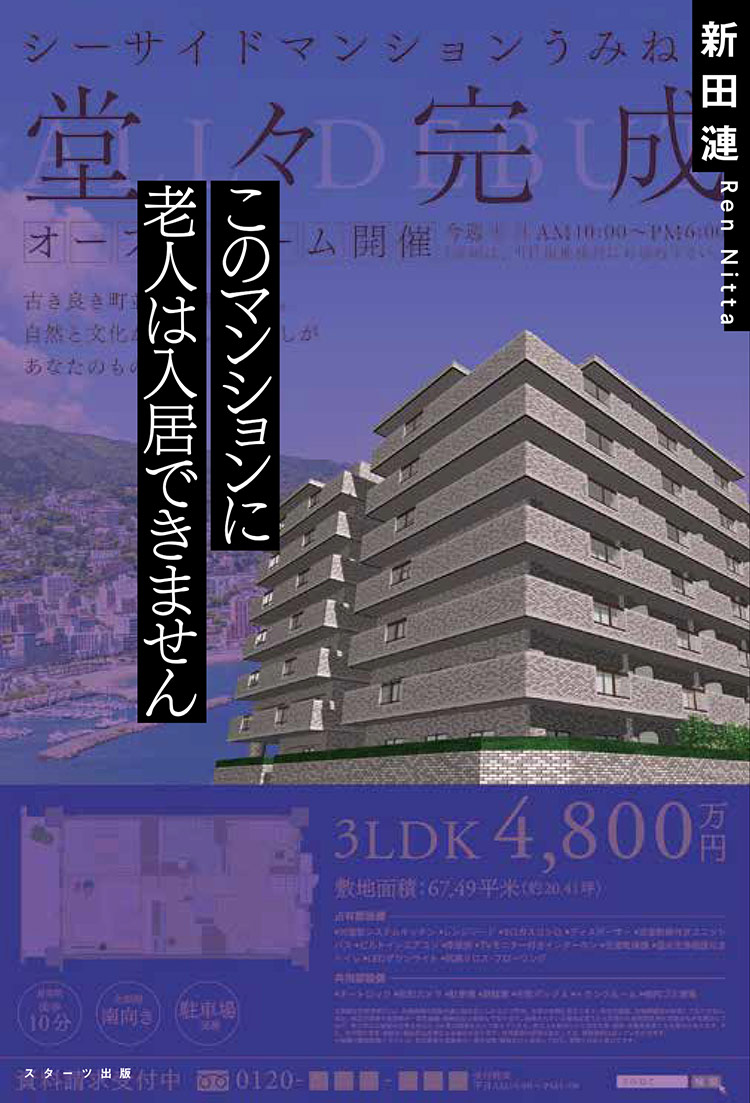「――キミ、どうしたの?」
ふと、打ち寄せる波音に混ざって柔らかい声がした。
振り向くと、制服姿の女の子が立っていた。
同い年くらいだろうか。緩やかなウェーブがかかった黒色のロングへアに、思わず視線が吸い寄せられてしまうほど形のよい二重瞼。そして、月明かりに照らされる琥珀色の瞳が印象的だった。
「この辺りは不良も人攫いもいないけれど、夜の海は危ないよ」
「いや、えっと」
よほど僕の様子がおかしかったのだろうか、女の子は心配そうに僕を覗き込む。
慣れない視線に、気恥ずかしさを覚えてしまう。
「見ない顔だね。どこから来たの」
「ずっと、ここに住んでるけど……」
「えっ、私もずっと住んでるよ?」
女の子はなぜか、驚いたような反応を見せる。
なぜだろうと考えて、ひとつの疑問が浮上する。
僕はこの女の子を見たことがない。
島に住んでいる同年代は全員知っている。中学校も高校も、島にはひとつしかないからだ。仮に不登校の生徒であっても噂は広まる。知らない同年代の女の子がいるなんて、ありえない話だった。
女の子も同じ疑問を抱いているのか、眉間に皺を寄せるようにして僕を凝視してきた。だんだんと顔が近づいてくるので、防波堤に追い詰められてしまう。
そこで初めて、女の子の制服が見慣れないデザインだと気がついた。
「その制服、どこのやつ?」
思わず、質問が漏れる。
女の子はきょとんとした顔をしつつも、すぐに答えてくれた。
「土高だよ。へへ、可愛いでしょ」
女の子はひらりとその場で回転し、スカートを花のように広げてみせる。
「でも土高の制服を知らないなんて、キミはやっぱりこの島の人じゃなさそうだね」
そして得意げな表情で僕を見た。名探偵ここにあり、と言わんばかりのドヤ顔だ。
けれど、今の僕には拍手してあげられるほどの余裕はなかった。
「いや、知らないもなにも……ありえないよ」
心臓の鼓動が速くなる。
抱き続けてきた違和感の正体が、ゆっくりと紐解かれていく。
「ありえないって、どうして?」
「だって、土高はもう……」
自分のものだとわからないくらい、声が震えていた。
土高。正式名称は香川県立土庄高等学校。この高校は香川県立小豆島高等学校と数年前に統合し、僕が通っている高校になった。
つまり土高とは、今はない高校の略称だ。
「ちょっと、どうしたの。顔色悪いよ!?」
だとしたら、信号機がなくなっていた理由もわかる。撤去されたのではなく、まだ設置されていないのだ。町の空気や通行人の服が変なのも同様だろう。
荒くなった息を整えつつ、悪い予感を確信にするための問いかけを口にする。
「ねえ。今って、西暦何年?」
この状況下における一番ベタな質問は、相手に不信感を抱かせるには十分だったらしい。
女の子はいよいよ怪訝な表情を浮かべたが、たじろぎつつも答えてくれた。
「一九七五年だよ。キミ……本当に大丈夫?」
告げられたのは、今からちょうど五十年前。
にわかに信じられないけれど、どうやら僕は過去にタイムスリップしたみたいだ。
もはや笑うしかなかった。
岬が助かる未来を願ったはずなのに、なぜか僕が過去に飛ばされている。
ドッキリかもしれない、なんて疑いはなかった。土高の制服は用意できても、島全体を巻き込むのは不可能だ。それに、僕を騙すためだけに信号機を撤去するはずがない。
なぜこうなったのかはわからないけれど、現状は把握できた。
ただ、タイムスリップを馬鹿正直に打ち明けるのはよろしくない気がした。
本格的に頭のおかしな奴だと思われて、警察に通報されてしまうかもしれない。
今の僕では、身分証明さえままならないのだ。
ひとまずこの女の子を安心させて、立ち去ってもらおう。
「えっと、大丈夫。ちょっとだけ意識が朦朧として、変なこと聞いちゃっただけだから。もうなんともないよ」
「それならいいけど……体調が悪いなら、早く帰って寝たほうがいいよ」
「ああ、その。実は僕、家出中なんだ」
笑顔を作り、咄嗟に嘘をつく。
訳ありなのが伝われば、面倒臭がってここから立ち去ってくれるだろう。僕が逆の立場だったら、家出中の人間なんてかかわりたくもない。
そう睨んだのに、女の子はなぜか離れようとしなかった。
「そっか。じゃあ、行くところがないんだ?」
そればかりか興味津々とばかりに詰め寄ってきて、腕を掴んでくる。
予想外の行動だったので、僕は反射的に頷いてしまう。
「だったら、とりあえずウチに来なよ。今日は空いてる部屋もあるからさ」
「空いてる部屋?」
「そ。ウチ、民宿やってるんだ。ホテルと比べたら小さいけど、結構評判いいんだよ」
そう言って女の子は白い歯を覗かせる。
行くあてのない僕としてはありがたい申し出だった。けれど、なにか裏があるんじゃないかと勘ぐってしまう。会ったばかりの他人に、ここまで優しくする意味はあるのだろうか。
「ね? どうかな?」
「……君の両親は、娘が見ず知らずの人間を家に招いても怒らないの?」
「きっと大丈夫だよ。お父さんもお母さんも、すっごく優しいから」
「もし僕が、逃走中の犯罪者だったらどうするの」
「えー? そんな感じには見えないけどなぁ」
「人は見かけによらないものだよ」
「私は人を見る目があるから、なんの問題もなし!」
女の子は、自信満々といった様子で胸を張る。
そういえば、亡くなった祖母も随分お人好しだった記憶がある。五十年前はこういったお節介が普通だったのかもしれない。
それなら、この好意は素直に受け取ったほうが怪しまれないだろう。
「……じゃあ、今晩だけお世話になります」
僕がそう言うと、女の子は満足げに頷いた。
「うん、よろしくね。私は赤上美羽だよ。好きに呼んでね!」
「赤上さん」
「堅っ。呼び捨てにしてよ」
「赤上」
「できれば名前で」
「……美羽」
「うんうん、それでよし」
「好きに呼んでよかったんじゃ……」
僕のツッコミなどお構いなしに、美羽はお腹を抱えて笑っている。
身振り手振りが大きく、感情表現が豊かな女の子だなと感心してしまう。
「それより、キミの名前は?」
「多々良千晴。多々良海岸の多々良に、漢数字の千に、快晴の晴」
「千晴くんかあ。珍しい名前でいいね、仲間だ仲間」
「そんなに珍しいかな」
「だって千晴と美羽だよ? 友達は裕子なのに」
唇を尖らせる美羽を見て、そういえば名前が現代的だなと気づく。
美羽。声に出さないよう、心の中で呟いてみる。
僕の感覚ではとても綺麗な響きだった。
「いい名前だと思うよ」
素直にそう告げると、美羽の口元が一気に緩んだ。
「あ、ありがとう」
そして、ぷいと顔を背けてしまう。暗くてよくわからなかったけれど、髪の隙間から覗いた耳が赤く染まっているようにも見えた。感情がすべて表に出てしまうのだろうか。
だとしたら、隠し事には向いてなさそうだけれど、きっと周囲から愛されている。
僕とは、正反対だ。
感傷を誤魔化すように上を向くと、宝石を砕いたような星空がどこまでも広がっていた。なんだか久しぶりに、空が澄んでいるような気がした。
ふと、打ち寄せる波音に混ざって柔らかい声がした。
振り向くと、制服姿の女の子が立っていた。
同い年くらいだろうか。緩やかなウェーブがかかった黒色のロングへアに、思わず視線が吸い寄せられてしまうほど形のよい二重瞼。そして、月明かりに照らされる琥珀色の瞳が印象的だった。
「この辺りは不良も人攫いもいないけれど、夜の海は危ないよ」
「いや、えっと」
よほど僕の様子がおかしかったのだろうか、女の子は心配そうに僕を覗き込む。
慣れない視線に、気恥ずかしさを覚えてしまう。
「見ない顔だね。どこから来たの」
「ずっと、ここに住んでるけど……」
「えっ、私もずっと住んでるよ?」
女の子はなぜか、驚いたような反応を見せる。
なぜだろうと考えて、ひとつの疑問が浮上する。
僕はこの女の子を見たことがない。
島に住んでいる同年代は全員知っている。中学校も高校も、島にはひとつしかないからだ。仮に不登校の生徒であっても噂は広まる。知らない同年代の女の子がいるなんて、ありえない話だった。
女の子も同じ疑問を抱いているのか、眉間に皺を寄せるようにして僕を凝視してきた。だんだんと顔が近づいてくるので、防波堤に追い詰められてしまう。
そこで初めて、女の子の制服が見慣れないデザインだと気がついた。
「その制服、どこのやつ?」
思わず、質問が漏れる。
女の子はきょとんとした顔をしつつも、すぐに答えてくれた。
「土高だよ。へへ、可愛いでしょ」
女の子はひらりとその場で回転し、スカートを花のように広げてみせる。
「でも土高の制服を知らないなんて、キミはやっぱりこの島の人じゃなさそうだね」
そして得意げな表情で僕を見た。名探偵ここにあり、と言わんばかりのドヤ顔だ。
けれど、今の僕には拍手してあげられるほどの余裕はなかった。
「いや、知らないもなにも……ありえないよ」
心臓の鼓動が速くなる。
抱き続けてきた違和感の正体が、ゆっくりと紐解かれていく。
「ありえないって、どうして?」
「だって、土高はもう……」
自分のものだとわからないくらい、声が震えていた。
土高。正式名称は香川県立土庄高等学校。この高校は香川県立小豆島高等学校と数年前に統合し、僕が通っている高校になった。
つまり土高とは、今はない高校の略称だ。
「ちょっと、どうしたの。顔色悪いよ!?」
だとしたら、信号機がなくなっていた理由もわかる。撤去されたのではなく、まだ設置されていないのだ。町の空気や通行人の服が変なのも同様だろう。
荒くなった息を整えつつ、悪い予感を確信にするための問いかけを口にする。
「ねえ。今って、西暦何年?」
この状況下における一番ベタな質問は、相手に不信感を抱かせるには十分だったらしい。
女の子はいよいよ怪訝な表情を浮かべたが、たじろぎつつも答えてくれた。
「一九七五年だよ。キミ……本当に大丈夫?」
告げられたのは、今からちょうど五十年前。
にわかに信じられないけれど、どうやら僕は過去にタイムスリップしたみたいだ。
もはや笑うしかなかった。
岬が助かる未来を願ったはずなのに、なぜか僕が過去に飛ばされている。
ドッキリかもしれない、なんて疑いはなかった。土高の制服は用意できても、島全体を巻き込むのは不可能だ。それに、僕を騙すためだけに信号機を撤去するはずがない。
なぜこうなったのかはわからないけれど、現状は把握できた。
ただ、タイムスリップを馬鹿正直に打ち明けるのはよろしくない気がした。
本格的に頭のおかしな奴だと思われて、警察に通報されてしまうかもしれない。
今の僕では、身分証明さえままならないのだ。
ひとまずこの女の子を安心させて、立ち去ってもらおう。
「えっと、大丈夫。ちょっとだけ意識が朦朧として、変なこと聞いちゃっただけだから。もうなんともないよ」
「それならいいけど……体調が悪いなら、早く帰って寝たほうがいいよ」
「ああ、その。実は僕、家出中なんだ」
笑顔を作り、咄嗟に嘘をつく。
訳ありなのが伝われば、面倒臭がってここから立ち去ってくれるだろう。僕が逆の立場だったら、家出中の人間なんてかかわりたくもない。
そう睨んだのに、女の子はなぜか離れようとしなかった。
「そっか。じゃあ、行くところがないんだ?」
そればかりか興味津々とばかりに詰め寄ってきて、腕を掴んでくる。
予想外の行動だったので、僕は反射的に頷いてしまう。
「だったら、とりあえずウチに来なよ。今日は空いてる部屋もあるからさ」
「空いてる部屋?」
「そ。ウチ、民宿やってるんだ。ホテルと比べたら小さいけど、結構評判いいんだよ」
そう言って女の子は白い歯を覗かせる。
行くあてのない僕としてはありがたい申し出だった。けれど、なにか裏があるんじゃないかと勘ぐってしまう。会ったばかりの他人に、ここまで優しくする意味はあるのだろうか。
「ね? どうかな?」
「……君の両親は、娘が見ず知らずの人間を家に招いても怒らないの?」
「きっと大丈夫だよ。お父さんもお母さんも、すっごく優しいから」
「もし僕が、逃走中の犯罪者だったらどうするの」
「えー? そんな感じには見えないけどなぁ」
「人は見かけによらないものだよ」
「私は人を見る目があるから、なんの問題もなし!」
女の子は、自信満々といった様子で胸を張る。
そういえば、亡くなった祖母も随分お人好しだった記憶がある。五十年前はこういったお節介が普通だったのかもしれない。
それなら、この好意は素直に受け取ったほうが怪しまれないだろう。
「……じゃあ、今晩だけお世話になります」
僕がそう言うと、女の子は満足げに頷いた。
「うん、よろしくね。私は赤上美羽だよ。好きに呼んでね!」
「赤上さん」
「堅っ。呼び捨てにしてよ」
「赤上」
「できれば名前で」
「……美羽」
「うんうん、それでよし」
「好きに呼んでよかったんじゃ……」
僕のツッコミなどお構いなしに、美羽はお腹を抱えて笑っている。
身振り手振りが大きく、感情表現が豊かな女の子だなと感心してしまう。
「それより、キミの名前は?」
「多々良千晴。多々良海岸の多々良に、漢数字の千に、快晴の晴」
「千晴くんかあ。珍しい名前でいいね、仲間だ仲間」
「そんなに珍しいかな」
「だって千晴と美羽だよ? 友達は裕子なのに」
唇を尖らせる美羽を見て、そういえば名前が現代的だなと気づく。
美羽。声に出さないよう、心の中で呟いてみる。
僕の感覚ではとても綺麗な響きだった。
「いい名前だと思うよ」
素直にそう告げると、美羽の口元が一気に緩んだ。
「あ、ありがとう」
そして、ぷいと顔を背けてしまう。暗くてよくわからなかったけれど、髪の隙間から覗いた耳が赤く染まっているようにも見えた。感情がすべて表に出てしまうのだろうか。
だとしたら、隠し事には向いてなさそうだけれど、きっと周囲から愛されている。
僕とは、正反対だ。
感傷を誤魔化すように上を向くと、宝石を砕いたような星空がどこまでも広がっていた。なんだか久しぶりに、空が澄んでいるような気がした。