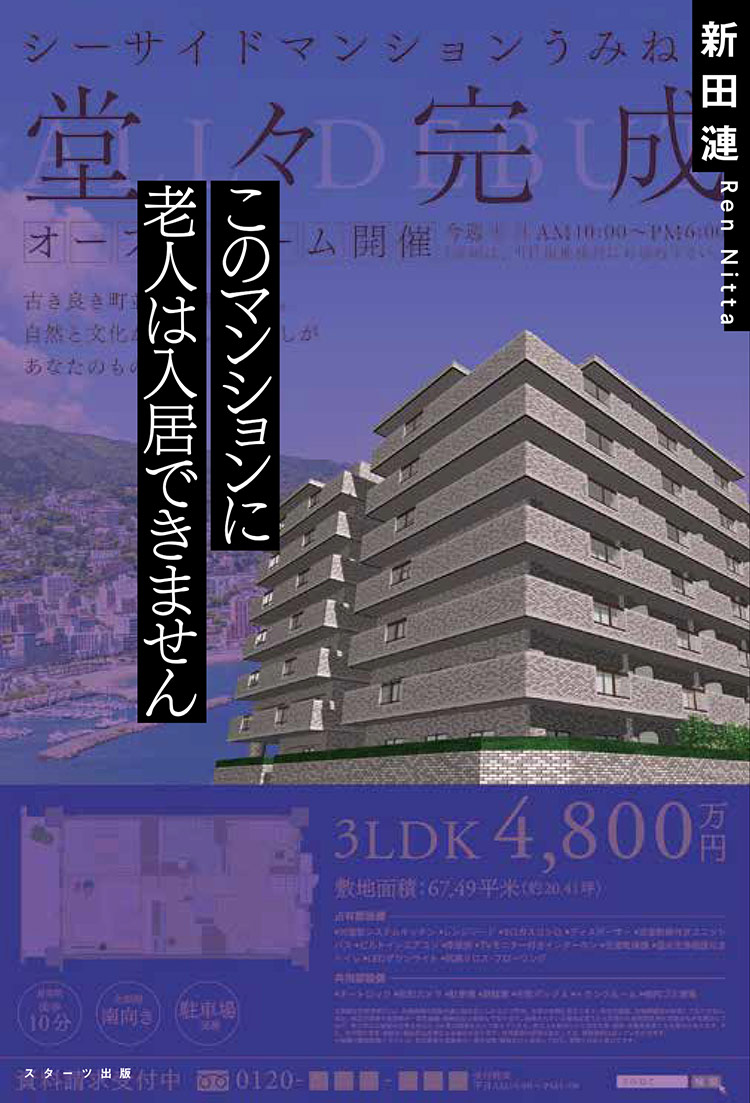突き立てた鍵の先端で、粉状になった丹色の塗料が膨らんでいく。
僕はそれを指で払いのけ、鳥居にふたたび鍵を走らせる。
罪悪感は、先人が刻んだ傷の数だけ薄れていた。
辺りは橙に染まりつつあった。このまま夜を迎えたら、下山できなくなるかもしれない。そうわかっているのに急ぐ気になれないのは、心のどこかでそれを願っているからだろうか。
「……馬鹿らしいな」
作業を中断して、ぬるくなったペットボトルのコーラを飲む。
炭酸で喉を潤すと、蒸し暑い空気の中でも頭だけはすっと冴えた。
いったい、僕はなにをしているのか。
こんなことをしたって、死んだ岬が戻ってくるはずがないのに。
風が吹いて、葉が擦れる。さわさわとした音が、遠くから聞こえるヒグラシの声と混ざり合う。木々の隙間から夕日が細く差し込んで、鍵の先端が鏡のように煌めいた。
もし自分の表情が反射していたら、きっと酷い顔だったに違いない。岬が死んでから半年が経つけれど、未だによく眠れないのだから。
僕はふたたび鳥居を傷つけながら、柱の間を何度もくぐる。
馬鹿らしい。
何度もそう否定しながら、心のどこかで奇跡を願っている。
『お兄ちゃん、知ってる?』
風に乗って、岬の声が流れてくる。いつもの幻聴だった。岬はきっと僕を許していないから、こうして天国から語りかけてくる。
『裏山にある鳥居を鍵で傷つけて、願い事をして、何回もくぐるの。そしたら、願い事が叶うんだってさ! あたしもね――』
七歳児らしい、幼さが残る言葉遣い。
小学生が好みそうな信憑性に欠けるおまじない。
そんなものに縋り付いたって、なにも起きやしない。
そう理解しているけれど、この苦しみから解放される方法が他に思いつかなかった。
目を瞑り、鳥居の前に立つ。あの日の光景はいつだって鮮明に思い出せる。
よそ見した僕を押し退ける岬が、猛スピードで突っ込んできた赤い車に轢かれてしまうシーン。空中で一回転する身体と、命がアスファルトに叩きつけられる音。死を直感するには十分すぎる情報が、脳裏に焼き付いて離れてくれやしない。
もしもあの日に戻れたら。
いいや、違う。
戻ったところで、僕はきっとなにもできない。両親からも、高校のクラスメイトからも、期待されたことなんてない。取り立てて特技もなく、夢や目標もない。薄く引き伸ばしたような日々を惰性で送り続けた僕に、運命をひっくり返す力なんてあるはずがなかった。
それなのに、岬はちいさな両手で僕なんかの命を守り、死んだ。
岬は普段から僕のことを気にかけていた。蜂が飛んできたり、散歩中の犬が吠えたりすると、僕を庇うようにして両手を広げてくれた。本来なら兄である僕が、もっとしっかりしなくちゃいけないのに。僕が、岬を守るべき立場だったのに。
だから、切に願う。
岬が助かる未来が訪れてほしい。
鳥居をくぐる。風が吹く。制服のシャツが膨らみを帯びる。
ただそれだけで、他にはなにも起きなかった。
「そりゃ、そうだよな」
やがて日が落ち始め、僕の心が溶け出したように空が青紫に染まっていく。どうやら時間切れだ。傍らに置いていたスクールバッグを背負い、大きな息を吐いた。
これから、岬がいない家に帰らなくちゃいけない。
両親もまだショックから立ち直れておらず、食卓の空気はいつだって重い。そればかりか、母の視線は僕を責めるように鋭く、硝子の切っ先を突きつけられているようだった。無理もない。岬が生まれてからの多々良家は、岬を中心に回り続けていたのだから。
学校で向けられる視線も同様に冷たかった。久しぶりに登校すると、研ぎ澄まされた視線が容赦なく僕に向けられた。薄情者。妹を見捨てたクズ。無言でそんなレッテルが貼られていく。もともとクラスメイトとの交流が薄かったので、否定する気力さえ湧かなかった。
大丈夫、卒業までの辛抱だから。そう言い聞かせても精神はすり減っていく。生きている意味のない無価値な存在だと、日を追うごとに自覚していく。
それでも人生は終わってくれやしないのだから、神様なんていないのかもしれない。
いや、神様がいるからこそ、僕に罰を与えているのかもしれないけれど。
そんなことを考えながら、僕は神社の跡地を後にする。人々から見捨てられ、竹林に囲まれるようにして朽ち果てた鳥居は、結局なにも応えてくれなかった。
背負い直したスクールバックは、来たときよりもずっと重かった。
僕はそれを指で払いのけ、鳥居にふたたび鍵を走らせる。
罪悪感は、先人が刻んだ傷の数だけ薄れていた。
辺りは橙に染まりつつあった。このまま夜を迎えたら、下山できなくなるかもしれない。そうわかっているのに急ぐ気になれないのは、心のどこかでそれを願っているからだろうか。
「……馬鹿らしいな」
作業を中断して、ぬるくなったペットボトルのコーラを飲む。
炭酸で喉を潤すと、蒸し暑い空気の中でも頭だけはすっと冴えた。
いったい、僕はなにをしているのか。
こんなことをしたって、死んだ岬が戻ってくるはずがないのに。
風が吹いて、葉が擦れる。さわさわとした音が、遠くから聞こえるヒグラシの声と混ざり合う。木々の隙間から夕日が細く差し込んで、鍵の先端が鏡のように煌めいた。
もし自分の表情が反射していたら、きっと酷い顔だったに違いない。岬が死んでから半年が経つけれど、未だによく眠れないのだから。
僕はふたたび鳥居を傷つけながら、柱の間を何度もくぐる。
馬鹿らしい。
何度もそう否定しながら、心のどこかで奇跡を願っている。
『お兄ちゃん、知ってる?』
風に乗って、岬の声が流れてくる。いつもの幻聴だった。岬はきっと僕を許していないから、こうして天国から語りかけてくる。
『裏山にある鳥居を鍵で傷つけて、願い事をして、何回もくぐるの。そしたら、願い事が叶うんだってさ! あたしもね――』
七歳児らしい、幼さが残る言葉遣い。
小学生が好みそうな信憑性に欠けるおまじない。
そんなものに縋り付いたって、なにも起きやしない。
そう理解しているけれど、この苦しみから解放される方法が他に思いつかなかった。
目を瞑り、鳥居の前に立つ。あの日の光景はいつだって鮮明に思い出せる。
よそ見した僕を押し退ける岬が、猛スピードで突っ込んできた赤い車に轢かれてしまうシーン。空中で一回転する身体と、命がアスファルトに叩きつけられる音。死を直感するには十分すぎる情報が、脳裏に焼き付いて離れてくれやしない。
もしもあの日に戻れたら。
いいや、違う。
戻ったところで、僕はきっとなにもできない。両親からも、高校のクラスメイトからも、期待されたことなんてない。取り立てて特技もなく、夢や目標もない。薄く引き伸ばしたような日々を惰性で送り続けた僕に、運命をひっくり返す力なんてあるはずがなかった。
それなのに、岬はちいさな両手で僕なんかの命を守り、死んだ。
岬は普段から僕のことを気にかけていた。蜂が飛んできたり、散歩中の犬が吠えたりすると、僕を庇うようにして両手を広げてくれた。本来なら兄である僕が、もっとしっかりしなくちゃいけないのに。僕が、岬を守るべき立場だったのに。
だから、切に願う。
岬が助かる未来が訪れてほしい。
鳥居をくぐる。風が吹く。制服のシャツが膨らみを帯びる。
ただそれだけで、他にはなにも起きなかった。
「そりゃ、そうだよな」
やがて日が落ち始め、僕の心が溶け出したように空が青紫に染まっていく。どうやら時間切れだ。傍らに置いていたスクールバッグを背負い、大きな息を吐いた。
これから、岬がいない家に帰らなくちゃいけない。
両親もまだショックから立ち直れておらず、食卓の空気はいつだって重い。そればかりか、母の視線は僕を責めるように鋭く、硝子の切っ先を突きつけられているようだった。無理もない。岬が生まれてからの多々良家は、岬を中心に回り続けていたのだから。
学校で向けられる視線も同様に冷たかった。久しぶりに登校すると、研ぎ澄まされた視線が容赦なく僕に向けられた。薄情者。妹を見捨てたクズ。無言でそんなレッテルが貼られていく。もともとクラスメイトとの交流が薄かったので、否定する気力さえ湧かなかった。
大丈夫、卒業までの辛抱だから。そう言い聞かせても精神はすり減っていく。生きている意味のない無価値な存在だと、日を追うごとに自覚していく。
それでも人生は終わってくれやしないのだから、神様なんていないのかもしれない。
いや、神様がいるからこそ、僕に罰を与えているのかもしれないけれど。
そんなことを考えながら、僕は神社の跡地を後にする。人々から見捨てられ、竹林に囲まれるようにして朽ち果てた鳥居は、結局なにも応えてくれなかった。
背負い直したスクールバックは、来たときよりもずっと重かった。