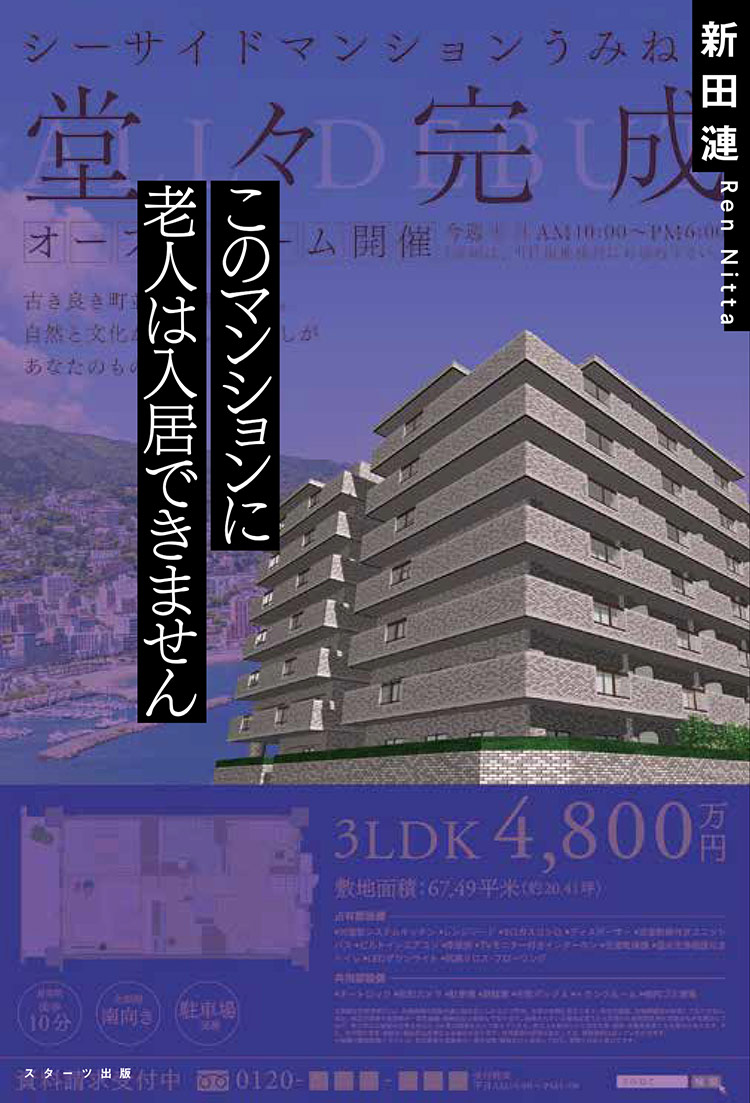僕と美羽は、ほとんど無言のまま朝を迎えた。
荷物を抱えながら床で寝転んだ僕は一睡もできず、ただ美羽の言動について考えることしかできなかった。美羽もまた、眠れなかったらしい。目の下にはうっすらとクマが浮かんでいて、ときおり大きなあくびをしている。
美羽の両親には響さんが連絡してくれたみたいで、チェックアウトの際に僕たちはお礼を述べた。突然の外泊、それも男女が同じ部屋で過ごすにもかかわらず寛容なのは、きっと美羽の体調が関係している。見ず知らずの僕を赤上荘で雇ってくれたのも同様だろう。
ビジネスホテルを出ると、僕の心を投影したように鈍色の空が広がっていた。厚い雲がどこまでも町を覆い、今にも雨が降り出しそうな気配だった。
「今日は早めに帰ろっか」
美羽の言葉に僕は頷く。
どことなく、美羽の横顔は仄暗かった。
昨夜、なぜ停滞を望んでいたのか。その答えは未だわからない。自身の体調を案じているのか、僕がこの時代の人間じゃないことを悲しんでいるのか、それすら判別できない。無力な僕は、美羽の体調を心配することしかできなかった。
池田港に到着した僕と美羽は、そのまま土庄行きの路線バスに乗り込んだ。次第に雨が降ってきて、窓ガラスを打ち鳴らす。不規則な音に耳を傾けていると、左肩に重みを感じた。
「美羽?」
規則的な寝息を立てながら、美羽は眠っている。その表情はとても安らかで、いたって健康な女の子にしか見えない。
僕が考えていることなんて杞憂で、あの錠剤はただの風邪薬だ。
そんな都合のいい可能性に縋りながら、ほのかな体温を感じていた。
土庄町に到着した頃には雨が本降りになっており、僕たちは身体を濡らしながら必死になって駆けた。
「あはは、びしょ濡れになっちゃうね」
僕の前を走る美羽は、とても力強く見える。
まるで、僕の不安を吹き飛ばすような足取りだった。
きっと考えすぎなのだ。
何事もなく夏は過ぎ去って、僕はゆっくりと決断を下せる。
そんな祈りを胸にしながら、赤上荘の母屋に辿り着いた。
美羽は髪から雨を滴らせながら「ただいま」と元気よく声を出す。
居間から恵子さんが顔を出し、僕たちの姿を見て呆れたように笑う。
「バスタオル持ってくるわね」
「うん、ありがとう」
僕たちは身体を拭き、交代で入浴した。そうして落ち着くと、一気に睡魔が襲いかかってきた。昨日ろくに眠れなかったツケが回ってきたのだろう。
僕は自分の部屋に戻り、敷布団の上で横になる。
そのまま目を瞑ると、すぐに意識が薄れていく。
どこからか声が聞こえる。
僕を呼ぶ声が反響のように重なり合い、やがてひとつに収束していく。僕の脳を中心にして、くるくると回転するような感覚。
そんな微睡みに身を委ねていると、いつしか意識を手放していた。
それから、どれくらいの時間が経ったのだろう。
次に僕の名前を呼んだのは、恵子さんだった。
激しく身体を揺さぶられ、僕は半ば無理やり覚醒する。
「――千晴くん!」
違う。これは夢じゃない。
慌てて飛び起きると、恵子さんが必死の形相で僕を揺さぶっていた。
「ど、どうしたんですか」
「美羽がどこにもいないの。母屋にも、民宿にも見当たらなくて……」
絞り出すような声には、悲壮感が滲み出ていた。
時計を見やると、時刻はすでに二十三時を回っていた。相変わらず外は激しい雨で、散弾銃のような音が絶え間なく鳴り響いている。
こんな時間、そのうえ悪天候。
外に出なければいけない用事なんて、あるはずがなかった。
「――捜してきます!」
恵子さんの静止を振り切って、すぐに部屋を飛び出した。スニーカーの踵を踏んづけたまま外に出て、美羽の名前を叫んだ。けれど、闇の中で降り注ぐ雨は視界どころか音をも遮ってしまう。それでも僕は、白い霧を切り裂くように走り、どこにいるかもわからない美羽を捜す。
「どこに行ったんだよ!」
あてがない、心当たりがない。
こんな状況下で頼るべき人物は、一人しかいなかった。
喫茶店の前に辿り着いた僕は、扉を何度もノックする。雨音に間違われないよう、壊れるんじゃないかと思うくらいに力強く。
「うるせぇな、何時だと思ってんだ……」
勢いよく開いた扉から、怒り心頭の裕子が顔を出す。
けれど僕の姿を認めた瞬間、異常事態を察したようだった。
裕子は落ち着きを取り戻し、静かに問いかけてくる。
「どうしたんだよ」
その反応は、ここにも美羽がいない証でもあった。
僕は俯きながら、事の経緯を手短に説明する。
「美羽がどこにもいないんだ。心当たりはない?」
「こんな時間に美羽が行きそうな場所なんて、どこにもないぞ」
裕子も思い当たる節がないらしく、苦々しく顔を歪める。
僕は礼を述べて、ひどく重い全身に鞭を打つ。
「――おい、千晴!」
裕子の声を無視して、僕はふたたび闇の中へと駆け出した。
どこかで靴が脱げてしまったらしく、左足の裏に鋭い痛みが走る。白い靴下は赤く滲み、雨と一緒に血が滴り流れていく。それでも僕は美羽を捜し続けた。
このまま、二度と会えないかもしれない。そんな不安が大きくなってくる。
「どこにいるんだよ」
寒さと痛さで意識が朦朧としたまま歩いていると、いつの間にか美羽と出会った防波堤の前にいた。夜のなかで海は荒れ、打ち付ける波が道路にまで押し寄せる。たくさんの音と飛沫が混ざり合い、僕の視覚と聴覚はほとんど意味を成さなかった。前後左右がわからないまま、激しく転倒してしまう。疲労なのか、打ち寄せた波に足を取られたのかさえわからない。身体が引きずられ、激しい痛みが全身に伝わっていく。
雨音と波音。
「――千晴くん」
薄れゆく意識のなかで、美羽の声が届く。
美羽が近くにいる。
それだけを頼りにして、身体を起こそうとする。
まるで全身が泥に埋もれたみたいに重たくて、何度も何度ももがき続ける。
「――美羽!」
身体の奥底から出た叫びとともに覚醒する。
窓から差し込む朝日に、暖かい布団。
激しい音は小鳥の囀りになり、かりそめの平穏を運んでくる。
フリップ時計は、朝の六時半を示していた。
「……あれ、僕。なんで、ここに」
意味がわからず、呆けてしまう。
辺りを見渡す。見間違えるはずがない。
ここは赤上荘の部屋の中だ。訳がわからない。
あれは夢だったのか。
頬をつねる。しっかりと痛みを感じる。
「なにが起きてるんだ……」
呟いても、答えは返ってこない。
「そうだ、美羽は!?」
飛び起きて母屋へ向かうと、玄関の扉がすっと開き、美羽が姿を現した。
「あれ、千晴くん頭ボッサボサだよ。もしかして寝坊した?」
美羽が冗談っぽく頬を膨らます。
白い格子柄のワンピースに、いつもよりカールが強い髪型。
目眩がするほどの既視感を覚えつつ、疑念を振り払うようにして美羽の肩を掴む。
「美羽、なんだよね?」
涙声で伝えると、美羽は怪訝な表情で僕を見た。
なんの話だ、といわんばかりに。
「もう、寝ぼけてるでしょ。このままじゃフェリーに乗り遅れるから、早く用意してきなよ」
「え?」
「え? じゃないよ。今から高松に行くんでしょ?」
その言葉で、確信してしまう。
「嘘だろ、そんなはず……」
言葉が夏に溶けていく。
僕はなぜか、美羽と高松へ出かける日に戻っていた。