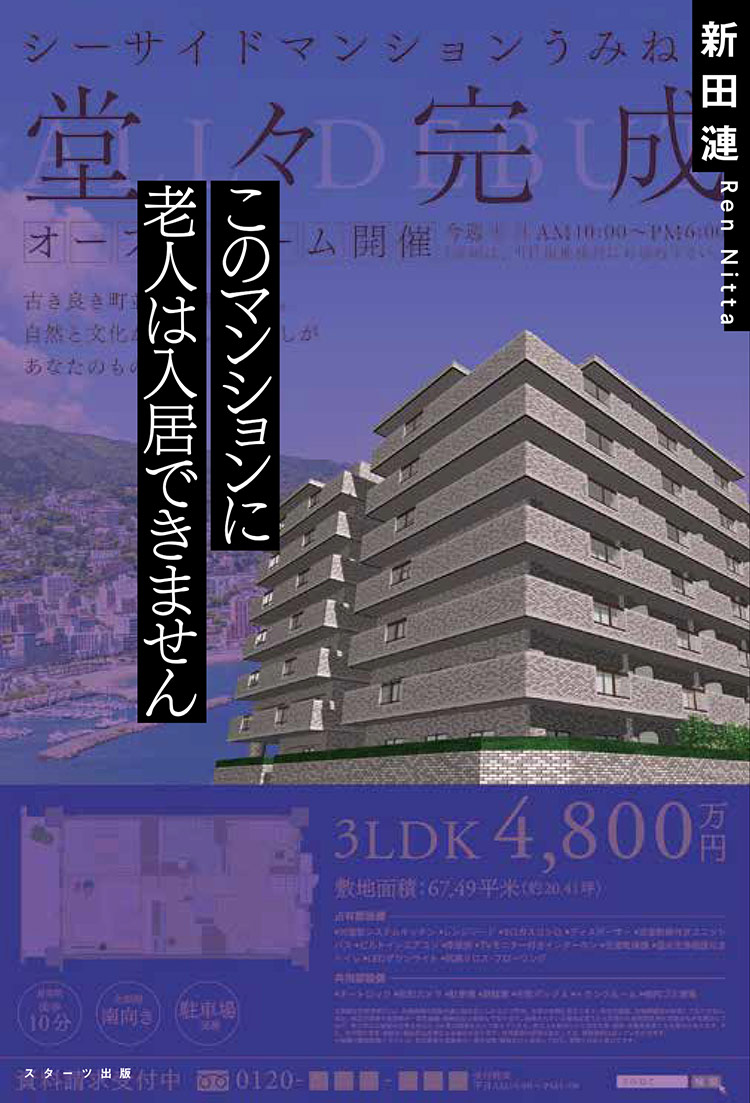「まずは千晴くんに、この時代を好きになってもらおうではないか」
喫茶店を出た僕たちは、美羽の案内で瓦町付近を歩いていた。
この辺りは、元の時代と変わらず人の往来が多い。夏休みの影響もあり、家族連れの姿も目立っている。父親にアイスを買ってもらったのか、ちいさな女の子が満面の笑みで僕の隣を通り抜けていった。なんとなく微笑ましい気持ちになる。
「人が多いね。大丈夫?」
美羽は軽い足取りで道を歩き、ときおり笑顔で話しかけてくる。さきほど覗かせた表情の陰りは見られない。気のせいだったのだろう。内心で安堵していると、いつの間にかボウリング場に到着していた。
昭和はボウリングが盛んだったと聞いたことがあるが、すでにブームは終焉に向かいつつあるらしい。夏休みシーズンにもかかわらず、客足はまばらだった。
従業員にレーンへ案内された僕と美羽は、各自準備を始める。とはいっても、自分の腕力に合った重さの球を持ってくるだけだ。僕がいつも使っている重さの球を探そうとすると、美羽がつんつんと肩を小突いてくる。
「ふふん、ボウリングってやったことないでしょ」
「いや、普通にあるよ」
「えっ、まだボウリングって人気あるの!?」
「取り立てて流行ってるわけじゃないけど、娯楽の定番ではあるかな」
「そ、そうなんだ。あちこちでボウリング場が閉店してるらしいし、千晴くんの時代にはないと思ってたのに」
美羽はがっくりと肩を落とす。泣き出してしまうんじゃないかと思うくらいに眉が八の字になっている。どうやら僕の時代にはない遊びを楽しんでもらおうと意気込んでいたらしい。
「……どちらかといえばボウリングは好きだし、気にしなくて大丈夫だよ」
「本当? へへ、私も好きー。そうだ、勝負しようよ。負けたらジュース奢り!」
ころころと変わる表情は忙しなく、見ていて飽きなかった。
僕と美羽はさっそく一投目を投じる。お互いにストライクだった。ボウリングをするのは久しぶりだったけれど、あまり感覚は鈍っていないようだ。
「やるね千晴くん。でも、部屋でイメトレを何年も続けてきた私に勝てるかな?」
「そこは実践じゃないんだ」
いつものような冗談だと思ったので、僕はすかさずツッコミを入れる。
しかし美羽は、ばつが悪そうな笑顔で「そうなんだよねえ」と言うだけだった。
予想外の反応だったので、僕は固まってしまう。
がこん、と遠く離れたレーンから音が響く。
視線を向けると、ちいさな女の子が両手で球を転がしたあとだった。
「そういえばさ、千晴くんはちいさな女の子を見ても大丈夫になったよね」
「……あ、たしかに」
美羽に指摘され、僕自身も初めて気がつく。一緒の空間にいるだけで具合が悪くなったのに、最近はすれ違ってもなにも思わなくなった。岬の影を見たときだって、混乱はしたものの強烈な頭痛には苛まれなかった。以前より症状が緩和しているのは間違いない。
「美羽に打ち明けたのがよかったのかも。なんだか胸のつかえが取れたというか」
きっかけといえば、やはり石段に座ってアイスを食べた日のことだろう。
あの日から、岬に対する考え方が変わったのだから。
「そっかそっか」
美羽は立ち上がり、自然な動作で投球フォームへと移行する。
しかし手元が狂ったのか、投じた球はピンに到達することなくガターになった。
「……私は恩人ってことになるねえ」
美羽は前方を向いたまま言う。表情は窺えないが、冗談めいた口調だ。
「そうだね。感謝してるよ」
「だったらジュースでも奢ってもらおうかなっ」
「いや、このままだと美羽が奢る側だよ」
「甘いよ千晴くん。まだ勝負は始まったばかりだからね」
美羽は強がるように言って、二投目を投じる。
ふらふらとした軌道を描く球はピンのわずか手前で右に折れ、ガターになってしまった。
結局、その後も美羽はあまりピンを倒せなかった。終わってみればボウリング対決は僕の圧勝で、勝者の証である瓶のコーラを手にすることができた。
ボウリング場を後にすると、美羽は「お腹がすいたね」と呟きながら、ちらちらと僕を見てきた。休憩したいらしい。僕はあまりお腹が減っていなかったけれど同調し、おすすめの飲食店を聞いてみた。
「うーん。逆に、千晴くんはどんなの食べてたの?」
「マックが多かったかな」
「誰? 外国人?」
「……そりゃそうなるよね」
この時代には、僕がよく利用していたファストフードのチェーン店がない。もしかすると東京にはあるのかもしれないけれど、高松市にはまだ上陸していないみたいだった。
お互いに妙案が浮かばなかったので、歩きながら店を探すことにした。行き交う人はやはり髪型が野暮ったくて、服もぴっちりしている。来た当初ほど違和感がなくなったとはいえ時代を感じてしまう。
それなのに美羽の服装が魅力的に思えるのは、なぜだろう。
「やっぱりハンバーグランチかな。でも人参はあんまり好きじゃないから、千晴くんにあげるね。健康になってね」
美羽は卓上のメニュー表を眺めながらも、すでにオーダーが決まっている様子だった。僕はビフテキにしようと決めていたので、すぐに店員を呼ぶことにした。
注文を終えると、美羽は「ぶええ」と息を吐きながら椅子に全体重を預けるような姿勢になった。
「ボウリングで疲れたの?」
「そうかも。普段あんまり使わない筋肉を使ったからかな」
「でも、民宿の仕事で鍛えてるんじゃ」
「いつもの仕事は筋肉Aしか使わないけど、ボウリングで使うのは筋肉Bだから」
美羽は自分の二の腕を指差しながら、よくわからない表現で部位の説明をしてくれた。僕は曖昧に頷きつつも、腕の細さに驚いてしまう。普段は注意深く観察していなかったせいか、あまり気にならなかった。けれど、いちど目についてしまうと視線が吸い寄せられるものだ。
「……やっぱり好き嫌いせず、人参も食べなよ」
「えー、やだ。クレヨンみたいな味するから」
「この時代の人って、クレヨンを食べるの?」
「うん、健康のためにね。どれもおいしくないけど、赤色が一番まずいの」
「……この時代に馴染める自信がなくなってきた」
「あはは、嘘だよっ」
美羽がからからと笑う。そんなやり取りを続けていると、店員がハンバーグランチを運んできた。デミグラスソースがたっぷりかかったハンバーグは、僕がいた時代のものより上等に見える。きっと原価率や値上げ云々で、この時代のハンバーグのほうが大きいからだろう。
やがて僕のビフテキも運ばれてきた。肉厚で、うっすらと赤身が残るミディアムレアだった。ソースが鉄板の上で音を立てながら蒸発して、玉ねぎの香りがふわっと広がる。視覚と聴覚から胃袋を鷲掴みにされ、僕は本能のままかぶりついた。ほどよく柔らかくて、噛むたびに旨味が溢れ出す。
「おいしい」
「こっちもおいしいよ! 島にもこういうお店があったらいいのにな」
美羽は目を細め、多幸感を滲ませている。
「そういえばさ、千晴くんがいた時代の小豆島ってどんな感じになってるの?」
「あんまり変わってないけど、この時代のほうが観光客はたくさんいるかな。あと、学校も減ってる」
「そっか。すこしずつ過疎化してるんだね」
僕は美羽の問いかけに答えながらも、内心で緊張していた。
赤上荘の話題になったら、どう答えるのが正解なのだろう。
「あ、またなにか考えてる」
「……僕って、そんなに顔に出るのかな」
「うん。なに考えてたか当ててみよっか?」
美羽はハンバーグをナイフで切り分けながら、ふふんと得意げに白い歯をこぼす。
「赤上荘の話になったらどう答えようかなーって悩んでたでしょ?」
「……美羽ってエスパーなの?」
「千晴くんがわかりやすいんだよ。なに考えてるかわかんないよりいいけどね」
美羽はハンバーグを口に放り込み、一口目と同じリアクションで破顔した。
「ま、千晴くんが気にすることじゃないよ」
「なにが?」
「赤上荘のことだよ。五十年後には潰れちゃってるんだよね」
美羽の推理を受けて、僕はナイフを落としてしまう。
お皿に当たってしまったせいで、硬質の音が店内に鳴り響く。
「……どうして、そう思うの」
明言を避けつつ逆に問いかける。
美羽の表情は赤上荘の破滅をすでに予測しており、かつ衝撃を覚えていないように映った。美羽はゆっくりと咀嚼してから、グラスの水を飲む。
そして僕の瞳を真正面から射抜くように、ただただじっと見つめた。
「――実はね、私も未来から来たんだ」
美羽がそう告げた瞬間、体温がすっと下がっていく。
一瞬で口の中が干からびて、僕は言葉を発せなくなった。
そんな僕の様子を、美羽は心配そうに眺めている。いや、どちらかといえば申し訳なさそうな表情だった。なんなら、今にも吹き出しそうな顔をしている。
「えと、ごめん。冗談のつもりだったんだけど、そこまで真に受けちゃうとは思わなくて」
「ねえちょっと」
「まあまあ、おいしい人参でも食べて機嫌直してよ」
ハンバーグがのった皿から、乱切りにされた人参がこちらに移住してくる。呆れた僕がなにも言わないのをいいことに、美羽はブロッコリーの引っ越しまで成功させた。
僕が視線だけで咎めると、美羽は悪戯がばれた子どものようにわざとらしく口笛を吹いてみせた。
おどけた表情はいつもと同じはずなのに、どこか硬いような気がする。
けれど、僕はその違和感をいつまでも紐解けなかった。
喫茶店を出た僕たちは、美羽の案内で瓦町付近を歩いていた。
この辺りは、元の時代と変わらず人の往来が多い。夏休みの影響もあり、家族連れの姿も目立っている。父親にアイスを買ってもらったのか、ちいさな女の子が満面の笑みで僕の隣を通り抜けていった。なんとなく微笑ましい気持ちになる。
「人が多いね。大丈夫?」
美羽は軽い足取りで道を歩き、ときおり笑顔で話しかけてくる。さきほど覗かせた表情の陰りは見られない。気のせいだったのだろう。内心で安堵していると、いつの間にかボウリング場に到着していた。
昭和はボウリングが盛んだったと聞いたことがあるが、すでにブームは終焉に向かいつつあるらしい。夏休みシーズンにもかかわらず、客足はまばらだった。
従業員にレーンへ案内された僕と美羽は、各自準備を始める。とはいっても、自分の腕力に合った重さの球を持ってくるだけだ。僕がいつも使っている重さの球を探そうとすると、美羽がつんつんと肩を小突いてくる。
「ふふん、ボウリングってやったことないでしょ」
「いや、普通にあるよ」
「えっ、まだボウリングって人気あるの!?」
「取り立てて流行ってるわけじゃないけど、娯楽の定番ではあるかな」
「そ、そうなんだ。あちこちでボウリング場が閉店してるらしいし、千晴くんの時代にはないと思ってたのに」
美羽はがっくりと肩を落とす。泣き出してしまうんじゃないかと思うくらいに眉が八の字になっている。どうやら僕の時代にはない遊びを楽しんでもらおうと意気込んでいたらしい。
「……どちらかといえばボウリングは好きだし、気にしなくて大丈夫だよ」
「本当? へへ、私も好きー。そうだ、勝負しようよ。負けたらジュース奢り!」
ころころと変わる表情は忙しなく、見ていて飽きなかった。
僕と美羽はさっそく一投目を投じる。お互いにストライクだった。ボウリングをするのは久しぶりだったけれど、あまり感覚は鈍っていないようだ。
「やるね千晴くん。でも、部屋でイメトレを何年も続けてきた私に勝てるかな?」
「そこは実践じゃないんだ」
いつものような冗談だと思ったので、僕はすかさずツッコミを入れる。
しかし美羽は、ばつが悪そうな笑顔で「そうなんだよねえ」と言うだけだった。
予想外の反応だったので、僕は固まってしまう。
がこん、と遠く離れたレーンから音が響く。
視線を向けると、ちいさな女の子が両手で球を転がしたあとだった。
「そういえばさ、千晴くんはちいさな女の子を見ても大丈夫になったよね」
「……あ、たしかに」
美羽に指摘され、僕自身も初めて気がつく。一緒の空間にいるだけで具合が悪くなったのに、最近はすれ違ってもなにも思わなくなった。岬の影を見たときだって、混乱はしたものの強烈な頭痛には苛まれなかった。以前より症状が緩和しているのは間違いない。
「美羽に打ち明けたのがよかったのかも。なんだか胸のつかえが取れたというか」
きっかけといえば、やはり石段に座ってアイスを食べた日のことだろう。
あの日から、岬に対する考え方が変わったのだから。
「そっかそっか」
美羽は立ち上がり、自然な動作で投球フォームへと移行する。
しかし手元が狂ったのか、投じた球はピンに到達することなくガターになった。
「……私は恩人ってことになるねえ」
美羽は前方を向いたまま言う。表情は窺えないが、冗談めいた口調だ。
「そうだね。感謝してるよ」
「だったらジュースでも奢ってもらおうかなっ」
「いや、このままだと美羽が奢る側だよ」
「甘いよ千晴くん。まだ勝負は始まったばかりだからね」
美羽は強がるように言って、二投目を投じる。
ふらふらとした軌道を描く球はピンのわずか手前で右に折れ、ガターになってしまった。
結局、その後も美羽はあまりピンを倒せなかった。終わってみればボウリング対決は僕の圧勝で、勝者の証である瓶のコーラを手にすることができた。
ボウリング場を後にすると、美羽は「お腹がすいたね」と呟きながら、ちらちらと僕を見てきた。休憩したいらしい。僕はあまりお腹が減っていなかったけれど同調し、おすすめの飲食店を聞いてみた。
「うーん。逆に、千晴くんはどんなの食べてたの?」
「マックが多かったかな」
「誰? 外国人?」
「……そりゃそうなるよね」
この時代には、僕がよく利用していたファストフードのチェーン店がない。もしかすると東京にはあるのかもしれないけれど、高松市にはまだ上陸していないみたいだった。
お互いに妙案が浮かばなかったので、歩きながら店を探すことにした。行き交う人はやはり髪型が野暮ったくて、服もぴっちりしている。来た当初ほど違和感がなくなったとはいえ時代を感じてしまう。
それなのに美羽の服装が魅力的に思えるのは、なぜだろう。
「やっぱりハンバーグランチかな。でも人参はあんまり好きじゃないから、千晴くんにあげるね。健康になってね」
美羽は卓上のメニュー表を眺めながらも、すでにオーダーが決まっている様子だった。僕はビフテキにしようと決めていたので、すぐに店員を呼ぶことにした。
注文を終えると、美羽は「ぶええ」と息を吐きながら椅子に全体重を預けるような姿勢になった。
「ボウリングで疲れたの?」
「そうかも。普段あんまり使わない筋肉を使ったからかな」
「でも、民宿の仕事で鍛えてるんじゃ」
「いつもの仕事は筋肉Aしか使わないけど、ボウリングで使うのは筋肉Bだから」
美羽は自分の二の腕を指差しながら、よくわからない表現で部位の説明をしてくれた。僕は曖昧に頷きつつも、腕の細さに驚いてしまう。普段は注意深く観察していなかったせいか、あまり気にならなかった。けれど、いちど目についてしまうと視線が吸い寄せられるものだ。
「……やっぱり好き嫌いせず、人参も食べなよ」
「えー、やだ。クレヨンみたいな味するから」
「この時代の人って、クレヨンを食べるの?」
「うん、健康のためにね。どれもおいしくないけど、赤色が一番まずいの」
「……この時代に馴染める自信がなくなってきた」
「あはは、嘘だよっ」
美羽がからからと笑う。そんなやり取りを続けていると、店員がハンバーグランチを運んできた。デミグラスソースがたっぷりかかったハンバーグは、僕がいた時代のものより上等に見える。きっと原価率や値上げ云々で、この時代のハンバーグのほうが大きいからだろう。
やがて僕のビフテキも運ばれてきた。肉厚で、うっすらと赤身が残るミディアムレアだった。ソースが鉄板の上で音を立てながら蒸発して、玉ねぎの香りがふわっと広がる。視覚と聴覚から胃袋を鷲掴みにされ、僕は本能のままかぶりついた。ほどよく柔らかくて、噛むたびに旨味が溢れ出す。
「おいしい」
「こっちもおいしいよ! 島にもこういうお店があったらいいのにな」
美羽は目を細め、多幸感を滲ませている。
「そういえばさ、千晴くんがいた時代の小豆島ってどんな感じになってるの?」
「あんまり変わってないけど、この時代のほうが観光客はたくさんいるかな。あと、学校も減ってる」
「そっか。すこしずつ過疎化してるんだね」
僕は美羽の問いかけに答えながらも、内心で緊張していた。
赤上荘の話題になったら、どう答えるのが正解なのだろう。
「あ、またなにか考えてる」
「……僕って、そんなに顔に出るのかな」
「うん。なに考えてたか当ててみよっか?」
美羽はハンバーグをナイフで切り分けながら、ふふんと得意げに白い歯をこぼす。
「赤上荘の話になったらどう答えようかなーって悩んでたでしょ?」
「……美羽ってエスパーなの?」
「千晴くんがわかりやすいんだよ。なに考えてるかわかんないよりいいけどね」
美羽はハンバーグを口に放り込み、一口目と同じリアクションで破顔した。
「ま、千晴くんが気にすることじゃないよ」
「なにが?」
「赤上荘のことだよ。五十年後には潰れちゃってるんだよね」
美羽の推理を受けて、僕はナイフを落としてしまう。
お皿に当たってしまったせいで、硬質の音が店内に鳴り響く。
「……どうして、そう思うの」
明言を避けつつ逆に問いかける。
美羽の表情は赤上荘の破滅をすでに予測しており、かつ衝撃を覚えていないように映った。美羽はゆっくりと咀嚼してから、グラスの水を飲む。
そして僕の瞳を真正面から射抜くように、ただただじっと見つめた。
「――実はね、私も未来から来たんだ」
美羽がそう告げた瞬間、体温がすっと下がっていく。
一瞬で口の中が干からびて、僕は言葉を発せなくなった。
そんな僕の様子を、美羽は心配そうに眺めている。いや、どちらかといえば申し訳なさそうな表情だった。なんなら、今にも吹き出しそうな顔をしている。
「えと、ごめん。冗談のつもりだったんだけど、そこまで真に受けちゃうとは思わなくて」
「ねえちょっと」
「まあまあ、おいしい人参でも食べて機嫌直してよ」
ハンバーグがのった皿から、乱切りにされた人参がこちらに移住してくる。呆れた僕がなにも言わないのをいいことに、美羽はブロッコリーの引っ越しまで成功させた。
僕が視線だけで咎めると、美羽は悪戯がばれた子どものようにわざとらしく口笛を吹いてみせた。
おどけた表情はいつもと同じはずなのに、どこか硬いような気がする。
けれど、僕はその違和感をいつまでも紐解けなかった。