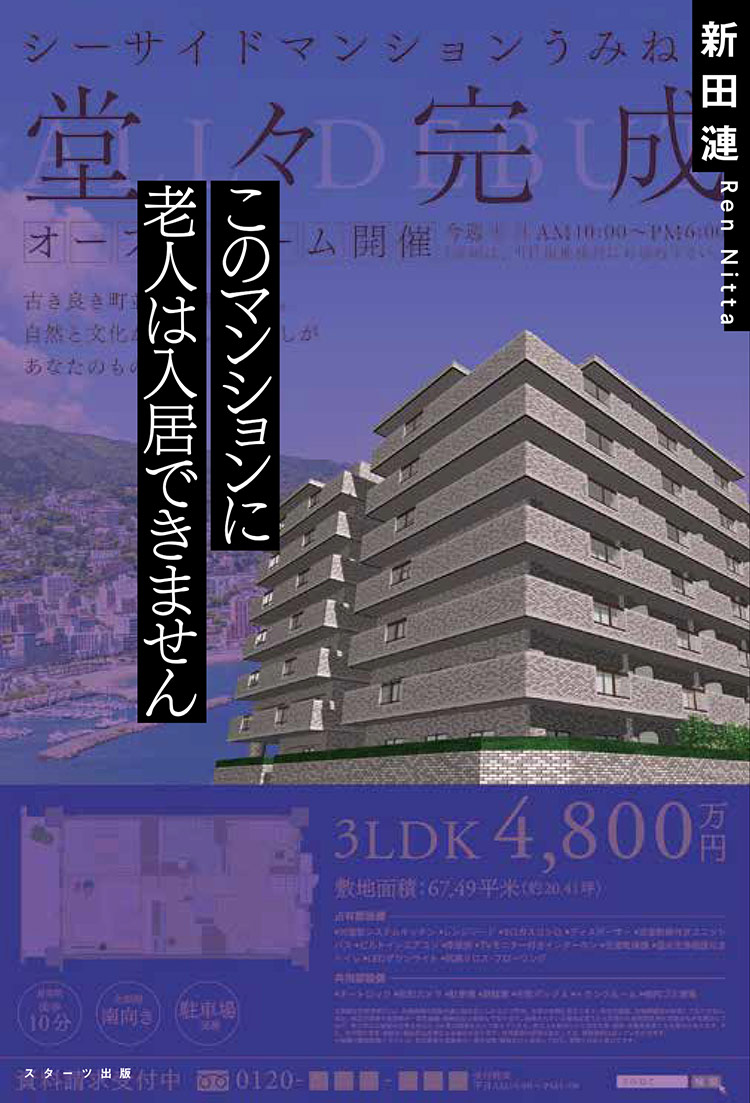五十年前の高松市内は、想像していたよりも空が広かった。視界を遮る建物が少ないからだ。それだけに、建物のひとつひとつを細部まで眺めてしまう。この時代の看板は文字やイラストが主流らしく、モデルの写真を起用したものはほとんど見られない。当然ではあるけれど、昭和を舞台にした映画のセットみたいな光景がどこまでも広がっていた。
「高松に来たのは初めて?」
僕の事情を知る由もない美羽は、初めて訪れる町に興奮していると解釈したらしい。
「……久しぶり、かな」
僕は当たり障りのない返答を口にする。
けれど、こうして隠し続けるのは限界がある。
「やっぱり千晴くんって謎めいてるよね。どこに住んでたか全然わかんないし」
案の定、美羽は呆れたように笑った。口調こそ柔らかい。でも、内心では不信感を募らせているのだろう。もう二週間近く一緒にいるのに、僕はまだ一番大事なことを伝えていないのだから。心臓を掴まれたような痛みが、胸の奥にじんわりと広がった。
今すぐにでも、秘密を打ち明けたい。
「ねえ、美羽」
呼び止めると、美羽は振り返って首を傾げた。
白いワンピースの裾が花のように広がり、やがて萎んでいく。
「話があるんだ」
「それって、真面目なやつ?」
「かなりね。冗談だと思われるかもしれないけど」
信号が赤になり、僕たちは立ち止まる。
目の前の車道をセダンや軽トラックが行き交い、轟音を響かせていく。
意を決し、唇を開く。
「実は僕」
「――ま、待って」
が、止められる。
美羽はこちらに手のひらを向け、大袈裟なくらい深呼吸を繰り返す。
「ここ、ここで言うの? もっとこう、もうすこし暗くなってからというか、ムードというか……ただの道だよ!?」
なぜか視線が合わない。
なにやら美羽は、とんでもない勘違いをしているのでは。
「えっと、伝えたいのは僕の秘密についてなんだけど」
「……あー、うん。千晴くんの秘密だよね。わかってた、わかってたよ。そんなのわかってました」
美羽は半ば逆ギレのようなテンションになり、ぷいとこちらに背を向けてしまう。
僕も妙に恥ずかしくなり、二の句が継げなくなった。
信号が青になり、美羽がぜんまいで巻いたロボットのような挙動でぎこちなく歩き出す。ふわふわと髪が揺れる。曲線を描く毛先を眺めながら、僕は美羽に対してどんな感情を抱いているのだろうと自問する。
恩人ではあるけれど、好きだと言い切るほどの自信はない。というよりも、まともな人間関係を築けない僕には、美羽に抱いている感情の名前さえわからなかった。
「……で、話って?」
ようやく平静を取り戻したであろう美羽が、静かに問いかけてくる。僕はすこしだけ間を置いて、明日の天気の話をするみたいに自然体を装って言う。
「僕は皇踏山にある鳥居をくぐって、五十年後の未来から来たんだ」
青信号が点滅する。
横断歩道を渡りきった美羽が振り返る。
「……鳥居って、あの、願いを叶えてくれるやつだよね?」
太陽の光を吸い込んだせいか、琥珀色の瞳はいつもより煌めいて見えた。
「高松に来たのは初めて?」
僕の事情を知る由もない美羽は、初めて訪れる町に興奮していると解釈したらしい。
「……久しぶり、かな」
僕は当たり障りのない返答を口にする。
けれど、こうして隠し続けるのは限界がある。
「やっぱり千晴くんって謎めいてるよね。どこに住んでたか全然わかんないし」
案の定、美羽は呆れたように笑った。口調こそ柔らかい。でも、内心では不信感を募らせているのだろう。もう二週間近く一緒にいるのに、僕はまだ一番大事なことを伝えていないのだから。心臓を掴まれたような痛みが、胸の奥にじんわりと広がった。
今すぐにでも、秘密を打ち明けたい。
「ねえ、美羽」
呼び止めると、美羽は振り返って首を傾げた。
白いワンピースの裾が花のように広がり、やがて萎んでいく。
「話があるんだ」
「それって、真面目なやつ?」
「かなりね。冗談だと思われるかもしれないけど」
信号が赤になり、僕たちは立ち止まる。
目の前の車道をセダンや軽トラックが行き交い、轟音を響かせていく。
意を決し、唇を開く。
「実は僕」
「――ま、待って」
が、止められる。
美羽はこちらに手のひらを向け、大袈裟なくらい深呼吸を繰り返す。
「ここ、ここで言うの? もっとこう、もうすこし暗くなってからというか、ムードというか……ただの道だよ!?」
なぜか視線が合わない。
なにやら美羽は、とんでもない勘違いをしているのでは。
「えっと、伝えたいのは僕の秘密についてなんだけど」
「……あー、うん。千晴くんの秘密だよね。わかってた、わかってたよ。そんなのわかってました」
美羽は半ば逆ギレのようなテンションになり、ぷいとこちらに背を向けてしまう。
僕も妙に恥ずかしくなり、二の句が継げなくなった。
信号が青になり、美羽がぜんまいで巻いたロボットのような挙動でぎこちなく歩き出す。ふわふわと髪が揺れる。曲線を描く毛先を眺めながら、僕は美羽に対してどんな感情を抱いているのだろうと自問する。
恩人ではあるけれど、好きだと言い切るほどの自信はない。というよりも、まともな人間関係を築けない僕には、美羽に抱いている感情の名前さえわからなかった。
「……で、話って?」
ようやく平静を取り戻したであろう美羽が、静かに問いかけてくる。僕はすこしだけ間を置いて、明日の天気の話をするみたいに自然体を装って言う。
「僕は皇踏山にある鳥居をくぐって、五十年後の未来から来たんだ」
青信号が点滅する。
横断歩道を渡りきった美羽が振り返る。
「……鳥居って、あの、願いを叶えてくれるやつだよね?」
太陽の光を吸い込んだせいか、琥珀色の瞳はいつもより煌めいて見えた。