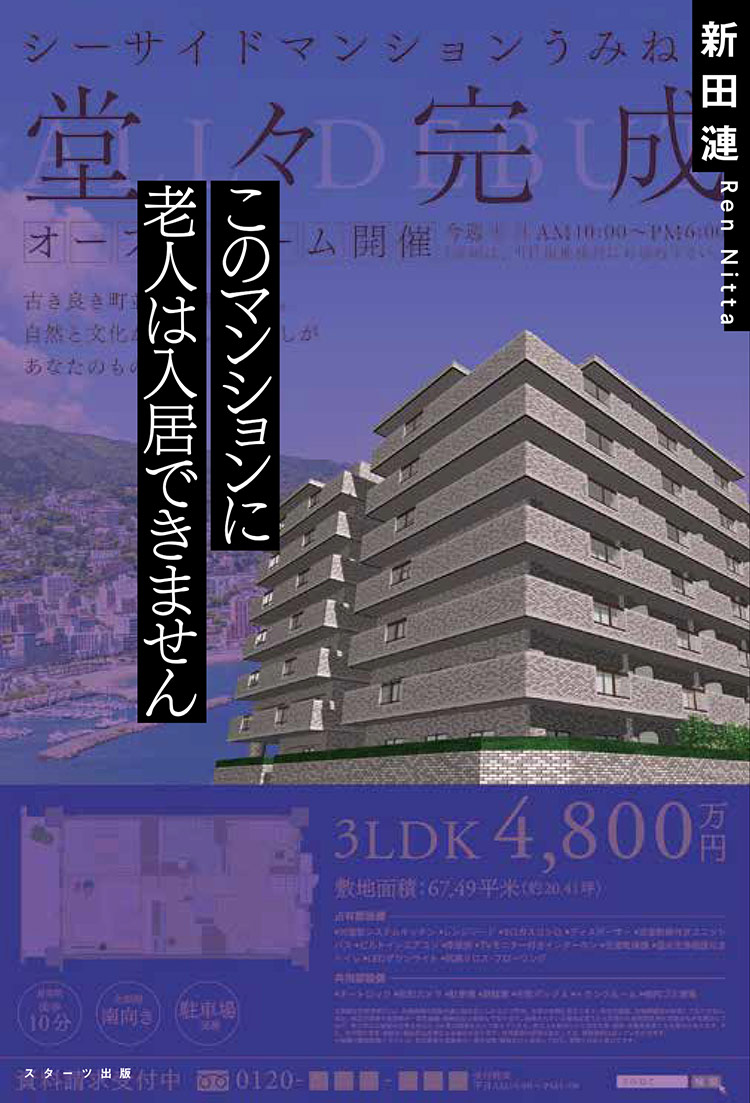翌朝目覚めると、鎖から解き放たれたように身体が軽かった。窓から差し込む朝日に目を細めながら、久しぶりの爽快感を全身で味わう。岬を失ってから半年間、うなされては夜中に起きてしまう日々が続いていた。けれど、今日は夢さえも覚えていない。
待ち合わせの時間までは余裕があった。ゆっくりと身支度を整えても時間が余るだろう。スクールバックの中からスマホを取り出し、画像フォルダを見返すことにした。
未来から来たと信じてもらうには、写真を見せるのが効果的だろう。
秘密を打ち明ける。
そう考えただけで緊張した。排他的な生活を送ってきた僕にとって、かなり踏み込んだコミュニケーションだ。そのうえ、岬の件と違って僕から話を切り出さなくちゃいけないのだから。
何度も深呼吸して、気持ちを落ち着かせる。
そうしていると、さっきは気がつかなかった違和感に思い当たる。
「……ペットボトルのゴミって、どこかに捨てたっけ」
元の時代で飲んでいたコーラは、スクールバックに突っ込んだままだった。そのまま捨てるタイミングを見失っていたので、突然なくなるわけがなかった。
なくなって困るものでもないけれど、妙に気になってしまう。この部屋は鍵がないので、襖を開けば誰でも簡単に入れる。とはいえ他の荷物を物色された形跡がないし、そもそもゴミなんて盗んでも意味がないだろう。
まあいいか。
そう割り切って、フリップ時計を見る。
いつの間にか、集合時間の六時半を表示していた。赤上荘を出て母屋の前へ向かうと、美羽がちょうど玄関から出てくるところだった。
「あ、おはよう」
美羽は格子模様の白いワンピースに、赤いパンプスを合わせている。以前見たときよりも違和感がなく、むしろ可愛いと思ってしまうのは、僕がこの時代の服装に慣れてきたからなのかもしれない。
「じゃ、港に向かうよっ」
美羽は僕を先導するように歩く。いつもよりカールの強い髪が揺れ、潮風が吹くたびに整髪料の香りがした。女子のお洒落は褒めるべきだと岬との生活で学んでいる。けれど、岬を褒めるのとは訳が違うので、うまく言葉が出てこなかった。
「今日の髪型、いいね」
だから端的に、気持ち悪さが滲み出ないように、さりげなく伝えてみる。
すると美羽は足を止め、目尻に笑みを湛えながら振り向いた。
「ホント? よかった。今日は朝からセット頑張ったからね」
美羽は鼻歌交じりに歩き出す。僕は寝癖を抑えただけなので、なんだか申し訳なくなる。服だって、保さんから借りっぱなしのチノパンと黒いポロシャツだ。もっと身嗜みを整えればよかった。
「そういえば千晴くんって、いつも珍しい靴を履いてるよね」
「そうかな。普通にアディダスだよ」
「普段着に合わせるのってかなり新しいよ。サッカーしてたの?」
美羽の質問で、この時代のアディダスはスポーツ用品のイメージしかないのだと気づく。僕は「まあ、ちょっとだけ」と曖昧な返事で誤魔化し、服よりも先に靴を買おうと心に決めた。
高松に行くには、まず池田港まで路線バスで向かう必要があるらしい。
元の時代では土庄港から高松に行っていたので、反対側のバスに乗り込むのはなんだか妙に落ち着かなかった。池田港に降り立つと、すでにフェリーの利用客らしき人たちがたむろしていた。高松へは『こくさい丸』で約六十分。所要時間は元の時代とあまり変わらないみたいだ。
僕たちはチケットを購入し、待合室のベンチでフェリーの到着を待った。潮風が吹き抜ける立地だからか、バスの中よりも涼しかった。
「向こうに着いたら喫茶店で朝ごはん食べよっか」
「そうだね。久しぶりにパンも食べたいし」
「もしかして、千晴くんの家はパン派だったの?」
「基本はトーストだったかな。各々が自分で焼けば済むし」
「へえ、お洒落だねえ」
もっとも、岬がいた頃は朝食が用意されていたし、家族揃って食卓を囲んでいた。
岬の死は、家族の心も生活リズムもバラバラにしてしまったのだ。
重くなった気分を切り替えるため海を眺めていると、前方の座席でちいさな影が動いた気がした。窓から日差しが差し込んでいるはずなのに、ちいさな影の周りだけがトンネルの中に入ったみたいに暗かった。
岬だ。
そう気づいた瞬間、ちいさな影はくるりとこちらを向いた。顔はまっくろで、表情は窺えない。けれど、僕をじっと見ていることは理解できる。
「岬ちゃんのこと、思い出してる?」
ふと、美羽の声が届いた。
僕は息を押し出すようにして、質問する。
「もしかして、美羽にも見えるの?」
だとすれば、岬の影は幻影なんかじゃない。
しかし美羽は、ぽかんとした顔で僕を眺めるばかりだった。
「え、なにが? ただ、千晴くんの眉間がみゅっとしてただけだよ。千晴くんって、考え事してるとき顔に出るタイプだもん」
よくわからない擬音で解説される。僕は表情が変わらないタイプだと思っていただけに、わりと衝撃的な事実だった。
「えっと。あそこに……」
慌てて指差すと、いつの間にかちいさな影は消えていた。
やがてフェリーの汽笛が轟いて、従業員がメガホンで乗車案内を呼びかけた。
「いや、なんでもない」
僕は首を横に振り、美羽と一緒にフェリー乗り場へと向かう。
きっと、岬は僕を恨んでいる。
数日前までは、そんな強迫観念に駆られていた。けれど美羽に秘密を打ち明けてから、自分のなかで考えが変わりつつあった。そもそも岬は、僕を恨むような性格じゃないはずだ。いや、もし僕を恨んでいたとしても、その視線から逃げてはいけない。
岬はきっと、僕になにかを伝えようとしている気がするから。
僕はすこしだけ顔を上げ、タラップを渡った。
船内は僕が利用していたフェリーとさほど変わらない。黄緑色のシートが等間隔で並んでおり、窓辺の席からは瀬戸内海が一望できる。美羽が慣れた様子で二人掛けの席に陣取ったので、僕も隣に座る。
「高松に行くときはいつもこの席なんだよね」
「そんなに頻繁に乗るんだ」
「ちょっと前まではね」
美羽はそう言って、窓のほうを見やる。
出航の合図とともに、ゆっくりと波が切り裂かれていく。やがて白いしぶきが細かく舞い、とぎれとぎれの線を描いていく。どこか名残惜しそうに消える波を、美羽はいつまでも眺めていた。
待ち合わせの時間までは余裕があった。ゆっくりと身支度を整えても時間が余るだろう。スクールバックの中からスマホを取り出し、画像フォルダを見返すことにした。
未来から来たと信じてもらうには、写真を見せるのが効果的だろう。
秘密を打ち明ける。
そう考えただけで緊張した。排他的な生活を送ってきた僕にとって、かなり踏み込んだコミュニケーションだ。そのうえ、岬の件と違って僕から話を切り出さなくちゃいけないのだから。
何度も深呼吸して、気持ちを落ち着かせる。
そうしていると、さっきは気がつかなかった違和感に思い当たる。
「……ペットボトルのゴミって、どこかに捨てたっけ」
元の時代で飲んでいたコーラは、スクールバックに突っ込んだままだった。そのまま捨てるタイミングを見失っていたので、突然なくなるわけがなかった。
なくなって困るものでもないけれど、妙に気になってしまう。この部屋は鍵がないので、襖を開けば誰でも簡単に入れる。とはいえ他の荷物を物色された形跡がないし、そもそもゴミなんて盗んでも意味がないだろう。
まあいいか。
そう割り切って、フリップ時計を見る。
いつの間にか、集合時間の六時半を表示していた。赤上荘を出て母屋の前へ向かうと、美羽がちょうど玄関から出てくるところだった。
「あ、おはよう」
美羽は格子模様の白いワンピースに、赤いパンプスを合わせている。以前見たときよりも違和感がなく、むしろ可愛いと思ってしまうのは、僕がこの時代の服装に慣れてきたからなのかもしれない。
「じゃ、港に向かうよっ」
美羽は僕を先導するように歩く。いつもよりカールの強い髪が揺れ、潮風が吹くたびに整髪料の香りがした。女子のお洒落は褒めるべきだと岬との生活で学んでいる。けれど、岬を褒めるのとは訳が違うので、うまく言葉が出てこなかった。
「今日の髪型、いいね」
だから端的に、気持ち悪さが滲み出ないように、さりげなく伝えてみる。
すると美羽は足を止め、目尻に笑みを湛えながら振り向いた。
「ホント? よかった。今日は朝からセット頑張ったからね」
美羽は鼻歌交じりに歩き出す。僕は寝癖を抑えただけなので、なんだか申し訳なくなる。服だって、保さんから借りっぱなしのチノパンと黒いポロシャツだ。もっと身嗜みを整えればよかった。
「そういえば千晴くんって、いつも珍しい靴を履いてるよね」
「そうかな。普通にアディダスだよ」
「普段着に合わせるのってかなり新しいよ。サッカーしてたの?」
美羽の質問で、この時代のアディダスはスポーツ用品のイメージしかないのだと気づく。僕は「まあ、ちょっとだけ」と曖昧な返事で誤魔化し、服よりも先に靴を買おうと心に決めた。
高松に行くには、まず池田港まで路線バスで向かう必要があるらしい。
元の時代では土庄港から高松に行っていたので、反対側のバスに乗り込むのはなんだか妙に落ち着かなかった。池田港に降り立つと、すでにフェリーの利用客らしき人たちがたむろしていた。高松へは『こくさい丸』で約六十分。所要時間は元の時代とあまり変わらないみたいだ。
僕たちはチケットを購入し、待合室のベンチでフェリーの到着を待った。潮風が吹き抜ける立地だからか、バスの中よりも涼しかった。
「向こうに着いたら喫茶店で朝ごはん食べよっか」
「そうだね。久しぶりにパンも食べたいし」
「もしかして、千晴くんの家はパン派だったの?」
「基本はトーストだったかな。各々が自分で焼けば済むし」
「へえ、お洒落だねえ」
もっとも、岬がいた頃は朝食が用意されていたし、家族揃って食卓を囲んでいた。
岬の死は、家族の心も生活リズムもバラバラにしてしまったのだ。
重くなった気分を切り替えるため海を眺めていると、前方の座席でちいさな影が動いた気がした。窓から日差しが差し込んでいるはずなのに、ちいさな影の周りだけがトンネルの中に入ったみたいに暗かった。
岬だ。
そう気づいた瞬間、ちいさな影はくるりとこちらを向いた。顔はまっくろで、表情は窺えない。けれど、僕をじっと見ていることは理解できる。
「岬ちゃんのこと、思い出してる?」
ふと、美羽の声が届いた。
僕は息を押し出すようにして、質問する。
「もしかして、美羽にも見えるの?」
だとすれば、岬の影は幻影なんかじゃない。
しかし美羽は、ぽかんとした顔で僕を眺めるばかりだった。
「え、なにが? ただ、千晴くんの眉間がみゅっとしてただけだよ。千晴くんって、考え事してるとき顔に出るタイプだもん」
よくわからない擬音で解説される。僕は表情が変わらないタイプだと思っていただけに、わりと衝撃的な事実だった。
「えっと。あそこに……」
慌てて指差すと、いつの間にかちいさな影は消えていた。
やがてフェリーの汽笛が轟いて、従業員がメガホンで乗車案内を呼びかけた。
「いや、なんでもない」
僕は首を横に振り、美羽と一緒にフェリー乗り場へと向かう。
きっと、岬は僕を恨んでいる。
数日前までは、そんな強迫観念に駆られていた。けれど美羽に秘密を打ち明けてから、自分のなかで考えが変わりつつあった。そもそも岬は、僕を恨むような性格じゃないはずだ。いや、もし僕を恨んでいたとしても、その視線から逃げてはいけない。
岬はきっと、僕になにかを伝えようとしている気がするから。
僕はすこしだけ顔を上げ、タラップを渡った。
船内は僕が利用していたフェリーとさほど変わらない。黄緑色のシートが等間隔で並んでおり、窓辺の席からは瀬戸内海が一望できる。美羽が慣れた様子で二人掛けの席に陣取ったので、僕も隣に座る。
「高松に行くときはいつもこの席なんだよね」
「そんなに頻繁に乗るんだ」
「ちょっと前まではね」
美羽はそう言って、窓のほうを見やる。
出航の合図とともに、ゆっくりと波が切り裂かれていく。やがて白いしぶきが細かく舞い、とぎれとぎれの線を描いていく。どこか名残惜しそうに消える波を、美羽はいつまでも眺めていた。