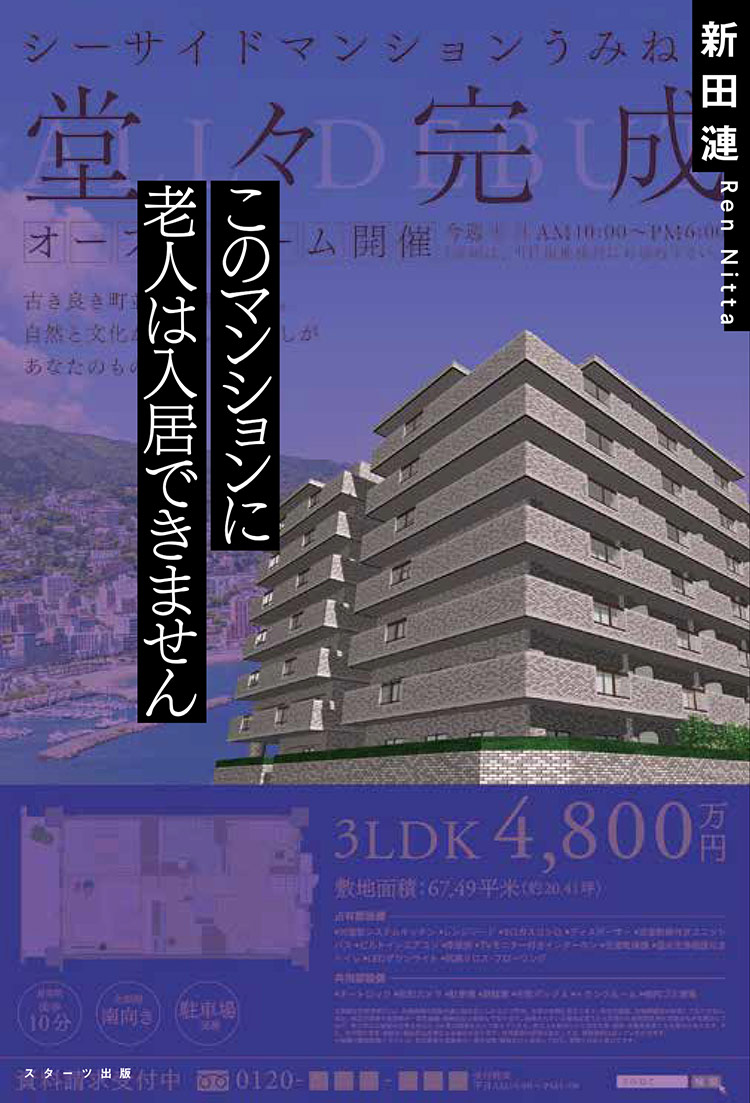美羽もなにかしらの秘密を抱えているのかもしれない。
そんな疑問を心の奥底で抱きつつも、僕はいつもと変わらない生活を続けていた。
人は誰しもが秘密を抱えているし、安易に踏み込むものではない。保さんの口ぶりから察するに、そのときが訪れたら美羽のほうから打ち明けてくれるだろう。
そう結論づけて毎日働いていると、いつの間にか七月が終わり、八月一日になっていた。
まばらだった蝉の鳴き声は大合唱に変わり、太陽から降り注ぐ日差しも容赦なく肌を突き刺してくる。涼しい気候に慣れてしまったせいか、真夏日の気温をほんのすこし超えただけでも気だるさを覚えてしまう。それでも母屋の裏手に出て、潮風を浴びると心は落ち着く。ハマボウが咲く海岸線は、見渡す限りどこまでも夏だった。
「千晴くん、明日から三日間休んでいいわよ。美羽も今のうちに休んじゃいなさい」
そんなタイミングで、恵子さんから突然の休暇を言い渡された。いつもように、美羽と母屋で昼食を摂っている最中だった。
正直、疲れが溜まっていたので休めるのはありがたい。けれど、赤上荘は夏休みに入ってから連日大盛況だ。
そんな状況下でのんびり休むのは、さすがに申し訳なかった。
「忙しい時期なのに、大丈夫なんですか」
「うん、大丈夫よ」
恵子さんは僕の疑問を相槌で受け止めつつ、口の端を吊り上げて不敵な笑みを浮かべた。ただならぬ気配を察し、僕は隣に座る美羽のほうを見やる。
すると、さすが母娘というべき瓜ふたつの表情で美羽もにたりと笑っていた。
「千晴くん。あのね、今のうちに休んでおかないと、きっと、死んじゃうよ」
それぞれの文節を強調するように、美羽は力強く僕に言う。
「なんだか不穏だ」
「だって千晴くんは、お盆の忙しさをまだ知らないでしょ――」
美羽はそう前置きし、小豆島のお盆休みがいかに忙しいかを説明してくれた。
これまでは観光客が大半だったが、今度は帰省客も島に大挙する。その光景を見ていると「フェリーから人が溢れてしまうのでは」と不安になるらしい。当然ながら港付近は大渋滞。乗用車に観光バス、さらには送迎用のワンボックスといった車が狭い道路で混ざり合い、排気ガスで島全体が黒に染まるという。
「……さすがに冗談だよね?」
「どうでしょうねえ。でも、そう思っちゃうくらい忙しいから覚悟してね」
神妙な面持ちで美羽はそう言って、味噌汁をゆっくりと飲み干した。
果たして僕に乗り切れるだろうかと不安になっていると、美羽は「それよりさ」と話題を転換し、ぱっと明るい表情になった。
「せっかくのお休みだし遊びに出かけようよ。高松とか!」
麦茶を飲みながら考える。
僕はインドア派なので、休みは寝ていたい。でも、五十年前の高松市内がどんな景色だったのかはとても気になる。きっと貴重な体験になるだろう。
「……そうだね、遊ぼっか。今日のうちになにか用意しておくものはある?」
「遊ぶ金とか」
「犯行動機でしか聞かないような表現だ」
ツッコミを入れつつ、そういえば手持ちのお金がないことを思い出す。さすがに美羽から借りるのは気が引けるなと考えていると、恵子さんが茶封筒をこちらに手渡してくれた。
「はいこれ、千晴くんのお給料。あんまり多くは渡せないけれど、これで美羽と遊んできてあげて」
アルバイトをしたことがない僕にとって、初めての給料だった。金額がいくらであろうと、ずっしりとした重みを感じる。僕は恵子さんに深々と頭を下げ「今月もよろしくお願いします」と告げる。ここにいる限りは期待に応えたかった。
「よかったね。これで千晴くんも一人前の男の子だよ。いいなあ、いいなあ」
いつの間にか美羽が僕の隣にいて、茶封筒を凝視していた。なんだか妙な圧を感じる。美羽は「なんだか申し訳ない」という理由で給料を受け取っていないので、やはり懐事情が寂しいのかもしない。
「……なにかプレゼントしようか?」
「え、いいの⁉」
「うん。僕はあまり欲しいものもないから。なにか欲しいものがあるの?」
そう尋ねると、美羽のテンションが一気に上昇する。
「そりゃあもう、たっくさんあるよ。ポックリ靴とか欲しいなあ」
なにその靴、という疑問が口から飛び出そうになったので慌てて飲み込んだ。可愛い語感だけに外見が想像できなかった。
「でも、千晴くんがプレゼントしてくれるならなんでも嬉しいよ。楽しみにしてるね」
美羽はそう言い残し、ぱたぱたと居間を後にする。
「あ、そうだ」
かと思いきや、廊下から顔だけを出した。
「明日は早起きするから、夜更かしはダメだよ」
「わかった」
僕が頷くと、美羽は満面の笑みを浮かべて去っていく。等間隔の足音からは上機嫌な様子が伝わってきた。
「本当に仲良しね」
「そう、ですね。ありがたいです」
僕は素直にそう言いつつ、美羽にはあまり友達がいないという事実を飲み込めずにいた。あれだけ人当たりがよく、明るい性格なのに。
たとえばなにか、周囲から避けられる理由があるのだろうか。
保さんから言われたように、僕は美羽をあまり知らない。まずはこの時代に慣れるのが先決だと、どこか自分に言い訳していたからだ。
すっと立ち上がり、背筋を伸ばす。
美羽は僕の境遇に共感して、涙を流してくれた。
だからこそ、美羽の視線にこれ以上痛みを覚えたくない。
この休日を機に秘密を打ち明けて、美羽の心に踏み込んでみよう。
そんな疑問を心の奥底で抱きつつも、僕はいつもと変わらない生活を続けていた。
人は誰しもが秘密を抱えているし、安易に踏み込むものではない。保さんの口ぶりから察するに、そのときが訪れたら美羽のほうから打ち明けてくれるだろう。
そう結論づけて毎日働いていると、いつの間にか七月が終わり、八月一日になっていた。
まばらだった蝉の鳴き声は大合唱に変わり、太陽から降り注ぐ日差しも容赦なく肌を突き刺してくる。涼しい気候に慣れてしまったせいか、真夏日の気温をほんのすこし超えただけでも気だるさを覚えてしまう。それでも母屋の裏手に出て、潮風を浴びると心は落ち着く。ハマボウが咲く海岸線は、見渡す限りどこまでも夏だった。
「千晴くん、明日から三日間休んでいいわよ。美羽も今のうちに休んじゃいなさい」
そんなタイミングで、恵子さんから突然の休暇を言い渡された。いつもように、美羽と母屋で昼食を摂っている最中だった。
正直、疲れが溜まっていたので休めるのはありがたい。けれど、赤上荘は夏休みに入ってから連日大盛況だ。
そんな状況下でのんびり休むのは、さすがに申し訳なかった。
「忙しい時期なのに、大丈夫なんですか」
「うん、大丈夫よ」
恵子さんは僕の疑問を相槌で受け止めつつ、口の端を吊り上げて不敵な笑みを浮かべた。ただならぬ気配を察し、僕は隣に座る美羽のほうを見やる。
すると、さすが母娘というべき瓜ふたつの表情で美羽もにたりと笑っていた。
「千晴くん。あのね、今のうちに休んでおかないと、きっと、死んじゃうよ」
それぞれの文節を強調するように、美羽は力強く僕に言う。
「なんだか不穏だ」
「だって千晴くんは、お盆の忙しさをまだ知らないでしょ――」
美羽はそう前置きし、小豆島のお盆休みがいかに忙しいかを説明してくれた。
これまでは観光客が大半だったが、今度は帰省客も島に大挙する。その光景を見ていると「フェリーから人が溢れてしまうのでは」と不安になるらしい。当然ながら港付近は大渋滞。乗用車に観光バス、さらには送迎用のワンボックスといった車が狭い道路で混ざり合い、排気ガスで島全体が黒に染まるという。
「……さすがに冗談だよね?」
「どうでしょうねえ。でも、そう思っちゃうくらい忙しいから覚悟してね」
神妙な面持ちで美羽はそう言って、味噌汁をゆっくりと飲み干した。
果たして僕に乗り切れるだろうかと不安になっていると、美羽は「それよりさ」と話題を転換し、ぱっと明るい表情になった。
「せっかくのお休みだし遊びに出かけようよ。高松とか!」
麦茶を飲みながら考える。
僕はインドア派なので、休みは寝ていたい。でも、五十年前の高松市内がどんな景色だったのかはとても気になる。きっと貴重な体験になるだろう。
「……そうだね、遊ぼっか。今日のうちになにか用意しておくものはある?」
「遊ぶ金とか」
「犯行動機でしか聞かないような表現だ」
ツッコミを入れつつ、そういえば手持ちのお金がないことを思い出す。さすがに美羽から借りるのは気が引けるなと考えていると、恵子さんが茶封筒をこちらに手渡してくれた。
「はいこれ、千晴くんのお給料。あんまり多くは渡せないけれど、これで美羽と遊んできてあげて」
アルバイトをしたことがない僕にとって、初めての給料だった。金額がいくらであろうと、ずっしりとした重みを感じる。僕は恵子さんに深々と頭を下げ「今月もよろしくお願いします」と告げる。ここにいる限りは期待に応えたかった。
「よかったね。これで千晴くんも一人前の男の子だよ。いいなあ、いいなあ」
いつの間にか美羽が僕の隣にいて、茶封筒を凝視していた。なんだか妙な圧を感じる。美羽は「なんだか申し訳ない」という理由で給料を受け取っていないので、やはり懐事情が寂しいのかもしない。
「……なにかプレゼントしようか?」
「え、いいの⁉」
「うん。僕はあまり欲しいものもないから。なにか欲しいものがあるの?」
そう尋ねると、美羽のテンションが一気に上昇する。
「そりゃあもう、たっくさんあるよ。ポックリ靴とか欲しいなあ」
なにその靴、という疑問が口から飛び出そうになったので慌てて飲み込んだ。可愛い語感だけに外見が想像できなかった。
「でも、千晴くんがプレゼントしてくれるならなんでも嬉しいよ。楽しみにしてるね」
美羽はそう言い残し、ぱたぱたと居間を後にする。
「あ、そうだ」
かと思いきや、廊下から顔だけを出した。
「明日は早起きするから、夜更かしはダメだよ」
「わかった」
僕が頷くと、美羽は満面の笑みを浮かべて去っていく。等間隔の足音からは上機嫌な様子が伝わってきた。
「本当に仲良しね」
「そう、ですね。ありがたいです」
僕は素直にそう言いつつ、美羽にはあまり友達がいないという事実を飲み込めずにいた。あれだけ人当たりがよく、明るい性格なのに。
たとえばなにか、周囲から避けられる理由があるのだろうか。
保さんから言われたように、僕は美羽をあまり知らない。まずはこの時代に慣れるのが先決だと、どこか自分に言い訳していたからだ。
すっと立ち上がり、背筋を伸ばす。
美羽は僕の境遇に共感して、涙を流してくれた。
だからこそ、美羽の視線にこれ以上痛みを覚えたくない。
この休日を機に秘密を打ち明けて、美羽の心に踏み込んでみよう。