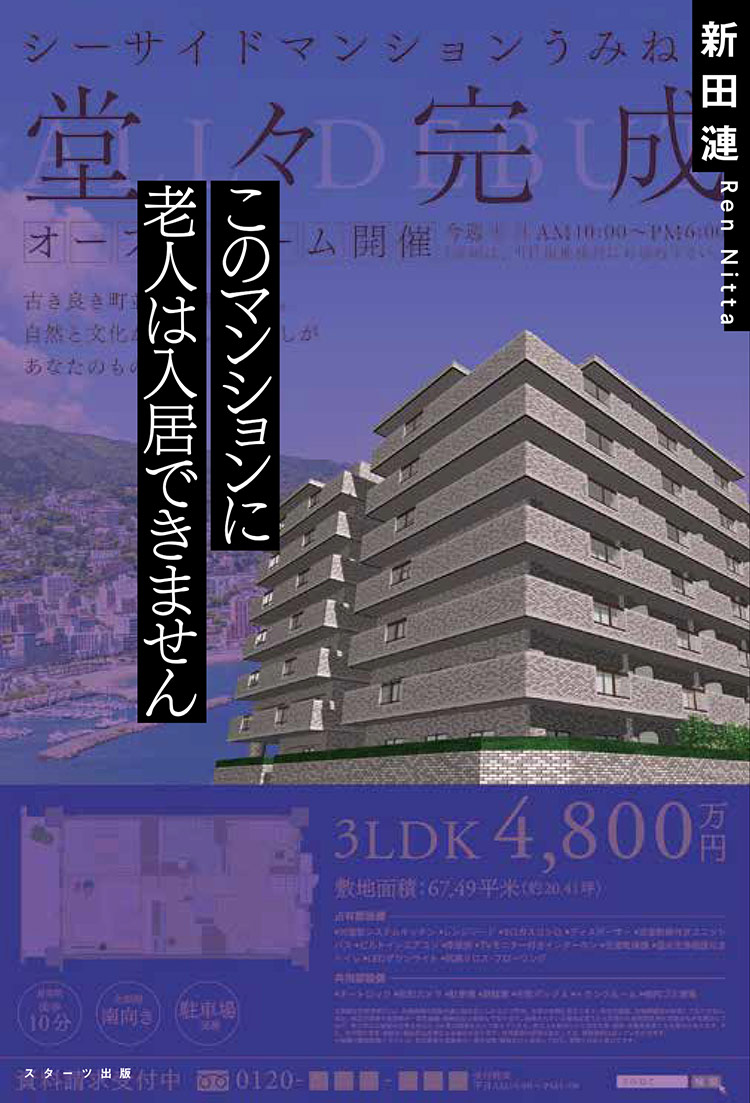大浴場の湯船に浸かりながら、お昼の出来事を回顧する。
岬の件で美羽が僕よりも泣くのは予想外だった。見ず知らずの僕を助けてくれた優しい女の子とはいえ、あそこまで感情移入できるものだろうか。もちろん、純粋にありがたい。だからこそ、真実を伝えきれないことに対して罪悪感を募らせてしまう。
いっそ、美羽にだけ伝えてみようか。
スマホを見せれば信じてもらえるだろう。ネットに繋がらないとはいえ、この時代の人を驚かせるには十分すぎる代物だ。
ただそれは、少なからずリスクを孕む。僕が正体を明かすことで、未来が変わってしまう可能性は否めない。いわゆるバタフライエフェクトというやつだ。
「まあ、僕がここにいる時点で影響は生まれてるはずだよな……」
湯船に肩まで沈み、大きく息を吐く。
わからないことが多すぎて、考えても仕方ない気もする。
うんうん唸っていると、大浴場の扉がゆっくりと開いた。
湯気を切り裂くようにして現れたのは、保さんだった。
「お疲れ様です。お先に失礼してます」
僕が挨拶すると、保さんは「ゆっくりしてていいよ」と鷹揚に頷いた。筋骨隆々な体躯は、宿の主人というより漁師だと説明されたほうが腑に落ちてしまう。保さんは掛け湯をしてから湯船に入り、僕から二メートルほど離れた場所に座る。広がった波紋が、目の前の湯を揺らしていく。
気まずい。
保さんにとっての僕は、娘が連れてきた得体の知れない男でしかない。業務上の話はするけれど、こうしたプライベートな空間じゃ共通の話題が見つからない。とはいえ、すぐに立ち去るのも逆に失礼だし、この沈黙に耐えるしかなさそうだ。
「ありがとうね」
そんな覚悟を決めた矢先、保さんから不意に感謝の言葉が届いた。思い当たる節がなかったので、僕は小首を傾げてしまう。
「えっと、なにかしましたっけ」
「美羽と仲良くしてくれて、ありがとう」
なるほど。そういうことか。
「どちらかといえば、僕が仲良くしてもらってる側ですよ。美羽……さんには、感謝してもしきれないです。友人も多いはずなのに、いつも気にかけてくれますから」
もしこの時代に来て最初に出会ったのが美羽じゃなければ、僕は生き延びていないかもしれない。嘘偽りなく、彼女には心の底から感謝していた。
「千晴くんは、美羽のことをあまり知らないんだね」
しかし、予想外の言葉が耳に届いた。
「え?」
「美羽って、友達は少ないんだよ。今でも仲がいいのは裕子ちゃんくらいかな」
その事実に、少なからず衝撃を受ける。美羽は人懐っこい性格だから、てっきり友達がたくさんいると思い込んでいた。
「だから美羽にとって、君の存在は大きいんじゃないかな」
美羽から信頼されているのならば、それは嬉しいことだ。
心の奥底が、火が灯ったように温かくなる。
「そうだと、嬉しいですね」
僕が笑顔でそう答えると、保さんは首だけをぎゅるりとこちらに向けてきた。
「もっとも、僕の目が黒いうちは交際なんて認めないけどね」
強い勢いで釘を刺されてしまい、体感温度がみるみる下降していく。
「僕たちはそういう関係じゃないので……」
なにやら話がよくない方向に転がりそうだ。退散しようと腰を上げる。しかし保さんがざばざばと河童のように距離を詰めてきたので、肌が触れ合うほど近くなってしまう。
「交際前はみんなそう言うんだよ。ああ、もし美羽が頬を赤らめて君の話をしちゃったら、僕はどうしたらいいんだろうか。そうなる前に、いっそここで君を沈めてしまえば……」
「えっと、とりあえず落ち着いてください」
「――き、君にお父さんと言われる筋合いはない!」
「まだ呼んでないですから」
混乱する保さんをどうにか宥めてから、僕は逃げるように湯船から脱出する。このままだと本当に沈められてしまいそうだ。娘を想う父親とは、こうも暴走してしまうのだろうか。もし岬が美羽の年齢まで生きていれば、僕の父親もこうなっていたのだろうか。
「千晴くん」
そんなことを考えていると、保さんに呼び止められる。さきほどまでとは打って変わって、真剣な表情だった。僕はゆっくりと振り返り、視線で会話の続きを促す。
「美羽はもう、君にあの話はしてるのかな」
「……あの話?」
声色から察するに、大事な話に違いない。けれど、まったく心当たりがなかった。
僕はすこし逡巡して、静かに首を横に振る。
「いえ、とくになにも」
「そうか、知らないならいいんだ。今日もお疲れ様」
労いの言葉からは、追及をどこか遠ざけたい意図が隠れている気がした。深掘りできる空気じゃなかったので、僕も「お疲れ様です」と返し大浴場を後にする。
「なんだったんだ」
更衣室の隅に置かれた扇風機からは、からからと油切れのような音が鳴り響いていた。
岬の件で美羽が僕よりも泣くのは予想外だった。見ず知らずの僕を助けてくれた優しい女の子とはいえ、あそこまで感情移入できるものだろうか。もちろん、純粋にありがたい。だからこそ、真実を伝えきれないことに対して罪悪感を募らせてしまう。
いっそ、美羽にだけ伝えてみようか。
スマホを見せれば信じてもらえるだろう。ネットに繋がらないとはいえ、この時代の人を驚かせるには十分すぎる代物だ。
ただそれは、少なからずリスクを孕む。僕が正体を明かすことで、未来が変わってしまう可能性は否めない。いわゆるバタフライエフェクトというやつだ。
「まあ、僕がここにいる時点で影響は生まれてるはずだよな……」
湯船に肩まで沈み、大きく息を吐く。
わからないことが多すぎて、考えても仕方ない気もする。
うんうん唸っていると、大浴場の扉がゆっくりと開いた。
湯気を切り裂くようにして現れたのは、保さんだった。
「お疲れ様です。お先に失礼してます」
僕が挨拶すると、保さんは「ゆっくりしてていいよ」と鷹揚に頷いた。筋骨隆々な体躯は、宿の主人というより漁師だと説明されたほうが腑に落ちてしまう。保さんは掛け湯をしてから湯船に入り、僕から二メートルほど離れた場所に座る。広がった波紋が、目の前の湯を揺らしていく。
気まずい。
保さんにとっての僕は、娘が連れてきた得体の知れない男でしかない。業務上の話はするけれど、こうしたプライベートな空間じゃ共通の話題が見つからない。とはいえ、すぐに立ち去るのも逆に失礼だし、この沈黙に耐えるしかなさそうだ。
「ありがとうね」
そんな覚悟を決めた矢先、保さんから不意に感謝の言葉が届いた。思い当たる節がなかったので、僕は小首を傾げてしまう。
「えっと、なにかしましたっけ」
「美羽と仲良くしてくれて、ありがとう」
なるほど。そういうことか。
「どちらかといえば、僕が仲良くしてもらってる側ですよ。美羽……さんには、感謝してもしきれないです。友人も多いはずなのに、いつも気にかけてくれますから」
もしこの時代に来て最初に出会ったのが美羽じゃなければ、僕は生き延びていないかもしれない。嘘偽りなく、彼女には心の底から感謝していた。
「千晴くんは、美羽のことをあまり知らないんだね」
しかし、予想外の言葉が耳に届いた。
「え?」
「美羽って、友達は少ないんだよ。今でも仲がいいのは裕子ちゃんくらいかな」
その事実に、少なからず衝撃を受ける。美羽は人懐っこい性格だから、てっきり友達がたくさんいると思い込んでいた。
「だから美羽にとって、君の存在は大きいんじゃないかな」
美羽から信頼されているのならば、それは嬉しいことだ。
心の奥底が、火が灯ったように温かくなる。
「そうだと、嬉しいですね」
僕が笑顔でそう答えると、保さんは首だけをぎゅるりとこちらに向けてきた。
「もっとも、僕の目が黒いうちは交際なんて認めないけどね」
強い勢いで釘を刺されてしまい、体感温度がみるみる下降していく。
「僕たちはそういう関係じゃないので……」
なにやら話がよくない方向に転がりそうだ。退散しようと腰を上げる。しかし保さんがざばざばと河童のように距離を詰めてきたので、肌が触れ合うほど近くなってしまう。
「交際前はみんなそう言うんだよ。ああ、もし美羽が頬を赤らめて君の話をしちゃったら、僕はどうしたらいいんだろうか。そうなる前に、いっそここで君を沈めてしまえば……」
「えっと、とりあえず落ち着いてください」
「――き、君にお父さんと言われる筋合いはない!」
「まだ呼んでないですから」
混乱する保さんをどうにか宥めてから、僕は逃げるように湯船から脱出する。このままだと本当に沈められてしまいそうだ。娘を想う父親とは、こうも暴走してしまうのだろうか。もし岬が美羽の年齢まで生きていれば、僕の父親もこうなっていたのだろうか。
「千晴くん」
そんなことを考えていると、保さんに呼び止められる。さきほどまでとは打って変わって、真剣な表情だった。僕はゆっくりと振り返り、視線で会話の続きを促す。
「美羽はもう、君にあの話はしてるのかな」
「……あの話?」
声色から察するに、大事な話に違いない。けれど、まったく心当たりがなかった。
僕はすこし逡巡して、静かに首を横に振る。
「いえ、とくになにも」
「そうか、知らないならいいんだ。今日もお疲れ様」
労いの言葉からは、追及をどこか遠ざけたい意図が隠れている気がした。深掘りできる空気じゃなかったので、僕も「お疲れ様です」と返し大浴場を後にする。
「なんだったんだ」
更衣室の隅に置かれた扇風機からは、からからと油切れのような音が鳴り響いていた。