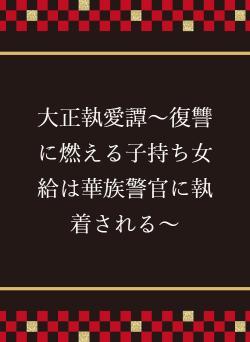体が回復してから、一週間が過ぎた。
まだ朝靄の残る霊獣寮の前庭は、白砂が淡く光り、槙や桜の葉が風にさざめいている。涼やかな空気を胸いっぱいに吸い込みながら、私は門をくぐった。
再びここへ来る日が、こんなに早く訪れるとは思わなかった。
周囲の仲間たちは「無理するな」と笑ってくれたけれど、胸の奥にあったのは別の緊張――宗直様が、どんな顔をされるだろうという不安だった。
女であることが……知られてしまったのだから。打ち明けるつもりなんて、なかったのに。
けれど、姿を見せた途端、宗直様はほんの一瞬だけ目を見開き、すぐに声を落として言った。
「身体、大丈夫か? 無理だけはするなよ」
その低くあたたかな響きが、胸の奥にじんわりと染み込んでいく。
こわばっていた肩が、ふっと緩んだ。白虎が、すぐ傍で尾を揺らしてくれたような気がした。
この日は久しぶりの内裏巡回。宗直様と並んで歩く足取りは、まだ緊張を含みつつも、不思議としっかりしていた。白虎の氣が、そっと背中を押してくれている――そんな感覚があった。
やがて、内裏の奥――後宮へと足を踏み入れる。朱塗りの回廊が連なり、格子窓の向こうには緑濃い庭が広がっている。その景色の中を進むうち、承香殿の前で私たちはふいに立ち止まった。
ぱちりと視線を上げた瞬間、陽の光をまとったように麗しい女性が目に映った。
思わず反射的に頭を下げる。額が膝につきそうなほど深く、顔を伏せた。――顔を上げる勇気は、とてもなかった。
あれは……登花殿女御様では?
私の父・藤原宵家の当主の姉であるその女御様を、一度だけ、宵家の屋敷で遠くから見たことがある。
女御様の背後には、燁子がいた。
変わらず可憐で、絵のように美しい姿。その周囲を、色とりどりの装束をまとった女房たちが、花の列のように取り巻いている。
「……あら、巡回かしら?」
登花殿女御様の声は、透き通るほど澄んでいるのに、頬を撫でる風よりも冷たかった。
「登花殿女御様、浮橋の君にお伝えしたきことがございます」
宗直様が、背筋を正しながら静かに告げる。
「申してみよ」
凛とした声が空気を震わせる。なのに、耳には針のように刺さる響き。
宗直様が、一瞬だけ言葉を探すように黙り、細く息を吐いた。
「……姿を偽っている者がおります」
その言葉に、心臓がどくんと大きく跳ねた。
え……なにを……言って……?
「……私は、嘘をつきたくない」
そう呟くと、宗直様の手が私の髪紐に伸びてきた。
逃げようと足に力を入れたのに、動けない。指先が紐を解く感触が、耳の奥まで届く。
するり――肩先を黒髪が滑り落ちる。
一瞬の沈黙のあと、周囲の空気がざわりと揺れた。
「女……!?」
「まさか女で殿上童とは……!」
女房たちのざわめきが、四方から押し寄せる波のように私を包む。
喉がひゅっと鳴り、呼吸が浅くなる。声も出せないまま、足が床に縫いとめられたみたいに動かない。
「よくぞ教えてくれた。そなた、何者だ。何故その姿で後宮に入り込んだ? その顔を見せてみよ」
女御様の声が、矢のように突き刺さる。
震える指で顔を覆い、ただうつむいた。
「女御様が仰せだ」
宗直様の声が、静かに背後から降りてくる。優しいはずなのに、今は抗えない命令の響きを帯びていた。
私は、ゆっくりと顔を上げた。
視線が一斉に集まり、わずかな衣擦れの音すら鮮やかに耳へと届く。
その気配に、喉の奥で小さく息が詰まった。
「……そのお顔……まさか、姉さま?」
振り向いた燁子の瞳が、大きく見開かれた。朱をさした唇が、わずかに震える。
登花殿女御様の眉が、きゅっと吊り上がる。
「宵家の、側室のか?」
「そうです。まさかこんなところでお会いできるなんて……お姉さま、心配したのですよ」
袖を翻し、燁子がすべるように駆け寄ってくる。香の匂いがふわりと鼻をくすぐり、指先が私の手を柔らかく包み込んだ。涙に濡れたような瞳が、まっすぐこちらを射抜く。
胸の奥が痛んだ。
「ご、ごめんね……」
絞り出すように声を出した瞬間、周囲の空気がざわりと揺れた。
「……霊獣騒乱事件のあと、行方不明になった姉君……?」
「変装していたなんて……」
「女房に化けても潜り込めるでしょう」
女房たちの唇が動くたび、衣擦れの音と囁きが耳に絡みつく。視線が次々と突き刺さり、背中にじっとりと汗が滲む。
「浮橋である燁子の足を引っ張るお荷物……そなたがやったのか?」
鋭い声が飛び、胸の奥がひやりと凍った。
「ち、違います! 私は変装なんてしていません。霊獣騒乱事件は“香”で引き起こされたんです!」
思わず声を張り上げると、燁子がわずかに首を傾け、口元を手で押さえた。指の隙間から、探るような微笑がのぞく。
「香……? お姉さまがお得意の香ですか?」
その声は甘く響くのに、瞳の奥がきらりと光った。
「香が得意だったのか、そなた」
女御様が片眉を上げ、扇の先で私を指し示すように動かす。
「……得意ですが、私じゃありません。それは潤氣を乱す香。私には……そんなもの作れません!」
喉が焼けつくように熱い。足は床に縫いつけられたように動かず、ただ心臓の鼓動だけが耳の奥で、どくん、どくんと響いていた。
「……それは、本当だろうか」
一瞬、空気が固まった。その沈黙を破ったのは、宗直様の低い声だった。
胸の奥がきゅっと縮む。
「宗直様……?」
思わず名を呼ぶと、彼は私から視線を外し、静かに告げた。
「この者は白虎を引き連れております」
ざわめきの中から、女御様の細い吐息が漏れる。
「まあ、白虎を」
「霊獣白虎を従えるとは、潤氣を扱えないとできない。潤氣を乱す香を調合できないなど、考えられぬ」
別の声が私を突き刺す。
「霊獣騒乱事件の折、弘徽殿の女房の局から妙な香が漂っていたそうです」
「殿上童が弘徽殿に目をかけてもらっているらしいし、手引きする女房がいてもおかしくないわ」
視線が四方から絡みつき、肩に重しがかかったように息が苦しい。
「お姉さま、なんてことを……まさか帝まで……」
燁子の声が震え、涙が光る。
「ありえること。帝をも狙うとは、大罪人ね」
その一言が、背骨を冷たくなぞる。
「そんな……私は、そんな香を作っていません!」
声が裏返るほどの勢いで叫んだ。喉が焼け、耳の奥で自分の鼓動がうるさく響く。
そのとき――。
「――ああ、そうだ。この者は潤氣を乱す香を作れない」
凪いだ水面に石を落としたように、場の空気が揺れた。
振り返ると、朱の柱の陰から宮様が歩み出てくる。
「宮様……!」
空気が、ぴたりと止まった。
さっきまで耳を刺していた囁きも、疑いの声も――すべてを押し流すように、静かに、一歩。
回廊の奥から、宮様が現れた。
その歩みは、廊を撫でる風すらひれ伏させるようで、裾がわずかに揺れるたび、空気が澄んでいくのがわかる。
誰もが息を呑み、ざわめきはいつしか、敬意を帯びた沈黙に変わっていた。
「――この者は、今回の事件を探るため、霊獣寮に協力してもらっていた者です」
低く落ち着いた声が、糾弾の空気を断ち切る。
「あなたが……潜り込ませたのか?」
登花殿女御様の声音は抑えられているのに、扇の先から鋭さが滲む。
「はい。ご不安にさせたことは心苦しいのですが……おかげで、ようやく解決の糸口が見えました」
宮様は、私の方へわずかに目をやると、すっと右手を差し出した。
その掌に乗っていたのは、小さな布袋。
練香――。
「これに、見覚えは?」
布袋の口を開くと、ふわりと柔らかな薫りが広がり、春の朝露をまとった花のような甘さが鼻をくすぐった。
胸が一瞬、ざわりと揺れる。私も知っている香り――。
宮様は、その香を手にしたまま、囁くように言う。
「……朝露に濡れた花のように、ふんわりとやさしく薫り立つ……素敵な香りだ」
「それは……わたくしの香ですわ」
燁子が微笑んだ。長い睫毛が影を落とし、その表情はまるで贈り物を喜ぶ姫のようだった。
「そうか。しかし、これは弘徽殿の女房、三条殿から借り受けたものだ」
「……どなたかしら?」
燁子が小首を傾げる。金の簪がかすかに揺れた。
「自分のものだと言ったのに、彼女のことは知らないのか」
宮様の視線が、静かに燁子を射抜く。
「はい。なぜその方が持っているのかも、わたくしにはわかりませんわ」
涼しげな笑みは崩れず、声にも震えはない。
そのとき――宮様の声に、わずかな鋭さが混じった。
場の温度が、またひとつ下がった気がした。
「三条殿は、恋人である源敏行からもらったと言っていた。しかし、彼女が弘徽殿でそれを焚いたことで、霊獣騒乱事件が引き起こされた。三条殿はショックのあまり、実家へ戻られている」
「まあ……お可哀そうに」
燁子が、扇の影からさらりと声を落とした。ひどくあっさりとしたその響きに、背筋がひやりとする。
宮様の瞳が、細く鋭くなる。
「可哀そう、か? これがあなたの香であってもか」
登花殿女御様が、低く問う。
「それの……何の関係があるのか?」
「三条殿は、恋人と会えぬ寂しさを紛らわせるため、源敏行殿が香を纏って出仕した。そのまま、清涼殿に……」
「……まさか、それは――」
扇を握る女御様の指が、かすかに震えた。
「金龍が失踪し、帝が倒れられた原因です」
その一言が落ちた瞬間、空気が凍る。
誰かが息を呑む音がはっきりと聞こえた。登花殿女御様の顔から血の気が引き、ゆっくりと燁子へ視線を向ける。
燁子は、その視線を正面から受けながらも、淡く顔を曇らせるだけだった。
「そんな……驚きですわ……ひどい……」
その声には、涙の重みも熱もなかった。
「では犯人は、源敏行殿か?」
女御様の問いに、宮様は静かに首を横に振る。
「いいえ。違います。霊獣を扱えぬ源敏行殿では、潤氣擾乱香は調合できません。それは三条殿にも同じことが言える。二人とも、実行させられてしまったのです」
胸の奥が、強く脈打つ。
「……だ、誰から……」
自分の声が震えているのがわかった。
宮様の視線が、ゆっくりと宗直様へ向けられる。
「ここにいる、宗直だ」
「宗直様が……!?」
全身の血が一瞬で引く。
「宗直。源敏行殿に香を渡したな?」
「そ、それは……」
宗直様は唇を噛み、目を逸らした。
だが、宮様のまなざしは鋼のように揺るがず、その沈黙さえ許さない気配が廊の空気を張り詰めさせていた。
「そなたが香を作ったとは思えない。どこから手に入れた?」
宮様の声は、氷の縁をなぞるように低く、静かだった。
「……いただいたものです」
宗直様は、肩をわずかに揺らし、視線を畳の目に落とした。
「誰から?」
「……浮橋の君からです」
その瞬間、周囲の女房たちの視線が、燁子へと一斉に集まった。
「いつ、知り合ったのだ?」
「もう……一年以上になります。宮中の巡回中に、偶然……」
言葉を吐くたびに、宗直様の声が細くなっていく。
「なるほど」
宮様の眼差しが、刃のように燁子へと向かう。
「宗直はそう言っているが、あなたは香を渡したのか?」
「渡したことは……ありますわ」
燁子は、扇を傾けて唇を隠し、しっとりとした視線を落とす。
「でも、人にあげてしまうなんて……悲しいですわ」
「しかし、もともと俺への贈り物ではなかったでしょう!」
宗直様の声が一気に熱を帯び、握りしめた拳が膝の上で震えた。
「どうして?」
燁子が小首を傾け、耳飾りがかすかに揺れた。
「あなたが香を俺の手に渡したとき、“あの方がこの香を手に取ってくださったら嬉しいのだけど”とおっしゃったじゃないですか!」
「わたくしの言葉で誤解を招いてしまったのね。ごめんなさい。きっと伝え方が少し拙かったのね」
柔らかな声音。だが、瞳の奥には波ひとつ立たない。
「勘違いって……!」
宗直様は唇を噛みしめ、肩をわずかに震わせる。
「確かに、渡してほしいとは言っていないな。その言葉だと」
宮様が淡々と告げ、間を一拍置く。
「誰に渡す必要があると思ったのだ?」
「……それは……宮様です」
宗直様は俯き、声を絞り出す。
「でも、渡したくなったから。浮橋の君の心は、いつも……宮様に向いているから……」
ふぅ――。
宮様が長く息を吐く。その吐息は静かなのに、廊の空気をさらに冷たく締めつけた。
「では、宵家の二の姫に聞く。潤氣擾乱香を渡したのはあなただ。つまり、所持していたことになる。霊獣を従える姫君がこれを作っても、おかしくはない」
宮様の言葉は、鋼のように冷たく澄んでいた。
燁子は、わずかに肩を震わせ、可憐な頬にほんのりと紅をさす。伏せた睫毛の影が長く落ち、声は頼りなげに震えている。
「お恥ずかしながら……わたくし、香を作るのが苦手で……ごめんなさい。それを作ったのは……お姉さまです。わたくしの香は、いつもお姉さまが作ってくれるんです」
その儚げな言葉の奥で、わずかに口角が動いたように見えたのは――私の気のせいだっただろうか。
「確かに、燁子の香は私が作りました。でも……それは、私じゃありません」
胸の奥がざわりと揺れ、言葉が自然に口を突いた。
「この者ではない」
宮様の声音は揺るぎなく、場の空気をさらに重くする。
「じゃあ……」
燁子はゆっくりと顔を上げ、困ったように宗直様へ視線を向ける。眉尻が柔らかく下がり、その瞳が水をたたえたように揺れた。
「俺じゃありません!」
宗直様は、咄嗟に声を張った。拳を握りしめ、膝の上で震えている。
「じゃあ、誰が作ったというのだ」
登花殿女御様が、扇を少し下げて静かに問う。その扇先から放たれる視線は、鋭い刃のようだった。
宮様は、ゆっくりと歩みを進め、燁子をまっすぐに見据える。
「宵家の二の姫。あなたですよ」
その瞬間、廊に張りつめた空気がさらに凝縮する。女房たちの衣擦れの音すら、やけに大きく響いた。
燁子は、小さく息をのみ、すぐに可憐な首を傾げる。長い黒髪がさらりと肩からこぼれ、唇には控えめな笑み。
「まあ……どういうことでしょう……」
その声音はあくまで柔らかく、困惑を装っている。
「誤魔化しても無駄です。潤氣擾乱香は、霊獣師であっても潤氣の特定は困難。だが、それを見抜ける存在がいる」
心臓が早鐘を打つ。私は息を詰め、宮様を見た。
「そ、それは……」
「――金龍だ」
宮様のその言葉が落ちた瞬間、廊に張りつめた空気がびり、と震えた。
音ではない。雷でも風でもない。もっと深く、底の見えぬ何か――魂の奥を直接叩く衝撃が、私たちを包み込む。
天井のどこかで、ぎしり、と梁が軋むような音がした。張り詰めた空間が、わずかに揺らぎ始める。
白虎が、背後で低く唸った。
その声が私の背骨を這い上がり、熱と震えを同時に残していく。呼吸を忘れた私の背に、あの白い氣配が寄り添った。
胸の奥がざわめき、言葉でも音でもない「何か」が、確かにこちらへ近づいてくる。
ひゅう――。
一陣の風が、宮中を抜けた。
その刹那。
天のひさしが裂けるように、まばゆい金色の光が降り注いだ。雲を裂き、空を貫き、宮中の真上からゆっくりと――まるで天から垂れる帯のように――金の筋が地上へ伸びていく。
そして、その光の中に――姿があった。
――金龍。
息を飲む。
一枚一枚の鱗が宝玉のように輝き、光をはね返すたび、周囲の空間まで金色に染まる。悠々とたなびく尾が、空を泳ぐように揺れ、その存在だけで世界の均衡が変わるようだった。
誰かが小さく「あ……」と息を漏らす。その瞬間を境に、そこにいた全員が瞳を見開き、やがて一人、また一人と膝をついた。衣擦れの音だけが、静まり返った空間に小さく重なっていく。
私も、立っていられなかった。膝が床に触れる音が、やけに大きく耳に響いた。
「神泉苑に足を踏み入れ、我に呼びかけた者よ。そなたであるな?」
耳ではないところで響く聲――。
鼓膜ではない。空気の振動でもない。
魂そのものに、直接触れてくるような聲だった。
懐かしいような、胸が苦しくなるような、それでも泣きたくなるほど温かい響き。
喉が詰まり、声が出ない。私はただ、心の奥で静かに頷いた。
「……はい」
金龍の瞳が、私をまっすぐに射抜く。底知れぬ光の奥に、揺るがぬ意志があった。
「そなたの聲が、我を神泉苑からここへ導いた」
その響きが胸の奥に染み込んだ瞬間、心臓の鼓動がひときわ強く打ち、内側から熱がじわりと広がっていった。
何か言おうと、喉がわずかに動いたその瞬間――。
「この場に集いし者よ、聞け」
金龍の聲が、堂内の空気を震わせた。
耳で聞くというより、胸の奥を直に叩かれたような衝撃。石壁の彫り物すら微かに鳴るような、重く深い響きだった。
誰一人、口を挟むことも、息を呑む音すら立てられない。
「この氣に満ちた香には、蛟の潤氣が用いられている」
ぴしり、と。
目に見えない糸が、場の全員の首筋を縛りつけたように、空気が張り詰めた。
一瞬で、視線が一斉に燁子へと突き刺さる。
そのとき、彼女は――。
ふわり、と長い睫毛が揺れ、潤んだ瞳に一粒の涙を浮かべた。
頬を伝う前に指先でそっと押さえ、その指がわずかに震える。
「わ、わたくしでは……ございません……そんな、ひどいこと……」
その聲は、絹糸のように柔らかく、壊れそうなほど哀れを帯びていた。
見ている者の心を「守らねば」という錯覚に誘い込むような優美さだった。
「それはそなたがわかっているはずだ。――そなたを浮橋にしたいからこそ、真実を告げる」
金龍の聲が、低く鋭く響く。
その一言が、彼女の涙の膜を鋭利に切り裂いたように感じられた。
「は……? 浮橋にしたい?」
登花殿女御様の声は、かすれていた。
紅を引いた唇がわずかに開き、白い喉がひくりと動く。
やがて、彼女は信じられないものを見るように震えながら立ち上がった。
「それでは……燁子が、浮橋ではないと……?」
宮様が一歩、静かに前へ出る。
その足音が、妙に鮮やかに響いた。
「はい。その通りです。私は“導く器”。金龍が現れ、浮橋を選ぶということは――」
女御様の瞳が、ゆっくりと見開かれていく。
その奥で感情が渦を巻き、形を持たぬまま揺れていた。
「……つまり……燁子は偽りの浮橋だったと……そう言うのか」
宮様は短く目を閉じ、そして静かに頷いた。
「偽り、というより……“選ばれていなかった”だけです」
その瞬間。
女御様の手が宙を彷徨い、指先が何も掴めぬまま力を失った。
次の瞬間、衣の裾がふわりと揺れ、体が崩れ落ちる。
「女御様!」
女房たちの声と衣擦れの音が一斉に起こり、慌てて彼女を抱き起こす。
この場にいる誰もが「当たり前」だと信じていたものが。
金龍の一言が、それを静かに、確実に塗り替えていく音だった。
宮中を覆う沈黙の中、金龍の聲が燁子に向かって放たれた。
冷ややかで、透き通る金の鈴の音のような響き――それが胸の奥をひやりと撫で、空気をさらに重くする。
「――問う。そなたは、本当に浮橋となる覚悟があるか」
まるで刃の先を突きつけられるような、逃げ場のない問いだった。
思わず私は、息を呑んで燁子に目を向ける。
薄紅の袖にかけられた指先が、わずかに震えている。
その震えを悟らせぬよう、彼女はひと呼吸置き、ゆっくりと顔を上げた。
涙に濡れた頬を、ためらいもなく白い指でなぞり、雫を払う。
次いで、長い睫毛を伏せて呼吸を整え、そして――すっと瞼を開いた。
「……わたくしは、浮橋になります」
細いけれど芯の通った聲だった。
澄み渡る朝の水面のように冷ややかで、なめらかで、触れることをためらわせる美しさがあった。
そして彼女は、ためらいも迷いもなく言葉を続ける。
「宮様と結ばれるために――それが、わたくしの望みです」
その瞬間、胸の奥が、ぎゅっと音を立てて締めつけられた。
“結ばれる”――たったそれだけの言葉なのに、どうしてこんなにも深く刺さるのだろう。
心臓の鼓動が耳の奥で響き、呼吸が浅くなる。
周囲の女官たちがざわめき、袖口の影で視線を交わす。
誰もがその一言の重さを、噛みしめるように感じ取っているのがわかった。
金龍が長い睫毛のような鱗を静かに閉じ、命を告げるような低い聲を響かせた。
「導く器よ。そなたの心のままに、選べ」
さらに空気が沈んだ。
そのとき――宮様の視線が、一瞬だけ、私を射抜いた気がした。
けれど、それは本当に刹那のこと。
すぐにその目は、燁子へと向けられる。
そして、低く穏やかで、しかし決意の色をはらんだ声が響いた。
「……金龍よ。この者、宵家の二の姫を、浮橋とする」
その言葉とともに、燁子の表情がぱっと華やいだ。
次の瞬間、彼女の周囲に金の潤氣がふわりと舞い始める。
やわらかく、春の嵐の前触れのように――けれど、その美しさは儚くて、息を呑むほどに恐ろしいほど綺麗だった。
薄く金色に光る文様が、燁子の足元からじわりと広がり、絡み合いながら天へと昇っていく。
風ひとつないのに、彼女の袖がゆるやかに舞い上がり、その動きに合わせて光がきらめきを増す。
私は、その光景から目を離せなかった。
――これが、「浮橋」なのだ。
「……浮橋だ……ほんとうに……」
気づけば、唇から小さな声がこぼれていた。
自分でも驚くほど、弱く、頼りない声だった。
燁子の瞳には、金色の光が宿り、満たされたような微笑みが浮かんでいた。
それは、すべてを手に入れた者の顔。
どこか遠い存在のようで――それでも、私のすぐ前にいた。
……そのときだった。
胸の奥に、ざぶん、と波が押し寄せるような熱が走った。
痛みと呼ぶには熱すぎて、けれど言葉にはできない感情が、私を内側から揺らす。
――いやだ。
その聲は、心の奥で小さく、それでもはっきりと鳴った。
宮様と燁子が結ばれる。
ただ、それだけのことが――どうして、こんなにも苦しいのか。
私はずっと、傍観者のふりをしてきた。
妹の背を見つめながら、嫉妬なんて知らないふりをしていた。
でも今、心が叫んでいる。
――それは、いやだ。
白虎が、そっと私の横に身を伏せた。
大きな体から伝わる温もりが、震える私を包み込む。
頬をその毛並みに寄せると、柔らかな感触の奥で、ゆったりとした鼓動が響いていた。
まるで、「わかっているよ」と語りかけてくれるように。
私は唇を噛みしめたまま、光に包まれる燁子を見つめた。
神々しさすら帯びたその姿が、まぶしくて、遠い。
――けれど、その光の外側で。
私の心は、ようやく気づいてしまった。
はっきりと。
……私は、宮様を、好きだったんだ。
声にならない聲が、胸の奥で、ぽつりとこぼれ落ちた。
金龍が燁子を浮橋と認めた瞬間、堂内を覆っていた張りつめた空気が、わずかにほどけかけた。
その安堵の息は――すぐに断ち切られる。
「……金龍よ、お許しください。この場を借りて、もう一つ明らかにすべき真実があります」
宮様の声が、刃のように鋭く響いた。
静かでありながら、冷たく肌をなぞるような響きに、私の背筋がぞわりと粟立つ。
「宮中で起こった霊獣騒乱事件……あれを裏から仕組んだのは、宵家の二の姫でした」
「……あ……」
燁子の長い睫毛が瞬きを忘れたように止まり、その瞳が一瞬だけ大きく見開かれた。
だが、驚きの色はすぐにふっと消え、彼女は視線を落として唇を小さく結ぶ。
袖口の下で、細い指がかすかに握られるのが見えた。
「私と共に行動するため――霊獣が暴れる状況を“演出”した。浮橋としての役割を果たすことを利用し、自らを必要な存在に見せかけるために」
宮様の声は揺らがない。
その冷ややかな響きに、堂内の空気がさらに重く沈んでいく。
燁子は何も返さず、ただ伏し目のまま、長い睫毛の影で表情を隠した。
……燁子……。
胸が痛む。
彼女は、きっと宮様と一緒にいたかっただけ。
それだけのはずだった。
けれど――そのために、どれだけの人が傷つき、霊獣が苦しみ、私も……。
「愚かなる動機だが、確かに“選ばれた素質”ではある。手放すものを手放せば良いだけだ」
金龍の聲が低く響き、どこか哀れみを帯びる。
金色の瞳が、燁子をまっすぐに射抜いた。
「そなたはもう我の浮橋だ」
その瞬間、燁子の顔がふっと綻んだ。
頬に花が咲いたような、純粋な笑み。
まるで、長い間欲しかった宝物をようやく抱きしめた子どものようだった。
「だが、浮橋とは“我が子”となる者。神の器たる資格を得るがゆえ、人の縁は断たねばならぬ」
空気が、一気に凍りつく。
女官たちは互いに顔を見合わせ、小さく息を呑んだ。
燁子は笑みを保ったまま、何の迷いも見せずに答える。
「……はい」
その声音は、澄んでいて、痛いほど真っ直ぐだった。
私は唇を噛み、視線を逸らすことができなかった。
――だが。
金龍の潤氣が、ふたたび燁子を包み込んだ。
それは春先の陽だまりのようにやわらかく、母の胎に還るかのようなぬくもりを帯びていた。
けれど、その甘やかさの奥に、決して抗うことの許されぬ圧が潜んでいる。
肌に触れるその氣に、私は背筋の奥がざわりと軋むのを感じた。
「……あれ……? 宮様……?」
燁子の頬が、わずかに引きつる。
薄紅の唇が形を探すように震え、目が必死に何かを求めて彷徨った。
「宮様……なぜ……手を……取ってくださらないの?」
彼女はゆっくりと腕を伸ばす。
けれど、金色の潤氣が薄い膜のようにその前に立ちはだかり、指先は空を掻くことすらできず、ただ宙で小刻みに震えていた。
「金龍が言ったであろう。人の縁は断たねばならぬ、と」
宮様の声音は、静かで、しかし冷たい刃のように鋭かった。
「まさか……これって……わたくし……結ばれないの?」
その問いは震えていたが、どこか信じたい答えを待つ色があった。
「結ばれる? ありえない。そなたに恋焦がれる気持ちなど、持ち合わせていないのに」
――その瞬間を、私は見た。
燁子の中に、真実という冷たい刃がようやく突き刺さり、形を持って侵入していく瞬間を。
彼女の瞳から、透明な滴がひとすじ、頬を滑り落ちた。
「うそ……うそでしょう……」
潤んだ瞳が揺れる。
唇が必死に言葉を紡ぐが、それは頼りなく震えていた。
「恋心を抱く者は、龍に仕える“浮橋”とはなれぬ。しかし導く器として、浮橋に相応しい素質を持つ者はそなただけだと結論づけた。それゆえ、そなたには恋心を手放してもらう」
「いや……いやよ……わたくしは、宮様と……結ばれたいのに……」
「私がそなたと結ばれることなど、未来永劫ない」
その冷淡な声が、燁子の顔から色を奪い取った。
華やいでいた頬も、艶やかな唇も、一瞬で力を失い、ただ白く乾いていく。
「……こんなの……聞いてない……わたし……浮橋になりたかったのに……あなたのせいよ!」
鋭く突き出された指先が、まっすぐに宗直様を指し示す。
その刹那、承香殿の空気がぴん、と張り詰めた。
宗直様は一歩、後ろに下がり、見開いた瞳のまま言葉を失っていた。
「白虎と一緒にいた、わたくしの邪魔をしたお姉さまを……あなたがちゃんと始末しなかったから!」
――始末。
その言葉が私の耳に届いた瞬間、背筋から氷が滑り落ちるような感覚が走った。
手足が強張り、息が浅くなる。
「“始末”って……」
自分の声が、自分のものではないみたいにかすれていた。
「……宗直、それは事実か?」
宮様の声は、低く鋭く、空気を裂いた。
その瞬間、宗直様の膝が力を失い、畳に崩れ落ちる。
「……はい……在原貞親と共に……白虎といた者を……燁子さまのお気持ちに応えるために……」
かすれた声が、堂内の壁に吸い込まれるように消えた。
女房のひとりが、短く息を呑み、それは悲鳴へと変わった。
「宗直。貞親が鈴音を霊獣で襲い、そなたが意図的に鈴音を池に突き落としたのだな」
宮様の言葉は、刃物のように容赦なかった。
宗直様は、視線を落とし、唇を固く結ぶ。
答えはなかった。
けれど、その沈黙が、すべてを肯定していた。
「そなたの潤氣の強さは真であった。しかし、それは“己のために人を傷つける”潤氣として誤った使い方をした。だが、これからは正しく潤氣が使える」
金龍の聲が、鈍い雷鳴のように胸に響く。
私は喉が固まり、何も言えなかった。
ただ――燁子を見ていた。
「わたくしが、浮橋なのに……どうして……」
燁子の声は糸のように細く震えた。
「嫌、嫌よ……!」
次の瞬間、彼女の背後でどろりと氣が揺らぎ、暗い水底から泡が弾けるみたいに、蛟がぬらりと姿を現した。濡れた黒の鱗が怒りに滲み、紅い瞳が灼けた鉄のようにきらめく。
ぞわりと背筋に悪寒が這い上がり、息を飲んだ。
蛟の目の前で金龍の潤氣が、ふたたび燁子を包み込む。胸の奥まで沁みるような、あたたかいのに抗えない光の胎。
「助けて、蛟!」
燁子の絶叫と同時に、蛟の巨体がどくんと脈動した。鱗が怒りに滲むように光り、風を裂く轟音が承香殿を打ち破る。黒い影が咆哮をあげ、光の檻めがけて突進した。
その姿に心臓が喉までせり上がる。喉がひゅっと狭まって空気しか漏れない。足がすくんで動かなかった。
だって、あれは。
脳裏に明滅する記憶が蘇る。
それはあの初めて宮中に足を踏み入れた夜に、私を襲った黒い影。背中を強打した衝撃で肺から空気が押し出され、喉がきしむ。胸の奥が固く閉ざされて、視界がぐらりと揺れ、足元がどこまでも抜けていくようだった。
あれと、同じだ。
次の瞬間、白い閃光が視界を貫いた。
「白虎……!?」
金龍を守るように間へ飛び込み、爪が閃いて蛟の顎を裂いた。蛟の巨体がよろめき、地を叩きつける音が轟く。地に這いつくばった紅い瞳が苦悶に濁った。
「……あの夜、鈴音を狙った蛟は――二の姫の霊獣だったのか」
宮様の声が鋭く響く。
ああ、やっぱり。胸が冷たく凍りつく。
「……わたしを襲った霊獣は……燁子の、蛟」
震える声は自分のものとは思えなかった。心のどこかでまだ燁子を信じたかったのかもしれない。それは打ち砕かれ足元からがくりと崩れそうになる。
――怯えるな。仇は必ず討つ
胸の奥に音が届いた。
はっと顔を上げると、白虎が振り返って黄金の瞳で私を射抜く。白虎の低い唸り声が胸を震わせ、私は無意識に拳を握り締める。
「……白虎、わたしの力を――あなたに託す」
白虎が頷いたように見えた。それは一瞬のことで再び力強く駆けた。
鋭い爪と牙が閃光となり、蛟の鱗を切り裂く。黒い氣が弾け、轟音が殿を揺らす。蛟の咆哮は怒号から悲鳴へと変わり、白虎によってその巨体は地に叩き伏せられた。
なおももがく蛟へ、追い打ちのように金龍の潤氣が淡く降り注ぐ。金の光が絡みつき、鱗をすり抜け全身を縛る。蛟の動きは次第に鈍り、やがて力なく沈黙した。
「蛟、蛟!」
淡い光はなおも広がり、燁子の身体を、やさしく、けれど抗えない抱擁で包みこむ。肩が小刻みに跳ね、見開かれた瞳が焦点をなくしていく。
「うそ……うそでしょう……」
唇がかすかにふるえ、声にならない息がこぼれた。
「嫌……こんなの……嫌……わたし、あなたと……結ばれたかったのに……」
蛟の紅い瞳がこちらを掠める。怨嗟とも、庇護ともつかぬ色が瞬いて――次の波で、黒い影はさらに遠くへ押しやられた。咆哮が細くほどけ、やがて尾の先から力が抜けてゆく。
光のうちの燁子は、絵巻の一場面のように美しかった。だからこそ、その美しさは絶望の底色をはっきりと帯びていた。胸がきゅっと縮み、喉が熱いのに、涙は出ない。鉛のように重たい苦しみだけが、肺の奥に沈殿する。
「……燁子……」
気づけば白虎が私の側にやってきて、励ますようにすりすりと大きな体を私に寄せる。伝わる潤氣が白虎が「ここにいる」と告げてくる。その潤氣からじわりと温もりが沁みる。
金の繭がゆっくりと閉じる。光の層の向こうで、燁子の輪郭が薄れ、最後に――頬を伝った一筋の涙だけが、細い銀の線となって残った。蛟はなお遠くで低く唸り、しかし踏み固められた金の静けさを破ることはできない。
誰ひとり、動けなかった。声も出せなかった。ただ、朝に溶けていく最後の焔を見送るみたいに、その場に立ち尽くしていた。白虎の体温を受けとめながら、私はゆっくりと息を吐く。
淡い光が、承香殿の柱や床を撫でるように広がり、やがて静かに薄れていく。
残されたのは、どこまでも透きとおった沈黙。誰もがその場に釘づけにされ、動くこともできず、ただ息を呑んで立ち尽くしていた。
蛟の低い唸りも消え、燁子の氣も、もう届かない。
光が引いたあとに残るのは、ただ重たく張り詰めた空気だけ――。
その沈黙を切り裂くように、金龍の聲が、再び深く響き渡った。
「導く器よ。浮橋が現れた今、そなたの務めは終わった。自由となれ」
その言葉を受けて、宮様の背筋がすっと伸びる。
見えない鎖がほどけ落ちるように、空気がふっと変わった。
肩先から何かがふっと剥がれ落ち、長く纏っていた重さが、ようやく解けていく――そんな気配。
思わず、息を呑む。
宮様は、まだ淡く揺れている光の残滓をじっと見つめていた。
その眼差しには、安堵とも、名残惜しさともつかぬ影が宿っている。燁子が立っていた場所を凝視したまま、しばらく動かなかった。
やがて、ゆっくりとその視線がこちらへ移る。
深い湖の底を覗き込むような、揺らぎのない瞳。吸い込まれそうになって、思わず胸が小さく震えた。
「……鈴太。いや、鈴音」
名を呼ばれた瞬間、唇が乾き、無意識に指先に力がこもる。
宮様は、一歩こちらに歩を進めると、低く、静かに口を開いた。
「浮橋は現れた。長き懸念が、ようやく果たされた。……だが、それは私ひとりの力ではない。そなたがいてくれたからこそだ。……感謝する」
「……わ、わたし……?」
自分に向けられた言葉だと理解するまで、少しの間が必要だった。
胸が大きく跳ね上がり、心臓の音が耳の奥で響く。
これまで「いるだけで厄介」と言われ、否定され続けてきたこの私に――感謝だなんて。
驚きに声が震え、視線を落とすと、足元で白虎がそっと尾を揺らしていた。まるで「受け取れ」と促すように。
宮様の声が、さらに近くで響いた。
「霊獣師ですらないそなたに、ここまで助けられるとは思わなかった。そなたの存在は、確かに私を救ったのだ」
その言葉は、冷えきった胸の奥にじんわりと染みていく。
温かな泉に沈められるように、全身が熱で満たされていく。
宵家で過ごした日々――見下され、否定され、ただ居場所を奪われていった記憶が脳裏をよぎる。
それでも今、この人は揺るぎのない声で私を「必要だった」と告げてくれている。
視界がじんと滲んだ。けれど、それは涙ではなかった。
胸の奥に、確かな火が灯ったのを感じた。
そのときだった。天から降り注ぐように、金龍の聲が境内を満たした。
「そなたは、霊獣たちに安寧を与える潤氣を持っている。そなたもまた、力強き潤氣を持つ者だ」
胸の奥に、低く柔らかな響きが沁みわたり、背筋がぞくりと震える。
けれど同時に――心の深みに影が差す。
……わたしなんて。燁子のような大きな力を持つわけじゃない。浮橋には到底、及ばないのに。
思わず視線を落とす。
その足元に、白虎がすっと歩み寄ってきて、鼻先を私の手に押しつけた。
毛並みのぬくもりが、かたく閉じかけていた心を、やさしく解いていく。
そんな私の耳に、今度は宮様の声が響いた。
「金龍の言う通りだ。浮橋は金龍の側に仕える者だが、そなたは霊獣と共に歩むにふさわしい力を持つ者だ。その力は、霊獣師にこそふさわしい」
その言葉は、不安を射抜きながらも、深く温かい余韻を残した。
顔を上げると、宮様の真摯な眼差しが、まっすぐに私を映していた。
白虎が低く喉を鳴らし、尾を一度大きく振る。
まるで「信じろ」と背中を押してくれるように。
そして――宮様は、迷いなく言葉を告げた。
「鈴音。霊獣師にならないか? 霊獣頭として、そなたを迎えたい」
「……!」
息が詰まり、視界が一瞬にして揺らぐ。
想像もしなかった未来が、目の前に差し出されている。
驚きと、胸の奥からこみ上げる熱とが入り混じり、喉がひゅっと狭まって、言葉にならなかった。
私は思わず胸に手を当てた。衣の下で鼓動が跳ねている。でも嬉しいはずなのに、心の底では黒い影がもぞりと動いた。
わたしなんて……本当に、霊獣師になっていいの……? 浮橋の燁子と比べたら、あまりにも力が小さい……。
不安が喉を塞ぎ、声は掠れて震えた。
「……わ、わたしが……霊獣師になっても、いいのでしょうか」
自分でも情けなくなるほど頼りない響き。
けれど、その言葉がこぼれ落ちた瞬間、宮様がゆっくりと一歩を踏み出された。
衣の裾がさらりと床を擦る音がやけに鮮やかに響き、私の胸を打つ。
「鈴音だからいいのだ。……そなたでなければならぬ」
まっすぐな声音に、思わず息を止めた。
その瞳には、一片の迷いもない。私が長いあいだ欲していた「認める光」が、確かに宿っていた。
足元で白虎が小さく鳴いた。黄金の瞳が私を真っ直ぐに映し出し、迷うなと告げている。
柔らかな毛並みが私の足首をくすぐり、震える心を支える。
私は唇をぎゅっと噛みしめた。
胸の奥からせり上がってくる熱を、そのまま言葉にのせる。
「……私、霊獣師を引き受けます」
声は小さくとも、揺るぎない灯火のように力を帯びていた。
その瞬間、宮様の眼差しがやわらぎ、唇がわずかに緩む。
静かに、しかし力強く頷かれた。
「……よろしく頼む」
その瞬間――ふわりと、見えない波紋のように柔らかな氣の揺らぎが広がった。
はじめはかすかな気配だったのに、すぐに承香殿の影から、庭の木々の間から、光の粒をまとった影が次々に現れはじめる。
霊獣たちだ。
尾を振りながら駆け寄ってくるもの、羽を大きく震わせて煌めきを散らすもの、静かに頭を垂れ歩み寄るもの――。
みな一様に、目を細め、身体から柔らかな光をあふれさせていた。まるで嬉しさを隠しきれない子供たちのように。
胸の奥が熱くなり、両手を胸元でぎゅっと握りしめた。
足元にすり寄る白虎の温もりとともに、ひしひしと伝わってくる。
……本当に、受け入れてくれている……。
その実感が心を満たし、目の奥がじんわり熱を帯びていった。
そのとき、空気を震わせるように金龍の聲が降り注いだ。
「人の子らよ。我が霊獣たちを、頼むぞ」
低くも威厳に満ちた響きが、宮中の屋根瓦を鳴らし、石畳の大地をも震わせる。
その聲に応えるように、霊獣たちが一斉に仰ぎ見て、澄んだ鳴き声を重ねた。
次の瞬間――燁子を包み込む金の繭が、淡い光を放ちながら天へと浮かび上がる。
その傍らには、力尽きて横たわる蛟の黒い身が、静かに従っていた。
金龍は彼らを導くように、その巨大な身をゆるやかにたなびかせ、やがて虚空へとすうっと姿を溶かしていった。
残された空気には、光の粒子が静かに舞い降りる。
朝の風に混じって、きらめく欠片が私の頬をかすめ、指先に落ちては溶けていった。
それは祝福の名残のようで、ただ息を呑むしかなかった。
◆◆ ◆
朝の空気は、刃の背でそっと肌を撫でるように冷たかった。
薄く漂う霧が足元にまとわりつき、白んだ空の下、陽はまだ昇らず、世界は深い静けさに沈んでいる。
私は殿上童の姿ではない。霊獣寮で用意された、女性でありながら動きやすい簡素な装束。袂をきゅっと握り直すと、生地の感触が冷えて指先に沁みた。
「……ここで待っていて」
白虎の額へ掌をそっとあてる。毛並みの奥から伝わる温もりに、ほんの少し胸が緩む。
澄んだ金の瞳が、何かを言いたげに一度瞬いた。けれど、やがて彼は首を低く垂れ、地面に身を伏せたまま動かなくなった。その姿が、背中を押すようにも、引き止めるようにも見えた。
神泉苑の門をひとりでくぐる。
途端に、空気が変わる。
足音が霧に吸われ、耳に届くはずの音がすべて遠のく。肌の上に、結界の膜がすうっと這い、胸の奥にかすかな緊張が走った。
池のほとりまで来たところで、自然と足が止まった。
――いた。
水面の向こう、霧の薄衣をまとったような白い姿。
燁子が、水の上に浮かぶように座っていた。
風も鳥の聲もない世界で、ただ彼女だけが、こちらには向けぬ笑顔を浮かべている。頬の弧は柔らかく、目元は無垢そのもの――けれど、その笑みの底に隠された棘を、私は知っていた。
……あの笑顔。 子どものころ、何度も見た。
誰かを試すとき、何かを奪うときにだけ浮かぶ、あの形。
浮橋になった。あの子が、ずっと望んでいた通りに。
私は水辺へ一歩踏み出し、波紋も立てぬ水を隔てて彼女を見据える。
霧の向こうの燁子は、天を仰ぎ、微笑んだまま瞬きもしない。
「……燁子。浮橋になれて、本当に良かったわね」
声は静かに池へ落ちたが、水は揺れもせず、風も返さない。
燁子は依然としてこちらを見ない。
その笑みは、天のどこかにいる見えぬ誰かとだけ語り合っているようで、私の存在など初めからなかったみたいだ。
「……私、ずっと気づいていたのよ」
喉の奥がきゅっと詰まり、息が揺れる。
「あなたは、望んだものを手に入れるために、周りの人を微笑みで包み込んで魅了して……なんでもさせてきた。……わたしのお母さまも……」
声の震えは、冷えた空気のせいではなかった。
冷たい水に指先をそっと浸したように――胸の奥で、古い記憶がゆらゆらと波紋を広げていった。
それでも私は、息を整え、言葉を押し出す。
「……私、この時を、ずっと待っていたの。あなたが……壊れていくのを」
唇がわずかに震え、視界の端が滲む。頬に触れそうなほど近くにある涙を、必死でこらえた。
「待つことしかできなかった。何もできなかった……。わたしは、強くなかったから」
吐き出した瞬間、その情けなさが胸をえぐる。それでも、それが私の本当だった。
「燁子……私は、あなたにずっと怯えていた」
自分でも驚くほど静かな声だった。
「でも……白虎がそばにいてくれて、宮様が……わたしを信じてくれた」
喉の奥に溜まった熱を飲み込み、背筋を伸ばす。
「だから……ようやく、ここに立てたの」
霧の中、妹は何も返さない。
ただ、どこか別の時を生きるように、天を仰いで笑っている。
「待ち望んだ状況になったら、大声で笑うんだろうなと思ったけれど……そうじゃないんだね」
ふと視線を落とすと、胸の奥に小さな棘が刺さったように痛んだ。
「あなたのせいで失ったものも、たくさんある」
霧が冷たく頬をかすめる。
「けれど……もう、あなたのことを憎んだままではいたくない」
燁子はやはり、返事をしなかった。
その笑顔は、子どものころのまま。無垢に見えて、何かを飲み込む深さを湛えていた。
――ああ、この子は、やっと欲しかった場所に辿り着いたのだ。
そう思うと、胸の奥に安堵とも痛みともつかない熱がじんわり広がった。
「あなたを許すわ。そして……あなたのことを、思い出として置いていく」
声は、もう震えていなかった。
「浮橋として、頑張って。……わたしは、霊獣師として生きていく」
ゆっくりと膝を折り、小さく一礼する。
目を閉じた瞬間、池の上を渡るような微かな風が頬を撫でた。
私は静かに背を向けた。
足音は淡く、しかし一歩ごとに確かだった。
もう――振り返らない。
神泉苑の門をくぐった瞬間、胸の奥に張りついていた糸が、ぷつりと切れたように緊張がほどけた。
霊的な結界の圧がすっと消え、肩がわずかに落ちる。朝の風が頬を撫で、指の先まで新しい空気が流れ込む。
そのとき――白虎が、小さく低く鳴いた。
「……!」
はっとして顔を上げる。そこに、ひときわ静かな気配が立っていた。
――宮様。
心臓が、ひとつ大きく脈を打った。
どうしてここに、と問いかける前に、胸の奥に灯る温かな光を感じた。それは驚きではなく、確かに待っていた気配に包まれる感覚だった。
「……お待たせしました」
言葉を紡ぐと、宮様は黙って、深くうなずいた。
微笑みはない。それでも、その沈黙がなぜか胸の奥を温める。
白虎が足元に身を寄せ、鼻先で足の甲をやさしく押す。
私はその柔らかな額を撫で、温もりを掌に確かめながら、ゆっくりと宮様へ歩み寄った。
東の空がわずかに白み、朝の光が石畳の端を淡く照らし始めている。
「そなたが行くと思っていた」
静かで真っ直ぐな声が、空気を震わせた。
私はふっと微笑む。
「はい。わたし自身のために……あの子に、会う必要がありました」
「そなたはあの場で、きちんと向き合った。……立派だった」
その言葉が、やさしい雨粒のように胸の奥に落ちて広がる。
私はほんの少し視線を落とし、息をひとつ、静かに吐いた。
「……でも、少しだけ悔しいんです」
声に出した瞬間、胸の奥がちくりと痛んだ。
「あの子のせいで、たくさんのことを失ったから」
足元で白虎がぴくりと耳を動かし、じっとこちらの聲に耳をすませるように身じろいだ。その温かな体温が、無言の励ましのように伝わってくる。
「でも……それを抱えたままでは、前に進めない気がして」
ふっと顔を上げると、宮様が目を細めてこちらを見ていた。そのまなざしは鋭さを帯びながらも、どこか深い思慮を含んでいる。
「悔しがっていい」
静かな声だった。
「潤氣とは、清らかさだけではない。怒りも、痛みも――そなたの力の一部だ」
その言葉が、胸の深い場所にじんわりと落ちていく。氷のように固まっていた感情が、ゆっくりと溶けて流れ出すのを感じた。思わず肩の力がほどけ、呼吸がひとつ楽になる。
ようやく――ほんの少しだけ、顔を上げられた。空の端が淡く白み、夜の名残を押しのけていく。
「そなたは、もう誰かに導かれる存在ではない」
宮様の聲が、朝の静けさにしみわたる。
「自ら道を選び、霊獣たちを導ける」
私は力強くうなずいた。
「……私も、ようやくそう思えるようになりました。私なりの役割がある」
宮様の瞳が、やわらかさを帯びる。その光に胸の奥が熱くなる。
「霊獣たちの潤氣は、そなたの中で穏やかに育っている。金龍でさえ、それを認めた」
私は小さく息を整え、正直な気持ちを口にした。
「それでも、あの時……信じてくれたのは、宮様でした。ありがとうございます」
その言葉に、宮様の目がふっと和らぎ、口元にかすかな微笑みが浮かんだ。
「礼などいらない。私は、そなたの潤氣に救われた」
――ああ。
その微笑みに触れた瞬間、胸がふわりと熱を帯びていく。
少しの沈黙ののち、彼は静かに言った。
「これからは……私も、そなたとともに歩みたい。導く者としてだけでなく、一人の男として」
頬に、熱がふわりと広がった。鼓動がせり上がり、声が出せない。
白虎が隣で、満足そうに目を細め、静かに喉を鳴らす。
木々の間から差し込んだ朝の光が、世界をやわらかに染め始めた。
その光の中で、胸に芽吹いた想いが確かな形をとっていく。
――これからは、自分の足で歩いていける。
その隣に、彼がいてくれるのなら。
神泉苑を背に、私はゆっくりと歩き出した。
隣には白虎。柔らかな毛並みが朝の光を淡く受け止め、ひとつひとつの毛先まで輝いて見える。
そのすぐ脇には――宮様がいた。
言葉はなかった。けれど、沈黙がこれほどまでに穏やかに心を包むものだと知ったのは、きっと今日が初めてだった。
草を踏む足音が、ふたりと一頭を静かにつなぎとめる。規則正しく響くその音に、胸の奥がしだいに落ち着いていく。
昔は、この人の隣を歩くなんて、考えたこともなかったのに……。
そう思ったとき、不意に頬を撫でるような風が吹き抜け、髪がふわりと揺れた。白虎が鼻を鳴らし、尾をぱたぱたと振る。その仕草がまるで、この静かな朝を祝福してくれているように見え、思わず口元がやわらかくなる。
そのとき、宮様の声が低く落ち着いた響きで耳に届いた。
「……霊獣寮の再編も急がねばな」
唐突な言葉に、足がわずかに止まりかける。
続いた声は、揺るぎない静けさを帯びていた。
「新しい霊獣師の筆頭として、そなたにも手伝ってもらおう」
「……えっ?」
思いがけない言葉に、私は立ち止まり、宮様を見上げてしまった。
「わ、わたしで……いいのですか?」
驚きと戸惑いが混じり、声がわずかに上ずる。胸の奥で心臓が跳ねる音が、自分でもはっきりわかった。
宮様は、まっすぐに私を見つめて言った。
「――誰よりもふさわしい。そなたほど霊獣の心に寄り添える者はいない」
その言葉が胸に落ちた瞬間、奥底でぽうっと温かな灯がともる。羞恥でも、戸惑いでもない。
ただ、自分という存在を、確かに認めてくれる声。その事実が、心を静かに震わせた。
「ありがとうございます。……これからも、どうかよろしくお願いします」
深く頭を下げると、宮様は静かにうなずいた。
そして次の瞬間――。
「こちらこそ、鈴音」
名を呼ばれただけなのに、胸の奥に小さな灯が芽吹く。
きっとそれは、まだかすかで頼りないけれど……恋という名の、はじまりの想い。
東の空が白みはじめ、雲の切れ間からやわらかな朝日が差しこんでくる。宮中の屋根が金色に染まり、世界がゆっくりと目を覚ましていく。
私はふと足を止め、神殿の方を振り返った。
あの奥には、浮橋となった燁子がいる。もう、決して届かぬ場所に行ってしまった妹。
胸の奥にちくりと痛みが走るけれど、涙は落ちなかった。
白虎がくるりと私の足元を回り、誇らしげな瞳で見上げてきた。柔らかな尾が草を揺らし、凛とした氣を纏っている。
「これからが本当の始まりだ」
宮様の低い声が、朝の静けさに溶けて響く。
私は小さく微笑み、うなずいて応えた。
三つの足音が重なり、やがてひとつの道を進んでいく。
朝日が昇る、その先へ。まだ見ぬ世界の方へ。
背後で、やわらかな風が頬を撫でた。
遠くで霊獣たちの潤氣がふわりと揺れた気がした。
それはきっと――私に託された道を、祝福する声だった。
まだ朝靄の残る霊獣寮の前庭は、白砂が淡く光り、槙や桜の葉が風にさざめいている。涼やかな空気を胸いっぱいに吸い込みながら、私は門をくぐった。
再びここへ来る日が、こんなに早く訪れるとは思わなかった。
周囲の仲間たちは「無理するな」と笑ってくれたけれど、胸の奥にあったのは別の緊張――宗直様が、どんな顔をされるだろうという不安だった。
女であることが……知られてしまったのだから。打ち明けるつもりなんて、なかったのに。
けれど、姿を見せた途端、宗直様はほんの一瞬だけ目を見開き、すぐに声を落として言った。
「身体、大丈夫か? 無理だけはするなよ」
その低くあたたかな響きが、胸の奥にじんわりと染み込んでいく。
こわばっていた肩が、ふっと緩んだ。白虎が、すぐ傍で尾を揺らしてくれたような気がした。
この日は久しぶりの内裏巡回。宗直様と並んで歩く足取りは、まだ緊張を含みつつも、不思議としっかりしていた。白虎の氣が、そっと背中を押してくれている――そんな感覚があった。
やがて、内裏の奥――後宮へと足を踏み入れる。朱塗りの回廊が連なり、格子窓の向こうには緑濃い庭が広がっている。その景色の中を進むうち、承香殿の前で私たちはふいに立ち止まった。
ぱちりと視線を上げた瞬間、陽の光をまとったように麗しい女性が目に映った。
思わず反射的に頭を下げる。額が膝につきそうなほど深く、顔を伏せた。――顔を上げる勇気は、とてもなかった。
あれは……登花殿女御様では?
私の父・藤原宵家の当主の姉であるその女御様を、一度だけ、宵家の屋敷で遠くから見たことがある。
女御様の背後には、燁子がいた。
変わらず可憐で、絵のように美しい姿。その周囲を、色とりどりの装束をまとった女房たちが、花の列のように取り巻いている。
「……あら、巡回かしら?」
登花殿女御様の声は、透き通るほど澄んでいるのに、頬を撫でる風よりも冷たかった。
「登花殿女御様、浮橋の君にお伝えしたきことがございます」
宗直様が、背筋を正しながら静かに告げる。
「申してみよ」
凛とした声が空気を震わせる。なのに、耳には針のように刺さる響き。
宗直様が、一瞬だけ言葉を探すように黙り、細く息を吐いた。
「……姿を偽っている者がおります」
その言葉に、心臓がどくんと大きく跳ねた。
え……なにを……言って……?
「……私は、嘘をつきたくない」
そう呟くと、宗直様の手が私の髪紐に伸びてきた。
逃げようと足に力を入れたのに、動けない。指先が紐を解く感触が、耳の奥まで届く。
するり――肩先を黒髪が滑り落ちる。
一瞬の沈黙のあと、周囲の空気がざわりと揺れた。
「女……!?」
「まさか女で殿上童とは……!」
女房たちのざわめきが、四方から押し寄せる波のように私を包む。
喉がひゅっと鳴り、呼吸が浅くなる。声も出せないまま、足が床に縫いとめられたみたいに動かない。
「よくぞ教えてくれた。そなた、何者だ。何故その姿で後宮に入り込んだ? その顔を見せてみよ」
女御様の声が、矢のように突き刺さる。
震える指で顔を覆い、ただうつむいた。
「女御様が仰せだ」
宗直様の声が、静かに背後から降りてくる。優しいはずなのに、今は抗えない命令の響きを帯びていた。
私は、ゆっくりと顔を上げた。
視線が一斉に集まり、わずかな衣擦れの音すら鮮やかに耳へと届く。
その気配に、喉の奥で小さく息が詰まった。
「……そのお顔……まさか、姉さま?」
振り向いた燁子の瞳が、大きく見開かれた。朱をさした唇が、わずかに震える。
登花殿女御様の眉が、きゅっと吊り上がる。
「宵家の、側室のか?」
「そうです。まさかこんなところでお会いできるなんて……お姉さま、心配したのですよ」
袖を翻し、燁子がすべるように駆け寄ってくる。香の匂いがふわりと鼻をくすぐり、指先が私の手を柔らかく包み込んだ。涙に濡れたような瞳が、まっすぐこちらを射抜く。
胸の奥が痛んだ。
「ご、ごめんね……」
絞り出すように声を出した瞬間、周囲の空気がざわりと揺れた。
「……霊獣騒乱事件のあと、行方不明になった姉君……?」
「変装していたなんて……」
「女房に化けても潜り込めるでしょう」
女房たちの唇が動くたび、衣擦れの音と囁きが耳に絡みつく。視線が次々と突き刺さり、背中にじっとりと汗が滲む。
「浮橋である燁子の足を引っ張るお荷物……そなたがやったのか?」
鋭い声が飛び、胸の奥がひやりと凍った。
「ち、違います! 私は変装なんてしていません。霊獣騒乱事件は“香”で引き起こされたんです!」
思わず声を張り上げると、燁子がわずかに首を傾け、口元を手で押さえた。指の隙間から、探るような微笑がのぞく。
「香……? お姉さまがお得意の香ですか?」
その声は甘く響くのに、瞳の奥がきらりと光った。
「香が得意だったのか、そなた」
女御様が片眉を上げ、扇の先で私を指し示すように動かす。
「……得意ですが、私じゃありません。それは潤氣を乱す香。私には……そんなもの作れません!」
喉が焼けつくように熱い。足は床に縫いつけられたように動かず、ただ心臓の鼓動だけが耳の奥で、どくん、どくんと響いていた。
「……それは、本当だろうか」
一瞬、空気が固まった。その沈黙を破ったのは、宗直様の低い声だった。
胸の奥がきゅっと縮む。
「宗直様……?」
思わず名を呼ぶと、彼は私から視線を外し、静かに告げた。
「この者は白虎を引き連れております」
ざわめきの中から、女御様の細い吐息が漏れる。
「まあ、白虎を」
「霊獣白虎を従えるとは、潤氣を扱えないとできない。潤氣を乱す香を調合できないなど、考えられぬ」
別の声が私を突き刺す。
「霊獣騒乱事件の折、弘徽殿の女房の局から妙な香が漂っていたそうです」
「殿上童が弘徽殿に目をかけてもらっているらしいし、手引きする女房がいてもおかしくないわ」
視線が四方から絡みつき、肩に重しがかかったように息が苦しい。
「お姉さま、なんてことを……まさか帝まで……」
燁子の声が震え、涙が光る。
「ありえること。帝をも狙うとは、大罪人ね」
その一言が、背骨を冷たくなぞる。
「そんな……私は、そんな香を作っていません!」
声が裏返るほどの勢いで叫んだ。喉が焼け、耳の奥で自分の鼓動がうるさく響く。
そのとき――。
「――ああ、そうだ。この者は潤氣を乱す香を作れない」
凪いだ水面に石を落としたように、場の空気が揺れた。
振り返ると、朱の柱の陰から宮様が歩み出てくる。
「宮様……!」
空気が、ぴたりと止まった。
さっきまで耳を刺していた囁きも、疑いの声も――すべてを押し流すように、静かに、一歩。
回廊の奥から、宮様が現れた。
その歩みは、廊を撫でる風すらひれ伏させるようで、裾がわずかに揺れるたび、空気が澄んでいくのがわかる。
誰もが息を呑み、ざわめきはいつしか、敬意を帯びた沈黙に変わっていた。
「――この者は、今回の事件を探るため、霊獣寮に協力してもらっていた者です」
低く落ち着いた声が、糾弾の空気を断ち切る。
「あなたが……潜り込ませたのか?」
登花殿女御様の声音は抑えられているのに、扇の先から鋭さが滲む。
「はい。ご不安にさせたことは心苦しいのですが……おかげで、ようやく解決の糸口が見えました」
宮様は、私の方へわずかに目をやると、すっと右手を差し出した。
その掌に乗っていたのは、小さな布袋。
練香――。
「これに、見覚えは?」
布袋の口を開くと、ふわりと柔らかな薫りが広がり、春の朝露をまとった花のような甘さが鼻をくすぐった。
胸が一瞬、ざわりと揺れる。私も知っている香り――。
宮様は、その香を手にしたまま、囁くように言う。
「……朝露に濡れた花のように、ふんわりとやさしく薫り立つ……素敵な香りだ」
「それは……わたくしの香ですわ」
燁子が微笑んだ。長い睫毛が影を落とし、その表情はまるで贈り物を喜ぶ姫のようだった。
「そうか。しかし、これは弘徽殿の女房、三条殿から借り受けたものだ」
「……どなたかしら?」
燁子が小首を傾げる。金の簪がかすかに揺れた。
「自分のものだと言ったのに、彼女のことは知らないのか」
宮様の視線が、静かに燁子を射抜く。
「はい。なぜその方が持っているのかも、わたくしにはわかりませんわ」
涼しげな笑みは崩れず、声にも震えはない。
そのとき――宮様の声に、わずかな鋭さが混じった。
場の温度が、またひとつ下がった気がした。
「三条殿は、恋人である源敏行からもらったと言っていた。しかし、彼女が弘徽殿でそれを焚いたことで、霊獣騒乱事件が引き起こされた。三条殿はショックのあまり、実家へ戻られている」
「まあ……お可哀そうに」
燁子が、扇の影からさらりと声を落とした。ひどくあっさりとしたその響きに、背筋がひやりとする。
宮様の瞳が、細く鋭くなる。
「可哀そう、か? これがあなたの香であってもか」
登花殿女御様が、低く問う。
「それの……何の関係があるのか?」
「三条殿は、恋人と会えぬ寂しさを紛らわせるため、源敏行殿が香を纏って出仕した。そのまま、清涼殿に……」
「……まさか、それは――」
扇を握る女御様の指が、かすかに震えた。
「金龍が失踪し、帝が倒れられた原因です」
その一言が落ちた瞬間、空気が凍る。
誰かが息を呑む音がはっきりと聞こえた。登花殿女御様の顔から血の気が引き、ゆっくりと燁子へ視線を向ける。
燁子は、その視線を正面から受けながらも、淡く顔を曇らせるだけだった。
「そんな……驚きですわ……ひどい……」
その声には、涙の重みも熱もなかった。
「では犯人は、源敏行殿か?」
女御様の問いに、宮様は静かに首を横に振る。
「いいえ。違います。霊獣を扱えぬ源敏行殿では、潤氣擾乱香は調合できません。それは三条殿にも同じことが言える。二人とも、実行させられてしまったのです」
胸の奥が、強く脈打つ。
「……だ、誰から……」
自分の声が震えているのがわかった。
宮様の視線が、ゆっくりと宗直様へ向けられる。
「ここにいる、宗直だ」
「宗直様が……!?」
全身の血が一瞬で引く。
「宗直。源敏行殿に香を渡したな?」
「そ、それは……」
宗直様は唇を噛み、目を逸らした。
だが、宮様のまなざしは鋼のように揺るがず、その沈黙さえ許さない気配が廊の空気を張り詰めさせていた。
「そなたが香を作ったとは思えない。どこから手に入れた?」
宮様の声は、氷の縁をなぞるように低く、静かだった。
「……いただいたものです」
宗直様は、肩をわずかに揺らし、視線を畳の目に落とした。
「誰から?」
「……浮橋の君からです」
その瞬間、周囲の女房たちの視線が、燁子へと一斉に集まった。
「いつ、知り合ったのだ?」
「もう……一年以上になります。宮中の巡回中に、偶然……」
言葉を吐くたびに、宗直様の声が細くなっていく。
「なるほど」
宮様の眼差しが、刃のように燁子へと向かう。
「宗直はそう言っているが、あなたは香を渡したのか?」
「渡したことは……ありますわ」
燁子は、扇を傾けて唇を隠し、しっとりとした視線を落とす。
「でも、人にあげてしまうなんて……悲しいですわ」
「しかし、もともと俺への贈り物ではなかったでしょう!」
宗直様の声が一気に熱を帯び、握りしめた拳が膝の上で震えた。
「どうして?」
燁子が小首を傾け、耳飾りがかすかに揺れた。
「あなたが香を俺の手に渡したとき、“あの方がこの香を手に取ってくださったら嬉しいのだけど”とおっしゃったじゃないですか!」
「わたくしの言葉で誤解を招いてしまったのね。ごめんなさい。きっと伝え方が少し拙かったのね」
柔らかな声音。だが、瞳の奥には波ひとつ立たない。
「勘違いって……!」
宗直様は唇を噛みしめ、肩をわずかに震わせる。
「確かに、渡してほしいとは言っていないな。その言葉だと」
宮様が淡々と告げ、間を一拍置く。
「誰に渡す必要があると思ったのだ?」
「……それは……宮様です」
宗直様は俯き、声を絞り出す。
「でも、渡したくなったから。浮橋の君の心は、いつも……宮様に向いているから……」
ふぅ――。
宮様が長く息を吐く。その吐息は静かなのに、廊の空気をさらに冷たく締めつけた。
「では、宵家の二の姫に聞く。潤氣擾乱香を渡したのはあなただ。つまり、所持していたことになる。霊獣を従える姫君がこれを作っても、おかしくはない」
宮様の言葉は、鋼のように冷たく澄んでいた。
燁子は、わずかに肩を震わせ、可憐な頬にほんのりと紅をさす。伏せた睫毛の影が長く落ち、声は頼りなげに震えている。
「お恥ずかしながら……わたくし、香を作るのが苦手で……ごめんなさい。それを作ったのは……お姉さまです。わたくしの香は、いつもお姉さまが作ってくれるんです」
その儚げな言葉の奥で、わずかに口角が動いたように見えたのは――私の気のせいだっただろうか。
「確かに、燁子の香は私が作りました。でも……それは、私じゃありません」
胸の奥がざわりと揺れ、言葉が自然に口を突いた。
「この者ではない」
宮様の声音は揺るぎなく、場の空気をさらに重くする。
「じゃあ……」
燁子はゆっくりと顔を上げ、困ったように宗直様へ視線を向ける。眉尻が柔らかく下がり、その瞳が水をたたえたように揺れた。
「俺じゃありません!」
宗直様は、咄嗟に声を張った。拳を握りしめ、膝の上で震えている。
「じゃあ、誰が作ったというのだ」
登花殿女御様が、扇を少し下げて静かに問う。その扇先から放たれる視線は、鋭い刃のようだった。
宮様は、ゆっくりと歩みを進め、燁子をまっすぐに見据える。
「宵家の二の姫。あなたですよ」
その瞬間、廊に張りつめた空気がさらに凝縮する。女房たちの衣擦れの音すら、やけに大きく響いた。
燁子は、小さく息をのみ、すぐに可憐な首を傾げる。長い黒髪がさらりと肩からこぼれ、唇には控えめな笑み。
「まあ……どういうことでしょう……」
その声音はあくまで柔らかく、困惑を装っている。
「誤魔化しても無駄です。潤氣擾乱香は、霊獣師であっても潤氣の特定は困難。だが、それを見抜ける存在がいる」
心臓が早鐘を打つ。私は息を詰め、宮様を見た。
「そ、それは……」
「――金龍だ」
宮様のその言葉が落ちた瞬間、廊に張りつめた空気がびり、と震えた。
音ではない。雷でも風でもない。もっと深く、底の見えぬ何か――魂の奥を直接叩く衝撃が、私たちを包み込む。
天井のどこかで、ぎしり、と梁が軋むような音がした。張り詰めた空間が、わずかに揺らぎ始める。
白虎が、背後で低く唸った。
その声が私の背骨を這い上がり、熱と震えを同時に残していく。呼吸を忘れた私の背に、あの白い氣配が寄り添った。
胸の奥がざわめき、言葉でも音でもない「何か」が、確かにこちらへ近づいてくる。
ひゅう――。
一陣の風が、宮中を抜けた。
その刹那。
天のひさしが裂けるように、まばゆい金色の光が降り注いだ。雲を裂き、空を貫き、宮中の真上からゆっくりと――まるで天から垂れる帯のように――金の筋が地上へ伸びていく。
そして、その光の中に――姿があった。
――金龍。
息を飲む。
一枚一枚の鱗が宝玉のように輝き、光をはね返すたび、周囲の空間まで金色に染まる。悠々とたなびく尾が、空を泳ぐように揺れ、その存在だけで世界の均衡が変わるようだった。
誰かが小さく「あ……」と息を漏らす。その瞬間を境に、そこにいた全員が瞳を見開き、やがて一人、また一人と膝をついた。衣擦れの音だけが、静まり返った空間に小さく重なっていく。
私も、立っていられなかった。膝が床に触れる音が、やけに大きく耳に響いた。
「神泉苑に足を踏み入れ、我に呼びかけた者よ。そなたであるな?」
耳ではないところで響く聲――。
鼓膜ではない。空気の振動でもない。
魂そのものに、直接触れてくるような聲だった。
懐かしいような、胸が苦しくなるような、それでも泣きたくなるほど温かい響き。
喉が詰まり、声が出ない。私はただ、心の奥で静かに頷いた。
「……はい」
金龍の瞳が、私をまっすぐに射抜く。底知れぬ光の奥に、揺るがぬ意志があった。
「そなたの聲が、我を神泉苑からここへ導いた」
その響きが胸の奥に染み込んだ瞬間、心臓の鼓動がひときわ強く打ち、内側から熱がじわりと広がっていった。
何か言おうと、喉がわずかに動いたその瞬間――。
「この場に集いし者よ、聞け」
金龍の聲が、堂内の空気を震わせた。
耳で聞くというより、胸の奥を直に叩かれたような衝撃。石壁の彫り物すら微かに鳴るような、重く深い響きだった。
誰一人、口を挟むことも、息を呑む音すら立てられない。
「この氣に満ちた香には、蛟の潤氣が用いられている」
ぴしり、と。
目に見えない糸が、場の全員の首筋を縛りつけたように、空気が張り詰めた。
一瞬で、視線が一斉に燁子へと突き刺さる。
そのとき、彼女は――。
ふわり、と長い睫毛が揺れ、潤んだ瞳に一粒の涙を浮かべた。
頬を伝う前に指先でそっと押さえ、その指がわずかに震える。
「わ、わたくしでは……ございません……そんな、ひどいこと……」
その聲は、絹糸のように柔らかく、壊れそうなほど哀れを帯びていた。
見ている者の心を「守らねば」という錯覚に誘い込むような優美さだった。
「それはそなたがわかっているはずだ。――そなたを浮橋にしたいからこそ、真実を告げる」
金龍の聲が、低く鋭く響く。
その一言が、彼女の涙の膜を鋭利に切り裂いたように感じられた。
「は……? 浮橋にしたい?」
登花殿女御様の声は、かすれていた。
紅を引いた唇がわずかに開き、白い喉がひくりと動く。
やがて、彼女は信じられないものを見るように震えながら立ち上がった。
「それでは……燁子が、浮橋ではないと……?」
宮様が一歩、静かに前へ出る。
その足音が、妙に鮮やかに響いた。
「はい。その通りです。私は“導く器”。金龍が現れ、浮橋を選ぶということは――」
女御様の瞳が、ゆっくりと見開かれていく。
その奥で感情が渦を巻き、形を持たぬまま揺れていた。
「……つまり……燁子は偽りの浮橋だったと……そう言うのか」
宮様は短く目を閉じ、そして静かに頷いた。
「偽り、というより……“選ばれていなかった”だけです」
その瞬間。
女御様の手が宙を彷徨い、指先が何も掴めぬまま力を失った。
次の瞬間、衣の裾がふわりと揺れ、体が崩れ落ちる。
「女御様!」
女房たちの声と衣擦れの音が一斉に起こり、慌てて彼女を抱き起こす。
この場にいる誰もが「当たり前」だと信じていたものが。
金龍の一言が、それを静かに、確実に塗り替えていく音だった。
宮中を覆う沈黙の中、金龍の聲が燁子に向かって放たれた。
冷ややかで、透き通る金の鈴の音のような響き――それが胸の奥をひやりと撫で、空気をさらに重くする。
「――問う。そなたは、本当に浮橋となる覚悟があるか」
まるで刃の先を突きつけられるような、逃げ場のない問いだった。
思わず私は、息を呑んで燁子に目を向ける。
薄紅の袖にかけられた指先が、わずかに震えている。
その震えを悟らせぬよう、彼女はひと呼吸置き、ゆっくりと顔を上げた。
涙に濡れた頬を、ためらいもなく白い指でなぞり、雫を払う。
次いで、長い睫毛を伏せて呼吸を整え、そして――すっと瞼を開いた。
「……わたくしは、浮橋になります」
細いけれど芯の通った聲だった。
澄み渡る朝の水面のように冷ややかで、なめらかで、触れることをためらわせる美しさがあった。
そして彼女は、ためらいも迷いもなく言葉を続ける。
「宮様と結ばれるために――それが、わたくしの望みです」
その瞬間、胸の奥が、ぎゅっと音を立てて締めつけられた。
“結ばれる”――たったそれだけの言葉なのに、どうしてこんなにも深く刺さるのだろう。
心臓の鼓動が耳の奥で響き、呼吸が浅くなる。
周囲の女官たちがざわめき、袖口の影で視線を交わす。
誰もがその一言の重さを、噛みしめるように感じ取っているのがわかった。
金龍が長い睫毛のような鱗を静かに閉じ、命を告げるような低い聲を響かせた。
「導く器よ。そなたの心のままに、選べ」
さらに空気が沈んだ。
そのとき――宮様の視線が、一瞬だけ、私を射抜いた気がした。
けれど、それは本当に刹那のこと。
すぐにその目は、燁子へと向けられる。
そして、低く穏やかで、しかし決意の色をはらんだ声が響いた。
「……金龍よ。この者、宵家の二の姫を、浮橋とする」
その言葉とともに、燁子の表情がぱっと華やいだ。
次の瞬間、彼女の周囲に金の潤氣がふわりと舞い始める。
やわらかく、春の嵐の前触れのように――けれど、その美しさは儚くて、息を呑むほどに恐ろしいほど綺麗だった。
薄く金色に光る文様が、燁子の足元からじわりと広がり、絡み合いながら天へと昇っていく。
風ひとつないのに、彼女の袖がゆるやかに舞い上がり、その動きに合わせて光がきらめきを増す。
私は、その光景から目を離せなかった。
――これが、「浮橋」なのだ。
「……浮橋だ……ほんとうに……」
気づけば、唇から小さな声がこぼれていた。
自分でも驚くほど、弱く、頼りない声だった。
燁子の瞳には、金色の光が宿り、満たされたような微笑みが浮かんでいた。
それは、すべてを手に入れた者の顔。
どこか遠い存在のようで――それでも、私のすぐ前にいた。
……そのときだった。
胸の奥に、ざぶん、と波が押し寄せるような熱が走った。
痛みと呼ぶには熱すぎて、けれど言葉にはできない感情が、私を内側から揺らす。
――いやだ。
その聲は、心の奥で小さく、それでもはっきりと鳴った。
宮様と燁子が結ばれる。
ただ、それだけのことが――どうして、こんなにも苦しいのか。
私はずっと、傍観者のふりをしてきた。
妹の背を見つめながら、嫉妬なんて知らないふりをしていた。
でも今、心が叫んでいる。
――それは、いやだ。
白虎が、そっと私の横に身を伏せた。
大きな体から伝わる温もりが、震える私を包み込む。
頬をその毛並みに寄せると、柔らかな感触の奥で、ゆったりとした鼓動が響いていた。
まるで、「わかっているよ」と語りかけてくれるように。
私は唇を噛みしめたまま、光に包まれる燁子を見つめた。
神々しさすら帯びたその姿が、まぶしくて、遠い。
――けれど、その光の外側で。
私の心は、ようやく気づいてしまった。
はっきりと。
……私は、宮様を、好きだったんだ。
声にならない聲が、胸の奥で、ぽつりとこぼれ落ちた。
金龍が燁子を浮橋と認めた瞬間、堂内を覆っていた張りつめた空気が、わずかにほどけかけた。
その安堵の息は――すぐに断ち切られる。
「……金龍よ、お許しください。この場を借りて、もう一つ明らかにすべき真実があります」
宮様の声が、刃のように鋭く響いた。
静かでありながら、冷たく肌をなぞるような響きに、私の背筋がぞわりと粟立つ。
「宮中で起こった霊獣騒乱事件……あれを裏から仕組んだのは、宵家の二の姫でした」
「……あ……」
燁子の長い睫毛が瞬きを忘れたように止まり、その瞳が一瞬だけ大きく見開かれた。
だが、驚きの色はすぐにふっと消え、彼女は視線を落として唇を小さく結ぶ。
袖口の下で、細い指がかすかに握られるのが見えた。
「私と共に行動するため――霊獣が暴れる状況を“演出”した。浮橋としての役割を果たすことを利用し、自らを必要な存在に見せかけるために」
宮様の声は揺らがない。
その冷ややかな響きに、堂内の空気がさらに重く沈んでいく。
燁子は何も返さず、ただ伏し目のまま、長い睫毛の影で表情を隠した。
……燁子……。
胸が痛む。
彼女は、きっと宮様と一緒にいたかっただけ。
それだけのはずだった。
けれど――そのために、どれだけの人が傷つき、霊獣が苦しみ、私も……。
「愚かなる動機だが、確かに“選ばれた素質”ではある。手放すものを手放せば良いだけだ」
金龍の聲が低く響き、どこか哀れみを帯びる。
金色の瞳が、燁子をまっすぐに射抜いた。
「そなたはもう我の浮橋だ」
その瞬間、燁子の顔がふっと綻んだ。
頬に花が咲いたような、純粋な笑み。
まるで、長い間欲しかった宝物をようやく抱きしめた子どものようだった。
「だが、浮橋とは“我が子”となる者。神の器たる資格を得るがゆえ、人の縁は断たねばならぬ」
空気が、一気に凍りつく。
女官たちは互いに顔を見合わせ、小さく息を呑んだ。
燁子は笑みを保ったまま、何の迷いも見せずに答える。
「……はい」
その声音は、澄んでいて、痛いほど真っ直ぐだった。
私は唇を噛み、視線を逸らすことができなかった。
――だが。
金龍の潤氣が、ふたたび燁子を包み込んだ。
それは春先の陽だまりのようにやわらかく、母の胎に還るかのようなぬくもりを帯びていた。
けれど、その甘やかさの奥に、決して抗うことの許されぬ圧が潜んでいる。
肌に触れるその氣に、私は背筋の奥がざわりと軋むのを感じた。
「……あれ……? 宮様……?」
燁子の頬が、わずかに引きつる。
薄紅の唇が形を探すように震え、目が必死に何かを求めて彷徨った。
「宮様……なぜ……手を……取ってくださらないの?」
彼女はゆっくりと腕を伸ばす。
けれど、金色の潤氣が薄い膜のようにその前に立ちはだかり、指先は空を掻くことすらできず、ただ宙で小刻みに震えていた。
「金龍が言ったであろう。人の縁は断たねばならぬ、と」
宮様の声音は、静かで、しかし冷たい刃のように鋭かった。
「まさか……これって……わたくし……結ばれないの?」
その問いは震えていたが、どこか信じたい答えを待つ色があった。
「結ばれる? ありえない。そなたに恋焦がれる気持ちなど、持ち合わせていないのに」
――その瞬間を、私は見た。
燁子の中に、真実という冷たい刃がようやく突き刺さり、形を持って侵入していく瞬間を。
彼女の瞳から、透明な滴がひとすじ、頬を滑り落ちた。
「うそ……うそでしょう……」
潤んだ瞳が揺れる。
唇が必死に言葉を紡ぐが、それは頼りなく震えていた。
「恋心を抱く者は、龍に仕える“浮橋”とはなれぬ。しかし導く器として、浮橋に相応しい素質を持つ者はそなただけだと結論づけた。それゆえ、そなたには恋心を手放してもらう」
「いや……いやよ……わたくしは、宮様と……結ばれたいのに……」
「私がそなたと結ばれることなど、未来永劫ない」
その冷淡な声が、燁子の顔から色を奪い取った。
華やいでいた頬も、艶やかな唇も、一瞬で力を失い、ただ白く乾いていく。
「……こんなの……聞いてない……わたし……浮橋になりたかったのに……あなたのせいよ!」
鋭く突き出された指先が、まっすぐに宗直様を指し示す。
その刹那、承香殿の空気がぴん、と張り詰めた。
宗直様は一歩、後ろに下がり、見開いた瞳のまま言葉を失っていた。
「白虎と一緒にいた、わたくしの邪魔をしたお姉さまを……あなたがちゃんと始末しなかったから!」
――始末。
その言葉が私の耳に届いた瞬間、背筋から氷が滑り落ちるような感覚が走った。
手足が強張り、息が浅くなる。
「“始末”って……」
自分の声が、自分のものではないみたいにかすれていた。
「……宗直、それは事実か?」
宮様の声は、低く鋭く、空気を裂いた。
その瞬間、宗直様の膝が力を失い、畳に崩れ落ちる。
「……はい……在原貞親と共に……白虎といた者を……燁子さまのお気持ちに応えるために……」
かすれた声が、堂内の壁に吸い込まれるように消えた。
女房のひとりが、短く息を呑み、それは悲鳴へと変わった。
「宗直。貞親が鈴音を霊獣で襲い、そなたが意図的に鈴音を池に突き落としたのだな」
宮様の言葉は、刃物のように容赦なかった。
宗直様は、視線を落とし、唇を固く結ぶ。
答えはなかった。
けれど、その沈黙が、すべてを肯定していた。
「そなたの潤氣の強さは真であった。しかし、それは“己のために人を傷つける”潤氣として誤った使い方をした。だが、これからは正しく潤氣が使える」
金龍の聲が、鈍い雷鳴のように胸に響く。
私は喉が固まり、何も言えなかった。
ただ――燁子を見ていた。
「わたくしが、浮橋なのに……どうして……」
燁子の声は糸のように細く震えた。
「嫌、嫌よ……!」
次の瞬間、彼女の背後でどろりと氣が揺らぎ、暗い水底から泡が弾けるみたいに、蛟がぬらりと姿を現した。濡れた黒の鱗が怒りに滲み、紅い瞳が灼けた鉄のようにきらめく。
ぞわりと背筋に悪寒が這い上がり、息を飲んだ。
蛟の目の前で金龍の潤氣が、ふたたび燁子を包み込む。胸の奥まで沁みるような、あたたかいのに抗えない光の胎。
「助けて、蛟!」
燁子の絶叫と同時に、蛟の巨体がどくんと脈動した。鱗が怒りに滲むように光り、風を裂く轟音が承香殿を打ち破る。黒い影が咆哮をあげ、光の檻めがけて突進した。
その姿に心臓が喉までせり上がる。喉がひゅっと狭まって空気しか漏れない。足がすくんで動かなかった。
だって、あれは。
脳裏に明滅する記憶が蘇る。
それはあの初めて宮中に足を踏み入れた夜に、私を襲った黒い影。背中を強打した衝撃で肺から空気が押し出され、喉がきしむ。胸の奥が固く閉ざされて、視界がぐらりと揺れ、足元がどこまでも抜けていくようだった。
あれと、同じだ。
次の瞬間、白い閃光が視界を貫いた。
「白虎……!?」
金龍を守るように間へ飛び込み、爪が閃いて蛟の顎を裂いた。蛟の巨体がよろめき、地を叩きつける音が轟く。地に這いつくばった紅い瞳が苦悶に濁った。
「……あの夜、鈴音を狙った蛟は――二の姫の霊獣だったのか」
宮様の声が鋭く響く。
ああ、やっぱり。胸が冷たく凍りつく。
「……わたしを襲った霊獣は……燁子の、蛟」
震える声は自分のものとは思えなかった。心のどこかでまだ燁子を信じたかったのかもしれない。それは打ち砕かれ足元からがくりと崩れそうになる。
――怯えるな。仇は必ず討つ
胸の奥に音が届いた。
はっと顔を上げると、白虎が振り返って黄金の瞳で私を射抜く。白虎の低い唸り声が胸を震わせ、私は無意識に拳を握り締める。
「……白虎、わたしの力を――あなたに託す」
白虎が頷いたように見えた。それは一瞬のことで再び力強く駆けた。
鋭い爪と牙が閃光となり、蛟の鱗を切り裂く。黒い氣が弾け、轟音が殿を揺らす。蛟の咆哮は怒号から悲鳴へと変わり、白虎によってその巨体は地に叩き伏せられた。
なおももがく蛟へ、追い打ちのように金龍の潤氣が淡く降り注ぐ。金の光が絡みつき、鱗をすり抜け全身を縛る。蛟の動きは次第に鈍り、やがて力なく沈黙した。
「蛟、蛟!」
淡い光はなおも広がり、燁子の身体を、やさしく、けれど抗えない抱擁で包みこむ。肩が小刻みに跳ね、見開かれた瞳が焦点をなくしていく。
「うそ……うそでしょう……」
唇がかすかにふるえ、声にならない息がこぼれた。
「嫌……こんなの……嫌……わたし、あなたと……結ばれたかったのに……」
蛟の紅い瞳がこちらを掠める。怨嗟とも、庇護ともつかぬ色が瞬いて――次の波で、黒い影はさらに遠くへ押しやられた。咆哮が細くほどけ、やがて尾の先から力が抜けてゆく。
光のうちの燁子は、絵巻の一場面のように美しかった。だからこそ、その美しさは絶望の底色をはっきりと帯びていた。胸がきゅっと縮み、喉が熱いのに、涙は出ない。鉛のように重たい苦しみだけが、肺の奥に沈殿する。
「……燁子……」
気づけば白虎が私の側にやってきて、励ますようにすりすりと大きな体を私に寄せる。伝わる潤氣が白虎が「ここにいる」と告げてくる。その潤氣からじわりと温もりが沁みる。
金の繭がゆっくりと閉じる。光の層の向こうで、燁子の輪郭が薄れ、最後に――頬を伝った一筋の涙だけが、細い銀の線となって残った。蛟はなお遠くで低く唸り、しかし踏み固められた金の静けさを破ることはできない。
誰ひとり、動けなかった。声も出せなかった。ただ、朝に溶けていく最後の焔を見送るみたいに、その場に立ち尽くしていた。白虎の体温を受けとめながら、私はゆっくりと息を吐く。
淡い光が、承香殿の柱や床を撫でるように広がり、やがて静かに薄れていく。
残されたのは、どこまでも透きとおった沈黙。誰もがその場に釘づけにされ、動くこともできず、ただ息を呑んで立ち尽くしていた。
蛟の低い唸りも消え、燁子の氣も、もう届かない。
光が引いたあとに残るのは、ただ重たく張り詰めた空気だけ――。
その沈黙を切り裂くように、金龍の聲が、再び深く響き渡った。
「導く器よ。浮橋が現れた今、そなたの務めは終わった。自由となれ」
その言葉を受けて、宮様の背筋がすっと伸びる。
見えない鎖がほどけ落ちるように、空気がふっと変わった。
肩先から何かがふっと剥がれ落ち、長く纏っていた重さが、ようやく解けていく――そんな気配。
思わず、息を呑む。
宮様は、まだ淡く揺れている光の残滓をじっと見つめていた。
その眼差しには、安堵とも、名残惜しさともつかぬ影が宿っている。燁子が立っていた場所を凝視したまま、しばらく動かなかった。
やがて、ゆっくりとその視線がこちらへ移る。
深い湖の底を覗き込むような、揺らぎのない瞳。吸い込まれそうになって、思わず胸が小さく震えた。
「……鈴太。いや、鈴音」
名を呼ばれた瞬間、唇が乾き、無意識に指先に力がこもる。
宮様は、一歩こちらに歩を進めると、低く、静かに口を開いた。
「浮橋は現れた。長き懸念が、ようやく果たされた。……だが、それは私ひとりの力ではない。そなたがいてくれたからこそだ。……感謝する」
「……わ、わたし……?」
自分に向けられた言葉だと理解するまで、少しの間が必要だった。
胸が大きく跳ね上がり、心臓の音が耳の奥で響く。
これまで「いるだけで厄介」と言われ、否定され続けてきたこの私に――感謝だなんて。
驚きに声が震え、視線を落とすと、足元で白虎がそっと尾を揺らしていた。まるで「受け取れ」と促すように。
宮様の声が、さらに近くで響いた。
「霊獣師ですらないそなたに、ここまで助けられるとは思わなかった。そなたの存在は、確かに私を救ったのだ」
その言葉は、冷えきった胸の奥にじんわりと染みていく。
温かな泉に沈められるように、全身が熱で満たされていく。
宵家で過ごした日々――見下され、否定され、ただ居場所を奪われていった記憶が脳裏をよぎる。
それでも今、この人は揺るぎのない声で私を「必要だった」と告げてくれている。
視界がじんと滲んだ。けれど、それは涙ではなかった。
胸の奥に、確かな火が灯ったのを感じた。
そのときだった。天から降り注ぐように、金龍の聲が境内を満たした。
「そなたは、霊獣たちに安寧を与える潤氣を持っている。そなたもまた、力強き潤氣を持つ者だ」
胸の奥に、低く柔らかな響きが沁みわたり、背筋がぞくりと震える。
けれど同時に――心の深みに影が差す。
……わたしなんて。燁子のような大きな力を持つわけじゃない。浮橋には到底、及ばないのに。
思わず視線を落とす。
その足元に、白虎がすっと歩み寄ってきて、鼻先を私の手に押しつけた。
毛並みのぬくもりが、かたく閉じかけていた心を、やさしく解いていく。
そんな私の耳に、今度は宮様の声が響いた。
「金龍の言う通りだ。浮橋は金龍の側に仕える者だが、そなたは霊獣と共に歩むにふさわしい力を持つ者だ。その力は、霊獣師にこそふさわしい」
その言葉は、不安を射抜きながらも、深く温かい余韻を残した。
顔を上げると、宮様の真摯な眼差しが、まっすぐに私を映していた。
白虎が低く喉を鳴らし、尾を一度大きく振る。
まるで「信じろ」と背中を押してくれるように。
そして――宮様は、迷いなく言葉を告げた。
「鈴音。霊獣師にならないか? 霊獣頭として、そなたを迎えたい」
「……!」
息が詰まり、視界が一瞬にして揺らぐ。
想像もしなかった未来が、目の前に差し出されている。
驚きと、胸の奥からこみ上げる熱とが入り混じり、喉がひゅっと狭まって、言葉にならなかった。
私は思わず胸に手を当てた。衣の下で鼓動が跳ねている。でも嬉しいはずなのに、心の底では黒い影がもぞりと動いた。
わたしなんて……本当に、霊獣師になっていいの……? 浮橋の燁子と比べたら、あまりにも力が小さい……。
不安が喉を塞ぎ、声は掠れて震えた。
「……わ、わたしが……霊獣師になっても、いいのでしょうか」
自分でも情けなくなるほど頼りない響き。
けれど、その言葉がこぼれ落ちた瞬間、宮様がゆっくりと一歩を踏み出された。
衣の裾がさらりと床を擦る音がやけに鮮やかに響き、私の胸を打つ。
「鈴音だからいいのだ。……そなたでなければならぬ」
まっすぐな声音に、思わず息を止めた。
その瞳には、一片の迷いもない。私が長いあいだ欲していた「認める光」が、確かに宿っていた。
足元で白虎が小さく鳴いた。黄金の瞳が私を真っ直ぐに映し出し、迷うなと告げている。
柔らかな毛並みが私の足首をくすぐり、震える心を支える。
私は唇をぎゅっと噛みしめた。
胸の奥からせり上がってくる熱を、そのまま言葉にのせる。
「……私、霊獣師を引き受けます」
声は小さくとも、揺るぎない灯火のように力を帯びていた。
その瞬間、宮様の眼差しがやわらぎ、唇がわずかに緩む。
静かに、しかし力強く頷かれた。
「……よろしく頼む」
その瞬間――ふわりと、見えない波紋のように柔らかな氣の揺らぎが広がった。
はじめはかすかな気配だったのに、すぐに承香殿の影から、庭の木々の間から、光の粒をまとった影が次々に現れはじめる。
霊獣たちだ。
尾を振りながら駆け寄ってくるもの、羽を大きく震わせて煌めきを散らすもの、静かに頭を垂れ歩み寄るもの――。
みな一様に、目を細め、身体から柔らかな光をあふれさせていた。まるで嬉しさを隠しきれない子供たちのように。
胸の奥が熱くなり、両手を胸元でぎゅっと握りしめた。
足元にすり寄る白虎の温もりとともに、ひしひしと伝わってくる。
……本当に、受け入れてくれている……。
その実感が心を満たし、目の奥がじんわり熱を帯びていった。
そのとき、空気を震わせるように金龍の聲が降り注いだ。
「人の子らよ。我が霊獣たちを、頼むぞ」
低くも威厳に満ちた響きが、宮中の屋根瓦を鳴らし、石畳の大地をも震わせる。
その聲に応えるように、霊獣たちが一斉に仰ぎ見て、澄んだ鳴き声を重ねた。
次の瞬間――燁子を包み込む金の繭が、淡い光を放ちながら天へと浮かび上がる。
その傍らには、力尽きて横たわる蛟の黒い身が、静かに従っていた。
金龍は彼らを導くように、その巨大な身をゆるやかにたなびかせ、やがて虚空へとすうっと姿を溶かしていった。
残された空気には、光の粒子が静かに舞い降りる。
朝の風に混じって、きらめく欠片が私の頬をかすめ、指先に落ちては溶けていった。
それは祝福の名残のようで、ただ息を呑むしかなかった。
◆◆ ◆
朝の空気は、刃の背でそっと肌を撫でるように冷たかった。
薄く漂う霧が足元にまとわりつき、白んだ空の下、陽はまだ昇らず、世界は深い静けさに沈んでいる。
私は殿上童の姿ではない。霊獣寮で用意された、女性でありながら動きやすい簡素な装束。袂をきゅっと握り直すと、生地の感触が冷えて指先に沁みた。
「……ここで待っていて」
白虎の額へ掌をそっとあてる。毛並みの奥から伝わる温もりに、ほんの少し胸が緩む。
澄んだ金の瞳が、何かを言いたげに一度瞬いた。けれど、やがて彼は首を低く垂れ、地面に身を伏せたまま動かなくなった。その姿が、背中を押すようにも、引き止めるようにも見えた。
神泉苑の門をひとりでくぐる。
途端に、空気が変わる。
足音が霧に吸われ、耳に届くはずの音がすべて遠のく。肌の上に、結界の膜がすうっと這い、胸の奥にかすかな緊張が走った。
池のほとりまで来たところで、自然と足が止まった。
――いた。
水面の向こう、霧の薄衣をまとったような白い姿。
燁子が、水の上に浮かぶように座っていた。
風も鳥の聲もない世界で、ただ彼女だけが、こちらには向けぬ笑顔を浮かべている。頬の弧は柔らかく、目元は無垢そのもの――けれど、その笑みの底に隠された棘を、私は知っていた。
……あの笑顔。 子どものころ、何度も見た。
誰かを試すとき、何かを奪うときにだけ浮かぶ、あの形。
浮橋になった。あの子が、ずっと望んでいた通りに。
私は水辺へ一歩踏み出し、波紋も立てぬ水を隔てて彼女を見据える。
霧の向こうの燁子は、天を仰ぎ、微笑んだまま瞬きもしない。
「……燁子。浮橋になれて、本当に良かったわね」
声は静かに池へ落ちたが、水は揺れもせず、風も返さない。
燁子は依然としてこちらを見ない。
その笑みは、天のどこかにいる見えぬ誰かとだけ語り合っているようで、私の存在など初めからなかったみたいだ。
「……私、ずっと気づいていたのよ」
喉の奥がきゅっと詰まり、息が揺れる。
「あなたは、望んだものを手に入れるために、周りの人を微笑みで包み込んで魅了して……なんでもさせてきた。……わたしのお母さまも……」
声の震えは、冷えた空気のせいではなかった。
冷たい水に指先をそっと浸したように――胸の奥で、古い記憶がゆらゆらと波紋を広げていった。
それでも私は、息を整え、言葉を押し出す。
「……私、この時を、ずっと待っていたの。あなたが……壊れていくのを」
唇がわずかに震え、視界の端が滲む。頬に触れそうなほど近くにある涙を、必死でこらえた。
「待つことしかできなかった。何もできなかった……。わたしは、強くなかったから」
吐き出した瞬間、その情けなさが胸をえぐる。それでも、それが私の本当だった。
「燁子……私は、あなたにずっと怯えていた」
自分でも驚くほど静かな声だった。
「でも……白虎がそばにいてくれて、宮様が……わたしを信じてくれた」
喉の奥に溜まった熱を飲み込み、背筋を伸ばす。
「だから……ようやく、ここに立てたの」
霧の中、妹は何も返さない。
ただ、どこか別の時を生きるように、天を仰いで笑っている。
「待ち望んだ状況になったら、大声で笑うんだろうなと思ったけれど……そうじゃないんだね」
ふと視線を落とすと、胸の奥に小さな棘が刺さったように痛んだ。
「あなたのせいで失ったものも、たくさんある」
霧が冷たく頬をかすめる。
「けれど……もう、あなたのことを憎んだままではいたくない」
燁子はやはり、返事をしなかった。
その笑顔は、子どものころのまま。無垢に見えて、何かを飲み込む深さを湛えていた。
――ああ、この子は、やっと欲しかった場所に辿り着いたのだ。
そう思うと、胸の奥に安堵とも痛みともつかない熱がじんわり広がった。
「あなたを許すわ。そして……あなたのことを、思い出として置いていく」
声は、もう震えていなかった。
「浮橋として、頑張って。……わたしは、霊獣師として生きていく」
ゆっくりと膝を折り、小さく一礼する。
目を閉じた瞬間、池の上を渡るような微かな風が頬を撫でた。
私は静かに背を向けた。
足音は淡く、しかし一歩ごとに確かだった。
もう――振り返らない。
神泉苑の門をくぐった瞬間、胸の奥に張りついていた糸が、ぷつりと切れたように緊張がほどけた。
霊的な結界の圧がすっと消え、肩がわずかに落ちる。朝の風が頬を撫で、指の先まで新しい空気が流れ込む。
そのとき――白虎が、小さく低く鳴いた。
「……!」
はっとして顔を上げる。そこに、ひときわ静かな気配が立っていた。
――宮様。
心臓が、ひとつ大きく脈を打った。
どうしてここに、と問いかける前に、胸の奥に灯る温かな光を感じた。それは驚きではなく、確かに待っていた気配に包まれる感覚だった。
「……お待たせしました」
言葉を紡ぐと、宮様は黙って、深くうなずいた。
微笑みはない。それでも、その沈黙がなぜか胸の奥を温める。
白虎が足元に身を寄せ、鼻先で足の甲をやさしく押す。
私はその柔らかな額を撫で、温もりを掌に確かめながら、ゆっくりと宮様へ歩み寄った。
東の空がわずかに白み、朝の光が石畳の端を淡く照らし始めている。
「そなたが行くと思っていた」
静かで真っ直ぐな声が、空気を震わせた。
私はふっと微笑む。
「はい。わたし自身のために……あの子に、会う必要がありました」
「そなたはあの場で、きちんと向き合った。……立派だった」
その言葉が、やさしい雨粒のように胸の奥に落ちて広がる。
私はほんの少し視線を落とし、息をひとつ、静かに吐いた。
「……でも、少しだけ悔しいんです」
声に出した瞬間、胸の奥がちくりと痛んだ。
「あの子のせいで、たくさんのことを失ったから」
足元で白虎がぴくりと耳を動かし、じっとこちらの聲に耳をすませるように身じろいだ。その温かな体温が、無言の励ましのように伝わってくる。
「でも……それを抱えたままでは、前に進めない気がして」
ふっと顔を上げると、宮様が目を細めてこちらを見ていた。そのまなざしは鋭さを帯びながらも、どこか深い思慮を含んでいる。
「悔しがっていい」
静かな声だった。
「潤氣とは、清らかさだけではない。怒りも、痛みも――そなたの力の一部だ」
その言葉が、胸の深い場所にじんわりと落ちていく。氷のように固まっていた感情が、ゆっくりと溶けて流れ出すのを感じた。思わず肩の力がほどけ、呼吸がひとつ楽になる。
ようやく――ほんの少しだけ、顔を上げられた。空の端が淡く白み、夜の名残を押しのけていく。
「そなたは、もう誰かに導かれる存在ではない」
宮様の聲が、朝の静けさにしみわたる。
「自ら道を選び、霊獣たちを導ける」
私は力強くうなずいた。
「……私も、ようやくそう思えるようになりました。私なりの役割がある」
宮様の瞳が、やわらかさを帯びる。その光に胸の奥が熱くなる。
「霊獣たちの潤氣は、そなたの中で穏やかに育っている。金龍でさえ、それを認めた」
私は小さく息を整え、正直な気持ちを口にした。
「それでも、あの時……信じてくれたのは、宮様でした。ありがとうございます」
その言葉に、宮様の目がふっと和らぎ、口元にかすかな微笑みが浮かんだ。
「礼などいらない。私は、そなたの潤氣に救われた」
――ああ。
その微笑みに触れた瞬間、胸がふわりと熱を帯びていく。
少しの沈黙ののち、彼は静かに言った。
「これからは……私も、そなたとともに歩みたい。導く者としてだけでなく、一人の男として」
頬に、熱がふわりと広がった。鼓動がせり上がり、声が出せない。
白虎が隣で、満足そうに目を細め、静かに喉を鳴らす。
木々の間から差し込んだ朝の光が、世界をやわらかに染め始めた。
その光の中で、胸に芽吹いた想いが確かな形をとっていく。
――これからは、自分の足で歩いていける。
その隣に、彼がいてくれるのなら。
神泉苑を背に、私はゆっくりと歩き出した。
隣には白虎。柔らかな毛並みが朝の光を淡く受け止め、ひとつひとつの毛先まで輝いて見える。
そのすぐ脇には――宮様がいた。
言葉はなかった。けれど、沈黙がこれほどまでに穏やかに心を包むものだと知ったのは、きっと今日が初めてだった。
草を踏む足音が、ふたりと一頭を静かにつなぎとめる。規則正しく響くその音に、胸の奥がしだいに落ち着いていく。
昔は、この人の隣を歩くなんて、考えたこともなかったのに……。
そう思ったとき、不意に頬を撫でるような風が吹き抜け、髪がふわりと揺れた。白虎が鼻を鳴らし、尾をぱたぱたと振る。その仕草がまるで、この静かな朝を祝福してくれているように見え、思わず口元がやわらかくなる。
そのとき、宮様の声が低く落ち着いた響きで耳に届いた。
「……霊獣寮の再編も急がねばな」
唐突な言葉に、足がわずかに止まりかける。
続いた声は、揺るぎない静けさを帯びていた。
「新しい霊獣師の筆頭として、そなたにも手伝ってもらおう」
「……えっ?」
思いがけない言葉に、私は立ち止まり、宮様を見上げてしまった。
「わ、わたしで……いいのですか?」
驚きと戸惑いが混じり、声がわずかに上ずる。胸の奥で心臓が跳ねる音が、自分でもはっきりわかった。
宮様は、まっすぐに私を見つめて言った。
「――誰よりもふさわしい。そなたほど霊獣の心に寄り添える者はいない」
その言葉が胸に落ちた瞬間、奥底でぽうっと温かな灯がともる。羞恥でも、戸惑いでもない。
ただ、自分という存在を、確かに認めてくれる声。その事実が、心を静かに震わせた。
「ありがとうございます。……これからも、どうかよろしくお願いします」
深く頭を下げると、宮様は静かにうなずいた。
そして次の瞬間――。
「こちらこそ、鈴音」
名を呼ばれただけなのに、胸の奥に小さな灯が芽吹く。
きっとそれは、まだかすかで頼りないけれど……恋という名の、はじまりの想い。
東の空が白みはじめ、雲の切れ間からやわらかな朝日が差しこんでくる。宮中の屋根が金色に染まり、世界がゆっくりと目を覚ましていく。
私はふと足を止め、神殿の方を振り返った。
あの奥には、浮橋となった燁子がいる。もう、決して届かぬ場所に行ってしまった妹。
胸の奥にちくりと痛みが走るけれど、涙は落ちなかった。
白虎がくるりと私の足元を回り、誇らしげな瞳で見上げてきた。柔らかな尾が草を揺らし、凛とした氣を纏っている。
「これからが本当の始まりだ」
宮様の低い声が、朝の静けさに溶けて響く。
私は小さく微笑み、うなずいて応えた。
三つの足音が重なり、やがてひとつの道を進んでいく。
朝日が昇る、その先へ。まだ見ぬ世界の方へ。
背後で、やわらかな風が頬を撫でた。
遠くで霊獣たちの潤氣がふわりと揺れた気がした。
それはきっと――私に託された道を、祝福する声だった。