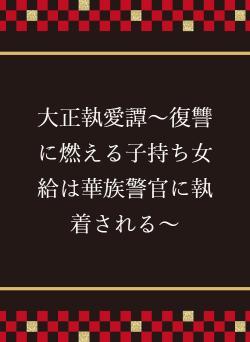私は白虎とともに金龍の痕跡を辿ったのち、静かに宮様のあとを追い、殿上の間へと戻ってきた。
「戻ってきたのか」
私たちに気が付いた頭中将様の声に疲労がにじみ出ていた。
宮様が一歩、畳の上に足を進めた。その背筋の伸びた立ち姿に、私は自然と息を呑む。
「神泉苑へ調査に向かいたく存じます。金龍の氣は、あちらへ流れていました」
その声は、深く澄んでいて、まるで風を割るように真っ直ぐだった。
数瞬の沈黙のあと、頭中将様は眉間に深く皺を寄せ、短く言葉を落とした。
「そうか。帝を頼む。そなたに一任するよ」
簡潔で揺るぎのない声。けれどその底に、かすかに滲んだ感情があった。責任という名の重さと、抗えぬ焦りが、静かに揺らめいていた。
神泉苑……この國にとって、最も清き地。その氣が乱れているというの……?
胸の奥に、ひやりとした冷気が走る。名を思うだけで、空気の質が変わった気がした。まるで、そこに触れてはならぬものが潜んでいるかのように。
宮様は静かに一礼をすると、踵を返した。私に視線を向け、軽く頷く。迷いのない眼差しに、私は心の奥をそっと正された気がした。
そのまま、私たちは殿上の間を後にし、霊獣寮へと急いだ。
霊獣寮の門をくぐると、朝の光が静かに差し込み、建物の白木が淡く輝いていた。玄関の脇には、宗直様が箒を片手に、掃除道具を片付けている姿があった。
「あ、宮様。お戻りでしたか!」
ぱっと明るくなる宗直様の声。思わずこちらの頬も緩みそうになる。
けれど、宮様はすぐに要件を告げた。
「宗直、神泉苑へ向かう。補佐として同行せよ」
一瞬、宗直様の目が大きく見開かれる。驚きと緊張が入り混じった気配——だがそれはすぐに、はにかむような笑みに変わった。
「はいっ!」
返事と同時に、宗直様の視線が私に向けられる。少し照れたような表情で、軽く会釈してくれた。
そんななか、宮様は立ち止まり、静かに言葉を紡ぎ始めた。
「神泉苑は、異界と地が繋がる龍穴。かつて龍神が住まいした場所と伝えられている」
その声音は淡々としていたけれど、ひとつひとつの語が、胸の奥にじんわりと沈んでいった。目に見えぬ重みが言葉に宿っていて、私の心に波紋を広げる。
「霊獣の氣が乱れる場所だ。うまく帰ってこられるとは限らぬ。鈴音……おまえの白虎が頼りだ。そして宗直――おまえは鈴音よりは劣るが、霊獣に好かれやすい。その資質を使うときだ」
宗直様が、すぐに反応した。
「任せてください!」
胸を張り、まっすぐな目で宮様を見つめるその姿は、まるで少年のような無邪気さと責任感が入り混じっていて、少しだけ空気が和らいだ気がした。
そして、私たちは出立した。
私たちは馬を使わず、静かに歩き出した。
白虎の足音は響かず、私の呼吸も、まるで風の音に溶けるようだった。
選んだのは、人目を避けるための宮中の裏道。
それは、表通りの華やかさとはかけ離れた、静まりかえった路だった。瓦屋根が重なり合う隙間から、朝の光が薄く差し込んでいるが、その光はまるで夢の残滓のように淡く、どこか現実離れしていた。
苔むした石垣、竹垣の隙間から伸びる野の草、しんとした闇の残る路地。空を見上げても、陽の光はどこか翳って見えた。ひとつ、またひとつと足を進めるたび、まるでこの世ではない場所へ踏み込んでいるような、不思議な感覚に囚われた。
神泉苑が近づくにつれて、空気が変わっていくのが分かった。
ただ冷たいのではない。何か、見えない膜のようなものが空間を覆い始める。その膜が、皮膚の上をそっと撫でるようにして、じわりと足元から這い上がってくる。冷えというより“氣”そのものが、肌に触れているような……そんな感覚。
次の瞬間、胸の奥に、ふっと小さな波紋が広がった。
白虎の氣が、呼応するように脈を打つ。微かだけれど、はっきりと私の中で震えている。
氣ではない。これは、呼び声——。
……なにか、いる。すぐ近くに。白虎も、呼ばれてる……
私は思わず、手のひらを握りしめた。白虎は沈黙していたけれど、私の心に届くその感覚は、疑いようもなく明確だった。まるで、胸の奥に灯る火が、見えない風に揺れたような感覚。
前を歩く宮様の背には、気配のようなものが静かに立ち昇っていた。
宗直様も、ふだんの陽気さはどこかへ消え、無言のまま歩いている。肩の辺りに、ぎこちなさがにじんでいた。
やがて、石畳の先に開けた景色が現れた。おそらくここが神泉苑だ。
◆◆ ◆
神泉苑の敷地に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。
音もなく、色もない。ただそこにあるだけの空間——それなのに、全身を包む氣の密度が、たしかに違っていた。
古の苑を囲む森は、薄曇りの空を背景に、墨絵のように静まり返っている。鳥も鳴かず、葉も揺れない。風が通っていないはずなのに、どこか、ざわりとする氣配が肌を撫でた。
正面には、池へと続く石橋。年月を重ね、角が丸くなったその橋は、苔むして深い緑をまとっていた。まるで千年の眠りからまだ目覚めず、今も時の流れを拒んでいるかのように、ひっそりと佇んでいる。
池の水面は静かで、空を映しながらもどこか深く濁って見えた。木々に囲まれたその空間全体が、息をひそめている。音も、光も、時間さえも、すべてが止まっているように思えた。
……ここは、まるで時間が止まっているみたい。
胸の奥で、ぽつりと呟きがこぼれ落ちた。そのとき、私の前をすっと、ひときわ長い影が横切る。
宮様だ。立ち止まり、池の水面を見つめている。
「二人とも、何か感じるか」
低く、けれど遠くまで届くような、澄んだ声音だった。
私は胸元に手を当て、そっと目を閉じる。まるで耳の奥にまで静けさを浸透させるように。
……そのとき、宮様の声が、すぐそばで響いた。
「金龍は……おそらく池にいる。どこかにいるはずだ。探すぞ」
その声は、確信と迷いをないまぜにしたような、複雑な響きを持っていた。
と、その瞬間。
池の水面が、不意に大きく盛り上がった。
次の瞬間――爆ぜた。
轟音とともに、白金の奔流が天を裂き、眩しさに目が焼けそうになる。
「っ――!」
声にならぬ叫びが喉を突き抜け、思わず腕で顔を覆った。隙間から覗いた視界には、乱反射する無数の鱗。ひとつひとつが刃のように煌めき、視界を支配する。
空気が唸りをあげた。
突風――いや、鋭い爪そのものの氣が、容赦なくこちらへ迫る。
息が詰まる。体がすくむ。
「避けろ!」
宮様の声が、怒号のように耳を打つ。
直後、熱風が頬を裂き、髪がばさりと浮いた。ほんの一瞬でも遅れていたら……その爪に切り裂かれていた。背筋に冷たいものが走る。
ぱちり、と火の粉が散った。
炎の羽音。
朱の光が私の横を駆け抜ける。
「……鳳凰!」
宮様の掌から解き放たれた潤氣が紅蓮となり、空を裂いて舞い降りる。
炎を纏った鳥の翼が広がり、金龍の爪の氣を受け止めるように広げられた。
耳をつんざく衝突音――光と炎がぶつかり合い、視界が白と朱に塗りつぶされる。
「狛犬!」
宗直様の声が、鋭い刃のように響いた。
大地を揺らすような咆哮。
黒と白の影が池の縁を駆け抜け、飛び出す。
狛犬だ。石を砕くほどの牙を剥き、金龍へと飛びかかる。
氣と氣が噛み合い、火花のように弾けた。
押し寄せる圧に、空気そのものが震えている。肺が縮み、息が思うように入ってこない。
熱、衝撃、轟音――それらすべてが一度に押し寄せ、体が小さく震えた。
これが……金龍の力……! このままじゃ――!
私は息を詰め、立ちすくんだ――その刹那。
金龍の尾が弧を描き、唸りをあげながらこちらへ薙ぎ払われる。
「っ――!」
足がすくみ、喉がひきつる。逃げようと頭で叫んでも、体が凍りついて動かない。
だが、衝撃は訪れなかった。
目の前に、白の影が飛び込む。
どん、と大地を揺らす衝突音。
白虎――。
その巨躯が私の前に立ちふさがり、しなやかな四肢で踏ん張る。
鋭い爪が金龍の尾を受け止め、氣と氣がぶつかり合って火花のように散った。
衝撃の余波が頬を打ち、息が奪われる。
「な、な、な……なんで……こんなところに、白虎が……!」
宗直様の声が裏返った。
その目は見開かれ、信じられないものを見たように震えている。
足が半歩、思わず後ろに引かれた。
白虎が低く唸る。その咆哮は地を揺らし、胸骨の奥まで響いてきた。
鳳凰の炎が空を裂き、狛犬の牙が閃き、そして白虎の氣が唸りを上げる。
三つの霊獣が金龍に挑み、池のほとりは光と影の奔流に呑まれた。
耳をつんざく轟音と熱気に、息を吸うことさえ苦しい。
胸がぎゅっと締めつけられる。
だめ……こんなの、望んでない……! 戦わせたいわけじゃないのに……!
「やめて――!」
自分の声が嵐に吸い込まれていく。それでも必死に叫んだ。
爪と尾が閃き、白虎が踏みとどまり、鳳凰が炎を散らし、狛犬が牙を立てる。
氣と氣が衝突し、池のほとりは光の奔流に呑まれていた。
「私たちは……あなたと戦いたいんじゃない!」
喉が裂けそうに痛む。けれど言葉は止まらない。
「もう……誰も、ひとりにしたくないんです。あなたも……苦しかったでしょう?」
金龍の瞳が、ちらりとこちらを向いた。
その視線に射すくめられ、膝が震えた。
けれど、後ろには仲間たちが必死で支えている。
私は一歩踏み出した。
「だから……一緒に帰りましょう。宮中へ。帝も……霊獣たちも……あなたを待っています!」
その言葉と同時に、胸の奥から潤氣が溢れた。
光がひと筋、金龍へと伸びる。
――触れた。
金龍の瞳がかすかに揺らぎ、荒々しい氣の奔流が一瞬だけ弱まる。
その隙間から、言葉ではない。“音なき聲”が、心の奥に直接、流れ込んでくる。
——霊獣たちは、香によって氣を乱され、帝の氣は断たれた。
まぶしい光が、突然、胸の奥で弾けた。
私の知らない記憶が、次々に流れ込んでくる。
暴れ狂う霊獣たち。
苦しげに呻く白虎。
その傍らで、倒れ伏す帝の姿——
言葉にならない衝撃が、私の心を揺さぶった。
けれど、それは終わりではなかった。もうひとつ、聲が重なる。
——浮橋がいたなら、氣の乱れは、ここまでにはならなかった。
「……浮橋……?」
その言葉が、胸の奥からぽつりと零れた。
私は、金龍を見つめながら、呟くように口にした。
「……燁子は、“浮橋”じゃないんですか……?」
その瞬間——空気が、かすかに揺れた。
金龍の瞳が、わずかに揺らいだように見えた。
その中に、確かに一瞬、悲しみのような色が灯った。
返事はなかった。けれど、その沈黙は、確かに「否」と言っていた。
◆◆ ◆
金龍の氣が渦を巻いた。
光のうねりが視界を満たしていく。白金の霧が静かに立ちのぼり、私のまわりの現実が、ゆっくりと遠ざかっていった。
音が消えた。風も、匂いも、重力さえも。
ただ、ひとつ——心の奥にふれた、あたたかな掌のような氣だけが残っていた。
不安よりも、懐かしさが胸に広がっていく。これは……記憶?
霧の向こうから、景色が現れた。
朝の光がうっすらと差し込む、静かな庭だった。整えられた白砂の庭に、長い影が伸びている。張り詰めた空気のなか、私は息をひそめるように立っていた——いや、私はここにいる。でも同時に、誰にも気づかれていない。
視線の先。庭の中央に、小さな背中があった。
白い布をまとい、地に膝をついている少女。
まだ十にも届かぬだろう、小さな肩がかすかに震えていた。
……燁子。
気づけば、私は名前を呟いていた。
間違いない。あの後ろ姿は、幼い頃の彼女だった。
その肩に、寄り添うように小さな龍がいる。
鱗はまだ淡く透けていて、澄んだ潤氣が肌に触れるたび、やわらかな光を散らしていた。
蛟じゃない……? あれはまだ、神聖な龍の氣……。蛟は龍の幼体だったの?
燁子の背に、少女らしい緊張と、覚悟が混ざっているのが見えた。顔は伏せていても、氣の流れがまっすぐだった。
その場には神祇官たちが整列し、祝詞が低く響いていた。
左右には、雅な装束に身を包んだ貴族たちの姿。そのなかで、私はひとりの青年に気づく。
宮様……?
まだ幼さを残した面差しだったけれど、その背筋は今と同じように、真っすぐだった。
彼の視線は、静かに燁子の方へと注がれている。
燁子は——その目を、ちらりと彼に向けた。
ほんの一瞬のことだった。けれど私は、見逃さなかった。
最初は、尊敬のようだった。けれどすぐに、それが別のものへと変わる。
憧れ——いや、それ以上の、恋心。
子どもらしい無垢さに混じる、微かな執着。
燁子の視線が離れたとき、私は胸の奥がざわつくのを感じた。
それは、儀式の中心にある氣の流れが、微かに濁った瞬間だった。
空が淡く染まり始める。
雲の切れ間から、金龍の氣が降りてくる。
天から静かに垂れた光の帯が、燁子に触れようとした、その刹那——
ぴたり、と。
氣が、止まった。
空気がふっと冷える。
何かが、途中で切れたような感覚が、肌を這った。
私の中にまで、びりりと走る“拒絶”の感覚。
燁子は顔を伏せたまま、ただじっとしていた。まるで何も感じていないかのように。
けれど、金龍の氣は、もう彼女へは降りてこなかった。
聲が響いた。けれど、耳ではなく、胸の奥で。
——「恋心を抱く者は、龍に仕える“浮橋”とはなれぬ」
その言葉と同時に、金龍の視線がふいに逸れた。
視線の先には——宮様がいた。
金龍の瞳は、まるで「選び取る」ように、彼を見つめていた。
——「あの者を、浮橋を導く“導く器”とした」
……あのとき……金龍は、宮様を……。
氣が揺れる。
儀式の氣脈がふたたび波打ち、景色がかき消えてゆく。
次に現れたのは、閉ざされた空間だった。
帳が垂れ、香の煙がゆるやかに漂う薄暗い広間。
いくつもの公卿たちの姿が、畳に膝をつけ、顔を寄せ合っていた。
「……儀式の失敗は、外には漏らすな」
「金龍は、拒絶などしておられぬ。ただ、静かにお鎮まりになっただけだ」
「燁子殿こそが、浮橋として最もふさわしい」
「記録など、整えればよい。形があれば、誰も疑わぬ」
低く、湿った声が、次々と交わされる。
誰が何を決めたのか、明確には分からない。けれど、その場にいた全員が“同じ方向”を向いていた。
……違う……金龍は、拒んでいた……。
言葉に出せない。ただ、心の中で否定が渦を巻く。
燁子は、選ばれてなどいなかった。けれど、選ばれたことに“された”。
目の前で、白く染まっていた光景がぱちん、と弾けて消えた。
はっと息を呑む。視界が戻る。
耳をつんざく轟音、熱を帯びた風、飛び散る火花。夢の底にいたはずの私の目の前で、まだ戦いは続いていた。
鳳凰の炎が舞い、狛犬の牙が閃き、白虎の咆哮が夜を震わせる。
金龍の尾が振り下ろされ、大地ごと抉る氣が襲う。
……これは……まだ終わってない!
私は胸を押さえ、声を振り絞った。
「待ってください! もう戦わないで!」
必死の叫びに、ほんの一瞬、霊獣たちの動きが揺らいだ。
だが――
「鈴太っ!」
誰かの叫びが、耳を裂いた。
次の瞬間――影が横から襲いかかってきた。
牙を剥き、爪を閃かせる狛犬。その姿を目にした瞬間、全身が凍りついた。
「宗直……さま……?」
信じられない。なぜ、狛犬が私に――。
視界の端に、宗直様の顔が映った。
驚きでも焦りでもない。押し殺したような決意が、わずかに揺らぐ瞳の奥に覗いていた。
「やっ……!」
声を上げるより早く、狛犬の巨体がぶつかった。
骨が軋むほどの衝撃。肺の中の空気が一瞬で奪われ、私は宙へと弾き飛ばされる。
「きゃ――っ!」
視界がひっくり返る。燃える炎も、唸る金龍も、すべてが逆さに混じり合い――背中に、氷のような冷たさが走った。
池の水面が裂ける。
どぼん、と重たい音がして、世界が一瞬で暗い底へと反転する。
水が耳を塞ぎ、喉に冷たさが押し込まれる。
必死に手足を動かすけれど、濡れた衣が絡みつき、重りのように沈めていく。
どうして……宗直様……!
問いは声にならず、泡となって弾ける。
光が遠ざかり、金龍の咆哮も、白虎の叫びも、狛犬の唸りも――すべてが水に呑まれていった。
ただ暗い深みへ、ひたすら引きずり込まれていく。
水の冷たさに肺を掴まれたみたいで、息ができない。重たい衣が体にまとわりついて、手足を動かしても水の底に引きずり込まれていく。
だめ……苦しい……!
そのとき――腕をぐっと抱き寄せられた。
水の中でさえはっきりわかる強い力。顔を向けると、揺れる水の向こうに宮様の輪郭が見えた。
「……っ!」
言葉にはならない。けれど、必死に伸ばした手を宮様が掴んで、ぐっと体ごと引き寄せてくる。
水をかき分ける力強い蹴り。視界に泡が弾け、次の瞬間――眩しいほどの光と冷たい夜気が頬を打った。
「ぷはっ……!」
喉が裂けるように空気を吸い込む。肺が燃えるみたいに熱い。宮様の腕の中で必死に咳き込みながら、なんとか息を整えた。
冷たい水の重みから解き放たれるように、私は宮様の腕に抱え上げられ、岸へと運ばれていった。
ぐっしょりと濡れた衣が肌に張りつき、体温がどんどん奪われていく。息はまだ浅く、胸の奥がひゅうひゅうと鳴って苦しい。
その時、轟音が耳を打つ。
振り返った瞬間、目を覆いたくなるような光景が広がっていた。
金龍の巨大な尾が、怒涛の勢いでうねり迫る――。
その刹那、白い影が飛び込んだ。
白虎だ。
私と宮様の前に立ちふさがり、鋭い爪で龍の尾を受け止めた。氣と氣がぶつかり合い、火花のように散って夜空を裂く。
「白虎……!」
思わず息を呑む。震える声が漏れた。
さらに、朱の炎が闇を払った。
宮様の鳳凰だ。炎の羽根を広げ、烈火のような光で金龍を包む。
火の粉が散り、赤と白の輝きが池のほとりを覆った。
咆哮。衝突。氣の奔流。
世界そのものが震えているようだった。
私は宮様の腕にすがりつき、目を開けていられないほどの閃光と熱風の中で、ただ必死に呼吸を繰り返していた。
炎と光の奔流のただ中で、胸の奥がじんわりと熱を帯びているのに気づいた。
……まだ、繋がってる……?
さっき水底で触れた金龍の氣の残滓が、潤氣を伝って私の中に微かに残っている。鼓動に合わせて脈打つように、かすかな波が広がっていった。
その瞬間――金龍の瞳が、こちらを振り返った。
氷のような光を湛えていたはずの眼差しに、一瞬だけ迷いの影が揺らめいた。
うねる尾が止まり、空気の緊張がふっと緩む。
「……」
言葉はない。けれど、胸の奥に響いたのは、戦いに意味を見出さぬ嘆息のような氣の揺らぎ。
それは「人と争う時ではない」と告げるようでもあり、ただ深い孤独を吐き出すようでもあった。
次の刹那、金龍は大きく首を仰け反らせ、夜を揺るがす咆哮を轟かせた。
空気そのものが震え、鼓膜が裂けそうになる。胸が締めつけられるほどの声――怒りでも、悲しみでもない。もっと遠い場所に向けた、叫び。
その巨躯が白金の光をまとい、池の水面を巻き上げながら天へと舞い上がっていく。
鱗が煌めき、夜空を裂くように遠ざかる。
「……!」
私はただ、呆然とその背を見上げていた。
確かに戦いは終わっていない。けれど、今ここで命を奪い合うことを金龍は選ばなかった。
残響のように胸に震えが残り、私は震える唇をかすかに噛んだ。
また……必ず、会う……。
「大丈夫ですか、宮様!」
宗直様がこちらへ走りこんできた。そんな宗直様へ、鋭い声音が突きつけられる。
「……なぜだ。なぜ狛犬が鈴太を狙った」
空気が一瞬で凍りついた。
いつもの柔らかな響きを持つ宮様の声が、今は刃のように冷たい。
宗直様の顔が見る間に青ざめていく。唇がわなないて、かろうじて声が絞り出された。
「す、すみません! 狙ったなんてとんでもない! 鈴太が……足を滑らせたように見えて、助けようと……!」
その言葉が耳に届いた瞬間、胸の奥がずきりと痛んだ。
――違う。あの狛犬は確かに、私めがけて突き飛ばしてきた。
けれど声にならない。喉の奥が冷たさと恐怖に塞がれ、私は宮様の衣に縋るように小さく震えるだけだった。
そのとき、ふいに自分の身体の感触に気づく。
濡れた衣が肌にぴたりと張りつき、胸の線も腰の曲線も、布越しにあらわになっている――。
……だめ! こんな姿を見られたら……!
慌てて腕で胸元を押さえる。けれど水に透けた布は思うように隠してくれない。
焦りに心臓が乱打する。宗直様に、女だと知られてしまう――その恐怖が、金龍に襲われた時よりも鋭く胸を突いた。
その予感はすぐに現実になった。
宗直様の目が、私の濡れた姿に釘付けになる。血の気が引いていくように顔が強張り、言葉が喉に詰まったようにこぼれた。
「そ、その姿……鈴太……おまえ……女なのか……」
その言葉が夜気を震わせ、私の耳に突き刺さる。
その刹那、宮様の腕が私をさらに強く抱き寄せた。私を覆うように立ち、宗直様を射抜く鋭い眼差しを向ける。低く、鋼のような声音が落ちた。
「……今夜見たことは、すべて忘れろ」
返事を待つまでもなく、その言葉が空気を支配した。
「……はっ」
宗直様はその場に膝をつき、青ざめた顔で短く答えた。
私の方を見ることもできず、ただ数歩、後ずさるようにして姿を遠ざかった。
次の瞬間――あれほど荒れ狂っていた氣の嵐が、ふっと霧が晴れるように消え去った。
耳に残るのは、水の雫が滴り落ちる音と、自分の荒い息づかいだけ。
金龍が去ったあとの静寂は、かえって胸に重くのしかかり、張りつめていた背筋が急に力を失った。
「鈴太!」
名を呼ばれ、私は顔を上げる。すぐそばに、宮様の瞳。
その眼差しが、先ほど宗直様へ向けられていた冷たさとは違って、ひどく切実で――。
次の瞬間、私は強く抱き寄せられていた。
濡れた衣の冷えとは対照的に、宮様の胸の奥から伝わる熱。
それに触れた途端、張り詰めていたものが解けて、力が抜けていく。
震える指先さえも包み込むような腕の中で、ようやく「生きている」と実感した。
――そのとき。
白く、穏やかな氣が私の背を撫でた。
振り返らずともわかる。白虎だ。姿は見えないのに、確かに寄り添ってくれている。
……守ってくれている……。
胸の奥に、熱とも涙ともつかないものが込み上げる。
もう抗う気力もなく、私はその氣に、そして宮様の温もりにすべてを委ねた。
視界が静かに揺らぎ、闇がやさしく滲み広がっていく。
最後に感じたのは、抱きしめる腕の確かさと、白虎の氣が寄り添う安らぎだった。
◆◆ ◆
夢の底に沈んでいたのか、それとも、遠い海のなかを漂っていたのか――。
そんなぼやけた感覚の奥から、ふっと、意識が浮かび上がった。
瞼をわずかに開くと、見知らぬ天井が静かに広がっていた。
御簾の向こうから、やわらかな朝の光が射し込み、室内の空気を金色に染めている。
音も匂いもやさしく、胸の奥をじんわり温めるような空間――どこか、懐かしさすら混じっていた。
……ここは……?
輪郭の定まらない思考のまま、首をゆっくりと巡らせる。
すると、額にそっと触れるものがあった。布のような……けれど、人の手のぬくもりも感じる。
隣には、年配の女房が座っていた。しわの浮いた手で、古びた手巾をやさしく私の額にあてている。見覚えのある、あの穏やかな顔――たきさんだ。
「まあ……目を覚まされたのですね。よう生きていてくださいました」
微笑む声が、やわらかく耳に届く。
その一言で、私はようやく、自分が生きているのだと知った。
「わたし……いったい……」
「姫様は三日ほど眠り続けておられましたよ」
「……え、三日も!?」
思わず声が大きくなる。けれど自分の声はかすれていて、驚きがじわりと現実味を帯びていく。
「すぐに、お知らせして参ります」
たきさんは静かに立ち上がり、畳を踏む足音も軽やかに、廊下へと駆けていった。
その背中を目で追いながら、私は布団の中で小さく息をついた。
胸の奥には、まだ遠い夢の波の余韻が、かすかに揺れていた。
廊下の向こうから、畳を踏む足音が二つ。やがて御簾がするりと持ち上がり、たきさんの後ろに――宮様が現れた。
いつものきちんと整えられた姿とは違い、髪は乱れ、衣の裾がまだ湿っている。私を見るその瞳だけが、変わらず真っ直ぐだった。
慌てて身を起こそうとした瞬間、力が抜けて体が傾く。
ふっと支える腕の感触。宮様だ。
「大丈夫か」
耳に届く声は、低く抑えているのに、揺れが混じっていた。
「……はい。すみません、ご心配を……」
掠れた自分の声が情けなくて、視線を落とす。
「無理もない。三日も眠り続けて……生きた心地がしなかった。薬師を呼ぼう」
肩を支えていた手が離れ、たきさんが代わりに寄り添ってくれる。宮様はそのまま私のそばに座り込んだ。
「楽にしてくれ。少し、話がしたい」
「あ……」
神泉苑の光景が、一気に胸の奥まで押し寄せる。冷たい水、白虎の咆哮、そして――
「……宗直様に、気づかれてしまいました」
その名を告げると、宮様の眉がほんのわずかに寄った。
「あれは仕方ない。そなたのせいではない。宗直には釘を刺しておいた」
言葉を聞きながらも、あの時の感触が消えない。背に走った衝撃、振り返る前に見えた宗直様の視線――一瞬の揺れと、逃げるような足の動き。
胸の奥で、水面がゆらりと波を立てた。
「……金龍とは、何を話した」
宮様の声が、静かに、しかし逃げ場を塞ぐように落ちてきた。
喉の奥がひりつく。私は息を整え、神泉苑で見た光景を、言葉にすくい上げていった。
――潤氣擾乱香に狂った霊獣たち。
――氣を断たれ、崩れるように倒れた帝の姿。
――そして、金龍の聲。「浮橋がいれば、このようなことにはならなかった」と。
指先がじんと熱くなる。あの時、どうしても訊かずにはいられなかった。
「……燁子は、本当に浮橋なのかって……」
唇が震える。
「金龍は……戻るとは言いませんでした。ただ……私の聲に、応えてくれた気がして」
宮様は、しばし目を伏せたまま沈黙した。拳を膝の上でゆっくり握り込む。やがて、その眼差しがまっすぐこちらを射抜いた。
「……浮橋のこと、本当の話なのですか?」
自分でも驚くほど、声が細くなっていた。
低く、重い頷き。
「……ああ。本当だ」
その瞬間、部屋の空気が少し冷たくなった気がした。
宮様は視線を落とし、ゆっくりと言葉を紡いだ。
「四年前――浮橋を決める儀式の日だ。本来なら、あの日に浮橋は生まれるはずだった。だが……金龍は誰も選ばなかった」
御簾越しの光が、彼の横顔を薄く縁取る。
「それを“失敗”と見なした公卿たちは、國が乱れるのを恐れた。だから……金龍の意志を無視し、燁子を浮橋に据えた。記録にも残らぬ、密やかな決定だ」
言葉が、胸の奥まで深く沈んでいく。息をするたび、問いがひとつ、またひとつ、泡のように浮かび上がった。
「……では、本物の浮橋は、どうやって生まれるのですか?」
問いかけると、宮様はすぐには答えなかった。
私の問いに、宮様はゆっくりと顔を上げた。
御簾越しの朝の光が、その瞳の奥で淡く揺れる。
「“導く器”は……金龍に選ばれた“器”だ」
言葉を選ぶように、低く落ち着いた声が続く。
「浮橋になる者を導き、指名する。自らの感情も意志も押さえ込み、ただ神意だけを伝える存在だ」
その響きが、胸の奥にじわりと沈んでいく。
「神意を伝える存在……」
口の中でそっと転がしながら、気づけば次の言葉が漏れていた。
「では……今、“導く器”は、どなたなのですか?」
短い沈黙。外の気配さえ遠く感じられたとき――
「……私だ」
「え……」
息が喉にひっかかる。思わず、その横顔を探してしまった。
いつもの冷ややかな静けさの奥に、一瞬だけ揺らいだ影――それは見間違いだったのだろうか。
「幼い頃、“器”として選ばれた。だが……」
宮様は視線を落とし、指先で袂の端をひとつ、ゆっくり握った。
「私はまだ、“導く器”としての指名を果たしていない。ゆえに――浮橋はいない」
胸の奥に、ことりと小石が落ちるような音がした。
「じゃあ……燁子は、本当に浮橋ではないのですね」
「ああ。そうだ」
答えを聞いた瞬間、胸の奥がひやりとする。燁子の姿、そして儀式の光景が脳裏をかすめた。
でも、その向こうに――私の目の前で静かに座る宮様の姿が重なる。
感情を押し殺したようなその横顔。
まるで心の奥まで固く封じられているようで、思わず見つめてしまう。
「……ずっと……そうやって、心を抑えてこられたのですか?」
言葉にしてから、自分でも胸が少し痛んだ。
「感情も意志も抑えられて……苦しくはないのですか?」
宮様は目を伏せ、短く息を吐いた。そして、感情をすべて水底に沈めたような声が返ってきた。
「もう……苦しみがどんなものかわからぬ」
胸がきゅうっと締めつけられる。
この方もまた、神に仕える役目の中で……人としての感情を――
言葉を探す私の沈黙と、宮様の沈黙が、同じ色をした静けさとなって部屋を満たしていった。
「戻ってきたのか」
私たちに気が付いた頭中将様の声に疲労がにじみ出ていた。
宮様が一歩、畳の上に足を進めた。その背筋の伸びた立ち姿に、私は自然と息を呑む。
「神泉苑へ調査に向かいたく存じます。金龍の氣は、あちらへ流れていました」
その声は、深く澄んでいて、まるで風を割るように真っ直ぐだった。
数瞬の沈黙のあと、頭中将様は眉間に深く皺を寄せ、短く言葉を落とした。
「そうか。帝を頼む。そなたに一任するよ」
簡潔で揺るぎのない声。けれどその底に、かすかに滲んだ感情があった。責任という名の重さと、抗えぬ焦りが、静かに揺らめいていた。
神泉苑……この國にとって、最も清き地。その氣が乱れているというの……?
胸の奥に、ひやりとした冷気が走る。名を思うだけで、空気の質が変わった気がした。まるで、そこに触れてはならぬものが潜んでいるかのように。
宮様は静かに一礼をすると、踵を返した。私に視線を向け、軽く頷く。迷いのない眼差しに、私は心の奥をそっと正された気がした。
そのまま、私たちは殿上の間を後にし、霊獣寮へと急いだ。
霊獣寮の門をくぐると、朝の光が静かに差し込み、建物の白木が淡く輝いていた。玄関の脇には、宗直様が箒を片手に、掃除道具を片付けている姿があった。
「あ、宮様。お戻りでしたか!」
ぱっと明るくなる宗直様の声。思わずこちらの頬も緩みそうになる。
けれど、宮様はすぐに要件を告げた。
「宗直、神泉苑へ向かう。補佐として同行せよ」
一瞬、宗直様の目が大きく見開かれる。驚きと緊張が入り混じった気配——だがそれはすぐに、はにかむような笑みに変わった。
「はいっ!」
返事と同時に、宗直様の視線が私に向けられる。少し照れたような表情で、軽く会釈してくれた。
そんななか、宮様は立ち止まり、静かに言葉を紡ぎ始めた。
「神泉苑は、異界と地が繋がる龍穴。かつて龍神が住まいした場所と伝えられている」
その声音は淡々としていたけれど、ひとつひとつの語が、胸の奥にじんわりと沈んでいった。目に見えぬ重みが言葉に宿っていて、私の心に波紋を広げる。
「霊獣の氣が乱れる場所だ。うまく帰ってこられるとは限らぬ。鈴音……おまえの白虎が頼りだ。そして宗直――おまえは鈴音よりは劣るが、霊獣に好かれやすい。その資質を使うときだ」
宗直様が、すぐに反応した。
「任せてください!」
胸を張り、まっすぐな目で宮様を見つめるその姿は、まるで少年のような無邪気さと責任感が入り混じっていて、少しだけ空気が和らいだ気がした。
そして、私たちは出立した。
私たちは馬を使わず、静かに歩き出した。
白虎の足音は響かず、私の呼吸も、まるで風の音に溶けるようだった。
選んだのは、人目を避けるための宮中の裏道。
それは、表通りの華やかさとはかけ離れた、静まりかえった路だった。瓦屋根が重なり合う隙間から、朝の光が薄く差し込んでいるが、その光はまるで夢の残滓のように淡く、どこか現実離れしていた。
苔むした石垣、竹垣の隙間から伸びる野の草、しんとした闇の残る路地。空を見上げても、陽の光はどこか翳って見えた。ひとつ、またひとつと足を進めるたび、まるでこの世ではない場所へ踏み込んでいるような、不思議な感覚に囚われた。
神泉苑が近づくにつれて、空気が変わっていくのが分かった。
ただ冷たいのではない。何か、見えない膜のようなものが空間を覆い始める。その膜が、皮膚の上をそっと撫でるようにして、じわりと足元から這い上がってくる。冷えというより“氣”そのものが、肌に触れているような……そんな感覚。
次の瞬間、胸の奥に、ふっと小さな波紋が広がった。
白虎の氣が、呼応するように脈を打つ。微かだけれど、はっきりと私の中で震えている。
氣ではない。これは、呼び声——。
……なにか、いる。すぐ近くに。白虎も、呼ばれてる……
私は思わず、手のひらを握りしめた。白虎は沈黙していたけれど、私の心に届くその感覚は、疑いようもなく明確だった。まるで、胸の奥に灯る火が、見えない風に揺れたような感覚。
前を歩く宮様の背には、気配のようなものが静かに立ち昇っていた。
宗直様も、ふだんの陽気さはどこかへ消え、無言のまま歩いている。肩の辺りに、ぎこちなさがにじんでいた。
やがて、石畳の先に開けた景色が現れた。おそらくここが神泉苑だ。
◆◆ ◆
神泉苑の敷地に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。
音もなく、色もない。ただそこにあるだけの空間——それなのに、全身を包む氣の密度が、たしかに違っていた。
古の苑を囲む森は、薄曇りの空を背景に、墨絵のように静まり返っている。鳥も鳴かず、葉も揺れない。風が通っていないはずなのに、どこか、ざわりとする氣配が肌を撫でた。
正面には、池へと続く石橋。年月を重ね、角が丸くなったその橋は、苔むして深い緑をまとっていた。まるで千年の眠りからまだ目覚めず、今も時の流れを拒んでいるかのように、ひっそりと佇んでいる。
池の水面は静かで、空を映しながらもどこか深く濁って見えた。木々に囲まれたその空間全体が、息をひそめている。音も、光も、時間さえも、すべてが止まっているように思えた。
……ここは、まるで時間が止まっているみたい。
胸の奥で、ぽつりと呟きがこぼれ落ちた。そのとき、私の前をすっと、ひときわ長い影が横切る。
宮様だ。立ち止まり、池の水面を見つめている。
「二人とも、何か感じるか」
低く、けれど遠くまで届くような、澄んだ声音だった。
私は胸元に手を当て、そっと目を閉じる。まるで耳の奥にまで静けさを浸透させるように。
……そのとき、宮様の声が、すぐそばで響いた。
「金龍は……おそらく池にいる。どこかにいるはずだ。探すぞ」
その声は、確信と迷いをないまぜにしたような、複雑な響きを持っていた。
と、その瞬間。
池の水面が、不意に大きく盛り上がった。
次の瞬間――爆ぜた。
轟音とともに、白金の奔流が天を裂き、眩しさに目が焼けそうになる。
「っ――!」
声にならぬ叫びが喉を突き抜け、思わず腕で顔を覆った。隙間から覗いた視界には、乱反射する無数の鱗。ひとつひとつが刃のように煌めき、視界を支配する。
空気が唸りをあげた。
突風――いや、鋭い爪そのものの氣が、容赦なくこちらへ迫る。
息が詰まる。体がすくむ。
「避けろ!」
宮様の声が、怒号のように耳を打つ。
直後、熱風が頬を裂き、髪がばさりと浮いた。ほんの一瞬でも遅れていたら……その爪に切り裂かれていた。背筋に冷たいものが走る。
ぱちり、と火の粉が散った。
炎の羽音。
朱の光が私の横を駆け抜ける。
「……鳳凰!」
宮様の掌から解き放たれた潤氣が紅蓮となり、空を裂いて舞い降りる。
炎を纏った鳥の翼が広がり、金龍の爪の氣を受け止めるように広げられた。
耳をつんざく衝突音――光と炎がぶつかり合い、視界が白と朱に塗りつぶされる。
「狛犬!」
宗直様の声が、鋭い刃のように響いた。
大地を揺らすような咆哮。
黒と白の影が池の縁を駆け抜け、飛び出す。
狛犬だ。石を砕くほどの牙を剥き、金龍へと飛びかかる。
氣と氣が噛み合い、火花のように弾けた。
押し寄せる圧に、空気そのものが震えている。肺が縮み、息が思うように入ってこない。
熱、衝撃、轟音――それらすべてが一度に押し寄せ、体が小さく震えた。
これが……金龍の力……! このままじゃ――!
私は息を詰め、立ちすくんだ――その刹那。
金龍の尾が弧を描き、唸りをあげながらこちらへ薙ぎ払われる。
「っ――!」
足がすくみ、喉がひきつる。逃げようと頭で叫んでも、体が凍りついて動かない。
だが、衝撃は訪れなかった。
目の前に、白の影が飛び込む。
どん、と大地を揺らす衝突音。
白虎――。
その巨躯が私の前に立ちふさがり、しなやかな四肢で踏ん張る。
鋭い爪が金龍の尾を受け止め、氣と氣がぶつかり合って火花のように散った。
衝撃の余波が頬を打ち、息が奪われる。
「な、な、な……なんで……こんなところに、白虎が……!」
宗直様の声が裏返った。
その目は見開かれ、信じられないものを見たように震えている。
足が半歩、思わず後ろに引かれた。
白虎が低く唸る。その咆哮は地を揺らし、胸骨の奥まで響いてきた。
鳳凰の炎が空を裂き、狛犬の牙が閃き、そして白虎の氣が唸りを上げる。
三つの霊獣が金龍に挑み、池のほとりは光と影の奔流に呑まれた。
耳をつんざく轟音と熱気に、息を吸うことさえ苦しい。
胸がぎゅっと締めつけられる。
だめ……こんなの、望んでない……! 戦わせたいわけじゃないのに……!
「やめて――!」
自分の声が嵐に吸い込まれていく。それでも必死に叫んだ。
爪と尾が閃き、白虎が踏みとどまり、鳳凰が炎を散らし、狛犬が牙を立てる。
氣と氣が衝突し、池のほとりは光の奔流に呑まれていた。
「私たちは……あなたと戦いたいんじゃない!」
喉が裂けそうに痛む。けれど言葉は止まらない。
「もう……誰も、ひとりにしたくないんです。あなたも……苦しかったでしょう?」
金龍の瞳が、ちらりとこちらを向いた。
その視線に射すくめられ、膝が震えた。
けれど、後ろには仲間たちが必死で支えている。
私は一歩踏み出した。
「だから……一緒に帰りましょう。宮中へ。帝も……霊獣たちも……あなたを待っています!」
その言葉と同時に、胸の奥から潤氣が溢れた。
光がひと筋、金龍へと伸びる。
――触れた。
金龍の瞳がかすかに揺らぎ、荒々しい氣の奔流が一瞬だけ弱まる。
その隙間から、言葉ではない。“音なき聲”が、心の奥に直接、流れ込んでくる。
——霊獣たちは、香によって氣を乱され、帝の氣は断たれた。
まぶしい光が、突然、胸の奥で弾けた。
私の知らない記憶が、次々に流れ込んでくる。
暴れ狂う霊獣たち。
苦しげに呻く白虎。
その傍らで、倒れ伏す帝の姿——
言葉にならない衝撃が、私の心を揺さぶった。
けれど、それは終わりではなかった。もうひとつ、聲が重なる。
——浮橋がいたなら、氣の乱れは、ここまでにはならなかった。
「……浮橋……?」
その言葉が、胸の奥からぽつりと零れた。
私は、金龍を見つめながら、呟くように口にした。
「……燁子は、“浮橋”じゃないんですか……?」
その瞬間——空気が、かすかに揺れた。
金龍の瞳が、わずかに揺らいだように見えた。
その中に、確かに一瞬、悲しみのような色が灯った。
返事はなかった。けれど、その沈黙は、確かに「否」と言っていた。
◆◆ ◆
金龍の氣が渦を巻いた。
光のうねりが視界を満たしていく。白金の霧が静かに立ちのぼり、私のまわりの現実が、ゆっくりと遠ざかっていった。
音が消えた。風も、匂いも、重力さえも。
ただ、ひとつ——心の奥にふれた、あたたかな掌のような氣だけが残っていた。
不安よりも、懐かしさが胸に広がっていく。これは……記憶?
霧の向こうから、景色が現れた。
朝の光がうっすらと差し込む、静かな庭だった。整えられた白砂の庭に、長い影が伸びている。張り詰めた空気のなか、私は息をひそめるように立っていた——いや、私はここにいる。でも同時に、誰にも気づかれていない。
視線の先。庭の中央に、小さな背中があった。
白い布をまとい、地に膝をついている少女。
まだ十にも届かぬだろう、小さな肩がかすかに震えていた。
……燁子。
気づけば、私は名前を呟いていた。
間違いない。あの後ろ姿は、幼い頃の彼女だった。
その肩に、寄り添うように小さな龍がいる。
鱗はまだ淡く透けていて、澄んだ潤氣が肌に触れるたび、やわらかな光を散らしていた。
蛟じゃない……? あれはまだ、神聖な龍の氣……。蛟は龍の幼体だったの?
燁子の背に、少女らしい緊張と、覚悟が混ざっているのが見えた。顔は伏せていても、氣の流れがまっすぐだった。
その場には神祇官たちが整列し、祝詞が低く響いていた。
左右には、雅な装束に身を包んだ貴族たちの姿。そのなかで、私はひとりの青年に気づく。
宮様……?
まだ幼さを残した面差しだったけれど、その背筋は今と同じように、真っすぐだった。
彼の視線は、静かに燁子の方へと注がれている。
燁子は——その目を、ちらりと彼に向けた。
ほんの一瞬のことだった。けれど私は、見逃さなかった。
最初は、尊敬のようだった。けれどすぐに、それが別のものへと変わる。
憧れ——いや、それ以上の、恋心。
子どもらしい無垢さに混じる、微かな執着。
燁子の視線が離れたとき、私は胸の奥がざわつくのを感じた。
それは、儀式の中心にある氣の流れが、微かに濁った瞬間だった。
空が淡く染まり始める。
雲の切れ間から、金龍の氣が降りてくる。
天から静かに垂れた光の帯が、燁子に触れようとした、その刹那——
ぴたり、と。
氣が、止まった。
空気がふっと冷える。
何かが、途中で切れたような感覚が、肌を這った。
私の中にまで、びりりと走る“拒絶”の感覚。
燁子は顔を伏せたまま、ただじっとしていた。まるで何も感じていないかのように。
けれど、金龍の氣は、もう彼女へは降りてこなかった。
聲が響いた。けれど、耳ではなく、胸の奥で。
——「恋心を抱く者は、龍に仕える“浮橋”とはなれぬ」
その言葉と同時に、金龍の視線がふいに逸れた。
視線の先には——宮様がいた。
金龍の瞳は、まるで「選び取る」ように、彼を見つめていた。
——「あの者を、浮橋を導く“導く器”とした」
……あのとき……金龍は、宮様を……。
氣が揺れる。
儀式の氣脈がふたたび波打ち、景色がかき消えてゆく。
次に現れたのは、閉ざされた空間だった。
帳が垂れ、香の煙がゆるやかに漂う薄暗い広間。
いくつもの公卿たちの姿が、畳に膝をつけ、顔を寄せ合っていた。
「……儀式の失敗は、外には漏らすな」
「金龍は、拒絶などしておられぬ。ただ、静かにお鎮まりになっただけだ」
「燁子殿こそが、浮橋として最もふさわしい」
「記録など、整えればよい。形があれば、誰も疑わぬ」
低く、湿った声が、次々と交わされる。
誰が何を決めたのか、明確には分からない。けれど、その場にいた全員が“同じ方向”を向いていた。
……違う……金龍は、拒んでいた……。
言葉に出せない。ただ、心の中で否定が渦を巻く。
燁子は、選ばれてなどいなかった。けれど、選ばれたことに“された”。
目の前で、白く染まっていた光景がぱちん、と弾けて消えた。
はっと息を呑む。視界が戻る。
耳をつんざく轟音、熱を帯びた風、飛び散る火花。夢の底にいたはずの私の目の前で、まだ戦いは続いていた。
鳳凰の炎が舞い、狛犬の牙が閃き、白虎の咆哮が夜を震わせる。
金龍の尾が振り下ろされ、大地ごと抉る氣が襲う。
……これは……まだ終わってない!
私は胸を押さえ、声を振り絞った。
「待ってください! もう戦わないで!」
必死の叫びに、ほんの一瞬、霊獣たちの動きが揺らいだ。
だが――
「鈴太っ!」
誰かの叫びが、耳を裂いた。
次の瞬間――影が横から襲いかかってきた。
牙を剥き、爪を閃かせる狛犬。その姿を目にした瞬間、全身が凍りついた。
「宗直……さま……?」
信じられない。なぜ、狛犬が私に――。
視界の端に、宗直様の顔が映った。
驚きでも焦りでもない。押し殺したような決意が、わずかに揺らぐ瞳の奥に覗いていた。
「やっ……!」
声を上げるより早く、狛犬の巨体がぶつかった。
骨が軋むほどの衝撃。肺の中の空気が一瞬で奪われ、私は宙へと弾き飛ばされる。
「きゃ――っ!」
視界がひっくり返る。燃える炎も、唸る金龍も、すべてが逆さに混じり合い――背中に、氷のような冷たさが走った。
池の水面が裂ける。
どぼん、と重たい音がして、世界が一瞬で暗い底へと反転する。
水が耳を塞ぎ、喉に冷たさが押し込まれる。
必死に手足を動かすけれど、濡れた衣が絡みつき、重りのように沈めていく。
どうして……宗直様……!
問いは声にならず、泡となって弾ける。
光が遠ざかり、金龍の咆哮も、白虎の叫びも、狛犬の唸りも――すべてが水に呑まれていった。
ただ暗い深みへ、ひたすら引きずり込まれていく。
水の冷たさに肺を掴まれたみたいで、息ができない。重たい衣が体にまとわりついて、手足を動かしても水の底に引きずり込まれていく。
だめ……苦しい……!
そのとき――腕をぐっと抱き寄せられた。
水の中でさえはっきりわかる強い力。顔を向けると、揺れる水の向こうに宮様の輪郭が見えた。
「……っ!」
言葉にはならない。けれど、必死に伸ばした手を宮様が掴んで、ぐっと体ごと引き寄せてくる。
水をかき分ける力強い蹴り。視界に泡が弾け、次の瞬間――眩しいほどの光と冷たい夜気が頬を打った。
「ぷはっ……!」
喉が裂けるように空気を吸い込む。肺が燃えるみたいに熱い。宮様の腕の中で必死に咳き込みながら、なんとか息を整えた。
冷たい水の重みから解き放たれるように、私は宮様の腕に抱え上げられ、岸へと運ばれていった。
ぐっしょりと濡れた衣が肌に張りつき、体温がどんどん奪われていく。息はまだ浅く、胸の奥がひゅうひゅうと鳴って苦しい。
その時、轟音が耳を打つ。
振り返った瞬間、目を覆いたくなるような光景が広がっていた。
金龍の巨大な尾が、怒涛の勢いでうねり迫る――。
その刹那、白い影が飛び込んだ。
白虎だ。
私と宮様の前に立ちふさがり、鋭い爪で龍の尾を受け止めた。氣と氣がぶつかり合い、火花のように散って夜空を裂く。
「白虎……!」
思わず息を呑む。震える声が漏れた。
さらに、朱の炎が闇を払った。
宮様の鳳凰だ。炎の羽根を広げ、烈火のような光で金龍を包む。
火の粉が散り、赤と白の輝きが池のほとりを覆った。
咆哮。衝突。氣の奔流。
世界そのものが震えているようだった。
私は宮様の腕にすがりつき、目を開けていられないほどの閃光と熱風の中で、ただ必死に呼吸を繰り返していた。
炎と光の奔流のただ中で、胸の奥がじんわりと熱を帯びているのに気づいた。
……まだ、繋がってる……?
さっき水底で触れた金龍の氣の残滓が、潤氣を伝って私の中に微かに残っている。鼓動に合わせて脈打つように、かすかな波が広がっていった。
その瞬間――金龍の瞳が、こちらを振り返った。
氷のような光を湛えていたはずの眼差しに、一瞬だけ迷いの影が揺らめいた。
うねる尾が止まり、空気の緊張がふっと緩む。
「……」
言葉はない。けれど、胸の奥に響いたのは、戦いに意味を見出さぬ嘆息のような氣の揺らぎ。
それは「人と争う時ではない」と告げるようでもあり、ただ深い孤独を吐き出すようでもあった。
次の刹那、金龍は大きく首を仰け反らせ、夜を揺るがす咆哮を轟かせた。
空気そのものが震え、鼓膜が裂けそうになる。胸が締めつけられるほどの声――怒りでも、悲しみでもない。もっと遠い場所に向けた、叫び。
その巨躯が白金の光をまとい、池の水面を巻き上げながら天へと舞い上がっていく。
鱗が煌めき、夜空を裂くように遠ざかる。
「……!」
私はただ、呆然とその背を見上げていた。
確かに戦いは終わっていない。けれど、今ここで命を奪い合うことを金龍は選ばなかった。
残響のように胸に震えが残り、私は震える唇をかすかに噛んだ。
また……必ず、会う……。
「大丈夫ですか、宮様!」
宗直様がこちらへ走りこんできた。そんな宗直様へ、鋭い声音が突きつけられる。
「……なぜだ。なぜ狛犬が鈴太を狙った」
空気が一瞬で凍りついた。
いつもの柔らかな響きを持つ宮様の声が、今は刃のように冷たい。
宗直様の顔が見る間に青ざめていく。唇がわなないて、かろうじて声が絞り出された。
「す、すみません! 狙ったなんてとんでもない! 鈴太が……足を滑らせたように見えて、助けようと……!」
その言葉が耳に届いた瞬間、胸の奥がずきりと痛んだ。
――違う。あの狛犬は確かに、私めがけて突き飛ばしてきた。
けれど声にならない。喉の奥が冷たさと恐怖に塞がれ、私は宮様の衣に縋るように小さく震えるだけだった。
そのとき、ふいに自分の身体の感触に気づく。
濡れた衣が肌にぴたりと張りつき、胸の線も腰の曲線も、布越しにあらわになっている――。
……だめ! こんな姿を見られたら……!
慌てて腕で胸元を押さえる。けれど水に透けた布は思うように隠してくれない。
焦りに心臓が乱打する。宗直様に、女だと知られてしまう――その恐怖が、金龍に襲われた時よりも鋭く胸を突いた。
その予感はすぐに現実になった。
宗直様の目が、私の濡れた姿に釘付けになる。血の気が引いていくように顔が強張り、言葉が喉に詰まったようにこぼれた。
「そ、その姿……鈴太……おまえ……女なのか……」
その言葉が夜気を震わせ、私の耳に突き刺さる。
その刹那、宮様の腕が私をさらに強く抱き寄せた。私を覆うように立ち、宗直様を射抜く鋭い眼差しを向ける。低く、鋼のような声音が落ちた。
「……今夜見たことは、すべて忘れろ」
返事を待つまでもなく、その言葉が空気を支配した。
「……はっ」
宗直様はその場に膝をつき、青ざめた顔で短く答えた。
私の方を見ることもできず、ただ数歩、後ずさるようにして姿を遠ざかった。
次の瞬間――あれほど荒れ狂っていた氣の嵐が、ふっと霧が晴れるように消え去った。
耳に残るのは、水の雫が滴り落ちる音と、自分の荒い息づかいだけ。
金龍が去ったあとの静寂は、かえって胸に重くのしかかり、張りつめていた背筋が急に力を失った。
「鈴太!」
名を呼ばれ、私は顔を上げる。すぐそばに、宮様の瞳。
その眼差しが、先ほど宗直様へ向けられていた冷たさとは違って、ひどく切実で――。
次の瞬間、私は強く抱き寄せられていた。
濡れた衣の冷えとは対照的に、宮様の胸の奥から伝わる熱。
それに触れた途端、張り詰めていたものが解けて、力が抜けていく。
震える指先さえも包み込むような腕の中で、ようやく「生きている」と実感した。
――そのとき。
白く、穏やかな氣が私の背を撫でた。
振り返らずともわかる。白虎だ。姿は見えないのに、確かに寄り添ってくれている。
……守ってくれている……。
胸の奥に、熱とも涙ともつかないものが込み上げる。
もう抗う気力もなく、私はその氣に、そして宮様の温もりにすべてを委ねた。
視界が静かに揺らぎ、闇がやさしく滲み広がっていく。
最後に感じたのは、抱きしめる腕の確かさと、白虎の氣が寄り添う安らぎだった。
◆◆ ◆
夢の底に沈んでいたのか、それとも、遠い海のなかを漂っていたのか――。
そんなぼやけた感覚の奥から、ふっと、意識が浮かび上がった。
瞼をわずかに開くと、見知らぬ天井が静かに広がっていた。
御簾の向こうから、やわらかな朝の光が射し込み、室内の空気を金色に染めている。
音も匂いもやさしく、胸の奥をじんわり温めるような空間――どこか、懐かしさすら混じっていた。
……ここは……?
輪郭の定まらない思考のまま、首をゆっくりと巡らせる。
すると、額にそっと触れるものがあった。布のような……けれど、人の手のぬくもりも感じる。
隣には、年配の女房が座っていた。しわの浮いた手で、古びた手巾をやさしく私の額にあてている。見覚えのある、あの穏やかな顔――たきさんだ。
「まあ……目を覚まされたのですね。よう生きていてくださいました」
微笑む声が、やわらかく耳に届く。
その一言で、私はようやく、自分が生きているのだと知った。
「わたし……いったい……」
「姫様は三日ほど眠り続けておられましたよ」
「……え、三日も!?」
思わず声が大きくなる。けれど自分の声はかすれていて、驚きがじわりと現実味を帯びていく。
「すぐに、お知らせして参ります」
たきさんは静かに立ち上がり、畳を踏む足音も軽やかに、廊下へと駆けていった。
その背中を目で追いながら、私は布団の中で小さく息をついた。
胸の奥には、まだ遠い夢の波の余韻が、かすかに揺れていた。
廊下の向こうから、畳を踏む足音が二つ。やがて御簾がするりと持ち上がり、たきさんの後ろに――宮様が現れた。
いつものきちんと整えられた姿とは違い、髪は乱れ、衣の裾がまだ湿っている。私を見るその瞳だけが、変わらず真っ直ぐだった。
慌てて身を起こそうとした瞬間、力が抜けて体が傾く。
ふっと支える腕の感触。宮様だ。
「大丈夫か」
耳に届く声は、低く抑えているのに、揺れが混じっていた。
「……はい。すみません、ご心配を……」
掠れた自分の声が情けなくて、視線を落とす。
「無理もない。三日も眠り続けて……生きた心地がしなかった。薬師を呼ぼう」
肩を支えていた手が離れ、たきさんが代わりに寄り添ってくれる。宮様はそのまま私のそばに座り込んだ。
「楽にしてくれ。少し、話がしたい」
「あ……」
神泉苑の光景が、一気に胸の奥まで押し寄せる。冷たい水、白虎の咆哮、そして――
「……宗直様に、気づかれてしまいました」
その名を告げると、宮様の眉がほんのわずかに寄った。
「あれは仕方ない。そなたのせいではない。宗直には釘を刺しておいた」
言葉を聞きながらも、あの時の感触が消えない。背に走った衝撃、振り返る前に見えた宗直様の視線――一瞬の揺れと、逃げるような足の動き。
胸の奥で、水面がゆらりと波を立てた。
「……金龍とは、何を話した」
宮様の声が、静かに、しかし逃げ場を塞ぐように落ちてきた。
喉の奥がひりつく。私は息を整え、神泉苑で見た光景を、言葉にすくい上げていった。
――潤氣擾乱香に狂った霊獣たち。
――氣を断たれ、崩れるように倒れた帝の姿。
――そして、金龍の聲。「浮橋がいれば、このようなことにはならなかった」と。
指先がじんと熱くなる。あの時、どうしても訊かずにはいられなかった。
「……燁子は、本当に浮橋なのかって……」
唇が震える。
「金龍は……戻るとは言いませんでした。ただ……私の聲に、応えてくれた気がして」
宮様は、しばし目を伏せたまま沈黙した。拳を膝の上でゆっくり握り込む。やがて、その眼差しがまっすぐこちらを射抜いた。
「……浮橋のこと、本当の話なのですか?」
自分でも驚くほど、声が細くなっていた。
低く、重い頷き。
「……ああ。本当だ」
その瞬間、部屋の空気が少し冷たくなった気がした。
宮様は視線を落とし、ゆっくりと言葉を紡いだ。
「四年前――浮橋を決める儀式の日だ。本来なら、あの日に浮橋は生まれるはずだった。だが……金龍は誰も選ばなかった」
御簾越しの光が、彼の横顔を薄く縁取る。
「それを“失敗”と見なした公卿たちは、國が乱れるのを恐れた。だから……金龍の意志を無視し、燁子を浮橋に据えた。記録にも残らぬ、密やかな決定だ」
言葉が、胸の奥まで深く沈んでいく。息をするたび、問いがひとつ、またひとつ、泡のように浮かび上がった。
「……では、本物の浮橋は、どうやって生まれるのですか?」
問いかけると、宮様はすぐには答えなかった。
私の問いに、宮様はゆっくりと顔を上げた。
御簾越しの朝の光が、その瞳の奥で淡く揺れる。
「“導く器”は……金龍に選ばれた“器”だ」
言葉を選ぶように、低く落ち着いた声が続く。
「浮橋になる者を導き、指名する。自らの感情も意志も押さえ込み、ただ神意だけを伝える存在だ」
その響きが、胸の奥にじわりと沈んでいく。
「神意を伝える存在……」
口の中でそっと転がしながら、気づけば次の言葉が漏れていた。
「では……今、“導く器”は、どなたなのですか?」
短い沈黙。外の気配さえ遠く感じられたとき――
「……私だ」
「え……」
息が喉にひっかかる。思わず、その横顔を探してしまった。
いつもの冷ややかな静けさの奥に、一瞬だけ揺らいだ影――それは見間違いだったのだろうか。
「幼い頃、“器”として選ばれた。だが……」
宮様は視線を落とし、指先で袂の端をひとつ、ゆっくり握った。
「私はまだ、“導く器”としての指名を果たしていない。ゆえに――浮橋はいない」
胸の奥に、ことりと小石が落ちるような音がした。
「じゃあ……燁子は、本当に浮橋ではないのですね」
「ああ。そうだ」
答えを聞いた瞬間、胸の奥がひやりとする。燁子の姿、そして儀式の光景が脳裏をかすめた。
でも、その向こうに――私の目の前で静かに座る宮様の姿が重なる。
感情を押し殺したようなその横顔。
まるで心の奥まで固く封じられているようで、思わず見つめてしまう。
「……ずっと……そうやって、心を抑えてこられたのですか?」
言葉にしてから、自分でも胸が少し痛んだ。
「感情も意志も抑えられて……苦しくはないのですか?」
宮様は目を伏せ、短く息を吐いた。そして、感情をすべて水底に沈めたような声が返ってきた。
「もう……苦しみがどんなものかわからぬ」
胸がきゅうっと締めつけられる。
この方もまた、神に仕える役目の中で……人としての感情を――
言葉を探す私の沈黙と、宮様の沈黙が、同じ色をした静けさとなって部屋を満たしていった。