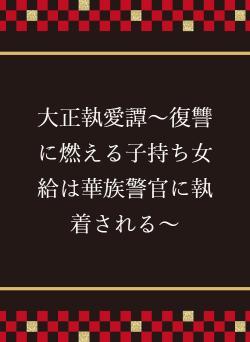霊獣寮の朝は、どこか落ち着かない空気に包まれていた。
いつもなら霊獣たちの潤氣が穏やかに流れ、朝露のような静けさが広がっているはずなのに、今日は空気がぴりついている。中庭の木立がざわめき、空を渡る風もどこかせわしない。霊獣たちも、普段より敏感に周囲をうかがっているようだった。
そんな中、私は宗直様の少し後ろを、控えめな歩幅でついていった。
これから内裏の巡回に向かうのだという。私はまだ正式な補佐ではないけれど、それでも――外に出られることが、ただ嬉しかった。霊獣寮という世界の中に身を置くようになってから、こうして任務に加わることが、少しずつ自分の居場所になっていく気がしていた。
「鈴太、そろそろ行くか」
呼びかけられて、私は軽くうなずいた。
「はい」
宗直様に続いて霊獣寮の門をくぐろうとした、その時だった。
目の前に、三つの人影が立ちはだかった。誰かと思えば――在原貞親様。狛猪を連れた、先輩の霊獣師だ。後ろには、いつも貞親様の傍にいる取り巻きの二人がいて、冷えた視線をこちらに向けていた。
「殿上童のお前が、どうして内裏の巡回なんて任されるんだ!」
貞親様の声が、早朝の空気を裂く。強い潤氣を含んだ怒気が、目に見えぬ波のように押し寄せてきた。
「俺の補佐だよ。補佐。宮様の指示だろう。お前が口出すところじゃない」
宗直様は、いつも通りの軽やかな口ぶりだった。けれど、その目はほんの少し鋭く光っていた。ふざけた言葉の奥に、決して引かぬ強さがにじんでいる。
私は、思わず宗直様の袖の端を握った。胸の奥で、小さな警鐘が鳴る。
「なにを……!」
貞親様が一歩、踏み出す。その動きに呼応するように、狛猪の潤氣がぶわりと膨れあがった。怒りの氣が空間を震わせ、私の皮膚にぴりりとした痛みが走る。狛猪の目がぎらりと光り、今にも飛びかかってきそうな気配を放つ。
噛みつかれる、そう思った瞬間だった。
「た、大変です! 霊獣頭殿はいらっしゃいますか!」
霊獣寮の奥から、若い蔵人が駆け込んできた。顔は青ざめ、額には玉のような汗。息を切らし、震える手で袖を押さえていた。
あまりの形相に、貞親様も宗直様も、さきほどまでの怒気を忘れたかのように振り返った。
「こちらです!」
宗直様が声をかけ、私も小走りであとに続く。
蔵人の顔――ただならぬ気配だった。胸の内に、ひやりと冷たいものが流れ込んでくる。
霊獣寮の一角。朝の光が几帳越しに差し込み、淡く光る畳の上に静けさが降りていた。宮様は文台に向かい、筆を走らせておられた。この一角だけは時間が止まっているように思えた。
その静寂を足音が破った。
「失礼いたします。霊獣頭殿!」
息を切らした声。土間に砂を跳ね上げて、新蔵人さまが飛び込む。
袴の裾が乱れ、顔面は青ざめ、手はわずかに震えている。
「何事か」
「帝が、帝がお倒れになりました!」
駆け込んできた新蔵人さまの声は、風を裂くように鋭かった。肩で息をしながら、必死の形相で言葉をつづける。
「原因は……まだ、突き止められておりません。つきましては、霊獣頭殿に、帝の金龍を……ご覧いただきたく……」
新蔵人さまの声が掠れ、畳に両手をついた。
宮様は、顔を上げた。
ほんのわずかに、筆を止める動きが遅れた。
……その一瞬。私は見た。
あの方の目の奥に、かすかな揺らぎが走ったのを。感情の色――心の底に沈めているはずの波が、ふっと光に触れたように。
「清涼殿へ向かう」
ただそれだけ。低く、静かに告げて、宮様は立ち上がられた。
「宗直、霊獣師の皆に伝えよ。霊獣騒乱事件があったばかりだ。大臣や女御方の霊獣の潤氣を確認するのだ。異変があれば、すぐに報せよ」
「はっ!」
号令のように声が返り、霊獣師たちが四方へ駆け出す。
廊下の板が軋み、足音が響く。空気が動き、静寂が熱を帯びて騒がしくなる。
宗直様も踵を返して走り出そうとした。
「あの!」
私は思わず袖をつかんでいた。肩に力が入っていた。自分の声が少し上ずっていた。
「わたしも、行かせてください。なにか……私にもできるかもしれません」
宗直様の顔が近くにあった。困ったように笑って、でも、目だけは優しかった。
「……鈴太は、留守を頼む」
「え……」
「今回は、殿上童の身分じゃ行けない任務だ。すまんな」
そのひとことが、冷たく鋭い刃のように胸に刺さった。
何も言えずに、私はただ、首を縦にふることしかできなかった。
宗直様の背が、視界の向こうに遠ざかっていく。
宮様も、新蔵人さまに案内されて、静かにそのあとを追われた。
ふたたび静けさが戻った霊獣寮。
私はその場に立ち尽くしていた。風もなく、音もないのに、心の中にぽっかりと穴があいたようだった。
そのとき、白虎の氣がそっと触れてきた。姿は見えない。でも、確かにいる。
――だいじょうぶ、と言ってくれている気がした。
私はそっと胸に手をあて、唇をかみしめた。
でも、心のどこかでまだ――あの背中を、追いたいと思ってしまっていた。
◆◆ ◆
霊獣寮の朝は、変わらぬ静けさに包まれていた。
けれど、澄んだ空気の奥底をそっとかき乱すように、私の胸の中だけが落ち着かなかった。
――帝が倒れた。
その知らせが届いてから、もう三日が経つ。
寮の天井から差し込む光はいつもどおりで、庭に降る露も、木々のざわめきも変わらない。けれど世界のどこかが、もう戻らない場所へと動いてしまった気がしてならなかった。
宗直様たちは、内裏の巡回に出ている。私は霊獣寮に残り、留守番をしていた。
誰もいない廊下を一人で歩くと、足音がやけに大きく響く。
ひとりきりの空間に、心の奥のざわめきがこだましてしまいそうだった。
「……掃除でも、しようかな」
誰に向けるでもなく、呟いた。
そうして何かしていないと、胸の奥の不安がどんどんふくらんで、追いつめられてしまいそうだった。
帝のことは、もちろん心配だ。
けれど、それ以上に気がかりだったのは、宮様のことだった。
あの方にとって、帝は父。
静かに自分を律しておられるあの方の中で、何かが崩れてしまっていなければいい――そう思うと、じっとしていられなかった。
私は箒を手に庭へ出た。
苔むした石畳の隙間から、桐の葉が風に舞っていた。
ひとつひとつを集めながら、呼吸を整えるように箒を動かす。
しんと張りつめた空気の中に、ふとやわらかな氣配が混じった。
振り返らなくてもわかる。
小さな霊獣たちが、どこからともなく現れていた。
最初に来たのは、ころんと丸い、鈴のような霊獣。金属のようにきらきらした体が、光を反射してふるふると震えている。
次に姿を見せたのは、花のような耳を持つ鳥型の霊獣。ふわりと枝にとまり、首をかしげて私を見つめた。
ひとつ、またひとつ――霊獣たちは、まるで私の心を読み取ったかのように、静かに集まってきた。
私のそばに寄り添い、肩に乗り、袖にすがるようにして、そっと温もりをくれる。
「……ありがとう」
小さく声を出すと、小さな霊獣たちは、ぴぃ、と鳴いて応えてくれた。
私はしゃがんで、そっとその背を撫でる。
やわらかくて、あたたかい。そのぬくもりが、胸の奥の冷たさをじんわりと溶かしていく。
こらえようとしても、まぶたの裏が熱くなる。
でも泣いちゃだめ。だって、誰かが見ている――そう思った瞬間だった。
風が……鳴らなかった。
音もなく、影のように現れたその姿に、私は息を呑んだ。
白虎。
「……!」
気高く、堂々としていて、どこか人を寄せつけない静謐さをまとっている。
けれど、その双眸だけは違っていた。深く静かに、まるで心の奥を覗きこむように、私を見つめている。
「白虎……」
名前を呼ぶと、白虎は一歩、また一歩と音もなく近づいてくる。
その大きな体が地を踏むたび、空気が震えるような気がした。
何も言わず、ただ私のそばに腰を下ろす。
霊獣たちが、白虎のまわりに静かに集まってきた。
丸い子も、羽根のある子も、皆おだやかにその姿を囲む。
音のない静けさの中に、ぬくもりだけが、ひっそりと満ちていく。
私は両手を胸元に重ねて、白虎の氣にそっと意識をゆだねた。
大丈夫、そう言ってくれているようだった。
「へえ、こんなところに白虎がいるなんてな」
その声が落ちた瞬間、私の背筋に冷たいものが走った。
風の止んだ庭に、硬質な靴音が響く。
「……貞親様……?」
振り向くと、木立の陰から姿を現した貞親様が、こちらを真っすぐに見ていた。
その目は冷えきっていて、まるで人ではないもののように感じた。
「どうして……巡回は……」
「ああ、早めに終わったから戻ってきたんだ。おかげでいいものを見つけたよ」
問いかけた声は、自分でも驚くほどか細かった。
答える代わりに、彼は私と白虎、それに周囲の霊獣たちを睨みつける。
「まさか……お前が白虎を従えているなんてな」
「従えてなんか、いません」
私は言った。震えをこらえながら。
「なぜか、白虎が……そばにいてくれてるだけで……」
その言葉が終わるより先に、貞親様の表情が歪んだ。
憎しみがあらわになる。言葉ではなく、呪いのようだった。
「そんなことは、どうでもいいんだよ」
低く、くぐもった声が響く。
「……あの方が言ってた。悲しげに――白虎とともにいる“誰か”に、心を傷つけられたと」
「……何の話ですか!?」
私の問いかけには応えず、貞親様は淡々と呟いた。
「……あの方の安寧のために――お前には、消えてもらう」
一瞬、時が止まったように感じた。
その直後。
「狛猪――ッ!!」
地を裂くような咆哮。貞親様の霊獣・狛猪が、檻を破った獣のように飛び出した。
「っ……!」
重い地響きが迫る。空気が震え、地面の小石が跳ねた。
小さな霊獣たちが悲鳴のように鳴いて、空へ逃げる。
目の前に、白虎の白い影が飛び出した。
「白虎……!」
その背が、私を守るように立ちはだかる。
牙と牙がぶつかりあい、獣同士の氣が衝突する轟音があたりに響く。
白虎が狛猪の突進を正面から受け止めた――そのはずだった。
けれど、次の瞬間。
「白虎……!?」
白虎の足が、わずかに滑った。
狛猪の頭突きが肩をかすめ、白虎の体が後方へ吹き飛ぶ。
「白虎!」
私は思わず駆け出した。
その間にも、狛猪は止まらない。次の突進に向けて氣を高めている。
白虎が立ち上がる。けれど、動きが鈍い。
いつもの冴えがない。牙を向けながらも、どこか迷いがあるようだった。
なぜ――? どうして迷っているの?
「白虎!」
私は叫びながらその背に手を伸ばした。
ぬくもりが、手のひらに伝わる。けれど、その奥にある氣は揺れていた。
苦しさと、迷いと、ためらい――まるで、自分を責めているような。
「お願い、動かないで……無理しないで……!」
白虎は、私を振り返らなかった。
ただ、前を向いていた。狛猪に向けて、もう一度体を低く構える。
再び衝突の音。肉と氣の激突。
――でも、押されている。
狛猪の爪が白虎の肩を裂いた。血が飛ぶ。白虎の咆哮。苦痛の響きが、私の胸を切り裂いた。
「もうやめて……白虎……!」
私はその背中にすがった。震える手で、白虎の体を抱きしめる。
でも、白虎は私の前に立ち続けた。
たとえ傷ついても、倒れても、私の盾であろうとするように。
「……下がれ」
冷たい刃のような声が、私の背に突き刺さった。
空気が一瞬で変わった。胸の奥に、ひやりとしたものが走る。
振り返ったとき、私は思わず息をのんだ。
「宮様……!」
そこにいたのは、まさしく――
光をまとい、鳳凰を背に従えた宮様だった。
長衣が風に揺れ、足元には靄のような潤氣が漂っている。
その姿は、夜の底に射す陽光のように、凛としていて、絶対だった。
鳳凰が、ふわりと羽ばたいた。
――ぶわ、と音もなく、空気が跳ね上がる。
重力がねじれたように感じた。
世界の氣が、逆巻くように反転する。
「……!」
私の呼吸が止まった。肌が焼けるように熱くなる。
黄金の炎――それが、天から差し込むように降ってきた。鳳凰の潤氣だ。
「グゥオオオオ……ッ!」
狛猪が悲鳴のような声を上げた。
目を剥き、足を暴れさせるが、もう抗えない。
鳳凰の氣に包まれたその体は、まるで重力に呑まれるようにねじ伏せられていく。
「――っ!」
地を這うような音とともに、狛猪の巨体が宙を舞い、地面に叩きつけられた。
振動が足元を伝う。
埃が舞い、空気が震える。
あの狛猪が――まるで木の葉のように、吹き飛ばされた。
「っ……貞親様……!」
小さくそう呟いたとき、彼の体が崩れるように倒れた。
目を見開いたまま、口元には泡。
わずかに痙攣しているが、意識は――ない。
私はまだ、白虎の背にしがみついていた。
白虎の體は温かく、けれどかすかに震えていた。
さっきの一撃が、全身に響いていたのだろう。私の手のひらにも、それが残っていた。
「……白虎……ありがとう」
その名をそっと口にした瞬間、鳳凰が低く鳴いた。
空を円を描くように飛びながら、場の氣を撫でていく。
そして――白虎は、ふとこちらを振り返ると、そのまま氣の流れに身を融かすようにして、姿を消した。
「無事か」
すぐ近くで、低く、けれど優しい声がした。
顔を上げると、宮様がすでに私の傍らに立っていた。
すべてを見通すような眼差し。けれど、その奥にあるのは、責めではなく、心配だった。
「……はい、でも……わたしにも、どうしてこんなことになったのか……」
言葉がうまく出てこなかった。
「白虎を見てから、急に、貞親様の様子が……」
「白虎を“見て”から、か」
その言葉に、宮様の眉がわずかに寄った。
そして、一拍の間のあとで、声を落として言った。
「……このことは、誰にも告げるな」
私はこくりと頷いた。
宮様は静かに貞親様のもとへ歩いていく。
しゃがみこみ、その額に手を置いた。
鳳凰がひときわ明るく光る。
その氣が、やわらかく、まるで記憶をなぞるように流れこんでいく。
「……貞親の中から、白虎に関する記憶を消した。おそらく、誰かの潤氣が、感情を過剰に増幅させている」
言いながら、宮様の目が細められた。
そこへ、あわただしい足音が近づいてきた。
宗直様たちだ。
「貞親!? どうした、何が……!」
霊獣師たちが目を見開き、倒れた貞親様に駆け寄る。
「霊獣騒乱事件と関係がある可能性がある」
宮様がすっと立ち上がる。
「詳しくは追って伝える。まずは彼を薬師に見せてくれ」
「はっ!」
霊獣師たちが肩を貸して、意識のない貞親様が運ばれていく。
その騒がしさの中、宮様がそっと私の耳元に口を寄せた。
「白虎のことは、誰にも言うな。それと……話がある。あとは屋敷で」
その言葉に、私は小さく頷いた。
白虎の残した氣の名残が、まだ胸の奥で揺れていた。
その揺れが、私の中の何かと静かに響き合っていた。
◆◆ ◆
宮様の屋敷の庭に、夜の帳がゆっくりと降り始めていた。
昼間の混乱が嘘のように、虫の声がかすかに響いている。
灯籠の火が風に揺れ、影がゆらゆらと地面を這っていくのを、私はぼんやりと見つめていた。
夕餉の後、たきさんに呼ばれた。宮様が、お話があるとおっしゃっている、と。
胸の奥に、どこかひりつくような緊張を抱えながら、私はそっと障子を開けた。
御簾の向こう――そこに座しておられるその姿は、いつもと変わらず、凛としていた。
背筋を真っ直ぐに伸ばし、静かに佇む姿は、まるで揺るがぬ松のようで、決して弱さを見せない。
けれど――わかる。気配で。空気で。
宮様の胸の奥に、今は、重たい何かがあるのだと。
「来たか」
その声に、私は膝をつき、静かに頭を下げた。
「お呼びと伺いましたので」
一拍の間のあと、宮様はぽつりと言葉を落とした。
「……今日の清涼殿で、帝の氣を視た。深く沈んでいた。そして……金龍の気配が、完全に途絶えていた」
思わず、息を呑んだ。
金龍――帝に寄り添い、護る霊獣。
帝と心を通わせ、常に清涼殿に在るはずの、あの金龍が……消えた?
「痕跡すら……なかった。誰かが意図的に断ち切ったか、それとも、金龍自身が、何かを感じて身を隠したのか……」
宮様の声が低く沈む。部屋の灯が揺れ、御簾の影が、より深くその横顔に落ちる。
「帝は……金龍とつながっておられるのですよね。じゃあ……その金龍がいなくなったから、倒れられたのですか……?」
私の問いに、宮様は静かに頷いた。
「そうだ。あの日からずっと、帝は床に伏したままだ。……これは、この國の均衡そのものに関わることだ」
その言葉に、背筋がひやりと冷たくなる。
國の均衡――そんな、途方もないことが、いま、自分の目の前で起きているなんて。
でも、私の目は、ふとあるものを捉えていた。
宮様の拳が、膝の上で強く握られていた。その指先が、かすかに白くなっている。
どんなに冷静を装っていても、心はきっと――揺れているのだ。
宮様……。
誰よりも、帝を、御父上を想っている。その痛みを、誰にも見せずに抱えている。
言葉が、自然とこぼれていた。
「探しましょう、金龍を。……宮様のために、私、絶対に見つけます!」
思いがけず大きな声になった。でも、それは私の真心だった。
宮様の眉が、ほんの少しだけ上がる。
「……私の、ために?」
その声は、ほんの少し、からかうように響いた。けれど、私は怯まなかった。むしろ胸を張って答えた。
「当たり前じゃないですか! だって、宮様、帝を大切に想っていらっしゃるし……御父上でしょう?」
その言葉に、宮様は目を伏せた。眉が、わずかに寄る。
そして――壁をつくるように、静かで冷ややかな声が落ちた。
「……今は、霊獣頭として、職務を果たしているだけだ」
けれど、私はもう一歩、踏み込んだ。
「誰かを大切に想うことができるって、幸せなことだと思います。……いなくなってからでは、大事にしたくても、できないから」
母の面影が脳裏に浮かぶ。でも、その想いは飲み込んだ。
私の想いは、今、この人に届いてほしいから。
宮様の肩が、ほんのわずかに揺れた気がした。
御簾の向こう、闇の奥から、そのまなざしが静かに私を捉える。口元に、かすかな笑みが浮かんだ。ほんとうに、ほんとうに、ちいさな笑みだった。けれど、それは確かな光だった。
「……そなたがそこまで言うのなら、頼りにしよう」
「はいっ!」
声が少し上ずってしまったのが恥ずかしかったけれど、
胸の奥には、じんわりとあたたかいものが広がっていた。
「早速だが――金龍の痕跡を探ってほしい」
不意にそう告げられ、私は思わず背筋を伸ばした。
「……私が、ですか?」
問い返した声は、かすかに震えていたかもしれない。
「そなたには、霊獣と心を通わせ、その聲を聴き取る力がある。癒し、共鳴し、そして――迷える霊獣の魂に、呼びかける力が」
宮様は、ゆっくりと言葉を紡ぎながら、わずかに身を乗り出した。
「私は、霊獣を従え、制御し、命じることはできる。だが……彼らの声までは、届かぬ。ましてや、心の奥底に触れるような真似は、私にはできない」
その瞳は静かに揺れていた。力を持つ者ゆえの、越えられぬ壁。
どんなに氣を研ぎ澄ませても、理では届かない領域が、確かにあるのだと、私はそのとき知った。
「……でも、金龍なんて……そんな高位の霊獣に、私が……」
金龍――この国の頂点に立つ霊獣。そんな存在に、私が触れられるのだろうか。
言いかけたそのときだった。
「できる」
宮様の言葉が、ぴたりと私の思考を止めた。その目には一切の迷いがなかった。
「だが、そのためには“縁”の道を繋がねばならない」
言葉の温度が、ほんの少し、重くなる。
「白虎と“主従”の契約を結ばなければならない」
脈が跳ねるのを感じた。
「白虎と……?」
「そうだ。そなたが狙われたのも、白虎と共にいたからだ。だが、本来なら、狛猪ごときに押されるような霊獣ではない」
宮様の言葉に、あの激突の光景が胸によみがえる。
あのときの白虎――たしかに、どこか力が鈍っていた。
「白虎は、主との契約――“誓いの儀式”を経なければ、真の力を使えない」
その瞳が、まっすぐに私を射抜いた。
「白虎自身も、それを理解している。……だから、そなたの前に姿を見せたのだ」
私は、自然と目を閉じていた。
あのとき、白虎の中に感じたもの――怒り、そして哀しみ。
それは確かに、私の中にある何かと、深く呼応していた。
あの霊獣は、言葉ではなく、心で何かを訴えかけていた。
あのとき……私を見ていた。
不意に、胸の奥が温かくなった。
けれど、迷いが完全に消えたわけではない。
「でも……私なんかが、主になってもいいのでしょうか……」
ぽつりと漏れた弱音に、宮様はすぐに答えた。
「白虎は、もうそなたを選んでいる。あとは、受け入れるかどうかだけだ」
静かに告げられたその一言が、私の背中を押してくれた。
私は、小さく息を吸い、そして――頷いた。
「……わかりました。私、白虎と……誓いの儀式をします」
部屋の空気が、すっと静まり返った。その静けさは、不思議とやさしかった。
ふと、心の奥で微かな風が吹いたような感覚がした。
白虎が、どこかで私の声を聞いている気がした――
そう思えたのは、きっと、もう心が決まっていたからだ。
◆◆ ◆
夜の気配が、ゆるやかに庭を包みはじめていた。
宮様の屋敷の庭――昼間の熱を吐き出した石畳が、しっとりと夜の涼しさを吸い込んでいる。
風が細く吹き抜け、草の匂いとわずかな湿り氣を運んできた。
木々の葉が遠くで擦れ合い、小さな虫の音が、静けさの奥から響いてくる。
深く静まりかえった空間の中、私はひとり、庭の中央に立っていた。
「白虎……来てくれるかな」
ぽつりと、思いが漏れる。そのときだった。風がふっと、逆巻くように向きを変えた。
次の瞬間。木陰から、音もなく――白虎が姿を現した。
白銀の毛並みが、月の光を受けて淡く輝き、その大きな体は、まるで風が形をなしたように滑らかだった。
無駄のない動き、鋭く、それでいてどこか静かな気配。
気づけば、庭の空気がぴんと張りつめ、白虎の氣が空間を支配していた。
風がざわめき、木々がひそやかに身を震わせる。
そのとき、背後から宮様の声が聞こえた。
「すべては、そなたと白虎の心が、響き合うかどうかにかかっている」
「……はい」
私は息を吸い、白虎のもとへと歩み出した。
一歩、また一歩。
そのたびに、白虎の瞳がまっすぐ私を捉える。
深い、澄んだ――けれど、どこか切なさを湛えた光。
視線が重なった瞬間、胸の奥がぎゅっと熱くなった。
高鳴る鼓動とともに、何かが私の中で震えた。
白虎の瞳にあったもの。それは、恐れでも威厳でもない。
――痛み。そして、孤独。
その感情が、私の中のどこかと共鳴した。
心がふるえた。言葉にせずにはいられなかった。
「……怖くないよ。私も……ずっと一人だったから」
ぽつりとこぼれたその言葉に、白虎の目がふっと細められる。
低く、胸の奥に響くようなうなり声。
そして、白虎は一歩、静かに近づいてきた。
そのときだった。聲なき聲が、私の心に、すうっと届いた。
《我はそなたを主として決めた。我を受け入れよ》
大きな頭が傾き、白虎はそのたてがみの奥――うなじを、私の前に差し出してくる。
触れかけた手を、私は一度止めた。
「……本当に、私でいいの?」
問いかけた瞬間、また聲が、私の心に寄り添った。
《そなたが、いいのだ》
静かに、でも確かに――胸の奥が熱くなった。
頬に涙が伝う。理由なんて、わからなかった。ただ、あたたかかった。
私はそっと手を伸ばし、白虎のうなじに掌を添えた。
その瞬間――
私の掌から、ふわりとあたたかい潤氣がこぼれた。
やわらかく、でも確かに脈打つそれは、光の川のように白虎の体へと流れ込んでいく。
すると、白虎の大きな身体の輪郭に、ふいに鈴の音が鳴るような光の“輪”が浮かび上がった。
その光は、ゆらゆらと揺れて、私の掌へと戻ってきた。
そして――私の肌に、白虎の姿を模した淡い潤氣紋が浮かび上がる。
それはまるで、彼の魂の写し鏡。美しく、凛として、どこか儚い光だった。
次の瞬間、空気が変わった。
空間全体に柔らかな光が差し込み、まるで夜の庭そのものが呼吸を始めたように、氣の波がふわりと広がる。
音のない共鳴が、空気中にふわりふわりときらめいて、私の氣と白虎の氣が――溶け合っていくのが、はっきりとわかった。
心の奥が、深く揺れた。
私の中に、白虎がいる。白虎の中に、私がいる。
やがて、光が静かに落ち着いたとき。
白虎はそっと目を閉じて、私の胸元に頭を預けてきた。
その動きは、どこまでも静かで、優しくて……まるで、長い旅を終えた子どもが、ようやく帰る場所を見つけたかのようだった。
「……ありがとう。これから、よろしくね」
その言葉に応えるように、白虎のしっぽがふわりと揺れた。
と――背後から、足音が近づく。
振り返ると、月明かりの中に宮様の姿があった。
静かに歩み寄り、私の掌に残る潤氣紋を見つめる。
「……無事に儀式を終え、縁が結ばれたようだな。よくやったな」
その声は、いつもより少しだけ柔らかかった。目元に浮かんだ微かな笑みが、それを物語っていた。
「白虎は、そなたを“ただの主”としてではなく、“心を重ねる者”として選んだ。……誇れ」
その言葉が、すとんと胸の奥に落ちて、静かに沁みていった。
私は、はじめて心の底から笑った。何の迷いもない、まっすぐな笑みだった。
「ありがとうございます」
そう答えた私を見て、宮様はふい、と視線を逸らす。
その仕草があまりに不自然で、思わずくすりと笑ってしまった。
「……礼を言うのは、私の方だ」
その言葉に、ますます笑みがこぼれた私は、思わず口元を押さえる。
宮様は、照れ隠しのように咳払いをひとつして、ふいに表情を引き締めた。
「これで……金龍の痕跡を辿れそうだな。期待している」
「はい!」
夜風に乗って返事が高く響いた。その声は、月の光とともに空へ溶けていった。
まるで、白虎と私の新しい一歩を、そっと祝福してくれているかのように。
◆◆ ◆
翌朝――陽はまだ低く、東の空がようやく白みはじめたばかりだった。
宮様の屋敷の庭には朝露が淡く光り、若葉の先に宿った雫が、朝の光を受けてきらきらと瞬いていた。
その静けさの中を、私は霊獣寮には寄らず、宮様とともに歩き出す。
目指すは、内裏。
冷たい朝の空気が頬を撫でるたびに、胸の奥が、ふっと温かくなるのを感じていた。
歩幅を合わせながら、私はそっと掌を見下ろした。
そこには、淡く光を帯びた潤氣紋――白虎を模した紋様が、かすかに残っていた。
……白虎と、私は繋がった。
まだ夢の中にいるような感覚だった。
でも、これは幻じゃない。
白虎が私を“主”として選び、魂を重ねてくれた。そのぬくもりが、いまも私の中に確かに息づいている。
あの目、あの氣の感触……全部、本物だった。
白虎の氣が、背中から静かに支えてくれている。
まだうまく言葉にはできないけれど、心の深い場所で、私は確かに変わり始めていた。
やがて、内裏の立派な門が近づいてくる。
大きく、重々しく開かれたその門をくぐった瞬間――空気ががらりと変わった。
肌に触れる風が、ぴたりと止まった気がした。
張りつめた氣が、朝の澄んだ空にうっすらと漂っている。
まるで見えない氷の膜が地面を這っているような、ひりついた静寂が辺りを満たしていた。
内裏の回廊は、異様なまでに静かだった。
女房たちの足音、公達の衣擦れ――そのどれもが、必要以上に耳に届く。
それだけ、皆が息をひそめているのだ。何かを口にすることすら、はばかられている。
それはきっと――帝が、今も目をお閉じになったままだから。
誰もが、不安を口にできないまま、ただ沈黙している。
恐れが空気に染みこんでいるようだった。
宮様の背にぴたりとついて、渡殿を抜ける。薄暗い天井に灯された灯火が、微かに揺れていた。
弘徽殿が見えてきた。正面の庭には、季節の花が控えめに咲いている。
けれど、どの花もどこか下を向いているように見えた。
気のせいだろうか――いや、違う。あれは、白鹿の氣だ。
気高く、美しく。それでいて、何かをひたすら耐えるような、静かな力がこの庭に満ちている。その気配が、咲く花々にまで宿っているのだ。
私は小さく息を吸い、目の前の扉を見つめた。
この先にあるのは、帝の病の真実と――金龍の行方。
そして、これから私たちが向き合うべき“何か”だった。
「霊獣寮の宮様がいらっしゃいました」
女官の澄んだ声が、弘徽殿の御簾の奥へと通された。
その響きは、静かな空間にすっと溶け込む。
少しの間を置いて、やわらかな返答が返ってきた。
「ありがとう。……わざわざ来てくださったのね」
弘徽殿女御様の声は落ち着いていたけれど、言葉の奥に小さな震えがあった。
それはきっと、不安の揺らぎだった。
宮様が、御簾の前に進み出て、恭しく頭を垂れる。
「帝のご様子は――いかがでしょうか」
女御はすぐには答えなかった。
わずかな間のあと、静かな声が、空気を震わせるように返ってくる。
「……容体は変わりません。金龍の氣も、日に日に……薄れてゆくのを感じます」
その声を聞いたとき、私の隣にいた白鹿の氣が、ふっと沈んだ気がした。
背筋を伸ばしているのに、どこか寂しげで、影を背負っているようだった。
白鹿……。
霊獣は、主の心を映す存在。女御の想いが、そのまま白鹿へ伝わっているのだろう。
胸がきゅっとなった。霊獣たちは、どんなに苦しくても声に出さない。
ただ、そっと寄り添うだけ――それが彼らの優しさなのだ。
宮様が静かに口を開く。
「霊獣寮として、清涼殿における金龍の痕跡を探らせていただきたく思います。……ご許可を」
その言葉は簡潔で、けれどまっすぐだった。
声には迷いがなかった。責任を背負う者の、凛とした響き。
御簾の奥から、女御の返事が静かに届く。
「……帝と、金龍を……どうか、お願い申し上げます」
「もちろんです」
短く、それでも温度のある言葉。
宮様らしい誠実さが滲んでいて、私は心のなかで深く頷いた。
そのとき、女御がふいに私のほうを向いた氣がした。
そして、やわらかく声をかけてくださる。
「鈴太。あなたも、よろしくね」
その声は、どこまでも優しくて――まるで私を信じてくれているのだと、そう思えた。
私は両手を膝に添え、まっすぐに背を伸ばし、小さく、でもしっかりと頷いた。
「……はい」
御簾の奥に、私を見つめてくれる“まなざし”があった気がした。
言葉にはされなかった願い。けれど、はっきりと伝わってくる“想い”があった。
弘徽殿を後にし、ふたりで静かに歩き出す。
回廊の空気はひんやりとしていて、石畳に落ちる足音が遠くまで響いた。
すると、宮様がぽつりと呟く。
「……清涼殿へ向かう。痕跡は、そこにある」
その声音には、揺るぎない確信があった。
見えない何かを、きっと感じ取っている――そんな響きだった。
私はそっと、自分の掌を握る。そこには、白虎の潤氣紋が、かすかに残っていた。
白虎……。
私たちは、もう繋がっている。この絆が、道を切り拓いてくれると――信じられた。
静かに吹いた風が、背中を優しく押してくれた。
まるで白虎が「行け」と言ってくれているみたいに。
そして私は、少しだけ強くなった足取りで、清涼殿へと向かって歩みを進めた。
◆◆ ◆
弘徽殿をあとにして、私たちは静かに清涼殿へと向かっていた。
回廊を渡る足音が、白砂の敷かれた中庭にかすかに響く。
帝の命を支えてきた金龍の痕跡を、私が――
初めて任された大きな役目。その責任が、肩にじわりと重くのしかかっていた。
でも、心の奥に確かなあたたかさがあった。
背後には、白虎の気配。ひたり、と寄り添うように静かに、けれど確かにそこにいる。
昨日、あの庭で……。
あのとき交わした誓いが、まだ胸の内で柔らかく息づいていた。
白虎の聲なき聲が、今も私の中で響いている。
そんな折――
遠くで、複数の足音が近づいてくるのを感じた。
床板の軋みを耳が拾う。どうやらこちらへ向かってくるらしい。私はぴたりと足を止めた。息が浅くなる。
この感じ……。
姿が見えるよりも先に、嫌な気配が皮膚を這った。
回廊の向こうに現れたのは、数人の女房たち、そして――
その中心に立つ、一際華やかな存在。
「……燁子」
その名を、思わず声にならぬ息で漏らした。
背筋がひやりと冷え、体がひとりでに後ずさる。
白昼の空気が、急に硬くなったようだった。
陽の光は変わらぬはずなのに、まるで温度がひとつ下がったかのように感じた。
そのときだった。
隣にいた宮様が、音もなく一歩、私の前へ出た。
無言のまま、私を隠すようにすっと立ちはだかる。
その所作はあまりにも自然で、あまりにも静かだったのに、私を包む空気は一瞬で変わった。
まるで、強くてやさしい風が、私を包み込んでくれたような――そんな感じだった。
私はそっと一歩身を引き、宮様の背に隠れるようにように立った。
お願い……見つかりませんように……。
心臓が、ばくばくとうるさく鳴っていた。
耳の奥で、鼓動の音がひどく反響している。
「まあ、宮様……こんなところでお会いするなんて」
ぱっと花が咲くように、明るい声が響いた。
あまりにも華やかで、あまりにも軽やかで。その声を聞くだけで、心の奥に冷たいものが落ちるのを感じた。
どうか、このまま……通り過ぎて……。
私はただ、見つからないことを祈りながら、じっと陰に隠れた。
「金龍の件は、もうご存知でしょうか?」
その声が響いた瞬間、私は思わず息を止めた。
まるで空気に指先を這わせるような、甘く滑らかな声音。けれど、心の奥をじわりと冷やすような響きだった。
燁子は一歩、また一歩と、ためらいなく歩みを進めてくる。
裾を引く衣の揺れまでもが、計算されたように優雅だった。周囲の女房たちは距離をとり、立ち止まっていたが、彼女だけはまっすぐ、宮様のもとへ。
けれど――
「……ああ」
宮様は、その言葉を短く返すだけだった。礼もせず、ただ彼女を見据える。
その無表情の奥に、ひどくはっきりとした拒絶があった。
「大変なことになりましたね」
燁子の目元がわずかに曇る。
「わたくしも、登花殿女御様に呼ばれて参っておりましたの。金龍が……いなくなるなんて。とても、心配なのです」
私はそっと息を吐いた。
整った声色、伏せられた長い睫毛、憂いを帯びた横顔。どこを切り取っても絵のような美しさ――けれど、私の中に広がったのは、不思議なざわつきだった。
「浮橋として、金龍を探しに行こうと思っていたのです」
その瞬間、宮様の声が鋭くなった。
「……金龍探索は霊獣寮の任務だ」
声は低く、静か。だが、明確な線を引く響きだった。
「貴女が行く必要はない」
燁子は一瞬、瞬きをし、それから口角をふわりと上げて笑った。
「でも、私も連れて行ってくださいな。少しでも、お力になれればと思いまして」
「断る」
宮様の返事は即答だった。声は平坦なのに、拒絶の意志がはっきりと伝わる。
空気が、ぴんと張り詰めた。
燁子の笑顔が、かすかにひきつった。
「ただ、あなたさまが心配なのです。そばにいれば、わたくしが守れますのに。……あなたも、心配でしょう?」
やわらかな声音だった。甘く染まった声の先に、笑顔――
ちらりと目を向けて飛び込んできたその笑みは、どこかこちらを試すようだった。
胸の奥にひやりと冷たいものが差し込む。私は思わず息を飲んだ。
燁子のしてほしいことがわかる。ずっと燁子の世話を焼いてきたから。
まるで「欲しいものは、すべて手に入って当然」と言っているかのような――。
それは私にとってあの屋敷で生きるために必要だった振る舞いだったと今ならわかる。
でも、今の私は宮様にお世話になっている身。従うのはどちらなのかなんて決まっている。
私はうつむいたまま、ほんのわずかに首を横に振った。
「……お強い方ですので」
それだけを、はっきりと口にした。声は小さくても、迷いはなかった。
燁子が一瞬息を飲んだ音が聞こえた。
ちらりと視線を上げれば、ゆっくりと信じられないものを見るように目を見開き――
「まあ……」
小さく漏らして、こてりと首を傾けた。その仕草は、花が揺れるように優美だった。
けれど、ぞわり、と背筋が震える。
不意に、横にいた宮様が、ふっと私の顔を覗き込んだ。
目が合うと、ほんのわずか――ほんとうにわずかにだけ、唇がゆるんだ。
「……行くぞ」
その一言で、私は我に返った。
「はい」
短く返事をして、宮様のあとを追う。どうやら返事は正解だったみたい。
燁子のことなど見ていない。視線を背に浴びながらも、私たちは歩き出した。
静かすぎる廊の空気を切り裂くように。言葉もなく、ただ前を向いて。
背中に残った視線が、じりじりと焼けつくように痛かった。
けれど、もう振り返らなかった。
◆◆ ◆
燁子とのやりとりを終えたあと、あたりの空気が妙に濃く感じられた。
喉の奥に澱のように残る緊張――言葉にできない重さが、静かに尾を引いている。
私は宮様のすぐ後ろを歩いていた。自然と視線が足元へ落ちていた。
ふいに、足元をかすかな風がかすめた。
誰もいないはずの脇を、“何か”がすっと通り抜けていく気配。
私は思わず立ち止まり、そっと後ろを振り返った。
……白虎?
名を呼ぶより先に、胸の奥がじんわりとあたたかくなった。
姿は見えない。でも、確かに感じる。
白虎の氣が、すぐそばにある。言葉もなく、ただ静かに――私の歩みに寄り添うように。
「心配ない」と、そっと背を押してくれるような……そんな氣配。
ありがとう。私は心の中でそっとつぶやいて、再び歩き出した。
やがて、正面に清涼殿の屋根が見えてくる。
近づくにつれ、空気が変わった。音が、消えている。
鳥のさえずりも、風のざわめきも、どこか遠くへ置き去りにされたように。
まるで、世界全体が息を潜めているみたいだった。
「この静けさは……金龍の氣が完全に沈んでいる証拠だな」
宮様の低く沈んだ声が、静寂のなかに落ちる。
その響きすら、殿舎に吸い込まれていくようだった。
殿上の間に足を踏み入れると、そこには一人の男がいた。
文を手にしたまま、じっと佇んでいるのは――頭中将さま。
精悍な顔立ちのその表情には深い疲労がにじんでいて、目の下の陰は、ここ数日の混乱を雄弁に物語っていた。
宮様が静かに一礼する。
「清涼殿にて、金龍の氣を調べさせていただきたく参上しました」
頭中将さまは小さく頷き、低く息を吐いた。
「……ああ。お労しいが、好きにしてくれ。私も正直、気が気でない」
「……やはり、帝がお倒れになられてから、執務に支障が?」
「それもあるが……敏行が、顔を出さないのだ」
その名が出たとたん、宮様の表情がわずかに動いた。
「氏蔵人殿が?」
「ああ。あの男、律儀だったからな。帝が倒れられた日を境に、姿を見せていない。どうにも胸騒ぎがしてな……」
氏蔵人と言えば源敏行さま。弘徽殿の女房の三条さまの恋人……。
名を聞いただけで、胸のどこかがざわりとした。でも、何がそうさせたのかはまだ、言葉にできなかった。
「……ご報告の件、承知しました。清涼殿内の調査を続けます」
宮様が深く一礼すると、頭中将さまも、静かにうなずいた。そのやりとりの隙間に、私はまた一歩、殿の奥へと歩みを進めた。手のひらに感じる白虎の紋が、静かに脈打つ。
見つけよう、きっと……。
私は目を伏せ、強く、そう願った。
私たちは、静かに足音を忍ばせながら、帝の御寝所のすぐ傍まで進んだ。
言葉にするまでもなく、ここが“特別な場所”であることは、足を踏み入れた瞬間にわかった。
空気が違っていた。澄んでいるはずなのに、どこか張り詰めていて、喉の奥がきゅっと詰まるような氣配。それでも、私は足を止めなかった。宮様の背が、確かな導きとなってそこにあったから。
周囲に誰もいないのを確かめた宮様が、ふいに立ち止まった。
そして、静かに手を上げ、指先で印を結ぶ。その動作に合わせるように、場の空気がぴんと張り詰めていく。
まるで、薄い水面の上に目に見えない波紋が広がっていくようだった。
光も音も、わずかに歪み、空間全体が結界の膜で包まれていく。
「白虎と共鳴して、この空間に残る“氣の残響”を辿れ」
宮様の声は低く、落ち着いていて、でも、芯の奥に確かな力を宿していた。
私は、小さく頷く。
そして、心の中で白虎の名をそっと呼ぶ。
――白虎、お願い。来て。
次の瞬間、空気の密度がふわりと変わった。
それは風でもなく、音でもなく、ただ「氣」が動いた感覚。
やがて、静寂のなかに、白銀の光がゆらりと浮かび上がった。
庭での誓いのときと同じように、白虎が現れた。
半透明の身体。輪郭がゆらめいていて、まるで夢と現実の狭間に立つ幻のようだった。
けれど、その氣は確かだった。深く、力強く、私の心の奥に触れてくる。
白虎は音もなく近づき、そっと鼻先で、私の手に触れた。
……ありがとう。来てくれて。
そのぬくもりが、まるで心に灯る小さな焔のように、私の不安を溶かしていく。
私は深く息を吸って、ゆっくりと目を閉じた。
掌を白虎の額にそっと添える。
――私は、あなたとつながりたい。
金龍の聲を、一緒に探したいの。心の奥で、そう祈った。
すると、白虎の氣が、私の内側へと奔流のように流れ込んできた。
ぐらり、と世界が揺れた。
外の音が遠のき、色彩が溶け、視界は淡い白金色の霧に包まれていく。
宮様の存在も、気配も、もうずっと遠くへ離れていった。
私は今、ただ白虎とふたり。意識がするすると沈み込み、“氣の層”へと導かれていく。
私自身が、空気そのものになっていくような感覚。
風の流れが肌をなぞるのではなく、私の中を通り抜けていく。
音が耳に届くのではなく、光の粒となって心に語りかけてくる。
五感が、静かに、けれど確かに――
世界そのものと、ひとつに溶け合っていった。
やがて意識がはっきりしてくると視界が開けてくる。
ここは――清涼殿、か。
張りつめた静寂の中に、空間全体を包み込むような、重たくも穏やかな氣が満ちていた。
淡い金色のひかりが、宙に揺らめく。空気の層が折り重なるように、その氣は静かに漂い、私の頬にかすかな温もりを残していく。
……金龍の氣……思わず、息を呑んだ。
それは威厳に満ちていながら、どこかあたたかく、優しさを秘めた氣。
まるでこの清涼殿という空間そのものが、金龍に護られていたかのように、柔らかく満ちていた。
確かに……ここに、いたんだ。
けれど――その流れは、ある一点でふいに“ぷつり”と断ち切られていた。
風が止まり、空気が一瞬、真空のように沈黙する。
私の胸の奥で、白虎の氣がかすかに震えた。
それは、私の感じた確信と、ぴたりと重なっていた。
「……金龍はここで……強制的に、“氣を断たれた”んだ」
その言葉を口にした瞬間、胸の奥が痛む。
断ち切られた氣の断層から、何かが流れ出しているのがわかった。
それは――氣の名残。
微かな残響が、水脈のように足元を伝い、“下”へと降りていく。
この流れ……掌を床に近づけた瞬間、目の奥に浮かび上がるような感覚があった。
氣の糸が、ゆるやかに編まれていく。その先は、ひとつの場所を示していた。
神泉苑……。
「……あそこに、金龍はいる」
私の言葉に応えるように、氣の帯が細く鋭く光る。
けれど、その流れには、もうひとつ異質な氣が絡んでいた。
墨を水に落としたように、濁り、混ざり、にじんでいく氣。
それは自然のものではなかった。人の手によって放たれた、強い意図を持つ氣――
そのときだった。ふいに、香の記憶が鼻腔をかすめた。
甘く、けれど刺すような刺激。どこか湿っていて、肌の奥にまとわりつくような重たい香り。
「……この香り……」
私の指先に、氣の痕跡がまとわりついているのを感じた。
それは、擾乱香――霊獣の氣を乱すために仕掛けられた、邪の香。
白虎が、低く唸った。それは怒りとも警戒ともつかない、けれど確かな“拒絶”の音。
そしてその瞬間、視界の奥に像が浮かび上がった。
香を纏った衣。薄暗い室内に、ひとり立つ影。それは――
……氏蔵人さま……?
その姿は、この清涼殿で見かけたときと同じだった。白虎の中にある強い警戒が、私の胸に流れ込んでくる。
氣の探知はまだ続いている。でも、心が――追いつかない。
揺らぐ景色のなかで、私は小さく息を吸い込んだ。
そのときだった。
白虎の氣が、私をさらに深く引き込んできた。
まるで静かな水底へ吸い込まれていくように、私の内側がゆっくりと深層へと潜っていく。視界は、淡い金色に染まり始めた。
光でもなく、霧でもない――それは、氣の記憶。まるで誰かの心の奥を、夢のように覗き見るような感覚。
……これは……金龍の、記憶……?
遠くに、まばゆい空が広がる。その空を悠然と舞う、威風堂々たる龍――金龍。
その姿は、ただそこに在るだけで空間を支配していた。
厳かで、慈愛に満ちていて、それでいてどこか哀しみを秘めている。
その氣が、胸の奥にずしりと響く。王の氣。揺るぎなき、守護の氣。
そして、その背に――もうひとつ、幼い龍の姿。
金龍の尾に絡むように、ちいさな身を寄せ、守られるようにして飛んでいた。
まるで、眷属。慈しみ育てられる、小さな命。
……あれも……金龍の一部……?
世界が、ふっと揺れた。光の流れが変わる。場面が変わる。
花が静かに舞い、薫き立つ香が空気を包む、神聖な場――これは何かの儀式?
そこに立っているのは、見覚えのある横顔。今よりも幼い燁子に見える。
白い神聖な装束を纏い、長い黒髪が艶やかに流れる。両手を胸前に掲げ、霊獣と氣を繋いでいる様子はまるで神霊の使いのよう。
その場からは少し離れて座しているのは、同じく若き日の――宮様。
まだ幼さを残した顔立ち。それでも、その瞳の奥にあるのは今と変わらぬ、凛としたまなざしで儀式を見つめている。
ふっと二人の視線が絡んだ。
燁子は頬をほんのり染めて、まっすぐに宮様を見つめている。
その瞳にあったのは――憧れ、恋慕、そして……決意。
なに……これ……。
胸がきゅっと縮まった。
もしかして、これは――“浮橋”の儀?
氣の共鳴が、ふいに乱れた。白虎が、低く唸る。私の動揺を敏感に察したのだ。
視界の端が揺らぎ始める。
波紋のように、夢の記憶がにじみ、形を崩していく。
……まだ……見ていたいのに……。
金龍の記憶。その深層には、きっともっと重要なものが――
けれど。白虎が、強く氣を震わせた。その共鳴の一撃が、私を現実へと引き戻す。
ぐらりと重心が浮いた感覚のあと、空間が微かにきしむ音が響いた。
濃く満ちていた金の霧が、ふわりと風に溶けるようにして散っていく。
光も音も、色も輪郭も、現実の世界が戻ってくる。
私は、膝から崩れるようにして座り込んだ。全身から力が抜け、肩が勝手に上下する。
いつの間にか、浅くなっていた息にようやく気づいた。
……まだ……心が追いつかない。
金龍の氣の残滓。擾乱香の残り香。
そして、あの少女の――燁子の瞳に宿っていた、あの感情。
あれは、憧れなどという甘やかなものではなかった。
もっと深く、もっと強く、もっと……執着に近いもの。
あの頃から……ずっと……?
胸の奥に、ざわりと重たい渦が巻いた。
白虎の氣が、そっとそれを鎮めるように寄り添ってくれるのを感じながら、私はゆっくりと顔を上げた。
夢の余韻はまだ、指先の感覚に残っていた。
「大丈夫か」
耳元に落ちてきたのは、低く、けれどどこまでもやわらかな声だった。
ふと顔を上げると、宮様がすぐそばにいた。
いつの間にか、私の背中に――あたたかな掌がそっと添えられている。
……優しい。その掌の温度に、心がほろりとほどけそうになる。
けれど、その優しさに触れてしまったせいで、逆に胸が締めつけられた。
目の奥が熱くなりかけて、私は慌ててまぶたを伏せた。
まだ言葉が、うまく繋がらない。気持ちが、整理できていない。
小さく息を吐いて、ようやく私は声をしぼり出した。
「……はい」
たったそれだけが、今の私の限界だった。
視線を膝に落とし、手を握る。震えていないか、確かめるように。
「見えたのか」
静かな問いが、すぐに落ちてくる。
「はい」
「何が見えた? 話してくれ」
急かすでもなく、ただまっすぐな声だった。
けれど、その声の奥には確かな真剣さがあった。
私は言葉を選びながら、ゆっくりと口を開いた。
「……金龍の氣は、神泉苑の方角に流れていました」
「神泉苑か……」
低くつぶやく宮様の声が、空気のなかに沈んでいく。
私の隣には、白虎が静かに座っていた。
言葉はなくとも、その大きな身が、私にそっと寄り添ってくれている。
分かってくれてる……。
そのぬくもりが、胸の奥にじんわりと広がった。
私は、もうひとつの大きな氣配を、思い出す。言葉にするのは怖かったけれど、それでも、告げねばならない。
「それと……擾乱香を纏っていたのは、氏蔵人の……源敏行さまでした」
その名を口にした瞬間、宮様の表情がかすかに動いた。
息を短く吸い込んだあと、目を伏せ、低くつぶやく。
「……氏蔵人殿、そうか」
短い沈黙が流れる。
その間に、宮様は何かを振り返るように、遠い目をしていた。
やがて、その静けさを破るように、落ち着いた声が返ってきた。
「……実家に戻った三条に、鳳凰を通して様子を見させていたんだが……昨日、敏行殿が一度だけ顔を出したという」
「三条さまのところに……?」
驚きと不安が混ざった声が、自然と口をついて出る。
「何か、つながりがあるのかもしれない。そう思って、今、別筋で調べさせている」
その声には、迷いのない意思がこもっていた。けれど、そのすぐあと、少しだけ声音が沈む。
「……だが。たとえ繋がりがあったとしても、霊獣を持たぬ者が、なぜ“潤氣擾乱香”を使えたのか。そして、それを帝のおわす清涼殿で使った理由が、どうしても分からぬ」
低く抑えた声の奥に、苛立ちとも焦りともつかぬ感情がにじんでいた。
「ともかく、まずは金龍を見つけ出さねばならぬ」
宮様の瞳が、まっすぐに私を射抜いた。
「……向かうぞ、神泉苑へ」
その一言に、私は深く、強くうなずく。
「はい」
風がひと筋、私たちのあいだをすり抜けていった。
白虎が立ち上がる。その足元に残された氣の名残が、かすかに揺れた。
いつもなら霊獣たちの潤氣が穏やかに流れ、朝露のような静けさが広がっているはずなのに、今日は空気がぴりついている。中庭の木立がざわめき、空を渡る風もどこかせわしない。霊獣たちも、普段より敏感に周囲をうかがっているようだった。
そんな中、私は宗直様の少し後ろを、控えめな歩幅でついていった。
これから内裏の巡回に向かうのだという。私はまだ正式な補佐ではないけれど、それでも――外に出られることが、ただ嬉しかった。霊獣寮という世界の中に身を置くようになってから、こうして任務に加わることが、少しずつ自分の居場所になっていく気がしていた。
「鈴太、そろそろ行くか」
呼びかけられて、私は軽くうなずいた。
「はい」
宗直様に続いて霊獣寮の門をくぐろうとした、その時だった。
目の前に、三つの人影が立ちはだかった。誰かと思えば――在原貞親様。狛猪を連れた、先輩の霊獣師だ。後ろには、いつも貞親様の傍にいる取り巻きの二人がいて、冷えた視線をこちらに向けていた。
「殿上童のお前が、どうして内裏の巡回なんて任されるんだ!」
貞親様の声が、早朝の空気を裂く。強い潤氣を含んだ怒気が、目に見えぬ波のように押し寄せてきた。
「俺の補佐だよ。補佐。宮様の指示だろう。お前が口出すところじゃない」
宗直様は、いつも通りの軽やかな口ぶりだった。けれど、その目はほんの少し鋭く光っていた。ふざけた言葉の奥に、決して引かぬ強さがにじんでいる。
私は、思わず宗直様の袖の端を握った。胸の奥で、小さな警鐘が鳴る。
「なにを……!」
貞親様が一歩、踏み出す。その動きに呼応するように、狛猪の潤氣がぶわりと膨れあがった。怒りの氣が空間を震わせ、私の皮膚にぴりりとした痛みが走る。狛猪の目がぎらりと光り、今にも飛びかかってきそうな気配を放つ。
噛みつかれる、そう思った瞬間だった。
「た、大変です! 霊獣頭殿はいらっしゃいますか!」
霊獣寮の奥から、若い蔵人が駆け込んできた。顔は青ざめ、額には玉のような汗。息を切らし、震える手で袖を押さえていた。
あまりの形相に、貞親様も宗直様も、さきほどまでの怒気を忘れたかのように振り返った。
「こちらです!」
宗直様が声をかけ、私も小走りであとに続く。
蔵人の顔――ただならぬ気配だった。胸の内に、ひやりと冷たいものが流れ込んでくる。
霊獣寮の一角。朝の光が几帳越しに差し込み、淡く光る畳の上に静けさが降りていた。宮様は文台に向かい、筆を走らせておられた。この一角だけは時間が止まっているように思えた。
その静寂を足音が破った。
「失礼いたします。霊獣頭殿!」
息を切らした声。土間に砂を跳ね上げて、新蔵人さまが飛び込む。
袴の裾が乱れ、顔面は青ざめ、手はわずかに震えている。
「何事か」
「帝が、帝がお倒れになりました!」
駆け込んできた新蔵人さまの声は、風を裂くように鋭かった。肩で息をしながら、必死の形相で言葉をつづける。
「原因は……まだ、突き止められておりません。つきましては、霊獣頭殿に、帝の金龍を……ご覧いただきたく……」
新蔵人さまの声が掠れ、畳に両手をついた。
宮様は、顔を上げた。
ほんのわずかに、筆を止める動きが遅れた。
……その一瞬。私は見た。
あの方の目の奥に、かすかな揺らぎが走ったのを。感情の色――心の底に沈めているはずの波が、ふっと光に触れたように。
「清涼殿へ向かう」
ただそれだけ。低く、静かに告げて、宮様は立ち上がられた。
「宗直、霊獣師の皆に伝えよ。霊獣騒乱事件があったばかりだ。大臣や女御方の霊獣の潤氣を確認するのだ。異変があれば、すぐに報せよ」
「はっ!」
号令のように声が返り、霊獣師たちが四方へ駆け出す。
廊下の板が軋み、足音が響く。空気が動き、静寂が熱を帯びて騒がしくなる。
宗直様も踵を返して走り出そうとした。
「あの!」
私は思わず袖をつかんでいた。肩に力が入っていた。自分の声が少し上ずっていた。
「わたしも、行かせてください。なにか……私にもできるかもしれません」
宗直様の顔が近くにあった。困ったように笑って、でも、目だけは優しかった。
「……鈴太は、留守を頼む」
「え……」
「今回は、殿上童の身分じゃ行けない任務だ。すまんな」
そのひとことが、冷たく鋭い刃のように胸に刺さった。
何も言えずに、私はただ、首を縦にふることしかできなかった。
宗直様の背が、視界の向こうに遠ざかっていく。
宮様も、新蔵人さまに案内されて、静かにそのあとを追われた。
ふたたび静けさが戻った霊獣寮。
私はその場に立ち尽くしていた。風もなく、音もないのに、心の中にぽっかりと穴があいたようだった。
そのとき、白虎の氣がそっと触れてきた。姿は見えない。でも、確かにいる。
――だいじょうぶ、と言ってくれている気がした。
私はそっと胸に手をあて、唇をかみしめた。
でも、心のどこかでまだ――あの背中を、追いたいと思ってしまっていた。
◆◆ ◆
霊獣寮の朝は、変わらぬ静けさに包まれていた。
けれど、澄んだ空気の奥底をそっとかき乱すように、私の胸の中だけが落ち着かなかった。
――帝が倒れた。
その知らせが届いてから、もう三日が経つ。
寮の天井から差し込む光はいつもどおりで、庭に降る露も、木々のざわめきも変わらない。けれど世界のどこかが、もう戻らない場所へと動いてしまった気がしてならなかった。
宗直様たちは、内裏の巡回に出ている。私は霊獣寮に残り、留守番をしていた。
誰もいない廊下を一人で歩くと、足音がやけに大きく響く。
ひとりきりの空間に、心の奥のざわめきがこだましてしまいそうだった。
「……掃除でも、しようかな」
誰に向けるでもなく、呟いた。
そうして何かしていないと、胸の奥の不安がどんどんふくらんで、追いつめられてしまいそうだった。
帝のことは、もちろん心配だ。
けれど、それ以上に気がかりだったのは、宮様のことだった。
あの方にとって、帝は父。
静かに自分を律しておられるあの方の中で、何かが崩れてしまっていなければいい――そう思うと、じっとしていられなかった。
私は箒を手に庭へ出た。
苔むした石畳の隙間から、桐の葉が風に舞っていた。
ひとつひとつを集めながら、呼吸を整えるように箒を動かす。
しんと張りつめた空気の中に、ふとやわらかな氣配が混じった。
振り返らなくてもわかる。
小さな霊獣たちが、どこからともなく現れていた。
最初に来たのは、ころんと丸い、鈴のような霊獣。金属のようにきらきらした体が、光を反射してふるふると震えている。
次に姿を見せたのは、花のような耳を持つ鳥型の霊獣。ふわりと枝にとまり、首をかしげて私を見つめた。
ひとつ、またひとつ――霊獣たちは、まるで私の心を読み取ったかのように、静かに集まってきた。
私のそばに寄り添い、肩に乗り、袖にすがるようにして、そっと温もりをくれる。
「……ありがとう」
小さく声を出すと、小さな霊獣たちは、ぴぃ、と鳴いて応えてくれた。
私はしゃがんで、そっとその背を撫でる。
やわらかくて、あたたかい。そのぬくもりが、胸の奥の冷たさをじんわりと溶かしていく。
こらえようとしても、まぶたの裏が熱くなる。
でも泣いちゃだめ。だって、誰かが見ている――そう思った瞬間だった。
風が……鳴らなかった。
音もなく、影のように現れたその姿に、私は息を呑んだ。
白虎。
「……!」
気高く、堂々としていて、どこか人を寄せつけない静謐さをまとっている。
けれど、その双眸だけは違っていた。深く静かに、まるで心の奥を覗きこむように、私を見つめている。
「白虎……」
名前を呼ぶと、白虎は一歩、また一歩と音もなく近づいてくる。
その大きな体が地を踏むたび、空気が震えるような気がした。
何も言わず、ただ私のそばに腰を下ろす。
霊獣たちが、白虎のまわりに静かに集まってきた。
丸い子も、羽根のある子も、皆おだやかにその姿を囲む。
音のない静けさの中に、ぬくもりだけが、ひっそりと満ちていく。
私は両手を胸元に重ねて、白虎の氣にそっと意識をゆだねた。
大丈夫、そう言ってくれているようだった。
「へえ、こんなところに白虎がいるなんてな」
その声が落ちた瞬間、私の背筋に冷たいものが走った。
風の止んだ庭に、硬質な靴音が響く。
「……貞親様……?」
振り向くと、木立の陰から姿を現した貞親様が、こちらを真っすぐに見ていた。
その目は冷えきっていて、まるで人ではないもののように感じた。
「どうして……巡回は……」
「ああ、早めに終わったから戻ってきたんだ。おかげでいいものを見つけたよ」
問いかけた声は、自分でも驚くほどか細かった。
答える代わりに、彼は私と白虎、それに周囲の霊獣たちを睨みつける。
「まさか……お前が白虎を従えているなんてな」
「従えてなんか、いません」
私は言った。震えをこらえながら。
「なぜか、白虎が……そばにいてくれてるだけで……」
その言葉が終わるより先に、貞親様の表情が歪んだ。
憎しみがあらわになる。言葉ではなく、呪いのようだった。
「そんなことは、どうでもいいんだよ」
低く、くぐもった声が響く。
「……あの方が言ってた。悲しげに――白虎とともにいる“誰か”に、心を傷つけられたと」
「……何の話ですか!?」
私の問いかけには応えず、貞親様は淡々と呟いた。
「……あの方の安寧のために――お前には、消えてもらう」
一瞬、時が止まったように感じた。
その直後。
「狛猪――ッ!!」
地を裂くような咆哮。貞親様の霊獣・狛猪が、檻を破った獣のように飛び出した。
「っ……!」
重い地響きが迫る。空気が震え、地面の小石が跳ねた。
小さな霊獣たちが悲鳴のように鳴いて、空へ逃げる。
目の前に、白虎の白い影が飛び出した。
「白虎……!」
その背が、私を守るように立ちはだかる。
牙と牙がぶつかりあい、獣同士の氣が衝突する轟音があたりに響く。
白虎が狛猪の突進を正面から受け止めた――そのはずだった。
けれど、次の瞬間。
「白虎……!?」
白虎の足が、わずかに滑った。
狛猪の頭突きが肩をかすめ、白虎の体が後方へ吹き飛ぶ。
「白虎!」
私は思わず駆け出した。
その間にも、狛猪は止まらない。次の突進に向けて氣を高めている。
白虎が立ち上がる。けれど、動きが鈍い。
いつもの冴えがない。牙を向けながらも、どこか迷いがあるようだった。
なぜ――? どうして迷っているの?
「白虎!」
私は叫びながらその背に手を伸ばした。
ぬくもりが、手のひらに伝わる。けれど、その奥にある氣は揺れていた。
苦しさと、迷いと、ためらい――まるで、自分を責めているような。
「お願い、動かないで……無理しないで……!」
白虎は、私を振り返らなかった。
ただ、前を向いていた。狛猪に向けて、もう一度体を低く構える。
再び衝突の音。肉と氣の激突。
――でも、押されている。
狛猪の爪が白虎の肩を裂いた。血が飛ぶ。白虎の咆哮。苦痛の響きが、私の胸を切り裂いた。
「もうやめて……白虎……!」
私はその背中にすがった。震える手で、白虎の体を抱きしめる。
でも、白虎は私の前に立ち続けた。
たとえ傷ついても、倒れても、私の盾であろうとするように。
「……下がれ」
冷たい刃のような声が、私の背に突き刺さった。
空気が一瞬で変わった。胸の奥に、ひやりとしたものが走る。
振り返ったとき、私は思わず息をのんだ。
「宮様……!」
そこにいたのは、まさしく――
光をまとい、鳳凰を背に従えた宮様だった。
長衣が風に揺れ、足元には靄のような潤氣が漂っている。
その姿は、夜の底に射す陽光のように、凛としていて、絶対だった。
鳳凰が、ふわりと羽ばたいた。
――ぶわ、と音もなく、空気が跳ね上がる。
重力がねじれたように感じた。
世界の氣が、逆巻くように反転する。
「……!」
私の呼吸が止まった。肌が焼けるように熱くなる。
黄金の炎――それが、天から差し込むように降ってきた。鳳凰の潤氣だ。
「グゥオオオオ……ッ!」
狛猪が悲鳴のような声を上げた。
目を剥き、足を暴れさせるが、もう抗えない。
鳳凰の氣に包まれたその体は、まるで重力に呑まれるようにねじ伏せられていく。
「――っ!」
地を這うような音とともに、狛猪の巨体が宙を舞い、地面に叩きつけられた。
振動が足元を伝う。
埃が舞い、空気が震える。
あの狛猪が――まるで木の葉のように、吹き飛ばされた。
「っ……貞親様……!」
小さくそう呟いたとき、彼の体が崩れるように倒れた。
目を見開いたまま、口元には泡。
わずかに痙攣しているが、意識は――ない。
私はまだ、白虎の背にしがみついていた。
白虎の體は温かく、けれどかすかに震えていた。
さっきの一撃が、全身に響いていたのだろう。私の手のひらにも、それが残っていた。
「……白虎……ありがとう」
その名をそっと口にした瞬間、鳳凰が低く鳴いた。
空を円を描くように飛びながら、場の氣を撫でていく。
そして――白虎は、ふとこちらを振り返ると、そのまま氣の流れに身を融かすようにして、姿を消した。
「無事か」
すぐ近くで、低く、けれど優しい声がした。
顔を上げると、宮様がすでに私の傍らに立っていた。
すべてを見通すような眼差し。けれど、その奥にあるのは、責めではなく、心配だった。
「……はい、でも……わたしにも、どうしてこんなことになったのか……」
言葉がうまく出てこなかった。
「白虎を見てから、急に、貞親様の様子が……」
「白虎を“見て”から、か」
その言葉に、宮様の眉がわずかに寄った。
そして、一拍の間のあとで、声を落として言った。
「……このことは、誰にも告げるな」
私はこくりと頷いた。
宮様は静かに貞親様のもとへ歩いていく。
しゃがみこみ、その額に手を置いた。
鳳凰がひときわ明るく光る。
その氣が、やわらかく、まるで記憶をなぞるように流れこんでいく。
「……貞親の中から、白虎に関する記憶を消した。おそらく、誰かの潤氣が、感情を過剰に増幅させている」
言いながら、宮様の目が細められた。
そこへ、あわただしい足音が近づいてきた。
宗直様たちだ。
「貞親!? どうした、何が……!」
霊獣師たちが目を見開き、倒れた貞親様に駆け寄る。
「霊獣騒乱事件と関係がある可能性がある」
宮様がすっと立ち上がる。
「詳しくは追って伝える。まずは彼を薬師に見せてくれ」
「はっ!」
霊獣師たちが肩を貸して、意識のない貞親様が運ばれていく。
その騒がしさの中、宮様がそっと私の耳元に口を寄せた。
「白虎のことは、誰にも言うな。それと……話がある。あとは屋敷で」
その言葉に、私は小さく頷いた。
白虎の残した氣の名残が、まだ胸の奥で揺れていた。
その揺れが、私の中の何かと静かに響き合っていた。
◆◆ ◆
宮様の屋敷の庭に、夜の帳がゆっくりと降り始めていた。
昼間の混乱が嘘のように、虫の声がかすかに響いている。
灯籠の火が風に揺れ、影がゆらゆらと地面を這っていくのを、私はぼんやりと見つめていた。
夕餉の後、たきさんに呼ばれた。宮様が、お話があるとおっしゃっている、と。
胸の奥に、どこかひりつくような緊張を抱えながら、私はそっと障子を開けた。
御簾の向こう――そこに座しておられるその姿は、いつもと変わらず、凛としていた。
背筋を真っ直ぐに伸ばし、静かに佇む姿は、まるで揺るがぬ松のようで、決して弱さを見せない。
けれど――わかる。気配で。空気で。
宮様の胸の奥に、今は、重たい何かがあるのだと。
「来たか」
その声に、私は膝をつき、静かに頭を下げた。
「お呼びと伺いましたので」
一拍の間のあと、宮様はぽつりと言葉を落とした。
「……今日の清涼殿で、帝の氣を視た。深く沈んでいた。そして……金龍の気配が、完全に途絶えていた」
思わず、息を呑んだ。
金龍――帝に寄り添い、護る霊獣。
帝と心を通わせ、常に清涼殿に在るはずの、あの金龍が……消えた?
「痕跡すら……なかった。誰かが意図的に断ち切ったか、それとも、金龍自身が、何かを感じて身を隠したのか……」
宮様の声が低く沈む。部屋の灯が揺れ、御簾の影が、より深くその横顔に落ちる。
「帝は……金龍とつながっておられるのですよね。じゃあ……その金龍がいなくなったから、倒れられたのですか……?」
私の問いに、宮様は静かに頷いた。
「そうだ。あの日からずっと、帝は床に伏したままだ。……これは、この國の均衡そのものに関わることだ」
その言葉に、背筋がひやりと冷たくなる。
國の均衡――そんな、途方もないことが、いま、自分の目の前で起きているなんて。
でも、私の目は、ふとあるものを捉えていた。
宮様の拳が、膝の上で強く握られていた。その指先が、かすかに白くなっている。
どんなに冷静を装っていても、心はきっと――揺れているのだ。
宮様……。
誰よりも、帝を、御父上を想っている。その痛みを、誰にも見せずに抱えている。
言葉が、自然とこぼれていた。
「探しましょう、金龍を。……宮様のために、私、絶対に見つけます!」
思いがけず大きな声になった。でも、それは私の真心だった。
宮様の眉が、ほんの少しだけ上がる。
「……私の、ために?」
その声は、ほんの少し、からかうように響いた。けれど、私は怯まなかった。むしろ胸を張って答えた。
「当たり前じゃないですか! だって、宮様、帝を大切に想っていらっしゃるし……御父上でしょう?」
その言葉に、宮様は目を伏せた。眉が、わずかに寄る。
そして――壁をつくるように、静かで冷ややかな声が落ちた。
「……今は、霊獣頭として、職務を果たしているだけだ」
けれど、私はもう一歩、踏み込んだ。
「誰かを大切に想うことができるって、幸せなことだと思います。……いなくなってからでは、大事にしたくても、できないから」
母の面影が脳裏に浮かぶ。でも、その想いは飲み込んだ。
私の想いは、今、この人に届いてほしいから。
宮様の肩が、ほんのわずかに揺れた気がした。
御簾の向こう、闇の奥から、そのまなざしが静かに私を捉える。口元に、かすかな笑みが浮かんだ。ほんとうに、ほんとうに、ちいさな笑みだった。けれど、それは確かな光だった。
「……そなたがそこまで言うのなら、頼りにしよう」
「はいっ!」
声が少し上ずってしまったのが恥ずかしかったけれど、
胸の奥には、じんわりとあたたかいものが広がっていた。
「早速だが――金龍の痕跡を探ってほしい」
不意にそう告げられ、私は思わず背筋を伸ばした。
「……私が、ですか?」
問い返した声は、かすかに震えていたかもしれない。
「そなたには、霊獣と心を通わせ、その聲を聴き取る力がある。癒し、共鳴し、そして――迷える霊獣の魂に、呼びかける力が」
宮様は、ゆっくりと言葉を紡ぎながら、わずかに身を乗り出した。
「私は、霊獣を従え、制御し、命じることはできる。だが……彼らの声までは、届かぬ。ましてや、心の奥底に触れるような真似は、私にはできない」
その瞳は静かに揺れていた。力を持つ者ゆえの、越えられぬ壁。
どんなに氣を研ぎ澄ませても、理では届かない領域が、確かにあるのだと、私はそのとき知った。
「……でも、金龍なんて……そんな高位の霊獣に、私が……」
金龍――この国の頂点に立つ霊獣。そんな存在に、私が触れられるのだろうか。
言いかけたそのときだった。
「できる」
宮様の言葉が、ぴたりと私の思考を止めた。その目には一切の迷いがなかった。
「だが、そのためには“縁”の道を繋がねばならない」
言葉の温度が、ほんの少し、重くなる。
「白虎と“主従”の契約を結ばなければならない」
脈が跳ねるのを感じた。
「白虎と……?」
「そうだ。そなたが狙われたのも、白虎と共にいたからだ。だが、本来なら、狛猪ごときに押されるような霊獣ではない」
宮様の言葉に、あの激突の光景が胸によみがえる。
あのときの白虎――たしかに、どこか力が鈍っていた。
「白虎は、主との契約――“誓いの儀式”を経なければ、真の力を使えない」
その瞳が、まっすぐに私を射抜いた。
「白虎自身も、それを理解している。……だから、そなたの前に姿を見せたのだ」
私は、自然と目を閉じていた。
あのとき、白虎の中に感じたもの――怒り、そして哀しみ。
それは確かに、私の中にある何かと、深く呼応していた。
あの霊獣は、言葉ではなく、心で何かを訴えかけていた。
あのとき……私を見ていた。
不意に、胸の奥が温かくなった。
けれど、迷いが完全に消えたわけではない。
「でも……私なんかが、主になってもいいのでしょうか……」
ぽつりと漏れた弱音に、宮様はすぐに答えた。
「白虎は、もうそなたを選んでいる。あとは、受け入れるかどうかだけだ」
静かに告げられたその一言が、私の背中を押してくれた。
私は、小さく息を吸い、そして――頷いた。
「……わかりました。私、白虎と……誓いの儀式をします」
部屋の空気が、すっと静まり返った。その静けさは、不思議とやさしかった。
ふと、心の奥で微かな風が吹いたような感覚がした。
白虎が、どこかで私の声を聞いている気がした――
そう思えたのは、きっと、もう心が決まっていたからだ。
◆◆ ◆
夜の気配が、ゆるやかに庭を包みはじめていた。
宮様の屋敷の庭――昼間の熱を吐き出した石畳が、しっとりと夜の涼しさを吸い込んでいる。
風が細く吹き抜け、草の匂いとわずかな湿り氣を運んできた。
木々の葉が遠くで擦れ合い、小さな虫の音が、静けさの奥から響いてくる。
深く静まりかえった空間の中、私はひとり、庭の中央に立っていた。
「白虎……来てくれるかな」
ぽつりと、思いが漏れる。そのときだった。風がふっと、逆巻くように向きを変えた。
次の瞬間。木陰から、音もなく――白虎が姿を現した。
白銀の毛並みが、月の光を受けて淡く輝き、その大きな体は、まるで風が形をなしたように滑らかだった。
無駄のない動き、鋭く、それでいてどこか静かな気配。
気づけば、庭の空気がぴんと張りつめ、白虎の氣が空間を支配していた。
風がざわめき、木々がひそやかに身を震わせる。
そのとき、背後から宮様の声が聞こえた。
「すべては、そなたと白虎の心が、響き合うかどうかにかかっている」
「……はい」
私は息を吸い、白虎のもとへと歩み出した。
一歩、また一歩。
そのたびに、白虎の瞳がまっすぐ私を捉える。
深い、澄んだ――けれど、どこか切なさを湛えた光。
視線が重なった瞬間、胸の奥がぎゅっと熱くなった。
高鳴る鼓動とともに、何かが私の中で震えた。
白虎の瞳にあったもの。それは、恐れでも威厳でもない。
――痛み。そして、孤独。
その感情が、私の中のどこかと共鳴した。
心がふるえた。言葉にせずにはいられなかった。
「……怖くないよ。私も……ずっと一人だったから」
ぽつりとこぼれたその言葉に、白虎の目がふっと細められる。
低く、胸の奥に響くようなうなり声。
そして、白虎は一歩、静かに近づいてきた。
そのときだった。聲なき聲が、私の心に、すうっと届いた。
《我はそなたを主として決めた。我を受け入れよ》
大きな頭が傾き、白虎はそのたてがみの奥――うなじを、私の前に差し出してくる。
触れかけた手を、私は一度止めた。
「……本当に、私でいいの?」
問いかけた瞬間、また聲が、私の心に寄り添った。
《そなたが、いいのだ》
静かに、でも確かに――胸の奥が熱くなった。
頬に涙が伝う。理由なんて、わからなかった。ただ、あたたかかった。
私はそっと手を伸ばし、白虎のうなじに掌を添えた。
その瞬間――
私の掌から、ふわりとあたたかい潤氣がこぼれた。
やわらかく、でも確かに脈打つそれは、光の川のように白虎の体へと流れ込んでいく。
すると、白虎の大きな身体の輪郭に、ふいに鈴の音が鳴るような光の“輪”が浮かび上がった。
その光は、ゆらゆらと揺れて、私の掌へと戻ってきた。
そして――私の肌に、白虎の姿を模した淡い潤氣紋が浮かび上がる。
それはまるで、彼の魂の写し鏡。美しく、凛として、どこか儚い光だった。
次の瞬間、空気が変わった。
空間全体に柔らかな光が差し込み、まるで夜の庭そのものが呼吸を始めたように、氣の波がふわりと広がる。
音のない共鳴が、空気中にふわりふわりときらめいて、私の氣と白虎の氣が――溶け合っていくのが、はっきりとわかった。
心の奥が、深く揺れた。
私の中に、白虎がいる。白虎の中に、私がいる。
やがて、光が静かに落ち着いたとき。
白虎はそっと目を閉じて、私の胸元に頭を預けてきた。
その動きは、どこまでも静かで、優しくて……まるで、長い旅を終えた子どもが、ようやく帰る場所を見つけたかのようだった。
「……ありがとう。これから、よろしくね」
その言葉に応えるように、白虎のしっぽがふわりと揺れた。
と――背後から、足音が近づく。
振り返ると、月明かりの中に宮様の姿があった。
静かに歩み寄り、私の掌に残る潤氣紋を見つめる。
「……無事に儀式を終え、縁が結ばれたようだな。よくやったな」
その声は、いつもより少しだけ柔らかかった。目元に浮かんだ微かな笑みが、それを物語っていた。
「白虎は、そなたを“ただの主”としてではなく、“心を重ねる者”として選んだ。……誇れ」
その言葉が、すとんと胸の奥に落ちて、静かに沁みていった。
私は、はじめて心の底から笑った。何の迷いもない、まっすぐな笑みだった。
「ありがとうございます」
そう答えた私を見て、宮様はふい、と視線を逸らす。
その仕草があまりに不自然で、思わずくすりと笑ってしまった。
「……礼を言うのは、私の方だ」
その言葉に、ますます笑みがこぼれた私は、思わず口元を押さえる。
宮様は、照れ隠しのように咳払いをひとつして、ふいに表情を引き締めた。
「これで……金龍の痕跡を辿れそうだな。期待している」
「はい!」
夜風に乗って返事が高く響いた。その声は、月の光とともに空へ溶けていった。
まるで、白虎と私の新しい一歩を、そっと祝福してくれているかのように。
◆◆ ◆
翌朝――陽はまだ低く、東の空がようやく白みはじめたばかりだった。
宮様の屋敷の庭には朝露が淡く光り、若葉の先に宿った雫が、朝の光を受けてきらきらと瞬いていた。
その静けさの中を、私は霊獣寮には寄らず、宮様とともに歩き出す。
目指すは、内裏。
冷たい朝の空気が頬を撫でるたびに、胸の奥が、ふっと温かくなるのを感じていた。
歩幅を合わせながら、私はそっと掌を見下ろした。
そこには、淡く光を帯びた潤氣紋――白虎を模した紋様が、かすかに残っていた。
……白虎と、私は繋がった。
まだ夢の中にいるような感覚だった。
でも、これは幻じゃない。
白虎が私を“主”として選び、魂を重ねてくれた。そのぬくもりが、いまも私の中に確かに息づいている。
あの目、あの氣の感触……全部、本物だった。
白虎の氣が、背中から静かに支えてくれている。
まだうまく言葉にはできないけれど、心の深い場所で、私は確かに変わり始めていた。
やがて、内裏の立派な門が近づいてくる。
大きく、重々しく開かれたその門をくぐった瞬間――空気ががらりと変わった。
肌に触れる風が、ぴたりと止まった気がした。
張りつめた氣が、朝の澄んだ空にうっすらと漂っている。
まるで見えない氷の膜が地面を這っているような、ひりついた静寂が辺りを満たしていた。
内裏の回廊は、異様なまでに静かだった。
女房たちの足音、公達の衣擦れ――そのどれもが、必要以上に耳に届く。
それだけ、皆が息をひそめているのだ。何かを口にすることすら、はばかられている。
それはきっと――帝が、今も目をお閉じになったままだから。
誰もが、不安を口にできないまま、ただ沈黙している。
恐れが空気に染みこんでいるようだった。
宮様の背にぴたりとついて、渡殿を抜ける。薄暗い天井に灯された灯火が、微かに揺れていた。
弘徽殿が見えてきた。正面の庭には、季節の花が控えめに咲いている。
けれど、どの花もどこか下を向いているように見えた。
気のせいだろうか――いや、違う。あれは、白鹿の氣だ。
気高く、美しく。それでいて、何かをひたすら耐えるような、静かな力がこの庭に満ちている。その気配が、咲く花々にまで宿っているのだ。
私は小さく息を吸い、目の前の扉を見つめた。
この先にあるのは、帝の病の真実と――金龍の行方。
そして、これから私たちが向き合うべき“何か”だった。
「霊獣寮の宮様がいらっしゃいました」
女官の澄んだ声が、弘徽殿の御簾の奥へと通された。
その響きは、静かな空間にすっと溶け込む。
少しの間を置いて、やわらかな返答が返ってきた。
「ありがとう。……わざわざ来てくださったのね」
弘徽殿女御様の声は落ち着いていたけれど、言葉の奥に小さな震えがあった。
それはきっと、不安の揺らぎだった。
宮様が、御簾の前に進み出て、恭しく頭を垂れる。
「帝のご様子は――いかがでしょうか」
女御はすぐには答えなかった。
わずかな間のあと、静かな声が、空気を震わせるように返ってくる。
「……容体は変わりません。金龍の氣も、日に日に……薄れてゆくのを感じます」
その声を聞いたとき、私の隣にいた白鹿の氣が、ふっと沈んだ気がした。
背筋を伸ばしているのに、どこか寂しげで、影を背負っているようだった。
白鹿……。
霊獣は、主の心を映す存在。女御の想いが、そのまま白鹿へ伝わっているのだろう。
胸がきゅっとなった。霊獣たちは、どんなに苦しくても声に出さない。
ただ、そっと寄り添うだけ――それが彼らの優しさなのだ。
宮様が静かに口を開く。
「霊獣寮として、清涼殿における金龍の痕跡を探らせていただきたく思います。……ご許可を」
その言葉は簡潔で、けれどまっすぐだった。
声には迷いがなかった。責任を背負う者の、凛とした響き。
御簾の奥から、女御の返事が静かに届く。
「……帝と、金龍を……どうか、お願い申し上げます」
「もちろんです」
短く、それでも温度のある言葉。
宮様らしい誠実さが滲んでいて、私は心のなかで深く頷いた。
そのとき、女御がふいに私のほうを向いた氣がした。
そして、やわらかく声をかけてくださる。
「鈴太。あなたも、よろしくね」
その声は、どこまでも優しくて――まるで私を信じてくれているのだと、そう思えた。
私は両手を膝に添え、まっすぐに背を伸ばし、小さく、でもしっかりと頷いた。
「……はい」
御簾の奥に、私を見つめてくれる“まなざし”があった気がした。
言葉にはされなかった願い。けれど、はっきりと伝わってくる“想い”があった。
弘徽殿を後にし、ふたりで静かに歩き出す。
回廊の空気はひんやりとしていて、石畳に落ちる足音が遠くまで響いた。
すると、宮様がぽつりと呟く。
「……清涼殿へ向かう。痕跡は、そこにある」
その声音には、揺るぎない確信があった。
見えない何かを、きっと感じ取っている――そんな響きだった。
私はそっと、自分の掌を握る。そこには、白虎の潤氣紋が、かすかに残っていた。
白虎……。
私たちは、もう繋がっている。この絆が、道を切り拓いてくれると――信じられた。
静かに吹いた風が、背中を優しく押してくれた。
まるで白虎が「行け」と言ってくれているみたいに。
そして私は、少しだけ強くなった足取りで、清涼殿へと向かって歩みを進めた。
◆◆ ◆
弘徽殿をあとにして、私たちは静かに清涼殿へと向かっていた。
回廊を渡る足音が、白砂の敷かれた中庭にかすかに響く。
帝の命を支えてきた金龍の痕跡を、私が――
初めて任された大きな役目。その責任が、肩にじわりと重くのしかかっていた。
でも、心の奥に確かなあたたかさがあった。
背後には、白虎の気配。ひたり、と寄り添うように静かに、けれど確かにそこにいる。
昨日、あの庭で……。
あのとき交わした誓いが、まだ胸の内で柔らかく息づいていた。
白虎の聲なき聲が、今も私の中で響いている。
そんな折――
遠くで、複数の足音が近づいてくるのを感じた。
床板の軋みを耳が拾う。どうやらこちらへ向かってくるらしい。私はぴたりと足を止めた。息が浅くなる。
この感じ……。
姿が見えるよりも先に、嫌な気配が皮膚を這った。
回廊の向こうに現れたのは、数人の女房たち、そして――
その中心に立つ、一際華やかな存在。
「……燁子」
その名を、思わず声にならぬ息で漏らした。
背筋がひやりと冷え、体がひとりでに後ずさる。
白昼の空気が、急に硬くなったようだった。
陽の光は変わらぬはずなのに、まるで温度がひとつ下がったかのように感じた。
そのときだった。
隣にいた宮様が、音もなく一歩、私の前へ出た。
無言のまま、私を隠すようにすっと立ちはだかる。
その所作はあまりにも自然で、あまりにも静かだったのに、私を包む空気は一瞬で変わった。
まるで、強くてやさしい風が、私を包み込んでくれたような――そんな感じだった。
私はそっと一歩身を引き、宮様の背に隠れるようにように立った。
お願い……見つかりませんように……。
心臓が、ばくばくとうるさく鳴っていた。
耳の奥で、鼓動の音がひどく反響している。
「まあ、宮様……こんなところでお会いするなんて」
ぱっと花が咲くように、明るい声が響いた。
あまりにも華やかで、あまりにも軽やかで。その声を聞くだけで、心の奥に冷たいものが落ちるのを感じた。
どうか、このまま……通り過ぎて……。
私はただ、見つからないことを祈りながら、じっと陰に隠れた。
「金龍の件は、もうご存知でしょうか?」
その声が響いた瞬間、私は思わず息を止めた。
まるで空気に指先を這わせるような、甘く滑らかな声音。けれど、心の奥をじわりと冷やすような響きだった。
燁子は一歩、また一歩と、ためらいなく歩みを進めてくる。
裾を引く衣の揺れまでもが、計算されたように優雅だった。周囲の女房たちは距離をとり、立ち止まっていたが、彼女だけはまっすぐ、宮様のもとへ。
けれど――
「……ああ」
宮様は、その言葉を短く返すだけだった。礼もせず、ただ彼女を見据える。
その無表情の奥に、ひどくはっきりとした拒絶があった。
「大変なことになりましたね」
燁子の目元がわずかに曇る。
「わたくしも、登花殿女御様に呼ばれて参っておりましたの。金龍が……いなくなるなんて。とても、心配なのです」
私はそっと息を吐いた。
整った声色、伏せられた長い睫毛、憂いを帯びた横顔。どこを切り取っても絵のような美しさ――けれど、私の中に広がったのは、不思議なざわつきだった。
「浮橋として、金龍を探しに行こうと思っていたのです」
その瞬間、宮様の声が鋭くなった。
「……金龍探索は霊獣寮の任務だ」
声は低く、静か。だが、明確な線を引く響きだった。
「貴女が行く必要はない」
燁子は一瞬、瞬きをし、それから口角をふわりと上げて笑った。
「でも、私も連れて行ってくださいな。少しでも、お力になれればと思いまして」
「断る」
宮様の返事は即答だった。声は平坦なのに、拒絶の意志がはっきりと伝わる。
空気が、ぴんと張り詰めた。
燁子の笑顔が、かすかにひきつった。
「ただ、あなたさまが心配なのです。そばにいれば、わたくしが守れますのに。……あなたも、心配でしょう?」
やわらかな声音だった。甘く染まった声の先に、笑顔――
ちらりと目を向けて飛び込んできたその笑みは、どこかこちらを試すようだった。
胸の奥にひやりと冷たいものが差し込む。私は思わず息を飲んだ。
燁子のしてほしいことがわかる。ずっと燁子の世話を焼いてきたから。
まるで「欲しいものは、すべて手に入って当然」と言っているかのような――。
それは私にとってあの屋敷で生きるために必要だった振る舞いだったと今ならわかる。
でも、今の私は宮様にお世話になっている身。従うのはどちらなのかなんて決まっている。
私はうつむいたまま、ほんのわずかに首を横に振った。
「……お強い方ですので」
それだけを、はっきりと口にした。声は小さくても、迷いはなかった。
燁子が一瞬息を飲んだ音が聞こえた。
ちらりと視線を上げれば、ゆっくりと信じられないものを見るように目を見開き――
「まあ……」
小さく漏らして、こてりと首を傾けた。その仕草は、花が揺れるように優美だった。
けれど、ぞわり、と背筋が震える。
不意に、横にいた宮様が、ふっと私の顔を覗き込んだ。
目が合うと、ほんのわずか――ほんとうにわずかにだけ、唇がゆるんだ。
「……行くぞ」
その一言で、私は我に返った。
「はい」
短く返事をして、宮様のあとを追う。どうやら返事は正解だったみたい。
燁子のことなど見ていない。視線を背に浴びながらも、私たちは歩き出した。
静かすぎる廊の空気を切り裂くように。言葉もなく、ただ前を向いて。
背中に残った視線が、じりじりと焼けつくように痛かった。
けれど、もう振り返らなかった。
◆◆ ◆
燁子とのやりとりを終えたあと、あたりの空気が妙に濃く感じられた。
喉の奥に澱のように残る緊張――言葉にできない重さが、静かに尾を引いている。
私は宮様のすぐ後ろを歩いていた。自然と視線が足元へ落ちていた。
ふいに、足元をかすかな風がかすめた。
誰もいないはずの脇を、“何か”がすっと通り抜けていく気配。
私は思わず立ち止まり、そっと後ろを振り返った。
……白虎?
名を呼ぶより先に、胸の奥がじんわりとあたたかくなった。
姿は見えない。でも、確かに感じる。
白虎の氣が、すぐそばにある。言葉もなく、ただ静かに――私の歩みに寄り添うように。
「心配ない」と、そっと背を押してくれるような……そんな氣配。
ありがとう。私は心の中でそっとつぶやいて、再び歩き出した。
やがて、正面に清涼殿の屋根が見えてくる。
近づくにつれ、空気が変わった。音が、消えている。
鳥のさえずりも、風のざわめきも、どこか遠くへ置き去りにされたように。
まるで、世界全体が息を潜めているみたいだった。
「この静けさは……金龍の氣が完全に沈んでいる証拠だな」
宮様の低く沈んだ声が、静寂のなかに落ちる。
その響きすら、殿舎に吸い込まれていくようだった。
殿上の間に足を踏み入れると、そこには一人の男がいた。
文を手にしたまま、じっと佇んでいるのは――頭中将さま。
精悍な顔立ちのその表情には深い疲労がにじんでいて、目の下の陰は、ここ数日の混乱を雄弁に物語っていた。
宮様が静かに一礼する。
「清涼殿にて、金龍の氣を調べさせていただきたく参上しました」
頭中将さまは小さく頷き、低く息を吐いた。
「……ああ。お労しいが、好きにしてくれ。私も正直、気が気でない」
「……やはり、帝がお倒れになられてから、執務に支障が?」
「それもあるが……敏行が、顔を出さないのだ」
その名が出たとたん、宮様の表情がわずかに動いた。
「氏蔵人殿が?」
「ああ。あの男、律儀だったからな。帝が倒れられた日を境に、姿を見せていない。どうにも胸騒ぎがしてな……」
氏蔵人と言えば源敏行さま。弘徽殿の女房の三条さまの恋人……。
名を聞いただけで、胸のどこかがざわりとした。でも、何がそうさせたのかはまだ、言葉にできなかった。
「……ご報告の件、承知しました。清涼殿内の調査を続けます」
宮様が深く一礼すると、頭中将さまも、静かにうなずいた。そのやりとりの隙間に、私はまた一歩、殿の奥へと歩みを進めた。手のひらに感じる白虎の紋が、静かに脈打つ。
見つけよう、きっと……。
私は目を伏せ、強く、そう願った。
私たちは、静かに足音を忍ばせながら、帝の御寝所のすぐ傍まで進んだ。
言葉にするまでもなく、ここが“特別な場所”であることは、足を踏み入れた瞬間にわかった。
空気が違っていた。澄んでいるはずなのに、どこか張り詰めていて、喉の奥がきゅっと詰まるような氣配。それでも、私は足を止めなかった。宮様の背が、確かな導きとなってそこにあったから。
周囲に誰もいないのを確かめた宮様が、ふいに立ち止まった。
そして、静かに手を上げ、指先で印を結ぶ。その動作に合わせるように、場の空気がぴんと張り詰めていく。
まるで、薄い水面の上に目に見えない波紋が広がっていくようだった。
光も音も、わずかに歪み、空間全体が結界の膜で包まれていく。
「白虎と共鳴して、この空間に残る“氣の残響”を辿れ」
宮様の声は低く、落ち着いていて、でも、芯の奥に確かな力を宿していた。
私は、小さく頷く。
そして、心の中で白虎の名をそっと呼ぶ。
――白虎、お願い。来て。
次の瞬間、空気の密度がふわりと変わった。
それは風でもなく、音でもなく、ただ「氣」が動いた感覚。
やがて、静寂のなかに、白銀の光がゆらりと浮かび上がった。
庭での誓いのときと同じように、白虎が現れた。
半透明の身体。輪郭がゆらめいていて、まるで夢と現実の狭間に立つ幻のようだった。
けれど、その氣は確かだった。深く、力強く、私の心の奥に触れてくる。
白虎は音もなく近づき、そっと鼻先で、私の手に触れた。
……ありがとう。来てくれて。
そのぬくもりが、まるで心に灯る小さな焔のように、私の不安を溶かしていく。
私は深く息を吸って、ゆっくりと目を閉じた。
掌を白虎の額にそっと添える。
――私は、あなたとつながりたい。
金龍の聲を、一緒に探したいの。心の奥で、そう祈った。
すると、白虎の氣が、私の内側へと奔流のように流れ込んできた。
ぐらり、と世界が揺れた。
外の音が遠のき、色彩が溶け、視界は淡い白金色の霧に包まれていく。
宮様の存在も、気配も、もうずっと遠くへ離れていった。
私は今、ただ白虎とふたり。意識がするすると沈み込み、“氣の層”へと導かれていく。
私自身が、空気そのものになっていくような感覚。
風の流れが肌をなぞるのではなく、私の中を通り抜けていく。
音が耳に届くのではなく、光の粒となって心に語りかけてくる。
五感が、静かに、けれど確かに――
世界そのものと、ひとつに溶け合っていった。
やがて意識がはっきりしてくると視界が開けてくる。
ここは――清涼殿、か。
張りつめた静寂の中に、空間全体を包み込むような、重たくも穏やかな氣が満ちていた。
淡い金色のひかりが、宙に揺らめく。空気の層が折り重なるように、その氣は静かに漂い、私の頬にかすかな温もりを残していく。
……金龍の氣……思わず、息を呑んだ。
それは威厳に満ちていながら、どこかあたたかく、優しさを秘めた氣。
まるでこの清涼殿という空間そのものが、金龍に護られていたかのように、柔らかく満ちていた。
確かに……ここに、いたんだ。
けれど――その流れは、ある一点でふいに“ぷつり”と断ち切られていた。
風が止まり、空気が一瞬、真空のように沈黙する。
私の胸の奥で、白虎の氣がかすかに震えた。
それは、私の感じた確信と、ぴたりと重なっていた。
「……金龍はここで……強制的に、“氣を断たれた”んだ」
その言葉を口にした瞬間、胸の奥が痛む。
断ち切られた氣の断層から、何かが流れ出しているのがわかった。
それは――氣の名残。
微かな残響が、水脈のように足元を伝い、“下”へと降りていく。
この流れ……掌を床に近づけた瞬間、目の奥に浮かび上がるような感覚があった。
氣の糸が、ゆるやかに編まれていく。その先は、ひとつの場所を示していた。
神泉苑……。
「……あそこに、金龍はいる」
私の言葉に応えるように、氣の帯が細く鋭く光る。
けれど、その流れには、もうひとつ異質な氣が絡んでいた。
墨を水に落としたように、濁り、混ざり、にじんでいく氣。
それは自然のものではなかった。人の手によって放たれた、強い意図を持つ氣――
そのときだった。ふいに、香の記憶が鼻腔をかすめた。
甘く、けれど刺すような刺激。どこか湿っていて、肌の奥にまとわりつくような重たい香り。
「……この香り……」
私の指先に、氣の痕跡がまとわりついているのを感じた。
それは、擾乱香――霊獣の氣を乱すために仕掛けられた、邪の香。
白虎が、低く唸った。それは怒りとも警戒ともつかない、けれど確かな“拒絶”の音。
そしてその瞬間、視界の奥に像が浮かび上がった。
香を纏った衣。薄暗い室内に、ひとり立つ影。それは――
……氏蔵人さま……?
その姿は、この清涼殿で見かけたときと同じだった。白虎の中にある強い警戒が、私の胸に流れ込んでくる。
氣の探知はまだ続いている。でも、心が――追いつかない。
揺らぐ景色のなかで、私は小さく息を吸い込んだ。
そのときだった。
白虎の氣が、私をさらに深く引き込んできた。
まるで静かな水底へ吸い込まれていくように、私の内側がゆっくりと深層へと潜っていく。視界は、淡い金色に染まり始めた。
光でもなく、霧でもない――それは、氣の記憶。まるで誰かの心の奥を、夢のように覗き見るような感覚。
……これは……金龍の、記憶……?
遠くに、まばゆい空が広がる。その空を悠然と舞う、威風堂々たる龍――金龍。
その姿は、ただそこに在るだけで空間を支配していた。
厳かで、慈愛に満ちていて、それでいてどこか哀しみを秘めている。
その氣が、胸の奥にずしりと響く。王の氣。揺るぎなき、守護の氣。
そして、その背に――もうひとつ、幼い龍の姿。
金龍の尾に絡むように、ちいさな身を寄せ、守られるようにして飛んでいた。
まるで、眷属。慈しみ育てられる、小さな命。
……あれも……金龍の一部……?
世界が、ふっと揺れた。光の流れが変わる。場面が変わる。
花が静かに舞い、薫き立つ香が空気を包む、神聖な場――これは何かの儀式?
そこに立っているのは、見覚えのある横顔。今よりも幼い燁子に見える。
白い神聖な装束を纏い、長い黒髪が艶やかに流れる。両手を胸前に掲げ、霊獣と氣を繋いでいる様子はまるで神霊の使いのよう。
その場からは少し離れて座しているのは、同じく若き日の――宮様。
まだ幼さを残した顔立ち。それでも、その瞳の奥にあるのは今と変わらぬ、凛としたまなざしで儀式を見つめている。
ふっと二人の視線が絡んだ。
燁子は頬をほんのり染めて、まっすぐに宮様を見つめている。
その瞳にあったのは――憧れ、恋慕、そして……決意。
なに……これ……。
胸がきゅっと縮まった。
もしかして、これは――“浮橋”の儀?
氣の共鳴が、ふいに乱れた。白虎が、低く唸る。私の動揺を敏感に察したのだ。
視界の端が揺らぎ始める。
波紋のように、夢の記憶がにじみ、形を崩していく。
……まだ……見ていたいのに……。
金龍の記憶。その深層には、きっともっと重要なものが――
けれど。白虎が、強く氣を震わせた。その共鳴の一撃が、私を現実へと引き戻す。
ぐらりと重心が浮いた感覚のあと、空間が微かにきしむ音が響いた。
濃く満ちていた金の霧が、ふわりと風に溶けるようにして散っていく。
光も音も、色も輪郭も、現実の世界が戻ってくる。
私は、膝から崩れるようにして座り込んだ。全身から力が抜け、肩が勝手に上下する。
いつの間にか、浅くなっていた息にようやく気づいた。
……まだ……心が追いつかない。
金龍の氣の残滓。擾乱香の残り香。
そして、あの少女の――燁子の瞳に宿っていた、あの感情。
あれは、憧れなどという甘やかなものではなかった。
もっと深く、もっと強く、もっと……執着に近いもの。
あの頃から……ずっと……?
胸の奥に、ざわりと重たい渦が巻いた。
白虎の氣が、そっとそれを鎮めるように寄り添ってくれるのを感じながら、私はゆっくりと顔を上げた。
夢の余韻はまだ、指先の感覚に残っていた。
「大丈夫か」
耳元に落ちてきたのは、低く、けれどどこまでもやわらかな声だった。
ふと顔を上げると、宮様がすぐそばにいた。
いつの間にか、私の背中に――あたたかな掌がそっと添えられている。
……優しい。その掌の温度に、心がほろりとほどけそうになる。
けれど、その優しさに触れてしまったせいで、逆に胸が締めつけられた。
目の奥が熱くなりかけて、私は慌ててまぶたを伏せた。
まだ言葉が、うまく繋がらない。気持ちが、整理できていない。
小さく息を吐いて、ようやく私は声をしぼり出した。
「……はい」
たったそれだけが、今の私の限界だった。
視線を膝に落とし、手を握る。震えていないか、確かめるように。
「見えたのか」
静かな問いが、すぐに落ちてくる。
「はい」
「何が見えた? 話してくれ」
急かすでもなく、ただまっすぐな声だった。
けれど、その声の奥には確かな真剣さがあった。
私は言葉を選びながら、ゆっくりと口を開いた。
「……金龍の氣は、神泉苑の方角に流れていました」
「神泉苑か……」
低くつぶやく宮様の声が、空気のなかに沈んでいく。
私の隣には、白虎が静かに座っていた。
言葉はなくとも、その大きな身が、私にそっと寄り添ってくれている。
分かってくれてる……。
そのぬくもりが、胸の奥にじんわりと広がった。
私は、もうひとつの大きな氣配を、思い出す。言葉にするのは怖かったけれど、それでも、告げねばならない。
「それと……擾乱香を纏っていたのは、氏蔵人の……源敏行さまでした」
その名を口にした瞬間、宮様の表情がかすかに動いた。
息を短く吸い込んだあと、目を伏せ、低くつぶやく。
「……氏蔵人殿、そうか」
短い沈黙が流れる。
その間に、宮様は何かを振り返るように、遠い目をしていた。
やがて、その静けさを破るように、落ち着いた声が返ってきた。
「……実家に戻った三条に、鳳凰を通して様子を見させていたんだが……昨日、敏行殿が一度だけ顔を出したという」
「三条さまのところに……?」
驚きと不安が混ざった声が、自然と口をついて出る。
「何か、つながりがあるのかもしれない。そう思って、今、別筋で調べさせている」
その声には、迷いのない意思がこもっていた。けれど、そのすぐあと、少しだけ声音が沈む。
「……だが。たとえ繋がりがあったとしても、霊獣を持たぬ者が、なぜ“潤氣擾乱香”を使えたのか。そして、それを帝のおわす清涼殿で使った理由が、どうしても分からぬ」
低く抑えた声の奥に、苛立ちとも焦りともつかぬ感情がにじんでいた。
「ともかく、まずは金龍を見つけ出さねばならぬ」
宮様の瞳が、まっすぐに私を射抜いた。
「……向かうぞ、神泉苑へ」
その一言に、私は深く、強くうなずく。
「はい」
風がひと筋、私たちのあいだをすり抜けていった。
白虎が立ち上がる。その足元に残された氣の名残が、かすかに揺れた。