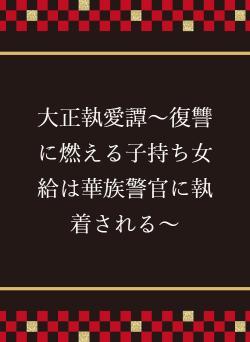まぶたの裏にかすかな光が滲んでいた。その淡い光で意識が少しずつ浮かび上がる。自分の血がゆっくりと脈打つ音が、静かに身体を満たしていた。
あ、生きている。ふと、それが浮かんだ。
まぶたをゆっくりと持ち上げると、御簾越しに射し込む陽の光が、やわらかな筋となって床を撫でていたのが見えた。ほのかに檜の香りが漂う。ここはどこなのだろう。
それにしても、どこかほっとするような温もりを肌で感じる。その心地よさの奥に、どこか引っかかるような違和感があった。
そっと指先を動かす。腕に力を入れて上体をわずかに起こすと、
「……え?」
目を見開いて、体が固まった。
視界に映るのは白銀の毛並み。しんと静まり返った空間の中、気高い霊獣が目を閉じ、穏やかな呼吸を繰り返している。私のすぐそばに、なぜか白虎がいた。
そして、その白虎ももたれかかるように、いくつもの種類の小さな霊獣たちが丸まって眠っていた。
不思議なぬくもりに満ちた空間。胸の奥からじんわりと熱を帯びる。すうと息を吸った瞬間に優しい潤氣が肺にいっぱいに満ちた。
ずっとここで眠っていたいんだけど。でも、一体どこからこの霊獣たちはやってきたのだろう。それに、
「ここ……どこ……?」
つい漏れた声は、自分でも驚くほど小さく掠れていた。誰にというわけでもなく、問いかけるように呟いた。
「目覚めたか」
低く、静かな声が耳の奥を震わせる。びくんと反射的に肩が跳ねた。音のした方へ振り向けば、御簾がすっと上がり、光の縁取りの中から姿を現したのは、
「霊獣に囲まれて眠るとは、珍しい」
陽の光を背に立つその人は、いつもと変わらぬ端正な顔立ちで、凛とした気配を纏っていた。けれど、その瞳の奥にほんの少し、柔らかな色が揺れている気がした。かすかに口の端も上がっているような。
「霊獣にやけに好かれているな。宵家の大姫の」
「……っ!」
き、今上帝の二の宮・彰仁親王さま!
血の気が一気に頭に昇った。ぽうっと顔が熱を持ち、心臓が跳ね上がる。それなのに寝ぼけた頭に冷水をかけられたように、意識がはっきりした。
「きゃあああっ! な、なな、なんで、ここにっ!?」
声が裏返り、言葉がつっかえる。私は咄嗟に着物を引き寄せて、上体を隠した。起き抜けの私を、よりにもよって、やんごとなき宮様に見られてしまったなんて!
羞恥心で頭が真っ白になる。どうしても目が合わせられない。
「……支度をしてやってくれ」
宮様は私の取り乱しにも動じることなく、静かに背を向けて部屋を出ていく。
「え、あの、ちょ、ちょっと……!」
「かしこまりました、若宮様」
その声に導かれるように、気づけば傍らには年配の女房が立っていた。やわらかな笑みを浮かべて、すっと頭を下げる。
「はじめまして、姫様。私は、たきと申します」
「た、たき様。初めまして」
慌てて同じように頭を下げると、ふふと笑い声がこぼれた。
「あらあら、かわいらしい方。頭をお上げになってください。私に様はいりませんよ。若宮様より、姫様にお仕えするよう仰せつかっております。どうぞよろしくお願いいたしますね」
「は、はい」
温かく響くたきさんの声に顔を上げる。なぜか張り詰めていた胸の糸がふっと緩むのを感じた。
「さ、お支度をいたしましょう」
「し、支度……?」
そう言って、たきさんは私にふわりと広がった衣を見せた。白地に繊細な刺繍が施された童直衣。
えっと、なんで?
「え、あの……これって……」
「ふふ、驚かれるのも無理はありません。殿上童としてのお召しものですが、お似合いになると思います」
「殿上童!?」
にこやかに話すのに、どこか押しの強いたきさんに、言われるがまま着せられる。
たきさんは手際よく私の腕を通し、帯を結び、裾を整えていく。するすると動く指先は、水の流れのように自然で、着せられているはずの私の身体が、まるで自分からその衣に馴染んでいくような、不思議な感覚さえした。
「はい、よくお似合いです」
そう言ってたきさんは今度は櫛を手に取る。私の背後に回るとそっと髪を梳き始めた。その動作もまた驚くほど丁寧で、優しかった。くしけずられるたびに、ふわりと髪がほぐれていく。心も同じように、からまったものがほどけていくようだった。
「あの……そもそも、ここは……?」
恐る恐る尋ねると、たきさまは髪をすく手を止めずに、穏やかに答えてくれた。
「ここは若宮様のお屋敷でございますよ」
「えっ」
思わず声が裏返った。宮様の……お屋敷? えっと、本当になんで?
戸惑いと混乱で頭がぐるぐるしているうちに、たきさまは最後に髪のまとめを整えて、にっこりと笑った。
「さあ、若宮様がお待ちですよ。ご挨拶に参りましょう」
「ま、待ってください、まだ心の準備が……!」
だって起きたばかりの姿を見られただけで、もう顔から火が出そうなのに! 思わず立ち上がりかけたところを、優しく背中に手を添えられる。
「大丈夫ですよ。きれいに整いましたからね」
たきさん目を細めて、やさしく私の背を押した。手のひらのあたたかさが、私の緊張をほんの少し和らげる。歩き出した足元がたしかな感触を伝えてくるのに、気持ちはまだどこか夢の中のままだった。
朝の光が整えられた屋敷の庭に射し込み、ちちちち、とどこからか鳥の鳴き声が聞こえてくる。私はたきさんに伴われて宮様のお屋敷の寝殿へと足を踏み入れた。御簾の向こうには宮様がいる。胸がそわそわとして落ち着かなかった。
「失礼いたします」
たきさんの声を合図に、私は深く頭を下げた。
「似合っているではないか」
ふいに、その声が御簾の奥から届いた。
宮様の声に心臓が跳ねた。冷たさを纏った澄んだ響き。けれど、わずかに笑みを含んでいるような気がした。
私は思わず着ている童直衣のをぎゅっと握りしめた。袖の中の指先がじんわりと熱を持つ。まさかこんな姿を男性に、しかも今上帝の二の宮様に見られるなんて思ってもみない。
「座りなさい。不思議そうな顔をしているな。宵家の大姫」
「あ、あの……」
「なんだ。申してみよ」
言葉を出すのが怖かった。でも、聞かずにはいられなかった。
「どうして、私を連れてきたのですか? それにこの格好は……どうして童のような……」
御簾の向こうは短い沈黙のあとに、静かに返された。その声は夜明け前の風のように凜としていた。
「……宮中で霊獣を鎮めた後のことだ」
「後、ですか」
宮様の声が低く穏やかに重なる。
「闇夜の奥から何かが飛び出してきた。霊獣の類と見られるものだ。それがそなたににぶつかり、おまえはそのまま意識を失ったのだ」
私は小さく息を呑んだ。
そうだわ、私……脳裏に記憶が明滅する。しなる黒い尾、禍々しく輝く紅い瞳。まるで夜そのものが形をとったような、美しくも恐ろしい存在。
「白虎がそなたを背に乗せ、私のもとへと駆けてきた。霊獣・白虎が危機を感じ取り、そなたを守ろうとした。私はそのまま白虎と共に、そなたをここへ連れて帰った」
言葉は淡々としていたけれど、そこには嘘のない確かさがあった。だからこそ、肩が竦み顔が青ざめる。額が床板にくっつきそうなほど頭を下げた。
「そうでしたか。ありがとうございます。宮様のお手を煩わせて申し訳ございませんでした」
「よい。気にするな。妖獣となって暴れた霊獣たちは、そなたのおかげで霊獣に戻った。こちらこそ、礼を言う」
「滅相もございません!」
はしたないとは思ったけれど、ぶんぶんと横に首を振った。
「だが、今回の犯人はいまだ見つかっていない」
「え……」
「内裏のあちらこちらに影響を与えたが、特に氣の乱れが激しかったのは後宮だった」
その言葉が落ちた瞬間、部屋の温度が少し下がったような気がした。
「犯人が意図的に霊獣を妖獣へと変貌させた可能性は否定できない。そして、大姫。そなたは、結果として“狙われた”ように見える」
凍るような静けさの中に、確かな警告が混じっていた。
「理由はわからない。ただわからないからこそ、また同じことが起こるかもしれない」
また同じことが、本当に? 私は無意識に胸元に手を当てていた。白虎の氣がそこに宿っているような気がして。背を支えられ包まれ導かれた感覚が、まだ体の奥に残っているような気がする。
「この度の宮中で起きた件は、霊獣騒乱事件として霊獣寮の管轄となった。しかし上では、いまだに騒ぎが収まらぬらしい。だが、霊獣を鎮めたのが誰か、それは伏せている」
言葉の一つひとつが、冷たくも厳しく感じられる。
「藤原宵家ではもう話が出回っているそうだぞ。『西の対の姫が霊獣に襲われ、行方知れずになった』と」
私は小さく肩を震わせた。まるで自分のことではないみたいだった。けれど、その“姫”とは、まぎれもなく私。
「そう、ですか」
小さな声が漏れた。そのまま宮様は淡々と続けた。
「ちょうどよい。今、都から宵家の大姫という存在が消えた方が都合がよい。ならば利用するまでだ」
「ゆ、行方不明になるんですか、私が……?」
「そなたを守るためだ。それから、その姿のままでは、そなたが何者かをすぐに嗅ぎつけられる。だから、殿上童として名を変え、霊獣寮に属してもらう」
「へ!?」
目を見開いて固まった。とんでもないことを言われた気がする! 私が殿上童になるの!?
驚きを隠せない私とは対照的に、御簾の向こうでは、淡々と静かに紙をめくるような音がした。
「霊獣師たちと同じように後宮へも出入りできるようにしよう。氣の乱れがあれば、すぐ私に知らせよ。事件は何も解決していないし、あの場には……まだ澱んだ氣が残っている」
私の喉が音を立てた。何かを呑み込むようにして。聞けば聞くほど怖い。けれど、宮様から告げられることに、拒む言葉が出てこなかった。ただ、押し寄せてくる現実の波に、足を取られぬよう耐えるので精一杯だった。
「それから住まいは、ここに」
「え……!?」
今度は声が上ずった。宮様の屋敷に!?
そんな大それたことが許されるのだろうかと、体が一瞬すくんだ。けれど、彼の声には一片の迷いもない。それが命令だということを、私はようやく理解した。
「……謹んで、お受けいたします」
そう言うしか、なかった。いや、そうするしかなかった。
短い沈黙のあと、ふいに問いが返ってくる。
「宵家に、知らせておくべき者はいるか?」
その一言が胸の奥を突いた。思わず目を伏せたまま、呼吸が止まりそうになった。きっと宮様から優しさをいただいたのだろう。燁子の顔が浮かび、そして、すぐに消えた。
「……必要ありません」
唇が自然と動いていた。
「私のことなど、気にかける者はいないはずです」
言って唇を噛んだ。それが嘘ではないことが、逆に寂しかった。
御簾の向こうの気配が、ほんのわずかに揺らいだように思えた。
言葉にはならなかったけれど、空気の向こうから、なにかがそっと伝わってきた。
私はその一瞬を、胸の奥でそっと包んだ。
それが、どれほど小さくても、誰かが私を見てくれていたという証のような気がして。
◆◆ ◆
「ここが、内裏」
見上げた先には立派な門。思わずこぼれた声が、朝の澄んだ空気に溶けていった。
足元の白い敷石が光を弾き、まるで雲の上を歩いているみたいに眩しい。檜皮葺の大屋根は空へと悠然と伸び、風に揺れる柳の梢が青空と重なり合って、境界が消えていくようだった。
妹の燁子が呼ばれる遠くから憧れるだけだった場所。その中へ、いま自分の足で入っていくなんて。胸の奥がふわりと浮く。
先を行く宮様の背を追って歩を速めたとき、低い声がふいに落ちてきた。
「その姿、違和感はないな」
「そうでしょうか」
からかうような響きに、私は思わずうつむいた。十六、七にもなって――女として花の盛りを迎えるはずの自分が、殿上童の姿を褒められるなんて、いいのか悪いのか、女心は複雑だ。
「霊獣寮へ向かう前に、そなたの名を決めねばな。そうだな……そなたの名は鈴太とする。私の遠縁ということにしておこう。忘れぬようにな」
「鈴太、ですね。わかりました。鈴太、鈴太……」
心の中で何度も唱える。新しい名を忘れないように、必死で刻み込む。
「女だと気づかれぬように。殿上童として細心の注意を払って振舞ってくれ」
その言葉に思わず喉がからからになった。私は強ばったまま、こくりと小さく頷く。
すると宮様は、足を止め、ゆるやかにこちらを振り返った。
「そなたが鈴太としてふるまう以上、仮面は私が守る。……安心せよ」
その一言が、胸の奥にすとんと落ちた。守る──命令ではなく、支えのような響き。
「はい」
私は肩の力をふっと抜き、今度はまっすぐに声を返した。
そうして歩を進めると、霊獣寮の建物が見えてきた。
霊獣寮の建物は想像よりも静かだった。宮様が扉を開けて中に進むと、中からふわりと木と香の匂いが流れてきた。
室内では世話しなく霊獣師たちが働いていた。私たちの気配に気づいた瞬間、何人かがこちらを振り返った。足が少し止まりかける。
「宮様。おはようございます。その子は……?」
「遠縁の子だ。名は鈴太。今日からここで修練を積む」
宮様が短くそう言っただけで、空気がわずかに揺れた。その場にいた霊獣師たちの視線が一斉に私に向けられる。その視線には色があった。淡い興味、用心深さ、少しの警戒。そして、ほんのわずかに滲む嘲りのような何か。
じわりと背中が熱を持つ。思わず肩がすくんだ。
「……萎縮せずとも良い。背筋だけ伸ばしておけ」
宮様の声がすぐ耳元に落ちてきた。あたたかくも冷静な声。私は息を整えて、背すじを伸ばす。肩の力を抜いて、ただ、まっすぐに立つ──それだけで、少し呼吸がしやすくなった気がした。
「こちらへ」
そう促されて私は宮様のあとに続いた。
「みなさん、お忙しそうですね」
「そうだな。霊獣寮は都の霊獣、特に宮中の霊獣に関することを一手に引き受けているからな。霊獣師たちは多忙だ」
「あの、浮橋の君のように、霊獣師は霊獣を従えているのですか?」
「霊獣と主の関係は、命令と服従だけではない」
その言葉に、思わず足が半歩遅れる。
「氣の流れを通して互いが響き合う。主の心の在り方が、霊獣の氣を変える。穏やかであれば潤い、乱れれば濁る」
「じゃあ、霊獣の異変は“氣”が濁った結果……」
思わず口に出していた。宮様が振り返り、ほんの少しだけ口の端が上がっていたような気がした。けれど何も言わず、再び前を向いて歩き出す。
知らないことばかりだ。でも、なぜかそれらは、胸のどこかにすとんと落ちていく気がする。私にはまだ何もない。だけど、霊獣たちが見せてくれたあの光や聲──それを思い出すと理解できる気がした。
霊獣師たちの邪魔にならないような広間の一角までやってきた。宮様が足を止めた。
「そなたには宮中の巡回に出てもらおう。まずは場所を覚えること。支度をしてくるから、鈴太はここで待て」
振り返りもせずに言い残すと、軽やかに歩いて去っていく。
その背を目で追いながら、私はそっと息を吐いた。すごいところに来てしまった。霊獣師の仕事なんて初めて見た。
「おい、そこの新人」
不意に背後から声が落ちてきた。
反射的に振り返ると、影がひとつ、二つ、三つと足音と共に前へ出てくる。三人の男が私を取り囲むように並んで立っていた。
真ん中の男が、すっと私の方へ歩を進める。目元の鋭い男だ。ふてぶてしい笑みが唇に浮かんだ。
「殿上童なんざ、霊獣の扱いも知らねえのに何しに来た? 新人のくせに、やけに偉そうな顔しているじゃねぇか」
ぐっと喉の奥が詰まった。言葉が出ない。その男はわざとらしく私の前に立つと、顎をしゃくった。
「俺は在原貞親。先に名乗ってやったんだ、何か言えよ、鈴太坊や」
ニヤリと笑われたと同時に、私の背中からうっすらと氣のざわめきが立ち上がる。
だめ、出てこないで。白虎。
ぐるるると反応する白虎に心の中で呼びかける。姿を消しているのだが、白虎がついていくと聞かなかったのだ。
白虎……お願い。ここは、私が。
すると伝わったのか、白虎の氣が、すっと引いていく。私を信じてくれた、その感触だけが残った。
「なんだよその目。睨んでいるのか?」
貞親の左右にいた取り巻きが、わざとらしく顔を見合わせてから、含み笑いを漏らした。
「本当に宮様の遠縁か? 聞いたことないけど。若宮さまの気まぐれってやつ?」
「気まぐれだなんて、何を言っているんですか、そんなはず」
「殿上童をいじめるなんて、どうかしているぞ!」
元気のよい空気が弾けるような声が場に割って入った。割り込んできたのは、明るい色の直衣を着た青年だった。真っ直ぐな笑顔で、貞親たちの間にぐいと割り入ると、両手を腰に当てた。
「はじめまして! 俺は清原宗直。鈴太だっけ? これからよろしくな」
一瞬、何が起きたかわからず、私はぽかんと口を開けていた。
「……なに勝手に話、終わらせてんだよ」
貞親が舌打ちを落とした。
「悪い悪い。でもまあ、そのくらいにしとこうぜ、貞親殿。宮様にバレると大変だぞ」
宗直様は笑ったまま、貞親の肩をぽんと叩いた。
貞親は舌を鳴らして踵を返し、取り巻きを連れて去っていった。
「さっきのが在原貞親。霊獣寮の中じゃ、ちょっと気の立つやつでね。俺のことも嫌いみたいだ」
宗直様が声をひそめて言う。その目が私を見て、片方だけ、くいっとウインクした。空気が、ふっと緩んだ。
「困ったら俺がついてるから。何でも言ってくれていいぞ」
「ありがとうございます。宗直様。助かりました」
「どうした」
低く静かな声が響いた。背筋が自然と伸びる。振り向かずとも分かる。宮様だ。私は慌てて姿勢を正した。
「たいしたことではありません、宮様。鈴太を歓迎していたら、ちょっと賑やかになりまして」
しばしの沈黙ののち、宮様の視線がすっと私をかすめた。
目は合わなかったけれど、そこに怒りはなかった。
「鈴太、内裏の巡回に行くぞ」
「は、はい!」
声が少し上ずった。慌てて口を閉じる。
「ちょうどよかった。宗直、君も同行するように」
「承知しました。宮様」
宗直様が肩を回して笑いながらついてくる。私たちは三人で歩き出した。
◆◆ ◆
清涼殿の敷石は、まるで鏡のように白く冷たく光っていた。
高く張られた格子の向こうから陽が静かに差し込んで殿の奥まで届いている。この空間の隅々にまで、言葉にできない緊張が満ちていた。
帝が政を執る内裏の中でも最も重要な場所。そんなところに、体がかちこちに固まっている私は、足音を立てぬように歩いていた。
「……あの、巡回って……内裏の中をまわるだけじゃないんですか?」
思いきって出した声は思ったよりも小さく、まるで水面に落ちた石のように、ぽちゃんと空気に吸い込まれていった。隣を歩く宗直様が、少し口元を引きつらせて囁いた。
「まあまあ、鈴太くん。黙ってついて行こう。な?」
いつもの調子に似ているけれど、どこか浮ついた響きが混じっていた。宗直様ですら落ち着かないのなら、やっぱりここは特別な場所なのだ。
清涼殿の殿上の間へと足を踏み入れると、すぐに気配がこちらをとらえた。
部屋に控えていた数人のうち、一人がゆっくりと立ち上がる。
「やあ。病弱と噂される霊獣頭が、清涼殿に現れるとは。珍しいこともあるもんだな」
すっと伸びた背筋に鋭い眼光を持つ公達。でも軽やかに笑う声に、どこかからかいのようなものが混じっている。誰だろうと思っていると、小声で宗直様が教えてくれた。
「蔵人所の頭中将の藤原公孝様だ。……めんどくさい人だよ」
その表現が妙に納得できた。言葉も態度も軽やかなのに、どこか全てを見透かされているような圧がある。
「敏行、すまない。この書状を手配しておいてくれ」
頭中将さまは横に控えていた細身の若い男へ、手にしていた文を渡した。
「上司に扱き使われるとは、氏蔵人殿も大変だな」
宮様がふっと笑う。それに敏行という名の青年は、少しだけ眉尻を下げて応じた。
「とんでもございません。これも務めですから」
「真面目だな」
宮様が微かに笑みを浮かべた。その柔らかな表情が、場の張り詰めた空気をわずかに解いた気がした。
「敏行のことはいいんだよ。貴方は何か用があってきたのだろう?」
本題を促すように、頭中将が表情を戻す。宮様は落ち着いた口調のまま一歩踏み出し、静かに頭を下げた。
「先の霊獣の件、霊獣寮にて引き受けることとなりました。その旨、報せに参りました」
「そうか」
「では、私も報せを聞こうか」
その瞬間、殿内に風が駆け抜けた気がした。
視線を向けると、御簾の奥からゆっくりと影が現れる。上等な柔らかな衣の裾がそよ風のように揺れた。一歩踏み出したその姿を目にして息が止まった。
一瞬にして、この場にいる者たちがすっと頭を下げた。
声の主が誰なのか、問うまでもなかった。
この方が今上帝。内裏の主で、この国を安寧に導くお方。
額が畳に触れそうになるくらい身を折る。思考が真っ白になった。鼓動の音だけが妙に大きく響く。
隣の宗直様をちらりと見ると彼もまた硬直しながら頭を下げていた。普段は軽やかな笑みを浮かべている彼が、まるで凍りついた石像のようだった。
ああ……本当に、滅多にお会いできないる方なのね。
その事実がようやく胸に染みてくる。
ただ何事にも動じなく、落ち着き払っていてたのは宮様だった。
ああ、そうだ。この方は宮様のお父上だった。
「主上、紹介します。霊獣師の清原宗直。そしてこの童は、殿上童として任じられた鈴太でございます」
名を呼ばれて私はぴくりと背を正した。緊張で喉が詰まりそうだったが、懸命に頭を下げる。鼓動が早すぎて、体の中の音がうるさく響いた。
「そなたの部下か。仕事に励むように」
帝の声がゆっくりと降りてきた。まるで水面を撫でる風のような静けさと、決して揺るがぬ重みをまとった言葉。たったひとことだったのに。胸の奥がきゅっと締めつけられた。
ありがたくて、誇らしくて、でもどこか夢の中にいるようで。
忘れない……絶対に。
帝から直接、言葉をかけていただいた。それだけで、身体の奥に炎のようなものが灯るのを感じた。宗直様も感極まったように唇を引き結び、まっすぐ頭を下げている。
「宮、報せを直接聞こうか。頭中将もこちらへ」
帝がそう告げると、宮様と頭中将様がすっと進み出た。
振り返らずに宮様が言った。
「宗直、鈴太。先に内裏の巡回に出ておけ」
「は、はい!」
「了解であります!」
思わず声が裏返りそうになりながらも、私は勢いよく頭を下げた。
宗直様も元気よくそれに続く。
広間を離れ、静けさから解き放たれたとき、私はようやく小さく息を吐いた。
巡回の初日で、まさか帝にまでお目にかかるなんて。
夢のような時間の余韻に揺れながら、私はそっと胸に手を当てた。
そこには、白虎の氣が静かに寄り添っていた。
まるで「よく頑張ったね」と言ってくれているようで、じんわりとあたたかい。
私は歩き出す。鈴太として、霊獣寮の殿上童として。
けれどその心の奥には、誰にも明かせぬ鈴音の私が、静かに息づいていた。
◆◆ ◆
内裏の回廊は朝の光に包まれて、どこまでも静かで澄んでいた。
白木の板が丁寧に敷き詰められ、踏み出すたびに足音がほのかに響く。その床には、差し込む陽が薄く反射していて、歩く自分の影が淡く揺れて映っていた。
まるで夢の中を歩いているようで、私は何度も瞬きをして確かめた。
「鈴太、きょろきょろしすぎ」
隣から声がして顔を向ける。宗直様が、肩をすくめて笑っていた。
「顔に“初めてです”って書いてあるよ」
「……そ、その通りなので……」
恥ずかしさを隠せなくて、つい小声で返す。
だって、ほんとうに初めてなのだ。こんなにも奥深い、宮中の廊下を歩くなんて。
すれ違う二人の女房たちが、にこやかに頭を下げながら口々に言う。
「あらあら。見かけない顔だけれども、かわいらしい」
「まぁ、かわいらしくて初々しいじゃないの」
頬がかっと熱を帯びる。笑顔で交わされる好意的な言葉に、うまく笑い返せず、つい視線を伏せた。宗直様がふっと笑った。
「なんだ、恥ずかしいのか? 誉められたら、素直にありがとうって思っておけばいいさ」
その声音には、からかいではなく、どこか励ますようなやさしさが滲んでいた。
私は小さくうなずいた。胸の奥が少しだけ軽くなる。
「すみません。少しお話をいいですか?」
宗直様がすれ違いざまに、女房たちに声をかけた。
「どうされたの?」
「先日、霊獣が暴れた事件がありましたが、皆さんや霊獣はご無事でいらっしゃいますか?」
宗直様の言葉に、二人の女房が顔を見合わせた。女官は周囲を気にするように一歩近づくと、低く抑えた声で告げた。
「実は……女御様方の霊獣が、ここのところずっとおびえておりまして」
「……おびえて?」
私が聞き返すと、女官は小さく頷いた。
「そうなの。霊獣が暴れた夜──あのとき、香の匂いがしたの。ふわっと漂うような、でもどこか甘くて。あまり嗅いだことのないものだったわ」
「香、ですか」
その言葉に心が引っかかった。
香か。目に見えない薫りは、氣や術に混じって使うにはうってつけの手段かもしれない。女房は慎重に言葉を選びながらも、確信を持っているようだった。
「はい。あの香を境に、霊獣の様子が一変したのです。落ち着きがなくなって、まるで何かを怖がっているように……。気のせいではないと思います」
私は女房の言葉を深く胸に刻んだ。もしかすると、事件の手がかりになるかもしれない。
白虎の氣が、背中で静かに揺れた。もしかして霊獣の本能が何かを覚えている? もしそうならそれを無駄にはしたくない。
「ありがとうございます。霊獣頭にお伝えします」
自然と声に力がこもっていた。女房たちはほっとしたようにうなずいて、静かにその場を離れていった。
さらに歩を進めた、そのときだった。廊下の奥、宗直様に教えてもらった登花殿から、ふわりと現れた姿に私は足を止めた。
朝の光を背に受け、まるで淡い光を身にまとっているかのような存在感。その人物は、登花殿の前に立っていた。
……燁子だわ。宮中で初めて見た。いつも宵家の屋敷だったから。
つややかな黒髪が、肩先でやさしく揺れている。纏っているのはやわらかな朱色の美しい唐衣。光沢を含んだ絹が、動くたびに空気を撫でるようにひるがえり、彼女の輪郭をより儚く、美しく見せていた。
燁子は登花殿から出てきた女房たちに囲まれて、にこにこと笑顔を向けられている。
「浮橋の君が来てくださったおかげで、女御様も霊獣もすっかりお元気に……」
「ありがとうございます、浮橋の君」
声をかけられるたびに、燁子はふんわりと微笑んだ。やさしく余裕に満ちた笑顔で。その姿はまるで、屏風絵の中から抜け出した姫君のようで。私はまばたきも忘れて見つめていた。隣にいた宗直様も、ぽかんと口を開けたまま見とれていた。
「……本当に、立派な方だな。まさに“浮橋の君”にふさわしい」
その呟きが胸の奥で小さく刺さった。わけもなく肩の辺りがきゅっと強ばる。
その時、女房の一人が声を上げた。
「宵家の屋敷を、霊獣が襲って大変だったと聞きました」
その言葉に燁子の表情がわずかに曇った。
「屋敷の皆は、なんとか無事だったのですけれど……」
彼女は言葉を切ってから少しだけ俯いた。
「お姉さまが……霊獣に襲われて、行方不明になってしまって……」
その大きな瞳に、涙がにじむ。
「まあ……おいたわしい……」
「なんてこと……」
女房たちが口々に同情の声を重ねる。その中心で、燁子は悲しみをたたえたまま、じっと立っていた。何も飾らず、ただ悲しみを受け止める姿は、見る者の心を自然と打つのだろう。
“お姉さま”──それは、私のこと。ここにいるのに、いないふりをしなければならない。息を吸うのさえ、どこか苦しかった。
「あらあら、登花殿の女房方じゃないの」
声がした方向を見ると、廊下の向こうに女房の一団がいた。
「まあ。弘徽殿の女房たちだわ」
登花殿の女房のひとりが忌々しそうに口にした。
まるで誰もが偶然を装っているのに、互いにその“偶然”を待ち構えていたような──そんな空気。
「……弘徽殿女御様は東宮のご母堂だ。この後宮で最も大きな力を持つ女御様だ」
隣にいる宗直様がそっと教えてくれる。
弘徽殿の女房たちは髪ひと筋の乱れもなく、表情の端々まで研ぎ澄まされていた。
「霊獣が襲ったのは、内裏と宵家だけだったと聞きましたが」
先に口を開いたのは、弘徽殿の女房のひとりだった。やわらかな物腰を装いながら、その声音には冷たく細い刃が仕込まれている。彼女の視線は、まっすぐに燁子を射抜いていた。
「まさか、浮橋の君のお屋敷を狙うなんて……妙ですね」
その一言に、登花殿の女房が眉を跳ね上げた。
「なっ……! まさか浮橋の君が、霊獣を操ったとでも!?」
声がひときわ高く響くと、廊下の空気がすっと張り詰めた。衣擦れの音ひとつで、空気が裂けそうなくらいに。
燁子は何も言わなかった。ただ、ゆっくりと視線を弘徽殿の女房に向ける。そのまなざしに揺らぎはなく、けれど敵意もない。静かな水面のような眼差しに、女房のほうがわずかに視線を逸らした。
「まあ、でも……霊獣が暴走したのは……行方不明になった“誰か”のせいでは?」
ぽつりと落とされた言葉は、登花殿の側にいた若い女房からだった。言ってしまってからハッとしたように口元を手でおさえる。
私の背筋に、ぞくりと冷たいものが走った。
“誰か”──それは、きっと私のことだ。
視界がゆらいだ気がした。白虎が、胸の奥で氣をざわつかせるのを感じる。けれど、だめ。今は絶対に出てきてはだめ。
白虎……お願い、静かに。
心の中でそっと呼びかけると、氣の波がゆっくりとおさまっていった。
足元を見つめたまま、私は唇をきゅっと噛んだ。言いたいことが、喉の奥につかえて出てこない。言ってはいけない。私の名も、真実も。
ただの「鈴太」として、この場に立っているしかない。それが今の役目。でも、言葉を発しなかったその沈黙が、私自身の存在を否定するようで、胸の奥がじくじくと痛んだ。
ひとこと。たったひとこと、真実を言えたなら。けれど、今それをすれば、すべてが崩れる。私は息を小さく吐いた。震える氣を、胸の奥に押し込めて──目を伏せたまま、嵐の通り過ぎるのを待った。
「お姉様は、そんなことしないわ!」
その言葉に周囲のざわめきが止まった。
燁子はまっすぐ前を見据えていた。大きな瞳に涙が滲んでいる。光を宿した涙が白い頬をつたってこぼれ落ちた。一幅の絵のようで美しかった。
「失礼いたしました、浮橋の君」
弘徽殿の女房が頭を下げた。だが燁子は、それを追い払うように首を振り、震える声で続けた。
「でも、でも……本当にそうだったら……わたくし……」
言葉の先が、細くちぎれそうになりながらも、涙とともに落ちてゆく。
「まあ……お気の毒に……」
「こんなに浮橋の君を悲しませるなんて。宵家のお荷物とまで言われていた姫のくせに」
「本当に行方不明なのかしら。霊獣に襲われたって、そんな大げさな……」
「卑しい姫と噂の、ね?」
「そうそう、どこかの屋敷で物乞いでもしてるんじゃないかしら」
その矛先が、ゆっくりと見えない刃のようにこちらに向けられてゆく。
“鈴太”であるはずの私に──“鈴音”としての、私に。
足元からじわじわと凍りつくような感覚。背筋をつたう冷や汗。誰も触れていないのに、胸の奥が、きゅっと縮こまってゆく。
なに、これ──
燁子の涙は本物に見える。揺らめく睫毛。やわらかな声音。たおやかな立ち居振る舞い。守りたくなる人。誰もが、そう思うだろう。
だけど……これは、一体、なんだろう。
私の心の奥がすっと冷えていく。
……私じゃないのに。
思わず、喉の奥でそうつぶやきかけていた。だけど、声にはならなかった。言ってしまえば、すべてが崩れる。この中の誰かにでも気づかれたら、終わりだ。
白虎の氣がわずかに波打つのを感じた。私は奥歯を噛みしめる。
だめ。絶対に、ばれてはならない。
たとえこの違和感が、私を飲み込むほど大きくなっても。たとえ胸が軋むほど痛くても。
私は、鈴太。浮橋の君の「姉」などでは、決して、ない。
「……何をしている」
その場の空気がすうっと冷えた。女房たちの刺々しい声が交差する中で、廊下に凛とした足音が響きはじめた。
「もう一度言う。何をしている」
その声は低く、静かでありながら、空気を一気に裂く鋭さを持っていた。
ぱたり、と。全員の視線がその方向に向かう。登花殿の女房も、弘徽殿の女房も、そして燁子も。息を詰める音が、耳の奥で重なった。
一歩、また一歩と、無駄のない動きで歩み寄ってくるその姿は、ただそこにいるだけで空気を一変させる。威厳と静けさをまとった存在。
「二の宮様!」
その瞬間、燁子がぱっと振り返った。
さっきまで涙に濡れていたはずのその顔は、まるで別人のように明るく輝いていた。張りのある声。嬉しさを隠そうともしない瞳。高鳴る想いが、全身からこぼれ出ている。
私は、不意にその横顔に目を奪われた。
その目はまっすぐに、まるで何もかもを託すように、宮様だけを見ていた。隠しもせず、揺れもせず、ただ一心に。
あの子……宮様に……。
その想いは作られたものではない。心からのものだと、ひと目でわかってしまった。胸の奥が、ひとつ波打つ。それは悲しみでも怒りでもない。けれど、心の深いところで、何かが軋むような音がした。
燁子がふたたび涙をにじませたまま、震える声で言う。
「お姉さまがいなくなって……私……とても心を痛めているんです……」
彼女の瞳が潤み、まぶたの縁が揺れた。誰もが、胸を打たれるであろうその姿。けれど、宮様はほんの一瞬だけ燁子に視線を向けると、あくまで淡々と、ただ一言だけ返した。
「そうか」
それだけだった。
え……と、私は思った。きっと、私だけではなかったはずだ。燁子の顔が、一瞬だけ動きを止めた。まるで糸が切れた人形のように。
けれど、その一瞬の空白は誰にも悟らせることなく、すぐにいつもの笑顔に差し替えられた。花のようにやわらかく、美しく。誰もが安心し守りたくなる、あの“浮橋の君”の笑顔に。
私の胸の奥にもう一度、ざわりと波が立った。それが何なのか、言葉にはまだできなかったけれど、確かにそこに不協和音があった。
そのとき、隣にいた宗直様が、ふうっと息を吐いた。
「……昔からさ。浮橋の君は、ずっとあの方に憧れているんだよな……」
ぽつりと落ちた声に、私はそっと横を向いた。
宗直様の横顔はどこか遠くを見ていた。その瞳に映っていたのは今この場ではない、もっと昔の情景なのかもしれない。その頬には笑みも怒りもなかったけれど、微かに滲んだ翳りが、胸に引っかかった。
宗直様は、もしかして。
私の胸の奥に確信のような感情が芽吹いていた。あの目はただの敬慕ではない。もっと深い感情の色を秘めている気がする。
「二人とも何をしておる。こちらへ来い。女御様を待たせるわけにはいかない」
宮様が私たちを見て、その声が空気をすっと引き締めた。振り返らず、静かに歩き出すその背中。
「はいっ」
我知らず、声が出た。それに続いて、宗直様も軽くうなずいて歩き出す。
「二の宮様!」
燁子の声が後ろから響いた。名を呼ぶその声音には揺れる情がこもっていた。
けれど、宮様の足は止まらなかった。まっすぐに弘徽殿の方へ。その背に一片の迷いもない。
その背を見送る登花殿の女房たちは、唇を噛みしめて黙ったまま。一方で、弘徽殿の女房たちは、勝ち誇ったように鼻先で笑った。女たちの戦場はこんなふうに、言葉よりも表情で火花を散らすのだと私は初めて知った。
歩き出しかけたとき、何気なく振り返ってしまった。
そこにいた燁子の横顔は、微笑んでいた。けれどその笑みに、さっきまでの透明さはもうなかった。どこか歪んで、張りつけたような微笑み。唇は上がっているのに、目だけが笑っていない。
燁子……? 私は初めて、彼女の“内側”を見た気がした。見えないはずの本音が、うっすらと面の下から透けて見える。その微かな隙間に、冷たい風が吹いたような気がして。
胸の奥が、きゅっと冷たくなる。私は振り払うように、背中を追いかけて弘徽殿へと歩を進めた。
◆◆ ◆
弘徽殿へとたどり着いた瞬間、胸の奥がふわりと軽くなった。
静かだった。風も音も、すべてがどこか遠くに置き去りにされたような、凛とした静けさ。陽の光も影もどこか上品におさまっている。
私は立ち止まり、そっと息を吸い込んだ。ほんのりと青草のような香りが鼻先をくすぐる。心がふっとほどけるような、そんな感覚。
あれ、霊獣の氣が漂っている。どこから?
氣を探れば、弘徽殿女御様の守り霊獣・白鹿にたどり着く。初めて感じたその氣配が、御殿全体をゆるやかに包んでいる。
柔らかいけれど、芯の通った力強さ。白虎の鋭く純粋な氣とは違う、深くて穏やかな波のような氣。まるで澄んだ湖の底に身を沈めたような、静謐で安心感のある空気だった。
すると、御簾の奥からやわらかな声が響いた。
「浮橋の君とのやり取り、聞こえてきましたよ。相変わらずですね、宮」
現れたのは、弘徽殿女御様だった。御簾越しから感じる華やかさも気品のある気配。言葉のひとつひとつが、丁寧でありながらも、相手の核心をさらりと突くような鋭さを帯びているのは、さすが後宮一の女御と言ったところか。
「女御様。ご紹介いたします」
宮様が一歩前へ出て、私と宗直様に一瞥を与える。その仕草に導かれ、私は慌てて前に出て、深く頭を下げた。
「清原宗直です。鈴太と共に巡回に入っております」
宗直様の声はいつもより少し張っていた。けれど、笑顔は変わらない。
「……鈴太と申します。どうぞ、よろしくお願い申し上げます」
声が少し上ずる。手のひらがじっとりと汗ばんでいた。
「おふたりとも、ご苦労さまです。こうして霊獣寮の若き力が後宮に入るのは、頼もしいことですわ」
その言葉に私は胸が熱くなった。歓迎されている。ちゃんと見てくださっている。そんな安心感が、言葉の端々から伝わってきた。
「事件後、何か変化はありましたか?」
宮様が落ち着いた声で問うと、女御様はふっと視線を落とした。
「……実は、三条という若い女房が心を病みまして。今は実家に戻しておりますの」
その名を聞いた瞬間、隣の宗直様がわずかに息を呑む気配を見せた。
「その子が事件の夜、“ある香”を焚いたそうです。香の名までは覚えていなかったようですが、焚いた直後に白鹿が強く怯え……気が荒れてしまったのです」
「香、ですか」
その一言に、私の中の感覚が鋭く立ち上がった。まるで光が差し込んだように、記憶のどこかが照らされる。
そうだわ。あの話を聞かせてくれた女房が言っていた。あの夜、どこか甘く、ふわっとした、嗅いだことのない香がしたと。
思わず手を握り締める。今の女御様の言葉が、あの証言とぴたりと重なる。
女御様がふっと視線を落とし、少し困ったように口をひらかれた。
「三条は、“香を焚いたあと、何かが壊れたような気がした”と申しておりましたの。でも香なんて、誰でも日常的に焚いているものでしょう? 彼女がそのとき焚いたからといって、あの騒動が彼女のせいだとは……私は、そうは思えないのです」
その声には女御様なりの葛藤と、女房への情がにじんでいた。
「そうですね。三条自身の思い違いという可能性もあります」
宮様が静かに言葉を継がれた。
「ですが、その香が“潤氣擾乱香”であったなら話は別です」
一瞬、場の空気が揺れたような気がした。女御様が小首を傾げられた。
「潤氣擾乱香……? 何ですか、それは」
「霊獣の潤氣の共鳴を狂わせ、異常を引き起こすものです。表向きは“癒し香”と称されておりますが、実際には蛟のような変質霊獣の氣を微かに含んでおり……霊獣の氣の流れを乱す作用があります」
「……そんな香が、存在するのですね。困ったわ」
女御様は息を詰め、心配を声に滲ませた。
「この霊獣騒乱事件は霊獣寮の管轄になりました。原因を必ず突き止めます」
宮様の言葉に、女御様は静かに頷かれた。
「お願いします……。三条は素直で真面目な子だったのです。あの夜を境に気の毒なことです」
「まずは事件の解決からです」
「そうですわね」
女御様のまなざしがふと、私の方へと向けられた。
「あなた……霊獣の氣にとても敏感なのですね?」
突然話しかけられて、思わず息が詰まりそうになる。私は戸惑いながらも、そっと小さく頷いていた。
「びっくりさせてしまったかしら。白鹿があなたに興味を持っているようなの。いつでもいらっしゃい」
胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じた。張りつめていた心のどこかが、そっとほどけるような感覚。私は小さく深呼吸し、そっとその空気を、胸いっぱいに吸い込んだ。白鹿の氣配と重なって、心がほのかに温まる。
そのぬくもりを胸にそっと包みながら、私は女御様に頭を下げた。
「ありがとうございます。……また、お邪魔いたします」
御簾の内側で女御様がやわらかくうなずかれた。
その言葉の後に、私と宗直様、そして宮様は、静かに弘徽殿をあとにした。
御殿を出た瞬間、外気が肌に触れた。内の氣と外の氣が交じる、そのわずかな変化に、私はふっと顔を上げる。白鹿の氣を含んだ空気が、背後に静かに揺れている。
そして、宮様がふと足を緩められた。
「三条の実家を調べさせる。……香の残り香があれば、確証が得られるだろう」
その言葉に、宗直様が即座に反応した。
「よし、俺が行きましょうか!」
勢いよく手を挙げた宗直様の声が、静けさに弾んで響く。けれど、宮様は涼やかに首を振られた。
「いや。鳳凰に偵察させる」
「……ですよねぇ」
宗直様が肩を落とす。その姿がなんとも可笑しくて、私は思わず唇を引き結んだ。笑いそうになったのをなんとか飲み込む。
ほんのり草の香が混じるこの空気の中で、私はふと口をひらいた。
「あの……霊獣たちが、あの香をすごく嫌がっていました。あれはやはり何か混ざっていたような、そういう感じがして……」
自分でも、なぜこんなふうに言葉が出たのか分からなかった。けれど、胸の奥から自然にこぼれてきた感覚だった。
そのとき、宮様がぴたりと立ち止まった。鋭くも静かなまなざしで、私を見つめる。
「宗直、そなたにはこれから三日に一度、後宮の巡回を頼む。鈴太を補佐につけよう」
「わ、私ですか?」
「ああ」
「了解しました! お任せください」
宗直様はまっすぐ背を伸ばし、晴れやかに胸を叩いた。
その声が頼もしく響いたあと、宮様は続ける。
「殿上童がいれば、女房たちも警戒心を解くだろう。彼女らから、事件につながる証言や痕跡が見つかれば……必ず報告してくれ」
「承知しました!」
私は黙って深くうなずいた。胸の奥にじわりと熱が灯る。
私、ここで役に立てるのかもしれない。
霊獣が教えてくれる氣の揺らぎ。誰かの言葉の奥にある、ほんとうの感情。気づけるのなら、見つけられるのなら――私はきっと、役に立てる。
足元がしっかりと地についていた。
その感覚を胸に、私はまた一つ、新しい役目を背負う覚悟を決めた。
あ、生きている。ふと、それが浮かんだ。
まぶたをゆっくりと持ち上げると、御簾越しに射し込む陽の光が、やわらかな筋となって床を撫でていたのが見えた。ほのかに檜の香りが漂う。ここはどこなのだろう。
それにしても、どこかほっとするような温もりを肌で感じる。その心地よさの奥に、どこか引っかかるような違和感があった。
そっと指先を動かす。腕に力を入れて上体をわずかに起こすと、
「……え?」
目を見開いて、体が固まった。
視界に映るのは白銀の毛並み。しんと静まり返った空間の中、気高い霊獣が目を閉じ、穏やかな呼吸を繰り返している。私のすぐそばに、なぜか白虎がいた。
そして、その白虎ももたれかかるように、いくつもの種類の小さな霊獣たちが丸まって眠っていた。
不思議なぬくもりに満ちた空間。胸の奥からじんわりと熱を帯びる。すうと息を吸った瞬間に優しい潤氣が肺にいっぱいに満ちた。
ずっとここで眠っていたいんだけど。でも、一体どこからこの霊獣たちはやってきたのだろう。それに、
「ここ……どこ……?」
つい漏れた声は、自分でも驚くほど小さく掠れていた。誰にというわけでもなく、問いかけるように呟いた。
「目覚めたか」
低く、静かな声が耳の奥を震わせる。びくんと反射的に肩が跳ねた。音のした方へ振り向けば、御簾がすっと上がり、光の縁取りの中から姿を現したのは、
「霊獣に囲まれて眠るとは、珍しい」
陽の光を背に立つその人は、いつもと変わらぬ端正な顔立ちで、凛とした気配を纏っていた。けれど、その瞳の奥にほんの少し、柔らかな色が揺れている気がした。かすかに口の端も上がっているような。
「霊獣にやけに好かれているな。宵家の大姫の」
「……っ!」
き、今上帝の二の宮・彰仁親王さま!
血の気が一気に頭に昇った。ぽうっと顔が熱を持ち、心臓が跳ね上がる。それなのに寝ぼけた頭に冷水をかけられたように、意識がはっきりした。
「きゃあああっ! な、なな、なんで、ここにっ!?」
声が裏返り、言葉がつっかえる。私は咄嗟に着物を引き寄せて、上体を隠した。起き抜けの私を、よりにもよって、やんごとなき宮様に見られてしまったなんて!
羞恥心で頭が真っ白になる。どうしても目が合わせられない。
「……支度をしてやってくれ」
宮様は私の取り乱しにも動じることなく、静かに背を向けて部屋を出ていく。
「え、あの、ちょ、ちょっと……!」
「かしこまりました、若宮様」
その声に導かれるように、気づけば傍らには年配の女房が立っていた。やわらかな笑みを浮かべて、すっと頭を下げる。
「はじめまして、姫様。私は、たきと申します」
「た、たき様。初めまして」
慌てて同じように頭を下げると、ふふと笑い声がこぼれた。
「あらあら、かわいらしい方。頭をお上げになってください。私に様はいりませんよ。若宮様より、姫様にお仕えするよう仰せつかっております。どうぞよろしくお願いいたしますね」
「は、はい」
温かく響くたきさんの声に顔を上げる。なぜか張り詰めていた胸の糸がふっと緩むのを感じた。
「さ、お支度をいたしましょう」
「し、支度……?」
そう言って、たきさんは私にふわりと広がった衣を見せた。白地に繊細な刺繍が施された童直衣。
えっと、なんで?
「え、あの……これって……」
「ふふ、驚かれるのも無理はありません。殿上童としてのお召しものですが、お似合いになると思います」
「殿上童!?」
にこやかに話すのに、どこか押しの強いたきさんに、言われるがまま着せられる。
たきさんは手際よく私の腕を通し、帯を結び、裾を整えていく。するすると動く指先は、水の流れのように自然で、着せられているはずの私の身体が、まるで自分からその衣に馴染んでいくような、不思議な感覚さえした。
「はい、よくお似合いです」
そう言ってたきさんは今度は櫛を手に取る。私の背後に回るとそっと髪を梳き始めた。その動作もまた驚くほど丁寧で、優しかった。くしけずられるたびに、ふわりと髪がほぐれていく。心も同じように、からまったものがほどけていくようだった。
「あの……そもそも、ここは……?」
恐る恐る尋ねると、たきさまは髪をすく手を止めずに、穏やかに答えてくれた。
「ここは若宮様のお屋敷でございますよ」
「えっ」
思わず声が裏返った。宮様の……お屋敷? えっと、本当になんで?
戸惑いと混乱で頭がぐるぐるしているうちに、たきさまは最後に髪のまとめを整えて、にっこりと笑った。
「さあ、若宮様がお待ちですよ。ご挨拶に参りましょう」
「ま、待ってください、まだ心の準備が……!」
だって起きたばかりの姿を見られただけで、もう顔から火が出そうなのに! 思わず立ち上がりかけたところを、優しく背中に手を添えられる。
「大丈夫ですよ。きれいに整いましたからね」
たきさん目を細めて、やさしく私の背を押した。手のひらのあたたかさが、私の緊張をほんの少し和らげる。歩き出した足元がたしかな感触を伝えてくるのに、気持ちはまだどこか夢の中のままだった。
朝の光が整えられた屋敷の庭に射し込み、ちちちち、とどこからか鳥の鳴き声が聞こえてくる。私はたきさんに伴われて宮様のお屋敷の寝殿へと足を踏み入れた。御簾の向こうには宮様がいる。胸がそわそわとして落ち着かなかった。
「失礼いたします」
たきさんの声を合図に、私は深く頭を下げた。
「似合っているではないか」
ふいに、その声が御簾の奥から届いた。
宮様の声に心臓が跳ねた。冷たさを纏った澄んだ響き。けれど、わずかに笑みを含んでいるような気がした。
私は思わず着ている童直衣のをぎゅっと握りしめた。袖の中の指先がじんわりと熱を持つ。まさかこんな姿を男性に、しかも今上帝の二の宮様に見られるなんて思ってもみない。
「座りなさい。不思議そうな顔をしているな。宵家の大姫」
「あ、あの……」
「なんだ。申してみよ」
言葉を出すのが怖かった。でも、聞かずにはいられなかった。
「どうして、私を連れてきたのですか? それにこの格好は……どうして童のような……」
御簾の向こうは短い沈黙のあとに、静かに返された。その声は夜明け前の風のように凜としていた。
「……宮中で霊獣を鎮めた後のことだ」
「後、ですか」
宮様の声が低く穏やかに重なる。
「闇夜の奥から何かが飛び出してきた。霊獣の類と見られるものだ。それがそなたににぶつかり、おまえはそのまま意識を失ったのだ」
私は小さく息を呑んだ。
そうだわ、私……脳裏に記憶が明滅する。しなる黒い尾、禍々しく輝く紅い瞳。まるで夜そのものが形をとったような、美しくも恐ろしい存在。
「白虎がそなたを背に乗せ、私のもとへと駆けてきた。霊獣・白虎が危機を感じ取り、そなたを守ろうとした。私はそのまま白虎と共に、そなたをここへ連れて帰った」
言葉は淡々としていたけれど、そこには嘘のない確かさがあった。だからこそ、肩が竦み顔が青ざめる。額が床板にくっつきそうなほど頭を下げた。
「そうでしたか。ありがとうございます。宮様のお手を煩わせて申し訳ございませんでした」
「よい。気にするな。妖獣となって暴れた霊獣たちは、そなたのおかげで霊獣に戻った。こちらこそ、礼を言う」
「滅相もございません!」
はしたないとは思ったけれど、ぶんぶんと横に首を振った。
「だが、今回の犯人はいまだ見つかっていない」
「え……」
「内裏のあちらこちらに影響を与えたが、特に氣の乱れが激しかったのは後宮だった」
その言葉が落ちた瞬間、部屋の温度が少し下がったような気がした。
「犯人が意図的に霊獣を妖獣へと変貌させた可能性は否定できない。そして、大姫。そなたは、結果として“狙われた”ように見える」
凍るような静けさの中に、確かな警告が混じっていた。
「理由はわからない。ただわからないからこそ、また同じことが起こるかもしれない」
また同じことが、本当に? 私は無意識に胸元に手を当てていた。白虎の氣がそこに宿っているような気がして。背を支えられ包まれ導かれた感覚が、まだ体の奥に残っているような気がする。
「この度の宮中で起きた件は、霊獣騒乱事件として霊獣寮の管轄となった。しかし上では、いまだに騒ぎが収まらぬらしい。だが、霊獣を鎮めたのが誰か、それは伏せている」
言葉の一つひとつが、冷たくも厳しく感じられる。
「藤原宵家ではもう話が出回っているそうだぞ。『西の対の姫が霊獣に襲われ、行方知れずになった』と」
私は小さく肩を震わせた。まるで自分のことではないみたいだった。けれど、その“姫”とは、まぎれもなく私。
「そう、ですか」
小さな声が漏れた。そのまま宮様は淡々と続けた。
「ちょうどよい。今、都から宵家の大姫という存在が消えた方が都合がよい。ならば利用するまでだ」
「ゆ、行方不明になるんですか、私が……?」
「そなたを守るためだ。それから、その姿のままでは、そなたが何者かをすぐに嗅ぎつけられる。だから、殿上童として名を変え、霊獣寮に属してもらう」
「へ!?」
目を見開いて固まった。とんでもないことを言われた気がする! 私が殿上童になるの!?
驚きを隠せない私とは対照的に、御簾の向こうでは、淡々と静かに紙をめくるような音がした。
「霊獣師たちと同じように後宮へも出入りできるようにしよう。氣の乱れがあれば、すぐ私に知らせよ。事件は何も解決していないし、あの場には……まだ澱んだ氣が残っている」
私の喉が音を立てた。何かを呑み込むようにして。聞けば聞くほど怖い。けれど、宮様から告げられることに、拒む言葉が出てこなかった。ただ、押し寄せてくる現実の波に、足を取られぬよう耐えるので精一杯だった。
「それから住まいは、ここに」
「え……!?」
今度は声が上ずった。宮様の屋敷に!?
そんな大それたことが許されるのだろうかと、体が一瞬すくんだ。けれど、彼の声には一片の迷いもない。それが命令だということを、私はようやく理解した。
「……謹んで、お受けいたします」
そう言うしか、なかった。いや、そうするしかなかった。
短い沈黙のあと、ふいに問いが返ってくる。
「宵家に、知らせておくべき者はいるか?」
その一言が胸の奥を突いた。思わず目を伏せたまま、呼吸が止まりそうになった。きっと宮様から優しさをいただいたのだろう。燁子の顔が浮かび、そして、すぐに消えた。
「……必要ありません」
唇が自然と動いていた。
「私のことなど、気にかける者はいないはずです」
言って唇を噛んだ。それが嘘ではないことが、逆に寂しかった。
御簾の向こうの気配が、ほんのわずかに揺らいだように思えた。
言葉にはならなかったけれど、空気の向こうから、なにかがそっと伝わってきた。
私はその一瞬を、胸の奥でそっと包んだ。
それが、どれほど小さくても、誰かが私を見てくれていたという証のような気がして。
◆◆ ◆
「ここが、内裏」
見上げた先には立派な門。思わずこぼれた声が、朝の澄んだ空気に溶けていった。
足元の白い敷石が光を弾き、まるで雲の上を歩いているみたいに眩しい。檜皮葺の大屋根は空へと悠然と伸び、風に揺れる柳の梢が青空と重なり合って、境界が消えていくようだった。
妹の燁子が呼ばれる遠くから憧れるだけだった場所。その中へ、いま自分の足で入っていくなんて。胸の奥がふわりと浮く。
先を行く宮様の背を追って歩を速めたとき、低い声がふいに落ちてきた。
「その姿、違和感はないな」
「そうでしょうか」
からかうような響きに、私は思わずうつむいた。十六、七にもなって――女として花の盛りを迎えるはずの自分が、殿上童の姿を褒められるなんて、いいのか悪いのか、女心は複雑だ。
「霊獣寮へ向かう前に、そなたの名を決めねばな。そうだな……そなたの名は鈴太とする。私の遠縁ということにしておこう。忘れぬようにな」
「鈴太、ですね。わかりました。鈴太、鈴太……」
心の中で何度も唱える。新しい名を忘れないように、必死で刻み込む。
「女だと気づかれぬように。殿上童として細心の注意を払って振舞ってくれ」
その言葉に思わず喉がからからになった。私は強ばったまま、こくりと小さく頷く。
すると宮様は、足を止め、ゆるやかにこちらを振り返った。
「そなたが鈴太としてふるまう以上、仮面は私が守る。……安心せよ」
その一言が、胸の奥にすとんと落ちた。守る──命令ではなく、支えのような響き。
「はい」
私は肩の力をふっと抜き、今度はまっすぐに声を返した。
そうして歩を進めると、霊獣寮の建物が見えてきた。
霊獣寮の建物は想像よりも静かだった。宮様が扉を開けて中に進むと、中からふわりと木と香の匂いが流れてきた。
室内では世話しなく霊獣師たちが働いていた。私たちの気配に気づいた瞬間、何人かがこちらを振り返った。足が少し止まりかける。
「宮様。おはようございます。その子は……?」
「遠縁の子だ。名は鈴太。今日からここで修練を積む」
宮様が短くそう言っただけで、空気がわずかに揺れた。その場にいた霊獣師たちの視線が一斉に私に向けられる。その視線には色があった。淡い興味、用心深さ、少しの警戒。そして、ほんのわずかに滲む嘲りのような何か。
じわりと背中が熱を持つ。思わず肩がすくんだ。
「……萎縮せずとも良い。背筋だけ伸ばしておけ」
宮様の声がすぐ耳元に落ちてきた。あたたかくも冷静な声。私は息を整えて、背すじを伸ばす。肩の力を抜いて、ただ、まっすぐに立つ──それだけで、少し呼吸がしやすくなった気がした。
「こちらへ」
そう促されて私は宮様のあとに続いた。
「みなさん、お忙しそうですね」
「そうだな。霊獣寮は都の霊獣、特に宮中の霊獣に関することを一手に引き受けているからな。霊獣師たちは多忙だ」
「あの、浮橋の君のように、霊獣師は霊獣を従えているのですか?」
「霊獣と主の関係は、命令と服従だけではない」
その言葉に、思わず足が半歩遅れる。
「氣の流れを通して互いが響き合う。主の心の在り方が、霊獣の氣を変える。穏やかであれば潤い、乱れれば濁る」
「じゃあ、霊獣の異変は“氣”が濁った結果……」
思わず口に出していた。宮様が振り返り、ほんの少しだけ口の端が上がっていたような気がした。けれど何も言わず、再び前を向いて歩き出す。
知らないことばかりだ。でも、なぜかそれらは、胸のどこかにすとんと落ちていく気がする。私にはまだ何もない。だけど、霊獣たちが見せてくれたあの光や聲──それを思い出すと理解できる気がした。
霊獣師たちの邪魔にならないような広間の一角までやってきた。宮様が足を止めた。
「そなたには宮中の巡回に出てもらおう。まずは場所を覚えること。支度をしてくるから、鈴太はここで待て」
振り返りもせずに言い残すと、軽やかに歩いて去っていく。
その背を目で追いながら、私はそっと息を吐いた。すごいところに来てしまった。霊獣師の仕事なんて初めて見た。
「おい、そこの新人」
不意に背後から声が落ちてきた。
反射的に振り返ると、影がひとつ、二つ、三つと足音と共に前へ出てくる。三人の男が私を取り囲むように並んで立っていた。
真ん中の男が、すっと私の方へ歩を進める。目元の鋭い男だ。ふてぶてしい笑みが唇に浮かんだ。
「殿上童なんざ、霊獣の扱いも知らねえのに何しに来た? 新人のくせに、やけに偉そうな顔しているじゃねぇか」
ぐっと喉の奥が詰まった。言葉が出ない。その男はわざとらしく私の前に立つと、顎をしゃくった。
「俺は在原貞親。先に名乗ってやったんだ、何か言えよ、鈴太坊や」
ニヤリと笑われたと同時に、私の背中からうっすらと氣のざわめきが立ち上がる。
だめ、出てこないで。白虎。
ぐるるると反応する白虎に心の中で呼びかける。姿を消しているのだが、白虎がついていくと聞かなかったのだ。
白虎……お願い。ここは、私が。
すると伝わったのか、白虎の氣が、すっと引いていく。私を信じてくれた、その感触だけが残った。
「なんだよその目。睨んでいるのか?」
貞親の左右にいた取り巻きが、わざとらしく顔を見合わせてから、含み笑いを漏らした。
「本当に宮様の遠縁か? 聞いたことないけど。若宮さまの気まぐれってやつ?」
「気まぐれだなんて、何を言っているんですか、そんなはず」
「殿上童をいじめるなんて、どうかしているぞ!」
元気のよい空気が弾けるような声が場に割って入った。割り込んできたのは、明るい色の直衣を着た青年だった。真っ直ぐな笑顔で、貞親たちの間にぐいと割り入ると、両手を腰に当てた。
「はじめまして! 俺は清原宗直。鈴太だっけ? これからよろしくな」
一瞬、何が起きたかわからず、私はぽかんと口を開けていた。
「……なに勝手に話、終わらせてんだよ」
貞親が舌打ちを落とした。
「悪い悪い。でもまあ、そのくらいにしとこうぜ、貞親殿。宮様にバレると大変だぞ」
宗直様は笑ったまま、貞親の肩をぽんと叩いた。
貞親は舌を鳴らして踵を返し、取り巻きを連れて去っていった。
「さっきのが在原貞親。霊獣寮の中じゃ、ちょっと気の立つやつでね。俺のことも嫌いみたいだ」
宗直様が声をひそめて言う。その目が私を見て、片方だけ、くいっとウインクした。空気が、ふっと緩んだ。
「困ったら俺がついてるから。何でも言ってくれていいぞ」
「ありがとうございます。宗直様。助かりました」
「どうした」
低く静かな声が響いた。背筋が自然と伸びる。振り向かずとも分かる。宮様だ。私は慌てて姿勢を正した。
「たいしたことではありません、宮様。鈴太を歓迎していたら、ちょっと賑やかになりまして」
しばしの沈黙ののち、宮様の視線がすっと私をかすめた。
目は合わなかったけれど、そこに怒りはなかった。
「鈴太、内裏の巡回に行くぞ」
「は、はい!」
声が少し上ずった。慌てて口を閉じる。
「ちょうどよかった。宗直、君も同行するように」
「承知しました。宮様」
宗直様が肩を回して笑いながらついてくる。私たちは三人で歩き出した。
◆◆ ◆
清涼殿の敷石は、まるで鏡のように白く冷たく光っていた。
高く張られた格子の向こうから陽が静かに差し込んで殿の奥まで届いている。この空間の隅々にまで、言葉にできない緊張が満ちていた。
帝が政を執る内裏の中でも最も重要な場所。そんなところに、体がかちこちに固まっている私は、足音を立てぬように歩いていた。
「……あの、巡回って……内裏の中をまわるだけじゃないんですか?」
思いきって出した声は思ったよりも小さく、まるで水面に落ちた石のように、ぽちゃんと空気に吸い込まれていった。隣を歩く宗直様が、少し口元を引きつらせて囁いた。
「まあまあ、鈴太くん。黙ってついて行こう。な?」
いつもの調子に似ているけれど、どこか浮ついた響きが混じっていた。宗直様ですら落ち着かないのなら、やっぱりここは特別な場所なのだ。
清涼殿の殿上の間へと足を踏み入れると、すぐに気配がこちらをとらえた。
部屋に控えていた数人のうち、一人がゆっくりと立ち上がる。
「やあ。病弱と噂される霊獣頭が、清涼殿に現れるとは。珍しいこともあるもんだな」
すっと伸びた背筋に鋭い眼光を持つ公達。でも軽やかに笑う声に、どこかからかいのようなものが混じっている。誰だろうと思っていると、小声で宗直様が教えてくれた。
「蔵人所の頭中将の藤原公孝様だ。……めんどくさい人だよ」
その表現が妙に納得できた。言葉も態度も軽やかなのに、どこか全てを見透かされているような圧がある。
「敏行、すまない。この書状を手配しておいてくれ」
頭中将さまは横に控えていた細身の若い男へ、手にしていた文を渡した。
「上司に扱き使われるとは、氏蔵人殿も大変だな」
宮様がふっと笑う。それに敏行という名の青年は、少しだけ眉尻を下げて応じた。
「とんでもございません。これも務めですから」
「真面目だな」
宮様が微かに笑みを浮かべた。その柔らかな表情が、場の張り詰めた空気をわずかに解いた気がした。
「敏行のことはいいんだよ。貴方は何か用があってきたのだろう?」
本題を促すように、頭中将が表情を戻す。宮様は落ち着いた口調のまま一歩踏み出し、静かに頭を下げた。
「先の霊獣の件、霊獣寮にて引き受けることとなりました。その旨、報せに参りました」
「そうか」
「では、私も報せを聞こうか」
その瞬間、殿内に風が駆け抜けた気がした。
視線を向けると、御簾の奥からゆっくりと影が現れる。上等な柔らかな衣の裾がそよ風のように揺れた。一歩踏み出したその姿を目にして息が止まった。
一瞬にして、この場にいる者たちがすっと頭を下げた。
声の主が誰なのか、問うまでもなかった。
この方が今上帝。内裏の主で、この国を安寧に導くお方。
額が畳に触れそうになるくらい身を折る。思考が真っ白になった。鼓動の音だけが妙に大きく響く。
隣の宗直様をちらりと見ると彼もまた硬直しながら頭を下げていた。普段は軽やかな笑みを浮かべている彼が、まるで凍りついた石像のようだった。
ああ……本当に、滅多にお会いできないる方なのね。
その事実がようやく胸に染みてくる。
ただ何事にも動じなく、落ち着き払っていてたのは宮様だった。
ああ、そうだ。この方は宮様のお父上だった。
「主上、紹介します。霊獣師の清原宗直。そしてこの童は、殿上童として任じられた鈴太でございます」
名を呼ばれて私はぴくりと背を正した。緊張で喉が詰まりそうだったが、懸命に頭を下げる。鼓動が早すぎて、体の中の音がうるさく響いた。
「そなたの部下か。仕事に励むように」
帝の声がゆっくりと降りてきた。まるで水面を撫でる風のような静けさと、決して揺るがぬ重みをまとった言葉。たったひとことだったのに。胸の奥がきゅっと締めつけられた。
ありがたくて、誇らしくて、でもどこか夢の中にいるようで。
忘れない……絶対に。
帝から直接、言葉をかけていただいた。それだけで、身体の奥に炎のようなものが灯るのを感じた。宗直様も感極まったように唇を引き結び、まっすぐ頭を下げている。
「宮、報せを直接聞こうか。頭中将もこちらへ」
帝がそう告げると、宮様と頭中将様がすっと進み出た。
振り返らずに宮様が言った。
「宗直、鈴太。先に内裏の巡回に出ておけ」
「は、はい!」
「了解であります!」
思わず声が裏返りそうになりながらも、私は勢いよく頭を下げた。
宗直様も元気よくそれに続く。
広間を離れ、静けさから解き放たれたとき、私はようやく小さく息を吐いた。
巡回の初日で、まさか帝にまでお目にかかるなんて。
夢のような時間の余韻に揺れながら、私はそっと胸に手を当てた。
そこには、白虎の氣が静かに寄り添っていた。
まるで「よく頑張ったね」と言ってくれているようで、じんわりとあたたかい。
私は歩き出す。鈴太として、霊獣寮の殿上童として。
けれどその心の奥には、誰にも明かせぬ鈴音の私が、静かに息づいていた。
◆◆ ◆
内裏の回廊は朝の光に包まれて、どこまでも静かで澄んでいた。
白木の板が丁寧に敷き詰められ、踏み出すたびに足音がほのかに響く。その床には、差し込む陽が薄く反射していて、歩く自分の影が淡く揺れて映っていた。
まるで夢の中を歩いているようで、私は何度も瞬きをして確かめた。
「鈴太、きょろきょろしすぎ」
隣から声がして顔を向ける。宗直様が、肩をすくめて笑っていた。
「顔に“初めてです”って書いてあるよ」
「……そ、その通りなので……」
恥ずかしさを隠せなくて、つい小声で返す。
だって、ほんとうに初めてなのだ。こんなにも奥深い、宮中の廊下を歩くなんて。
すれ違う二人の女房たちが、にこやかに頭を下げながら口々に言う。
「あらあら。見かけない顔だけれども、かわいらしい」
「まぁ、かわいらしくて初々しいじゃないの」
頬がかっと熱を帯びる。笑顔で交わされる好意的な言葉に、うまく笑い返せず、つい視線を伏せた。宗直様がふっと笑った。
「なんだ、恥ずかしいのか? 誉められたら、素直にありがとうって思っておけばいいさ」
その声音には、からかいではなく、どこか励ますようなやさしさが滲んでいた。
私は小さくうなずいた。胸の奥が少しだけ軽くなる。
「すみません。少しお話をいいですか?」
宗直様がすれ違いざまに、女房たちに声をかけた。
「どうされたの?」
「先日、霊獣が暴れた事件がありましたが、皆さんや霊獣はご無事でいらっしゃいますか?」
宗直様の言葉に、二人の女房が顔を見合わせた。女官は周囲を気にするように一歩近づくと、低く抑えた声で告げた。
「実は……女御様方の霊獣が、ここのところずっとおびえておりまして」
「……おびえて?」
私が聞き返すと、女官は小さく頷いた。
「そうなの。霊獣が暴れた夜──あのとき、香の匂いがしたの。ふわっと漂うような、でもどこか甘くて。あまり嗅いだことのないものだったわ」
「香、ですか」
その言葉に心が引っかかった。
香か。目に見えない薫りは、氣や術に混じって使うにはうってつけの手段かもしれない。女房は慎重に言葉を選びながらも、確信を持っているようだった。
「はい。あの香を境に、霊獣の様子が一変したのです。落ち着きがなくなって、まるで何かを怖がっているように……。気のせいではないと思います」
私は女房の言葉を深く胸に刻んだ。もしかすると、事件の手がかりになるかもしれない。
白虎の氣が、背中で静かに揺れた。もしかして霊獣の本能が何かを覚えている? もしそうならそれを無駄にはしたくない。
「ありがとうございます。霊獣頭にお伝えします」
自然と声に力がこもっていた。女房たちはほっとしたようにうなずいて、静かにその場を離れていった。
さらに歩を進めた、そのときだった。廊下の奥、宗直様に教えてもらった登花殿から、ふわりと現れた姿に私は足を止めた。
朝の光を背に受け、まるで淡い光を身にまとっているかのような存在感。その人物は、登花殿の前に立っていた。
……燁子だわ。宮中で初めて見た。いつも宵家の屋敷だったから。
つややかな黒髪が、肩先でやさしく揺れている。纏っているのはやわらかな朱色の美しい唐衣。光沢を含んだ絹が、動くたびに空気を撫でるようにひるがえり、彼女の輪郭をより儚く、美しく見せていた。
燁子は登花殿から出てきた女房たちに囲まれて、にこにこと笑顔を向けられている。
「浮橋の君が来てくださったおかげで、女御様も霊獣もすっかりお元気に……」
「ありがとうございます、浮橋の君」
声をかけられるたびに、燁子はふんわりと微笑んだ。やさしく余裕に満ちた笑顔で。その姿はまるで、屏風絵の中から抜け出した姫君のようで。私はまばたきも忘れて見つめていた。隣にいた宗直様も、ぽかんと口を開けたまま見とれていた。
「……本当に、立派な方だな。まさに“浮橋の君”にふさわしい」
その呟きが胸の奥で小さく刺さった。わけもなく肩の辺りがきゅっと強ばる。
その時、女房の一人が声を上げた。
「宵家の屋敷を、霊獣が襲って大変だったと聞きました」
その言葉に燁子の表情がわずかに曇った。
「屋敷の皆は、なんとか無事だったのですけれど……」
彼女は言葉を切ってから少しだけ俯いた。
「お姉さまが……霊獣に襲われて、行方不明になってしまって……」
その大きな瞳に、涙がにじむ。
「まあ……おいたわしい……」
「なんてこと……」
女房たちが口々に同情の声を重ねる。その中心で、燁子は悲しみをたたえたまま、じっと立っていた。何も飾らず、ただ悲しみを受け止める姿は、見る者の心を自然と打つのだろう。
“お姉さま”──それは、私のこと。ここにいるのに、いないふりをしなければならない。息を吸うのさえ、どこか苦しかった。
「あらあら、登花殿の女房方じゃないの」
声がした方向を見ると、廊下の向こうに女房の一団がいた。
「まあ。弘徽殿の女房たちだわ」
登花殿の女房のひとりが忌々しそうに口にした。
まるで誰もが偶然を装っているのに、互いにその“偶然”を待ち構えていたような──そんな空気。
「……弘徽殿女御様は東宮のご母堂だ。この後宮で最も大きな力を持つ女御様だ」
隣にいる宗直様がそっと教えてくれる。
弘徽殿の女房たちは髪ひと筋の乱れもなく、表情の端々まで研ぎ澄まされていた。
「霊獣が襲ったのは、内裏と宵家だけだったと聞きましたが」
先に口を開いたのは、弘徽殿の女房のひとりだった。やわらかな物腰を装いながら、その声音には冷たく細い刃が仕込まれている。彼女の視線は、まっすぐに燁子を射抜いていた。
「まさか、浮橋の君のお屋敷を狙うなんて……妙ですね」
その一言に、登花殿の女房が眉を跳ね上げた。
「なっ……! まさか浮橋の君が、霊獣を操ったとでも!?」
声がひときわ高く響くと、廊下の空気がすっと張り詰めた。衣擦れの音ひとつで、空気が裂けそうなくらいに。
燁子は何も言わなかった。ただ、ゆっくりと視線を弘徽殿の女房に向ける。そのまなざしに揺らぎはなく、けれど敵意もない。静かな水面のような眼差しに、女房のほうがわずかに視線を逸らした。
「まあ、でも……霊獣が暴走したのは……行方不明になった“誰か”のせいでは?」
ぽつりと落とされた言葉は、登花殿の側にいた若い女房からだった。言ってしまってからハッとしたように口元を手でおさえる。
私の背筋に、ぞくりと冷たいものが走った。
“誰か”──それは、きっと私のことだ。
視界がゆらいだ気がした。白虎が、胸の奥で氣をざわつかせるのを感じる。けれど、だめ。今は絶対に出てきてはだめ。
白虎……お願い、静かに。
心の中でそっと呼びかけると、氣の波がゆっくりとおさまっていった。
足元を見つめたまま、私は唇をきゅっと噛んだ。言いたいことが、喉の奥につかえて出てこない。言ってはいけない。私の名も、真実も。
ただの「鈴太」として、この場に立っているしかない。それが今の役目。でも、言葉を発しなかったその沈黙が、私自身の存在を否定するようで、胸の奥がじくじくと痛んだ。
ひとこと。たったひとこと、真実を言えたなら。けれど、今それをすれば、すべてが崩れる。私は息を小さく吐いた。震える氣を、胸の奥に押し込めて──目を伏せたまま、嵐の通り過ぎるのを待った。
「お姉様は、そんなことしないわ!」
その言葉に周囲のざわめきが止まった。
燁子はまっすぐ前を見据えていた。大きな瞳に涙が滲んでいる。光を宿した涙が白い頬をつたってこぼれ落ちた。一幅の絵のようで美しかった。
「失礼いたしました、浮橋の君」
弘徽殿の女房が頭を下げた。だが燁子は、それを追い払うように首を振り、震える声で続けた。
「でも、でも……本当にそうだったら……わたくし……」
言葉の先が、細くちぎれそうになりながらも、涙とともに落ちてゆく。
「まあ……お気の毒に……」
「こんなに浮橋の君を悲しませるなんて。宵家のお荷物とまで言われていた姫のくせに」
「本当に行方不明なのかしら。霊獣に襲われたって、そんな大げさな……」
「卑しい姫と噂の、ね?」
「そうそう、どこかの屋敷で物乞いでもしてるんじゃないかしら」
その矛先が、ゆっくりと見えない刃のようにこちらに向けられてゆく。
“鈴太”であるはずの私に──“鈴音”としての、私に。
足元からじわじわと凍りつくような感覚。背筋をつたう冷や汗。誰も触れていないのに、胸の奥が、きゅっと縮こまってゆく。
なに、これ──
燁子の涙は本物に見える。揺らめく睫毛。やわらかな声音。たおやかな立ち居振る舞い。守りたくなる人。誰もが、そう思うだろう。
だけど……これは、一体、なんだろう。
私の心の奥がすっと冷えていく。
……私じゃないのに。
思わず、喉の奥でそうつぶやきかけていた。だけど、声にはならなかった。言ってしまえば、すべてが崩れる。この中の誰かにでも気づかれたら、終わりだ。
白虎の氣がわずかに波打つのを感じた。私は奥歯を噛みしめる。
だめ。絶対に、ばれてはならない。
たとえこの違和感が、私を飲み込むほど大きくなっても。たとえ胸が軋むほど痛くても。
私は、鈴太。浮橋の君の「姉」などでは、決して、ない。
「……何をしている」
その場の空気がすうっと冷えた。女房たちの刺々しい声が交差する中で、廊下に凛とした足音が響きはじめた。
「もう一度言う。何をしている」
その声は低く、静かでありながら、空気を一気に裂く鋭さを持っていた。
ぱたり、と。全員の視線がその方向に向かう。登花殿の女房も、弘徽殿の女房も、そして燁子も。息を詰める音が、耳の奥で重なった。
一歩、また一歩と、無駄のない動きで歩み寄ってくるその姿は、ただそこにいるだけで空気を一変させる。威厳と静けさをまとった存在。
「二の宮様!」
その瞬間、燁子がぱっと振り返った。
さっきまで涙に濡れていたはずのその顔は、まるで別人のように明るく輝いていた。張りのある声。嬉しさを隠そうともしない瞳。高鳴る想いが、全身からこぼれ出ている。
私は、不意にその横顔に目を奪われた。
その目はまっすぐに、まるで何もかもを託すように、宮様だけを見ていた。隠しもせず、揺れもせず、ただ一心に。
あの子……宮様に……。
その想いは作られたものではない。心からのものだと、ひと目でわかってしまった。胸の奥が、ひとつ波打つ。それは悲しみでも怒りでもない。けれど、心の深いところで、何かが軋むような音がした。
燁子がふたたび涙をにじませたまま、震える声で言う。
「お姉さまがいなくなって……私……とても心を痛めているんです……」
彼女の瞳が潤み、まぶたの縁が揺れた。誰もが、胸を打たれるであろうその姿。けれど、宮様はほんの一瞬だけ燁子に視線を向けると、あくまで淡々と、ただ一言だけ返した。
「そうか」
それだけだった。
え……と、私は思った。きっと、私だけではなかったはずだ。燁子の顔が、一瞬だけ動きを止めた。まるで糸が切れた人形のように。
けれど、その一瞬の空白は誰にも悟らせることなく、すぐにいつもの笑顔に差し替えられた。花のようにやわらかく、美しく。誰もが安心し守りたくなる、あの“浮橋の君”の笑顔に。
私の胸の奥にもう一度、ざわりと波が立った。それが何なのか、言葉にはまだできなかったけれど、確かにそこに不協和音があった。
そのとき、隣にいた宗直様が、ふうっと息を吐いた。
「……昔からさ。浮橋の君は、ずっとあの方に憧れているんだよな……」
ぽつりと落ちた声に、私はそっと横を向いた。
宗直様の横顔はどこか遠くを見ていた。その瞳に映っていたのは今この場ではない、もっと昔の情景なのかもしれない。その頬には笑みも怒りもなかったけれど、微かに滲んだ翳りが、胸に引っかかった。
宗直様は、もしかして。
私の胸の奥に確信のような感情が芽吹いていた。あの目はただの敬慕ではない。もっと深い感情の色を秘めている気がする。
「二人とも何をしておる。こちらへ来い。女御様を待たせるわけにはいかない」
宮様が私たちを見て、その声が空気をすっと引き締めた。振り返らず、静かに歩き出すその背中。
「はいっ」
我知らず、声が出た。それに続いて、宗直様も軽くうなずいて歩き出す。
「二の宮様!」
燁子の声が後ろから響いた。名を呼ぶその声音には揺れる情がこもっていた。
けれど、宮様の足は止まらなかった。まっすぐに弘徽殿の方へ。その背に一片の迷いもない。
その背を見送る登花殿の女房たちは、唇を噛みしめて黙ったまま。一方で、弘徽殿の女房たちは、勝ち誇ったように鼻先で笑った。女たちの戦場はこんなふうに、言葉よりも表情で火花を散らすのだと私は初めて知った。
歩き出しかけたとき、何気なく振り返ってしまった。
そこにいた燁子の横顔は、微笑んでいた。けれどその笑みに、さっきまでの透明さはもうなかった。どこか歪んで、張りつけたような微笑み。唇は上がっているのに、目だけが笑っていない。
燁子……? 私は初めて、彼女の“内側”を見た気がした。見えないはずの本音が、うっすらと面の下から透けて見える。その微かな隙間に、冷たい風が吹いたような気がして。
胸の奥が、きゅっと冷たくなる。私は振り払うように、背中を追いかけて弘徽殿へと歩を進めた。
◆◆ ◆
弘徽殿へとたどり着いた瞬間、胸の奥がふわりと軽くなった。
静かだった。風も音も、すべてがどこか遠くに置き去りにされたような、凛とした静けさ。陽の光も影もどこか上品におさまっている。
私は立ち止まり、そっと息を吸い込んだ。ほんのりと青草のような香りが鼻先をくすぐる。心がふっとほどけるような、そんな感覚。
あれ、霊獣の氣が漂っている。どこから?
氣を探れば、弘徽殿女御様の守り霊獣・白鹿にたどり着く。初めて感じたその氣配が、御殿全体をゆるやかに包んでいる。
柔らかいけれど、芯の通った力強さ。白虎の鋭く純粋な氣とは違う、深くて穏やかな波のような氣。まるで澄んだ湖の底に身を沈めたような、静謐で安心感のある空気だった。
すると、御簾の奥からやわらかな声が響いた。
「浮橋の君とのやり取り、聞こえてきましたよ。相変わらずですね、宮」
現れたのは、弘徽殿女御様だった。御簾越しから感じる華やかさも気品のある気配。言葉のひとつひとつが、丁寧でありながらも、相手の核心をさらりと突くような鋭さを帯びているのは、さすが後宮一の女御と言ったところか。
「女御様。ご紹介いたします」
宮様が一歩前へ出て、私と宗直様に一瞥を与える。その仕草に導かれ、私は慌てて前に出て、深く頭を下げた。
「清原宗直です。鈴太と共に巡回に入っております」
宗直様の声はいつもより少し張っていた。けれど、笑顔は変わらない。
「……鈴太と申します。どうぞ、よろしくお願い申し上げます」
声が少し上ずる。手のひらがじっとりと汗ばんでいた。
「おふたりとも、ご苦労さまです。こうして霊獣寮の若き力が後宮に入るのは、頼もしいことですわ」
その言葉に私は胸が熱くなった。歓迎されている。ちゃんと見てくださっている。そんな安心感が、言葉の端々から伝わってきた。
「事件後、何か変化はありましたか?」
宮様が落ち着いた声で問うと、女御様はふっと視線を落とした。
「……実は、三条という若い女房が心を病みまして。今は実家に戻しておりますの」
その名を聞いた瞬間、隣の宗直様がわずかに息を呑む気配を見せた。
「その子が事件の夜、“ある香”を焚いたそうです。香の名までは覚えていなかったようですが、焚いた直後に白鹿が強く怯え……気が荒れてしまったのです」
「香、ですか」
その一言に、私の中の感覚が鋭く立ち上がった。まるで光が差し込んだように、記憶のどこかが照らされる。
そうだわ。あの話を聞かせてくれた女房が言っていた。あの夜、どこか甘く、ふわっとした、嗅いだことのない香がしたと。
思わず手を握り締める。今の女御様の言葉が、あの証言とぴたりと重なる。
女御様がふっと視線を落とし、少し困ったように口をひらかれた。
「三条は、“香を焚いたあと、何かが壊れたような気がした”と申しておりましたの。でも香なんて、誰でも日常的に焚いているものでしょう? 彼女がそのとき焚いたからといって、あの騒動が彼女のせいだとは……私は、そうは思えないのです」
その声には女御様なりの葛藤と、女房への情がにじんでいた。
「そうですね。三条自身の思い違いという可能性もあります」
宮様が静かに言葉を継がれた。
「ですが、その香が“潤氣擾乱香”であったなら話は別です」
一瞬、場の空気が揺れたような気がした。女御様が小首を傾げられた。
「潤氣擾乱香……? 何ですか、それは」
「霊獣の潤氣の共鳴を狂わせ、異常を引き起こすものです。表向きは“癒し香”と称されておりますが、実際には蛟のような変質霊獣の氣を微かに含んでおり……霊獣の氣の流れを乱す作用があります」
「……そんな香が、存在するのですね。困ったわ」
女御様は息を詰め、心配を声に滲ませた。
「この霊獣騒乱事件は霊獣寮の管轄になりました。原因を必ず突き止めます」
宮様の言葉に、女御様は静かに頷かれた。
「お願いします……。三条は素直で真面目な子だったのです。あの夜を境に気の毒なことです」
「まずは事件の解決からです」
「そうですわね」
女御様のまなざしがふと、私の方へと向けられた。
「あなた……霊獣の氣にとても敏感なのですね?」
突然話しかけられて、思わず息が詰まりそうになる。私は戸惑いながらも、そっと小さく頷いていた。
「びっくりさせてしまったかしら。白鹿があなたに興味を持っているようなの。いつでもいらっしゃい」
胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じた。張りつめていた心のどこかが、そっとほどけるような感覚。私は小さく深呼吸し、そっとその空気を、胸いっぱいに吸い込んだ。白鹿の氣配と重なって、心がほのかに温まる。
そのぬくもりを胸にそっと包みながら、私は女御様に頭を下げた。
「ありがとうございます。……また、お邪魔いたします」
御簾の内側で女御様がやわらかくうなずかれた。
その言葉の後に、私と宗直様、そして宮様は、静かに弘徽殿をあとにした。
御殿を出た瞬間、外気が肌に触れた。内の氣と外の氣が交じる、そのわずかな変化に、私はふっと顔を上げる。白鹿の氣を含んだ空気が、背後に静かに揺れている。
そして、宮様がふと足を緩められた。
「三条の実家を調べさせる。……香の残り香があれば、確証が得られるだろう」
その言葉に、宗直様が即座に反応した。
「よし、俺が行きましょうか!」
勢いよく手を挙げた宗直様の声が、静けさに弾んで響く。けれど、宮様は涼やかに首を振られた。
「いや。鳳凰に偵察させる」
「……ですよねぇ」
宗直様が肩を落とす。その姿がなんとも可笑しくて、私は思わず唇を引き結んだ。笑いそうになったのをなんとか飲み込む。
ほんのり草の香が混じるこの空気の中で、私はふと口をひらいた。
「あの……霊獣たちが、あの香をすごく嫌がっていました。あれはやはり何か混ざっていたような、そういう感じがして……」
自分でも、なぜこんなふうに言葉が出たのか分からなかった。けれど、胸の奥から自然にこぼれてきた感覚だった。
そのとき、宮様がぴたりと立ち止まった。鋭くも静かなまなざしで、私を見つめる。
「宗直、そなたにはこれから三日に一度、後宮の巡回を頼む。鈴太を補佐につけよう」
「わ、私ですか?」
「ああ」
「了解しました! お任せください」
宗直様はまっすぐ背を伸ばし、晴れやかに胸を叩いた。
その声が頼もしく響いたあと、宮様は続ける。
「殿上童がいれば、女房たちも警戒心を解くだろう。彼女らから、事件につながる証言や痕跡が見つかれば……必ず報告してくれ」
「承知しました!」
私は黙って深くうなずいた。胸の奥にじわりと熱が灯る。
私、ここで役に立てるのかもしれない。
霊獣が教えてくれる氣の揺らぎ。誰かの言葉の奥にある、ほんとうの感情。気づけるのなら、見つけられるのなら――私はきっと、役に立てる。
足元がしっかりと地についていた。
その感覚を胸に、私はまた一つ、新しい役目を背負う覚悟を決めた。