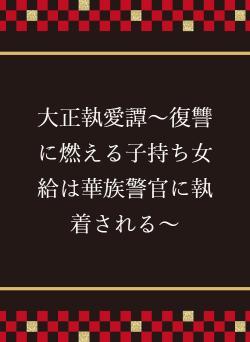ああ、いい香り。
藤原宵家の屋敷にある東の対は、朝の光をすり抜けた風が静かにゆれる、澄んだ空気に包まれていた。御簾の隙間から射し込む光が、白木の床に淡く差し、花籠の上にかけられた衣の桃色をやわらかく照らしていた。
その香りを深く吸い込む。鼻先をくすぐったのは、咲き誇る華やかな花のような薫り。ふんわりとしたやさしさ。やわらかく甘いその薫りは、どこか気高くて、それでいて胸の奥にそっと触れてくるような、そんなぬくもりを帯びていた。目の前にいる妹姫の微笑みに似ている、そんな気がした。
香りのもとは、花籠の上に丁寧に広げられた桃色の衣だった。香を焚きしめておいたそれが、布地にしみこみ薫りを帯びている。東の対の空気に溶け込みながら、ゆらゆらと揺れるように、室内いっぱいにその香りが広がってゆく。
「お姉さま。これは、とても良い香りね」
振り返った燁子が、無邪気な笑みを浮かべて言った。
「燁子、気に入ってくれた?」
「はい。もちろん」
「良かった。燁子に似合う香をまた作ったの。咲き誇る華やかな花のような香りの中に、優しい甘さと気高さを表現したの。それでね……」
「ふふ」
「あ、ごめん。私ばかりがしゃべって」
「わたくしはお姉さまのお話が好きよ。お姉さまは香がお上手ね」
瞳の形をふわりとゆるめた燁子は、どこまでも儚げで可憐だった。けれどその笑みは、夜空に浮かぶ綺羅星のように、どこか人を惹きつけてやまない輝きを放っている。燁子の美しさは、都で一、二を争うと言われていた。藤原宵家の自慢の妹姫だ。
「姫様によくお似合いの香です。鈴音も……まあ、良い働きをしましたね」
そばに控えていた燁子の乳母の松乃さんが、淡々と、けれど針のように冷たい声音でそう言った。言葉の端に棘があることは、もう何度も経験している。けれど、それでも心の奥にちくりとした痛みが走った。慣れているはずなのに。
「だめよ、松乃。そんな言い方。お姉さまは腹違いでも、わたくしのお姉さまなのだから」
燁子がきゅっと眉を寄せて、まるで私を庇うように松乃さんを窘めた。
「なんとお優しいのでしょう。さすが藤原宵家の北の方さまの姫。あなたも感謝しなければなりませんよ」
松乃さんは私に鋭い眼差しを投げつけたかと思うと、ふっと目を逸らす。
「もう、松乃。口を慎んで。お姉さまは腹違いだけれど、わたくしのお姉さまよ」
振り返った燁子は、やさしく笑いながら私を見つめてくる。その微笑みに胸の奥がじんわりとあたたかくなる。燁子の優しさに救われる。
「ありがとう、燁子。さあ、身支度をしてしまいましょう」
「それは、この松乃が――」
「嫌よ。お姉さまにしてもらいたいの」
燁子はふわりと身を翻し、私の目の前で背中を向けた。肩のあたりまで伸びた黒髪がさらりと揺れ、朝の光を受けて艶やかにきらめいた。
私は、燁子の髪に櫛を通しながら、静かに声をかけた。
「今日は……登花殿女御様のところへ?」
鏡越しに目が合うと、燁子はふふっと小さく笑った。
「ええ。女御様方の霊獣が、少し疲れているようだから。霊獣の蛟と一緒に潤氣の調整に伺うの」
「さすがは人と霊獣をつなぐ浮橋の君。姫様は女御様方と引けを取りませんわ」
「松乃ったら」
後ろに控えていた松乃さんの声に、得意げな響きが混ざる。
「浮橋の君である燁子様が入ってくだされば、女御様方も安心なさいますね」
別の女房が続けると、燁子はこともなげに、「そうだといいのだけれど」と答えた。その頬にはうっすらと紅が差していた。
――浮橋の君。人と霊獣をつなぐ、特別な存在。
私は何も言わずに、そっと手元の櫛に目を落とした。才のある妹姫。それと比べて、私は。
ふいに、空気の底が揺れるような感覚が走った。部屋の片隅。朝の光も届かぬ影のなかに、ひとつ、うごめく気配。
「……あら」
燁子が可憐な声と同時に現れたのは、闇に浮かび上がるような深い黒。滑らかな鱗が燭台の火を淡く映し、冷たい光を帯びてきらめく。長い尾が床をなぞるように揺れ、真紅の瞳がじっとこちらを見つめていた。
燁子の霊獣・蛟だ。
氷を落とされたような感触が、私の全身にひやりと広がる。
「まあ……なんと神々しい……」
女房のひとりが、思わず息を飲んで呟いた。
「夜の王のようですわ……姫様のご威光をそのまま映したような」
「ほんとうに……これほどの霊獣を従えておられるなんて」
松乃さんがにこやかに頷きながら、言葉を継いだ。
「やはり姫様には蛟のような高貴な霊獣がよく似合いますこと。どこかの方のように、霊獣の一体もそばにいないお姫様とは、格の違いがございますね」
“どこかの方”。それが私を指しているのだと、誰もが知っていた。
言葉に刺がざくざくとさ刺さる。私はただ、微笑を浮かべることしかできなかった。この屋敷で声を上げることが、どれほど愚かで危ういことか、もう知ってしまっているから。
「やめて、松乃」
燁子の声が、澄んだ鈴のように部屋に響いた。
「お姉さまは、霊獣よりももっと難しい香を扱えるのよ。ね? この間の香なんて、女御様にもお褒めいただいたくらい」
言いながら、彼女は鏡越しに私へ笑みを向ける。まるで、この空気の濁りをすべて拭い去るかのようなやわらかい笑顔。
燁子の声が部屋の空気をやわらかく撫でた瞬間、女房たちはそろって黙り込み、視線をそらした。けれど、苦い空気はあっという間に拭い去られた。
「やっぱり姫様はお優しいわぁ」
ほうと小さく漏れた感嘆の声に、他の女房たちがこくりと頷く。
「いつもわたしたちの話にも耳を傾けてくださるし」
「叱るときでさえ、笑顔を絶やされないのですもの」
「きっと東宮様も見初めていらっしゃるはずよ。うちの姫様は素敵ですもの」
この部屋に控えている女房たちがさえずる。
燁子は鏡越しにその声を聞きながら、ほんの少しだけ頬を染めた。
「そんなふうに言われると、くすぐったいわ。でもね……」
燁子が目を伏せていた。襟元を整える手が一瞬だけ止まり、光を避けるように視線が床へ落ちる。
「燁子、どうしたの?」
「あのね、お姉さま。実はわたくしには、宮中にお慕いしている方がいるの」
「え、そうなの?」
「でも……お体のこともあるし、なかなかお会いできないの」
その言葉に宿る柔らかな痛みに、私は小さく息を飲んだ。
“お体”――そう告げるその響きが、私の少ない知識の中で、ある人の姿を静かに呼び起こした。都で病弱と噂されるやんごとなき方。
燁子は何気ないそぶりで立ち上がり、女房の差し出した扇を受け取った。燁子が纏ったふわりと広がる桃色の衣が、朝の光に透けて、どこか夢の中のように揺れて見えた。
「でもね、お姉さま。今日こそは宮中でお会いできるかもしれないわ。これも浮橋というお役目をいただいているからだわ」
目じりを下げ柔らかに笑った燁子は可憐だ。この女神のこどく微笑みに心奪われない男性はいるのだろうか。
「そろそろ参りましょうか。姫様」
やがて支度がすべて整い、松乃さんが声をかける。燁子はふっと振り返った。
「お姉さま。お願いしていた香……作ってくれた?」
「もちろん」
私は袂からそっと香袋を取り出し、彼女の手のひらにそっとのせた。
淡い桜と丁子、そして藤の花をほんのひとしずく。燁子の香にふさわしい調合を、何度も試しながら心を込めてつくったものだった。
「ありがとう、お姉さま。お姉さまの香は、ほんとうに素敵。宮中でも評判なのよ。わたくし、鼻が高いの」
「さあ、姫様。お早く」
「はあい」
「燁子、いってらっしゃい」
燁子は一つ頷くと、女房によって巻き上げられた御簾の向こうへと進んでいく。その背を見送りながら、私はそっと頭を下げた。
顔を上げたとき、東の対の留守を任されている松乃さんと目が合った。
その目は冷えた石のように冷たく、感情が見えない。すぐに逸らされたその視線が、なぜか鋭く胸の奥に突き刺さった。さっきまでの華やかな空気が夢だったかのように、しんと冷えていく。
私は小さく息をついた。
――いつものこと。
これから私は、側室だった母とともに過ごしていた西の対へ戻るだけ。誰にも気づかれぬように立ち去る。何度も繰り返してきた役目の終わり。
私はそっと別の御簾を上げて東の対を後にしようとした。
「……お待ちなさいな」
まるで空気ごと凍らせるような声音。背筋がすっと冷えて、足が止まった。
振り返らずとも、誰かはわかっている。松乃さんだ。
「あなた、何を勘違いしているの。姫様に向かって、あんなに馴れ馴れしく……」
その声は乾いていて低かった。一言毎にこぼれ落ちるような棘があった。
「何度言えばわかるの? 姫様のお名前を呼ぶなんて、よくもまあ口にできたものね」
私はどう答えていいかわからず、喉の奥がきゅっとつまる。
ちゃんと、何か言わなくちゃ。うまく、傷つけない言い方を。怒らせないように。
けれど、考えようとすればするほど、頭の中にぐるぐる、ぐるぐると渦を巻き、言葉が霧のなかに沈んでいく。
その刹那。バシン――と音がして、頬に火が走った。
痛みのあとから、熱がじんじんと広がっていく。目の端がじわりと濡れた気がしたけれど、瞬きもできなかった。
「ぐずね。すぐに答えられないなんて。あなたは姫様とは違うのよ」
松乃さんは静かに言った。けれど、その声が鋭く深く突き刺さった。
「正室の娘でもない。卑しい身分の母親から生まれた、側室腹の子。姫でもなんでもないの」
言葉の刃が胸の奥でぽたりと落ちる。そこから静かに波紋が広がる。
私は言い返したかった。
――違う、と。
けれど、口が動かなかった。声にならなかった。
「姫様に対等な口をきくなんて、身のほどを弁えなさいな。今日の夕餉は抜きです。口の利き方を少しは学びなさい」
ぴしゃりと張りつけるような声が、耳に冷たく響く。
「あなたはいつまでこの宵家に居座るつもり? 姫様のご慈悲で、西の対に住まわせてもらっているだけでも、ありがたく思いなさい」
その言葉が、背中に、胸に、じわじわと沈んでくる。
もう何年も同じ言葉を聞いてきた。言い返すたびに、さらに深く抉られる。だから私は、いつしか反論しないことを選ぶようになってしまった。
どれが真実で、どれが呪いなのか。それすら、もうわからない。
松乃さんが鼻を鳴らして踵を返す。その足音が遠ざかっていって、やっと私は小さく息を吐いた。
足が鉛のように重い。ここにしゃがみ込んでしまいたい。
でも、それだけはしてはいけない。
誰もいないはずの回廊なのに、どこかに誰かの目が潜んでいるような気がして、私は背筋を正して、自分の住処へと戻る。歩き出した足音が、キイキイと寂しく床板が鳴った。
――お母さまがご健在だった頃は、まだ幸せだったのに。
不意に、母の手のぬくもりが脳裏に蘇った。
繕い物をする手はいつも静かでやさしくて、私はただその隣にいるだけで安心できた。もし、まだそばにいてくれたなら……私はもう少しだけ、強くなれていたのだろうか。
冷たい風が裾をかすめる。
敷石のうえに落ちた枯葉が、からり、からりと風で転がっていった。
西の対へ続くこの回廊は、同じ屋敷の中にあるのに、すれ違う人の気配もなく寂しげな静けさを纏い、どこか別の世界のように感じられる。
けれども、近づくたびに、身体の芯から少しずつもやが抜けていくようだった。
ようやくたどり着いた西の対は、あちらこちらに苔が張りつき、簀子縁の隙間からは草が顔を出していた。
誰の目も手も届かないこの場所は、どこかひっそりとしていて、でもそれが私にはちょうどよかった。
庭に出て、簀子にそっと腰を下ろす。太陽は少しずつ高くなり、けれど光はどこか翳り始めていた。
目の前に広がる庭は荒れていて、木々の枝はのび放題、草花も思うままに伸びていた。
でも、私はこの無造作な景色が嫌いじゃない。誰にも形を整えられていないからこそ、ここではすべてが“あるがまま”でいられる気がするのだ。
ふいに、足元にぬくもりが忍び寄ってきた。
「あら、また来たの?」
薄桃色の毛並みの兎の霊獣が、するりと簀子の隙間から這い上がってきた。
尖った耳がぴくりと動き、ふわふわの尾がくるくると踊る。その前足がそっと私の膝に触れた。
後ろからは、まだら模様の猫の霊獣が二匹、遠慮がちに顔を覗かせる。この子たちは何度も来ている常連だ。名もない小さな霊獣たち。
私はゆっくりと微笑んで、掌をそっと差し出した。
「おいで。今日もおなかが空いているのね」
指先に意識を集めると、掌から潤氣がじんわりとにじみ出す。霊獣・人・空間に満ちる“氣”の源である潤氣。
霊獣の額にそっと触れると、ほわりとした温かさが流れていった。すると、彼らは目を細め、小さな声で喉を鳴らした。
どうしてだか、昔から私はこうして霊獣たちに囲まれていた。眠れぬ夜も涙の朝も、彼らだけは変わらずそばにいてくれた。
私が“姫”かどうかなんて、きっと関係ない。
ただ掌から潤氣を注いで、そっと癒してあげるだけで、彼らはまっすぐに応えてくれる。
「あなたたちがいてくれて、良かった……」
その言葉は、誰に聞かせるでもなく、風にまぎれてどこかへ溶けていった。
霊獣たちが身を寄せ、私はそっと目を閉じた。陽だまりの温度が身体に染み入り、胸の奥の重たさが、ふっとほどけてゆく。
西の対には、何もない。でも、ここには、私の“心”があった。
◆◆ ◆
夜の帳がすっかり下りて、西の対は静寂に包まれていた。けれど、風の音が妙にざわついている。耳の奥に残るそのざわめきは、まるで地の底から湧き上がる声のようだった。どこか遠くで、何かが騒ぎはじめている。そんな気配が、じりじりと胸を締めつける。
私はひとつ寝返りを打った。けれど、眠気はとうにどこかへ消えていた。まるで、目に見えない何かが私を呼んでいる――そんな感覚。
息をひそめていた空気のなかで、私はそっと身を起こした。足音を忍ばせ、妻戸を開けて簀子へ出る。
夜気が肌に触れた瞬間、ひやりとした冷たさに肩が跳ねた。
空には雲一つなく、月が冴え冴えと光を投げかけている。あたりはひっそりとしているはずなのに、木々の葉がざわめき、風が騒いでいた。
刹那。
ズシンッ。
大地の奥から這い上がってきたような、重たい音が庭の奥から響いた。庭の闇が月明かりを呑んで膨らんだ。風が逆巻き、松の影が地を這う。
「……なに……?」
思わず声が漏れた。体の芯が凍る。足がすくんで動かない。それでも、私は目を逸らすことができなかった。
その闇の中心から――白いものが、にじみ出る。白銀の霊獣。
白いはずの毛並みはどす黒く濁り、尾の先は墨のように溶けて滴っていた。牙は赤く、瞳には光がなく、ただ紅い炎だけが揺らめいている。息を吐くたび、鼻の奥を刺す甘い匂いがまとわりつき、胸がざわついた。
これは本当に霊獣……?
「……っ」
地が沈むほどの踏み込みののち、巨体が跳ねた。
風圧が頬を打つ。爪が眼前に閃き、私は反射的に身をひねる。袖が裂け、布が宙で散った。足裏が空を踏み、簀子の縁から滑り落ちる。膝に衝撃を感じ、息が詰まる。
怖い。逃げたい。なのに。
――助けて。
耳で捉えてはいない、胸のもっと奥、腹の底で震える聲が聞こえた。
何、今の。
私は痛みをこらて、震える膝を叱咤する。唾を飲み込み、ただ一歩、前へ。
白虎が喉を鳴らし、再び飛んだ。赤い牙が月を裂く。
私は両手を広げ、低く息を吸った。
「――待って」
自分でも驚くほど、声は静かだった。
次の瞬間、掌がひらく。内側から白い潤氣が滲み出し、ぬくもりが指先に集まる。
触れた途端、氷と針が一度に走ったような痛みが腕を駆け上がった。思わず奥歯を噛む。視界が揺れる。それでも、手を退けない。
「大丈夫……戻ってきて。あなたは、霊獣よ」
爪が地を抉り、鼻先が私の胸元すれすれで止まる。熱い吐息と、荒い鼓動。
どうしてそんな姿になってしまったのか。
私は身を屈め、額――眉間の硬い骨にそっと掌を当てた。もう片方の手で顎を支える。喉元で震える唸りが、掌の骨を震わせる。
潤氣を重ねるたび、腕の内側が痺れていく。黒い氣が、触れたところからじりじりと逆流してくるみたいだ。胸の奥が締めつけられ、目の端が滲む。それでも流す。私のぬくもりを、少しずつ、少しずつ。
「痛いよね……その痛み、私に分けて」
白虎の瞳の紅がわずかに揺らいだ。
紅蓮の底に、針の先ほどの青が灯る。私はそこへ息を合わせる。掌の中心で、柔らかな白が波紋になって広がった。
黒ずんだ毛並みが、端から解けていく。
墨色の尾が白銀を取り戻し、赤く濁った牙の輝きが静まる。喉の唸りが低く、苦悶から嘆息へと変わる。私は膝をつき、その額にさらに深く手を押し当てた。
「もう、ひとりじゃない。帰ってきて」
頬にざらりとした鼻先が触れた。怯えた獣の、それでも甘えるみたいな、弱い押しつけ方。
大きな体がぐらりと揺れ、土の上に静かに伏す。肩が上下するたび、荒かった呼吸が少しずつ整い、紅い瞳の奥に残った青が夜を映した。
良かったぁ。はああと長く息を吐いた。
白虎は目を細め、鼻先を私の掌に寄せて、もう一度小さく安堵の音を洩らした。
震える膝に力が入らず、その場にへたり込みそうになった。
「……霊獣・白虎を、癒したのか」
夜気の中に澄んだ声が落ちた。
低く静かに響いたその声音は、風のざわめきよりも透きとおっていて、耳に届いた瞬間、胸の奥にまで染み込んだ。
「誰!?」
私ははっとして振り返った。
月明かりの下、庭の端にひとりの青年が立っていた。
黒曜石のような髪は夜風に揺れ、白い薄衣は光を透かして幽かにきらめく。その姿は人の世に在りながら、人ならぬ影をまとっているよう。
あまりに整いすぎた面差しは、温もりはなく冷ややかな静謐を湛えていた。見つめれば息を呑むより他なく、ただ存在するだけで闇さえ彼に従うようだった。
その肩には、金の尾をひるがえす霊獣・鳳凰が翼を畳んで寄り添っている。炎のように鮮烈な輝きを放ちながらも、青年の横顔に照らされているその光景は、不思議と凍りついた静けさの中にあった。
「潤氣を操ったのは、そなたか?」
その瞳が真っ直ぐに私を見据えた。
冷たさと鋭さと言葉にできない重みが、視線そのものに宿っているようで、私は思わず息をのんだ。
まるで、何もかも見透かしているような眼差し。
もしかして――病弱と言われている今上帝の二の宮・彰仁親王では。
噂に聞いたその姿とはあまりにも違っていた。か細いどころか、彼がそこに立つだけで、あたりの空気が凛と張り詰めていくようだった。
「……はい。あの……」
気づけば、言葉が口から零れていた。
「宵家の大姫だな」
「は、はい。鈴音と申します」
慌てて頭を下げたけれど、貴族の姫らしさのかけらもないのが恥ずかしい。
「宵家のお荷物やら、卑しい姫だの……宮中では、いろいろと聞いていたが」
「え……?」
思わず問い返そうとしたその瞬間、宮様は淡い月光のなかで静かに言った。
「どうやら噂とは違ったようだな」
その言葉の意味を私はすぐには掴めなかった。何かを返したかったのに、頭の中が白く霞んでしまって言葉が見つからない。
「癒してくれて助かった。私は今上帝の二の宮で、霊獣寮を預かる霊獣頭。この霊獣・白虎は妖獣になり、宮中で暴れていたのだ」
宮様の声は夜気を切るように低く響いた。
「……暴れていた? さっきのあの姿……」
思わず問い返すと、宮様の眼差しが私を射抜いた。
「強い氣が乱れると霊獣は歪む。己を見失い、悪しきものに堕ちる。妖獣となっていたのだ」
胸がひやりと凍りつく。白虎の鋭い牙や、狂った目の光が脳裏に蘇った。けれど今は……その白虎が静かにこちらを見ている。
「来い。そなたの力が、必要だ」
「……え? あの、どこに……!?」
「宮中だ。宮中で妖獣が暴れている」
戸惑うより早く、宮様の手が私の腕をとらえる。
その瞬間だった。
宮様の肩に収まっていた鳳凰の体が、白光を放ちながら膨らんでいく。翼がばたくたびに風が巻き起こり、庭の枝葉がざわめいた。小さな鳥のようだった姿は、瞬きの間に人の数倍の大きさに変わっていた。
「ひっ……!」
私は思わず息を呑み固まる。けれど、宮様に腕を引かれたまま鳳凰の背に乗せられた。
羽毛の感触は意外なほど柔らかく、けれど奥に熱い脈動が走っていて、座っただけで全身が震えた。
「……う、そ……これ、ほんとに……?」
思わず声が漏れる。足元の庭がみるみる遠ざかり、夜風が顔に痛いほど吹きつけてきた。
夜空を切り裂くように鳳凰が翔ける。
頬を叩く風は鋭く、衣の裾を容赦なくはためかせた。遠ざかる庭の闇の下、白銀の影がしなやかに駆けているのが見える。
白虎――。
吠えもせず、ただ真っ直ぐにこちらを追ってきていた。
土を蹴るたびに火花のような氣が散り、揺るがぬ脚取りはまるで大地そのものの意志のよう。置いていくことなど決して許さない、とその姿が訴えていた。
「……もしかして、一緒に来るつもりなの?」
その刹那、白虎の瞳が月光をはじいて煌めいた。
応えるように一層身を低くし、夜気を裂いて走り抜ける。その必死さが、風よりも強く私の胸に突き刺さった。ただその姿がすべてを伝えてくる。
私は鳳凰の背にしがみつきながら、小さく頷いた。
それだけで、白虎はまるで約束を交わしたかのように加速し、夜空を翔ける影に寄り添って走り続けた。
◆◆ ◆
金銀の星々が瞬く夜の帳を切り裂き、霊獣・鳳凰は宙を翔けていた。
眼下に広がるのは、黒々とした闇の海。その底に無数の青白い燐火がちらちらと揺れている。屋根に月が浮かび、松の影が長く伸び、白砂の庭が鈍く光を返す。そこは豪華絢爛な宮中であるはずだった。けれど、華麗さはどこにもなかった。
――きゃああああっ!
耳を劈く甲高い悲鳴。それから木の裂ける音、妖獣の咆哮。それらが夜風を震わせ、背筋をざわりと撫でていく。
私は優雅に翼を広げた大きな体躯の鳳凰の背に身を伏せ、必死に揺れに耐えながら、眼下に広がるその光景に目を逸らせないでいた。胸の奥が強張って呼吸が浅くなる。ぶるりと背筋が震えて、一瞬体がぐらりと傾いた。
「あ!」
その時、力強い腕が私の身体を支えた。触れると氷のように冷ややかなのに、揺るぎのない力のある宮様の腕。宮様の横顔は月光に照らされ、彫像めいた影を落としている。まるで人ではなく、夜の闇から切り出された存在のようで、ぞくりとするほど美しく冷たかった。
「――鳳凰」
耳の奥に響く艶のある低音が、夜気を震わせる。
刹那、鳳凰が羽ばたき、夜空に烈風が走った。眩い尾がひるがえり、白い矢のごとき潤氣が庭の中心へと撃ち込まれる。音もなく展開された結界が、地を這うように広がり、霊獣たちの狂乱をひととき封じ込めた。
その直後に鳳凰の翼が大きく翻り、月を遮る影となって急降下を始めた。夜気が渦を巻いて髪を乱し、熱気を帯びた風が頬を鋭く打つ。庭が迫るごとに、悲鳴と妖獣の咆哮が耳を裂き、何度も心臓が跳ねた。
「……っ!」
ドンッ、と強い衝撃とともに、鳳凰の爪が白砂を抉り地に降り立った。翼が風を巻き起こし、松の枝をざわめかせる。
大きな背が沈み、地面へと傾いた。支えるように差し伸べられた腕に導かれ、私は足を下ろす。柔らかな砂を踏む感覚がゆらりとして、まだ夢のようで現実感がなかった。
あたりを見回すと、地上の空気は空の上よりもはるかに濃く、荒れていた。湿りついた重く邪悪な潤氣が肌にまとわりつき、肌の奥まで刺すように入り込んでくる。
「女官たちが逃げ遅れている! 妖獣に喰われるぞ!」
遠くで武官の叫びが飛ぶ。
青白い燐火が宮中を覆い、女房たちが廊下の影にうずくまって、声を押し殺して泣いていた。
「どうして、こんなことに……それに、あれは……」
そのすぐ先で――妖獣たちが唸り声を上げてのたうっていた。狐も、鹿も、孔雀も、獅子も。赤く濁った瞳を見開き、理性を失ったように、濁った潤氣を吐き散らしながら。
この妖獣たちが、もともとは霊獣だったの? 本当に、あの子たちが……?
私は震える指先を胸元に押し当てれば、心臓を打ち付ける音が加速する。
その姿は私の知る霊獣ではなかった。瞳は血のように赤く濁り、氣は黒ずみ裂け、輪郭まで歪んでいる。
「まるで悪霊や妖のようだわ。これが妖獣」
その時、狐の妖獣と目があった気がした。次の瞬間、狐の妖獣がこちらに跳びかかってきた。
「――っ!」
思わず悲鳴をあげたその前に、白虎の咆哮が轟いた。
その影がすぐ傍らに滑り込む。銀の毛並みが月光を弾き、牙を剥き、爪で地を抉り、狐の体当たりを弾き飛ばす。火花のような氣が散った。
白虎は狐から目を離さず、私をかばうように低く喉を鳴らす。
「ありがとう、白虎」
ほんとうについてきたんだ。
胸が詰まる。襲い来るのを止めてくれたのだ――私を守るために。
「宵家の姫よ」
隣に立つ宮様が、低く言った。
「見ろ。これが――妖獣と成り果てた霊獣の暴走だ」
その言葉に振り向いたとき、宮様の瞳が夜の闇より深く、静かに光っていた。
「……鳳凰」
次の瞬間、鳳凰が高く舞い上がる。
その巨体が月光を覆い、尾がしなって夜空を裂く。
「静止の封」
白い矢のような潤氣が放たれ、庭の中央――暴れ狂う妖獣たちの周囲へと突き刺さった。
眩い光が地面を奔り、淡い紋を描き出す。
結界だ。きらり、と波紋のように揺れ、見えない壁が展開される。
狐が牙を剥いたまま硬直し、獅子が唸り声を喉に詰まらせる。
孔雀の羽ばたきも凍りついた。呻き声が重なり、結界の内側で空気が軋んだ。
「封じるだけでは足りぬ」
宮様が私を見据えた。鳳凰の炎の光を背に、その眼差しは鋭くも揺るぎなかった。
「癒せるのは……そなただ」
「わ、たし……?」
「このままでは皆やられてしまうぞ」
足が震える。怖い。けれど――聞こえる。
荒れた潤氣の奥から、小さな聲。
――痛い。
――たすけて。
「……大丈夫……大丈夫だから」
息を呑み、震える掌を差し出す。
白虎が前に立ちふさがり、牙をむき出して私を庇う。その背の陰で、私は狐にそっと触れた。尾の根元に掌を重ねる。
熱が流れ出す。
指先からじわりと潤氣を注ぎ込むたび、胸が焼けるように苦しい。
でも、狐の目の赤が少しずつ濁りを失っていくのが見えた。
「私の潤氣を分けるから。だから、もう苦しまないで」
狐が小さく鳴いた。
荒ぶっていた氣がほぐれ、目を閉じると、まるで深い眠りに落ちるようにその体を横たえた。
安堵する間もなく、今度は鹿が角を突き上げ、こちらへ突進してきた。
白虎が低く唸り、体をひねってその前に立ちはだかる。爪と角がぶつかり合い、火花のような氣が弾け飛んだ。
「……はぁ、はぁ……」
汗が滲み、膝が震える。それでも、私は鹿の額に手を添えた。
重い氣が流れ込んでくる。背中が鉛のように沈み込む。
でも、私の内から流れた潤氣に包まれた瞬間、鹿の震えがぴたりと止まった。濁った瞳が澄み、吐息が静かになっていく。
「次だ!」
再び宮様の声が鋭く響く。
視線の先で、獅子の妖獣が大地を抉るように足を踏み鳴らし、血走った瞳でこちらを睨み据えていた。牙の奥から漏れる唸りが、胸骨を震わせる。
「っ……!」
思わず後ずさりしかけたその瞬間、白虎が私を庇うように飛び出した。
獅子が吠え、巨体を揺らして突進してくる。白虎が横から躍りかかり、その鋭い爪で獅子の横腹を打った。鈍い衝撃音が響き、獅子の動きが一瞬だけ鈍る。
今だ!
私は震える足を前に出した。
荒い息を吐く獅子の胸に、掌をそっと重ねる。
熱い。獣の鼓動とともに、苦しみが直接流れ込んでくる。
「……もう、大丈夫……」
囁くように声をかけながら、潤氣を送り込む。濁った赤がじわじわとほどけ、金色の光が瞳に戻っていく。獅子は呻き声を残し、地に伏した。
「っ、はぁ……!」
息が切れる私の耳に、宮様の声が再び響いた。
「上からくるぞ! 孔雀だ!」
宮様の声が夜気を裂く。見上げれば、月を背にした巨大な影。
孔雀の妖獣が翼を広げ、刃のような羽を撒き散らしながら急降下してきた。光の反射で煌めいた羽先は、すべて鋭い凶器だった。
「鳳凰!」
宮様の呼び声に応え、背後で炎が爆ぜた。鳳凰が夜空へ舞い上がり、尾をひるがえす。燃えるような羽が光の壁を描き、孔雀の羽と激しくぶつかった。
金属を削るような轟音。
空気が震え、火花のような潤氣が四方へ散った。
だが孔雀は怯まない。血走った瞳が私を射抜き、巨体を揺らしてさらに突っ込んできた。
「姫よ、下がれ!」
宮様の鋭い声と同時に、白虎が地を蹴る。白銀の閃光のように跳びかかり、孔雀の脚を薙いだ。羽ばたきが乱れ、孔雀の巨体がバランスを崩す。
「今だ!」
宮様の声が心臓を打つ。恐怖で足がすくみそうになる。けれど――胸の奥に、あの聲が届いていた。
――たすけて。苦しい、痛い、こわい……。
「……わかった」
私は息をのみ、震える足を前に出した。羽をばさばさと震わせながら、孔雀が地に膝をつく。白虎がその前に立ち塞がり、低く唸って私を守る。
炎に包まれた鳳凰が頭上で輪を描き、孔雀の動きを封じるように煌めきを散らしていた。
その隙に、私は孔雀の胸元へと駆け寄った。
羽の根元に手を添えた瞬間、冷たく濁った氣が掌を突き抜ける。
「もう……大丈夫。ひとりで苦しまなくていいんだよ」
声を絞り出しながら、潤氣を流し込む。私の体が軋むように重くなり、膝が震える。けれどそのたびに、孔雀の瞳の紅がほのかにほどけ、静かな光が戻っていった。
「……ありがとう。もう、無理しないで」
大きな翼が力を失い、ゆっくりと畳まれていく。孔雀は地に伏し、まるで安らかな眠りにつくように瞼を閉じた。
「これで、もう大丈夫……」
ほおと安堵のため息がこぼれた。
ついさっきまで響いていた悲鳴も、獣の咆哮も、もうどこにもない。
気づけば、宮中の庭に満ちていた空気が嘘のように澄みきっていた。
「……助かった……」
「こわかった……」
「もう大丈夫ですわ……」
廊下に伏していた女房たちが、袖で涙を拭いながら顔を上げる。互いに手を取り合い、ぎこちなくも立ち上がっていった。
武官たちは槍を支えながら結界の綻びを点検し、侍たちが「無事か」「怪我はないか」と声を掛け合う。
どこかで、誰かが泣き出した。そのすぐ傍で、別の誰かが安堵の笑い声を漏らした。
張り詰めていた世界が、少しずつ、日常を取り戻していく。
私はそのただ中に立っていた。胸がまだ早鐘のように打ち、体の奥まで熱と痺れが残っている。
「……うそ。私にも……こんな力が、あったの?」
気づけば、唇が震えて言葉を紡いでいた。
風は止まり、潤氣の気配は澄んでいく。目の前の霊獣たちは穏やかに横たわり、苦悶の色はもうどこにもなかった。黒く濁っていた氣は晴れ、水面のように静かに凪いでいる。
本当に……これが、私の手で?
ふと視線を向けると、白虎が霊獣たちのそばに静かに身を横たえていた。
まるで仲間を気遣うように、濁った氣から解き放たれた獅子や鹿の傍に寄り添い、低く喉を鳴らしている。
その姿に、胸がじんと熱くなった。
一方、鳳凰はいつの間にか大きな姿をたたみ、ふたたび小さくなって宮様の肩に戻っていた。尾の金の羽根が月明かりに揺れ、炎の名残のようにほのかに輝いている。
「よくやった。そなたのおかげで鎮まった」
振り向いた瞬間、宮様の声が背を震わせた。
夜の闇を裂くようなその眼差しが、まっすぐに私を捉えている。
ただそれだけで、胸の奥が締めつけられるように熱くなった。
そして――彼が笑った。
ほんの一瞬。けれど、間違いなく。冷ややかで鋭いその瞳に、確かな温もりが宿っていた。
心臓が跳ねる。胸の奥で、なにかがほどけていく。
まるで、長い冬を越えた木々に初めて春の光が差し込んだように。冷え切っていた心に、あたたかさが広がっていく。
――私、役に立てたんだ。
その実感が胸の奥にふくらみ、目の奥が熱くなる。張りつめていた緊張がほどけ、全身から力が抜けた。思わず、胸の前で両手をぎゅっと握りしめる。
耳を澄ませば、遠くで女房たちのすすり泣きが混じり、武官たちの低い声が重なる。
世界が、ようやく静けさを取り戻しはじめていた。
――ぞわり。
背筋を、冷たい指先が這ったような感覚。夜気とは違う、澱んだ何かが髪の根元から首筋へ、氷のように流れ込んでくる。一瞬で鳥肌が立ち、息が喉に張りついて止まった。
「……っ?」
振り返ろうとした、その刹那。
闇が裂けた。
風を裂く轟音とともに、黒い影がこちらへ飛びかかってくる。逃げる間もなく、視界いっぱいに広がったのは、しなる尾と紅く光る瞳。
「――っ!」
胸の奥まで突き抜けるような重みが全身を叩きつけ、息が詰まる。
世界が反転し、白く弾ける視界のなかで、立っているはずの足元が崩れ落ちていく。
なに……これ……!
叫ぼうとしても声にならない。耳の奥で、遠く誰かが私の名を呼んでいる――それすら、夢の底から響く声のよう。目が開かない。体が冷たい。
それでも最後に、はっきり見えた。
しなる黒い尾、禍々しく輝く紅い瞳。まるで夜そのものが形をとったような、美しくも恐ろしい存在。
あれは……妖獣? でも、どこかで見たような……。
思考の端がかすれる。意識がふっと宙に浮かび、音も光も体さえも――すべてが遠ざかっていった。
藤原宵家の屋敷にある東の対は、朝の光をすり抜けた風が静かにゆれる、澄んだ空気に包まれていた。御簾の隙間から射し込む光が、白木の床に淡く差し、花籠の上にかけられた衣の桃色をやわらかく照らしていた。
その香りを深く吸い込む。鼻先をくすぐったのは、咲き誇る華やかな花のような薫り。ふんわりとしたやさしさ。やわらかく甘いその薫りは、どこか気高くて、それでいて胸の奥にそっと触れてくるような、そんなぬくもりを帯びていた。目の前にいる妹姫の微笑みに似ている、そんな気がした。
香りのもとは、花籠の上に丁寧に広げられた桃色の衣だった。香を焚きしめておいたそれが、布地にしみこみ薫りを帯びている。東の対の空気に溶け込みながら、ゆらゆらと揺れるように、室内いっぱいにその香りが広がってゆく。
「お姉さま。これは、とても良い香りね」
振り返った燁子が、無邪気な笑みを浮かべて言った。
「燁子、気に入ってくれた?」
「はい。もちろん」
「良かった。燁子に似合う香をまた作ったの。咲き誇る華やかな花のような香りの中に、優しい甘さと気高さを表現したの。それでね……」
「ふふ」
「あ、ごめん。私ばかりがしゃべって」
「わたくしはお姉さまのお話が好きよ。お姉さまは香がお上手ね」
瞳の形をふわりとゆるめた燁子は、どこまでも儚げで可憐だった。けれどその笑みは、夜空に浮かぶ綺羅星のように、どこか人を惹きつけてやまない輝きを放っている。燁子の美しさは、都で一、二を争うと言われていた。藤原宵家の自慢の妹姫だ。
「姫様によくお似合いの香です。鈴音も……まあ、良い働きをしましたね」
そばに控えていた燁子の乳母の松乃さんが、淡々と、けれど針のように冷たい声音でそう言った。言葉の端に棘があることは、もう何度も経験している。けれど、それでも心の奥にちくりとした痛みが走った。慣れているはずなのに。
「だめよ、松乃。そんな言い方。お姉さまは腹違いでも、わたくしのお姉さまなのだから」
燁子がきゅっと眉を寄せて、まるで私を庇うように松乃さんを窘めた。
「なんとお優しいのでしょう。さすが藤原宵家の北の方さまの姫。あなたも感謝しなければなりませんよ」
松乃さんは私に鋭い眼差しを投げつけたかと思うと、ふっと目を逸らす。
「もう、松乃。口を慎んで。お姉さまは腹違いだけれど、わたくしのお姉さまよ」
振り返った燁子は、やさしく笑いながら私を見つめてくる。その微笑みに胸の奥がじんわりとあたたかくなる。燁子の優しさに救われる。
「ありがとう、燁子。さあ、身支度をしてしまいましょう」
「それは、この松乃が――」
「嫌よ。お姉さまにしてもらいたいの」
燁子はふわりと身を翻し、私の目の前で背中を向けた。肩のあたりまで伸びた黒髪がさらりと揺れ、朝の光を受けて艶やかにきらめいた。
私は、燁子の髪に櫛を通しながら、静かに声をかけた。
「今日は……登花殿女御様のところへ?」
鏡越しに目が合うと、燁子はふふっと小さく笑った。
「ええ。女御様方の霊獣が、少し疲れているようだから。霊獣の蛟と一緒に潤氣の調整に伺うの」
「さすがは人と霊獣をつなぐ浮橋の君。姫様は女御様方と引けを取りませんわ」
「松乃ったら」
後ろに控えていた松乃さんの声に、得意げな響きが混ざる。
「浮橋の君である燁子様が入ってくだされば、女御様方も安心なさいますね」
別の女房が続けると、燁子はこともなげに、「そうだといいのだけれど」と答えた。その頬にはうっすらと紅が差していた。
――浮橋の君。人と霊獣をつなぐ、特別な存在。
私は何も言わずに、そっと手元の櫛に目を落とした。才のある妹姫。それと比べて、私は。
ふいに、空気の底が揺れるような感覚が走った。部屋の片隅。朝の光も届かぬ影のなかに、ひとつ、うごめく気配。
「……あら」
燁子が可憐な声と同時に現れたのは、闇に浮かび上がるような深い黒。滑らかな鱗が燭台の火を淡く映し、冷たい光を帯びてきらめく。長い尾が床をなぞるように揺れ、真紅の瞳がじっとこちらを見つめていた。
燁子の霊獣・蛟だ。
氷を落とされたような感触が、私の全身にひやりと広がる。
「まあ……なんと神々しい……」
女房のひとりが、思わず息を飲んで呟いた。
「夜の王のようですわ……姫様のご威光をそのまま映したような」
「ほんとうに……これほどの霊獣を従えておられるなんて」
松乃さんがにこやかに頷きながら、言葉を継いだ。
「やはり姫様には蛟のような高貴な霊獣がよく似合いますこと。どこかの方のように、霊獣の一体もそばにいないお姫様とは、格の違いがございますね」
“どこかの方”。それが私を指しているのだと、誰もが知っていた。
言葉に刺がざくざくとさ刺さる。私はただ、微笑を浮かべることしかできなかった。この屋敷で声を上げることが、どれほど愚かで危ういことか、もう知ってしまっているから。
「やめて、松乃」
燁子の声が、澄んだ鈴のように部屋に響いた。
「お姉さまは、霊獣よりももっと難しい香を扱えるのよ。ね? この間の香なんて、女御様にもお褒めいただいたくらい」
言いながら、彼女は鏡越しに私へ笑みを向ける。まるで、この空気の濁りをすべて拭い去るかのようなやわらかい笑顔。
燁子の声が部屋の空気をやわらかく撫でた瞬間、女房たちはそろって黙り込み、視線をそらした。けれど、苦い空気はあっという間に拭い去られた。
「やっぱり姫様はお優しいわぁ」
ほうと小さく漏れた感嘆の声に、他の女房たちがこくりと頷く。
「いつもわたしたちの話にも耳を傾けてくださるし」
「叱るときでさえ、笑顔を絶やされないのですもの」
「きっと東宮様も見初めていらっしゃるはずよ。うちの姫様は素敵ですもの」
この部屋に控えている女房たちがさえずる。
燁子は鏡越しにその声を聞きながら、ほんの少しだけ頬を染めた。
「そんなふうに言われると、くすぐったいわ。でもね……」
燁子が目を伏せていた。襟元を整える手が一瞬だけ止まり、光を避けるように視線が床へ落ちる。
「燁子、どうしたの?」
「あのね、お姉さま。実はわたくしには、宮中にお慕いしている方がいるの」
「え、そうなの?」
「でも……お体のこともあるし、なかなかお会いできないの」
その言葉に宿る柔らかな痛みに、私は小さく息を飲んだ。
“お体”――そう告げるその響きが、私の少ない知識の中で、ある人の姿を静かに呼び起こした。都で病弱と噂されるやんごとなき方。
燁子は何気ないそぶりで立ち上がり、女房の差し出した扇を受け取った。燁子が纏ったふわりと広がる桃色の衣が、朝の光に透けて、どこか夢の中のように揺れて見えた。
「でもね、お姉さま。今日こそは宮中でお会いできるかもしれないわ。これも浮橋というお役目をいただいているからだわ」
目じりを下げ柔らかに笑った燁子は可憐だ。この女神のこどく微笑みに心奪われない男性はいるのだろうか。
「そろそろ参りましょうか。姫様」
やがて支度がすべて整い、松乃さんが声をかける。燁子はふっと振り返った。
「お姉さま。お願いしていた香……作ってくれた?」
「もちろん」
私は袂からそっと香袋を取り出し、彼女の手のひらにそっとのせた。
淡い桜と丁子、そして藤の花をほんのひとしずく。燁子の香にふさわしい調合を、何度も試しながら心を込めてつくったものだった。
「ありがとう、お姉さま。お姉さまの香は、ほんとうに素敵。宮中でも評判なのよ。わたくし、鼻が高いの」
「さあ、姫様。お早く」
「はあい」
「燁子、いってらっしゃい」
燁子は一つ頷くと、女房によって巻き上げられた御簾の向こうへと進んでいく。その背を見送りながら、私はそっと頭を下げた。
顔を上げたとき、東の対の留守を任されている松乃さんと目が合った。
その目は冷えた石のように冷たく、感情が見えない。すぐに逸らされたその視線が、なぜか鋭く胸の奥に突き刺さった。さっきまでの華やかな空気が夢だったかのように、しんと冷えていく。
私は小さく息をついた。
――いつものこと。
これから私は、側室だった母とともに過ごしていた西の対へ戻るだけ。誰にも気づかれぬように立ち去る。何度も繰り返してきた役目の終わり。
私はそっと別の御簾を上げて東の対を後にしようとした。
「……お待ちなさいな」
まるで空気ごと凍らせるような声音。背筋がすっと冷えて、足が止まった。
振り返らずとも、誰かはわかっている。松乃さんだ。
「あなた、何を勘違いしているの。姫様に向かって、あんなに馴れ馴れしく……」
その声は乾いていて低かった。一言毎にこぼれ落ちるような棘があった。
「何度言えばわかるの? 姫様のお名前を呼ぶなんて、よくもまあ口にできたものね」
私はどう答えていいかわからず、喉の奥がきゅっとつまる。
ちゃんと、何か言わなくちゃ。うまく、傷つけない言い方を。怒らせないように。
けれど、考えようとすればするほど、頭の中にぐるぐる、ぐるぐると渦を巻き、言葉が霧のなかに沈んでいく。
その刹那。バシン――と音がして、頬に火が走った。
痛みのあとから、熱がじんじんと広がっていく。目の端がじわりと濡れた気がしたけれど、瞬きもできなかった。
「ぐずね。すぐに答えられないなんて。あなたは姫様とは違うのよ」
松乃さんは静かに言った。けれど、その声が鋭く深く突き刺さった。
「正室の娘でもない。卑しい身分の母親から生まれた、側室腹の子。姫でもなんでもないの」
言葉の刃が胸の奥でぽたりと落ちる。そこから静かに波紋が広がる。
私は言い返したかった。
――違う、と。
けれど、口が動かなかった。声にならなかった。
「姫様に対等な口をきくなんて、身のほどを弁えなさいな。今日の夕餉は抜きです。口の利き方を少しは学びなさい」
ぴしゃりと張りつけるような声が、耳に冷たく響く。
「あなたはいつまでこの宵家に居座るつもり? 姫様のご慈悲で、西の対に住まわせてもらっているだけでも、ありがたく思いなさい」
その言葉が、背中に、胸に、じわじわと沈んでくる。
もう何年も同じ言葉を聞いてきた。言い返すたびに、さらに深く抉られる。だから私は、いつしか反論しないことを選ぶようになってしまった。
どれが真実で、どれが呪いなのか。それすら、もうわからない。
松乃さんが鼻を鳴らして踵を返す。その足音が遠ざかっていって、やっと私は小さく息を吐いた。
足が鉛のように重い。ここにしゃがみ込んでしまいたい。
でも、それだけはしてはいけない。
誰もいないはずの回廊なのに、どこかに誰かの目が潜んでいるような気がして、私は背筋を正して、自分の住処へと戻る。歩き出した足音が、キイキイと寂しく床板が鳴った。
――お母さまがご健在だった頃は、まだ幸せだったのに。
不意に、母の手のぬくもりが脳裏に蘇った。
繕い物をする手はいつも静かでやさしくて、私はただその隣にいるだけで安心できた。もし、まだそばにいてくれたなら……私はもう少しだけ、強くなれていたのだろうか。
冷たい風が裾をかすめる。
敷石のうえに落ちた枯葉が、からり、からりと風で転がっていった。
西の対へ続くこの回廊は、同じ屋敷の中にあるのに、すれ違う人の気配もなく寂しげな静けさを纏い、どこか別の世界のように感じられる。
けれども、近づくたびに、身体の芯から少しずつもやが抜けていくようだった。
ようやくたどり着いた西の対は、あちらこちらに苔が張りつき、簀子縁の隙間からは草が顔を出していた。
誰の目も手も届かないこの場所は、どこかひっそりとしていて、でもそれが私にはちょうどよかった。
庭に出て、簀子にそっと腰を下ろす。太陽は少しずつ高くなり、けれど光はどこか翳り始めていた。
目の前に広がる庭は荒れていて、木々の枝はのび放題、草花も思うままに伸びていた。
でも、私はこの無造作な景色が嫌いじゃない。誰にも形を整えられていないからこそ、ここではすべてが“あるがまま”でいられる気がするのだ。
ふいに、足元にぬくもりが忍び寄ってきた。
「あら、また来たの?」
薄桃色の毛並みの兎の霊獣が、するりと簀子の隙間から這い上がってきた。
尖った耳がぴくりと動き、ふわふわの尾がくるくると踊る。その前足がそっと私の膝に触れた。
後ろからは、まだら模様の猫の霊獣が二匹、遠慮がちに顔を覗かせる。この子たちは何度も来ている常連だ。名もない小さな霊獣たち。
私はゆっくりと微笑んで、掌をそっと差し出した。
「おいで。今日もおなかが空いているのね」
指先に意識を集めると、掌から潤氣がじんわりとにじみ出す。霊獣・人・空間に満ちる“氣”の源である潤氣。
霊獣の額にそっと触れると、ほわりとした温かさが流れていった。すると、彼らは目を細め、小さな声で喉を鳴らした。
どうしてだか、昔から私はこうして霊獣たちに囲まれていた。眠れぬ夜も涙の朝も、彼らだけは変わらずそばにいてくれた。
私が“姫”かどうかなんて、きっと関係ない。
ただ掌から潤氣を注いで、そっと癒してあげるだけで、彼らはまっすぐに応えてくれる。
「あなたたちがいてくれて、良かった……」
その言葉は、誰に聞かせるでもなく、風にまぎれてどこかへ溶けていった。
霊獣たちが身を寄せ、私はそっと目を閉じた。陽だまりの温度が身体に染み入り、胸の奥の重たさが、ふっとほどけてゆく。
西の対には、何もない。でも、ここには、私の“心”があった。
◆◆ ◆
夜の帳がすっかり下りて、西の対は静寂に包まれていた。けれど、風の音が妙にざわついている。耳の奥に残るそのざわめきは、まるで地の底から湧き上がる声のようだった。どこか遠くで、何かが騒ぎはじめている。そんな気配が、じりじりと胸を締めつける。
私はひとつ寝返りを打った。けれど、眠気はとうにどこかへ消えていた。まるで、目に見えない何かが私を呼んでいる――そんな感覚。
息をひそめていた空気のなかで、私はそっと身を起こした。足音を忍ばせ、妻戸を開けて簀子へ出る。
夜気が肌に触れた瞬間、ひやりとした冷たさに肩が跳ねた。
空には雲一つなく、月が冴え冴えと光を投げかけている。あたりはひっそりとしているはずなのに、木々の葉がざわめき、風が騒いでいた。
刹那。
ズシンッ。
大地の奥から這い上がってきたような、重たい音が庭の奥から響いた。庭の闇が月明かりを呑んで膨らんだ。風が逆巻き、松の影が地を這う。
「……なに……?」
思わず声が漏れた。体の芯が凍る。足がすくんで動かない。それでも、私は目を逸らすことができなかった。
その闇の中心から――白いものが、にじみ出る。白銀の霊獣。
白いはずの毛並みはどす黒く濁り、尾の先は墨のように溶けて滴っていた。牙は赤く、瞳には光がなく、ただ紅い炎だけが揺らめいている。息を吐くたび、鼻の奥を刺す甘い匂いがまとわりつき、胸がざわついた。
これは本当に霊獣……?
「……っ」
地が沈むほどの踏み込みののち、巨体が跳ねた。
風圧が頬を打つ。爪が眼前に閃き、私は反射的に身をひねる。袖が裂け、布が宙で散った。足裏が空を踏み、簀子の縁から滑り落ちる。膝に衝撃を感じ、息が詰まる。
怖い。逃げたい。なのに。
――助けて。
耳で捉えてはいない、胸のもっと奥、腹の底で震える聲が聞こえた。
何、今の。
私は痛みをこらて、震える膝を叱咤する。唾を飲み込み、ただ一歩、前へ。
白虎が喉を鳴らし、再び飛んだ。赤い牙が月を裂く。
私は両手を広げ、低く息を吸った。
「――待って」
自分でも驚くほど、声は静かだった。
次の瞬間、掌がひらく。内側から白い潤氣が滲み出し、ぬくもりが指先に集まる。
触れた途端、氷と針が一度に走ったような痛みが腕を駆け上がった。思わず奥歯を噛む。視界が揺れる。それでも、手を退けない。
「大丈夫……戻ってきて。あなたは、霊獣よ」
爪が地を抉り、鼻先が私の胸元すれすれで止まる。熱い吐息と、荒い鼓動。
どうしてそんな姿になってしまったのか。
私は身を屈め、額――眉間の硬い骨にそっと掌を当てた。もう片方の手で顎を支える。喉元で震える唸りが、掌の骨を震わせる。
潤氣を重ねるたび、腕の内側が痺れていく。黒い氣が、触れたところからじりじりと逆流してくるみたいだ。胸の奥が締めつけられ、目の端が滲む。それでも流す。私のぬくもりを、少しずつ、少しずつ。
「痛いよね……その痛み、私に分けて」
白虎の瞳の紅がわずかに揺らいだ。
紅蓮の底に、針の先ほどの青が灯る。私はそこへ息を合わせる。掌の中心で、柔らかな白が波紋になって広がった。
黒ずんだ毛並みが、端から解けていく。
墨色の尾が白銀を取り戻し、赤く濁った牙の輝きが静まる。喉の唸りが低く、苦悶から嘆息へと変わる。私は膝をつき、その額にさらに深く手を押し当てた。
「もう、ひとりじゃない。帰ってきて」
頬にざらりとした鼻先が触れた。怯えた獣の、それでも甘えるみたいな、弱い押しつけ方。
大きな体がぐらりと揺れ、土の上に静かに伏す。肩が上下するたび、荒かった呼吸が少しずつ整い、紅い瞳の奥に残った青が夜を映した。
良かったぁ。はああと長く息を吐いた。
白虎は目を細め、鼻先を私の掌に寄せて、もう一度小さく安堵の音を洩らした。
震える膝に力が入らず、その場にへたり込みそうになった。
「……霊獣・白虎を、癒したのか」
夜気の中に澄んだ声が落ちた。
低く静かに響いたその声音は、風のざわめきよりも透きとおっていて、耳に届いた瞬間、胸の奥にまで染み込んだ。
「誰!?」
私ははっとして振り返った。
月明かりの下、庭の端にひとりの青年が立っていた。
黒曜石のような髪は夜風に揺れ、白い薄衣は光を透かして幽かにきらめく。その姿は人の世に在りながら、人ならぬ影をまとっているよう。
あまりに整いすぎた面差しは、温もりはなく冷ややかな静謐を湛えていた。見つめれば息を呑むより他なく、ただ存在するだけで闇さえ彼に従うようだった。
その肩には、金の尾をひるがえす霊獣・鳳凰が翼を畳んで寄り添っている。炎のように鮮烈な輝きを放ちながらも、青年の横顔に照らされているその光景は、不思議と凍りついた静けさの中にあった。
「潤氣を操ったのは、そなたか?」
その瞳が真っ直ぐに私を見据えた。
冷たさと鋭さと言葉にできない重みが、視線そのものに宿っているようで、私は思わず息をのんだ。
まるで、何もかも見透かしているような眼差し。
もしかして――病弱と言われている今上帝の二の宮・彰仁親王では。
噂に聞いたその姿とはあまりにも違っていた。か細いどころか、彼がそこに立つだけで、あたりの空気が凛と張り詰めていくようだった。
「……はい。あの……」
気づけば、言葉が口から零れていた。
「宵家の大姫だな」
「は、はい。鈴音と申します」
慌てて頭を下げたけれど、貴族の姫らしさのかけらもないのが恥ずかしい。
「宵家のお荷物やら、卑しい姫だの……宮中では、いろいろと聞いていたが」
「え……?」
思わず問い返そうとしたその瞬間、宮様は淡い月光のなかで静かに言った。
「どうやら噂とは違ったようだな」
その言葉の意味を私はすぐには掴めなかった。何かを返したかったのに、頭の中が白く霞んでしまって言葉が見つからない。
「癒してくれて助かった。私は今上帝の二の宮で、霊獣寮を預かる霊獣頭。この霊獣・白虎は妖獣になり、宮中で暴れていたのだ」
宮様の声は夜気を切るように低く響いた。
「……暴れていた? さっきのあの姿……」
思わず問い返すと、宮様の眼差しが私を射抜いた。
「強い氣が乱れると霊獣は歪む。己を見失い、悪しきものに堕ちる。妖獣となっていたのだ」
胸がひやりと凍りつく。白虎の鋭い牙や、狂った目の光が脳裏に蘇った。けれど今は……その白虎が静かにこちらを見ている。
「来い。そなたの力が、必要だ」
「……え? あの、どこに……!?」
「宮中だ。宮中で妖獣が暴れている」
戸惑うより早く、宮様の手が私の腕をとらえる。
その瞬間だった。
宮様の肩に収まっていた鳳凰の体が、白光を放ちながら膨らんでいく。翼がばたくたびに風が巻き起こり、庭の枝葉がざわめいた。小さな鳥のようだった姿は、瞬きの間に人の数倍の大きさに変わっていた。
「ひっ……!」
私は思わず息を呑み固まる。けれど、宮様に腕を引かれたまま鳳凰の背に乗せられた。
羽毛の感触は意外なほど柔らかく、けれど奥に熱い脈動が走っていて、座っただけで全身が震えた。
「……う、そ……これ、ほんとに……?」
思わず声が漏れる。足元の庭がみるみる遠ざかり、夜風が顔に痛いほど吹きつけてきた。
夜空を切り裂くように鳳凰が翔ける。
頬を叩く風は鋭く、衣の裾を容赦なくはためかせた。遠ざかる庭の闇の下、白銀の影がしなやかに駆けているのが見える。
白虎――。
吠えもせず、ただ真っ直ぐにこちらを追ってきていた。
土を蹴るたびに火花のような氣が散り、揺るがぬ脚取りはまるで大地そのものの意志のよう。置いていくことなど決して許さない、とその姿が訴えていた。
「……もしかして、一緒に来るつもりなの?」
その刹那、白虎の瞳が月光をはじいて煌めいた。
応えるように一層身を低くし、夜気を裂いて走り抜ける。その必死さが、風よりも強く私の胸に突き刺さった。ただその姿がすべてを伝えてくる。
私は鳳凰の背にしがみつきながら、小さく頷いた。
それだけで、白虎はまるで約束を交わしたかのように加速し、夜空を翔ける影に寄り添って走り続けた。
◆◆ ◆
金銀の星々が瞬く夜の帳を切り裂き、霊獣・鳳凰は宙を翔けていた。
眼下に広がるのは、黒々とした闇の海。その底に無数の青白い燐火がちらちらと揺れている。屋根に月が浮かび、松の影が長く伸び、白砂の庭が鈍く光を返す。そこは豪華絢爛な宮中であるはずだった。けれど、華麗さはどこにもなかった。
――きゃああああっ!
耳を劈く甲高い悲鳴。それから木の裂ける音、妖獣の咆哮。それらが夜風を震わせ、背筋をざわりと撫でていく。
私は優雅に翼を広げた大きな体躯の鳳凰の背に身を伏せ、必死に揺れに耐えながら、眼下に広がるその光景に目を逸らせないでいた。胸の奥が強張って呼吸が浅くなる。ぶるりと背筋が震えて、一瞬体がぐらりと傾いた。
「あ!」
その時、力強い腕が私の身体を支えた。触れると氷のように冷ややかなのに、揺るぎのない力のある宮様の腕。宮様の横顔は月光に照らされ、彫像めいた影を落としている。まるで人ではなく、夜の闇から切り出された存在のようで、ぞくりとするほど美しく冷たかった。
「――鳳凰」
耳の奥に響く艶のある低音が、夜気を震わせる。
刹那、鳳凰が羽ばたき、夜空に烈風が走った。眩い尾がひるがえり、白い矢のごとき潤氣が庭の中心へと撃ち込まれる。音もなく展開された結界が、地を這うように広がり、霊獣たちの狂乱をひととき封じ込めた。
その直後に鳳凰の翼が大きく翻り、月を遮る影となって急降下を始めた。夜気が渦を巻いて髪を乱し、熱気を帯びた風が頬を鋭く打つ。庭が迫るごとに、悲鳴と妖獣の咆哮が耳を裂き、何度も心臓が跳ねた。
「……っ!」
ドンッ、と強い衝撃とともに、鳳凰の爪が白砂を抉り地に降り立った。翼が風を巻き起こし、松の枝をざわめかせる。
大きな背が沈み、地面へと傾いた。支えるように差し伸べられた腕に導かれ、私は足を下ろす。柔らかな砂を踏む感覚がゆらりとして、まだ夢のようで現実感がなかった。
あたりを見回すと、地上の空気は空の上よりもはるかに濃く、荒れていた。湿りついた重く邪悪な潤氣が肌にまとわりつき、肌の奥まで刺すように入り込んでくる。
「女官たちが逃げ遅れている! 妖獣に喰われるぞ!」
遠くで武官の叫びが飛ぶ。
青白い燐火が宮中を覆い、女房たちが廊下の影にうずくまって、声を押し殺して泣いていた。
「どうして、こんなことに……それに、あれは……」
そのすぐ先で――妖獣たちが唸り声を上げてのたうっていた。狐も、鹿も、孔雀も、獅子も。赤く濁った瞳を見開き、理性を失ったように、濁った潤氣を吐き散らしながら。
この妖獣たちが、もともとは霊獣だったの? 本当に、あの子たちが……?
私は震える指先を胸元に押し当てれば、心臓を打ち付ける音が加速する。
その姿は私の知る霊獣ではなかった。瞳は血のように赤く濁り、氣は黒ずみ裂け、輪郭まで歪んでいる。
「まるで悪霊や妖のようだわ。これが妖獣」
その時、狐の妖獣と目があった気がした。次の瞬間、狐の妖獣がこちらに跳びかかってきた。
「――っ!」
思わず悲鳴をあげたその前に、白虎の咆哮が轟いた。
その影がすぐ傍らに滑り込む。銀の毛並みが月光を弾き、牙を剥き、爪で地を抉り、狐の体当たりを弾き飛ばす。火花のような氣が散った。
白虎は狐から目を離さず、私をかばうように低く喉を鳴らす。
「ありがとう、白虎」
ほんとうについてきたんだ。
胸が詰まる。襲い来るのを止めてくれたのだ――私を守るために。
「宵家の姫よ」
隣に立つ宮様が、低く言った。
「見ろ。これが――妖獣と成り果てた霊獣の暴走だ」
その言葉に振り向いたとき、宮様の瞳が夜の闇より深く、静かに光っていた。
「……鳳凰」
次の瞬間、鳳凰が高く舞い上がる。
その巨体が月光を覆い、尾がしなって夜空を裂く。
「静止の封」
白い矢のような潤氣が放たれ、庭の中央――暴れ狂う妖獣たちの周囲へと突き刺さった。
眩い光が地面を奔り、淡い紋を描き出す。
結界だ。きらり、と波紋のように揺れ、見えない壁が展開される。
狐が牙を剥いたまま硬直し、獅子が唸り声を喉に詰まらせる。
孔雀の羽ばたきも凍りついた。呻き声が重なり、結界の内側で空気が軋んだ。
「封じるだけでは足りぬ」
宮様が私を見据えた。鳳凰の炎の光を背に、その眼差しは鋭くも揺るぎなかった。
「癒せるのは……そなただ」
「わ、たし……?」
「このままでは皆やられてしまうぞ」
足が震える。怖い。けれど――聞こえる。
荒れた潤氣の奥から、小さな聲。
――痛い。
――たすけて。
「……大丈夫……大丈夫だから」
息を呑み、震える掌を差し出す。
白虎が前に立ちふさがり、牙をむき出して私を庇う。その背の陰で、私は狐にそっと触れた。尾の根元に掌を重ねる。
熱が流れ出す。
指先からじわりと潤氣を注ぎ込むたび、胸が焼けるように苦しい。
でも、狐の目の赤が少しずつ濁りを失っていくのが見えた。
「私の潤氣を分けるから。だから、もう苦しまないで」
狐が小さく鳴いた。
荒ぶっていた氣がほぐれ、目を閉じると、まるで深い眠りに落ちるようにその体を横たえた。
安堵する間もなく、今度は鹿が角を突き上げ、こちらへ突進してきた。
白虎が低く唸り、体をひねってその前に立ちはだかる。爪と角がぶつかり合い、火花のような氣が弾け飛んだ。
「……はぁ、はぁ……」
汗が滲み、膝が震える。それでも、私は鹿の額に手を添えた。
重い氣が流れ込んでくる。背中が鉛のように沈み込む。
でも、私の内から流れた潤氣に包まれた瞬間、鹿の震えがぴたりと止まった。濁った瞳が澄み、吐息が静かになっていく。
「次だ!」
再び宮様の声が鋭く響く。
視線の先で、獅子の妖獣が大地を抉るように足を踏み鳴らし、血走った瞳でこちらを睨み据えていた。牙の奥から漏れる唸りが、胸骨を震わせる。
「っ……!」
思わず後ずさりしかけたその瞬間、白虎が私を庇うように飛び出した。
獅子が吠え、巨体を揺らして突進してくる。白虎が横から躍りかかり、その鋭い爪で獅子の横腹を打った。鈍い衝撃音が響き、獅子の動きが一瞬だけ鈍る。
今だ!
私は震える足を前に出した。
荒い息を吐く獅子の胸に、掌をそっと重ねる。
熱い。獣の鼓動とともに、苦しみが直接流れ込んでくる。
「……もう、大丈夫……」
囁くように声をかけながら、潤氣を送り込む。濁った赤がじわじわとほどけ、金色の光が瞳に戻っていく。獅子は呻き声を残し、地に伏した。
「っ、はぁ……!」
息が切れる私の耳に、宮様の声が再び響いた。
「上からくるぞ! 孔雀だ!」
宮様の声が夜気を裂く。見上げれば、月を背にした巨大な影。
孔雀の妖獣が翼を広げ、刃のような羽を撒き散らしながら急降下してきた。光の反射で煌めいた羽先は、すべて鋭い凶器だった。
「鳳凰!」
宮様の呼び声に応え、背後で炎が爆ぜた。鳳凰が夜空へ舞い上がり、尾をひるがえす。燃えるような羽が光の壁を描き、孔雀の羽と激しくぶつかった。
金属を削るような轟音。
空気が震え、火花のような潤氣が四方へ散った。
だが孔雀は怯まない。血走った瞳が私を射抜き、巨体を揺らしてさらに突っ込んできた。
「姫よ、下がれ!」
宮様の鋭い声と同時に、白虎が地を蹴る。白銀の閃光のように跳びかかり、孔雀の脚を薙いだ。羽ばたきが乱れ、孔雀の巨体がバランスを崩す。
「今だ!」
宮様の声が心臓を打つ。恐怖で足がすくみそうになる。けれど――胸の奥に、あの聲が届いていた。
――たすけて。苦しい、痛い、こわい……。
「……わかった」
私は息をのみ、震える足を前に出した。羽をばさばさと震わせながら、孔雀が地に膝をつく。白虎がその前に立ち塞がり、低く唸って私を守る。
炎に包まれた鳳凰が頭上で輪を描き、孔雀の動きを封じるように煌めきを散らしていた。
その隙に、私は孔雀の胸元へと駆け寄った。
羽の根元に手を添えた瞬間、冷たく濁った氣が掌を突き抜ける。
「もう……大丈夫。ひとりで苦しまなくていいんだよ」
声を絞り出しながら、潤氣を流し込む。私の体が軋むように重くなり、膝が震える。けれどそのたびに、孔雀の瞳の紅がほのかにほどけ、静かな光が戻っていった。
「……ありがとう。もう、無理しないで」
大きな翼が力を失い、ゆっくりと畳まれていく。孔雀は地に伏し、まるで安らかな眠りにつくように瞼を閉じた。
「これで、もう大丈夫……」
ほおと安堵のため息がこぼれた。
ついさっきまで響いていた悲鳴も、獣の咆哮も、もうどこにもない。
気づけば、宮中の庭に満ちていた空気が嘘のように澄みきっていた。
「……助かった……」
「こわかった……」
「もう大丈夫ですわ……」
廊下に伏していた女房たちが、袖で涙を拭いながら顔を上げる。互いに手を取り合い、ぎこちなくも立ち上がっていった。
武官たちは槍を支えながら結界の綻びを点検し、侍たちが「無事か」「怪我はないか」と声を掛け合う。
どこかで、誰かが泣き出した。そのすぐ傍で、別の誰かが安堵の笑い声を漏らした。
張り詰めていた世界が、少しずつ、日常を取り戻していく。
私はそのただ中に立っていた。胸がまだ早鐘のように打ち、体の奥まで熱と痺れが残っている。
「……うそ。私にも……こんな力が、あったの?」
気づけば、唇が震えて言葉を紡いでいた。
風は止まり、潤氣の気配は澄んでいく。目の前の霊獣たちは穏やかに横たわり、苦悶の色はもうどこにもなかった。黒く濁っていた氣は晴れ、水面のように静かに凪いでいる。
本当に……これが、私の手で?
ふと視線を向けると、白虎が霊獣たちのそばに静かに身を横たえていた。
まるで仲間を気遣うように、濁った氣から解き放たれた獅子や鹿の傍に寄り添い、低く喉を鳴らしている。
その姿に、胸がじんと熱くなった。
一方、鳳凰はいつの間にか大きな姿をたたみ、ふたたび小さくなって宮様の肩に戻っていた。尾の金の羽根が月明かりに揺れ、炎の名残のようにほのかに輝いている。
「よくやった。そなたのおかげで鎮まった」
振り向いた瞬間、宮様の声が背を震わせた。
夜の闇を裂くようなその眼差しが、まっすぐに私を捉えている。
ただそれだけで、胸の奥が締めつけられるように熱くなった。
そして――彼が笑った。
ほんの一瞬。けれど、間違いなく。冷ややかで鋭いその瞳に、確かな温もりが宿っていた。
心臓が跳ねる。胸の奥で、なにかがほどけていく。
まるで、長い冬を越えた木々に初めて春の光が差し込んだように。冷え切っていた心に、あたたかさが広がっていく。
――私、役に立てたんだ。
その実感が胸の奥にふくらみ、目の奥が熱くなる。張りつめていた緊張がほどけ、全身から力が抜けた。思わず、胸の前で両手をぎゅっと握りしめる。
耳を澄ませば、遠くで女房たちのすすり泣きが混じり、武官たちの低い声が重なる。
世界が、ようやく静けさを取り戻しはじめていた。
――ぞわり。
背筋を、冷たい指先が這ったような感覚。夜気とは違う、澱んだ何かが髪の根元から首筋へ、氷のように流れ込んでくる。一瞬で鳥肌が立ち、息が喉に張りついて止まった。
「……っ?」
振り返ろうとした、その刹那。
闇が裂けた。
風を裂く轟音とともに、黒い影がこちらへ飛びかかってくる。逃げる間もなく、視界いっぱいに広がったのは、しなる尾と紅く光る瞳。
「――っ!」
胸の奥まで突き抜けるような重みが全身を叩きつけ、息が詰まる。
世界が反転し、白く弾ける視界のなかで、立っているはずの足元が崩れ落ちていく。
なに……これ……!
叫ぼうとしても声にならない。耳の奥で、遠く誰かが私の名を呼んでいる――それすら、夢の底から響く声のよう。目が開かない。体が冷たい。
それでも最後に、はっきり見えた。
しなる黒い尾、禍々しく輝く紅い瞳。まるで夜そのものが形をとったような、美しくも恐ろしい存在。
あれは……妖獣? でも、どこかで見たような……。
思考の端がかすれる。意識がふっと宙に浮かび、音も光も体さえも――すべてが遠ざかっていった。