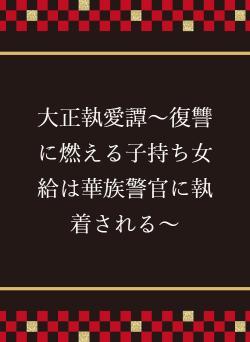金銀の星々が瞬く夜の帳を切り裂き、霊獣・鳳凰は宙を翔けていた。
眼下に広がるのは、黒々とした闇の海。その底に無数の青白い燐火がちらちらと揺れている。屋根に月が浮かび、松の影が長く伸び、白砂の庭が鈍く光を返す。そこは豪華絢爛な宮中であるはずだった。けれど、華麗さはどこにもなかった。
――きゃああああっ!
耳を劈く甲高い悲鳴。それから木の裂ける音、妖獣の咆哮。それらが夜風を震わせ、背筋をざわりと撫でていく。
私は優雅に翼を広げた大きな体躯の鳳凰の背に身を伏せ、必死に揺れに耐えながら、眼下に広がるその光景に目を逸らせないでいた。胸の奥が強張って呼吸が浅くなる。ぶるりと背筋が震えて、一瞬体がぐらりと傾いた。
「あ!」
その時、力強い腕が私の身体を支えた。触れると氷のように冷ややかなのに、揺るぎのない力のある男性の腕。その横顔は月光に照らされ、彫像めいた影を落としている。まるで人ではなく、夜の闇から切り出された存在のようで、ぞくりとするほど美しく冷たかった。
「――鳳凰」
耳の奥に響く艶のある低音が、夜気を震わせる。
刹那、鳳凰が羽ばたき、夜空に烈風が走った。眩い尾がひるがえり、白い矢のごとき潤氣が庭の中心へと撃ち込まれる。音もなく展開された結界が、地を這うように広がり、霊獣たちの狂乱をひととき封じ込めた。
その直後に鳳凰の翼が大きく翻り、月を遮る影となって急降下を始めた。夜気が渦を巻いて髪を乱し、熱気を帯びた風が頬を鋭く打つ。庭が迫るごとに、悲鳴と妖獣の咆哮が耳を裂き、何度も心臓が跳ねた。
「……っ!」
ドンッ、と強い衝撃とともに、鳳凰の爪が白砂を抉り地に降り立った。翼が風を巻き起こし、松の枝をざわめかせる。
大きな背が沈み、地面へと傾いた。支えるように差し伸べられた腕に導かれ、私は足を下ろす。柔らかな砂を踏む感覚がゆらりとして、まだ夢のようで現実感がなかった。
あたりを見回すと、地上の空気は空の上よりもはるかに濃く、荒れていた。湿りついた重く邪悪な潤氣が肌にまとわりつき、肌の奥まで刺すように入り込んでくる。
青白い燐火が宮中を覆い、女房たちが廊下の影にうずくまって、声を押し殺して泣いていた。
そのすぐ先で――妖獣たちが唸り声を上げてのたうっていた。狐も、鹿も、孔雀も、獅子も。赤く濁った瞳を見開き、理性を失ったように、濁った潤氣を吐き散らしながら。
この妖獣たちが、もともとは霊獣だったの? 本当に、あの子たちが……?
私は震える指先を胸元に押し当てれば、心臓を打ち付ける音が加速する。
狐が叫び、獅子が吠え、孔雀が羽を叩き、鹿が角を振り乱す。そんな姿を固唾を飲んで凝視していると、突然、荒れ狂う妖獣たちが硬直した。
「封じるだけでは足りぬ」
結界を作りだし妖獣を地に縫い付けた彼の声は、冷たくも温かくもなかった。ただ揺るぎなく耳の奥を震わせ、抗えぬ重さを持って胸の奥に沈み込んでいく。
「癒せるのは……そなただ」
彼の視線が、静かに私を射抜いた。闇を切り裂くような双眸の強さに、はくりと息を呑む。
「ま、待って……私には、そんな……」
思わず後ずさると、ざりっと砂が嫌な音を立てた。
私なんて、何もできない。
潤氣を自在に操り大きな力をもつ優秀な妹姫と違って、私は霊獣に懐かれるくらいしかなく、姫とし扱われないできそこない。そんな私に、何ができるというの?
喉が震え、声にならない息がこぼれる。
けれどその時、胸の奥、いやそれよりもっと深いところに音が届いた。
――助けて。
音が形を持つ。これは誰かの聲だ。
置き去りにされた幼子のように、その聲は私をまっすぐに求めていた。
きっと、泣いている。
「……っ」
気づけば足が動いていた。腹の底に渦巻いていた怖さも、迷いも、すべてを押しのけて。荒れ狂う潤氣の渦のただ中へ飛び込む。黒い風に頬を裂かれ、髪を乱されながら、私は走った。
伸ばした手のひらから、熱がにじみ出す。掌が脈打ち、指先が震える。胸の奥で心臓の鼓動と潤氣が重なり合う。
「……落ち着いて。大丈夫……もう、大丈夫だから……」
私のかすれた声が夜風に溶けた。
その瞬間、暗闇の中で妖獣の瞳がわずかに揺れた気がした。
眼下に広がるのは、黒々とした闇の海。その底に無数の青白い燐火がちらちらと揺れている。屋根に月が浮かび、松の影が長く伸び、白砂の庭が鈍く光を返す。そこは豪華絢爛な宮中であるはずだった。けれど、華麗さはどこにもなかった。
――きゃああああっ!
耳を劈く甲高い悲鳴。それから木の裂ける音、妖獣の咆哮。それらが夜風を震わせ、背筋をざわりと撫でていく。
私は優雅に翼を広げた大きな体躯の鳳凰の背に身を伏せ、必死に揺れに耐えながら、眼下に広がるその光景に目を逸らせないでいた。胸の奥が強張って呼吸が浅くなる。ぶるりと背筋が震えて、一瞬体がぐらりと傾いた。
「あ!」
その時、力強い腕が私の身体を支えた。触れると氷のように冷ややかなのに、揺るぎのない力のある男性の腕。その横顔は月光に照らされ、彫像めいた影を落としている。まるで人ではなく、夜の闇から切り出された存在のようで、ぞくりとするほど美しく冷たかった。
「――鳳凰」
耳の奥に響く艶のある低音が、夜気を震わせる。
刹那、鳳凰が羽ばたき、夜空に烈風が走った。眩い尾がひるがえり、白い矢のごとき潤氣が庭の中心へと撃ち込まれる。音もなく展開された結界が、地を這うように広がり、霊獣たちの狂乱をひととき封じ込めた。
その直後に鳳凰の翼が大きく翻り、月を遮る影となって急降下を始めた。夜気が渦を巻いて髪を乱し、熱気を帯びた風が頬を鋭く打つ。庭が迫るごとに、悲鳴と妖獣の咆哮が耳を裂き、何度も心臓が跳ねた。
「……っ!」
ドンッ、と強い衝撃とともに、鳳凰の爪が白砂を抉り地に降り立った。翼が風を巻き起こし、松の枝をざわめかせる。
大きな背が沈み、地面へと傾いた。支えるように差し伸べられた腕に導かれ、私は足を下ろす。柔らかな砂を踏む感覚がゆらりとして、まだ夢のようで現実感がなかった。
あたりを見回すと、地上の空気は空の上よりもはるかに濃く、荒れていた。湿りついた重く邪悪な潤氣が肌にまとわりつき、肌の奥まで刺すように入り込んでくる。
青白い燐火が宮中を覆い、女房たちが廊下の影にうずくまって、声を押し殺して泣いていた。
そのすぐ先で――妖獣たちが唸り声を上げてのたうっていた。狐も、鹿も、孔雀も、獅子も。赤く濁った瞳を見開き、理性を失ったように、濁った潤氣を吐き散らしながら。
この妖獣たちが、もともとは霊獣だったの? 本当に、あの子たちが……?
私は震える指先を胸元に押し当てれば、心臓を打ち付ける音が加速する。
狐が叫び、獅子が吠え、孔雀が羽を叩き、鹿が角を振り乱す。そんな姿を固唾を飲んで凝視していると、突然、荒れ狂う妖獣たちが硬直した。
「封じるだけでは足りぬ」
結界を作りだし妖獣を地に縫い付けた彼の声は、冷たくも温かくもなかった。ただ揺るぎなく耳の奥を震わせ、抗えぬ重さを持って胸の奥に沈み込んでいく。
「癒せるのは……そなただ」
彼の視線が、静かに私を射抜いた。闇を切り裂くような双眸の強さに、はくりと息を呑む。
「ま、待って……私には、そんな……」
思わず後ずさると、ざりっと砂が嫌な音を立てた。
私なんて、何もできない。
潤氣を自在に操り大きな力をもつ優秀な妹姫と違って、私は霊獣に懐かれるくらいしかなく、姫とし扱われないできそこない。そんな私に、何ができるというの?
喉が震え、声にならない息がこぼれる。
けれどその時、胸の奥、いやそれよりもっと深いところに音が届いた。
――助けて。
音が形を持つ。これは誰かの聲だ。
置き去りにされた幼子のように、その聲は私をまっすぐに求めていた。
きっと、泣いている。
「……っ」
気づけば足が動いていた。腹の底に渦巻いていた怖さも、迷いも、すべてを押しのけて。荒れ狂う潤氣の渦のただ中へ飛び込む。黒い風に頬を裂かれ、髪を乱されながら、私は走った。
伸ばした手のひらから、熱がにじみ出す。掌が脈打ち、指先が震える。胸の奥で心臓の鼓動と潤氣が重なり合う。
「……落ち着いて。大丈夫……もう、大丈夫だから……」
私のかすれた声が夜風に溶けた。
その瞬間、暗闇の中で妖獣の瞳がわずかに揺れた気がした。