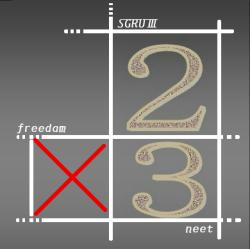ガチャ… (あれ?鍵開いてんのか…?)
「ただいま~、美加ちゃんかなぁ~♪」
奥からひょこっと茶髪の女性が現れた、風山の彼女は家で同棲していた。
「そうだよぉ~。」
抱き合う二人、風山は同窓会の後味悪い感じを消す為か、長いキスをした。
「あっそうだ、女の人が尋ねてきたよぉ?」
風山は吹き上がる嫌な予感を必死で否定しながら、美加の顔をのぞきこんだ。
「えっ…?」
「本当だよ!ついさっき友子って言う人が来たの、ずっと下向いてて顔よくわかんなかったけど知り合いな…。」
風山はつい先程の湧き上がる最悪を同窓会と同じ状態でフラッシュバックしていた。彼女の話など『友子』の名前が出た瞬間にプツリと途絶えてしまっている。
「…っ…ってねぇ?聞いてる?ねぇっ!」
「…っ!?あっ…?うん。」
風山は我に返った、誰かの悪戯だろうと思って平常心に戻した。だが、涌き出る冷や汗を止める事はできない。どんどん恐怖で体が冷めていく、温かい日常はもうどこにもない。
「大丈夫…?あ、そう言えば最後に来るって伝えてくださいだって…。」
「…さ…いご?」
「意味わかんないよね?」
猫の様に無邪気な彼女と対照的に、風山は震えが止まらなかった。
ごく自然な恐怖だった。
(まてよ最後って…?それじゃあ他のやつの所に…涼!?そうだ彼女が危ない!)
彼はまとわりつく彼女を乱暴に振り切り、電話に飛びついた。
「ほんっと今日は最悪だったわ、ねぇ聞いてるの…?」
「今俺バイトで忙しいからまた後にしてくれ、じゃあなっ!」
プップーップーッ、電話は一方的に切られた。
「たくっ!何よ彼女の話の途中で切りやがって!」 ピーンポーンピーンポーン
「誰かな…?こんな時間に…。」
ガチャ…、目の前には二つ括りの暗い感じをまとった女性がスッと立っていた。
「あの?誰ですか?」
チリリリリンッ!チリリリンッ!家の中の電話が激しく鳴るのが聞えた。
「あっ電話が…用があるんなら早く…。」
「やっと会えた…。」
「誰…、…っ…えっ…ちょっ…?」
目の前の女はゆっくりと顔をあげその全てを彼女にさらけた、涼は気がどんどん遠のき電話の呼び鈴もどこか遠くへ…。その場へ力なくへたり込んでいった。
「私ね…すごく苦しんだの、もうダメなの…、苦しくて苦しくて…ねぇ?聞いてるの…?本当に苦しいの…、私は今もあなたにイジメられっぱなしなの…。ねぇ…謝って…、苦しいの…、私を楽にしてよ…ねぇ?もう死んじゃったの?もっと苦しんでくれなきゃ…。」
…トゥルルル…トゥルルル…プッ
「只今留守にしております、メッセー…」 カチャ
「留守…?大丈夫かな…でも、友子はどうして俺を最後にしたんだ…?」
「どうしたの?変だよ何か…。」
心配そうに彼を見つめる美加、風山はでかける用意をしだした。
「えっ!?どこ行くの!?」
「ちょっと用事だ。」
そそくさと出ていった風山を美加は寂しげに見送った。
「浮気かなぁ…?でも顔が蒼冷めてたし…、どうしたんだろう…。」
風山は急いで車に乗って涼の家へ向かった。
「ハァッ…ハァッ…!?…涼っ!」
玄関は開けっぱなしだった。彼女の体は一点を凝視したまま冷たい通路に突っ伏していた。恐らく体は元気なのだ。しかし、精神が死に至っているのだろう。
「…くっ…!やっぱり…。」
風山は胸ポケットから携帯電話を取り出して恵にかけた、次は彼女なんじゃ…。
「もしもし、どうしたの?」
「はぁっはぁっ…涼が死んでしまった…。」
「えっ……!?」
「とりあえず俺が行くまで誰も家に入れるな!次はお前かもしれない!」
「うっうん…わかった。」
ピッ…恵は携帯を握り締めただ泣き崩れ、その迫り来る恐怖と親友の死に絶望した。
ピーンポーンピーンポーン…。呼び鈴が手招きをしている。恵は玄関のドアノブを握って混乱の極地に汗をにじませた。板一枚向こうに居るのは風山か、それとも…?
ピーンポーンピーンポーン、再び鳴る呼び鈴は脅迫めいた感じだった。彼女は手をガタガタと震えさせ、冷たい汗をダラダラと流し硬直していた。…コンコンコン!
「俺だ!無事か!?」
風山の声だ…!彼女は一気に安心してドアを開け放った。風山は肩で息をしていた。よほど急いできたらしい。嫌な恐怖心が彼の顔を見て、彼女はどれほど和らいだだろう。
「よかった…。」
「えっ…?それはこっちの台詞だよ、とにかく次は恵じゃなかったみただな。」
「うん…、でも本当に友子が涼を…?」
「後で言うよ、とりあえずここから離れた方が安全だ。移動中はこられないだろう。」
「…涼、本当に友子が…?ねぇ…、教えてよ…。」
恵は涼とのプリクラを見て、涙しながらつぶやいた。
「なぁ?恵、友子の住所知っているか?」
恵は突然の質問に首をかしげ、一抹の不安感を彼に抱いた。
「えっ…?知らないけど…、風山君の方が詳しいでしょ?」
「そうなんだけど新しい住所は住所録見ないとわからねぇ、家にあるから取りに帰るか。」
「家って…!それっ危ないんじゃ…。」
恵は再び冷や汗を流し、過ぎ去った恐怖感を再度背中につたわせた。
「大丈夫、俺は最後らしい。友子がどうして俺を最後にしたか知りたいんだよ…。」
車の中は黙った二人をあざ笑うかの様にガタガタとした音だけを反復させていた。
「なぁ…、友子って順番を守るやつだったか?」
恵は眉をひそめて「多分」と答えた、風山は開いたばかりの口をまた一文字に閉じる。
「私ら友子の事あんまり知らないんだよね…。」
例え順番通りに進んでも確実にその時はかならずくる。彼はその言い知れぬ重圧と恐怖を紛らわそうとこの様な質問をしたのだ。…一体今は何人目まで死んでいるのだろう…?
風山は恵を車に残して自宅に戻った。
「あっ…、大丈夫…?」
彼女は色々と心配している様なので、風山はなだめるように少し時間をとった。
「まぁあんまり無理しないでね、事情はよくわからないけど…。」
「あぁそれより同窓会の住所録どこにあるか知らないか?」
「え?同窓会の住所録は荒田さんの遺品だから綾子さんに渡したんじゃないの?」
「あ!そうだった、同窓会終わった後にビデオとかは彼女に…まさか…!」
風山は血相を変えて飛び出し、車へ駆け込んだ。
東奔西走な風山の姿に、恵はただ寝ている時の様に突然起こされた様な顔をしていた。
「急ぐぞ!俺は住所録を綾子に渡したんだ、あれなら友子の住所もわかるはずだ。」
「急ぐ必要ないと思うよ、綾子ちゃんなら最後の方だろうし。」
「…?どうして?」
「綾子ちゃん優しいから友子と目立たないように少し仲良しだったみたいだし。」
「なら安全かもな…ただし、彼女が住所録を持っていなければの話だと思うぜ。」
「どう言う事…?」
「いくら友子でも全員の住所は覚えてないだろう?涼はいじめの主催者だし、俺は同窓会の副幹事だ、綾子は友達だった…でも他の人の住所はわからないだろ?」
「じゃあ綾子が次に!?」
「あぁ、友子が全員に仕返しする気なら…急ごう!時間がない!」
─急いで走る二人、ようやく綾子の住むマンションの部屋の前まできた。
「頼む、間に合ってくれ!」
風山は真っ先に呼び鈴を鳴らした。ブ~ッブ~ッブ~ッ!あせってドアノブをまわしたがドアは鍵がかかっていなかったためゆっくりドアが開いた。中は光のない世界だった。
「あっ…開いてる…?」
風山はクツを脱ぎ、そろそろと手探りで電気のスイッチを探した。続けて恵も恐る恐る家に入った。家の中は人の残り香さえないようなほど静寂だ。
「綾ちゃんいてる~?留守かな…。」
カチッ、恵の背後でスイッチを押す音がした。パチッパチッパッ…
「…!?あっ…や…?」
遺憾千万だが、一点を凝視した綾子が居間で死んでいた。
「…私…死にたくない…。」
恵は涙を赤い目に潤ませた。立場が逆転した友子と自分達を惨めに痛感しながら…。
「…ない…、住所録が…。DVDもっ!」
「…どうして?どうしてこんなことに…。」
「くそっ…、これじゃ俺の番が来るのも時間の問題だな…。とりあえず友子の元住んでいた所に行ってみよう、何かわかるかもしれない。」
二人は何も語らない死体を背に感じながら、泰然自若を必死で装った。
コンコン…ガチャ、中から小奇麗な女の人が出てきた。表札には『藤田』とある…、やはり岡本一家はもうここにはいない…勿論友子も…。
「何でしょうか?」
夜遅くの訪問にも関わらず、全く嫌な顔せずその女の人は優しい笑顔で応対してくれた。
「すいません…、以前こちらに住まわれていた岡本さんについて何か知りませんか?」
「えぇ…、ですが、よそ様のことなので…。岡本さんとはどう言うご関係ですか?」
「…っと同級生です、彼女の住所の手掛かりを探してまして…。」
「同級生の方ですか…、そう…。……よければ中へどうぞ…。」
彼女は二人を招き入れた、きれいなリビングにあるソファーに二人は座るよう招かれた。
「夫はちょうど一週間前から出張なんで、今は私一人なんです。」
ニコニコしながらコーヒーと茶菓子を並べて、彼女もソファーに腰をかけた。
「寂しくはないんですか?」
風山は意味不明な質問をしていた、この家の持つ癒しの力のせいか…?
「そうですね、でも明日には帰って来ますし…。あっ、つい関係ない話を…。」
「いえ、こちらこそこんな遅くにお伺いしましてすみません…。」
「確か岡本さんの話でしたね…。」
風山は緩みきった顔に緊張感を戻し、顔を引き締めた…。
「岡本さんは十年前、ある事件をきっかけに東京の方に引っ越されたんです。」
「事件…?」
「一家心中があったそうなんです…、詳しい事はわかりませんが。」
「そんな事がっ!?」
「十数年前って…、あの、それっていつ頃か詳しく解りませんか?」
「確か三月頃で…、岡本さんの娘さんが卒業式の前か前々日ぐらいだったかしら?」
「卒業前にっ!?」
二人は一気に蒼褪めて沈黙した、あの約束の日は卒業後すぐ…ならあの映像の中の友子は一家心中の後でこの世の者ではないのでは……?
「…あ、でも娘さんだけは助かったんじゃないでしょか?東京の方に引っ越されたのは一人だけみたいですし…。引越した所も一人暮しする1DKマンションみたいですし…。」
「そうですか…、友子は東京の大学だったから:こっちじゃ便が悪いしね…。」
「恵、なんでそんな事:。忘れたんじゃなかったのか?」
「なんかね…、友子と一緒の大学受けた気がするの…。」
「そうか。で、友子さんは生きている事は確かなんでしょうか?」
「さぁ…生きていたかどうかは私も知りませんし…、不動産屋の方に聞いてみてはどうでしょう?以前ここで一家心中があったことを教えてくれたのも不動産屋の方ですし…。」
「…そうですか。」
「そうそう、ついこの間あなた達と同じ様な感じで荒田と言う方もこられましたが、同じ同級生かしら?」
「荒田がここに!?…そうか、あいつも住所がわからなくてここに来たのか…。」
「とにかく時間がないわ、不動産屋に行こう。あの、色々ありがとうございました。」
恵は少し焦っている様だった、風山も席を促されるまま立って礼をした。
「あの…一つよろしいですか?」
「なんでしょうか…?」
風山は振り向き返り、足を止めた。
「その友子さんの事なんですが…、心中事件で死体は母親しかあがらなかったそうなんです。父親は心中事件の少し前に死んだらしくて、長女は事件以後誰一人見ていないそうなんです…。あ、あくまで越して来た時に聞いた噂なんで本当のところはどうか…。」
「でしたら…死んだんじゃないんでしょうか…?」
「えぇ…、でも住所の変更や大学の入学手続きはされたらしくて。今住んでいる所は誰が尋ねても留守なのに、家賃はきちんと振り込まれてるって言うから変な話よね…?」
なんて気味の悪い話だろう…、二人はこの話を心には止めておかないよう消去した。
「…そう…ですね、お世話になりました。それでは、おやすみなさい…。」
二人は暖かさに満ちた家を名残惜しみながら後にした。しかし、車の中に戻った二人は再び顔を怖がらせていた。消去したはずのあの話は、余計な想像の格好の材料でしかない。
「なぁ恵…、お前どう思う?」
先に堪えきれなくなったのは風山だった、恵は体を一瞬ビクつかせ冷静を装った。
「どうって…。」
彼は最悪な想像ばかり頭の中で廻らせていた、同時にあの映像まで再演されている。
「あんま言いたくないんだけどさぁ…。」
「やめて!」
どうやら彼女も同じことを考えていたらしい、すぐに話を強制的に断った。風山は口に出してしまうと本当になりそうな最悪な創造を、なぜか無性にぶちまきたくなっていた。
それ自体に意味も悪意もなかった。言い知れぬ恐怖を明らかにしなければと言うよく解らない感情だった。…彼の限界点は意外に早く突破したらしい。
「…友子は…もう死んでいるんじゃないの…か?」
「もうやめてよっ!」
彼女は激しく取り乱した、沈黙を連れたまま車は夜の道路を疾走する…。ピリリピリリ携帯電話がその沈黙を世間知らずな若者の様に我が物顔で切り裂いた。 ピッ
「はい、もしもし…。えっ…?何て今っ…っ…そんな…。うん、じゃあね…。」
プッ 恵は肩を落として俯いてしまった。
「瀬田さんが死んでたんだって…、今何番目なんだろうね。」
風山は前を見たまま何も言わなかった。ただ、ギリギリと歯を食い縛っている音がするだけだ…。恵はうつむいたまま動かなくなった。今何人死んだかなんて考えたくもない。
「…悪りぃ…、限界だ。どっかで休もう、このままじゃぁ交通事故で死んでしまう…。」
「そうだね…、私は車の運転できないし。」
車は近くのビジネスホテルに入り、二人は死ぬ事なく朝を迎えた。
「なぁ…?どうして綾子は仲良かったのに殺されたんだろうな…。」
「住所録があったからじゃないの…?」
「でも、あいつはイジメていたやつを標的にするはずだろ?綾子は殺す必要ないだろ?」
「仲良しって言っても皆でいじめている時は同じ様にしていたからじゃない?」
「そうなのかな…?第一なんで俺が最後なんだ?」
彼は再び自分が最後の標的だということに疑問を湧き上がらせているようだった。
「心あたりないの?」
「いや…これと言って…、思い出せないだけかも知れない。」
「でもさぁ、どして不動産屋の人が住所を教えてくれるんだろうね?」
「そうだな…、個人情報を簡単にしゃべるはずないんだけど…。」
「もう私覚悟できてるからさ、順番なんて気にせず調べに行こうよ。」
「そうだな、わから無い事が多過ぎる。友子の事がわかればなんとかできるかも…。」
風山の携帯にはメールで三人の死が通達されていた、クラスは全部で三十二人…。
二人は荒田も尋ねたという不動産屋で経緯を話してみた。すると、一人の男が奥へ招いてくれた。恰幅の良い白髪混じりの男に誘われるがまま、二人は部屋に入った。
ややにごりのある緑茶と、黄砂のようなきな粉をまとったわらび餅が深緑の陶器に盛られ二人の前に置かれた。応対としては過剰とも思えるサービスだった。
「私、担当の川田重蔵と申します。今日はわざわざ遠くからお越しになられたそうで…そうだ、新婚さんにぴったりな良い物件があるんですよ。」
風山は飲んでいたお茶のせいでむせてしまった。
「ゴホッゴホッ!」
「違いますよ!同級生です、高校の時の単なる同級生です。」
「違った?こりゃ失敬!アハハハハ!」
高笑いする川田を二人は変なおやじと思いつつ、岡本一家について聞いてみる事にした。
「…岡本さんの事ですか、あんた達は悪い人じゃなさそうだし…お話しましょう。」
「え?本当に良いんですか…、あまり人に話せる様な事じゃないんじゃ…?」
「ハハハ、気にしなさんな。藤田さんにも話はしてありますし、大丈夫ですよ!」
(まぁ…あの人なら人が良いから悪い噂が立っても気にしないだろうな…。)
川田は立ち上がり棚から資料を取り出して、テーブルの上に開けた。どうやら新聞の切り抜きで、日付けは200X年二月二十七日。川田は指ざしで説明した。
「ここに家事で母子心中の記事があるでしょう、結構大きな火事でしたよ…。」
風山の最悪な想像が現実になる瞬間だった、一家心中のあった日はやはり皆で遊んだ日だった。つまりあのビデオに映った彼女は実体ではないと言う事だ…。
「岡本さん父親が事業に失敗して暴力を振るう様になったらしんですよ、母親の稼ぎで暮らしていたみたいですが一年ぐらいで家賃も滞納しがちになりましてね…。娘さんも受験に失敗して、まぁお気の毒な話ですよ…。」
「受験に失敗…?で、友子さんはどうなさったんですか?」
「どうやら東京に移り住んだみたいです、友子さんの名義でマンションも借りられてます。あー…、でも私は一度も彼女を見ていないんですよ。手続きは全てお母さんと一月頃にされましたし、友子さん本人は一度も見てないんです。しかし…、どうして受験に失敗されたのか…。友子さんは相当優秀で東京大学も楽勝でいける程だったそうなのに…。」
「…。」
「そう言えばもうお昼ですね…、お昼ご一緒にどうですか?ご馳走しますよ。」
「えっ…?そんな、初対面なのに…。」
「暗い顔をしている人を見ると放っておけなくてね、何を不安に思っているかは知りませんが物件を探すなら是非わが不動産屋をよろしく♪」
「ハハハハハ!」
二人は久々に笑った、お昼を食べ終わり深く礼をして。岡本友子が一人暮ししていると言うマンションに向けて車を走らせた。
「しかし、変わった人だったな!」
風山はボルドー産の白ワインを一本開けているため上機嫌だ。ちなみに飲酒運転で確実に捕まるアルコール量である。飲酒運転は良くない、状況が異常でもしかり。
「昼間から飲めるなんてもうないかもね♪」
彼女もシェリー酒や焼酎を4・5杯飲み干している。お酒を飲んでから一時間ぐらい休憩を取ったため日は暮れ始めていた。休憩を取っても、飲んだら乗らない…これ常識。
「着くのは夜中になるなぁ、そろそろだと思うんだけどなんか来ない気もしてきたぜ…。」
「そう言えば私、社長さんの話で思い出したことあるんだよね…。」
「どんな事だ?」
「私と友子、同じ大学を受験してたのは言ったよね?」
「あっ?あぁ、やっぱりそうだったのか?」
「うん、センターも本試験も一緒だった。確か本試験が二月ぐらいにあって…」
「そうか、それなら事件前だしな。」
「それでね…、思い出したの。奨学生の定員が一人余分になって…、友子が落とされた事を…。」
彼女は何かに媚びる様に暗い顔をして、小刻みに震えていた。
「その後に一家心中か…、つくづく不幸が続いてたんだな…。」
彼も深い溝に溜まる暗黒を顔に漂わせ、伏し目がちになった。
「…っ…しが…、…っ…たの…。」
「えっ?今何か言ったか?」
「私が…私、カンニングしたの…友子の答案を…。」
彼女は見えない影に必死に懺悔しながら、言葉に謝罪の心を詰め込んでいる様だった。
「なんだって…?」
「私…自信なくて…、友子が家の為に頑張ってるなんて知らなかったの。優等生ぶっているんだって…思ってた。…いえ、決め付けていた…。」
「そんな事を…」
「友子は同じ学校だし、名前も私は『音川』だからすぐ後ろの席だった…。」
「それで・・:?」
「試験が始まっても私は目の前の問題に手も足もでなかった…。でも、マークシートだからいっそデタラメに書こうかと思ったけど…。丸見えだったの…。友子の答案が…。気付いたら私…、彼女のイスに軽い蹴りをいれて…カンニングしてた…。」
風山は彼女の話に相槌をうつ事ができなくなった…。いや…しなくなったのだ。
「…………………。」
「カンニングはバレなかったわ…。それどころか私は好成績で奨学生として入学できる事に…。でもね、私は合格さえできりゃ良かった!偶然見えなかった一問がたまたま正解だったから…、友子の家庭がさぁ…んな・・・にさぁ…なっているって…。」
彼女はもはや話もできない程涙が溢れ出していた。涙は赤陽の紅に染まり、彼女の蒼冷めた頬とはあまりにも対照的であった…。友子にとってはどれ程の屈辱だっただろう…?
廃れ行く岡本家に唯一残された最後の希望、粉骨砕身してようやくそれを現実に変えようとしていた友子は、またしてもイジメによってブチ壊されたのだ…。絶望と崩壊に満たされて行く岡本の家族を風山は頭の中でシミュレートしながら車を運転していた。
「ただいま~、美加ちゃんかなぁ~♪」
奥からひょこっと茶髪の女性が現れた、風山の彼女は家で同棲していた。
「そうだよぉ~。」
抱き合う二人、風山は同窓会の後味悪い感じを消す為か、長いキスをした。
「あっそうだ、女の人が尋ねてきたよぉ?」
風山は吹き上がる嫌な予感を必死で否定しながら、美加の顔をのぞきこんだ。
「えっ…?」
「本当だよ!ついさっき友子って言う人が来たの、ずっと下向いてて顔よくわかんなかったけど知り合いな…。」
風山はつい先程の湧き上がる最悪を同窓会と同じ状態でフラッシュバックしていた。彼女の話など『友子』の名前が出た瞬間にプツリと途絶えてしまっている。
「…っ…ってねぇ?聞いてる?ねぇっ!」
「…っ!?あっ…?うん。」
風山は我に返った、誰かの悪戯だろうと思って平常心に戻した。だが、涌き出る冷や汗を止める事はできない。どんどん恐怖で体が冷めていく、温かい日常はもうどこにもない。
「大丈夫…?あ、そう言えば最後に来るって伝えてくださいだって…。」
「…さ…いご?」
「意味わかんないよね?」
猫の様に無邪気な彼女と対照的に、風山は震えが止まらなかった。
ごく自然な恐怖だった。
(まてよ最後って…?それじゃあ他のやつの所に…涼!?そうだ彼女が危ない!)
彼はまとわりつく彼女を乱暴に振り切り、電話に飛びついた。
「ほんっと今日は最悪だったわ、ねぇ聞いてるの…?」
「今俺バイトで忙しいからまた後にしてくれ、じゃあなっ!」
プップーップーッ、電話は一方的に切られた。
「たくっ!何よ彼女の話の途中で切りやがって!」 ピーンポーンピーンポーン
「誰かな…?こんな時間に…。」
ガチャ…、目の前には二つ括りの暗い感じをまとった女性がスッと立っていた。
「あの?誰ですか?」
チリリリリンッ!チリリリンッ!家の中の電話が激しく鳴るのが聞えた。
「あっ電話が…用があるんなら早く…。」
「やっと会えた…。」
「誰…、…っ…えっ…ちょっ…?」
目の前の女はゆっくりと顔をあげその全てを彼女にさらけた、涼は気がどんどん遠のき電話の呼び鈴もどこか遠くへ…。その場へ力なくへたり込んでいった。
「私ね…すごく苦しんだの、もうダメなの…、苦しくて苦しくて…ねぇ?聞いてるの…?本当に苦しいの…、私は今もあなたにイジメられっぱなしなの…。ねぇ…謝って…、苦しいの…、私を楽にしてよ…ねぇ?もう死んじゃったの?もっと苦しんでくれなきゃ…。」
…トゥルルル…トゥルルル…プッ
「只今留守にしております、メッセー…」 カチャ
「留守…?大丈夫かな…でも、友子はどうして俺を最後にしたんだ…?」
「どうしたの?変だよ何か…。」
心配そうに彼を見つめる美加、風山はでかける用意をしだした。
「えっ!?どこ行くの!?」
「ちょっと用事だ。」
そそくさと出ていった風山を美加は寂しげに見送った。
「浮気かなぁ…?でも顔が蒼冷めてたし…、どうしたんだろう…。」
風山は急いで車に乗って涼の家へ向かった。
「ハァッ…ハァッ…!?…涼っ!」
玄関は開けっぱなしだった。彼女の体は一点を凝視したまま冷たい通路に突っ伏していた。恐らく体は元気なのだ。しかし、精神が死に至っているのだろう。
「…くっ…!やっぱり…。」
風山は胸ポケットから携帯電話を取り出して恵にかけた、次は彼女なんじゃ…。
「もしもし、どうしたの?」
「はぁっはぁっ…涼が死んでしまった…。」
「えっ……!?」
「とりあえず俺が行くまで誰も家に入れるな!次はお前かもしれない!」
「うっうん…わかった。」
ピッ…恵は携帯を握り締めただ泣き崩れ、その迫り来る恐怖と親友の死に絶望した。
ピーンポーンピーンポーン…。呼び鈴が手招きをしている。恵は玄関のドアノブを握って混乱の極地に汗をにじませた。板一枚向こうに居るのは風山か、それとも…?
ピーンポーンピーンポーン、再び鳴る呼び鈴は脅迫めいた感じだった。彼女は手をガタガタと震えさせ、冷たい汗をダラダラと流し硬直していた。…コンコンコン!
「俺だ!無事か!?」
風山の声だ…!彼女は一気に安心してドアを開け放った。風山は肩で息をしていた。よほど急いできたらしい。嫌な恐怖心が彼の顔を見て、彼女はどれほど和らいだだろう。
「よかった…。」
「えっ…?それはこっちの台詞だよ、とにかく次は恵じゃなかったみただな。」
「うん…、でも本当に友子が涼を…?」
「後で言うよ、とりあえずここから離れた方が安全だ。移動中はこられないだろう。」
「…涼、本当に友子が…?ねぇ…、教えてよ…。」
恵は涼とのプリクラを見て、涙しながらつぶやいた。
「なぁ?恵、友子の住所知っているか?」
恵は突然の質問に首をかしげ、一抹の不安感を彼に抱いた。
「えっ…?知らないけど…、風山君の方が詳しいでしょ?」
「そうなんだけど新しい住所は住所録見ないとわからねぇ、家にあるから取りに帰るか。」
「家って…!それっ危ないんじゃ…。」
恵は再び冷や汗を流し、過ぎ去った恐怖感を再度背中につたわせた。
「大丈夫、俺は最後らしい。友子がどうして俺を最後にしたか知りたいんだよ…。」
車の中は黙った二人をあざ笑うかの様にガタガタとした音だけを反復させていた。
「なぁ…、友子って順番を守るやつだったか?」
恵は眉をひそめて「多分」と答えた、風山は開いたばかりの口をまた一文字に閉じる。
「私ら友子の事あんまり知らないんだよね…。」
例え順番通りに進んでも確実にその時はかならずくる。彼はその言い知れぬ重圧と恐怖を紛らわそうとこの様な質問をしたのだ。…一体今は何人目まで死んでいるのだろう…?
風山は恵を車に残して自宅に戻った。
「あっ…、大丈夫…?」
彼女は色々と心配している様なので、風山はなだめるように少し時間をとった。
「まぁあんまり無理しないでね、事情はよくわからないけど…。」
「あぁそれより同窓会の住所録どこにあるか知らないか?」
「え?同窓会の住所録は荒田さんの遺品だから綾子さんに渡したんじゃないの?」
「あ!そうだった、同窓会終わった後にビデオとかは彼女に…まさか…!」
風山は血相を変えて飛び出し、車へ駆け込んだ。
東奔西走な風山の姿に、恵はただ寝ている時の様に突然起こされた様な顔をしていた。
「急ぐぞ!俺は住所録を綾子に渡したんだ、あれなら友子の住所もわかるはずだ。」
「急ぐ必要ないと思うよ、綾子ちゃんなら最後の方だろうし。」
「…?どうして?」
「綾子ちゃん優しいから友子と目立たないように少し仲良しだったみたいだし。」
「なら安全かもな…ただし、彼女が住所録を持っていなければの話だと思うぜ。」
「どう言う事…?」
「いくら友子でも全員の住所は覚えてないだろう?涼はいじめの主催者だし、俺は同窓会の副幹事だ、綾子は友達だった…でも他の人の住所はわからないだろ?」
「じゃあ綾子が次に!?」
「あぁ、友子が全員に仕返しする気なら…急ごう!時間がない!」
─急いで走る二人、ようやく綾子の住むマンションの部屋の前まできた。
「頼む、間に合ってくれ!」
風山は真っ先に呼び鈴を鳴らした。ブ~ッブ~ッブ~ッ!あせってドアノブをまわしたがドアは鍵がかかっていなかったためゆっくりドアが開いた。中は光のない世界だった。
「あっ…開いてる…?」
風山はクツを脱ぎ、そろそろと手探りで電気のスイッチを探した。続けて恵も恐る恐る家に入った。家の中は人の残り香さえないようなほど静寂だ。
「綾ちゃんいてる~?留守かな…。」
カチッ、恵の背後でスイッチを押す音がした。パチッパチッパッ…
「…!?あっ…や…?」
遺憾千万だが、一点を凝視した綾子が居間で死んでいた。
「…私…死にたくない…。」
恵は涙を赤い目に潤ませた。立場が逆転した友子と自分達を惨めに痛感しながら…。
「…ない…、住所録が…。DVDもっ!」
「…どうして?どうしてこんなことに…。」
「くそっ…、これじゃ俺の番が来るのも時間の問題だな…。とりあえず友子の元住んでいた所に行ってみよう、何かわかるかもしれない。」
二人は何も語らない死体を背に感じながら、泰然自若を必死で装った。
コンコン…ガチャ、中から小奇麗な女の人が出てきた。表札には『藤田』とある…、やはり岡本一家はもうここにはいない…勿論友子も…。
「何でしょうか?」
夜遅くの訪問にも関わらず、全く嫌な顔せずその女の人は優しい笑顔で応対してくれた。
「すいません…、以前こちらに住まわれていた岡本さんについて何か知りませんか?」
「えぇ…、ですが、よそ様のことなので…。岡本さんとはどう言うご関係ですか?」
「…っと同級生です、彼女の住所の手掛かりを探してまして…。」
「同級生の方ですか…、そう…。……よければ中へどうぞ…。」
彼女は二人を招き入れた、きれいなリビングにあるソファーに二人は座るよう招かれた。
「夫はちょうど一週間前から出張なんで、今は私一人なんです。」
ニコニコしながらコーヒーと茶菓子を並べて、彼女もソファーに腰をかけた。
「寂しくはないんですか?」
風山は意味不明な質問をしていた、この家の持つ癒しの力のせいか…?
「そうですね、でも明日には帰って来ますし…。あっ、つい関係ない話を…。」
「いえ、こちらこそこんな遅くにお伺いしましてすみません…。」
「確か岡本さんの話でしたね…。」
風山は緩みきった顔に緊張感を戻し、顔を引き締めた…。
「岡本さんは十年前、ある事件をきっかけに東京の方に引っ越されたんです。」
「事件…?」
「一家心中があったそうなんです…、詳しい事はわかりませんが。」
「そんな事がっ!?」
「十数年前って…、あの、それっていつ頃か詳しく解りませんか?」
「確か三月頃で…、岡本さんの娘さんが卒業式の前か前々日ぐらいだったかしら?」
「卒業前にっ!?」
二人は一気に蒼褪めて沈黙した、あの約束の日は卒業後すぐ…ならあの映像の中の友子は一家心中の後でこの世の者ではないのでは……?
「…あ、でも娘さんだけは助かったんじゃないでしょか?東京の方に引っ越されたのは一人だけみたいですし…。引越した所も一人暮しする1DKマンションみたいですし…。」
「そうですか…、友子は東京の大学だったから:こっちじゃ便が悪いしね…。」
「恵、なんでそんな事:。忘れたんじゃなかったのか?」
「なんかね…、友子と一緒の大学受けた気がするの…。」
「そうか。で、友子さんは生きている事は確かなんでしょうか?」
「さぁ…生きていたかどうかは私も知りませんし…、不動産屋の方に聞いてみてはどうでしょう?以前ここで一家心中があったことを教えてくれたのも不動産屋の方ですし…。」
「…そうですか。」
「そうそう、ついこの間あなた達と同じ様な感じで荒田と言う方もこられましたが、同じ同級生かしら?」
「荒田がここに!?…そうか、あいつも住所がわからなくてここに来たのか…。」
「とにかく時間がないわ、不動産屋に行こう。あの、色々ありがとうございました。」
恵は少し焦っている様だった、風山も席を促されるまま立って礼をした。
「あの…一つよろしいですか?」
「なんでしょうか…?」
風山は振り向き返り、足を止めた。
「その友子さんの事なんですが…、心中事件で死体は母親しかあがらなかったそうなんです。父親は心中事件の少し前に死んだらしくて、長女は事件以後誰一人見ていないそうなんです…。あ、あくまで越して来た時に聞いた噂なんで本当のところはどうか…。」
「でしたら…死んだんじゃないんでしょうか…?」
「えぇ…、でも住所の変更や大学の入学手続きはされたらしくて。今住んでいる所は誰が尋ねても留守なのに、家賃はきちんと振り込まれてるって言うから変な話よね…?」
なんて気味の悪い話だろう…、二人はこの話を心には止めておかないよう消去した。
「…そう…ですね、お世話になりました。それでは、おやすみなさい…。」
二人は暖かさに満ちた家を名残惜しみながら後にした。しかし、車の中に戻った二人は再び顔を怖がらせていた。消去したはずのあの話は、余計な想像の格好の材料でしかない。
「なぁ恵…、お前どう思う?」
先に堪えきれなくなったのは風山だった、恵は体を一瞬ビクつかせ冷静を装った。
「どうって…。」
彼は最悪な想像ばかり頭の中で廻らせていた、同時にあの映像まで再演されている。
「あんま言いたくないんだけどさぁ…。」
「やめて!」
どうやら彼女も同じことを考えていたらしい、すぐに話を強制的に断った。風山は口に出してしまうと本当になりそうな最悪な創造を、なぜか無性にぶちまきたくなっていた。
それ自体に意味も悪意もなかった。言い知れぬ恐怖を明らかにしなければと言うよく解らない感情だった。…彼の限界点は意外に早く突破したらしい。
「…友子は…もう死んでいるんじゃないの…か?」
「もうやめてよっ!」
彼女は激しく取り乱した、沈黙を連れたまま車は夜の道路を疾走する…。ピリリピリリ携帯電話がその沈黙を世間知らずな若者の様に我が物顔で切り裂いた。 ピッ
「はい、もしもし…。えっ…?何て今っ…っ…そんな…。うん、じゃあね…。」
プッ 恵は肩を落として俯いてしまった。
「瀬田さんが死んでたんだって…、今何番目なんだろうね。」
風山は前を見たまま何も言わなかった。ただ、ギリギリと歯を食い縛っている音がするだけだ…。恵はうつむいたまま動かなくなった。今何人死んだかなんて考えたくもない。
「…悪りぃ…、限界だ。どっかで休もう、このままじゃぁ交通事故で死んでしまう…。」
「そうだね…、私は車の運転できないし。」
車は近くのビジネスホテルに入り、二人は死ぬ事なく朝を迎えた。
「なぁ…?どうして綾子は仲良かったのに殺されたんだろうな…。」
「住所録があったからじゃないの…?」
「でも、あいつはイジメていたやつを標的にするはずだろ?綾子は殺す必要ないだろ?」
「仲良しって言っても皆でいじめている時は同じ様にしていたからじゃない?」
「そうなのかな…?第一なんで俺が最後なんだ?」
彼は再び自分が最後の標的だということに疑問を湧き上がらせているようだった。
「心あたりないの?」
「いや…これと言って…、思い出せないだけかも知れない。」
「でもさぁ、どして不動産屋の人が住所を教えてくれるんだろうね?」
「そうだな…、個人情報を簡単にしゃべるはずないんだけど…。」
「もう私覚悟できてるからさ、順番なんて気にせず調べに行こうよ。」
「そうだな、わから無い事が多過ぎる。友子の事がわかればなんとかできるかも…。」
風山の携帯にはメールで三人の死が通達されていた、クラスは全部で三十二人…。
二人は荒田も尋ねたという不動産屋で経緯を話してみた。すると、一人の男が奥へ招いてくれた。恰幅の良い白髪混じりの男に誘われるがまま、二人は部屋に入った。
ややにごりのある緑茶と、黄砂のようなきな粉をまとったわらび餅が深緑の陶器に盛られ二人の前に置かれた。応対としては過剰とも思えるサービスだった。
「私、担当の川田重蔵と申します。今日はわざわざ遠くからお越しになられたそうで…そうだ、新婚さんにぴったりな良い物件があるんですよ。」
風山は飲んでいたお茶のせいでむせてしまった。
「ゴホッゴホッ!」
「違いますよ!同級生です、高校の時の単なる同級生です。」
「違った?こりゃ失敬!アハハハハ!」
高笑いする川田を二人は変なおやじと思いつつ、岡本一家について聞いてみる事にした。
「…岡本さんの事ですか、あんた達は悪い人じゃなさそうだし…お話しましょう。」
「え?本当に良いんですか…、あまり人に話せる様な事じゃないんじゃ…?」
「ハハハ、気にしなさんな。藤田さんにも話はしてありますし、大丈夫ですよ!」
(まぁ…あの人なら人が良いから悪い噂が立っても気にしないだろうな…。)
川田は立ち上がり棚から資料を取り出して、テーブルの上に開けた。どうやら新聞の切り抜きで、日付けは200X年二月二十七日。川田は指ざしで説明した。
「ここに家事で母子心中の記事があるでしょう、結構大きな火事でしたよ…。」
風山の最悪な想像が現実になる瞬間だった、一家心中のあった日はやはり皆で遊んだ日だった。つまりあのビデオに映った彼女は実体ではないと言う事だ…。
「岡本さん父親が事業に失敗して暴力を振るう様になったらしんですよ、母親の稼ぎで暮らしていたみたいですが一年ぐらいで家賃も滞納しがちになりましてね…。娘さんも受験に失敗して、まぁお気の毒な話ですよ…。」
「受験に失敗…?で、友子さんはどうなさったんですか?」
「どうやら東京に移り住んだみたいです、友子さんの名義でマンションも借りられてます。あー…、でも私は一度も彼女を見ていないんですよ。手続きは全てお母さんと一月頃にされましたし、友子さん本人は一度も見てないんです。しかし…、どうして受験に失敗されたのか…。友子さんは相当優秀で東京大学も楽勝でいける程だったそうなのに…。」
「…。」
「そう言えばもうお昼ですね…、お昼ご一緒にどうですか?ご馳走しますよ。」
「えっ…?そんな、初対面なのに…。」
「暗い顔をしている人を見ると放っておけなくてね、何を不安に思っているかは知りませんが物件を探すなら是非わが不動産屋をよろしく♪」
「ハハハハハ!」
二人は久々に笑った、お昼を食べ終わり深く礼をして。岡本友子が一人暮ししていると言うマンションに向けて車を走らせた。
「しかし、変わった人だったな!」
風山はボルドー産の白ワインを一本開けているため上機嫌だ。ちなみに飲酒運転で確実に捕まるアルコール量である。飲酒運転は良くない、状況が異常でもしかり。
「昼間から飲めるなんてもうないかもね♪」
彼女もシェリー酒や焼酎を4・5杯飲み干している。お酒を飲んでから一時間ぐらい休憩を取ったため日は暮れ始めていた。休憩を取っても、飲んだら乗らない…これ常識。
「着くのは夜中になるなぁ、そろそろだと思うんだけどなんか来ない気もしてきたぜ…。」
「そう言えば私、社長さんの話で思い出したことあるんだよね…。」
「どんな事だ?」
「私と友子、同じ大学を受験してたのは言ったよね?」
「あっ?あぁ、やっぱりそうだったのか?」
「うん、センターも本試験も一緒だった。確か本試験が二月ぐらいにあって…」
「そうか、それなら事件前だしな。」
「それでね…、思い出したの。奨学生の定員が一人余分になって…、友子が落とされた事を…。」
彼女は何かに媚びる様に暗い顔をして、小刻みに震えていた。
「その後に一家心中か…、つくづく不幸が続いてたんだな…。」
彼も深い溝に溜まる暗黒を顔に漂わせ、伏し目がちになった。
「…っ…しが…、…っ…たの…。」
「えっ?今何か言ったか?」
「私が…私、カンニングしたの…友子の答案を…。」
彼女は見えない影に必死に懺悔しながら、言葉に謝罪の心を詰め込んでいる様だった。
「なんだって…?」
「私…自信なくて…、友子が家の為に頑張ってるなんて知らなかったの。優等生ぶっているんだって…思ってた。…いえ、決め付けていた…。」
「そんな事を…」
「友子は同じ学校だし、名前も私は『音川』だからすぐ後ろの席だった…。」
「それで・・:?」
「試験が始まっても私は目の前の問題に手も足もでなかった…。でも、マークシートだからいっそデタラメに書こうかと思ったけど…。丸見えだったの…。友子の答案が…。気付いたら私…、彼女のイスに軽い蹴りをいれて…カンニングしてた…。」
風山は彼女の話に相槌をうつ事ができなくなった…。いや…しなくなったのだ。
「…………………。」
「カンニングはバレなかったわ…。それどころか私は好成績で奨学生として入学できる事に…。でもね、私は合格さえできりゃ良かった!偶然見えなかった一問がたまたま正解だったから…、友子の家庭がさぁ…んな・・・にさぁ…なっているって…。」
彼女はもはや話もできない程涙が溢れ出していた。涙は赤陽の紅に染まり、彼女の蒼冷めた頬とはあまりにも対照的であった…。友子にとってはどれ程の屈辱だっただろう…?
廃れ行く岡本家に唯一残された最後の希望、粉骨砕身してようやくそれを現実に変えようとしていた友子は、またしてもイジメによってブチ壊されたのだ…。絶望と崩壊に満たされて行く岡本の家族を風山は頭の中でシミュレートしながら車を運転していた。