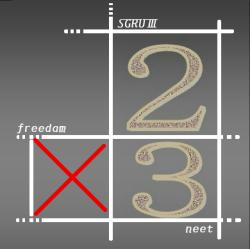ガチャガチャ…、少し中性脂肪の数値が高そうな男がDVDケースの山で何かしているのを綾子はそれを見て「またか…」と思いつつその様子をしばらく見ていた。
「ちょっと、さっきから何しているの?」
彼は自慢のビデオコレクションを整理しているらしいが、こちらから客観的に見れば散らかしていると言う方が正しい感じである。
「もう聞いてるの!?何してるのよ?」
「いやさぁ、撮影した動画が溜まってて困ってるんだよ。」
荒田は学生時代からカメラ撮影や映像加工が好きで、現在もその類の事を仕事としている。
「ラベル貼ってあるんでしょう?必要無い物捨てちゃえば?」
そう綾子は半分飽きれ気味で言ったその時、荒田の手が一つのDVDを掴んで静止した。
「何だ、このDVD?あったっけ?」と、首をかしげて言う。
綾子は仕事に行く支度をしながら、そこら辺りの管理もしていないのにヤケに物分り良く言った。付き合いが長いと、こう言う事も感覚的に理解しているのだろう。
「それってずいぶん前に『ハンディカメラで撮った映像はDVDにしたって』言った一部じゃないの?」
そう綾子に言われても荒田には合点がいかなかった、そもそもここに置いてあるのはいかがわしいDVD。妻にはバレまいとついた嘘に違いない…。そうなるとこのDVDは何なのだろか?とっ、荒田はDVDにふいと目をやった、『同窓会』と書かれたラベルが貼ってあった。同窓会……
「ああ!あれか!どうりで『同窓会』ってラベルが貼ってあんのか!」
彼は取り繕って、もっともらしい事をペラペラと彼女に言った。
「それで思い出したんだけど、もうすぐ同窓会だったんじゃない?」
そう言い終わると同時に彼女の携帯電話の呼び鈴がなった。ピリリッピリリッピッ
どうやらアラームのようである。
「早く行かなきゃ、私もうでるね!」
「そっか、俺はれがどんなやつか確かめとくよ。」
「うん、じゃぁね!」
ガチャン!慌しく出た様子からして時間だなと荒田は察し、DVDをデッキに入れた。
「懐かしいなぁ~。そういや同窓会してなかったな…ま、いっか。どれどれ…。」
彼はこうして同窓会のDVDを見る事にした。…しかし、多少疑問が残る。
彼は何故今日に限って片付けをしたのだろう?勿論、他に類を見ない程の気まぐれなら話は解るが、彼はそう言う性格を持ち合わせていない。普段から整理をしているような性格なら、どのDVDがどのような内容かわかるはず。つまり彼は普段から全く整理などせず、散らかり行くビデオを見て「あぁ片付けなきゃ」と思いつつ片付けられない性格の可能性が高い。
この性格は増え行くゴミの山を毎度見る度片付けようと思うが、後でまとめてやろうと思いながら、結局自分で片付けられる許容量を超えてしまうのが大半である。ならば何故片付けを今日に限ってしようと思ったのか?
「おさむぅ~、休みの日どこか連れて行ってよぉ~。」
「そうだなぁ~美加ちゃんの本性教えてくれたら海外にでも連れて行ってあげようかな」
「え~ぇ?じゃあ私、本性見せちゃおうかなぁ~っ?」
トゥルルルル…トゥルルル、なんとも間が悪い電話だ…。
「あ、電話だゴメン。」
「ちょっとぉ~っ!もぉ~っ!!」 カチャ
「はいもしもし風山ですが?」
「ハァハァッ…風山か…?」
随分息が切れている…。時間も深夜0時。その声は風山にとっては聞き覚えの無い様に彼は思った。しかし、ただ事ではない事は直感的に感じた。今思えば、この電話が全ての始まりとも言える…。風山は彼女に目で合図して、電話に専念した。
「たっ…ハァ…大変なんだ…ハァ…。」
「ちょっと待って?あんた誰だよ?」
「俺だよ!高校の時一緒だった荒田武だよっ!」
風山はしばらく黙った、…荒田…?
「あぁ~っ!!武じゃんか、久し振りだなおいっ!」
「そうだよっ!」
「どうしたんだ急に息切らして電話してくるなんて?」
「それが…!来週の日曜は俺らの高校の同窓会なんだ!」と、彼は力んだ。
「なんだそんな事か、そういや同窓会やってなかったな。休日だし、用事あるやつは休ませて来させりゃなんとか約束果たせるだろ。」
「…っ:おっ…おう。その辺りはお前が得意だろ?」
「ああ、でもお前よく同窓会の日なんか覚えてるよな?俺も皆で何日か決めた事は覚えてんだけど、それがいつかってのを忘れちゃってさぁ。」
そう彼は溜め息交じりに笑って言った。電話の向こうでも同じ風な笑い声が聞こえる。
「それが俺もすっかり忘れてたんだけどな、風山、高校の時にクラス全員が集まって遊んだ時の事は覚えてるか?あん時のビデオがあって、見た瞬間に思い出したんだよ!」
「…んっ?あぁ…あぁっ!やったやった!来週の日曜がちょうど約束の日って事か!?」
「そうだよ!DVDはお前の所に送っとくから同窓会の時にでも皆で見てくれ。」
「お前来ねぇの?」
「いや、行くには行くが…住所変わったやつ探すので当日遅れるかもしんねぇ。」
「でも、あん時に実家の住所は同窓会の日までなるべく変えないって約束したじゃん?」
「俺ら二十七だぜ?事情の変わったやつの目星も大体ついてんだ、高校の時新谷と一緒にチェックしたからな。」
「あいつかぁ、やたらに人脈広かったからな。」
「あぁ、それと同窓会の通知は二日前にしてくれ。」
風山は彼の言った事が、全然理解できなかった。
「はっ?なんで二日前なんだ?」
「だってさぁ、お前が忘れてるぐらいの同窓会だぜ?早く知らせたら盛り上がんねぇ~だろっ!?だからギリギリに通知しようぜ!」
彼はまるで高校生の頃のように、悪ふざけっぽく言った。
「それもそうだな、突然知らせた方が盛り上がるよな!」
風山もまた、彼と同じように心の中をあの頃に陶酔させて言った。
「あぁ、だから二日前に頼むぜ。二日もあれば事は足りるだろ?要注意人物は今から俺が片付けるから後は任せたぜ。」
「あぁ!高校の時の約束通り最高な同窓会にしような!」
風山が意気込んでこの会話の終幕は案外早くおとずれた。
電話を置いた荒田はメモとDVDをケースに入れてテーブルの上に置いて、話ていた通りに住所の変わったと思われる人の所へと情報を確認しに向かった。これから地獄の旅が始まるとも知らず、彼の声を最後に聞いたのが風山になると言う事も…、全てはDVDの意志だと言う事も…。
「えぇっとまずは山本、こいつは確か予備校のゼミで一緒だったな。あん時に住所は聞いたしこいつの家に行ってみるかっ!」 ブォォォォッ…
真夜中の人気の無い国道を車は走り出した。
…ふと荒田は思った、住所を聞いたりする準備はしていたのに何故同窓会の事を忘れていたのだろう…。確かあの時は同窓会に呼ぶ事が目的じゃなくて、ただ単に旧友と再開して今どこに住んでいるのかって話しで確認しただけだった…。思えば、同窓会の準備さえ忘れていて、偶然俺の性格が上手く転用されただけかもしれない…と。
ピンポーン、ガチャッ。中から明らかに肥満体型の三十近い女性が出てきた。人は良さそうだ。近眼なのだろう、セルタイプのあまりセンスの良くないメガネをしている。
「こんばんは、荒田と申します。」
彼は軽く会釈した、先程の女性もそれに呼応した。
「夜分遅くすみませんが、山本のぼるさんはいらっしゃいますか…?」
「主人ならちょうど出掛けた所で、何か急用ですか?」
「いえっ!別に急用ではないのでまた来ます、ありがとうございました。」
「えっ?ええぇ…。」
女性は少し首をかしげると扉を閉めた、荒田は急いで次に回って早く終わらせようと使命感に追いやられると言う感じでもあった。住所の確認さえ取れれば充分だ。
「次は瀬田さんか、確か俺の親戚の友達が栃木に移転したって言ってたな。詳しいことは親戚に聞けばなんとかなるだろう!」
こうして彼は高校の友人にはなるべく聞かず、身近な人もしくは自分や新谷の人脈から転居(連絡のつかなさそうな人)している人達の住所を次々確認していった。
「ふぅ~、まさか森山が秋田に越しているとはなぁ。下宿先が東京じゃなきゃ探すのもうちっと時間がかかってただろうな…。」
彼は手帳をめくる、夜は既に朝に近付き出そうとしている午前三時半…。
「もういねぇだろ…?ん~っと…岡本友子…?」
要チェックの欄に○がついているが斜線がその上から引かれ、さらにグシャグシャと上から書き潰すように消してある。よくわからないので後回しにしたものだった。
「誰だったけかな~?まぁ女の子だし、問題ありでも結構こう言うやつは化けたりするからな。とりあえず誘うだけ誘っておきゃ良いだろ?」
彼はそう言うと眠い目を凝らしてもう一度奮い立った。
「ダメだ…、誰に聞いてもわからねぇし…高校のやつが知っていても聞くに聞けないよなぁ…。転居しているのかどうかもわからないし…、とりあえず実家へ行ってみるか…。」
車を急いで岡本宅へと向かわせた、すると意外な事がわかった。現在岡本一家は数年前に事件があって長女だけが東京へ移ったらしい。他の家族はどうなったかは知らないと現在そこ(岡本の実家がもともとあった所)に住んでいた人に言われた。他に手立ても無いので彼はとりあえず長女だけが転居した東京へ行く事にした。現在住んでいた人や不動産屋の人等から情報を得るのに時間がかかり、すっかり夜中になってしまった。
ネオンがさんざめく都心からどれくらいの距離だろうか?その場所は都会っぽさが廃れた様なマンションがたたずみ、少し肌が冷えるような感覚を彼は直感的に感じた。郵便受けに「岡本」はなかったが他に手がかりはない。荒田は足早に階段を駆け上がった。
「あった、この部屋だ…。」
他の部屋も回ったが『岡本』の表札はその部屋だけだった。不動産屋等の情報から考えてもその部屋が『岡本友子』の転居先である事は恐らく確実であろう。
「でも…、こんな時間だしなぁ…起きていないかもしれない…。」
と、思いつつ呼び鈴を鳴らしてみた。ピンポーン………
「やっぱり出る訳ないか…。仕方ね、朝まで待つか。」
そこから去ろうとした瞬間、ガチャとカギの開く音がした。荒田は喜んだが、次には不安を心の中でグルグルさせた。
(どうしよう、怒らせたんじゃ…。)
こんな時間に起こされたのだ、相手が岡本ではなく全く別人であったならゲンコツの一発や二発食らうかもしれない。本人だとしても機嫌を損ねてしまったのでは?とも思った。
しかし、ドアはギィギィギィィとゆっくり隙間を作り、中から幽かに聞こえるかどうかわからない恐らく昼間なら雑音に掻き消されてなくなる程の声が漏れた。
「どうぞ…」
なんとも生力のない女性の声が聞えた。荒田は帰るのを止めて女性の部屋へと歩を進め返した。荒田がある程度ドアに近付くとドアはバタンッと閉まった、当然彼はまだ部屋に入っていない…、少し抵抗があったが思い切ってドアを開けた。ドアはとても重く、中と外の気圧の違いか早く開かずわずかに自分がちょうど入れる程度開けるのが限界だった。
部屋の中は暗く人も部屋も殆どわからない、荒田から2~3m離れた所に先程の声の主と思われる女性が立っていた。何故だか知らないが妙に部屋が冷たく寒い。
彼女はうつむいたまま言葉をあの生力のない声で再び奏で始めた。
「何ですか?」
「あっ…、え…っと」
荒田はあまりの雰囲気に圧倒され「何ですか」と聞かれて、はて何だったか自分にもよくわからなくなった。彼は全力を尽くして声を振り絞った。
「えっと…あっ!岡本さんだよね!?」
「ええ…そうです。」
会話の終わりに彼は激しい抵抗感を感じて、無理に会話を続けた。それは彼自身なんなのか全然わからなかったが、直感的に彼は意味なくそうせざるを得なかったのだ。
「さっ探すの大変だったんだ!」
彼自身は彼女の住所もわかったし早く帰りたかった、しかし会話を終わらせてはいけない、帰ってはいけないと言う自身にも意味のわからない焦りと恐怖感があった。
「そうですか…。」
会話が続かない…、薄暗い部屋に立ち尽くす二人の沈黙…。荒田の鼓動は意味なく臨界点へと跳ね上がり嫌な汗が額ににじむ。黙ってはいけない、彼は無理に声を絞り出す。
「あっ…っ…。」
何も喋る事がなくなった彼は絶望感で支配されていた。通常こんなこんな事はありえない、彼には制御できない第六感がそうさせていた。
「動画…。」
彼女はさき程よりハッキリ通る声でそう呟いた。まだうつむいたままだ。
「えっ…?」
「動画見て来てくれたんだ…。」
彼女はちょっとうれしそうだった。彼は言い知れぬ恐怖心に心臓を掌握され、何故彼女がその事を知っているのか…さらには彼女がそもそも誰なのか…そんな事を早送りする映像の様に考え続けた。…帰りたいのに足は硬直し、ただ彼女と向き合うしか術がない。
「…そうだけ…ど?」
こころとは裏腹に返答は明解だった。彼女はゆっくりと歩き出した。
「私の事覚えてる?」
何の質問なんだ?全く意味がわからない。荒田はその言葉を聞いて、必死で彼女の顔を思い出そうとしていた。わからない…、彼女は岡本友子…。でもそんな奴クラスにいたか?喋った事も、話題にもなってないし、誰とツルんでいたかもわからない。彼女が同じクラスだったのか彼には思い出せなくなっていた。
彼女はいつしか荒田の目の前にスッと立っていた…。冷たく重苦しい空気が荒田を押し潰し、彼は微動だすらできない。荒田は必死で同窓会の映像を頭の中でリプレイして彼女を探した。どこにもいない!どの場面にもどの思い出にも…。記憶のありとあるゆる引出しの中に彼女の断片など全くなかった。
「忘れたの?」
彼女は妙な優しさを含めてそう言うと荒田の手を握り絞めた。人間的な暖かさのない潤い過ぎた冷たい手を握った瞬間、彼の頭であの映像がもう一度再生された。今思うとあまりハッキリ見ていなかった気がするその映像。今度はあたかも今そこで見ているかのようにクッキリと細部まで鮮明に頭の中で上映され出した…。
荒田は自分の記憶は完璧だと自分でも間違いないと意気込んだ、彼女はやはりいないと。
しかし、途中から一人が何時からかは解らないが周囲の輪からのけ者にされ、一人でいる女の子に気がついた。荒田の記憶内にはどうも欠損してしまった人物らしく、覚えがない。
(こんな子いたっけ?)
その子のアップシーンになった、こんなシーンあったかどうか更に荒田は疑った…もしかして、この子が友子…?…友子…。彼の記憶で閉鎖されていた領域が徐々に開放されていた。それは開けてはいけない記憶の領域であるにも関わらず、一方的に開かれていく。
「思い出してくれたんだ…。」
彼女は微笑んだ様子だ。ゆっくりと顔を上げると、同時に現実と頭で起っているDVDの映像とシンクロした。どちらの彼女も荒田を冷たく直視していた。彼は全てを思い出し、えたいの知れない光景に声にならない声をおののいてあげた…。彼は急いで彼女の家を出て無我夢中で車を走らせようとしたが、ついに力尽きてハンドルに体を突っ伏した。
もう闇が明ける寸前だった、彼は死んでしまったのか…?それは定かではないが、ただもう二度と動かなかったことから考えれば死んでしまったのだろう。
「ちょっと、さっきから何しているの?」
彼は自慢のビデオコレクションを整理しているらしいが、こちらから客観的に見れば散らかしていると言う方が正しい感じである。
「もう聞いてるの!?何してるのよ?」
「いやさぁ、撮影した動画が溜まってて困ってるんだよ。」
荒田は学生時代からカメラ撮影や映像加工が好きで、現在もその類の事を仕事としている。
「ラベル貼ってあるんでしょう?必要無い物捨てちゃえば?」
そう綾子は半分飽きれ気味で言ったその時、荒田の手が一つのDVDを掴んで静止した。
「何だ、このDVD?あったっけ?」と、首をかしげて言う。
綾子は仕事に行く支度をしながら、そこら辺りの管理もしていないのにヤケに物分り良く言った。付き合いが長いと、こう言う事も感覚的に理解しているのだろう。
「それってずいぶん前に『ハンディカメラで撮った映像はDVDにしたって』言った一部じゃないの?」
そう綾子に言われても荒田には合点がいかなかった、そもそもここに置いてあるのはいかがわしいDVD。妻にはバレまいとついた嘘に違いない…。そうなるとこのDVDは何なのだろか?とっ、荒田はDVDにふいと目をやった、『同窓会』と書かれたラベルが貼ってあった。同窓会……
「ああ!あれか!どうりで『同窓会』ってラベルが貼ってあんのか!」
彼は取り繕って、もっともらしい事をペラペラと彼女に言った。
「それで思い出したんだけど、もうすぐ同窓会だったんじゃない?」
そう言い終わると同時に彼女の携帯電話の呼び鈴がなった。ピリリッピリリッピッ
どうやらアラームのようである。
「早く行かなきゃ、私もうでるね!」
「そっか、俺はれがどんなやつか確かめとくよ。」
「うん、じゃぁね!」
ガチャン!慌しく出た様子からして時間だなと荒田は察し、DVDをデッキに入れた。
「懐かしいなぁ~。そういや同窓会してなかったな…ま、いっか。どれどれ…。」
彼はこうして同窓会のDVDを見る事にした。…しかし、多少疑問が残る。
彼は何故今日に限って片付けをしたのだろう?勿論、他に類を見ない程の気まぐれなら話は解るが、彼はそう言う性格を持ち合わせていない。普段から整理をしているような性格なら、どのDVDがどのような内容かわかるはず。つまり彼は普段から全く整理などせず、散らかり行くビデオを見て「あぁ片付けなきゃ」と思いつつ片付けられない性格の可能性が高い。
この性格は増え行くゴミの山を毎度見る度片付けようと思うが、後でまとめてやろうと思いながら、結局自分で片付けられる許容量を超えてしまうのが大半である。ならば何故片付けを今日に限ってしようと思ったのか?
「おさむぅ~、休みの日どこか連れて行ってよぉ~。」
「そうだなぁ~美加ちゃんの本性教えてくれたら海外にでも連れて行ってあげようかな」
「え~ぇ?じゃあ私、本性見せちゃおうかなぁ~っ?」
トゥルルルル…トゥルルル、なんとも間が悪い電話だ…。
「あ、電話だゴメン。」
「ちょっとぉ~っ!もぉ~っ!!」 カチャ
「はいもしもし風山ですが?」
「ハァハァッ…風山か…?」
随分息が切れている…。時間も深夜0時。その声は風山にとっては聞き覚えの無い様に彼は思った。しかし、ただ事ではない事は直感的に感じた。今思えば、この電話が全ての始まりとも言える…。風山は彼女に目で合図して、電話に専念した。
「たっ…ハァ…大変なんだ…ハァ…。」
「ちょっと待って?あんた誰だよ?」
「俺だよ!高校の時一緒だった荒田武だよっ!」
風山はしばらく黙った、…荒田…?
「あぁ~っ!!武じゃんか、久し振りだなおいっ!」
「そうだよっ!」
「どうしたんだ急に息切らして電話してくるなんて?」
「それが…!来週の日曜は俺らの高校の同窓会なんだ!」と、彼は力んだ。
「なんだそんな事か、そういや同窓会やってなかったな。休日だし、用事あるやつは休ませて来させりゃなんとか約束果たせるだろ。」
「…っ:おっ…おう。その辺りはお前が得意だろ?」
「ああ、でもお前よく同窓会の日なんか覚えてるよな?俺も皆で何日か決めた事は覚えてんだけど、それがいつかってのを忘れちゃってさぁ。」
そう彼は溜め息交じりに笑って言った。電話の向こうでも同じ風な笑い声が聞こえる。
「それが俺もすっかり忘れてたんだけどな、風山、高校の時にクラス全員が集まって遊んだ時の事は覚えてるか?あん時のビデオがあって、見た瞬間に思い出したんだよ!」
「…んっ?あぁ…あぁっ!やったやった!来週の日曜がちょうど約束の日って事か!?」
「そうだよ!DVDはお前の所に送っとくから同窓会の時にでも皆で見てくれ。」
「お前来ねぇの?」
「いや、行くには行くが…住所変わったやつ探すので当日遅れるかもしんねぇ。」
「でも、あん時に実家の住所は同窓会の日までなるべく変えないって約束したじゃん?」
「俺ら二十七だぜ?事情の変わったやつの目星も大体ついてんだ、高校の時新谷と一緒にチェックしたからな。」
「あいつかぁ、やたらに人脈広かったからな。」
「あぁ、それと同窓会の通知は二日前にしてくれ。」
風山は彼の言った事が、全然理解できなかった。
「はっ?なんで二日前なんだ?」
「だってさぁ、お前が忘れてるぐらいの同窓会だぜ?早く知らせたら盛り上がんねぇ~だろっ!?だからギリギリに通知しようぜ!」
彼はまるで高校生の頃のように、悪ふざけっぽく言った。
「それもそうだな、突然知らせた方が盛り上がるよな!」
風山もまた、彼と同じように心の中をあの頃に陶酔させて言った。
「あぁ、だから二日前に頼むぜ。二日もあれば事は足りるだろ?要注意人物は今から俺が片付けるから後は任せたぜ。」
「あぁ!高校の時の約束通り最高な同窓会にしような!」
風山が意気込んでこの会話の終幕は案外早くおとずれた。
電話を置いた荒田はメモとDVDをケースに入れてテーブルの上に置いて、話ていた通りに住所の変わったと思われる人の所へと情報を確認しに向かった。これから地獄の旅が始まるとも知らず、彼の声を最後に聞いたのが風山になると言う事も…、全てはDVDの意志だと言う事も…。
「えぇっとまずは山本、こいつは確か予備校のゼミで一緒だったな。あん時に住所は聞いたしこいつの家に行ってみるかっ!」 ブォォォォッ…
真夜中の人気の無い国道を車は走り出した。
…ふと荒田は思った、住所を聞いたりする準備はしていたのに何故同窓会の事を忘れていたのだろう…。確かあの時は同窓会に呼ぶ事が目的じゃなくて、ただ単に旧友と再開して今どこに住んでいるのかって話しで確認しただけだった…。思えば、同窓会の準備さえ忘れていて、偶然俺の性格が上手く転用されただけかもしれない…と。
ピンポーン、ガチャッ。中から明らかに肥満体型の三十近い女性が出てきた。人は良さそうだ。近眼なのだろう、セルタイプのあまりセンスの良くないメガネをしている。
「こんばんは、荒田と申します。」
彼は軽く会釈した、先程の女性もそれに呼応した。
「夜分遅くすみませんが、山本のぼるさんはいらっしゃいますか…?」
「主人ならちょうど出掛けた所で、何か急用ですか?」
「いえっ!別に急用ではないのでまた来ます、ありがとうございました。」
「えっ?ええぇ…。」
女性は少し首をかしげると扉を閉めた、荒田は急いで次に回って早く終わらせようと使命感に追いやられると言う感じでもあった。住所の確認さえ取れれば充分だ。
「次は瀬田さんか、確か俺の親戚の友達が栃木に移転したって言ってたな。詳しいことは親戚に聞けばなんとかなるだろう!」
こうして彼は高校の友人にはなるべく聞かず、身近な人もしくは自分や新谷の人脈から転居(連絡のつかなさそうな人)している人達の住所を次々確認していった。
「ふぅ~、まさか森山が秋田に越しているとはなぁ。下宿先が東京じゃなきゃ探すのもうちっと時間がかかってただろうな…。」
彼は手帳をめくる、夜は既に朝に近付き出そうとしている午前三時半…。
「もういねぇだろ…?ん~っと…岡本友子…?」
要チェックの欄に○がついているが斜線がその上から引かれ、さらにグシャグシャと上から書き潰すように消してある。よくわからないので後回しにしたものだった。
「誰だったけかな~?まぁ女の子だし、問題ありでも結構こう言うやつは化けたりするからな。とりあえず誘うだけ誘っておきゃ良いだろ?」
彼はそう言うと眠い目を凝らしてもう一度奮い立った。
「ダメだ…、誰に聞いてもわからねぇし…高校のやつが知っていても聞くに聞けないよなぁ…。転居しているのかどうかもわからないし…、とりあえず実家へ行ってみるか…。」
車を急いで岡本宅へと向かわせた、すると意外な事がわかった。現在岡本一家は数年前に事件があって長女だけが東京へ移ったらしい。他の家族はどうなったかは知らないと現在そこ(岡本の実家がもともとあった所)に住んでいた人に言われた。他に手立ても無いので彼はとりあえず長女だけが転居した東京へ行く事にした。現在住んでいた人や不動産屋の人等から情報を得るのに時間がかかり、すっかり夜中になってしまった。
ネオンがさんざめく都心からどれくらいの距離だろうか?その場所は都会っぽさが廃れた様なマンションがたたずみ、少し肌が冷えるような感覚を彼は直感的に感じた。郵便受けに「岡本」はなかったが他に手がかりはない。荒田は足早に階段を駆け上がった。
「あった、この部屋だ…。」
他の部屋も回ったが『岡本』の表札はその部屋だけだった。不動産屋等の情報から考えてもその部屋が『岡本友子』の転居先である事は恐らく確実であろう。
「でも…、こんな時間だしなぁ…起きていないかもしれない…。」
と、思いつつ呼び鈴を鳴らしてみた。ピンポーン………
「やっぱり出る訳ないか…。仕方ね、朝まで待つか。」
そこから去ろうとした瞬間、ガチャとカギの開く音がした。荒田は喜んだが、次には不安を心の中でグルグルさせた。
(どうしよう、怒らせたんじゃ…。)
こんな時間に起こされたのだ、相手が岡本ではなく全く別人であったならゲンコツの一発や二発食らうかもしれない。本人だとしても機嫌を損ねてしまったのでは?とも思った。
しかし、ドアはギィギィギィィとゆっくり隙間を作り、中から幽かに聞こえるかどうかわからない恐らく昼間なら雑音に掻き消されてなくなる程の声が漏れた。
「どうぞ…」
なんとも生力のない女性の声が聞えた。荒田は帰るのを止めて女性の部屋へと歩を進め返した。荒田がある程度ドアに近付くとドアはバタンッと閉まった、当然彼はまだ部屋に入っていない…、少し抵抗があったが思い切ってドアを開けた。ドアはとても重く、中と外の気圧の違いか早く開かずわずかに自分がちょうど入れる程度開けるのが限界だった。
部屋の中は暗く人も部屋も殆どわからない、荒田から2~3m離れた所に先程の声の主と思われる女性が立っていた。何故だか知らないが妙に部屋が冷たく寒い。
彼女はうつむいたまま言葉をあの生力のない声で再び奏で始めた。
「何ですか?」
「あっ…、え…っと」
荒田はあまりの雰囲気に圧倒され「何ですか」と聞かれて、はて何だったか自分にもよくわからなくなった。彼は全力を尽くして声を振り絞った。
「えっと…あっ!岡本さんだよね!?」
「ええ…そうです。」
会話の終わりに彼は激しい抵抗感を感じて、無理に会話を続けた。それは彼自身なんなのか全然わからなかったが、直感的に彼は意味なくそうせざるを得なかったのだ。
「さっ探すの大変だったんだ!」
彼自身は彼女の住所もわかったし早く帰りたかった、しかし会話を終わらせてはいけない、帰ってはいけないと言う自身にも意味のわからない焦りと恐怖感があった。
「そうですか…。」
会話が続かない…、薄暗い部屋に立ち尽くす二人の沈黙…。荒田の鼓動は意味なく臨界点へと跳ね上がり嫌な汗が額ににじむ。黙ってはいけない、彼は無理に声を絞り出す。
「あっ…っ…。」
何も喋る事がなくなった彼は絶望感で支配されていた。通常こんなこんな事はありえない、彼には制御できない第六感がそうさせていた。
「動画…。」
彼女はさき程よりハッキリ通る声でそう呟いた。まだうつむいたままだ。
「えっ…?」
「動画見て来てくれたんだ…。」
彼女はちょっとうれしそうだった。彼は言い知れぬ恐怖心に心臓を掌握され、何故彼女がその事を知っているのか…さらには彼女がそもそも誰なのか…そんな事を早送りする映像の様に考え続けた。…帰りたいのに足は硬直し、ただ彼女と向き合うしか術がない。
「…そうだけ…ど?」
こころとは裏腹に返答は明解だった。彼女はゆっくりと歩き出した。
「私の事覚えてる?」
何の質問なんだ?全く意味がわからない。荒田はその言葉を聞いて、必死で彼女の顔を思い出そうとしていた。わからない…、彼女は岡本友子…。でもそんな奴クラスにいたか?喋った事も、話題にもなってないし、誰とツルんでいたかもわからない。彼女が同じクラスだったのか彼には思い出せなくなっていた。
彼女はいつしか荒田の目の前にスッと立っていた…。冷たく重苦しい空気が荒田を押し潰し、彼は微動だすらできない。荒田は必死で同窓会の映像を頭の中でリプレイして彼女を探した。どこにもいない!どの場面にもどの思い出にも…。記憶のありとあるゆる引出しの中に彼女の断片など全くなかった。
「忘れたの?」
彼女は妙な優しさを含めてそう言うと荒田の手を握り絞めた。人間的な暖かさのない潤い過ぎた冷たい手を握った瞬間、彼の頭であの映像がもう一度再生された。今思うとあまりハッキリ見ていなかった気がするその映像。今度はあたかも今そこで見ているかのようにクッキリと細部まで鮮明に頭の中で上映され出した…。
荒田は自分の記憶は完璧だと自分でも間違いないと意気込んだ、彼女はやはりいないと。
しかし、途中から一人が何時からかは解らないが周囲の輪からのけ者にされ、一人でいる女の子に気がついた。荒田の記憶内にはどうも欠損してしまった人物らしく、覚えがない。
(こんな子いたっけ?)
その子のアップシーンになった、こんなシーンあったかどうか更に荒田は疑った…もしかして、この子が友子…?…友子…。彼の記憶で閉鎖されていた領域が徐々に開放されていた。それは開けてはいけない記憶の領域であるにも関わらず、一方的に開かれていく。
「思い出してくれたんだ…。」
彼女は微笑んだ様子だ。ゆっくりと顔を上げると、同時に現実と頭で起っているDVDの映像とシンクロした。どちらの彼女も荒田を冷たく直視していた。彼は全てを思い出し、えたいの知れない光景に声にならない声をおののいてあげた…。彼は急いで彼女の家を出て無我夢中で車を走らせようとしたが、ついに力尽きてハンドルに体を突っ伏した。
もう闇が明ける寸前だった、彼は死んでしまったのか…?それは定かではないが、ただもう二度と動かなかったことから考えれば死んでしまったのだろう。