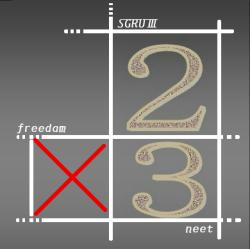どこからともなく聞こえる怒声…。
当り散らすように鳴る電話や、コピー機の発信音…
どこにでもある会社の日常が繰り返される。
「音川君!ちょっと…。」
部長の藤田が一人の女性を手招きして呼んでいる。
彼女は音川恵二十七歳、大学卒業後フリーターを辞めたばかりのOL二年生の新人である。良い男性がみつかるまでの暇潰し、今している仕事は彼女にとってはそれ程度だ。
「はい、なんですか…?」
少しつれない態度で小走りに部長の元へ行く。
「なんですか?じゃないだろ!?なんなんだこの予算報告は!間違いだらけじゃないか」
やはり、大抵こう言う時は叱られるものだ。
「すいません、やり直します。」
言い慣れたそのトーンが彼の頭を沸騰させる要因になるのは言うまでもない。
「あのねぇ、高村専務から君達を正しく指導するよう言われている俺の身にもなってみろ!お前も旭川も学生気分でやってちゃ困るんだよっ!」
(あ~ダルイ…、早く終わんないかなぁ~。)
誰から教るで訳でもなく、この年代の人は表面謝罪して、裏面では“柳の如く”なのが上等手段なのだ。相手にしない事でストレスを最小限にくいとめてしまう。
「あ~っ、もうまたシクちゃった!」
「私ら本当苦手っつうか身が入らないよねぇ~。特に事務作業とかさぁ~。」
彼女は高校時代から親友の旭川涼、以前は化粧品を扱う会社に勤めていたが、私が誘うとあっさりこの会社にくらがえした。
「よっこいしょっ!」
ちょうど中高年と言うぐらいの年齢に見える男が、何の断りも無く二人の楽しい昼食にずうずうしく割行った。
「!?」
「専務っ!」
「いやぁ~っ、良い天気だねぇっ!おっ、タコさんウインナー!ちょっともらうよ!」
顔に脂汗をにじませた中年男は了解を得ずに、指でウインナーを取り上げて口に運んだ。
「ちょっ…!」
「いやぁ~うまいうまい!良い嫁さんになれるよ!」
そう言うと高村は恵の肩に手を置いた。
(このオヤジィ~!)
「あっ!そうだメグ、まだ会計の書類ができてなかったんだ!行こっメグ!」
「うっ…うんっ!」
二人は弁当をイソイソと片付けて、走り去っていった。
「働き者だなぁ~ハハハハハ!」
(あ~助かった!)
彼女は言い様の無い嫌悪感を未だに感じながら、涼と顔を見合わせた。
「ありがとぉ~涼!」
「気をつけなよ恵~、ほんとあのオヤジ腹立よね。目つきがエロイし。」
「あっ!そうだ、今度の日曜日に一緒に食事行かない?私オゴるよ。」
「えっ!?やった、なんか無いとヤル気でないよ私!」
馴れ合いの日常、ただ過ぎて行く時。平平凡凡は骨頂を極め、今日も赤陽が地に沈む。
よそ行きの服装で会社からの束縛をいくらか開放して、待ち合わせの約束をした都内のカフェテリアへ午後の一時を過ごす…彼女達のささやかな幸せだ。
「お待たせぇ~っ!」
恵は足早にこちらへ来る涼に向かって、少し照れながら手を振り返した。
「もう~遅いよぉ~、朝のケーキバイキング終っちゃったよ~?」
「ゲェ~!?マジで~っ!?ちょっと服選んでたら遅くなっちゃってぇ…。」
「涼って高校の時もそんな理由で遅刻してたよねぇ♪」
「別に良いじゃ~ん、あっ私ミルフィーユとブルマンで。」
「ナニその組み合わせ!?超変!てか、にゃにゃにゃにゃ~いっ!」
二人は談笑を繰り返して、ホコリのように積もった不満を燃焼させ顔も明るくなった。
「高校って言ったらさぁ、私卒業してから皆とあんまり会ってないんだよねぇ。」
「私も~、綾子とかどうしてるんだろね~?」
「なんかナースやってるらしいよ、瀬和さんから聞いたから多分そうなんじゃない?」
「そうなんだ~、皆変わってくんだよねぇ~。ところでさぁその服…」
二人の会話はとめどなく続き、すっかり夜になった頃…彼女達の噂する“綾子”も自分の人生を彼女なりに人生を楽しんでいた…。
当り散らすように鳴る電話や、コピー機の発信音…
どこにでもある会社の日常が繰り返される。
「音川君!ちょっと…。」
部長の藤田が一人の女性を手招きして呼んでいる。
彼女は音川恵二十七歳、大学卒業後フリーターを辞めたばかりのOL二年生の新人である。良い男性がみつかるまでの暇潰し、今している仕事は彼女にとってはそれ程度だ。
「はい、なんですか…?」
少しつれない態度で小走りに部長の元へ行く。
「なんですか?じゃないだろ!?なんなんだこの予算報告は!間違いだらけじゃないか」
やはり、大抵こう言う時は叱られるものだ。
「すいません、やり直します。」
言い慣れたそのトーンが彼の頭を沸騰させる要因になるのは言うまでもない。
「あのねぇ、高村専務から君達を正しく指導するよう言われている俺の身にもなってみろ!お前も旭川も学生気分でやってちゃ困るんだよっ!」
(あ~ダルイ…、早く終わんないかなぁ~。)
誰から教るで訳でもなく、この年代の人は表面謝罪して、裏面では“柳の如く”なのが上等手段なのだ。相手にしない事でストレスを最小限にくいとめてしまう。
「あ~っ、もうまたシクちゃった!」
「私ら本当苦手っつうか身が入らないよねぇ~。特に事務作業とかさぁ~。」
彼女は高校時代から親友の旭川涼、以前は化粧品を扱う会社に勤めていたが、私が誘うとあっさりこの会社にくらがえした。
「よっこいしょっ!」
ちょうど中高年と言うぐらいの年齢に見える男が、何の断りも無く二人の楽しい昼食にずうずうしく割行った。
「!?」
「専務っ!」
「いやぁ~っ、良い天気だねぇっ!おっ、タコさんウインナー!ちょっともらうよ!」
顔に脂汗をにじませた中年男は了解を得ずに、指でウインナーを取り上げて口に運んだ。
「ちょっ…!」
「いやぁ~うまいうまい!良い嫁さんになれるよ!」
そう言うと高村は恵の肩に手を置いた。
(このオヤジィ~!)
「あっ!そうだメグ、まだ会計の書類ができてなかったんだ!行こっメグ!」
「うっ…うんっ!」
二人は弁当をイソイソと片付けて、走り去っていった。
「働き者だなぁ~ハハハハハ!」
(あ~助かった!)
彼女は言い様の無い嫌悪感を未だに感じながら、涼と顔を見合わせた。
「ありがとぉ~涼!」
「気をつけなよ恵~、ほんとあのオヤジ腹立よね。目つきがエロイし。」
「あっ!そうだ、今度の日曜日に一緒に食事行かない?私オゴるよ。」
「えっ!?やった、なんか無いとヤル気でないよ私!」
馴れ合いの日常、ただ過ぎて行く時。平平凡凡は骨頂を極め、今日も赤陽が地に沈む。
よそ行きの服装で会社からの束縛をいくらか開放して、待ち合わせの約束をした都内のカフェテリアへ午後の一時を過ごす…彼女達のささやかな幸せだ。
「お待たせぇ~っ!」
恵は足早にこちらへ来る涼に向かって、少し照れながら手を振り返した。
「もう~遅いよぉ~、朝のケーキバイキング終っちゃったよ~?」
「ゲェ~!?マジで~っ!?ちょっと服選んでたら遅くなっちゃってぇ…。」
「涼って高校の時もそんな理由で遅刻してたよねぇ♪」
「別に良いじゃ~ん、あっ私ミルフィーユとブルマンで。」
「ナニその組み合わせ!?超変!てか、にゃにゃにゃにゃ~いっ!」
二人は談笑を繰り返して、ホコリのように積もった不満を燃焼させ顔も明るくなった。
「高校って言ったらさぁ、私卒業してから皆とあんまり会ってないんだよねぇ。」
「私も~、綾子とかどうしてるんだろね~?」
「なんかナースやってるらしいよ、瀬和さんから聞いたから多分そうなんじゃない?」
「そうなんだ~、皆変わってくんだよねぇ~。ところでさぁその服…」
二人の会話はとめどなく続き、すっかり夜になった頃…彼女達の噂する“綾子”も自分の人生を彼女なりに人生を楽しんでいた…。