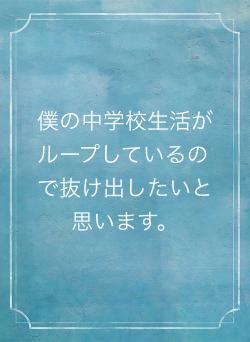週明け月曜日だと言うのに雨。
朝からどんよりした雰囲気が漂う中、高校へと向かう。
いつも早めにきているため、人がまばらの昇降口を通り、下駄箱を開ける。
うん。開けたのはいいんだ。開けたのは。
俺はそこにある物をどうにかしようとして、なぜか俊介を電話で呼んだ。
「あのさあ、俊介。」
『まず“もしもし”だろ、バカ。で、朝っぱらからなんのご用件ですかご主人様。なんでもいたしますよ。』
「変なキャラになりきるな。で、早速本題なんだが、下駄箱の中に綺麗な綺麗な不純物も何もない氷がピッタリ入っていたらどうする?」
『は?なに言ってるの?まあ、俺だったら先生に言うけど。』
「じゃあ、そうするわ。じゃあな。」
『ちょ、待て、なにがあったn』
ブツッ。
俺は昨日に引き続き、無理やり電話を切ってから、上履きを履かずに職員室へと向かった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「本当だ。バカげた話だから嘘だと思ったが、まさか本当に氷が下駄箱に。しかも、ただの氷じゃないな、これ。業務用か? どうやって運んだんだ……。恨みでも買ったか?」
「本当ですって。なにもやってませんよ。」
まあ、氷→水→雨と無理やり繋げていくと親衛隊の可能性があるがそれは言わないでおこう。
ただ、ちょうどこの生徒指導の教師がきてくれて本当に良かった。おかげで野次馬が少なくて済むし。
「まあ、今までにないことだからなにもいえん。ただ、今日早くきた人が犯人の可能性が高いな。」
「まあ、氷ですしね。」
「ましてや、こんな大きな物よく運べたよな…。あ、防犯カメラ!」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先生はすぐに防犯カメラを確認。
「……終わったな、あいつ。ほんとなにやってるんだ?お前は見覚え無いのかこいつに?」
先生が呆れ顔でつぶやく。
あ〜、終わったね。これは。あの親衛隊の自称幹部で俺に前絡んできた奴の1人がわざわざ親に頼んだのか車で氷をはこんできている姿がみられた。
「そういえば、あの自称変態集団に絡まれて…」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
そして授業が2時間目まで潰れて今に至る。
雨音親衛隊については先生も知っていたようで、今度全員集めて指導するとかしないとか。大体が上級生なのでまあ、こっちとしては上級生&雨音親衛隊の圧で攻めてくるあいつらが減るのかもと思うと嬉しいっちゃ嬉しい。
そのまま、教室へ帰ってきたのはいいが。
なにこれ。み…ず?
ツルッと綺麗に滑って一回転し、特に騒ぐこともなく奇跡的に頭と背中を打って気絶した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「お〜い、湊。大丈夫か〜?」
俊介の顔が天井に現れる。あ、俺が寝てるのか。
「まずはごめんよな。水浸しのせいで滑ってお前を持ち上げられなくて運べなかったこと。」
「おい、半分重いって言ってるようなもんだろ。」
「そして、お前の机の中の氷をどうにかどかそうとして、床に落として割ったことを。」
「…?おい、机の中どうなってる?」
慌てて聞く。めっちゃ大切にしているラノベは絶対自宅外に出さないが、学校の読書用で少し持ってきている。そして、土曜にそれを机の中に忘れていまに至るとすると。
「ギャアアアアアアーーーー」
机から取り出されたのは、土曜に置き忘れたラノベの残骸。俺の心の支えが、ただの水の塊になっていた。それを見た俺は、そのまま叫んでもう一度失神した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「…くん?…湊くん?」
声に気づいた俺は、パッと目が覚めて飛び起きる。
みたことの…ある天井。保健室だ。
横を見ると、ん?手を…?
その視線に気づいた雨音は慌てて手を離す。
「ご、ごめん。心配でついつい。」
心配で手を握ってしまうなんて親衛隊が聞いたらみんな仮病使いそうだな。と思うのは心の中だけにしておいて。
「俺のラノベは?」
恐る恐る聞く。まあ、結果は知っていた。
「え〜っとね。紙が水でくしゃくしゃになって…。」
よし、もう聞かないでおこう。俺の心が痛む。
「でさ、氷置いてあったくらいだから、湊くんになにがあったか全部話して。」
俺は仕方なく全てを話す。
「は?なんで氷?私の雨音って言う名前から連想するとか馬鹿じゃない?」
「まあまあ、憶測だから分かりませんが。」
「すごいよね、湊くんも。あの悲惨なラノベを見た瞬間気絶しちゃって…。まさかの授業2時間分寝てたし。」
「ラノベに命かけてたからな。まあ、家にある奴をやられるよりマシだが。」
「へえ、意外と男子だね。で、はい。これ。」
適当な意見が返ってきた後、レジ袋を渡された。
中には、あの行列のできる売店の人気カレーパンと揚げパン。
「うわ、これ買うの大変だったんじゃ…?」
「大丈夫。ほら、私の分もあるし、先生の許可もとってるから一緒に食べよ。」
そして、俺は白いシャツにカレーを見事墜落させたのであった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ようやく、放課後。
もう散々なことでいっぱいだった。
『今日は一人で帰らせるの安心できないから一緒に帰ろう』
と言うことで、雨の中相合傘している。
「本当に大丈夫?目が死んでるよ。」
「大丈夫だ。俺の右手がある限り。」
「やっぱりダメそうだね……。まあ、安静にしなさいよ」
「ありがとうございます、雨音様」
「なんなのその“様”呼び!」
「もう俺の精神状態がやばいからとっとと家にかえんなさい。」
軽口を叩き合っているうちに、気づけば彼女の家の前。
「本当に、ここまでで大丈夫?」
「大丈夫。ありがとな」
一人になってから、ふと空を見上げる。
しとしと降る雨は相変わらず嫌いだ。
けど、雨音と歩く雨だけは――まだ、嫌いになれないかもしれない。
朝からどんよりした雰囲気が漂う中、高校へと向かう。
いつも早めにきているため、人がまばらの昇降口を通り、下駄箱を開ける。
うん。開けたのはいいんだ。開けたのは。
俺はそこにある物をどうにかしようとして、なぜか俊介を電話で呼んだ。
「あのさあ、俊介。」
『まず“もしもし”だろ、バカ。で、朝っぱらからなんのご用件ですかご主人様。なんでもいたしますよ。』
「変なキャラになりきるな。で、早速本題なんだが、下駄箱の中に綺麗な綺麗な不純物も何もない氷がピッタリ入っていたらどうする?」
『は?なに言ってるの?まあ、俺だったら先生に言うけど。』
「じゃあ、そうするわ。じゃあな。」
『ちょ、待て、なにがあったn』
ブツッ。
俺は昨日に引き続き、無理やり電話を切ってから、上履きを履かずに職員室へと向かった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「本当だ。バカげた話だから嘘だと思ったが、まさか本当に氷が下駄箱に。しかも、ただの氷じゃないな、これ。業務用か? どうやって運んだんだ……。恨みでも買ったか?」
「本当ですって。なにもやってませんよ。」
まあ、氷→水→雨と無理やり繋げていくと親衛隊の可能性があるがそれは言わないでおこう。
ただ、ちょうどこの生徒指導の教師がきてくれて本当に良かった。おかげで野次馬が少なくて済むし。
「まあ、今までにないことだからなにもいえん。ただ、今日早くきた人が犯人の可能性が高いな。」
「まあ、氷ですしね。」
「ましてや、こんな大きな物よく運べたよな…。あ、防犯カメラ!」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先生はすぐに防犯カメラを確認。
「……終わったな、あいつ。ほんとなにやってるんだ?お前は見覚え無いのかこいつに?」
先生が呆れ顔でつぶやく。
あ〜、終わったね。これは。あの親衛隊の自称幹部で俺に前絡んできた奴の1人がわざわざ親に頼んだのか車で氷をはこんできている姿がみられた。
「そういえば、あの自称変態集団に絡まれて…」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
そして授業が2時間目まで潰れて今に至る。
雨音親衛隊については先生も知っていたようで、今度全員集めて指導するとかしないとか。大体が上級生なのでまあ、こっちとしては上級生&雨音親衛隊の圧で攻めてくるあいつらが減るのかもと思うと嬉しいっちゃ嬉しい。
そのまま、教室へ帰ってきたのはいいが。
なにこれ。み…ず?
ツルッと綺麗に滑って一回転し、特に騒ぐこともなく奇跡的に頭と背中を打って気絶した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「お〜い、湊。大丈夫か〜?」
俊介の顔が天井に現れる。あ、俺が寝てるのか。
「まずはごめんよな。水浸しのせいで滑ってお前を持ち上げられなくて運べなかったこと。」
「おい、半分重いって言ってるようなもんだろ。」
「そして、お前の机の中の氷をどうにかどかそうとして、床に落として割ったことを。」
「…?おい、机の中どうなってる?」
慌てて聞く。めっちゃ大切にしているラノベは絶対自宅外に出さないが、学校の読書用で少し持ってきている。そして、土曜にそれを机の中に忘れていまに至るとすると。
「ギャアアアアアアーーーー」
机から取り出されたのは、土曜に置き忘れたラノベの残骸。俺の心の支えが、ただの水の塊になっていた。それを見た俺は、そのまま叫んでもう一度失神した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「…くん?…湊くん?」
声に気づいた俺は、パッと目が覚めて飛び起きる。
みたことの…ある天井。保健室だ。
横を見ると、ん?手を…?
その視線に気づいた雨音は慌てて手を離す。
「ご、ごめん。心配でついつい。」
心配で手を握ってしまうなんて親衛隊が聞いたらみんな仮病使いそうだな。と思うのは心の中だけにしておいて。
「俺のラノベは?」
恐る恐る聞く。まあ、結果は知っていた。
「え〜っとね。紙が水でくしゃくしゃになって…。」
よし、もう聞かないでおこう。俺の心が痛む。
「でさ、氷置いてあったくらいだから、湊くんになにがあったか全部話して。」
俺は仕方なく全てを話す。
「は?なんで氷?私の雨音って言う名前から連想するとか馬鹿じゃない?」
「まあまあ、憶測だから分かりませんが。」
「すごいよね、湊くんも。あの悲惨なラノベを見た瞬間気絶しちゃって…。まさかの授業2時間分寝てたし。」
「ラノベに命かけてたからな。まあ、家にある奴をやられるよりマシだが。」
「へえ、意外と男子だね。で、はい。これ。」
適当な意見が返ってきた後、レジ袋を渡された。
中には、あの行列のできる売店の人気カレーパンと揚げパン。
「うわ、これ買うの大変だったんじゃ…?」
「大丈夫。ほら、私の分もあるし、先生の許可もとってるから一緒に食べよ。」
そして、俺は白いシャツにカレーを見事墜落させたのであった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ようやく、放課後。
もう散々なことでいっぱいだった。
『今日は一人で帰らせるの安心できないから一緒に帰ろう』
と言うことで、雨の中相合傘している。
「本当に大丈夫?目が死んでるよ。」
「大丈夫だ。俺の右手がある限り。」
「やっぱりダメそうだね……。まあ、安静にしなさいよ」
「ありがとうございます、雨音様」
「なんなのその“様”呼び!」
「もう俺の精神状態がやばいからとっとと家にかえんなさい。」
軽口を叩き合っているうちに、気づけば彼女の家の前。
「本当に、ここまでで大丈夫?」
「大丈夫。ありがとな」
一人になってから、ふと空を見上げる。
しとしと降る雨は相変わらず嫌いだ。
けど、雨音と歩く雨だけは――まだ、嫌いになれないかもしれない。