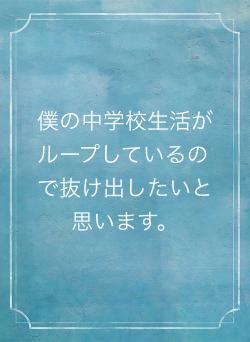今日も雨。予報ではここ1週間はずっと雨らしい。
とすると、今日もまた…
雨音が昇降口前に立っていた。
「あ、湊くん!ちょうどよかった。」
「ちょうどよかったって…何かあったんですか?」
「いや、ちょっとね。登校するときやらかしちゃって…」
と言いながら傘を見せてくる。雨音の傘は半分破れていた。
「何があったらこうなるんですか…?」
俺も流石に引くほど、それは、ボロボロになっていた。
「木に引っかかってしまって、どうにか取ろうと試みたら…。こうなっちゃって…」
なんて不器用なんだ、この人は。
結局今日も相合傘で帰ることになった。そういえば、周りから俺らってどう思われてるんだろ。噂とかになったりしないのかな?
「あ、湊くん。ちょっと、あ!待ってぶつか…」
俺は急に顔面に衝撃がきたことでようやく我に帰った。何にぶつかったのか、下がって見てみる。
まさかの、昨日の顔ぶれだ。
「お、来た来た! 雨音ちゃん、今日もそいつと帰るの?」
「マジで信じらんねー。てか湊、お前調子乗んなよ。そして、当たってくるなよ。わざとかよ。痛えんだよ。あ、お前の思考もたぶん痛いけどなw」
昨日以上に、あからさまな敵意。
俺は言い返す言葉も見つからず、ただ雨音の横に立つしかなかった。昨日の決心なんてどこへ行ってしまったのか。結局陰キャ属性のリーダーと言ってもいいくらいの奴がこんな陽キャのリーダー的なやつと絡んでるのがおかしいんだよな。
「再登場だね。迷惑だなぁ。」
と俺にこそっと言ってから、
「もう、やめてよ」
雨音は苦笑いしながら言い放った
「昨日も言ったけど、誰と帰るかは私の自由でしょ?」
「いやいや! だったら俺らのほうがいいだろ? なぁ雨音ちゃん!」
「そうそう! こんな地味男と歩くよりさ!」
くだらない冗談にしか聞こえないのに、俺の胸には鋭い棘のように刺さる。
雨音は一瞬だけ視線を伏せた後、俺の腕を軽くつついた。
「湊、行こ」
そう言って、雨音は俺の傘にすっと入り込む。え、今なんて?呼び捨て?
あいつらが見えなくなるまでずっと嫌な言葉の混ざった言葉が聞こえてくる。
「……悪いな」
「言ったでしょ。湊くんが悪いんじゃなくて、私が悪いんだから。気にしなくていいよ。あの人たち、前からちょっとしつこいんだ。本当にチクっちゃおうかな。」
笑ってはいるけど、目が少しだけ曇っているのを俺は見逃さなかった。
「いや、何もいえない俺も悪いんだ。そもそも陰キャの俺が雨音みたいな陽キャと吊り合えるわけないし…」
だから、もう今日で終わりにしよう。そう言おうとした時だ。
「そんなことないよ!!」
「え?」
「陰キャと陽キャとか関係ないし。なんでそんなので吊り合うとか決めちゃうの?親衛隊の人もクラスの人だってどうかしてる。あいつ陰キャだから話しかけないでおこうとか、そういうのよくないと思わない?私クラス委員でもあるのに、湊くんみたいな人いっぱいいるのに。何もできなくて。ごめんね。本当にごめん。こんな私でごめんね。あの人たちをどうにかできなくてごめん。クラスをちゃんとまとめられなくてごめん。本当に、本当…に……」
一回も見たことがない雨音が泣いている姿。いつもは強気な雨音が泣いてると言うことは結構やばいってことだ。俺はどうするのが正解なのだろうか?
「雨音、そこまで抱え込むなって。俺だって陰キャだけどさ、ゲームで夜更かししたり、同じ趣味のやつとくだらない話して笑ったり……そういう時間はちゃんと楽しいんだ。陰キャだからって不幸せなわけじゃない。逆に陽キャだって、別に全部が楽しいわけじゃないだろ。周りに気を使ったり、強がったりしてるやつもいる。人間なんて、結局はみんな同じ。ホモ・サピエンスだしな」
俺はちょっと笑いながら続けた。
「だからさ、分ける必要なんてないんだよ。陰キャとか陽キャとか、勝手に線引きして“上”とか“下”とか決めるから苦しくなる。雨音は優しいし、ちゃんとみんなを見てる。それだけで十分すげぇことだと思う。それに、もしクラスでいじめが起きたり差別が広がったりしたら、その時は怒っていい。でも“自分のせい”だなんて思うな。雨音がいるから、あのクラスはちゃんと回ってるんだ。俺、そう思ってる」
言いながら、雨音の涙が止まるのを待った。
「……だからさ。泣くなよ」
ん?なんか雨音の様子がまたおかしくなったような...?
見るとなぜかさっきとまでは違い、少し笑っていた。
「何に笑ってるんだよ、雨音」
「いや、ホモ・サピエンスまでくるのはないでしょ。フフッ。あー、やっぱり湊くんおもしろすぎだわー。」
「泣き止んだと思ったら今度はずっと笑って...。置いて行っちゃいますよ、傘を持って。」
「私傘あるからいいけど、置いていくのはやめてね。私、湊くんと話しながら帰るの好きだし。」
――昨日よりも近い距離で、彼女と歩く。
あの時の背後から聞こえる冷やかしの声が、雨の音で消してくれればよかったのにと思いながら――
とすると、今日もまた…
雨音が昇降口前に立っていた。
「あ、湊くん!ちょうどよかった。」
「ちょうどよかったって…何かあったんですか?」
「いや、ちょっとね。登校するときやらかしちゃって…」
と言いながら傘を見せてくる。雨音の傘は半分破れていた。
「何があったらこうなるんですか…?」
俺も流石に引くほど、それは、ボロボロになっていた。
「木に引っかかってしまって、どうにか取ろうと試みたら…。こうなっちゃって…」
なんて不器用なんだ、この人は。
結局今日も相合傘で帰ることになった。そういえば、周りから俺らってどう思われてるんだろ。噂とかになったりしないのかな?
「あ、湊くん。ちょっと、あ!待ってぶつか…」
俺は急に顔面に衝撃がきたことでようやく我に帰った。何にぶつかったのか、下がって見てみる。
まさかの、昨日の顔ぶれだ。
「お、来た来た! 雨音ちゃん、今日もそいつと帰るの?」
「マジで信じらんねー。てか湊、お前調子乗んなよ。そして、当たってくるなよ。わざとかよ。痛えんだよ。あ、お前の思考もたぶん痛いけどなw」
昨日以上に、あからさまな敵意。
俺は言い返す言葉も見つからず、ただ雨音の横に立つしかなかった。昨日の決心なんてどこへ行ってしまったのか。結局陰キャ属性のリーダーと言ってもいいくらいの奴がこんな陽キャのリーダー的なやつと絡んでるのがおかしいんだよな。
「再登場だね。迷惑だなぁ。」
と俺にこそっと言ってから、
「もう、やめてよ」
雨音は苦笑いしながら言い放った
「昨日も言ったけど、誰と帰るかは私の自由でしょ?」
「いやいや! だったら俺らのほうがいいだろ? なぁ雨音ちゃん!」
「そうそう! こんな地味男と歩くよりさ!」
くだらない冗談にしか聞こえないのに、俺の胸には鋭い棘のように刺さる。
雨音は一瞬だけ視線を伏せた後、俺の腕を軽くつついた。
「湊、行こ」
そう言って、雨音は俺の傘にすっと入り込む。え、今なんて?呼び捨て?
あいつらが見えなくなるまでずっと嫌な言葉の混ざった言葉が聞こえてくる。
「……悪いな」
「言ったでしょ。湊くんが悪いんじゃなくて、私が悪いんだから。気にしなくていいよ。あの人たち、前からちょっとしつこいんだ。本当にチクっちゃおうかな。」
笑ってはいるけど、目が少しだけ曇っているのを俺は見逃さなかった。
「いや、何もいえない俺も悪いんだ。そもそも陰キャの俺が雨音みたいな陽キャと吊り合えるわけないし…」
だから、もう今日で終わりにしよう。そう言おうとした時だ。
「そんなことないよ!!」
「え?」
「陰キャと陽キャとか関係ないし。なんでそんなので吊り合うとか決めちゃうの?親衛隊の人もクラスの人だってどうかしてる。あいつ陰キャだから話しかけないでおこうとか、そういうのよくないと思わない?私クラス委員でもあるのに、湊くんみたいな人いっぱいいるのに。何もできなくて。ごめんね。本当にごめん。こんな私でごめんね。あの人たちをどうにかできなくてごめん。クラスをちゃんとまとめられなくてごめん。本当に、本当…に……」
一回も見たことがない雨音が泣いている姿。いつもは強気な雨音が泣いてると言うことは結構やばいってことだ。俺はどうするのが正解なのだろうか?
「雨音、そこまで抱え込むなって。俺だって陰キャだけどさ、ゲームで夜更かししたり、同じ趣味のやつとくだらない話して笑ったり……そういう時間はちゃんと楽しいんだ。陰キャだからって不幸せなわけじゃない。逆に陽キャだって、別に全部が楽しいわけじゃないだろ。周りに気を使ったり、強がったりしてるやつもいる。人間なんて、結局はみんな同じ。ホモ・サピエンスだしな」
俺はちょっと笑いながら続けた。
「だからさ、分ける必要なんてないんだよ。陰キャとか陽キャとか、勝手に線引きして“上”とか“下”とか決めるから苦しくなる。雨音は優しいし、ちゃんとみんなを見てる。それだけで十分すげぇことだと思う。それに、もしクラスでいじめが起きたり差別が広がったりしたら、その時は怒っていい。でも“自分のせい”だなんて思うな。雨音がいるから、あのクラスはちゃんと回ってるんだ。俺、そう思ってる」
言いながら、雨音の涙が止まるのを待った。
「……だからさ。泣くなよ」
ん?なんか雨音の様子がまたおかしくなったような...?
見るとなぜかさっきとまでは違い、少し笑っていた。
「何に笑ってるんだよ、雨音」
「いや、ホモ・サピエンスまでくるのはないでしょ。フフッ。あー、やっぱり湊くんおもしろすぎだわー。」
「泣き止んだと思ったら今度はずっと笑って...。置いて行っちゃいますよ、傘を持って。」
「私傘あるからいいけど、置いていくのはやめてね。私、湊くんと話しながら帰るの好きだし。」
――昨日よりも近い距離で、彼女と歩く。
あの時の背後から聞こえる冷やかしの声が、雨の音で消してくれればよかったのにと思いながら――