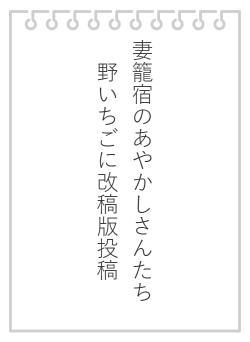・
・【10 持ち込む】
・
目を醒ますとまだ朝五時だった。
二度寝して中途半端に昭和二十年に飛び、ヨネコが近くにいなかったら嫌なので、歯磨きをしてから一階に行くと、お父さんが一人で朝ご飯を食べていた。
するとお父さんはこちらを見ずに、
「また見たのか、いつだった?」
「あっ、日付は聞かなかったけども、まだ八月一日前だった。警戒警報しか鳴っていなかったし」
「そうか、焼夷弾、調べたから分かったぞ。ということは最新の防災頭巾があるといいわけだが、アマゾンで取り寄せたの間に合うかな。なんせ日本製じゃないから」
「そんなことしてくれたんだっ」
と思いつつ、正直その発想は無かったと思った。
もっと早く自分で行動を起こしていれば、と考えたところで、
「今も日本国外では戦争が起きているから入荷待ちなんだよ、もしかしたら梨絵がすぐに注文していても間に合わないかもな」
「じゃあ意味無いじゃん」
「間に合ったら渡すから、枕元に置いておく」
「サンタクロースか、起こすの覚悟で頭に被せてよ」
でもそうか、今も日本国外では戦争が起きているんだ。
そりゃ兵器の種類も違うけども、あんな緊張感が他の国では既に起きていて。
対岸の火事だけども、やっぱり怖いと思う。いや今はそこまで他人事じゃないのかな?
教室へ着くと、凛々子が何だか含み笑いで私のことを待ち受けていた。
一体何だろうと思っていると、凛々子がバッグの中から何かを取り出した。
「はい! 手作り防災頭巾!」
なんと凛々子が私のために防災頭巾を手作りしていてくれたのだ!
凛々子は饒舌に喋る。
「まず布は基本耐火性のある布! でもガソリンが投下されるみたいだから、染みることも考えて、なんと梨絵が前にモトクロスバイクのレースみたいな何回もめくれるヤツがいいとか言っていたので、引っ張るとスルリと上の布から順番に投げ捨てられます! さらに一番下の、頭の接地面だね! ここは他の人間にはバレないと思うから! ヘルメット素材になっています! これで直撃しても大丈夫! なはず! というか包帯持ち越せるんだから被っているモノもきっと持ち越せるよね! そっちの世界に!」
「すごい! 凛々子有難う!」
「当然だよ!」
と凛々子がサムアップした時に「あっ」と思ってしまった。
何故なら、
「凛々子、指、ケガしてるよね……?」
「あぁ、これは工作というか裁縫でね、でもいいじゃん、これで梨絵と一緒だよ、お揃いだね、手のケガ!」
「そんなところまでお揃いにしなくていいのに……」
と私は申し訳無いという気持ちで言うと、凛々子は胸を張りながら、
「でも梨絵が体を張っているんだ、私だってやるべきことはやるよ!」
「そんな、凛々子が本来やるべきことじゃないじゃん……」
「だって梨絵は水泳で忙しいじゃない」
と凛々子はあっけらかんと言うので、私は力を込めて、
「凛々子だって一緒にしてくれているじゃん! プール付き添ってくれてるじゃん!」
「でも梨絵は夜も休めていないわけだから、というかアタシがやりたくてやってんの! 気にしないで!」
「有難う凛々子……」
と自然と涙がボロボロと零れ落ちてしまい、必死で拭おうとすると、
「大丈夫、梨絵は一人じゃないからさ」
「有難う、本当に有難う……」
「あとそうそう、まずは梨絵の分と思ったわけだけどもさ、確かそっちでも友達がいるんでしょ? 明日には友達の分も完成するから、上手く二個被って寝てよ」
「嘘……本当に嬉しい……手作りの防災頭巾、二個被って持ち越せるよう頑張ってみるよ」
「良かったぁ、まっ、一個作れればあとは慣れるから二個目はすぐ! すぐ!」
そう元気ハツラツに言った凛々子。
本当に凛々子には感謝しきれない。
そこからまた二人でどんな話をしたら喜ぶかという、令和の話を二人でしていった。
現在の長岡花火の話をしたら喜ぶかなとか、今の長岡市の話を詳しく話したらいいかなとか、普遍的な現在から長岡市の現在にフォーカスを当ててみたらどうかなという話をした。
放課後はいつも通り一緒にプールで泳ぎの練習をし、今日は凛々子とプールでバイバイということになった。
凛々子はついでに自分だけもう少し泳いでいくという話だ。
私は一応門限があるし、ちょっとだけやりたいことがあったので、急いで一回コンビニに寄ってから家へ戻って行った。
お母さんに軽く挨拶をして自分の部屋へ戻って、学校の宿題を済ます。
また長岡の空襲の体験記録を熟読して、その日に備える。情報はいくら詰め込んでもいいから。とにかく生き残るために必死で。
寝る前に私は凛々子が作ってくれた防災頭巾をかぶって、あとあれをポケットに入れて、眠りについた。
当たり前といった感じにまたあの場所で私はヨネコの隣で体育座りして、地面に座っていた。
木々の揺れる音はすぐにかき消すような警戒警報のサイレン。私も何だか慣れてしまった。
「また会えたね、本当は会えないほうがいいんだけどもね」
と笑ったヨネコ。
いや、
「私はヨネコに会いたいよ、ヨネコと未来の話、いっぱいしたいよ」
「有難う、じゃあ今日も聞かせて……って、防災頭巾しているんだね、リエは今日」
「うん、令和の世界の親友に作ってもらったんだ。ヨネコの分も作ってくれるって」
「そんな、何か申し訳無いよ、一度も会ったことないのに……」
「ううん、その子はリエの友達はわたしの友達ってほうだから大丈夫だよ、まあ少しだけ優劣を自分に付けてほしいって子だけども」
「何その子、わたしみたい!」
そう言って笑ったヨネコ。ヨネコもそういうほうなんだ。
というか防災頭巾の持ち込みができるということは分かった。
じゃあ二個かぶれば二個とも持ち込めるかもしれない。
いや違う、この一個をまさしく今、ヨネコに渡せばいいんだ。
「ヨネコ、この防災頭巾あげるね」
「えっ、リエのヤツじゃない!」
「いや当日二個持ち運べるか分からないから、先にヨネコに渡しておくよ。誰かに盗られないでね」
「分かった、ずっと付けているよ」
さて、かぶっている防災頭巾が持ち込めるということは当然こっちもと思い、ポケットの中を探ると案の定、入っていて、
「これ、未来のお菓子。グミって言うんだ」
と言って渡すと、ヨネコはそれをまじまじと見て、
「すごい……知らない素材に……」
とパッケージを見て言った。
「これはプラスチックという素材で今の主流だね、熱さにも冷たさにも強いんだ、加工もしやすくて」
「こんなモノもあるんだぁ」
「で、中身ね」
とチャックを開けて、中からカラフルなグミを取り出すと、ヨネコはキャッキャッと、
「すごい! 色がすごい! 本当に食べ物っ?」
「そうだよ、これ桃味で、噛むと中からさらに柔らかいソースのようなモノが出てくるよ」
「た、食べていい?」
「いいよ、食べようよ、二人で」
「桃味……」
と呟きながらヨネコはグミを口に運んだ。
ヨネコはまるで初めて炭酸を飲んだ子供のように目を光らせながら、
「甘くて美味しい!」
と叫んだ。
あんまりデカい声出すと、と思ったけども、サイレンが鳴っているから平気か。
「もっと食べていいっ? あっ! でも! 二人で!」
「いや私は向こうの世界に戻ればいつでも食べられるから大丈夫だよ」
「すごい! でも二人で食べよう!」
と言ってヨネコは可愛いなぁ、と思った。
結局私は三粒くらいにした。
ヨネコの幸せそうな顔を見れれば、それだけで十分だった。
するとヨネコが、
「この袋、わたしがもらっていい?」
「いやでも英語とか書いてあるから見つかったら大変かも」
「大丈夫、ここに基本埋めておくから。で、元気がほしい時に掘り起こして、眺めるだけだから」
そうなるといわゆるオーパーツというか、そういったものになるんじゃないかとかいろいいろ考えた結果、あまりにもヨネコの目が輝いていたので、了承することにした。
というか勝手に介入させられているんだから、これくらい別にいいでしょ。
ヨネコは嬉しそうに早速手ごろな大きさの石と手で地面を掘って、そこにこのグミの袋を埋めた、ところで、
「でもこのプラスチックって、土に還ったりしないの?」
「百年以上は平気だって話だよ、でもそれが逆に問題になっていることもあるんだ。土に還ったほうがいいからね」
「そっか、でもわたしは土に還らないでほしいなぁ」
そう言って楽しそうにそのグミの袋を埋めた場所を眺めていた。
グミの袋一個でそんなに騒ぐようなことが果たして私の人生にはあるのか。
私や今の時代の人たちは感覚が鈍化しているんじゃないか。
もっとこの世界の娯楽というかそういったモノをもっと有難がる必要があるんじゃないか。
何でもかんでも批評とかしていないで、もっと一つ一つにまず感謝する必要があるんじゃないか。
そんなことを思ってから、私はまたヨネコに未来の話をすることにした。
リバーサイド千秋の話や、長岡駅の話、バスケのスタジアムがあって、道の駅があって、長岡花火は毎年東京からも人が来るくらい有名だって。
私が長岡の花火は日本一と言えば、ヨネコは「当然でしょ!」と自分の手柄のように笑ったので、私も吹き出してしまった。
二人で笑い合って、こんな日々がずっと続けばいいのにって、本気でそう思った。
目が醒めた時に思った。きっともう八月一日はすぐそこだって。
感覚的にはあと一回、何も無い日を挟んだら……って、何も無い日なんてない。
毎日警戒警報が鳴っていて、ある意味それも鈍化している。恐怖に慣れてしまっている。
正負どちらにしても慣れてしまってはダメなんだ。常に感覚を研ぎ澄ませていないとダメなんだ。
そんなことを思いながら、歯磨きのために部屋から出ようとすると、部屋のドアの隙間から手紙があったので、読むことにした。
勿論というかお父さんからで、
『明日の夕方に俺の荷物が届くから開けてくれ。その中にはパウチに入った水が入っている。焼け石に水かもしれないが、それを持ち込んでほしい』
そうか、それも一つの手か、やっぱり自分以外の人間がいるということは素晴らしいことだ。
私一人じゃ思いつかないことをいっぱいしてくれる。
お父さんも凛々子も。
パウチに入った水も、自分で防災頭巾を作るということも私の念頭には無かった。
本当にみんなに(勿論お母さんにも包帯の時とかあったから)感謝しないといけない。
登校すると、凛々子が昨日言っていた通り、防災頭巾をもう一個くれたわけだけども、指のケガはもっと酷くなっていたので、
「作るの慣れるんじゃなかったの?」
「いやぁ、やっぱり急いでいるからさぁ」
「凛々子、無理しなくていいのに」
「無理ねぇ」
そう感慨深そうに頷いた凛々子。
いや、
「無理しないでよっ」
と私が少し強めに言うと、それを上回るように、凛々子は啖呵を切るみたいに、
「無理させてよ! 親友でしょ!」
と言ってから一息ついてから、
「まっ、そういう感じで、梨絵のためなら無理したいんだよ。だから笑顔で受け取ってよ」
「凛々子、本当に有難う……」
「まあ八月一日越えたらさ、アイス奢ってよ、いっぱい夏休み遊ぼうぜぇいっ!」
「うん! そうする!」
昼休みは久しぶりに普通の動画の話をした。
とはいっても私は見ていないので、凛々子の話だけ。
凛々子はできるだけ平然といった顔をしていたけども、どこか息詰まるように顔を歪ませる時があった。
何よりも凛々子のために生きなきゃ、と私は強くそう思った。
放課後、凛々子と一緒にプールへ行くと、係員さんがまるで私と凛々子を待ち構えるように立っていて、私は小首を傾げていると凛々子が、
「では今日はよろしくお願いします」
と頭をさげると、係員さんは奥から服を持ってきて、凛々子がそれに対して、
「保管して頂き有難うございます」
とまた頭をさげて一体何なんだと思っていると、凛々子が、
「梨絵、これ着て今日は水泳しよう。勿論梨絵だけだけども。だから目立つかも! ゴメンね!」
「いやいや! どういうこと!」
「だって服着た状態で泳げるかどうかしないとダメだし、そもそも本番と同じ服を着て練習できればいいじゃん」
と言ったところで凛々子は小声になり、
「ほら、黒で茶色で地味な感じのヤツ選んだから、戦時中でも目立たないよ」
「本当にどういうこと、凛々子っ」
「梨絵はきっと本の体験記録を熟読していて、他のことに頭が回らないだろうから、まず服で泳ぐ練習をするため私がプールに許可取りをした。そして服も買っておいた。戦時中に着ていても怪しまれないヤツねっ。あっ、事前に言わなかったのは、言ったらまた梨絵が服のお金とか言い出すと思ったから、サプライズって感じにしたんだっ」
「何でそこまで……」
「何でそこまでって何それ、あえて言ってほしいの?」
と言って不敵に笑った凛々子は、
「親友に死なれて嬉しい親友なんているはずないじゃん」
と言った。
あぁ、そんなことまでしてくれるなんて、私にそこまでの価値って別に無いでしょ。
凛々子は私の表情を見て察したのだろう、
「アタシってほら、誰彼も状況も構わず結構ボケるほうでさ、中学時代とかになったら、ちょっと浮き始めていたじゃん。そんなアタシに構ってくれるだけじゃなくて、めっちゃ上手くツッコんで人気者にしてくれたの、一生の恩だからね」
「そんなんたまたまだって」
「たまたまでも何でもいいの、アタシは梨絵がいないとダメなんだから。ゴメンね、メンヘラで」
「ううん、最高だよ、有難う」
そこから私は服に着替えて、服のまま泳ぐ練習を始めた。
どうやらそういうことにも適している服らしくて、非常に泳ぎやすかった。
練習を終えたところで凛々子が、
「その服、コインランドリーで洗って乾かそうよ」
「あ、でも門限」
「いいよ、アタシがついているよ」
と凛々子が優しく言ってくれたんだけども、私は、
「そうだ、お父さんにLINEする。お父さんにも実は言ったんだ、このこと。どうやらお父さんの家系みたいで、夢に見るヤツ」
「そうなんだ! そんなことあるんだ!」
「でもそうみたい。だからお父さんに言えば、夜に迎えに来てくれるかも。そうしたら、凛々子も送ってもらえるし」
「じゃあそうしてもらおうっと!」
と凛々子は笑った。
そのあと、二人で近くでコインランドリーに行き、なんせ乾かすヤツまでやるので、ちょっと長いのでお父さんにLINEすると快諾してもらって、帰りに寄ってくれるみたいだ。
服も乾ききったところでお父さんもやって来て、三人でお父さんの車に乗った。
お父さんが即座に、
「うちの梨絵のこと、お願いします」
とバックミラー越しに頭をさげて、
「付き合ってるみたいに言うな」
と私がツッコむと、凛々子が笑って、
「楽しいお父さんだねっ」
「いや楽しくはない」
と私がキッパリ言うと、お父さんは寂しそうに、
「結構泣くほうだから」
と言って、凛々子が爆笑した。
ちょっ、おま、恥ずかしい、これは恥ずかしい、自分が反抗期に突入した理由を思い出したと共に、私がツッコミ体質になった理由も分かってしまった。
凛々子は屈託の無い笑顔で、
「梨絵のお父さんって面白いねー」
お父さんは照れ臭そうに笑って、共感性羞恥がマックスだった。
凛々子は少し愚痴っぽく、
「うちは大家族なのにみんな生真面目な人ばっかりで」
と言ったんだけども、すぐに訂正するように、
「まっ、だからこそ防災頭巾を作る時、嫌な顔せず手伝ってくれたんだけどねっ」
「えっ、どうやって説明したの?」
「高校の課題で長岡空襲があるから、その時にこんな防災頭巾があればみたいな感じで一華さん……お母さんの妹さんに言ったりして。一華さん、ま、まあお母さんの妹さんなんだけども、監修は全部一華さんがしてくれて」
「そうなんだ、そういうことに理解がある家というのもいいね」
お父さんがウィンクしてきて、俺俺とアピールしてきたんだけどもそれは無視することにした。そもそもお父さんの家系のせいだろ。
凛々子は少し自慢げな声で、
「ひいおばあちゃんはさ、長岡空襲を実際生き抜いた人みたいで、アタシが発案の防災頭巾見たらビックリしちゃって、よろけて一瞬あわやだったんだよ」
「それは自慢げに言うことじゃないのでは」
「いやそれくらいひいおばあちゃんは画期的だって思ったんでしょ、だからちゃんとアイデアのもとは親友からって言っておいたよ、著作権は梨絵にあげる!」
「多分それを言うなら特許だね」
「勿論今のはボケだよ!」
とデカい声を出した凛々子。
いや、
「そんな小ボケ、絶対天然でしょ、今のは」
「著作権と特許を間違えるという大ボケ!」
「絶対大ボケにはならないよ、ありえる範囲だもん、だって」
「クソゥ!」
と悔しがった凛々子。
いや別にどっちでもいいんだけども、つい私がツッコミのテンションだったから論破してしまった。
そんな感じに和やかに凛々子のおうちへ着いた。
カーナビあるから勿論着くわけだけども、
「そう言えば、凛々子の家に行くのって久しぶりだね」
「まあうちはとにかく大家族だから、家が狭くてね。遊ぶといったら必ず梨絵の家だったね。最近行ってないけども」
「そうだね、まあ逆に私は一人っ子だから部屋に余裕があって。お父さんは基本土日も仕事だし、お母さんも昔はパートしていたし」
「じゃ! また明日!」
そう元気に手を振りながら、車から降りていった凛々子。
私も大きくバイバイしながら、車は発車した。
二人きりになってからお父さんが、
「良い友達ができて良かったな」
「親友ね、あとあんま恥ずかしいこと言わないで」
「そんな、結構泣くほうだから」
「それウケたと思わないで。凛々子はゲラだから大丈夫だっただけ」
「さすがに厳し過ぎる」
お父さんは肩を落とした。運転に集中してほしいな、と思っていると、お父さんが真面目なトーンで、
「もしかしたらもう会わないかもと思って手紙を流し込んだけども、読んでくれたか?」
「うん、水の入ったパウチが届くってヤツね」
「飲んだほうがいいみたいだぞ」
「うん、私も長岡の空襲という本を読んで、火災の前に行動する時は水をたらふく飲むという描写もあった」
「そうか、やっぱり俺より詳しいんだな」
「でも水の入ったパウチとか気が回らなかった、有難う、お父さん」
へへっと笑ったお父さん。それはまあキモいとして、私はお父さんの運転する車に優しく揺られて、家に着いた。
お母さんは何も言わず、お迎えしてくれた。
なんとなくお母さんの顔も緊張しているようだった。
まああのお父さんが話した”ホラ話”を覚えているとしたら、それが娘まで言い出してるかもと気付けば、表情も強張るか。
するとお母さんが迷った挙句といった感じに軽く手を伸ばしながら、
「梨絵、大丈夫なの?」
「やるべきことはやったよ」
と正直に答えると、お母さんは今にも泣き出しそうな面持ちで、
「もう! お父さん! 今日説明して!」
とお父さんのほうを向いてそう言って二階の自分の部屋へのぼっていった。
お父さんは軽く私に会釈すると、そのままお母さんを追いかけていった。
私はお風呂に入って、お母さんが用意してくれていた夕ご飯を一人で食べて、自分の部屋に戻った。
きっと猶予はあと一回、この次の次が八月一日だと思う。
凛々子が用意してくれた服に防災頭巾、服も防災頭巾も一応今日つけていこう。
もしかしたらもう今回かもしれないし。多分まだ一回猶予があると思うけども、それはなんとなくでしかないから。
服に着替えて防災頭巾をかぶって、私は眠りについた。
気が付くと、同じ防災頭巾をかぶったヨネコが隣に座っていた。
「いよいよだよ、リエ、今日が七月三十一日だよ」
と言ったところで、またしても警戒警報が鳴ったと思ったら、耳をつんざくような飛行機の音がして、えっ? と思ってしまった。
しかもまだ真昼間だ、私がここに来て歴史に介入してしまったばっかりに、変化が起きたのかと思ったら、上からビラが落ちてきた。
いやそうだった、前日にアメリカ軍のビラが落ちてくるんだった。
「これは歴史通りだよ」
と言って落ちてきたビラを掴んだ私。
ヨネコが即座に、
「すぐに偉い人に渡さないと」
と言って立ち上がって、私からビラを受け取った。
「私も一緒に行く」
「うん、お願い」
そう言って私とヨネコはビラを警察官と思われる人に渡して、またいつもの場所へ戻ってきた。
ビラが配布されたあとでも、警戒警報の音が消えず、ヨネコは震えているようだった。
するとヨネコが突然、
「ちょっと、グミの袋見るね」
と言って、埋めたところを掘り返したところで、またグミを持ってきてあげれば良かったと思った。
ヨネコはその袋を眺めて、
「まだ香りが残ってる」
「そうだね、グミの香料って強いからね」
「いつか食べられるのかな」
「グミ自体は昭和の終わり頃にはもうあると思うよ、詳しくは知らないけども。このグミは私の現代の、令和で発売されるグミだけども」
「楽しみだなぁ、グミ」
そう言ってまた袋を埋めたヨネコ。
ヨネコと会うのはこれがもう最後から二番目で、それ以降に会うことはきっと無くて。
「ヨネコ、絶対生きようね」
と私がヨネコの手を握ると、
「そう、絶対生きるよ、わたしはれいわという世の中まで生きるよっ」
「じゃあ令和になったら絶対会おうよ」
「うん、そうしよう」
その時は合言葉とかそんなものも決めずに気付いたら目が醒めていた。
目が醒めることを憎いと思うなんて思わなかった。もう少しで合言葉を決めれたはずなのに。
今回は時間にしては短かったと思うけども、しっかりもう現実は朝になっていた。
服を着替えて、歯磨きをして、一階へ降りていくとお母さんがテーブルに座って待っていた。
・【10 持ち込む】
・
目を醒ますとまだ朝五時だった。
二度寝して中途半端に昭和二十年に飛び、ヨネコが近くにいなかったら嫌なので、歯磨きをしてから一階に行くと、お父さんが一人で朝ご飯を食べていた。
するとお父さんはこちらを見ずに、
「また見たのか、いつだった?」
「あっ、日付は聞かなかったけども、まだ八月一日前だった。警戒警報しか鳴っていなかったし」
「そうか、焼夷弾、調べたから分かったぞ。ということは最新の防災頭巾があるといいわけだが、アマゾンで取り寄せたの間に合うかな。なんせ日本製じゃないから」
「そんなことしてくれたんだっ」
と思いつつ、正直その発想は無かったと思った。
もっと早く自分で行動を起こしていれば、と考えたところで、
「今も日本国外では戦争が起きているから入荷待ちなんだよ、もしかしたら梨絵がすぐに注文していても間に合わないかもな」
「じゃあ意味無いじゃん」
「間に合ったら渡すから、枕元に置いておく」
「サンタクロースか、起こすの覚悟で頭に被せてよ」
でもそうか、今も日本国外では戦争が起きているんだ。
そりゃ兵器の種類も違うけども、あんな緊張感が他の国では既に起きていて。
対岸の火事だけども、やっぱり怖いと思う。いや今はそこまで他人事じゃないのかな?
教室へ着くと、凛々子が何だか含み笑いで私のことを待ち受けていた。
一体何だろうと思っていると、凛々子がバッグの中から何かを取り出した。
「はい! 手作り防災頭巾!」
なんと凛々子が私のために防災頭巾を手作りしていてくれたのだ!
凛々子は饒舌に喋る。
「まず布は基本耐火性のある布! でもガソリンが投下されるみたいだから、染みることも考えて、なんと梨絵が前にモトクロスバイクのレースみたいな何回もめくれるヤツがいいとか言っていたので、引っ張るとスルリと上の布から順番に投げ捨てられます! さらに一番下の、頭の接地面だね! ここは他の人間にはバレないと思うから! ヘルメット素材になっています! これで直撃しても大丈夫! なはず! というか包帯持ち越せるんだから被っているモノもきっと持ち越せるよね! そっちの世界に!」
「すごい! 凛々子有難う!」
「当然だよ!」
と凛々子がサムアップした時に「あっ」と思ってしまった。
何故なら、
「凛々子、指、ケガしてるよね……?」
「あぁ、これは工作というか裁縫でね、でもいいじゃん、これで梨絵と一緒だよ、お揃いだね、手のケガ!」
「そんなところまでお揃いにしなくていいのに……」
と私は申し訳無いという気持ちで言うと、凛々子は胸を張りながら、
「でも梨絵が体を張っているんだ、私だってやるべきことはやるよ!」
「そんな、凛々子が本来やるべきことじゃないじゃん……」
「だって梨絵は水泳で忙しいじゃない」
と凛々子はあっけらかんと言うので、私は力を込めて、
「凛々子だって一緒にしてくれているじゃん! プール付き添ってくれてるじゃん!」
「でも梨絵は夜も休めていないわけだから、というかアタシがやりたくてやってんの! 気にしないで!」
「有難う凛々子……」
と自然と涙がボロボロと零れ落ちてしまい、必死で拭おうとすると、
「大丈夫、梨絵は一人じゃないからさ」
「有難う、本当に有難う……」
「あとそうそう、まずは梨絵の分と思ったわけだけどもさ、確かそっちでも友達がいるんでしょ? 明日には友達の分も完成するから、上手く二個被って寝てよ」
「嘘……本当に嬉しい……手作りの防災頭巾、二個被って持ち越せるよう頑張ってみるよ」
「良かったぁ、まっ、一個作れればあとは慣れるから二個目はすぐ! すぐ!」
そう元気ハツラツに言った凛々子。
本当に凛々子には感謝しきれない。
そこからまた二人でどんな話をしたら喜ぶかという、令和の話を二人でしていった。
現在の長岡花火の話をしたら喜ぶかなとか、今の長岡市の話を詳しく話したらいいかなとか、普遍的な現在から長岡市の現在にフォーカスを当ててみたらどうかなという話をした。
放課後はいつも通り一緒にプールで泳ぎの練習をし、今日は凛々子とプールでバイバイということになった。
凛々子はついでに自分だけもう少し泳いでいくという話だ。
私は一応門限があるし、ちょっとだけやりたいことがあったので、急いで一回コンビニに寄ってから家へ戻って行った。
お母さんに軽く挨拶をして自分の部屋へ戻って、学校の宿題を済ます。
また長岡の空襲の体験記録を熟読して、その日に備える。情報はいくら詰め込んでもいいから。とにかく生き残るために必死で。
寝る前に私は凛々子が作ってくれた防災頭巾をかぶって、あとあれをポケットに入れて、眠りについた。
当たり前といった感じにまたあの場所で私はヨネコの隣で体育座りして、地面に座っていた。
木々の揺れる音はすぐにかき消すような警戒警報のサイレン。私も何だか慣れてしまった。
「また会えたね、本当は会えないほうがいいんだけどもね」
と笑ったヨネコ。
いや、
「私はヨネコに会いたいよ、ヨネコと未来の話、いっぱいしたいよ」
「有難う、じゃあ今日も聞かせて……って、防災頭巾しているんだね、リエは今日」
「うん、令和の世界の親友に作ってもらったんだ。ヨネコの分も作ってくれるって」
「そんな、何か申し訳無いよ、一度も会ったことないのに……」
「ううん、その子はリエの友達はわたしの友達ってほうだから大丈夫だよ、まあ少しだけ優劣を自分に付けてほしいって子だけども」
「何その子、わたしみたい!」
そう言って笑ったヨネコ。ヨネコもそういうほうなんだ。
というか防災頭巾の持ち込みができるということは分かった。
じゃあ二個かぶれば二個とも持ち込めるかもしれない。
いや違う、この一個をまさしく今、ヨネコに渡せばいいんだ。
「ヨネコ、この防災頭巾あげるね」
「えっ、リエのヤツじゃない!」
「いや当日二個持ち運べるか分からないから、先にヨネコに渡しておくよ。誰かに盗られないでね」
「分かった、ずっと付けているよ」
さて、かぶっている防災頭巾が持ち込めるということは当然こっちもと思い、ポケットの中を探ると案の定、入っていて、
「これ、未来のお菓子。グミって言うんだ」
と言って渡すと、ヨネコはそれをまじまじと見て、
「すごい……知らない素材に……」
とパッケージを見て言った。
「これはプラスチックという素材で今の主流だね、熱さにも冷たさにも強いんだ、加工もしやすくて」
「こんなモノもあるんだぁ」
「で、中身ね」
とチャックを開けて、中からカラフルなグミを取り出すと、ヨネコはキャッキャッと、
「すごい! 色がすごい! 本当に食べ物っ?」
「そうだよ、これ桃味で、噛むと中からさらに柔らかいソースのようなモノが出てくるよ」
「た、食べていい?」
「いいよ、食べようよ、二人で」
「桃味……」
と呟きながらヨネコはグミを口に運んだ。
ヨネコはまるで初めて炭酸を飲んだ子供のように目を光らせながら、
「甘くて美味しい!」
と叫んだ。
あんまりデカい声出すと、と思ったけども、サイレンが鳴っているから平気か。
「もっと食べていいっ? あっ! でも! 二人で!」
「いや私は向こうの世界に戻ればいつでも食べられるから大丈夫だよ」
「すごい! でも二人で食べよう!」
と言ってヨネコは可愛いなぁ、と思った。
結局私は三粒くらいにした。
ヨネコの幸せそうな顔を見れれば、それだけで十分だった。
するとヨネコが、
「この袋、わたしがもらっていい?」
「いやでも英語とか書いてあるから見つかったら大変かも」
「大丈夫、ここに基本埋めておくから。で、元気がほしい時に掘り起こして、眺めるだけだから」
そうなるといわゆるオーパーツというか、そういったものになるんじゃないかとかいろいいろ考えた結果、あまりにもヨネコの目が輝いていたので、了承することにした。
というか勝手に介入させられているんだから、これくらい別にいいでしょ。
ヨネコは嬉しそうに早速手ごろな大きさの石と手で地面を掘って、そこにこのグミの袋を埋めた、ところで、
「でもこのプラスチックって、土に還ったりしないの?」
「百年以上は平気だって話だよ、でもそれが逆に問題になっていることもあるんだ。土に還ったほうがいいからね」
「そっか、でもわたしは土に還らないでほしいなぁ」
そう言って楽しそうにそのグミの袋を埋めた場所を眺めていた。
グミの袋一個でそんなに騒ぐようなことが果たして私の人生にはあるのか。
私や今の時代の人たちは感覚が鈍化しているんじゃないか。
もっとこの世界の娯楽というかそういったモノをもっと有難がる必要があるんじゃないか。
何でもかんでも批評とかしていないで、もっと一つ一つにまず感謝する必要があるんじゃないか。
そんなことを思ってから、私はまたヨネコに未来の話をすることにした。
リバーサイド千秋の話や、長岡駅の話、バスケのスタジアムがあって、道の駅があって、長岡花火は毎年東京からも人が来るくらい有名だって。
私が長岡の花火は日本一と言えば、ヨネコは「当然でしょ!」と自分の手柄のように笑ったので、私も吹き出してしまった。
二人で笑い合って、こんな日々がずっと続けばいいのにって、本気でそう思った。
目が醒めた時に思った。きっともう八月一日はすぐそこだって。
感覚的にはあと一回、何も無い日を挟んだら……って、何も無い日なんてない。
毎日警戒警報が鳴っていて、ある意味それも鈍化している。恐怖に慣れてしまっている。
正負どちらにしても慣れてしまってはダメなんだ。常に感覚を研ぎ澄ませていないとダメなんだ。
そんなことを思いながら、歯磨きのために部屋から出ようとすると、部屋のドアの隙間から手紙があったので、読むことにした。
勿論というかお父さんからで、
『明日の夕方に俺の荷物が届くから開けてくれ。その中にはパウチに入った水が入っている。焼け石に水かもしれないが、それを持ち込んでほしい』
そうか、それも一つの手か、やっぱり自分以外の人間がいるということは素晴らしいことだ。
私一人じゃ思いつかないことをいっぱいしてくれる。
お父さんも凛々子も。
パウチに入った水も、自分で防災頭巾を作るということも私の念頭には無かった。
本当にみんなに(勿論お母さんにも包帯の時とかあったから)感謝しないといけない。
登校すると、凛々子が昨日言っていた通り、防災頭巾をもう一個くれたわけだけども、指のケガはもっと酷くなっていたので、
「作るの慣れるんじゃなかったの?」
「いやぁ、やっぱり急いでいるからさぁ」
「凛々子、無理しなくていいのに」
「無理ねぇ」
そう感慨深そうに頷いた凛々子。
いや、
「無理しないでよっ」
と私が少し強めに言うと、それを上回るように、凛々子は啖呵を切るみたいに、
「無理させてよ! 親友でしょ!」
と言ってから一息ついてから、
「まっ、そういう感じで、梨絵のためなら無理したいんだよ。だから笑顔で受け取ってよ」
「凛々子、本当に有難う……」
「まあ八月一日越えたらさ、アイス奢ってよ、いっぱい夏休み遊ぼうぜぇいっ!」
「うん! そうする!」
昼休みは久しぶりに普通の動画の話をした。
とはいっても私は見ていないので、凛々子の話だけ。
凛々子はできるだけ平然といった顔をしていたけども、どこか息詰まるように顔を歪ませる時があった。
何よりも凛々子のために生きなきゃ、と私は強くそう思った。
放課後、凛々子と一緒にプールへ行くと、係員さんがまるで私と凛々子を待ち構えるように立っていて、私は小首を傾げていると凛々子が、
「では今日はよろしくお願いします」
と頭をさげると、係員さんは奥から服を持ってきて、凛々子がそれに対して、
「保管して頂き有難うございます」
とまた頭をさげて一体何なんだと思っていると、凛々子が、
「梨絵、これ着て今日は水泳しよう。勿論梨絵だけだけども。だから目立つかも! ゴメンね!」
「いやいや! どういうこと!」
「だって服着た状態で泳げるかどうかしないとダメだし、そもそも本番と同じ服を着て練習できればいいじゃん」
と言ったところで凛々子は小声になり、
「ほら、黒で茶色で地味な感じのヤツ選んだから、戦時中でも目立たないよ」
「本当にどういうこと、凛々子っ」
「梨絵はきっと本の体験記録を熟読していて、他のことに頭が回らないだろうから、まず服で泳ぐ練習をするため私がプールに許可取りをした。そして服も買っておいた。戦時中に着ていても怪しまれないヤツねっ。あっ、事前に言わなかったのは、言ったらまた梨絵が服のお金とか言い出すと思ったから、サプライズって感じにしたんだっ」
「何でそこまで……」
「何でそこまでって何それ、あえて言ってほしいの?」
と言って不敵に笑った凛々子は、
「親友に死なれて嬉しい親友なんているはずないじゃん」
と言った。
あぁ、そんなことまでしてくれるなんて、私にそこまでの価値って別に無いでしょ。
凛々子は私の表情を見て察したのだろう、
「アタシってほら、誰彼も状況も構わず結構ボケるほうでさ、中学時代とかになったら、ちょっと浮き始めていたじゃん。そんなアタシに構ってくれるだけじゃなくて、めっちゃ上手くツッコんで人気者にしてくれたの、一生の恩だからね」
「そんなんたまたまだって」
「たまたまでも何でもいいの、アタシは梨絵がいないとダメなんだから。ゴメンね、メンヘラで」
「ううん、最高だよ、有難う」
そこから私は服に着替えて、服のまま泳ぐ練習を始めた。
どうやらそういうことにも適している服らしくて、非常に泳ぎやすかった。
練習を終えたところで凛々子が、
「その服、コインランドリーで洗って乾かそうよ」
「あ、でも門限」
「いいよ、アタシがついているよ」
と凛々子が優しく言ってくれたんだけども、私は、
「そうだ、お父さんにLINEする。お父さんにも実は言ったんだ、このこと。どうやらお父さんの家系みたいで、夢に見るヤツ」
「そうなんだ! そんなことあるんだ!」
「でもそうみたい。だからお父さんに言えば、夜に迎えに来てくれるかも。そうしたら、凛々子も送ってもらえるし」
「じゃあそうしてもらおうっと!」
と凛々子は笑った。
そのあと、二人で近くでコインランドリーに行き、なんせ乾かすヤツまでやるので、ちょっと長いのでお父さんにLINEすると快諾してもらって、帰りに寄ってくれるみたいだ。
服も乾ききったところでお父さんもやって来て、三人でお父さんの車に乗った。
お父さんが即座に、
「うちの梨絵のこと、お願いします」
とバックミラー越しに頭をさげて、
「付き合ってるみたいに言うな」
と私がツッコむと、凛々子が笑って、
「楽しいお父さんだねっ」
「いや楽しくはない」
と私がキッパリ言うと、お父さんは寂しそうに、
「結構泣くほうだから」
と言って、凛々子が爆笑した。
ちょっ、おま、恥ずかしい、これは恥ずかしい、自分が反抗期に突入した理由を思い出したと共に、私がツッコミ体質になった理由も分かってしまった。
凛々子は屈託の無い笑顔で、
「梨絵のお父さんって面白いねー」
お父さんは照れ臭そうに笑って、共感性羞恥がマックスだった。
凛々子は少し愚痴っぽく、
「うちは大家族なのにみんな生真面目な人ばっかりで」
と言ったんだけども、すぐに訂正するように、
「まっ、だからこそ防災頭巾を作る時、嫌な顔せず手伝ってくれたんだけどねっ」
「えっ、どうやって説明したの?」
「高校の課題で長岡空襲があるから、その時にこんな防災頭巾があればみたいな感じで一華さん……お母さんの妹さんに言ったりして。一華さん、ま、まあお母さんの妹さんなんだけども、監修は全部一華さんがしてくれて」
「そうなんだ、そういうことに理解がある家というのもいいね」
お父さんがウィンクしてきて、俺俺とアピールしてきたんだけどもそれは無視することにした。そもそもお父さんの家系のせいだろ。
凛々子は少し自慢げな声で、
「ひいおばあちゃんはさ、長岡空襲を実際生き抜いた人みたいで、アタシが発案の防災頭巾見たらビックリしちゃって、よろけて一瞬あわやだったんだよ」
「それは自慢げに言うことじゃないのでは」
「いやそれくらいひいおばあちゃんは画期的だって思ったんでしょ、だからちゃんとアイデアのもとは親友からって言っておいたよ、著作権は梨絵にあげる!」
「多分それを言うなら特許だね」
「勿論今のはボケだよ!」
とデカい声を出した凛々子。
いや、
「そんな小ボケ、絶対天然でしょ、今のは」
「著作権と特許を間違えるという大ボケ!」
「絶対大ボケにはならないよ、ありえる範囲だもん、だって」
「クソゥ!」
と悔しがった凛々子。
いや別にどっちでもいいんだけども、つい私がツッコミのテンションだったから論破してしまった。
そんな感じに和やかに凛々子のおうちへ着いた。
カーナビあるから勿論着くわけだけども、
「そう言えば、凛々子の家に行くのって久しぶりだね」
「まあうちはとにかく大家族だから、家が狭くてね。遊ぶといったら必ず梨絵の家だったね。最近行ってないけども」
「そうだね、まあ逆に私は一人っ子だから部屋に余裕があって。お父さんは基本土日も仕事だし、お母さんも昔はパートしていたし」
「じゃ! また明日!」
そう元気に手を振りながら、車から降りていった凛々子。
私も大きくバイバイしながら、車は発車した。
二人きりになってからお父さんが、
「良い友達ができて良かったな」
「親友ね、あとあんま恥ずかしいこと言わないで」
「そんな、結構泣くほうだから」
「それウケたと思わないで。凛々子はゲラだから大丈夫だっただけ」
「さすがに厳し過ぎる」
お父さんは肩を落とした。運転に集中してほしいな、と思っていると、お父さんが真面目なトーンで、
「もしかしたらもう会わないかもと思って手紙を流し込んだけども、読んでくれたか?」
「うん、水の入ったパウチが届くってヤツね」
「飲んだほうがいいみたいだぞ」
「うん、私も長岡の空襲という本を読んで、火災の前に行動する時は水をたらふく飲むという描写もあった」
「そうか、やっぱり俺より詳しいんだな」
「でも水の入ったパウチとか気が回らなかった、有難う、お父さん」
へへっと笑ったお父さん。それはまあキモいとして、私はお父さんの運転する車に優しく揺られて、家に着いた。
お母さんは何も言わず、お迎えしてくれた。
なんとなくお母さんの顔も緊張しているようだった。
まああのお父さんが話した”ホラ話”を覚えているとしたら、それが娘まで言い出してるかもと気付けば、表情も強張るか。
するとお母さんが迷った挙句といった感じに軽く手を伸ばしながら、
「梨絵、大丈夫なの?」
「やるべきことはやったよ」
と正直に答えると、お母さんは今にも泣き出しそうな面持ちで、
「もう! お父さん! 今日説明して!」
とお父さんのほうを向いてそう言って二階の自分の部屋へのぼっていった。
お父さんは軽く私に会釈すると、そのままお母さんを追いかけていった。
私はお風呂に入って、お母さんが用意してくれていた夕ご飯を一人で食べて、自分の部屋に戻った。
きっと猶予はあと一回、この次の次が八月一日だと思う。
凛々子が用意してくれた服に防災頭巾、服も防災頭巾も一応今日つけていこう。
もしかしたらもう今回かもしれないし。多分まだ一回猶予があると思うけども、それはなんとなくでしかないから。
服に着替えて防災頭巾をかぶって、私は眠りについた。
気が付くと、同じ防災頭巾をかぶったヨネコが隣に座っていた。
「いよいよだよ、リエ、今日が七月三十一日だよ」
と言ったところで、またしても警戒警報が鳴ったと思ったら、耳をつんざくような飛行機の音がして、えっ? と思ってしまった。
しかもまだ真昼間だ、私がここに来て歴史に介入してしまったばっかりに、変化が起きたのかと思ったら、上からビラが落ちてきた。
いやそうだった、前日にアメリカ軍のビラが落ちてくるんだった。
「これは歴史通りだよ」
と言って落ちてきたビラを掴んだ私。
ヨネコが即座に、
「すぐに偉い人に渡さないと」
と言って立ち上がって、私からビラを受け取った。
「私も一緒に行く」
「うん、お願い」
そう言って私とヨネコはビラを警察官と思われる人に渡して、またいつもの場所へ戻ってきた。
ビラが配布されたあとでも、警戒警報の音が消えず、ヨネコは震えているようだった。
するとヨネコが突然、
「ちょっと、グミの袋見るね」
と言って、埋めたところを掘り返したところで、またグミを持ってきてあげれば良かったと思った。
ヨネコはその袋を眺めて、
「まだ香りが残ってる」
「そうだね、グミの香料って強いからね」
「いつか食べられるのかな」
「グミ自体は昭和の終わり頃にはもうあると思うよ、詳しくは知らないけども。このグミは私の現代の、令和で発売されるグミだけども」
「楽しみだなぁ、グミ」
そう言ってまた袋を埋めたヨネコ。
ヨネコと会うのはこれがもう最後から二番目で、それ以降に会うことはきっと無くて。
「ヨネコ、絶対生きようね」
と私がヨネコの手を握ると、
「そう、絶対生きるよ、わたしはれいわという世の中まで生きるよっ」
「じゃあ令和になったら絶対会おうよ」
「うん、そうしよう」
その時は合言葉とかそんなものも決めずに気付いたら目が醒めていた。
目が醒めることを憎いと思うなんて思わなかった。もう少しで合言葉を決めれたはずなのに。
今回は時間にしては短かったと思うけども、しっかりもう現実は朝になっていた。
服を着替えて、歯磨きをして、一階へ降りていくとお母さんがテーブルに座って待っていた。