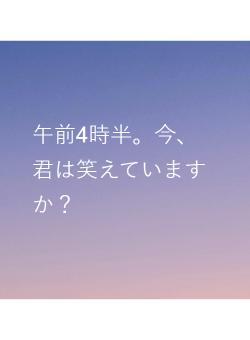一通の手紙が運命を変える。
*********
「灯里(あかり)ー!」
焚火を見ながら二時間の移動による疲れを癒していた時、コテージから天文部部長、二年の相坂(あいさか)秋帆(あきほ)に呼び出された。
今日は私の所属する天文部の天体観測合宿。山中にあるキャンプ場。冬休み七日目。二泊三日のうちの一日目。
現在二年生、昨年一年生だった四人で作った天文部。今年から一年生の貴多(きた)光志(こうし)と黒石(くろいし)深介(しんすけ)が加わり六人になった。
今二年生の四人は幼馴染で小さい頃から家族ぐるみでキャンプやグランピングをしていた。
毎回皆既月食や流星群等が見られる時期に行っていた。だからか自然と全員宇宙や天体観測が好きになっていた。
その流れで全員が同じ高校に合格したと決まったとき、天文部を作ろうと決めた。
そんな風に焚火を眺めながらこれまでを振り返っていたが、秋穂に呼ばれたら立ち上がるしかない。
重い腰を持ち上げ、秋帆のもとに向かった。
「今、先生と一年生が薪と買い忘れてた食材買いに行ってて、二年の男子組でベット組み立ててもらってるの。だから、灯里に水汲んでくるのを頼みたいんだよね」
私たちが今日過ごすのはコテージ。ここには水道が一つしかない。そのため水を他に用意しておかないと何かと不便。
よって誰かが水を汲みにいかなければならない。
みんながそれぞれ作業してくれている中、何もしないのは確かに良くない。ただ、一人で山の中へ向かうのが怖かった。
「秋帆も一緒に行こうよー。もう暗いし」
冬は昼が短い。そろそろ午後五時になる。
既に暗い。さらには山の中にあるキャンプ場であるからひらけてはいてもあまりにも光が少ない。
「私は皿洗いに行かなきゃなのよ……」
「そうだよね……。わかった! 懐中電灯ある?」
誰かが行くしかないからね。
行こう。寒いし、暗いし、怖いけど。
「売店からそのまま真っ直ぐ行くと水汲み場があるみたい。気をつけて行ってきて」
「秋穂もね」
アウトドア用のウォータージャグと懐中電灯を渡され、水汲み場に向かう。大きなキャンプ場だから水汲み場までかなり距離がある。急ごう。
懐中電灯と道に設置されているライトの光を頼りに歩いていた。
でも、なぜか一向に水汲み場まで辿り着けない。
売店を過ぎてからかなり経っている。これはおかしいと思ったときにはもう道がわからなくなっていた。
葉が揺れる音
水が流れる音
地面を踏む音
この場には私一人しかいないと強調してくる音達。
寒い 暗い 怖い
夜を越さなければならないかと思うほど現在地がわからなくなり、不安が押し寄せてきた。
小さな希望を胸に歩き続ける。しかし、やはり道はひらけない。明かりがない。
――パチ。
「あ……」
最悪な事態。懐中電灯の電池が切れた。こんなにあっけなく消えるものなのか。
ただでさえ小さな希望がマイクロ単位まで小さくなった。
今、何時なんだろう。部活の合宿だから当然スマホはない。腕時計はコテージに置いてきてしまった。
現在地も
時間も
周りに何があるのかも
わからない。
ずっと歩いていたから疲れてきた。朝早起きしてバスに揺られ、買い物をし、荷物を運んだ一日。久々に足がパンパンになっている。
もう、立ってられない。
そのまま地べたに座り込む。
きっと誰かが私の帰りが遅いことに気付き、助けに来てくれる。
たとえ、それがどれほど遅くたっていい。私がそんな弱いわけがないから。こんな短い時間じゃ凍え死なない。
強がり。
昔からの癖はいつまでも抜けないものだ。
星が綺麗だ。
なんで見えてしまうの。
本当なら今頃みんなで見ることができていたのに。
冬の大三角
こんなに綺麗に見られたのは何年振りだろう。まだ小学生の時が最後だった気がする。
山の中だと星の輝きが増して美しい。
みんなで見たかった。
ベテルギウス
プロキオン
シリウス
まだ当時は星の名前を知らなかった。
冬の大三角の存在しか知らず、星座に着目しなかった。オリオン座がはっきり見えて嬉しい。
しばらく星を見ていなかった。
ずっと下ばかり見ていた。
たまには上を見たほうがいいのだと思う。
雨かな?
頬を伝った水滴。
涙だった。
空から降ってくる何か。
星のように優しく輝きながら落ちてくる。
ひらひらと舞い降りてくる。
風が吹く。
遠くへ飛んでいってしまう。咄嗟に体が動き、追いかけていた。
足が痛むけど、なぜか立ち上がり、走っていた。
荷物を置いて。
「取れた……!」
掴んだのは手紙だった。封蝋が金色に光っている。輝きの正体だった。
誰に宛てたものかはわからないが、開けてしまった。空から降ってきた手紙。金色に輝く封蝋。好奇心が芽生えた。もう幼くないのに。
封筒の中に入っていたのは一枚の便箋だった。開いてみると、書かれた文字も金色に光っていた。
光の道を辿って――
その文章を読んだ瞬間、封蝋の光が蛍のように空を飛んだ。
直後、目の前に広がった景色はここが幻想空間なのではないかと錯覚させるほどの美しく、儚いものだった。
光の道
遠く遠く伸びていく光。地面を照らし、私をどこかへ導いてくれるように見える。
光を踏みしめると、さらに輝き、笑みを零させた。
握りしめていた便箋がさらに光った。
――大丈夫。そのまま光のとおり進んで。みんなのもとへ、一緒に帰ろう。
また長い道のりを歩く。辿る。
迷い込んだときと同じほど長く感じる。順調に進めているはずなのに。それほど遠くまで来てしまっていたようだ。
進んでいくと、赤い火の色が見えた。恐らく、キャンプ場の南側で行われていたキャンプファイヤー。コテージの反対側。
ようやく少しずつ人工の光が見えてきた。ようやく、みんなのもとへ帰れる。
懐中電灯。こちら側を照らしてきている。棒のようになった足を動かし、そちらへ走る。
「恵波先輩! よかった……!」
涙が溢れてきた。目の前にいたのは一年の貴多くん。
道が開けた瞬間、光の道が消えた。幻想的なあの世界がもうなくなってしまったのが少し悲しかった。
「先輩、泣かないでくださいよ」
そう慰めてくれる彼の手には星のチャームが付いたペンと光っている何かが握られていた。
*********
「ありがとう」
灯里先輩のことをベンチに座らせホットココアを手渡す。
灯里先輩の行方が分からなくなって五時間後、午後十時。先輩は目に涙を溜めていた。
「貴多くん」
「何ですか?」
ふいに名前を呼ばれ、驚きを隠せぬまま返答した。心臓に悪い。
何となく何を聞かれるのかは感づいていた。どうしよう。
「貴多くんはあの光のこと、何か知っているの?」
「何のことですかね」
しらばっくれてみた。だって、言えるわけない。
もし誰かに話した場合、思いっきり叱られる。存在を消される可能性すらある。それほど、危険で口外するのが禁断なこと。
「教えられないこと?」
鋭い。でも、上目遣いしながら話してくる。それに俺は弱い。
「ノーコメントで」
火照った頬を隠すために目を合わせず言葉を発する。
あ。
今、夜だった。
「とっても、幻想的な景色だったの」
目を輝かせながら話しだす先輩。幻想的な景色、どうだっていい。あなたのとっても麗しいその瞳を見つめていたい。
「星々の輝きのような明るく綺麗な道が突然つくられて、私のことを貴多くんのいるここまで導いてくれたんだよね」
あぁ。そんな輝かしい表情で褒められると言いたくなるじゃないか。先輩はずるい。どのタイミングでも可愛らしいから。
俺は、、
先輩のことが好きだ。
*********
「ねえ、灯里のこと見てない?」
深介と天文部顧問の結城(ゆうき)先生と追加の買い出しを終え、コテージに戻ってきたとき、部長から声をかけられた。
「俺ら今戻ってきたばかりっすよ」
「恵波先輩がどうかしたんですか?」
不安げな表情を浮かべる部長。
「水汲みをね、お願いしたの。でも、まだ戻ってきてなくて……」
もうとっくに日は暮れてる。不安になってくる。
「俺、探してくる」
気づけば走っていた。水汲みに行ったならいると考えられるのは水汲み場の周辺。灯里先輩のことだからきっと体力尽きて座り込んでる。だて、持久走の授業があった日の部活で疲れ果てて寝てたから。
手に持っていた懐中電灯。頼りない光。
夜空に手をかざし、目をつぶる。数多の星々を集めるように想像する。
手に集まった光の粒。もしも懐中電灯が消えたときの為、先輩の姿を全く見つけられなかったときの為。危険な状況のときの為。しっかり判断しなきゃ体が持たないから。
「恵波せんぱーい! 近くにいたら返事してください」
何一つ音が聞こえない山中。何一つ周りにあるものがはっきり見えない山中。静かに星が光っているのが見える山中。
怖かった。誰もいないから。灯里先輩に、会えないから。
俺が学校に行くのは灯里先輩に会えるから。
そのおかげで友達がたくさんできた。先輩後輩関係なく交友関係を築けた。天文部に出逢い、星が好きになった。――自分のことを好きになれた。
全て、灯里先輩のおかげ。
次第に抱いている恋愛感情が大きくなった。それでも、灯里先輩に俺は届かない。思いは届かない。
今は拝み、崇めている。それで十分だった。灯里先輩に会えるなら。
頭の中でここまでずっと誰か一人のことを考えるのは初めてだった。いわば初恋。実らなくてもいい。少しの時間だけでも一緒に過ごせればいい。それも一つの恋の形だと、俺は思っている。
どこにもいない。見つからない。時計に懐中電灯を照らし時刻を確認すると九時。
「え、俺、四時間も彷徨ってる」
これじゃ俺も迷子だ。
周りを見渡せば光は一つもなく、人の気配はない。
連絡手段は一つもない。俺自身も助けを求めることができない。
ここまで時間がかかるとは思っていなかった。すぐ見つけられると思っていた。一人で飛び込んだ俺が馬鹿だった。
灯里先輩のことがどんどん心配になり、不安になる。もう自分のことなんかどうでもいい。
使おう。
星の魔法を
空の月。
一枚の便箋。
一枚の封筒。
一番星のように輝く封蝋。
星の魔法が込められたボールペン。
祖父から受け継いだもの。
全てを合わせ、思いを込める。
先輩への手紙を作る。
キャンプ場まで導くため。
暗く、足元の悪い中作っているからしっかり届けられるかが不安だ。
出来上がった手紙は確かにキラキラと輝いた。
まずは、俺自身がキャンプ場に戻らなければそもそも導くことすらできない。
一日で二回も使えば確定で親に説教されるが、先輩の命には代えられない。
生きていく中で常に魔法を制限してきてはいたから数回使ったところで変わらない気はしている。
それでも怒られてしまうから秘密にしておこう。
今回で最後にして一生隠して生きていこう。
怒られるのはもうごめんだ。
北極星。
光を集め、矢印を作り出す。
北極星は本来、北極の方へ導いてくれるが、この魔法ではどの方角でも目的地がわかっていればどこへでも行ける。
光の矢印に沿って進む。
地図アプリのナビのようなもの。
スマホがあれば便利なものだが、部活であるからには仕方がない。
実際、誰もこのような事態になるとは想定していなかったわけだから。
誰かが動かなきゃ解決をすることはできない。
俺が、
俺が。
行動しなければ。
徐々に赤い光が見えてきた。
キャンプファイヤー。
止まるコテージの反対側で行われているキャンプファイヤー。
ずいぶん遠くまで来てしまったようだ。
開けた。
握りしめていた手紙を、
空に飛ばした。
**********