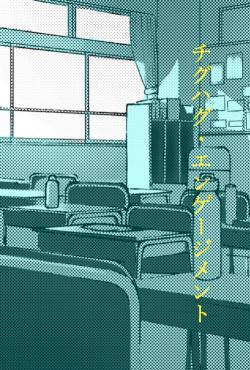一瞬にして変わる景色。
暖かく穏やかだった花園から、凍てつく氷の海に突き落とされる。そのまま深く深く沈んで海の底へ落ちていく。息がうまくできない。苦しい。目の前の景色が水面のように歪む。
『夏子。いや、いいよ。遅いし、そのまま菜乃花の家まで送るから大丈夫』
電話の向こうで交わされる自然でささいな会話。
目に浮かぶ光景はとてつもなく幸せそうに微笑み合う2人の姿。
「っ…」
私はなにをショックを受けているんだ。わかっていたでしょ。知っていたじゃないか。
こんなに優しい佑にぃちゃんに、彼女が、奥さんがいないワケがない。
それに目の前でお祝いをしたじゃないか。
色とりどりの花びらが舞う青空の下で、佑にぃちゃんの結婚式に参列して見送ったでしょ。
『じゃあ、菜乃花。大人しく待っているんだぞ』
「うん、わかっるってば。大人しく待ってる」
それでも、諦めきれない。断ち切ることができない。
「…夏子さんにも、よろしくね。あとでお礼しなきゃだ」
『あとお説教も待ってるからな』
「えぇー…いやだなー。菜乃花ちゃんは真面目で良い子なのに」
あぁ、なんてめんどくさい女なんだろうか。
私はちゃんと笑えているだろうか。
『はいはい、そうだな。じゃあ、いまから迎えにいくから』
「うん、待ってるね。佑にぃちゃん」
ぷつりと切れた電話。
煌々と光っていた画面が暗くなれば、私を照らす明かりは点々とある街灯だけになる。
「あーあ。私って本当にバカだなぁ」
見上げた空がだんだんとぼやけていく。
頬をなにが伝う。確認しなくてもわかる。
「いつになったら普通になれるのかな」
次から次からとあふれる涙を拭う。
それでも間に合わなくて、ぽとぽと地面に落ちていく涙は黒い染みを作る。
「佑にぃちゃんが迎えに来るまでに…止まるかな」
寒いのに、目頭が熱くなっていく。
勝手に喉の奥がひっくり返る。
「止まるかなじゃない、止めなきゃ、いけない」
喉にぐっと力を入れる。
「そうじゃなきゃ、ダメなんだよ…」
そうでなければ、いままで佑にぃちゃんの隣にいたことが意味がなくなってしまう。失ってしまう。そんなのは嫌だ。
想いを伝えずにいたこれまでのことを後悔しているわけじゃない。消したいわけじゃない。壊したいわけじゃない。大事な思い出で、記憶で。だから箱の中にしまっていた。胸の奥底に。
「どれくらいで、佑にぃちゃん来るのかな…」
携帯の画面に新しいメッセージはない。
佑にぃちゃんはちょっと抜けているところがある。
「もう、仕方がないな」
気付けば笑いがこぼれていた。
自分でもわかるほど声が濡れてしまっていて、おかしくてまた笑ってしまう。
「よし…」
そうだ。泣いてしまったことは全部全部、お酒のせいにしてやる。そして、なにも覚えてないって言うんだ。子供みたいな言い訳かもしれないけれど。きっと、私はそれでいいんだ。
また佑にぃちゃんに「まだまだ子供だな」「世話がかかるやつだ」って言われるかもしれないけれど、それでいいんだ。
「それでも…」
それでも私はあなたのことが大好きなのです。
知ってたよ。想いが伝わらないことを。
それでも、どんなカタチでもそばにいたいのです。
だから、どうか、あなたを想うことだけは自由にさせてください。
この冬の吐息のように、私のこの想いも、見えるのは私だけ。すぐに見えなくなればいい。
他の人には見えることができない、私だけの想いのままでありますように。
暖かく穏やかだった花園から、凍てつく氷の海に突き落とされる。そのまま深く深く沈んで海の底へ落ちていく。息がうまくできない。苦しい。目の前の景色が水面のように歪む。
『夏子。いや、いいよ。遅いし、そのまま菜乃花の家まで送るから大丈夫』
電話の向こうで交わされる自然でささいな会話。
目に浮かぶ光景はとてつもなく幸せそうに微笑み合う2人の姿。
「っ…」
私はなにをショックを受けているんだ。わかっていたでしょ。知っていたじゃないか。
こんなに優しい佑にぃちゃんに、彼女が、奥さんがいないワケがない。
それに目の前でお祝いをしたじゃないか。
色とりどりの花びらが舞う青空の下で、佑にぃちゃんの結婚式に参列して見送ったでしょ。
『じゃあ、菜乃花。大人しく待っているんだぞ』
「うん、わかっるってば。大人しく待ってる」
それでも、諦めきれない。断ち切ることができない。
「…夏子さんにも、よろしくね。あとでお礼しなきゃだ」
『あとお説教も待ってるからな』
「えぇー…いやだなー。菜乃花ちゃんは真面目で良い子なのに」
あぁ、なんてめんどくさい女なんだろうか。
私はちゃんと笑えているだろうか。
『はいはい、そうだな。じゃあ、いまから迎えにいくから』
「うん、待ってるね。佑にぃちゃん」
ぷつりと切れた電話。
煌々と光っていた画面が暗くなれば、私を照らす明かりは点々とある街灯だけになる。
「あーあ。私って本当にバカだなぁ」
見上げた空がだんだんとぼやけていく。
頬をなにが伝う。確認しなくてもわかる。
「いつになったら普通になれるのかな」
次から次からとあふれる涙を拭う。
それでも間に合わなくて、ぽとぽと地面に落ちていく涙は黒い染みを作る。
「佑にぃちゃんが迎えに来るまでに…止まるかな」
寒いのに、目頭が熱くなっていく。
勝手に喉の奥がひっくり返る。
「止まるかなじゃない、止めなきゃ、いけない」
喉にぐっと力を入れる。
「そうじゃなきゃ、ダメなんだよ…」
そうでなければ、いままで佑にぃちゃんの隣にいたことが意味がなくなってしまう。失ってしまう。そんなのは嫌だ。
想いを伝えずにいたこれまでのことを後悔しているわけじゃない。消したいわけじゃない。壊したいわけじゃない。大事な思い出で、記憶で。だから箱の中にしまっていた。胸の奥底に。
「どれくらいで、佑にぃちゃん来るのかな…」
携帯の画面に新しいメッセージはない。
佑にぃちゃんはちょっと抜けているところがある。
「もう、仕方がないな」
気付けば笑いがこぼれていた。
自分でもわかるほど声が濡れてしまっていて、おかしくてまた笑ってしまう。
「よし…」
そうだ。泣いてしまったことは全部全部、お酒のせいにしてやる。そして、なにも覚えてないって言うんだ。子供みたいな言い訳かもしれないけれど。きっと、私はそれでいいんだ。
また佑にぃちゃんに「まだまだ子供だな」「世話がかかるやつだ」って言われるかもしれないけれど、それでいいんだ。
「それでも…」
それでも私はあなたのことが大好きなのです。
知ってたよ。想いが伝わらないことを。
それでも、どんなカタチでもそばにいたいのです。
だから、どうか、あなたを想うことだけは自由にさせてください。
この冬の吐息のように、私のこの想いも、見えるのは私だけ。すぐに見えなくなればいい。
他の人には見えることができない、私だけの想いのままでありますように。