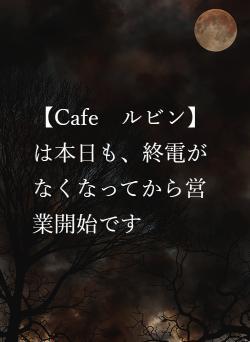「ここじゃ」
老人に連れてこられた場所は、小さな小屋のような家だった。1人暮らしなのか家具は最小限しか置かれていなかった。
「適当に座ってくれ。お茶を持ってくるから待っていてくれるかい」
「あの、お気遣いなく」
「いいからいいから。座ってなさい」
「…はい」
「ありがとうございます」
老人は俺たちの返事を聞いてから台所の方へ消えて行った。
座らせてもらっているだけではどうしても手持ち無沙汰なので辺りを見渡していると、家の窓から海がよく見えることに気づいた。
「ここからでも海が見えるんですね」
「本当だな。ここから見ると穏やかに見えるな」
「そうだろう。でもここの海は潮の満ち引きが早いんだ。ほれ、麦茶だ。待たせたな」
老人は麦茶を持ってきてくれた。コップに注いでくれたのを受け取り飲めば、冷たい麦茶が喉を通る感覚が心地よかった。
「それで、どうして海のことを…」
「ああ、そうだったな。実は渡したいものがあるんだ」
老人は部屋の隅に置かれたタンスの中から、1つの小さな箱を取り出した。
机に置かれたそれは古びているものの、丁寧に扱われていることがすぐに分かった。
「あの子は昨年の4月の初めにこの海に来たんだ」
老人は俺たちの向かいに座るとゆっくりと話し始めた。
昨年の4月というと、海が亡くなる1カ月前だ。
「まだ肌寒い時期に、1人で夜の海に入っていくから驚いてな。あの時のお前さんと同じように止めたんだよ」
「海が1人でここに来たんですか?」
「そうだ。わしの言うことは聞かず、どんどん進んで行ってな。結局、追いかけて捕まえたらその箱を持って泣いとった」
海が泣いている姿なんて想像できない。
それにここに来た理由も分からなかった。先生を見ても首を横に振るだけで心当たりがない様子だった。
「『この箱を海に捨てに来た』と言われた時は驚いたよ。でもどうせ捨てるならわしが持っておいてやろうと思って、今日まで保管しておいたんだ」
「その中身は何ですか?」
「聞いておらん。わしが開けるのは違うだろう」
「…海は、」
「まぁ、話を聞いてくれ。わしはあの子に目の前で死なれては後味が悪いから頭を冷やすように言ったんじゃ。そうしたら、宿がないなんて言うからこの家に泊めたんじゃ」
老人は隠すことなく正直に話してくれる。
「あの子はお前さんのことが心配だったようだぞ。ずっと気にかけていた」
「そこで俺の名前を知ったんですね」
老人は頷いた。
だからさっき、俺が戸田 翼という名前と知って驚いたのか。
「わしが目を覚ました時にはもうあの子はこの家にいなかった。それが昨年の4月にあったことだ。さて、何でお前さんたちをここに呼んだかだったな」
「はい」
「この箱をお前さんに預けようと思ったからだ」
老人は机の上に置かれた箱を指さした。暑いはずなのに、背筋が冷えていく感覚に襲われる。
「どうして俺に?」
「お前さんなら大切に扱ってくれると信じているからだよ」
俺は黙ったまま老人を見つめる。老人は真っ直ぐに俺の目を見て話を続けた。
「あの子は本当に変わった子だった。どんな枠組みにも囚われない子だと感じたよ。あの子、なんて呼び方をしているがそれすら当てはまっていないように思える」
老人の言葉は全て的を得ていた。海はどんな枠組からも外れていて自由だった。海は、現実の海そのもののようだと何度も思った。
「そんなあの子がお前さんのことばかり話すから、つい『お前さんはその翼という友のことを好いているのか?』と聞いてしまったさ」
「…海は何て言っていました?」
老人は湯気が立つほどの熱いお茶を飲んで一息つくと、俺の目を見た。
その目は本当に良いのか?と聞いているようだった。
覚悟を決めて頷くと、老人はゆっくりと口を開いた。
「笑いながら『これは恋でも愛でもないよ。僕はどんな翼でも受け止める海だから』と言っていた」
それは、あの夏休みの教室で先生が俺に投げかけた「水谷のことを恋愛感情で好きだったのか」という質問に対しての俺の返答に酷く似ていた。
お互いにお互いの言葉を聞く機会がなかったのに、こんなところで似ていることに気づかされるなんて思ってもみなかった。
泣きそうになるのを歯を食いしばって耐える。
「…戸田」
先生は何か言いたげだったが、俺は首を横に振った。きっと今口を開くと泣いてしまう。
「あの子は今どうしておる?」
「…去年の5月に持病で亡くなりました」
「…そうか」
老人はきっと察していたのだろう。驚くことなく目を伏せた。
それから少しして、机に置かれたままだった箱を俺の方に近づけてきた。
「この箱を引き取ってはくれないか?」
「え、」
「…渡すことがあの子の意思だ、なんてことは言わないがな」
「…何で俺なんですか。海の遺族とか…」
「わしがお前さんに渡すべきだと思うからだ」
老人は笑いながらそう言った。
それはずるいだろ。そんなことを言われたら引き取るしかなくなるじゃないか。
震える手を箱に伸ばす。持ち上げるとそれは予想以上に小さく、軽かった。
「…開けて、いいですか」
「ああ」
鍵も何も付いていない箱は簡単に開いた。
そこには数枚の紙と、海と砂浜をモチーフにした大きめの飾りがついたヘアゴムが入っていた。
「ヘアゴム…?」
「あ、それ見たことがある」
先生がヘアゴムを見て、驚いたように声を上げた。
先生は思い出すように唸ったかと思ったら、すぐに何度も頷いた。
「やっぱりそうだ。それ、水谷が学校に着けてきたんだけど校則違反だからって水谷の担任が没収したんだよ」
確かに少し前「先生にヘアゴム没収された〜」と半泣きになっていたのを思い出した。これのことだったのか。
「多分学校に着けて来ないことを約束して返したんだろうな」
「…でも、何でこれが箱に入っているんですかね」
「そこまではさすがに知らないな」
考えても分からないため、とりあえず箱の中にあった紙を手に取った。
それは病院の診断書だった。海の持病についてと手術について事細かに書かれていた。
「…これは海の病気についての診断書ですね」
「これを捨てたかったのか」
「やっぱり日記とか手紙は入ってないですね。そういうの3日坊主どころか買って終わるタイプだったので」
海に捨てようとしたぐらいだから日記や手紙のようなものが入っていてもおかしくないと思ったが、その類の物は入っていなかった。
少し考えてからヘアゴムを取り出し、診断書を箱に戻す。箱を閉めてから老人の方に近づけた。
「…やっぱりこれは引き取れません」
「……そうか」
「だから迷惑でなければ、預かっていてくれませんか」
突然の申し入れに老人は目を丸くした。
俺だって自分が何を言っているかよく分かっていない。ただ、これは俺が持っているべきではないと思った。
「戸田、それはご迷惑になるから…」
「…わしは老い先長くない。いつ死ぬかも分からん。ボケてこの箱を失えてしまうかもしれないぞ」
「それでもいいんです。きっとあなたがいなかったら海は去年の4月、この海で自殺していましたから」
2人が息を吞むのが聞こえた。
「これは俺の憶測でしかありません。でも、海が『この箱を捨てに来た』と言ったのはきっと咄嗟の言い訳だったと思います」
俺は実際に海が4月にこの海に来たところを見たわけではない。でも、何となく分かってしまうのだ。
「だからこの箱はここに置いておいてほしいんです。海はここで自殺したい気持ちを捨てたはずですから。持って帰っては海の決心が無駄になってしまいます」
「……分かった」
支離滅裂になってしまったが、老人は俺の伝えたいことを理解してくれた。先生は俺たちの様子を見守っていてくれた。
「それはいいのかね?」
老人は俺が持っているヘアゴムを指さした。
これを持っておくかは悩んだが、結局持っていくことにしたのだ。
海との繋がりを少しでも持っていたいと思ってしまった。
「でも、これは俺が持っています。海にどこまでも連れて行くと約束しましたので」
「そうか」
老人は立ち上がり、部屋の隅にあるタンスに仕舞った。