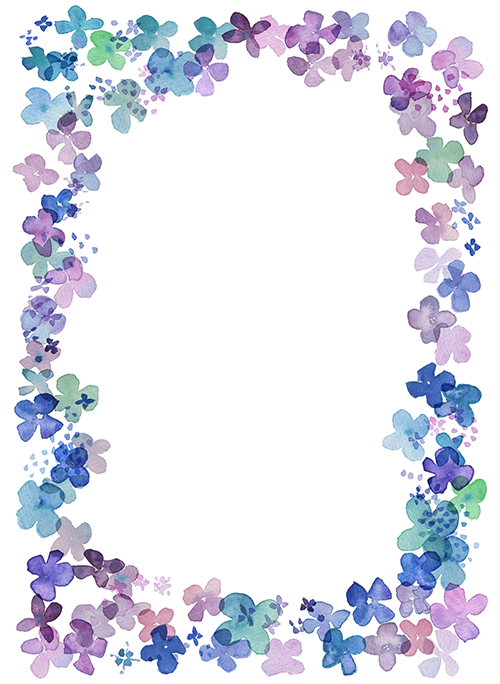夏休みが明けて一週間ほど。九月の頭。あっという間に文化祭はやってきた。ざわざわと人で賑わっている。それでも、文芸部の出しているスペースに人はあまり来ていなかった。
文芸部に宛がわれた部屋は3階の教室。主に賑わっているのは、1階体育館。人気のある手芸部や家庭科部の販売ゾーンは2階。3階まで来る人はあまりいない。一番最初に小澤が来たくらい。
俺がやること、一冊100円の部誌をお客さんに手渡して、お金を受け取る。それこそ模擬店、みたいな感じ。来たお客さんは今のところは小澤だけ。部誌を渡してお金を受け取る。人が来なくて静か。でも……
「星原くん、模擬店に行きたいとか、ステージ発表見たい、とかない? 大丈夫?」
「特にはないので、お昼だけ買えれば……」
「そっか。じゃあ、二人で過ごそっか。お昼ぐらいになったらちょこっと呼び込みしてくるから」
「は、はい……」
先輩と隣同士、二人きりで時間を過ごせる。ある意味ラッキーだったのかもしれない。
先輩と二人、しばらく過ごしていた時だった。
「レンくん~~~~~~!」
どくりと心臓が嫌な音を立てる。この声を、この呼び方を俺は知っている。城崎先輩だ。
やってきた城崎先輩はとても可愛らしい姿をしていた。ツインテールに、クラスTシャツをかわいくデコっている。ふわふわのチュールスカートメイクもばっちり。人気アイドル、と言われてもおかしくないような姿。
「レンくん、うちのクラス手伝ってもらえない? レンくんに来てもらえたら嬉しいな~!」
「人手、足りない感じ?」
「うーん、人手は大丈夫だと思うんだけど!」
「ごめんね。今日は僕は文芸部の方を優先したいんだ。後輩の星原くんを一人置いておく、というのは申し訳ないからね」
「そっか~。残念。じゃあね」
城崎先輩は少し残念そうな顔をして、俺達の前を去ってしまった。
「……あの、いいんですか。クラスの方に行かなくて」
「うん。大丈夫。シフト表とか見ても人手は足りてそうだし。……あと、星原くんと一緒にいたいからね」
「え、えっとそ、それは、頼りない、という意味で?」
「いや、純粋に、星原くんと一緒にいたいんだ」
先輩は視線を逸らして、どういう表情かきちんとは見えなかった。多分、今の俺、すごい顔してると思う。
そして、その後も俺は、先輩と二人きりで過ごしていた。来たお客さんに部誌を渡して、二人でお昼を食べて、二人の時間、だった。
そして、あっという間に文化祭の時間が終わり、後夜祭の時間。俺達は、三階の教室から部室に荷物を運んだ後、なんとなく疲れてしまって、そこに二人でいた。部室の外はもう完全に夜になっている。
「あの、先輩、後夜祭は行かないんですか?」
後夜祭は校庭で火を燃やして、その周りでダンスを踊るということになっている。つまりキャンプファイヤーみたいなことをする。小澤曰く「去年は演劇だったけれど今年の文化祭実行委員の先輩が“どうしてもそれをやりたいってゴネた”」という噂。噂だから本当のことはどうか分からないけれど。先輩が行くのであれば俺も行きたいな、と思っている。
「もしよかったら、ここで二人で一緒に見ない? こっちの方がなんとなく落ち着いてそうで」
「い、いいんですか?」
「星原くんがよかったらそうしたいな。それに、二人きりでいられるからね」
「は、はい……!」
部室の中、俺達二人は炎を眺めていた。校庭の真ん中で炎が燃え上がっている。花火とはまた違った燃え上がり方。
「あ、ダンス、始まりましたね」
炎を囲むようにして後夜祭に参加をしている人達が踊りを始めた。俺がぼーっとその光景を見ていると、先輩が俺の方に手を伸ばしてるのが見えた。まるで、王子様がお姫様に手を伸ばすように。
「せ、先輩……?」
「もしよかったら、ちょっと踊ってみない?」
「お、踊り、ですか?」
「昔、ちょっとだけ習ってたんだ。ダンス」
「は、はい……。その、踊ったこと、なんて全然ないんですけれど……」
踊り、なんて小さい頃の俺はドキドキしながら先輩の手を取った。夏だからか、先輩の少しだけ熱い手の温度が俺の手に伝わる。
「わっ……、わぁっ……!?」
そして、先輩が、俺の手を取って、そのまま、フォークダンスではないけれども、踊りを始める。先輩の動きに合わせて、俺は動く。それこそ、ダンスパーティーのような踊り。くるくると身体が回っている。なんだか、ロマンティックだ。
夜の闇の電灯に照らされた部室の中。まるでお姫様になったかのような気持ちが俺の身体に走っていた。
――
先輩の動きに合わせたように踊って、時間が過ぎていった。キャンプファイヤーの炎も気が付けば随分と小さくなっていた。
「付き合ってくれてありがとう」
「こ、こちらこそ、あ、ありがとうございました」
「そういえばね、星原くんに、伝えたいことがあるんだ。二つ、それぞれ系等の違うことなんだけれども」
「な、なんでしょうか……!」
「伝えたいんだけれどもね、少しだけ、心の準備が必要なんだ。だから、少し、待って欲しい」
「は、はい……」
家に帰ってからも、俺は文化祭のふわふわとした感覚を味わっていた。小澤からは「お前、本格的に小説家、目指した方いいんじゃね? 才能あるよ」と来た。それもなんだか嬉しかった。
「俺に、伝えたいこと、か……」
先輩が言いたい、俺に伝えたいこと、っていったい何だろう。気になりながらも、その内容が一体何なのか、は想像がつかなかった。
文芸部に宛がわれた部屋は3階の教室。主に賑わっているのは、1階体育館。人気のある手芸部や家庭科部の販売ゾーンは2階。3階まで来る人はあまりいない。一番最初に小澤が来たくらい。
俺がやること、一冊100円の部誌をお客さんに手渡して、お金を受け取る。それこそ模擬店、みたいな感じ。来たお客さんは今のところは小澤だけ。部誌を渡してお金を受け取る。人が来なくて静か。でも……
「星原くん、模擬店に行きたいとか、ステージ発表見たい、とかない? 大丈夫?」
「特にはないので、お昼だけ買えれば……」
「そっか。じゃあ、二人で過ごそっか。お昼ぐらいになったらちょこっと呼び込みしてくるから」
「は、はい……」
先輩と隣同士、二人きりで時間を過ごせる。ある意味ラッキーだったのかもしれない。
先輩と二人、しばらく過ごしていた時だった。
「レンくん~~~~~~!」
どくりと心臓が嫌な音を立てる。この声を、この呼び方を俺は知っている。城崎先輩だ。
やってきた城崎先輩はとても可愛らしい姿をしていた。ツインテールに、クラスTシャツをかわいくデコっている。ふわふわのチュールスカートメイクもばっちり。人気アイドル、と言われてもおかしくないような姿。
「レンくん、うちのクラス手伝ってもらえない? レンくんに来てもらえたら嬉しいな~!」
「人手、足りない感じ?」
「うーん、人手は大丈夫だと思うんだけど!」
「ごめんね。今日は僕は文芸部の方を優先したいんだ。後輩の星原くんを一人置いておく、というのは申し訳ないからね」
「そっか~。残念。じゃあね」
城崎先輩は少し残念そうな顔をして、俺達の前を去ってしまった。
「……あの、いいんですか。クラスの方に行かなくて」
「うん。大丈夫。シフト表とか見ても人手は足りてそうだし。……あと、星原くんと一緒にいたいからね」
「え、えっとそ、それは、頼りない、という意味で?」
「いや、純粋に、星原くんと一緒にいたいんだ」
先輩は視線を逸らして、どういう表情かきちんとは見えなかった。多分、今の俺、すごい顔してると思う。
そして、その後も俺は、先輩と二人きりで過ごしていた。来たお客さんに部誌を渡して、二人でお昼を食べて、二人の時間、だった。
そして、あっという間に文化祭の時間が終わり、後夜祭の時間。俺達は、三階の教室から部室に荷物を運んだ後、なんとなく疲れてしまって、そこに二人でいた。部室の外はもう完全に夜になっている。
「あの、先輩、後夜祭は行かないんですか?」
後夜祭は校庭で火を燃やして、その周りでダンスを踊るということになっている。つまりキャンプファイヤーみたいなことをする。小澤曰く「去年は演劇だったけれど今年の文化祭実行委員の先輩が“どうしてもそれをやりたいってゴネた”」という噂。噂だから本当のことはどうか分からないけれど。先輩が行くのであれば俺も行きたいな、と思っている。
「もしよかったら、ここで二人で一緒に見ない? こっちの方がなんとなく落ち着いてそうで」
「い、いいんですか?」
「星原くんがよかったらそうしたいな。それに、二人きりでいられるからね」
「は、はい……!」
部室の中、俺達二人は炎を眺めていた。校庭の真ん中で炎が燃え上がっている。花火とはまた違った燃え上がり方。
「あ、ダンス、始まりましたね」
炎を囲むようにして後夜祭に参加をしている人達が踊りを始めた。俺がぼーっとその光景を見ていると、先輩が俺の方に手を伸ばしてるのが見えた。まるで、王子様がお姫様に手を伸ばすように。
「せ、先輩……?」
「もしよかったら、ちょっと踊ってみない?」
「お、踊り、ですか?」
「昔、ちょっとだけ習ってたんだ。ダンス」
「は、はい……。その、踊ったこと、なんて全然ないんですけれど……」
踊り、なんて小さい頃の俺はドキドキしながら先輩の手を取った。夏だからか、先輩の少しだけ熱い手の温度が俺の手に伝わる。
「わっ……、わぁっ……!?」
そして、先輩が、俺の手を取って、そのまま、フォークダンスではないけれども、踊りを始める。先輩の動きに合わせて、俺は動く。それこそ、ダンスパーティーのような踊り。くるくると身体が回っている。なんだか、ロマンティックだ。
夜の闇の電灯に照らされた部室の中。まるでお姫様になったかのような気持ちが俺の身体に走っていた。
――
先輩の動きに合わせたように踊って、時間が過ぎていった。キャンプファイヤーの炎も気が付けば随分と小さくなっていた。
「付き合ってくれてありがとう」
「こ、こちらこそ、あ、ありがとうございました」
「そういえばね、星原くんに、伝えたいことがあるんだ。二つ、それぞれ系等の違うことなんだけれども」
「な、なんでしょうか……!」
「伝えたいんだけれどもね、少しだけ、心の準備が必要なんだ。だから、少し、待って欲しい」
「は、はい……」
家に帰ってからも、俺は文化祭のふわふわとした感覚を味わっていた。小澤からは「お前、本格的に小説家、目指した方いいんじゃね? 才能あるよ」と来た。それもなんだか嬉しかった。
「俺に、伝えたいこと、か……」
先輩が言いたい、俺に伝えたいこと、っていったい何だろう。気になりながらも、その内容が一体何なのか、は想像がつかなかった。