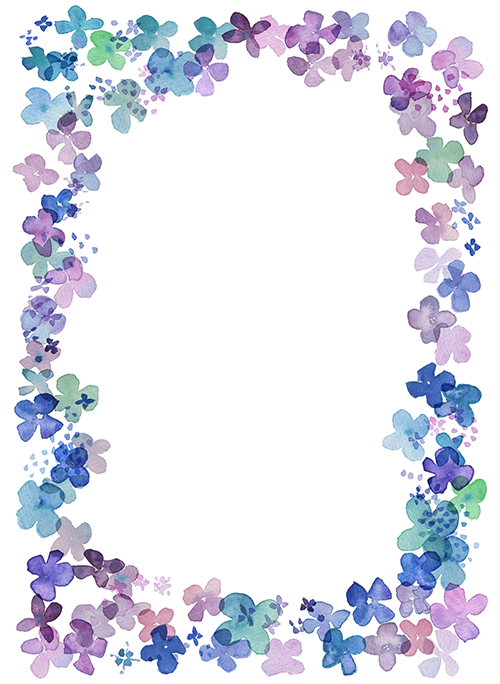「そっか。よかったな。楽しい夏休みだったんだな」
「うん。一緒に花火大会行けて……。その……手、繋いだり、とか……」
無事に原稿も提出することが出来た夏休み明け。俺は小澤に近況報告をしていた。あ
の花火大会の日のことを思いだして、俺の顔がひどく熱くなった。
「へー、それじゃあ、脈、ちょっとはあるんじゃないか?」
「……うん、もしかしたら、あるのかも、しれない」
脈があるのかもしれない。小澤にそう言ってもらえたことで、嬉しくなった。
「そういやもうすぐ文化祭だけど星原のとこはなんかやるのか?」
「うん。部誌売る予定」
「いいな~。文化祭!って感じで。バド部はなんもなし。クラスでも1年のうちは模擬店出来ねえもんなあ」
「そうだね。だからちょっと楽しみ」
「俺、文芸部行くからな」
「ありがとう。楽しみにしてる」
9月の頭に行われるうちの学校の文化祭は出展制限のために模擬店の出店は2年生から。そのために、俺達1年のクラスは模擬店は出さない。けれども部活単位でだったら模擬店、というか何かしらの出し物を出すことが出来る。文芸部も部誌を出して売ることになっていた。
―――
放課後。俺は部室にいた。今日からの部活動は文化祭の準備。そして、文化祭の準備期間が始まった。放課後一時間、クラスの文化祭の準備に当てられる。文化祭は、文化部の人達は基本は文化部の活動を優先していいことになっている。先輩も当日は文芸部の活動を優先してくれる。けれども、クラスの方に関して「全く手伝わないのも申し訳ないから」と放課後一時間だけは、クラスの方に行くことになっていた。
一人の部室。俺は、先輩から言われて部誌の落丁乱丁がないかをチェックしていた。一人の教室、思い出してしまうのは、先輩との花火大会の日のことだった。先輩の横顔、手の感触、あの日の体温……。そんなことが思い出されて、俺の身体の体温が上がってしまった。
「すみませーん」
ノックの後、間髪入れずに響いたふんわりとした高い女の人の声。来るのが珍しいこの文芸部の部室に人がやってきた。珍しいな、と思いながらも俺は扉を開けた。
「っ…………!?」
扉を開けて俺は驚いてぽっかり口を開けてしまった。そこにいたのはすごく綺麗な女の人だった。ぱっちりとした瞳にさらさらの黒髪。思わず圧倒されてしまうくらいの美人。それこそ、ハリウッド女優に圧倒される、みたいなそんな感じ。けど、初めて見た、ではない。どこかで会ったことがある気がする。誰だろう。でも、頭の中を巡らせても、俺はその人のことを思い出すことは出来なかった。
「大丈夫ですか?」
ぼーっとその女の人のことを眺めてしまっていた。けれども、その女の人の言葉で我に返った。
「あの、レンくんいますか?」
「レンくん、」
レンくん、と口に出す。レンくん、れん、れんり、連理、先輩のことだ。いつも「先輩」と呼んでいるから、先輩の名前と「レンくん」が結び着くのに一瞬時間がかかった。けれども、結びついた瞬間、俺の心臓が嫌な跳ね方をした。彼女は、先輩のことをレンくん、と呼ぶくらいに仲がいい。この人は、先輩と一体どういう関係なのだろうか。
「成神、連理先輩ですか?」
「そうそう!」
「先輩なら、さっきクラスの方に向かいました」
「そっかあ。入れ違いになっちゃったか。残念。じゃあ、もし戻ってきたら、レンくんにシロサキが来た、って伝えてもらってもいいかな?」
「は、はい、分かりました」
「じゃあね。対応してくれてありがとう!」
そして、シロサキさんはさらさらとした髪の毛を揺らしながら廊下を降りて部室棟から出て行こうとする。シロサキ、と名乗った先輩の後ろ姿を眺めているうちに、俺の頭の記憶と結びつく。
――城崎セリカ先輩。超美人の先輩。SNSのフォロワー万超えだとか、スカウト来てる、とか、かなり噂になってる
俺の頭の中で、彼女の名前が結びついた。小澤が言っていた城崎セリカ先輩。すごくモテる、ってあの先輩だ。先輩を見に行ったあの日、先輩のことを囲んでいた女の人の中の一人だ。
城崎先輩がその場を離れてからも、なんだか胸がざわついてしまった。
――あの、レンくんいますか?
――じゃあ、レンくんにシロサキが来た、って伝えてもらってもいいかな?
俺は、先輩を下の名前で呼んだことは俺もない。だから。城崎先輩は、すごく、仲のいい人だったのかな……。先輩は、人気者だから。城崎先輩と、先輩が仲よさげな様子は簡単に想像出来てしまった。こんな、面白みのない俺よりも、ずっと楽しそうな先輩の姿が。
先輩は好きな人のことを「秘密」と言っていた。まさか、城崎先輩と……。不安が俺の身体に走った。
「ただいま。ごめんね。遅くなっちゃって」
どのくらい時間が経ったのか。先輩の言葉で、俺は現実世界へと戻ってくる。先輩が部室に来ていた。随分ぼーっとしてたかもしれない。
「大丈夫? 暑さで熱中症っぽくなってたりする?」
「い、いえ。だ、大丈夫です。あの、せ、先輩」
「ん? どうしたの?」
「城崎さん、が部室に来て……」
「ああ、城崎さん。先ほど会ったよ。」
「先輩、あの、城崎さんとどういうご関係なんですか?」
少し声を震わせながら俺は先輩に言う。付き合ってる。とか、意中の相手だ、とか言われたらどうしようか。と思った。
「同じクラスの子だよ。僕に用があったみたいなんだ」
「そ、そうなんですね……」
「あと、城崎さんは11月の修学旅行で一緒の班になったんだ。それでいろいろ話す機会があってね」
「修学旅行、の班ですか……?」
「そう、自由行動の際に、同じ場所を回るんだ。僕のクラスは女性の方が多いクラスでね。部屋割りは男女で別れるけれども自由行動の際は男女混合グループになってるんだ。そこで、城崎さんとも一緒の班になってね」
「そうなんですね……」
俺は頷く。けれども、少し、心がざわついていた。その後の時間も、心のざわつきは治まることはなく、文芸部の活動をしていた。
部活が終わって、俺は部室の鍵を返しに職員室に向かう。そして鍵を返し終えて職員室から出た時だった。
「星原くん」
「本田先生」
顧問の本田先生に呼び止められた。ラフなポロシャツ姿。柔らかい雰囲気で僕の方に視線を向けていた。
「星原くん、文化祭の部誌の原稿、見せてもらったけれども、なかなかいいね」
「あ、ありがとうございます……!」
「文化祭、楽しんでね」
「は、はい……」
「これが、一度きりの文化祭だからね」
「えっと、一度きり、ですか……?」
本田先生は言う。ただの「部活頑張って」とはどこか違うどこか含みのある言い方だった。一体どういうことだろうか。俺は先生にどういうことか訊ねようとした瞬間だった。
「本田先生、お電話です!」
「あ、行かなきゃ。呼び止めちゃってごめんね」
「は、はい……」
俺が訊こうとする前に、本田先生は職員室に入って、電話応対に出てしまった。俺は本田先生の後ろ姿にぺこりと会釈して、昇降口の方まで向かう。話は地中で途切れてしまった。
「一度きり……」
昇降口に着いたところで、俺は思わず口にする。一度きり。どういうことだろう。今年の、俺が一年生の文化祭は一度きりだから、ということかな。まあ、言い回しはちょっと不思議だけれど、そう言われればなんとなく納得出来た。言い回しを少し独特にした、とかそういう感じかもしれない。
どこか残っている違和感には目を瞑り、一度きりの文化祭、いっぱい楽しもう、って思った。
「うん。一緒に花火大会行けて……。その……手、繋いだり、とか……」
無事に原稿も提出することが出来た夏休み明け。俺は小澤に近況報告をしていた。あ
の花火大会の日のことを思いだして、俺の顔がひどく熱くなった。
「へー、それじゃあ、脈、ちょっとはあるんじゃないか?」
「……うん、もしかしたら、あるのかも、しれない」
脈があるのかもしれない。小澤にそう言ってもらえたことで、嬉しくなった。
「そういやもうすぐ文化祭だけど星原のとこはなんかやるのか?」
「うん。部誌売る予定」
「いいな~。文化祭!って感じで。バド部はなんもなし。クラスでも1年のうちは模擬店出来ねえもんなあ」
「そうだね。だからちょっと楽しみ」
「俺、文芸部行くからな」
「ありがとう。楽しみにしてる」
9月の頭に行われるうちの学校の文化祭は出展制限のために模擬店の出店は2年生から。そのために、俺達1年のクラスは模擬店は出さない。けれども部活単位でだったら模擬店、というか何かしらの出し物を出すことが出来る。文芸部も部誌を出して売ることになっていた。
―――
放課後。俺は部室にいた。今日からの部活動は文化祭の準備。そして、文化祭の準備期間が始まった。放課後一時間、クラスの文化祭の準備に当てられる。文化祭は、文化部の人達は基本は文化部の活動を優先していいことになっている。先輩も当日は文芸部の活動を優先してくれる。けれども、クラスの方に関して「全く手伝わないのも申し訳ないから」と放課後一時間だけは、クラスの方に行くことになっていた。
一人の部室。俺は、先輩から言われて部誌の落丁乱丁がないかをチェックしていた。一人の教室、思い出してしまうのは、先輩との花火大会の日のことだった。先輩の横顔、手の感触、あの日の体温……。そんなことが思い出されて、俺の身体の体温が上がってしまった。
「すみませーん」
ノックの後、間髪入れずに響いたふんわりとした高い女の人の声。来るのが珍しいこの文芸部の部室に人がやってきた。珍しいな、と思いながらも俺は扉を開けた。
「っ…………!?」
扉を開けて俺は驚いてぽっかり口を開けてしまった。そこにいたのはすごく綺麗な女の人だった。ぱっちりとした瞳にさらさらの黒髪。思わず圧倒されてしまうくらいの美人。それこそ、ハリウッド女優に圧倒される、みたいなそんな感じ。けど、初めて見た、ではない。どこかで会ったことがある気がする。誰だろう。でも、頭の中を巡らせても、俺はその人のことを思い出すことは出来なかった。
「大丈夫ですか?」
ぼーっとその女の人のことを眺めてしまっていた。けれども、その女の人の言葉で我に返った。
「あの、レンくんいますか?」
「レンくん、」
レンくん、と口に出す。レンくん、れん、れんり、連理、先輩のことだ。いつも「先輩」と呼んでいるから、先輩の名前と「レンくん」が結び着くのに一瞬時間がかかった。けれども、結びついた瞬間、俺の心臓が嫌な跳ね方をした。彼女は、先輩のことをレンくん、と呼ぶくらいに仲がいい。この人は、先輩と一体どういう関係なのだろうか。
「成神、連理先輩ですか?」
「そうそう!」
「先輩なら、さっきクラスの方に向かいました」
「そっかあ。入れ違いになっちゃったか。残念。じゃあ、もし戻ってきたら、レンくんにシロサキが来た、って伝えてもらってもいいかな?」
「は、はい、分かりました」
「じゃあね。対応してくれてありがとう!」
そして、シロサキさんはさらさらとした髪の毛を揺らしながら廊下を降りて部室棟から出て行こうとする。シロサキ、と名乗った先輩の後ろ姿を眺めているうちに、俺の頭の記憶と結びつく。
――城崎セリカ先輩。超美人の先輩。SNSのフォロワー万超えだとか、スカウト来てる、とか、かなり噂になってる
俺の頭の中で、彼女の名前が結びついた。小澤が言っていた城崎セリカ先輩。すごくモテる、ってあの先輩だ。先輩を見に行ったあの日、先輩のことを囲んでいた女の人の中の一人だ。
城崎先輩がその場を離れてからも、なんだか胸がざわついてしまった。
――あの、レンくんいますか?
――じゃあ、レンくんにシロサキが来た、って伝えてもらってもいいかな?
俺は、先輩を下の名前で呼んだことは俺もない。だから。城崎先輩は、すごく、仲のいい人だったのかな……。先輩は、人気者だから。城崎先輩と、先輩が仲よさげな様子は簡単に想像出来てしまった。こんな、面白みのない俺よりも、ずっと楽しそうな先輩の姿が。
先輩は好きな人のことを「秘密」と言っていた。まさか、城崎先輩と……。不安が俺の身体に走った。
「ただいま。ごめんね。遅くなっちゃって」
どのくらい時間が経ったのか。先輩の言葉で、俺は現実世界へと戻ってくる。先輩が部室に来ていた。随分ぼーっとしてたかもしれない。
「大丈夫? 暑さで熱中症っぽくなってたりする?」
「い、いえ。だ、大丈夫です。あの、せ、先輩」
「ん? どうしたの?」
「城崎さん、が部室に来て……」
「ああ、城崎さん。先ほど会ったよ。」
「先輩、あの、城崎さんとどういうご関係なんですか?」
少し声を震わせながら俺は先輩に言う。付き合ってる。とか、意中の相手だ、とか言われたらどうしようか。と思った。
「同じクラスの子だよ。僕に用があったみたいなんだ」
「そ、そうなんですね……」
「あと、城崎さんは11月の修学旅行で一緒の班になったんだ。それでいろいろ話す機会があってね」
「修学旅行、の班ですか……?」
「そう、自由行動の際に、同じ場所を回るんだ。僕のクラスは女性の方が多いクラスでね。部屋割りは男女で別れるけれども自由行動の際は男女混合グループになってるんだ。そこで、城崎さんとも一緒の班になってね」
「そうなんですね……」
俺は頷く。けれども、少し、心がざわついていた。その後の時間も、心のざわつきは治まることはなく、文芸部の活動をしていた。
部活が終わって、俺は部室の鍵を返しに職員室に向かう。そして鍵を返し終えて職員室から出た時だった。
「星原くん」
「本田先生」
顧問の本田先生に呼び止められた。ラフなポロシャツ姿。柔らかい雰囲気で僕の方に視線を向けていた。
「星原くん、文化祭の部誌の原稿、見せてもらったけれども、なかなかいいね」
「あ、ありがとうございます……!」
「文化祭、楽しんでね」
「は、はい……」
「これが、一度きりの文化祭だからね」
「えっと、一度きり、ですか……?」
本田先生は言う。ただの「部活頑張って」とはどこか違うどこか含みのある言い方だった。一体どういうことだろうか。俺は先生にどういうことか訊ねようとした瞬間だった。
「本田先生、お電話です!」
「あ、行かなきゃ。呼び止めちゃってごめんね」
「は、はい……」
俺が訊こうとする前に、本田先生は職員室に入って、電話応対に出てしまった。俺は本田先生の後ろ姿にぺこりと会釈して、昇降口の方まで向かう。話は地中で途切れてしまった。
「一度きり……」
昇降口に着いたところで、俺は思わず口にする。一度きり。どういうことだろう。今年の、俺が一年生の文化祭は一度きりだから、ということかな。まあ、言い回しはちょっと不思議だけれど、そう言われればなんとなく納得出来た。言い回しを少し独特にした、とかそういう感じかもしれない。
どこか残っている違和感には目を瞑り、一度きりの文化祭、いっぱい楽しもう、って思った。