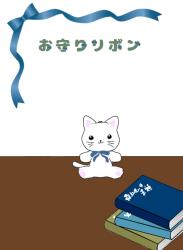目覚ましの音が鳴り響く朝。うるさいので一旦止めて………そしてまた寝よう。
だが俺の二度寝は姉によって台無しにされる。
「ケイー!もう朝だよー!起きてー!」
姉はもう着替え終わって後は大学に行くだけなようで、もうすぐ学校に行く時間だと言うのに何もしていない俺の姿を見て唖然としている。
「もう!また二度寝しようとしたでしょ!」
「うっせーな……五分くらいいいだろ」
「よくない!ちょっとでも努力したら友達なんていっぱいできるんだから!」
姉貴はいつもこうだ。すごいお節介焼きでとても過保護。
「俺には一人いれば充分なんだよ」
俺は姉貴を部屋から追い出し急いで着替えだす。着替え終わった頃にちょうど朝ごはんも出来上がったみたいで一階から大声で呼ばれた。
俺はそもそも朝はあまり食べない花ので朝ごはんをひとつまみだけして、しっかりマスクを付けてから家を出た。
俺は藤上慧。ごくごく普通の高校三年生。
いつもマスクをして顔を隠しているからか表情がわかりにくいという理由で友達は……多いほうじゃない。
「ケイ〜!おはよ!」
「……はよ」
こいつはたったひ……数少ない友達の一人、片野翔吾。俺よりもだいぶ頭が良く、女子たちからも人気でたまにお近づきになりたい女子からラブレターの伝達係や連絡先を教えてほしいと言われる。
今年は別々のクラスになってちょっと減ったけど。
「ケイ今日もマスクか〜、外してもいいのに」
「……俺はヤダ、どうせまた虐められる…」
「俺が事情伝えれば大丈夫じゃない?悪いこと全くしてないんだから」
「でも……」
「あ、やっべ俺今日日直だわ、またな」
「ばいばい」
俺は軽く手を振り翔吾を見送った後、自分も遅刻しそうになり急いで教室へと向かう。
俺がマスクで顔を隠す理由はマスクの下にある。
昔、児童館で放火事件が起こり火事になった。その時に逃げ遅れていた年下の子を庇った時に大火傷を負い今も火傷の跡が残っている。俺は生まれたて皮膚が強いほうじゃないので移植手術も難しいらしい。
その傷のせいで小学校では虐められ心を病んだ。それからすぐ引っ越したからあの時の子も今何をしているのか知らない。
このことを家族以外で知ってるのは翔吾だけ
俺がいつものようにスマホをいじっていると横から女子に肩をトンと叩かれた。
「ねね、お客さん。前の入口にすっごいイケメンの後輩くんが」
「え?俺に?」
「うん、藤上先輩いますかって」
俺にイケメン後輩の客が……?ありえない、だってそんな知り合い存在しないから。
でも呼ばれたなら一応行かなきゃな…俺は女子たちに道を開けてもらい噂の後輩の元へと向かった。
「藤上先輩こんにちは」
「……こんにちは」
やはり思った通り見覚えのない後輩が立っていた。しかも高一とは思えないほど高身長…高三で164センチの俺からしたら正直羨ましい。
「なんのようですか」
「んーそうだな……一緒にお昼食べません?」
「もう食べちゃったけど」
昼休憩から20分もしているのだから食べ終わっててもおかしくない。その後輩は「そうですよね」と言いながらも教室から離れようとしなかった。
「じゃ、これで」
「まっ、待って!」
「……何?」
「うーんと……じゃあ勉強教えてください」
「じゃあってなんだよ、俺あんまり頭よくないよ」
「うっ……」
「用がないなら帰ってくれない?」
「……じゃあ先輩とお話しをしたいんですけど」
元の要件はそれか……それなら最初からそう言ってよかったんじゃ?
「ごめんけどよく分かんないやつとは話したくない」
「あー……そうですよね、すみません急にこんなこと…」
「それじゃ……」
俺が後輩を置いて教室へ戻ろうとした時また後輩に呼び止められる。
「その……矢沢葵です。覚えてくれたら嬉しいです」
その言葉に俺は一瞬固まった。どこかで聞いたことあるような……思い出せない…
「……わかったもう帰んな、お前一年だろ。ここ三年のエリアだから授業遅れるぞ」
「はい、失礼します」
今度は満足したようでスッと教室のある四階の方へと戻っていった。
「矢沢くんっていうんだ……連絡先欲しくね?」
「それな〜後輩にあんなイケメンいたなんて」
女子たちは矢沢の話題でいっぱいだ。俺は別にどうでもいい、イケメン後輩なんていたってなんとも思わんし髪も染めてて見るからに危なそう。とりあえず関わらないでおこう…
…と思っていた放課後
「藤上先輩!一緒に帰りましょう!」
「……嫌だと言ったら?」
「一緒に帰宅する……?」
「変わってねえじゃん、一緒に帰らんよ」
「…じゃあこのまま放課後一緒に勉強しようってこと…!?」
なんでそうなるんだ…ポジティブすぎやしないか?
「しない。俺一緒に帰るやついるからお前は先帰れ、モテるんだし一緒に帰れるやつなんて山ほどいるだろ」
「えー……それって彼女ですか?」
「いや、男」
そんな話をしているとスマホに一通のLIMEが来た。
差出人は翔吾。『人多いから先校門で待ってる』とだけ送られていた。
確かに周りを見れば矢沢を取り囲む女子たちでいっぱいだ。
「ごめん、相手待たせてるから」
「……わかりました」
断ってもしつこく追いかけてきそうだと思ったのに思っていたよりすんなり解放してくれた。
翔吾を待たせても悪いので矢沢の顔も見ず、俺は急いで玄関へと向かった。
「おまたせ」
「遅かったね、なんかあった?」
翔吾は何か勘違いしているようで必要以上に心配をしてくる。
「大丈夫だから……後輩が俺に用事あったみたいでそれで…」
「……そう、ならいいんだけど…てっきりマスクでも外れて虐められたとかかと」
「そう簡単には外れないし……」
「まぁもしそんなこと起きても俺が守ってやるからな」
「ありがと、心強い」
まぁこいつなら周りからの信頼も厚いし人気だから……きっと本当にどうにかしてくれるんだろうな
唯一の友達だし………
「でもいいの?俺なんかと一緒にいて……俺マスク外さないから表情わかりにくいって言われてるからお前以外に友達いないし……」
「ゼロより寂しくないだろ?それに俺はケイの優しいところが好きで一緒にいるんだから」
「……でも何か言われない?あんなやつと一緒にいるなとか」
俺がこんな見た目だからマスクをしてても一定数いじめを受ける。小学校や中学校と比べれば少なくはなったが……
「そんなやつ雑魚だよ、かっこ悪くね?わざわざ人の容姿で好き嫌い決めるとかドン引き」
「そう……」
こいつがモテるのはこういうところなんだろうな……けど翔吾が俺意外と遊んだりしてるところを見たことがないけどなんでだろう………
「ケイ、今日この後レタバ寄らない?」
「まぁいいけど……外じゃ飲まないからな」
「やったー!ケイとデートだ!!」
「デートじゃねえ」
俺はそう言うが翔吾には聞こえていないようでいつの間にかレタバの前まで到着してしまった。
店の前に貼られている新作のポスターに目を輝かせながら外で待っていようとしていた俺を店の中まで引っ張った。
「な、あの新作飲もうぜ!」
「二人一緒の頼むの?」
「ダメ?おそろいがいい」
翔吾は俺を下から覗き込むがそんな顔をしても俺は……
「一緒の頼んでくれたらスペシャルジャンボクレープを買ってあげよう」
「……!!!」
スペシャルジャンボクレープといえば俺の大好物……季節のフルーツをたっぷり使っており隠れた人気がある。この時期だといちごやキウイが使われている。ただ量はものすごく多く食べきった最年少記録が去年立てた十六歳だ俺達のもともと俺はクレープが大好物でそのクレープが売られているクレープ屋とも顔見知り。
その店は夕方からオープンしてすぐ閉まってしまうのでファンの間でも幻のクレープ屋と呼ばれている。
「……仕方ないな…じゃあショートで……」
「きゃー!俺ケイのツンデレのデレの部分好きだよ〜」
「うざい、近い、それにデレでもねえ」
俺は抱きついてこようとする翔吾を払い除け出来上がった瞬間、商品を受け取り俺はそそくさと店を後にした。
「もう!ケイってば俺置いてかないでよね!」
「お前もあんな大勢いる前で抱きつこうとしてくるな、お前にだってファンいるんだぞ」
「えーいる?」
こいつ……自覚無いのか?いつも告白されてんだろ………
さっきだって女性客にこそこそ噂されてたのに……
「お前いつも告白されてんだろ、なんで誰とも付き合わないの?」
「ん?あー、あれがファンなんだ?いつも言われてっからわかんねー」
「キッ………!!」
これが格の違い……ってやつか……すっげー腹立つ
「あ、でもお前誰かと付き合ったりしたの?そういうとこ見たことないけど」
「えー誰とも付き合ってないよ」
「え、なんで?」
こいつがフリーだなんて思ってなかった、実は彼女いましたとか言うのかと思ってた………
でも俺がなんでかと聞いたところで翔吾はフリーズした。理由もなしに断ってるってことか?それは流石に図々しいんじゃ……
俺がそんな事を考えて引いていると何かを察したのか慌てて動き出した。
「なんでって……そりゃあ………」
「……他に好きなやつでもいる感じ?」
どうやら図星だったみたいでさっきまでも慌ただしかったのに更に加速していた。
こいつにも好きな人とかいるんだな。翔吾はミーハーだから恋愛にだってそこまで興味はないものだと思っていた。
「お前の好きな人ってどんなやつなの?気になる」
「………どんなやつだろうね」
「……?」
「それよりクレープ食いに行こうぜ」
「クレープ……!!」
さらっと流されたがクレープが食べれるならどうでもいいだろう。
俺はまんまと釣られ、クレープ屋へ向かうのであった。
「スペシャルジャンボクレープ二つで」
「すみません……本日あとお一つとなっておりまして」
店員が申し訳なさそうに伝えてくる………が翔吾は迷わず「じゃあ一つで!」と答えた。
こいつも結構甘党なもんだから俺の分はなさそうか。
仕方ない、次に好きないちごチョコクレープでも頼もう………
「じゃあ俺はいちごチョコクレープ……」
そう言うと翔吾は目を丸くしてこちらを見てきた。
「え、今日は二つ食う感じ?」
「え?」
「いや、あのクレープ地味にでけえしシェアしよっかなって思ってたけど」
なんだ、シェアするのかだったら最初から言えばいいのに……
いや、でも翔吾のおごりならいいので……
「あと、俺が奢るのはスペシャルジャンボクレープな?お前のことだから俺のおごりならこのままいちごチョコパフェも食おうとか思ってんだろ。頼むのは勝手だけど自分で払えよ」
「うっ………」
読まれていた……でもスペシャルジャンボクレープが食べられるのなら何でもいい。俺はいちごチョコパフェをキャンセルし、ウルトラジャンボクレープができるのを待っていた。
そんな時
「ちょっと!ウルトラジャンボクレープ売り切れなの!?なんでよ!!」
「すみません、大変人気な商品でして本日は材料が……」
「なんでよ!別のクレープの材料使えばいいじゃないの!!」
うわぁ……クレーマーか………
店員さんも大変だろうな……でも俺が入ったところで別になにか良くなるわけでもないし翔吾と一緒に待つか……
そう考えていると突然翔吾は立ち上がりクレーマーの元へと向かった。
「お姉さん、店員さん困ってるよ?お姉さんかわいいんだからそんな顔しちゃダメだよ?」
「な、なによ……」
「照れちゃいました?ほんとかわいいですね、でも今日は売り切れだそうですしまた明日早く来ちゃいましょう」
「やぁねぇ、私アラフィフよ?お姉さんじゃなくてもいいのに……」
なんだかどんどんクレーマーの声が小さくなってくる。これがイケメンパワー………
「ええ、嘘つかないでくださいよ〜まだ三十路手前でしょ?」
「そんなことないわよ〜!ま、今日は坊やに免じて明日また来るわ。バイバイ!」
そう言ってルンルン気分でクレーマーは店を出た。翔吾は笑顔で手を振り店員からも感謝されていた。
ちょうどクレープもできたみたいで翔吾は両手で抱えながら俺の方へと戻ってきた
「おまた~」
「……ねえあれめんどくないの?」
「え?」
「クレーマー追っ払ってたじゃん」
「あーあれね……」
「よくあんな事できたね」
「そりゃあ………ゴニョゴニョ……」
「え?」
今度は翔吾の声が小さくなるのか……
俺が聞き返すと翔吾は恥ずかしそうに俺の耳元まで寄り、囁いてきた
「その……あのまま……ケイまで巻き込まれて暴れでもしたら顔のことバレるかもだろ?ここカウンターから近いし………」
そんなことで恥ずかしいのか……いつも恥ずかしいくらいベッタリなくせに…かわいいとこあんじゃん。
「とっとといつものとこで食うか」
「……うん」
「丁度空いてるし」
そして俺達はあまり目立たない端の席へと移動した。
「おいし?」
「うん、うまい」
いつもの味だ。甘すぎなく食べやすいクリームと色鮮やかな季節のフルーツ、そしてしっとりとした生地。
今の俺だいぶ子供に見えそうだけど翔吾の前なら大丈夫だろう。
「ケイ、クリーム付いてるよ」
「え、どこ?」
俺が舌を伸ばすが逆だったようで翔吾に笑われながら指で教えられた。
「……翔吾が取ってくれても良かったのに」
「え、取っていいの!?」
「…いや、やっぱダメ」
こいつなら取ったついでにとなにかしてくるだろう………
そんな話をしている間に人が増えてきたので俺は急いでクレープを食べ終え、マスクを付け直した。
「えー、もう食べ終わったの?」
「だって人増えてきたし」
「はっ……!俺以外に素顔は見せたくないってこと!?」
なんでそうなるんだ、俺の周りにはポジティブすぎるやつしか寄ってこないのかよ……
翔吾が食べ終わるのを待っていると入ってくる客の中に例の後輩がいたことに気づいた。
アイツは俺に気づいてないみたいだけど………
「ケイ!食べ終わったし帰ろ♡」
「……ん、ああそうだな」
アイツに見つからないように……こっそりと………
なんとかバレずに逃げ切り自宅の前まで到着した
「じゃ、また明日!」
「……明日学校ないじゃん」
「知ってるよ〜、俺はケイとずっと一緒がいいの」
なんで俺にそんなにこだわるんだよ……俺より友達いるのに………
「……俺以外と遊んでるの?」
「ん?ああ、遊んでるけど?明後日は海斗たちとカラオケ行くし……あ、ケイも行きたいとか?」
「それはない、お前以外とは関わらん」
それにカラオケなんて何があるかもわからん。マスク外されてまた笑いものになるかもしれない。
ふと翔吾の方を見ると目をパーっと輝かせてこちらを見ていた。
「な、何?」
「だってそれって告白でしょ?俺意外と関わらないなんて……!こちらこそ………」
「違う、勘違いすんな。お前がべったりすぎるからお前以外と関わったことないんだよ」
「えー、友達できるチャンスじゃん」
「…もしこの顔見られたら何言われるかわからん……」
俺がそう言うと翔吾は一瞬困ったようなリアクションをしたが、俺が家に入ろうとすると俺の頭を撫でてきた。
「まぁ、そんなことでバカにしたりしないやつらだけどケイが嫌なら無理強いはしないよ。またね!」
「おう……」
こいつ距離感バグりすぎてるけどたまにめちゃくちゃ優しいから憎めないんだよな………
「……明日はどこ行くの」
仕方なく付き合ってやることにした俺は仕方なくどこに行くのかを聞く。変なところだったらただじゃおかないからな……
「んー、そうだなー…水族館とかケイ好きそう」
「行く!!」
昔から水族館のあの薄暗い感じが大好きだったもんで即答した。
翔吾は嬉しそうに「明日の11時からね、30分前に迎えに行くわ」と言って、手を振りながら俺の家を後にした。
……仕方ない、早起きして精一杯のオシャレくらいしてってやるか。
俺は自分の部屋に荷物を置き、一旦姉貴の部屋へと向かった
「ねえ姉貴」
「なによケイ、私今良いところなんだけど」
そんな姉貴はいつものようにBL漫画を読みながらダラダラしている。
良いところと言いながらページはめちゃくちゃ序盤で止まってるように見えるが……
「明日翔吾と水族館行くことになったんだけど服選んでくれない?」
俺がそういった途端、姉貴の手が止まり読みかけの本を置いてこちらへ近寄ってきた。
「翔吾くんって、いつもあんたといるイケメンくんよね」
「そうだけど………」
「あんたいつの間に翔吾くんとお付き合いを……」
「付き合ってねえよ」
姉貴、目がガチだ。デザイナー志望だからなんとかなるかもと思ったが聞く相手を間違えただろうか………
「お姉ちゃんに任せなさい」
……まぁ俺がやるよりはマシかもしれないし任せてみる価値はあるか。
俺は姉貴の言われるがままに着替え始める。
白のパーカーと紺デニム、黒の服にアーガイルのカーディガン、かわいらしいオーバーオールに猫耳キャスケット……といろいろと着させられる。というかこんなに服持ってたっけ?
「んー……あんた骨格ストレートっぽいわね」
「こっかくすとれえと?人によって違うん?」
「もちろんよ、私ナチュラルだからなぁ」
どうやら姉貴によると骨格にはストレート、ナチュラル、ウェーブの三種類があるそうだ。俺には違いがわからない………
「んー……あ、これなんてどう!?」
そう言って新たに渡してきたのは薄手のトレンチコートとカーゴパンツだった。
「……どう?」
「うんうん、ぴったりでいいじゃない!」
そう言って姉貴はスマホのカメラを連射する。俺は咄嗟に顔を隠し気になっていたことを聞いてみた。
「てかなんでこんなに服あるの?」
「え?ああ、デザインの参考にしようと思って……ほら!まだあるわよ!」
姉貴のクローゼットの中には女物の服から男物の服までずらりと並びまるでアパレルショップかと思った。
「こんなにどうしたんだよ」
「バイトよバイト!割と高時給なとこに就けてよかったわ」
「まさか………キャバクラ…」
「違うわ!」
姉貴は俺の頭を叩きクローゼットの中からお店のロゴが描かれた黒っぽい服を取り出した。
「私居酒屋で働いてんの、夜に開くからその分夜勤手当でがっぽりもらえるのよ」
「そう、俺も夜勤入れてえ」
「あんたももうすぐ働けるわよ!さ、明日デートでしょ!あんた朝激弱なんだから早く寝なさい!」
「デートじゃない……」
「とにかく早く寝なさいよ、遅刻したら嫌われるわよ?」
「うっ………」
確かに遅刻したらさすがのアイツでもキレてきそうかも……アイツが一番楽しみにしてるだろうし………
「あ、その服全部あんたにあげるから持ってって」
「わかったよ」
姉貴のことだからかさばるからいらないとかその辺だろう。それなら最初からこんなに買うなよとは思うが無料で服がもらえると思えば全然ありがたい。
「その猫耳キャスケット被ってったら?目とかくりくり二重だしきっと似合うわよ」
「余計なお世話じゃ」
「って言いつつ持って帰ってんじゃない」
「……姉貴には似合わないから俺が貰ってあげてるだけ」
「素直じゃないわね〜昔から猫とクレープと暗いところ好きだったくせに」
「…うっさい、寝る」
姉貴のニヤニヤした視線が正直キモかったが俺はさっさと貰った服を片付け、眠りについたのであった。
だが俺の二度寝は姉によって台無しにされる。
「ケイー!もう朝だよー!起きてー!」
姉はもう着替え終わって後は大学に行くだけなようで、もうすぐ学校に行く時間だと言うのに何もしていない俺の姿を見て唖然としている。
「もう!また二度寝しようとしたでしょ!」
「うっせーな……五分くらいいいだろ」
「よくない!ちょっとでも努力したら友達なんていっぱいできるんだから!」
姉貴はいつもこうだ。すごいお節介焼きでとても過保護。
「俺には一人いれば充分なんだよ」
俺は姉貴を部屋から追い出し急いで着替えだす。着替え終わった頃にちょうど朝ごはんも出来上がったみたいで一階から大声で呼ばれた。
俺はそもそも朝はあまり食べない花ので朝ごはんをひとつまみだけして、しっかりマスクを付けてから家を出た。
俺は藤上慧。ごくごく普通の高校三年生。
いつもマスクをして顔を隠しているからか表情がわかりにくいという理由で友達は……多いほうじゃない。
「ケイ〜!おはよ!」
「……はよ」
こいつはたったひ……数少ない友達の一人、片野翔吾。俺よりもだいぶ頭が良く、女子たちからも人気でたまにお近づきになりたい女子からラブレターの伝達係や連絡先を教えてほしいと言われる。
今年は別々のクラスになってちょっと減ったけど。
「ケイ今日もマスクか〜、外してもいいのに」
「……俺はヤダ、どうせまた虐められる…」
「俺が事情伝えれば大丈夫じゃない?悪いこと全くしてないんだから」
「でも……」
「あ、やっべ俺今日日直だわ、またな」
「ばいばい」
俺は軽く手を振り翔吾を見送った後、自分も遅刻しそうになり急いで教室へと向かう。
俺がマスクで顔を隠す理由はマスクの下にある。
昔、児童館で放火事件が起こり火事になった。その時に逃げ遅れていた年下の子を庇った時に大火傷を負い今も火傷の跡が残っている。俺は生まれたて皮膚が強いほうじゃないので移植手術も難しいらしい。
その傷のせいで小学校では虐められ心を病んだ。それからすぐ引っ越したからあの時の子も今何をしているのか知らない。
このことを家族以外で知ってるのは翔吾だけ
俺がいつものようにスマホをいじっていると横から女子に肩をトンと叩かれた。
「ねね、お客さん。前の入口にすっごいイケメンの後輩くんが」
「え?俺に?」
「うん、藤上先輩いますかって」
俺にイケメン後輩の客が……?ありえない、だってそんな知り合い存在しないから。
でも呼ばれたなら一応行かなきゃな…俺は女子たちに道を開けてもらい噂の後輩の元へと向かった。
「藤上先輩こんにちは」
「……こんにちは」
やはり思った通り見覚えのない後輩が立っていた。しかも高一とは思えないほど高身長…高三で164センチの俺からしたら正直羨ましい。
「なんのようですか」
「んーそうだな……一緒にお昼食べません?」
「もう食べちゃったけど」
昼休憩から20分もしているのだから食べ終わっててもおかしくない。その後輩は「そうですよね」と言いながらも教室から離れようとしなかった。
「じゃ、これで」
「まっ、待って!」
「……何?」
「うーんと……じゃあ勉強教えてください」
「じゃあってなんだよ、俺あんまり頭よくないよ」
「うっ……」
「用がないなら帰ってくれない?」
「……じゃあ先輩とお話しをしたいんですけど」
元の要件はそれか……それなら最初からそう言ってよかったんじゃ?
「ごめんけどよく分かんないやつとは話したくない」
「あー……そうですよね、すみません急にこんなこと…」
「それじゃ……」
俺が後輩を置いて教室へ戻ろうとした時また後輩に呼び止められる。
「その……矢沢葵です。覚えてくれたら嬉しいです」
その言葉に俺は一瞬固まった。どこかで聞いたことあるような……思い出せない…
「……わかったもう帰んな、お前一年だろ。ここ三年のエリアだから授業遅れるぞ」
「はい、失礼します」
今度は満足したようでスッと教室のある四階の方へと戻っていった。
「矢沢くんっていうんだ……連絡先欲しくね?」
「それな〜後輩にあんなイケメンいたなんて」
女子たちは矢沢の話題でいっぱいだ。俺は別にどうでもいい、イケメン後輩なんていたってなんとも思わんし髪も染めてて見るからに危なそう。とりあえず関わらないでおこう…
…と思っていた放課後
「藤上先輩!一緒に帰りましょう!」
「……嫌だと言ったら?」
「一緒に帰宅する……?」
「変わってねえじゃん、一緒に帰らんよ」
「…じゃあこのまま放課後一緒に勉強しようってこと…!?」
なんでそうなるんだ…ポジティブすぎやしないか?
「しない。俺一緒に帰るやついるからお前は先帰れ、モテるんだし一緒に帰れるやつなんて山ほどいるだろ」
「えー……それって彼女ですか?」
「いや、男」
そんな話をしているとスマホに一通のLIMEが来た。
差出人は翔吾。『人多いから先校門で待ってる』とだけ送られていた。
確かに周りを見れば矢沢を取り囲む女子たちでいっぱいだ。
「ごめん、相手待たせてるから」
「……わかりました」
断ってもしつこく追いかけてきそうだと思ったのに思っていたよりすんなり解放してくれた。
翔吾を待たせても悪いので矢沢の顔も見ず、俺は急いで玄関へと向かった。
「おまたせ」
「遅かったね、なんかあった?」
翔吾は何か勘違いしているようで必要以上に心配をしてくる。
「大丈夫だから……後輩が俺に用事あったみたいでそれで…」
「……そう、ならいいんだけど…てっきりマスクでも外れて虐められたとかかと」
「そう簡単には外れないし……」
「まぁもしそんなこと起きても俺が守ってやるからな」
「ありがと、心強い」
まぁこいつなら周りからの信頼も厚いし人気だから……きっと本当にどうにかしてくれるんだろうな
唯一の友達だし………
「でもいいの?俺なんかと一緒にいて……俺マスク外さないから表情わかりにくいって言われてるからお前以外に友達いないし……」
「ゼロより寂しくないだろ?それに俺はケイの優しいところが好きで一緒にいるんだから」
「……でも何か言われない?あんなやつと一緒にいるなとか」
俺がこんな見た目だからマスクをしてても一定数いじめを受ける。小学校や中学校と比べれば少なくはなったが……
「そんなやつ雑魚だよ、かっこ悪くね?わざわざ人の容姿で好き嫌い決めるとかドン引き」
「そう……」
こいつがモテるのはこういうところなんだろうな……けど翔吾が俺意外と遊んだりしてるところを見たことがないけどなんでだろう………
「ケイ、今日この後レタバ寄らない?」
「まぁいいけど……外じゃ飲まないからな」
「やったー!ケイとデートだ!!」
「デートじゃねえ」
俺はそう言うが翔吾には聞こえていないようでいつの間にかレタバの前まで到着してしまった。
店の前に貼られている新作のポスターに目を輝かせながら外で待っていようとしていた俺を店の中まで引っ張った。
「な、あの新作飲もうぜ!」
「二人一緒の頼むの?」
「ダメ?おそろいがいい」
翔吾は俺を下から覗き込むがそんな顔をしても俺は……
「一緒の頼んでくれたらスペシャルジャンボクレープを買ってあげよう」
「……!!!」
スペシャルジャンボクレープといえば俺の大好物……季節のフルーツをたっぷり使っており隠れた人気がある。この時期だといちごやキウイが使われている。ただ量はものすごく多く食べきった最年少記録が去年立てた十六歳だ俺達のもともと俺はクレープが大好物でそのクレープが売られているクレープ屋とも顔見知り。
その店は夕方からオープンしてすぐ閉まってしまうのでファンの間でも幻のクレープ屋と呼ばれている。
「……仕方ないな…じゃあショートで……」
「きゃー!俺ケイのツンデレのデレの部分好きだよ〜」
「うざい、近い、それにデレでもねえ」
俺は抱きついてこようとする翔吾を払い除け出来上がった瞬間、商品を受け取り俺はそそくさと店を後にした。
「もう!ケイってば俺置いてかないでよね!」
「お前もあんな大勢いる前で抱きつこうとしてくるな、お前にだってファンいるんだぞ」
「えーいる?」
こいつ……自覚無いのか?いつも告白されてんだろ………
さっきだって女性客にこそこそ噂されてたのに……
「お前いつも告白されてんだろ、なんで誰とも付き合わないの?」
「ん?あー、あれがファンなんだ?いつも言われてっからわかんねー」
「キッ………!!」
これが格の違い……ってやつか……すっげー腹立つ
「あ、でもお前誰かと付き合ったりしたの?そういうとこ見たことないけど」
「えー誰とも付き合ってないよ」
「え、なんで?」
こいつがフリーだなんて思ってなかった、実は彼女いましたとか言うのかと思ってた………
でも俺がなんでかと聞いたところで翔吾はフリーズした。理由もなしに断ってるってことか?それは流石に図々しいんじゃ……
俺がそんな事を考えて引いていると何かを察したのか慌てて動き出した。
「なんでって……そりゃあ………」
「……他に好きなやつでもいる感じ?」
どうやら図星だったみたいでさっきまでも慌ただしかったのに更に加速していた。
こいつにも好きな人とかいるんだな。翔吾はミーハーだから恋愛にだってそこまで興味はないものだと思っていた。
「お前の好きな人ってどんなやつなの?気になる」
「………どんなやつだろうね」
「……?」
「それよりクレープ食いに行こうぜ」
「クレープ……!!」
さらっと流されたがクレープが食べれるならどうでもいいだろう。
俺はまんまと釣られ、クレープ屋へ向かうのであった。
「スペシャルジャンボクレープ二つで」
「すみません……本日あとお一つとなっておりまして」
店員が申し訳なさそうに伝えてくる………が翔吾は迷わず「じゃあ一つで!」と答えた。
こいつも結構甘党なもんだから俺の分はなさそうか。
仕方ない、次に好きないちごチョコクレープでも頼もう………
「じゃあ俺はいちごチョコクレープ……」
そう言うと翔吾は目を丸くしてこちらを見てきた。
「え、今日は二つ食う感じ?」
「え?」
「いや、あのクレープ地味にでけえしシェアしよっかなって思ってたけど」
なんだ、シェアするのかだったら最初から言えばいいのに……
いや、でも翔吾のおごりならいいので……
「あと、俺が奢るのはスペシャルジャンボクレープな?お前のことだから俺のおごりならこのままいちごチョコパフェも食おうとか思ってんだろ。頼むのは勝手だけど自分で払えよ」
「うっ………」
読まれていた……でもスペシャルジャンボクレープが食べられるのなら何でもいい。俺はいちごチョコパフェをキャンセルし、ウルトラジャンボクレープができるのを待っていた。
そんな時
「ちょっと!ウルトラジャンボクレープ売り切れなの!?なんでよ!!」
「すみません、大変人気な商品でして本日は材料が……」
「なんでよ!別のクレープの材料使えばいいじゃないの!!」
うわぁ……クレーマーか………
店員さんも大変だろうな……でも俺が入ったところで別になにか良くなるわけでもないし翔吾と一緒に待つか……
そう考えていると突然翔吾は立ち上がりクレーマーの元へと向かった。
「お姉さん、店員さん困ってるよ?お姉さんかわいいんだからそんな顔しちゃダメだよ?」
「な、なによ……」
「照れちゃいました?ほんとかわいいですね、でも今日は売り切れだそうですしまた明日早く来ちゃいましょう」
「やぁねぇ、私アラフィフよ?お姉さんじゃなくてもいいのに……」
なんだかどんどんクレーマーの声が小さくなってくる。これがイケメンパワー………
「ええ、嘘つかないでくださいよ〜まだ三十路手前でしょ?」
「そんなことないわよ〜!ま、今日は坊やに免じて明日また来るわ。バイバイ!」
そう言ってルンルン気分でクレーマーは店を出た。翔吾は笑顔で手を振り店員からも感謝されていた。
ちょうどクレープもできたみたいで翔吾は両手で抱えながら俺の方へと戻ってきた
「おまた~」
「……ねえあれめんどくないの?」
「え?」
「クレーマー追っ払ってたじゃん」
「あーあれね……」
「よくあんな事できたね」
「そりゃあ………ゴニョゴニョ……」
「え?」
今度は翔吾の声が小さくなるのか……
俺が聞き返すと翔吾は恥ずかしそうに俺の耳元まで寄り、囁いてきた
「その……あのまま……ケイまで巻き込まれて暴れでもしたら顔のことバレるかもだろ?ここカウンターから近いし………」
そんなことで恥ずかしいのか……いつも恥ずかしいくらいベッタリなくせに…かわいいとこあんじゃん。
「とっとといつものとこで食うか」
「……うん」
「丁度空いてるし」
そして俺達はあまり目立たない端の席へと移動した。
「おいし?」
「うん、うまい」
いつもの味だ。甘すぎなく食べやすいクリームと色鮮やかな季節のフルーツ、そしてしっとりとした生地。
今の俺だいぶ子供に見えそうだけど翔吾の前なら大丈夫だろう。
「ケイ、クリーム付いてるよ」
「え、どこ?」
俺が舌を伸ばすが逆だったようで翔吾に笑われながら指で教えられた。
「……翔吾が取ってくれても良かったのに」
「え、取っていいの!?」
「…いや、やっぱダメ」
こいつなら取ったついでにとなにかしてくるだろう………
そんな話をしている間に人が増えてきたので俺は急いでクレープを食べ終え、マスクを付け直した。
「えー、もう食べ終わったの?」
「だって人増えてきたし」
「はっ……!俺以外に素顔は見せたくないってこと!?」
なんでそうなるんだ、俺の周りにはポジティブすぎるやつしか寄ってこないのかよ……
翔吾が食べ終わるのを待っていると入ってくる客の中に例の後輩がいたことに気づいた。
アイツは俺に気づいてないみたいだけど………
「ケイ!食べ終わったし帰ろ♡」
「……ん、ああそうだな」
アイツに見つからないように……こっそりと………
なんとかバレずに逃げ切り自宅の前まで到着した
「じゃ、また明日!」
「……明日学校ないじゃん」
「知ってるよ〜、俺はケイとずっと一緒がいいの」
なんで俺にそんなにこだわるんだよ……俺より友達いるのに………
「……俺以外と遊んでるの?」
「ん?ああ、遊んでるけど?明後日は海斗たちとカラオケ行くし……あ、ケイも行きたいとか?」
「それはない、お前以外とは関わらん」
それにカラオケなんて何があるかもわからん。マスク外されてまた笑いものになるかもしれない。
ふと翔吾の方を見ると目をパーっと輝かせてこちらを見ていた。
「な、何?」
「だってそれって告白でしょ?俺意外と関わらないなんて……!こちらこそ………」
「違う、勘違いすんな。お前がべったりすぎるからお前以外と関わったことないんだよ」
「えー、友達できるチャンスじゃん」
「…もしこの顔見られたら何言われるかわからん……」
俺がそう言うと翔吾は一瞬困ったようなリアクションをしたが、俺が家に入ろうとすると俺の頭を撫でてきた。
「まぁ、そんなことでバカにしたりしないやつらだけどケイが嫌なら無理強いはしないよ。またね!」
「おう……」
こいつ距離感バグりすぎてるけどたまにめちゃくちゃ優しいから憎めないんだよな………
「……明日はどこ行くの」
仕方なく付き合ってやることにした俺は仕方なくどこに行くのかを聞く。変なところだったらただじゃおかないからな……
「んー、そうだなー…水族館とかケイ好きそう」
「行く!!」
昔から水族館のあの薄暗い感じが大好きだったもんで即答した。
翔吾は嬉しそうに「明日の11時からね、30分前に迎えに行くわ」と言って、手を振りながら俺の家を後にした。
……仕方ない、早起きして精一杯のオシャレくらいしてってやるか。
俺は自分の部屋に荷物を置き、一旦姉貴の部屋へと向かった
「ねえ姉貴」
「なによケイ、私今良いところなんだけど」
そんな姉貴はいつものようにBL漫画を読みながらダラダラしている。
良いところと言いながらページはめちゃくちゃ序盤で止まってるように見えるが……
「明日翔吾と水族館行くことになったんだけど服選んでくれない?」
俺がそういった途端、姉貴の手が止まり読みかけの本を置いてこちらへ近寄ってきた。
「翔吾くんって、いつもあんたといるイケメンくんよね」
「そうだけど………」
「あんたいつの間に翔吾くんとお付き合いを……」
「付き合ってねえよ」
姉貴、目がガチだ。デザイナー志望だからなんとかなるかもと思ったが聞く相手を間違えただろうか………
「お姉ちゃんに任せなさい」
……まぁ俺がやるよりはマシかもしれないし任せてみる価値はあるか。
俺は姉貴の言われるがままに着替え始める。
白のパーカーと紺デニム、黒の服にアーガイルのカーディガン、かわいらしいオーバーオールに猫耳キャスケット……といろいろと着させられる。というかこんなに服持ってたっけ?
「んー……あんた骨格ストレートっぽいわね」
「こっかくすとれえと?人によって違うん?」
「もちろんよ、私ナチュラルだからなぁ」
どうやら姉貴によると骨格にはストレート、ナチュラル、ウェーブの三種類があるそうだ。俺には違いがわからない………
「んー……あ、これなんてどう!?」
そう言って新たに渡してきたのは薄手のトレンチコートとカーゴパンツだった。
「……どう?」
「うんうん、ぴったりでいいじゃない!」
そう言って姉貴はスマホのカメラを連射する。俺は咄嗟に顔を隠し気になっていたことを聞いてみた。
「てかなんでこんなに服あるの?」
「え?ああ、デザインの参考にしようと思って……ほら!まだあるわよ!」
姉貴のクローゼットの中には女物の服から男物の服までずらりと並びまるでアパレルショップかと思った。
「こんなにどうしたんだよ」
「バイトよバイト!割と高時給なとこに就けてよかったわ」
「まさか………キャバクラ…」
「違うわ!」
姉貴は俺の頭を叩きクローゼットの中からお店のロゴが描かれた黒っぽい服を取り出した。
「私居酒屋で働いてんの、夜に開くからその分夜勤手当でがっぽりもらえるのよ」
「そう、俺も夜勤入れてえ」
「あんたももうすぐ働けるわよ!さ、明日デートでしょ!あんた朝激弱なんだから早く寝なさい!」
「デートじゃない……」
「とにかく早く寝なさいよ、遅刻したら嫌われるわよ?」
「うっ………」
確かに遅刻したらさすがのアイツでもキレてきそうかも……アイツが一番楽しみにしてるだろうし………
「あ、その服全部あんたにあげるから持ってって」
「わかったよ」
姉貴のことだからかさばるからいらないとかその辺だろう。それなら最初からこんなに買うなよとは思うが無料で服がもらえると思えば全然ありがたい。
「その猫耳キャスケット被ってったら?目とかくりくり二重だしきっと似合うわよ」
「余計なお世話じゃ」
「って言いつつ持って帰ってんじゃない」
「……姉貴には似合わないから俺が貰ってあげてるだけ」
「素直じゃないわね〜昔から猫とクレープと暗いところ好きだったくせに」
「…うっさい、寝る」
姉貴のニヤニヤした視線が正直キモかったが俺はさっさと貰った服を片付け、眠りについたのであった。