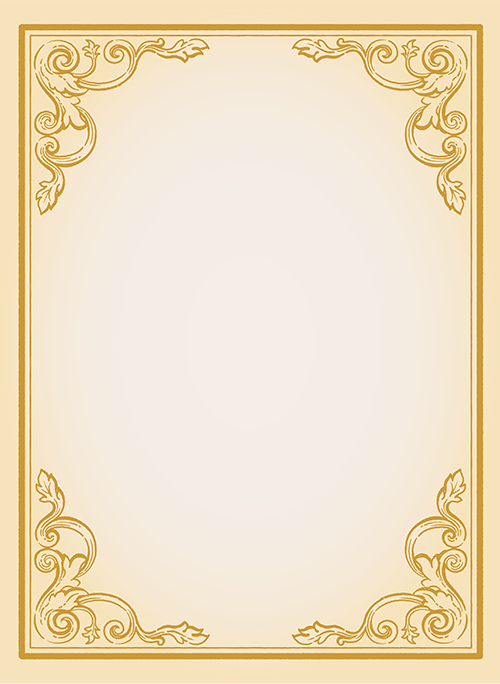「ねえ、姉さま。明日の公開演習、無理なさらないでくださいね?」
隣室の障子越しに、撫子の甘い声が滑り込んできた。
「花精が現れなかったら、また皆の前で笑いものに……姉さまの名が、汚れてしまいますもの」
その言葉に、紫乃の胸がちくりと刺された。
この国では、花名を持つ娘に宿る「花精」──神の使いを呼び出せるかどうかが、娘の価値を決める。
明日の公開演習では、生徒たちが壇上で花精を顕現させ、自分の花名を証明しなければならない。
そこで認められた者は、神祇院の「推挙候補」となり、やがて選ばれた一人が、花巫女として神託を伝える。
そして花巫女には、名門・藤宮家との婚姻という栄誉が約束されている。
撫子は鏡の前で髪をとかしながら、くすりと笑った。
「姉さまには、きっと難しいでしょうね」
紫乃は「はい」とだけ答え、膝の上の掌を見つめた。そこには、目に見えない花びらが、すうっと落ちた気がした。
翌日。
講義室は、いつもよりも一段と張り詰めた空気に包まれていた。
天井近くまで届く縦格子の窓からは、やわらかな春光が差し込み、床の敷板に影を落としている。
その中央、壇の上には金の文様をあしらった香台が置かれ、花名持ちの娘たちが順に壇上へと呼ばれていた。
「では次、撫子さま」
教師の声に、教室がざわめく。
撫子はゆっくりと立ち上がり、白いドレスの裾を揺らして壇へ上がった。
「花名は、撫子」
撫子は笑みを浮かべたまま、優雅に頭を下げる。
「花言葉は、無邪気──そして、可憐。ふふ……似合っておりますでしょう?」
同意を示すように、講義室に拍手が広がる。視察に来ていた神祇院の役人も、興味深げに頷いていた。
撫子はひと呼吸おいてから、静かに一歩を踏み出した。
香台に近づいたその瞬間──
空気が震えた。
香炉の火が、風もないのにふっと揺らぎ、澄んだ香がひとすじ、天へと昇っていく。
そのときだった。
撫子の背後に、ふわりと光が差す。
微細な金の粒子が空中に舞い、それが輪郭を描くように集まっていく。
やがて現れたのは、淡い光を纏った少女の姿。
撫子と同じ、細くしなやかな肢体。
少女の足元には、撫子の花名と同じ、風にゆれる撫子の花が静かに咲き広がる。
「……まあ」「顕現なさった……!」
さざ波のような感嘆の声が、場内を包んだ。
撫子は上品な笑みを浮かべ、一礼した。
花精の姿が香の煙とともに消えていくころ、彼女は何事もなかったかのように壇を降りた。
「……次。紫乃さま」
名を呼ばれても、紫乃の足はすくんだ。
撫子の背が、まばゆかった。
あまりに完璧で、美しくて──息を呑むほか、なかった。
誰もが見ていないふりをしながら、壇上へと意識を向けている。
紫乃は、静かに立ち上がり、壇へ上がった。
「……花名は、紫苑」
紫乃の声はかすかだった。
おそるおそる前を向いたそのとき、撫子はおもむろに手を挙げた。
「先生。申し訳ありませんが、お姉さまはまだ一度も、花精を顕現なさったことがないのです。この場に立たれるのは、お気の毒では……?」
静寂。
教師は何も言わず、眉をひそめたまま視線をそらした。
紫乃はゆっくりと一礼し、壇から降りた。
彼女の背には何も現れなかった。
しかし足元をかすめるように、ほんの一瞬、白紫の気配が揺れたのを──見ていた者が、ひとりだけいた。
藤真。
彼の視線は、教室の誰とも違っていた。
鋭く、でも優しく。
人知れず咲いた一輪の花を、見つめていたかのように。
*
講義のあと、紫乃はひとり、裏庭の藤棚の下に佇んでいた。
藤の根元に膝をつき、彼女は手を合わせた。背筋を伸ばし、目を閉じる。音もなく、祈る。
「……神さま」
指先に力がこもる。声は、祈りというより問いに近かった。
「わたしは『紫苑』と名づけられただけなのですか?」
紫乃は手のひらを見つめる。すると、風が指先を撫で、懐かしい紫苑の香りを運んできた。
初夏、母と歩いた小道。脇に咲く小さな紫の花──紫苑。
「失礼する」
低く、凛とした声だった。
紫乃が振り向くと、藤真がそこにいた。
制帽の影に隠れた藤色の瞳が、ゆっくりと彼女を見つめていた。
「香った。……わずかにだが、たしかに『紫苑』の気配があった」
紫乃は、言葉を返せなかった。
自分以外に、それを感じ取った人がいたことに、驚いていた。
藤真は懐から一冊の古い冊子を取り出す。
装丁の隅に『花名録』の文字があった。
「君の花名は、紫苑。──忘れられし者に寄り添う花だ」
「忘れられし、者……」
「だが同時に、『忘れまじ』と願う者の魂に宿る」
そこで、藤真はふと目を細める。
「紫苑は、人の背丈よりも高く育ち、霜にさえ耐える花だ。越冬し、何度も咲く──ただ儚いだけの花ではない」
「……強い、花ですね」
「ああ。だからこそ、その花精は猛々しい姿で顕現するかもしれない。──まるで、祈りを護る戦神のように」
その言葉に、紫乃の瞳は揺らいだ。
藤真はふと、制帽を外して手に持った。
艶やかな漆黒の髪が風にゆれ、夕映えにきらめく。
「君を見ていると、思い出すことがある」
藤真の声は低く、風にとけるように静かだった。
「幼い頃、藤の名を何度も呼んで祈った。でも、応えはなかった」
紫乃はそっと息を呑んだ。
「家はすぐ決めつけた──『才がない、信心が足りない』と。それ以来、祭祀の場に立てなかった」
藤真はふっと笑う。
「だが、一度顕現すれば皆が掌を返した。それが現実だ。以来、人とも神とも、距離を置く癖がついた」
淡々とした声の奥に、紫乃は静かな痛みを感じ取った。
風が吹いた。
頭上の藤の花が、さわりと揺れる。
すると、ほんの一瞬──紫乃の背に、花びらの幻影がふわりと浮かび、そして消えた。
紫乃がはっとして見上げると、藤真は静かに頷いた。
「花精は、君の祈りを見ていたよ」
その声が、胸の奥に深くしみ込んだ。
*
夜。
紫乃は灯の消えた部屋の片隅、小さな神棚の前で静かに手を合わせていた。
目を閉じ、紫苑の名を、心のなかでひそかに唱える。
花とは、名を呼び、祈りを捧げし者に応える──神祇院の古老がそう語っていた。
その教えのとおり、紫乃は毎晩、ひとり祈りを捧げている。
「姉さま、まだ起きていらっしゃるの?」
紫乃の姿を通りすがりに見た撫子は、一度、ふっと鼻先で笑った。
「ねえ、明日は藤真さまがいらっしゃるんですって。……神祇院の調査ということで。くれぐれも、お気を遣わせないようにね、姉さま?」
やさしく響く声色には、悪意の棘が混ざっていない。それでも、どこまでも透けて見える意図。
あなたには、何も起こらない。
撫子の声はそう告げていた。
その名──藤真。
紫乃の胸の奥で、波紋が広がった。
瞼の裏に浮かぶのは、遠い記憶の欠片。
藤真に初めて会った、七年前のことだった。
隣室の障子越しに、撫子の甘い声が滑り込んできた。
「花精が現れなかったら、また皆の前で笑いものに……姉さまの名が、汚れてしまいますもの」
その言葉に、紫乃の胸がちくりと刺された。
この国では、花名を持つ娘に宿る「花精」──神の使いを呼び出せるかどうかが、娘の価値を決める。
明日の公開演習では、生徒たちが壇上で花精を顕現させ、自分の花名を証明しなければならない。
そこで認められた者は、神祇院の「推挙候補」となり、やがて選ばれた一人が、花巫女として神託を伝える。
そして花巫女には、名門・藤宮家との婚姻という栄誉が約束されている。
撫子は鏡の前で髪をとかしながら、くすりと笑った。
「姉さまには、きっと難しいでしょうね」
紫乃は「はい」とだけ答え、膝の上の掌を見つめた。そこには、目に見えない花びらが、すうっと落ちた気がした。
翌日。
講義室は、いつもよりも一段と張り詰めた空気に包まれていた。
天井近くまで届く縦格子の窓からは、やわらかな春光が差し込み、床の敷板に影を落としている。
その中央、壇の上には金の文様をあしらった香台が置かれ、花名持ちの娘たちが順に壇上へと呼ばれていた。
「では次、撫子さま」
教師の声に、教室がざわめく。
撫子はゆっくりと立ち上がり、白いドレスの裾を揺らして壇へ上がった。
「花名は、撫子」
撫子は笑みを浮かべたまま、優雅に頭を下げる。
「花言葉は、無邪気──そして、可憐。ふふ……似合っておりますでしょう?」
同意を示すように、講義室に拍手が広がる。視察に来ていた神祇院の役人も、興味深げに頷いていた。
撫子はひと呼吸おいてから、静かに一歩を踏み出した。
香台に近づいたその瞬間──
空気が震えた。
香炉の火が、風もないのにふっと揺らぎ、澄んだ香がひとすじ、天へと昇っていく。
そのときだった。
撫子の背後に、ふわりと光が差す。
微細な金の粒子が空中に舞い、それが輪郭を描くように集まっていく。
やがて現れたのは、淡い光を纏った少女の姿。
撫子と同じ、細くしなやかな肢体。
少女の足元には、撫子の花名と同じ、風にゆれる撫子の花が静かに咲き広がる。
「……まあ」「顕現なさった……!」
さざ波のような感嘆の声が、場内を包んだ。
撫子は上品な笑みを浮かべ、一礼した。
花精の姿が香の煙とともに消えていくころ、彼女は何事もなかったかのように壇を降りた。
「……次。紫乃さま」
名を呼ばれても、紫乃の足はすくんだ。
撫子の背が、まばゆかった。
あまりに完璧で、美しくて──息を呑むほか、なかった。
誰もが見ていないふりをしながら、壇上へと意識を向けている。
紫乃は、静かに立ち上がり、壇へ上がった。
「……花名は、紫苑」
紫乃の声はかすかだった。
おそるおそる前を向いたそのとき、撫子はおもむろに手を挙げた。
「先生。申し訳ありませんが、お姉さまはまだ一度も、花精を顕現なさったことがないのです。この場に立たれるのは、お気の毒では……?」
静寂。
教師は何も言わず、眉をひそめたまま視線をそらした。
紫乃はゆっくりと一礼し、壇から降りた。
彼女の背には何も現れなかった。
しかし足元をかすめるように、ほんの一瞬、白紫の気配が揺れたのを──見ていた者が、ひとりだけいた。
藤真。
彼の視線は、教室の誰とも違っていた。
鋭く、でも優しく。
人知れず咲いた一輪の花を、見つめていたかのように。
*
講義のあと、紫乃はひとり、裏庭の藤棚の下に佇んでいた。
藤の根元に膝をつき、彼女は手を合わせた。背筋を伸ばし、目を閉じる。音もなく、祈る。
「……神さま」
指先に力がこもる。声は、祈りというより問いに近かった。
「わたしは『紫苑』と名づけられただけなのですか?」
紫乃は手のひらを見つめる。すると、風が指先を撫で、懐かしい紫苑の香りを運んできた。
初夏、母と歩いた小道。脇に咲く小さな紫の花──紫苑。
「失礼する」
低く、凛とした声だった。
紫乃が振り向くと、藤真がそこにいた。
制帽の影に隠れた藤色の瞳が、ゆっくりと彼女を見つめていた。
「香った。……わずかにだが、たしかに『紫苑』の気配があった」
紫乃は、言葉を返せなかった。
自分以外に、それを感じ取った人がいたことに、驚いていた。
藤真は懐から一冊の古い冊子を取り出す。
装丁の隅に『花名録』の文字があった。
「君の花名は、紫苑。──忘れられし者に寄り添う花だ」
「忘れられし、者……」
「だが同時に、『忘れまじ』と願う者の魂に宿る」
そこで、藤真はふと目を細める。
「紫苑は、人の背丈よりも高く育ち、霜にさえ耐える花だ。越冬し、何度も咲く──ただ儚いだけの花ではない」
「……強い、花ですね」
「ああ。だからこそ、その花精は猛々しい姿で顕現するかもしれない。──まるで、祈りを護る戦神のように」
その言葉に、紫乃の瞳は揺らいだ。
藤真はふと、制帽を外して手に持った。
艶やかな漆黒の髪が風にゆれ、夕映えにきらめく。
「君を見ていると、思い出すことがある」
藤真の声は低く、風にとけるように静かだった。
「幼い頃、藤の名を何度も呼んで祈った。でも、応えはなかった」
紫乃はそっと息を呑んだ。
「家はすぐ決めつけた──『才がない、信心が足りない』と。それ以来、祭祀の場に立てなかった」
藤真はふっと笑う。
「だが、一度顕現すれば皆が掌を返した。それが現実だ。以来、人とも神とも、距離を置く癖がついた」
淡々とした声の奥に、紫乃は静かな痛みを感じ取った。
風が吹いた。
頭上の藤の花が、さわりと揺れる。
すると、ほんの一瞬──紫乃の背に、花びらの幻影がふわりと浮かび、そして消えた。
紫乃がはっとして見上げると、藤真は静かに頷いた。
「花精は、君の祈りを見ていたよ」
その声が、胸の奥に深くしみ込んだ。
*
夜。
紫乃は灯の消えた部屋の片隅、小さな神棚の前で静かに手を合わせていた。
目を閉じ、紫苑の名を、心のなかでひそかに唱える。
花とは、名を呼び、祈りを捧げし者に応える──神祇院の古老がそう語っていた。
その教えのとおり、紫乃は毎晩、ひとり祈りを捧げている。
「姉さま、まだ起きていらっしゃるの?」
紫乃の姿を通りすがりに見た撫子は、一度、ふっと鼻先で笑った。
「ねえ、明日は藤真さまがいらっしゃるんですって。……神祇院の調査ということで。くれぐれも、お気を遣わせないようにね、姉さま?」
やさしく響く声色には、悪意の棘が混ざっていない。それでも、どこまでも透けて見える意図。
あなたには、何も起こらない。
撫子の声はそう告げていた。
その名──藤真。
紫乃の胸の奥で、波紋が広がった。
瞼の裏に浮かぶのは、遠い記憶の欠片。
藤真に初めて会った、七年前のことだった。