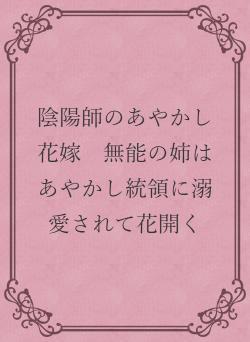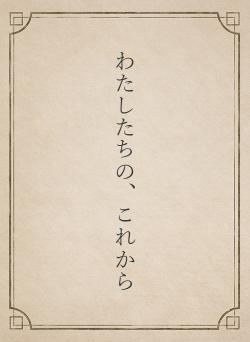結論から言うと、カメラは簡単に手に入った。
商店街の端っこにあるカメラ屋さんで、中古の一眼が安く売り出されていたのだ。
「これください」
「嬢ちゃんたち、めかしこんで撮影会か? いいね、めいっぱい楽しんできな」
薄暗い店内では、日置の低い声も、たしかに主張するのどぼとけも、骨ばった手もよく見えないらしい。中年の店主はうれしげにあたしたちを送り出してくれた。
日置に連れられて、あたしは商店街の近くの河川敷に来ていた。
「ここを押すんだ」
「ここ?」
純白のロリィタ(男)にレクチャーを受けて、シャッターを切るあたし。そろそろ人生を終わらせようと思っていたのに、世界で一番くだらないことをしている。
おそらく諦観がにじみきった目をしているであろうあたしとは真逆で、日置はどこか浮かれている。
「あと、俺のロリィタはこの角度から撮るのが一番いい」
「……詳しいね」
「ロリィタで撮影会をするコミュニティがあるんだ」
やれSNSがどうとか、やれサークルがどうとか、日置は自慢げにしゃべっていた。いつもの違う国の言葉じゃないけど、あたしはさして興味は持てなかった。
言われるがままに何枚か日置を撮っては飽き、空とか川とかもついでにフィルムに収めてみたけど、どれもこれもありきたりな長方形にしかならなかった。
あたしが思っていたような、時を止める魔法からはほど遠い。
「……思っていたよりつまんない」
あたしの言葉は人のいない河川敷に吸い込まれていく。
日置はあたしを見て、信じられないといった顔つきになった。「俺はこんなに楽しいのに!?」とでも叫びだしそうな表情をしている。
「でも、カメラはきらいじゃない」
「ならよかった」
日置はほっと息をつき、川べりに腰をおろした。
「ロリィタの日置は好き。今日の純白の衣装は一番好き。でも、違う国の言葉でしゃべる日置はきらい。小学校のときに給食に出たマンゴーのほうがきらい」
忘れもしない、小学四年生の給食の時間。味がしなくてゴムのような食感だけのマンゴーを嚥下するだけの時間を、永遠のように感じた。
「でも、あたし、自分のことが一番きらい。ママに捨てられて、パパに殴られて、学校に居場所がないあたしが一番いや」
「この世界には、あたしの呼吸がしやすい場所はないのかなぁ」
「……それは俺にもわかんねぇよ」
河川敷に座る日置は、きちんとハンカチを敷いて純白のロリィタが汚れないようにしていた。でも、脚はがばっと開いていて、族のような態度で悪態をついている。
男なのにロリィタが好き(あ、ロリィタを着ている自分に興奮するって言ってたからちょっと違うかも)で、メガネくんで、メイクがうまくて、鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員で、真面目で律儀で、喋りだすと止まらなくて、違う国の住人。
あたしはもう一度カメラを構えて、そんな日置の世界で一番くだらない時間を止めた。
商店街の端っこにあるカメラ屋さんで、中古の一眼が安く売り出されていたのだ。
「これください」
「嬢ちゃんたち、めかしこんで撮影会か? いいね、めいっぱい楽しんできな」
薄暗い店内では、日置の低い声も、たしかに主張するのどぼとけも、骨ばった手もよく見えないらしい。中年の店主はうれしげにあたしたちを送り出してくれた。
日置に連れられて、あたしは商店街の近くの河川敷に来ていた。
「ここを押すんだ」
「ここ?」
純白のロリィタ(男)にレクチャーを受けて、シャッターを切るあたし。そろそろ人生を終わらせようと思っていたのに、世界で一番くだらないことをしている。
おそらく諦観がにじみきった目をしているであろうあたしとは真逆で、日置はどこか浮かれている。
「あと、俺のロリィタはこの角度から撮るのが一番いい」
「……詳しいね」
「ロリィタで撮影会をするコミュニティがあるんだ」
やれSNSがどうとか、やれサークルがどうとか、日置は自慢げにしゃべっていた。いつもの違う国の言葉じゃないけど、あたしはさして興味は持てなかった。
言われるがままに何枚か日置を撮っては飽き、空とか川とかもついでにフィルムに収めてみたけど、どれもこれもありきたりな長方形にしかならなかった。
あたしが思っていたような、時を止める魔法からはほど遠い。
「……思っていたよりつまんない」
あたしの言葉は人のいない河川敷に吸い込まれていく。
日置はあたしを見て、信じられないといった顔つきになった。「俺はこんなに楽しいのに!?」とでも叫びだしそうな表情をしている。
「でも、カメラはきらいじゃない」
「ならよかった」
日置はほっと息をつき、川べりに腰をおろした。
「ロリィタの日置は好き。今日の純白の衣装は一番好き。でも、違う国の言葉でしゃべる日置はきらい。小学校のときに給食に出たマンゴーのほうがきらい」
忘れもしない、小学四年生の給食の時間。味がしなくてゴムのような食感だけのマンゴーを嚥下するだけの時間を、永遠のように感じた。
「でも、あたし、自分のことが一番きらい。ママに捨てられて、パパに殴られて、学校に居場所がないあたしが一番いや」
「この世界には、あたしの呼吸がしやすい場所はないのかなぁ」
「……それは俺にもわかんねぇよ」
河川敷に座る日置は、きちんとハンカチを敷いて純白のロリィタが汚れないようにしていた。でも、脚はがばっと開いていて、族のような態度で悪態をついている。
男なのにロリィタが好き(あ、ロリィタを着ている自分に興奮するって言ってたからちょっと違うかも)で、メガネくんで、メイクがうまくて、鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員で、真面目で律儀で、喋りだすと止まらなくて、違う国の住人。
あたしはもう一度カメラを構えて、そんな日置の世界で一番くだらない時間を止めた。