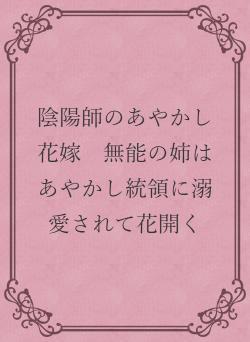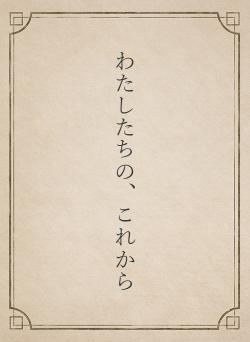翌週の火曜日、あたしはロリィタ男のつきまといを休んだ。
その次の週も気分がのらなくて外に出なかった。
そうしてどのくらい経ったかわからないけど、夏の終わりの風が吹くようになったころ。
あたしは湿ったシーツが鬱陶しくなって、ようやく外に出た。
いつものコンビニでアイスを買って、意味もなく商店街に向かう。
今日は十一時にアラームが鳴らなかったから、火曜日ではないはず。しかし、ロリィタ男――日置淳は完璧な装いで商店街の中心につったっていた。
「しばらく見なかったな」
腕を組み、仁王立ちであたしを見下ろす日置は、この世界のきらめきを全部集めたのではと思えるくらいに眩しかった。陽光を一身に受けて、商店街というステージに経つ純白のロリィタは、あたしだけの天使にすら見えてくる。
日置はあたしの胸中なんてつゆ知らず、いつものように前を歩きはじめる。
「高見響はやりたいこととか欲しいものとかないのか」
「やりたいことはいつも言ってるじゃん」
「それは俺には無理な相談だと何度も言っている」
あたしはもう、日置に願いを叶えてもらうのではなくて、自分で自分の人生を終わらせようと思っていた。
だから、あたしはもうヴィヴィッドなピンク色の爪をやめたし、まっくろでまっすぐな黒髪だってぼさぼさだ。
「じゃあ、欲しいものは?」
「ママ」
「それは難しい」
日置はつれなかった。もしこのロリィタ男があたしのママを連れてきてくれたのならば、ちょっとは計画を考えなおしてもいいと思っていたのに。
「ほかには?」
あんがい日置が粘るから、あたしは少しだけ真剣に考えることにする。
生活に必要なものはだいたい今泉さんが用意してくれていた。大好きだったいちごジャムはママがいなくなってから食べられなくなったし、もう好きなものはない。
――あ、でも。
「……カメラ」
あたしは入学式の日に見た写真部の先輩を思い出していた。
窮屈な列にならばされて、もう脱落してしまおうかと考えていたとき、一眼カメラを構えた先輩とレンズ越しに目があったのだ。
その瞬間、あたしの時間はたしかに止まった。
「カメラが欲しい。写真部の人が使ってた、おっきくて重そうでまん丸のガラスがついてるやつ」
「一眼か」
日置はぴたっと立ち止まり、振り返ってあたしを見た。
「それなら、買いに行こう」
その次の週も気分がのらなくて外に出なかった。
そうしてどのくらい経ったかわからないけど、夏の終わりの風が吹くようになったころ。
あたしは湿ったシーツが鬱陶しくなって、ようやく外に出た。
いつものコンビニでアイスを買って、意味もなく商店街に向かう。
今日は十一時にアラームが鳴らなかったから、火曜日ではないはず。しかし、ロリィタ男――日置淳は完璧な装いで商店街の中心につったっていた。
「しばらく見なかったな」
腕を組み、仁王立ちであたしを見下ろす日置は、この世界のきらめきを全部集めたのではと思えるくらいに眩しかった。陽光を一身に受けて、商店街というステージに経つ純白のロリィタは、あたしだけの天使にすら見えてくる。
日置はあたしの胸中なんてつゆ知らず、いつものように前を歩きはじめる。
「高見響はやりたいこととか欲しいものとかないのか」
「やりたいことはいつも言ってるじゃん」
「それは俺には無理な相談だと何度も言っている」
あたしはもう、日置に願いを叶えてもらうのではなくて、自分で自分の人生を終わらせようと思っていた。
だから、あたしはもうヴィヴィッドなピンク色の爪をやめたし、まっくろでまっすぐな黒髪だってぼさぼさだ。
「じゃあ、欲しいものは?」
「ママ」
「それは難しい」
日置はつれなかった。もしこのロリィタ男があたしのママを連れてきてくれたのならば、ちょっとは計画を考えなおしてもいいと思っていたのに。
「ほかには?」
あんがい日置が粘るから、あたしは少しだけ真剣に考えることにする。
生活に必要なものはだいたい今泉さんが用意してくれていた。大好きだったいちごジャムはママがいなくなってから食べられなくなったし、もう好きなものはない。
――あ、でも。
「……カメラ」
あたしは入学式の日に見た写真部の先輩を思い出していた。
窮屈な列にならばされて、もう脱落してしまおうかと考えていたとき、一眼カメラを構えた先輩とレンズ越しに目があったのだ。
その瞬間、あたしの時間はたしかに止まった。
「カメラが欲しい。写真部の人が使ってた、おっきくて重そうでまん丸のガラスがついてるやつ」
「一眼か」
日置はぴたっと立ち止まり、振り返ってあたしを見た。
「それなら、買いに行こう」