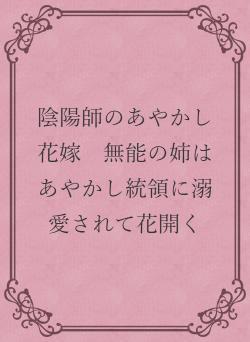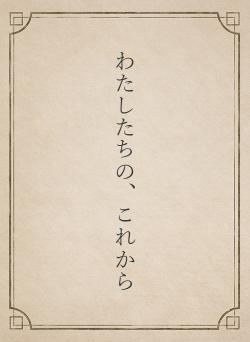「日置はなんでロリィタが好きなの?」
今日も今日とて商店街をロリィタで闊歩するクラスメイト(男)の背中に向かって、あたしはそう問いかけた。
日置の女装趣味を知ってから、あたしは日置につきまとっていた。
日置はだいたい毎週火曜日の正午に、お気に入りのロリィタで商店街に現れる。なぜ火曜日なのかと言うと、その日は世界で一番つまらない世界史の斜田の授業だからだそうだ。
あたしは十一時にアラームが鳴るとベッドから這いでて、ロリィタ男が出没する商店街に向かうのだった。途中のコンビニでアイスを買うことは忘れない。
今日は七月にしては涼しくてうれしいから、ちょっとだけ高いソフトクリームを買った。プレミアムな味がする、ような気がする。
日置はあたしを面倒くさがるけど、けっして無視はしない。だからおもしろかった。
先週と同じ質問をすると、先週とは違う答えが返ってきた。
「この服が好きなわけじゃない」
「どういうこと?」
今日の日置は、真っ黒いワンピースに白いエプロンのような衣装に身を包んでいた。よくあるかわいいメイド服のようだが、シルバーのごつい装飾が最高にロックで、いちだんと濃い化粧がクールに決まっていた。
かわいいものが好きじゃないのだとしたら、どうしてこんなへんてこな格好をしているのだろうか。
「ねえ、どういうことだって聞いてるの!」
沈黙をつらぬくロリィタに向かって、あたしは叫んだ。
「……俺は自分のことを男だと思っている。生殖機能も社会的にも男、という意味だ。他人もおおよそ同じような感想を抱くだろう。しかし、どこからどう見ても男の自分が、ロリィタなんか着て外を歩いている。それがいいんだ」
戸惑いがちに口を開いた日置だったが、しゃべりだしたら止まらない。饒舌にそう語ると、満足したのかとたんに口をつぐんだ。
あたしは眉をひそめる。
「いい、って楽しいってこと?」
「……楽しいよりももっと深い何かだ」
「『深い』って、本当に深いときには使わない言葉だよ」
「黙れ」
あたしはロリィタの背中に向かってべーっと舌を出す。
「言いようのない興奮を覚えるんだ。わかるか? わからないだろう。わからなくていい」
日置はふんっと鼻を鳴らす。
いつもだったらかわいいロリィタに合ってないしぐさだが、今日のロックな女装にはぴったりかもしれない。
「日置の言うとおり、あたしにはわからないよ。でも、わかってもらわなくていいって、そんなの寂しくないの?」
「理解者がほしいと思わなくはないが、高見響の問いには『寂しくはない』という回答になるな」
あたしは首を傾げる。
日置はときどき難解な話し方をする。違う国の住人みたいだってあたしは密かに思っている。海外に行ったことはないけど、たぶんこんな感じなんだと思う。
旅行に行くなら南の国がいいと空想していると、日置がふたたび口を開いた。
「誰かにわかってもらった気になって、その人に拒絶されたときが一番つらいだろう? ぬか喜びがこの世でもっとも愚かな感情だ」
「もっと簡単な言葉でしゃべってよ」
「……他者と自分の境界線は、強く濃くはっきりと引くべきだという話だ」
あたしは頭のなかで、小学校の校庭を想像する。
幼いあたしは小枝で砂利にまっすぐな線を引く。じゃりじゃりじゃりと何度も、何度も、引く。
そうやってできた濃くてはっきりとした線の向こうに、あたしではない別の人間がたくさん立ってあたしを見ている。
クラスメイト、商店街のおばちゃん、家政婦の今泉さん、保健室の先生。それから、パパもママもいる。
「……わからないけど、まったくわからないってわけではないかも」
「ならいい」
日置は満足げにうなった。
涼しい風が日置のスカートを揺らす。
「今度は俺が問おう。高見響はなぜ、好きな人に首を絞められて死にたいと思うのか?」
「前も言ったじゃん」
「『世界で一番幸せな死にざま』とかいうやつか? それこそ俺にはわからない」
「わかろうとしないからわからないんだよ。ばーか」
「なっ!」
ずっと前を歩いていた日置が振り返った。
あまりにも勢いよく振り返るもんだから、あたしは食べかけのソフトクリームを落としそうになる。
夏の日差し、女装男、不登校のあたし。われながら変な組み合わせだと思いながら、あたしは日置の隣に並んだ。
今日も今日とて商店街をロリィタで闊歩するクラスメイト(男)の背中に向かって、あたしはそう問いかけた。
日置の女装趣味を知ってから、あたしは日置につきまとっていた。
日置はだいたい毎週火曜日の正午に、お気に入りのロリィタで商店街に現れる。なぜ火曜日なのかと言うと、その日は世界で一番つまらない世界史の斜田の授業だからだそうだ。
あたしは十一時にアラームが鳴るとベッドから這いでて、ロリィタ男が出没する商店街に向かうのだった。途中のコンビニでアイスを買うことは忘れない。
今日は七月にしては涼しくてうれしいから、ちょっとだけ高いソフトクリームを買った。プレミアムな味がする、ような気がする。
日置はあたしを面倒くさがるけど、けっして無視はしない。だからおもしろかった。
先週と同じ質問をすると、先週とは違う答えが返ってきた。
「この服が好きなわけじゃない」
「どういうこと?」
今日の日置は、真っ黒いワンピースに白いエプロンのような衣装に身を包んでいた。よくあるかわいいメイド服のようだが、シルバーのごつい装飾が最高にロックで、いちだんと濃い化粧がクールに決まっていた。
かわいいものが好きじゃないのだとしたら、どうしてこんなへんてこな格好をしているのだろうか。
「ねえ、どういうことだって聞いてるの!」
沈黙をつらぬくロリィタに向かって、あたしは叫んだ。
「……俺は自分のことを男だと思っている。生殖機能も社会的にも男、という意味だ。他人もおおよそ同じような感想を抱くだろう。しかし、どこからどう見ても男の自分が、ロリィタなんか着て外を歩いている。それがいいんだ」
戸惑いがちに口を開いた日置だったが、しゃべりだしたら止まらない。饒舌にそう語ると、満足したのかとたんに口をつぐんだ。
あたしは眉をひそめる。
「いい、って楽しいってこと?」
「……楽しいよりももっと深い何かだ」
「『深い』って、本当に深いときには使わない言葉だよ」
「黙れ」
あたしはロリィタの背中に向かってべーっと舌を出す。
「言いようのない興奮を覚えるんだ。わかるか? わからないだろう。わからなくていい」
日置はふんっと鼻を鳴らす。
いつもだったらかわいいロリィタに合ってないしぐさだが、今日のロックな女装にはぴったりかもしれない。
「日置の言うとおり、あたしにはわからないよ。でも、わかってもらわなくていいって、そんなの寂しくないの?」
「理解者がほしいと思わなくはないが、高見響の問いには『寂しくはない』という回答になるな」
あたしは首を傾げる。
日置はときどき難解な話し方をする。違う国の住人みたいだってあたしは密かに思っている。海外に行ったことはないけど、たぶんこんな感じなんだと思う。
旅行に行くなら南の国がいいと空想していると、日置がふたたび口を開いた。
「誰かにわかってもらった気になって、その人に拒絶されたときが一番つらいだろう? ぬか喜びがこの世でもっとも愚かな感情だ」
「もっと簡単な言葉でしゃべってよ」
「……他者と自分の境界線は、強く濃くはっきりと引くべきだという話だ」
あたしは頭のなかで、小学校の校庭を想像する。
幼いあたしは小枝で砂利にまっすぐな線を引く。じゃりじゃりじゃりと何度も、何度も、引く。
そうやってできた濃くてはっきりとした線の向こうに、あたしではない別の人間がたくさん立ってあたしを見ている。
クラスメイト、商店街のおばちゃん、家政婦の今泉さん、保健室の先生。それから、パパもママもいる。
「……わからないけど、まったくわからないってわけではないかも」
「ならいい」
日置は満足げにうなった。
涼しい風が日置のスカートを揺らす。
「今度は俺が問おう。高見響はなぜ、好きな人に首を絞められて死にたいと思うのか?」
「前も言ったじゃん」
「『世界で一番幸せな死にざま』とかいうやつか? それこそ俺にはわからない」
「わかろうとしないからわからないんだよ。ばーか」
「なっ!」
ずっと前を歩いていた日置が振り返った。
あまりにも勢いよく振り返るもんだから、あたしは食べかけのソフトクリームを落としそうになる。
夏の日差し、女装男、不登校のあたし。われながら変な組み合わせだと思いながら、あたしは日置の隣に並んだ。