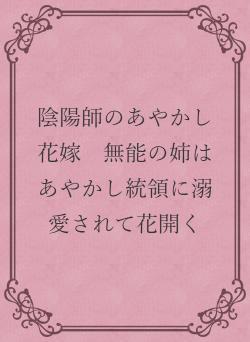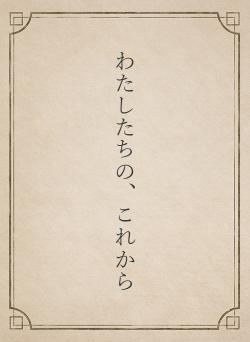「日置にはさ、あたしの首を絞めてもらいたいんだよね」
「おまえ、何言ってんだ」
あたしは、戸惑う日置の腕を無理やり引っ張って商店街の喫茶店に入った。
ドトールの横にある、潰れそうな個人店。いつ来ても人がいないからレコードの音がよく聴こえて、あたしはこの店が好きだった。
制服で昼間からコーヒー飲んでいても何も言われないし。
正面に座る日置は、あたしを遠慮がちに探るような目で見ていた。
落ちつきなく動く瞳を観察していると、きれいなアーモンド色のカラコンをつけていることに気づく。
――頭の先からつま先まで完璧。きっと、あのブーツの下はきれいな桃色のネイルをしているんだ。
かわいいものが好きなあたしはうれしい気持ちでいっぱいだったけど、きちんと訂正することは忘れない。
「おまえじゃなくて高見響ね」
「あ、ああ、すまない」
日置はまた、「高見響」とぶつぶつとつぶやいた。
注文したアイスティーには口をつけようとしない。
「高見響は、その……なんというか……死にたいのか?」
「うーん、死にたいってのはちょっと違うかも」
「じゃあ、なぜ……」
あたしは考える。
「なぜ」なんて、人に聞かれたことなんてなかった。
だって、友だちがいないから。
「あたし、長生きしたくない」
線香の煙のようにママの顔がぼんやりと脳裏に浮かびあがる。
めずらしくあたしの大好きないちごジャムを買ってきてくれた日の夜、あたしを置いて出ていった。
世界で唯一あたしのことを愛してくれたママがいなくなったら、もう誰もあたしのことを好きじゃない。あたしも誰のことも好きじゃない。
きっとママは、あたしとパパと一緒だと幸せになれないからいなくなった。大人は幸せになれないんだったら、あたし、将来なんていらない。いまだってこんなに退屈でしかたがないんだから。
残されたいちごジャムを食べる気にならなかったけど、瓶は綺麗に洗ってベルマークを入れている。そうやってママがやっていたのを、幼いあたしは覚えていた。
「あたしね、自分の人生の終わりは、あたしのことが大好きな人に首を絞めてもらいながら迎えたい。この世界で一番幸せな死にざまだと思うの」
「それは、まわりまわって高見響は死にたいと思っているということにならないか?」
「日置はそう感じるのかもしれないけど、あたしからしたら全然違うよ」
断言すると、日置は腕を組む。
そのしぐさはロリィタに似合っていない。いつもの――といってもあたしは不登校だからいつもの日置淳を知らないけど――鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員の日置淳でしかなかった。
「あたしが人生の最期に見る景色が、あたしのことを大好きな人でいっぱいだったら最高じゃんって思って」
あたしは半分まで飲んだアイスコーヒーにもう一個ガムシロップを入れて、ストローでかき混ぜる。
「あたしのことはいいの。日置はさ、あたしが死んだら、ロリィタ趣味が誰にもバレなくてラッキーでしょ」
「ま、まあ、そうなるが……」
「完全犯罪、成立!」
あたしは立ち上がって天井に指をさして高らかに宣言する。
今日のレコードはアップテンポのジャズで、あたしの門出を祝福してくれているように感じた。
そんなあたしとは真逆で、日置は冷静な口調で言葉を紡ぐ。
「いや、すまないが、『あたしのことを大好きな人』という条件に俺は当てはまらない。俺は高見響のことを何も知らない」
「たしかにそうかも」
あたしはぽかんとする。
日置の言葉が衝撃的すぎて、あたしの周囲十五センチの重力がなくなったような感じがして、ふかふかのソファに思いっきり体が落ちた。
「だろう? 今日のことはまわりに言ってほしくないが、とはいえ高見響の願いを叶えることはできな――」
「じゃあさ、日置、あたしのこと好きになってよ!」
日置は今度こそ珍獣を見るような目であたしを見た。
「おまえ、何言ってんだ」
あたしは、戸惑う日置の腕を無理やり引っ張って商店街の喫茶店に入った。
ドトールの横にある、潰れそうな個人店。いつ来ても人がいないからレコードの音がよく聴こえて、あたしはこの店が好きだった。
制服で昼間からコーヒー飲んでいても何も言われないし。
正面に座る日置は、あたしを遠慮がちに探るような目で見ていた。
落ちつきなく動く瞳を観察していると、きれいなアーモンド色のカラコンをつけていることに気づく。
――頭の先からつま先まで完璧。きっと、あのブーツの下はきれいな桃色のネイルをしているんだ。
かわいいものが好きなあたしはうれしい気持ちでいっぱいだったけど、きちんと訂正することは忘れない。
「おまえじゃなくて高見響ね」
「あ、ああ、すまない」
日置はまた、「高見響」とぶつぶつとつぶやいた。
注文したアイスティーには口をつけようとしない。
「高見響は、その……なんというか……死にたいのか?」
「うーん、死にたいってのはちょっと違うかも」
「じゃあ、なぜ……」
あたしは考える。
「なぜ」なんて、人に聞かれたことなんてなかった。
だって、友だちがいないから。
「あたし、長生きしたくない」
線香の煙のようにママの顔がぼんやりと脳裏に浮かびあがる。
めずらしくあたしの大好きないちごジャムを買ってきてくれた日の夜、あたしを置いて出ていった。
世界で唯一あたしのことを愛してくれたママがいなくなったら、もう誰もあたしのことを好きじゃない。あたしも誰のことも好きじゃない。
きっとママは、あたしとパパと一緒だと幸せになれないからいなくなった。大人は幸せになれないんだったら、あたし、将来なんていらない。いまだってこんなに退屈でしかたがないんだから。
残されたいちごジャムを食べる気にならなかったけど、瓶は綺麗に洗ってベルマークを入れている。そうやってママがやっていたのを、幼いあたしは覚えていた。
「あたしね、自分の人生の終わりは、あたしのことが大好きな人に首を絞めてもらいながら迎えたい。この世界で一番幸せな死にざまだと思うの」
「それは、まわりまわって高見響は死にたいと思っているということにならないか?」
「日置はそう感じるのかもしれないけど、あたしからしたら全然違うよ」
断言すると、日置は腕を組む。
そのしぐさはロリィタに似合っていない。いつもの――といってもあたしは不登校だからいつもの日置淳を知らないけど――鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員の日置淳でしかなかった。
「あたしが人生の最期に見る景色が、あたしのことを大好きな人でいっぱいだったら最高じゃんって思って」
あたしは半分まで飲んだアイスコーヒーにもう一個ガムシロップを入れて、ストローでかき混ぜる。
「あたしのことはいいの。日置はさ、あたしが死んだら、ロリィタ趣味が誰にもバレなくてラッキーでしょ」
「ま、まあ、そうなるが……」
「完全犯罪、成立!」
あたしは立ち上がって天井に指をさして高らかに宣言する。
今日のレコードはアップテンポのジャズで、あたしの門出を祝福してくれているように感じた。
そんなあたしとは真逆で、日置は冷静な口調で言葉を紡ぐ。
「いや、すまないが、『あたしのことを大好きな人』という条件に俺は当てはまらない。俺は高見響のことを何も知らない」
「たしかにそうかも」
あたしはぽかんとする。
日置の言葉が衝撃的すぎて、あたしの周囲十五センチの重力がなくなったような感じがして、ふかふかのソファに思いっきり体が落ちた。
「だろう? 今日のことはまわりに言ってほしくないが、とはいえ高見響の願いを叶えることはできな――」
「じゃあさ、日置、あたしのこと好きになってよ!」
日置は今度こそ珍獣を見るような目であたしを見た。