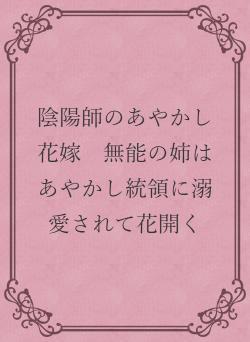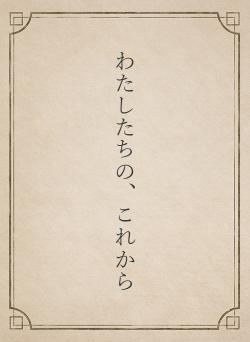その日、駅前の商店街で女装した日置淳を見つけたのは偶然のことだった。
男だと思っていたクラスメイトが、ロリィタを完璧に着こなして、閑散とした商店街を優雅な足取りで進む。
あたしはなんだか初めて虹を見た幼い日の雨あがりを思い出して、それをぼうっと見ていた。持っていたアイスが地面に落ちなければ、あたしはいつまでも日置に釘付けだったと思う。
ぼとり。
地球がアイスを吸っていく。落ちたぶんだけ棒の重力が軽くなってかなしい。
地面に落ちて溶けたアイスをまじまじと見つめながら、日置淳のことを考える。あたしは入学式の次の次の次の日から高校に行くのをやめたけど、クラスメイトだけではなく全校生徒の顔と名前を覚えている。
鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員。うちの高校は部活に必ず入らないといけないから、あたしみたいに適当なところに入るだけ入って一度も部室に行かない生徒が多い。日置もたしか同類だったと思う。
ちなみにあたしは写真部の幽霊。
カメラが欲しかったから入部希望届を出したけど、貸出制だと聞いて熱が冷めてしまった。時間を止めることができる魔法が欲しかっただけなのに。
――ロリィタ、似合ってる。
装いは完璧だし、本人も誰にも気づかれないと確信しているのだろう。それくらい、足取りが堂々としていた。
でも、あたしにはあれが日置淳だとすぐにわかった。
なんでかわからないけど、すぐにピンときたのだ。
毎日毎日、家のベッドで寝転んで、クラスメイトの顔がプリントされた自己紹介表を見ていたからだろうか。
日置淳はクラスメイトに「メガネくん」と呼ばれていた。説明が難しいのだが、まさにメガネくんって感じの見た目をしている。
メガネくんと呼ばれるにふさわしい地味な顔立ちだから逆に化粧映えするのか、痩身でいわゆる男らしい体つきじゃないからか、ロリィタファッションは妙にしっくりとしていた。
淡いピンク色の膝丈のワンピースはクラシカルな装いで、首元が白いレースになっていて可憐だった。白いレースのタイツに、純白の手袋、そしてワンピースとおそろいの日傘。
こんなにかわいい洋服はいったいどこに売っているのだろうか。
日置とはとくだん喋ったことはなかったが、あたしは好奇心が勝って思わず近寄っていた。
うしろから「日置」と声をかけると、ヘッドドレスの両サイドについた大きなリボンが弾かれるように揺れる。
「おまえ……」
振り返った日置は、あたしを見て目を丸くした。
パパに無関心な目を向けられたり、クラスメイトに指をさされたりするのとは違う、新鮮な反応だった。
まるで、熊にでも出会ったかのように固まっているもんだから、あたしはおかしくなって笑いそうになる。
でも、あたしはたぶん、いつものきつい顔をしているのだと思う。
六月下旬の湿気た夏日にもかかわらず、日置のファンデーションは完璧に肌を覆っていた。
「あたし、高見響。同じクラスだよ、わかんない?」
「いや、わかるが……」
日置は両手で日傘を持ち直し、あたしをじっと見る。
衣装とおそろいのピンクのアイメイクがかわいい。あたしの爪を飾ってるヴィヴィッドなピンクとは違って、淡い桃色。
「おまえこそ、俺がわかるのか」
「おまえじゃない、高見響ね」
「あ、ああ」
日置は混乱しているなかでも、真面目な顔で「高見響だったか、すまない」と言い直す。その律儀さがやっぱりあたしにはくすぐったかった。
男なのにロリィタを着てて、男なのに抜群にかわいいのに、やっぱり男みたいな低い声。商店街のガラス天井から漏れる晴天の日差しを受けて、きらきら光るロリィタ男。
――日置なら、あたしの願いを叶えてくれるかも。
「そうそう、高見響ね。日置はロリィタでどこ行くの?」
その瞬間、日置はあたしを睨んだ。部活だけじゃなくて学校の幽霊のあたしに気軽に話しかけられたのが、いまさら癪に触ったのだろうか。
「お、おまえもどうせ気持ち悪いとか思っているんだろう!」
ピンクのアイメイクが歪む。ピンクはいちばんかわいい色だから、汚いところに連れていかれてかわいそう。
「男が――それもこんなブサイクがロリィタなんて!」
あたしは日置の言っていることの意味がわからず、首を傾げた。
「外歩いていたらたまたまクラスメイトを見つけて、ロリィタが似合っていたから声掛けただけなんだけど」
「に、に、に、似合っている、だと……?」
あたしが頷くと、日置は強張っていた肩をすとんと落とした。
「はじめて言われた」
「そうなんだ」
うまく言えないけど、ロリィタが似合う人の種類ってたぶんある。日置は素直で律儀でいいやつだから、たぶんロリィタが似合うんだと思う。
あたしはこのきつい顔と生き様のせいできっと似合わない。
パパはあたしのことを「電波ちゃん」って呼ぶ。電波ちゃんがどんな意味なのかわからないけれど、パパがあたしの電波を受信する気がなさそうなのは火を見るよりも明らかだった。
「ねえ、日置」
あたしの頭のなかには、自分の願いを叶えるための道がつくられていた。
「日置はロリィタを着ていることがバレたくないんだよね?」
「あ、ああ。言わないでもらえな――」
「それならちょうどいいや」
あたしの足元に、食べかけのアイスがぼとりと落ちる。
「――あたしの首、絞めてよ」
日置が一歩あとずさる。
分厚い底のブーツがコンクリートと擦れる音がした。どの店の店員も昼休憩に出て人がいない正午の商店街に、その音が馬鹿みたいに大きな音で響いたように思えた。
あたしはたぶんいま、極悪人みたいな顔をして笑っている。
男だと思っていたクラスメイトが、ロリィタを完璧に着こなして、閑散とした商店街を優雅な足取りで進む。
あたしはなんだか初めて虹を見た幼い日の雨あがりを思い出して、それをぼうっと見ていた。持っていたアイスが地面に落ちなければ、あたしはいつまでも日置に釘付けだったと思う。
ぼとり。
地球がアイスを吸っていく。落ちたぶんだけ棒の重力が軽くなってかなしい。
地面に落ちて溶けたアイスをまじまじと見つめながら、日置淳のことを考える。あたしは入学式の次の次の次の日から高校に行くのをやめたけど、クラスメイトだけではなく全校生徒の顔と名前を覚えている。
鉄道研究会だか歴史研究会だか文芸部だかの幽霊部員。うちの高校は部活に必ず入らないといけないから、あたしみたいに適当なところに入るだけ入って一度も部室に行かない生徒が多い。日置もたしか同類だったと思う。
ちなみにあたしは写真部の幽霊。
カメラが欲しかったから入部希望届を出したけど、貸出制だと聞いて熱が冷めてしまった。時間を止めることができる魔法が欲しかっただけなのに。
――ロリィタ、似合ってる。
装いは完璧だし、本人も誰にも気づかれないと確信しているのだろう。それくらい、足取りが堂々としていた。
でも、あたしにはあれが日置淳だとすぐにわかった。
なんでかわからないけど、すぐにピンときたのだ。
毎日毎日、家のベッドで寝転んで、クラスメイトの顔がプリントされた自己紹介表を見ていたからだろうか。
日置淳はクラスメイトに「メガネくん」と呼ばれていた。説明が難しいのだが、まさにメガネくんって感じの見た目をしている。
メガネくんと呼ばれるにふさわしい地味な顔立ちだから逆に化粧映えするのか、痩身でいわゆる男らしい体つきじゃないからか、ロリィタファッションは妙にしっくりとしていた。
淡いピンク色の膝丈のワンピースはクラシカルな装いで、首元が白いレースになっていて可憐だった。白いレースのタイツに、純白の手袋、そしてワンピースとおそろいの日傘。
こんなにかわいい洋服はいったいどこに売っているのだろうか。
日置とはとくだん喋ったことはなかったが、あたしは好奇心が勝って思わず近寄っていた。
うしろから「日置」と声をかけると、ヘッドドレスの両サイドについた大きなリボンが弾かれるように揺れる。
「おまえ……」
振り返った日置は、あたしを見て目を丸くした。
パパに無関心な目を向けられたり、クラスメイトに指をさされたりするのとは違う、新鮮な反応だった。
まるで、熊にでも出会ったかのように固まっているもんだから、あたしはおかしくなって笑いそうになる。
でも、あたしはたぶん、いつものきつい顔をしているのだと思う。
六月下旬の湿気た夏日にもかかわらず、日置のファンデーションは完璧に肌を覆っていた。
「あたし、高見響。同じクラスだよ、わかんない?」
「いや、わかるが……」
日置は両手で日傘を持ち直し、あたしをじっと見る。
衣装とおそろいのピンクのアイメイクがかわいい。あたしの爪を飾ってるヴィヴィッドなピンクとは違って、淡い桃色。
「おまえこそ、俺がわかるのか」
「おまえじゃない、高見響ね」
「あ、ああ」
日置は混乱しているなかでも、真面目な顔で「高見響だったか、すまない」と言い直す。その律儀さがやっぱりあたしにはくすぐったかった。
男なのにロリィタを着てて、男なのに抜群にかわいいのに、やっぱり男みたいな低い声。商店街のガラス天井から漏れる晴天の日差しを受けて、きらきら光るロリィタ男。
――日置なら、あたしの願いを叶えてくれるかも。
「そうそう、高見響ね。日置はロリィタでどこ行くの?」
その瞬間、日置はあたしを睨んだ。部活だけじゃなくて学校の幽霊のあたしに気軽に話しかけられたのが、いまさら癪に触ったのだろうか。
「お、おまえもどうせ気持ち悪いとか思っているんだろう!」
ピンクのアイメイクが歪む。ピンクはいちばんかわいい色だから、汚いところに連れていかれてかわいそう。
「男が――それもこんなブサイクがロリィタなんて!」
あたしは日置の言っていることの意味がわからず、首を傾げた。
「外歩いていたらたまたまクラスメイトを見つけて、ロリィタが似合っていたから声掛けただけなんだけど」
「に、に、に、似合っている、だと……?」
あたしが頷くと、日置は強張っていた肩をすとんと落とした。
「はじめて言われた」
「そうなんだ」
うまく言えないけど、ロリィタが似合う人の種類ってたぶんある。日置は素直で律儀でいいやつだから、たぶんロリィタが似合うんだと思う。
あたしはこのきつい顔と生き様のせいできっと似合わない。
パパはあたしのことを「電波ちゃん」って呼ぶ。電波ちゃんがどんな意味なのかわからないけれど、パパがあたしの電波を受信する気がなさそうなのは火を見るよりも明らかだった。
「ねえ、日置」
あたしの頭のなかには、自分の願いを叶えるための道がつくられていた。
「日置はロリィタを着ていることがバレたくないんだよね?」
「あ、ああ。言わないでもらえな――」
「それならちょうどいいや」
あたしの足元に、食べかけのアイスがぼとりと落ちる。
「――あたしの首、絞めてよ」
日置が一歩あとずさる。
分厚い底のブーツがコンクリートと擦れる音がした。どの店の店員も昼休憩に出て人がいない正午の商店街に、その音が馬鹿みたいに大きな音で響いたように思えた。
あたしはたぶんいま、極悪人みたいな顔をして笑っている。