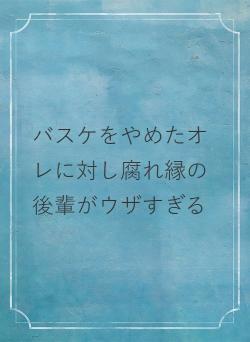なんだか緊張するなと思う。
何しろ、水谷の家には実は行ったことが一度もない。
水谷の父親がどんな人なのかも実は全く知らないのだ。
今回、水谷の両親には言わないことになっているが、今日行くのは恋人の家。
粗相のないようにしなければな。
そう、俺は思いながら水谷の後ろをついて行く。
しかし思った以上の距離を歩く。
ひょっとして水谷の家は思った以上に遠いのか? と思う。
そうなれば毎日結構な距離を歩いているんだなと思う。
尊敬に値する。
もう二十分は歩いた。
水谷と話しながらだと、そこまで疲れはしない。
が、水谷はもうすぐ着くと言ってくれるだけで、あとどれくらいの時間がかかるとは言ってくれない。
「着いてからのお楽しみだよ」
と、ただ言ってくれるだけなのだ。
そして、長距離歩いた後、ついに水谷の家に着いた。
そこは、普通のアパートだった。
一部屋を借りただけ、といった感じだろうか。
貧しくはないが、決して裕福でもないが正解なのだろうか。
「入っていいのか?」
ただ、その家を呆然と見る水谷に俺はそう訊いた。
「うん、いいよ」
その口ぶり。
何か思惑があるような言い草だ。
緊張はしている。
が、それはきっと俺の思い違いだろうか、それともこの家に俺を連れてきたことに対してのことなのか。
水谷の立場になって考えてみると自分の家に同性の彼氏を連れて来るのだ。
緊張をしないわけがない。
「上がるぞ」
そして俺はアパートのドアを開け――
「開かないぞ」
「緊張しすぎだよ。まだ鍵もあけてないんだし」
「そうか」
俺としたことが、開くはずもないドアに力を入れてしまっていた。
「じゃあ、開けるね」
「ああ」
俺は唾をのむ。
ここから先、どうなるかは分からない。
しかし、全てがいい方向に動くと良いな、と俺は思う。
その中には、一般的な、普通の家庭の雰囲気が広がっていた。
そして、俺は水谷の後ろをついて、歩いていく。
中は洋風の作りとなっている。そしてリビングへと入っていく。
そこには水谷のお母さんらしき人物がいた。
「あら、お友達?」
水谷のお母さんがそう訊いてくる。
それに水谷は「うん」と答えた。
「そう、ゆっくりして行ってね」
そう言われ、俺は近くの椅子に座る。
一番の目的の水谷の父親はまだ帰ってきて無い様だ。
水谷曰く、今日は早く帰ってくるという話だったが。
まだ家にはついていないのか。
とりあえず、せっかく来たのに、何も話さないのもなしだ。
「そう言えば引っ越しされるのって本当なんですか?」
俺は勢いそう口にした。
さっさと、水谷のお母さんと親睦も深めたいし、本題も話せるし、所謂一石二鳥と言ったやつだ。
「そうなのよ」
そう言う水谷のお母さんの顔は少しだけ暗かった。
「ごめんなさいね」
「俺は別に……」
と入ったが、引っ越さないで欲しいのが本心だ。
「でも何とか止められないんですか?」
「あの人が上から受けた命令だからねえ。なかなか難しいのよ。でも単身赴任してもらう訳にもいかないし、困ったものだわ」
水谷の家でも非常に困った問題として処理されている。
当然か。
「俺は水谷の親友です。水谷と別れたくないです」
俺は、切羽詰まったかのような表情で言う。
せっかく俺の中の溝を埋められそうな人と出会ったのに、もう終わりなんて嫌だ。
もっと一緒にしたいことだってたくさんある。
まだ一緒に映画とか温泉に行っただけだ。
それだけで満足しろだなんて酷いことを言うものだ。
たった一度のデートで満足できるほど、俺は人間出来過ぎてはいない。
俺は水谷に目配せをした。
すると水谷は軽くうなずき、
「僕だってまだ浅羽君とは離れたくないよ。僕は浅羽君が好きなんだよ」
「あら」
水谷のお母さんはそうこぼした。
「亮が自分の感情を矢面に出すなんて今までなかったのに、珍しいこともある物ね」
「珍しくはないさ。だって僕はまだ浅羽君と一緒にいたいんだもん」
「水谷……」
「私だってそうさせてあげたいわ。でも、でも」
水谷のお母さんは突如顔を手で覆う。
そして頭を強い力で自身の頭を掴む。
「私だって、亮の生活を第一に考えてあげたいの。でも、でも! 無理なのよ」
水谷のお母さんにも、水谷のために力になってあげたいという気持ちはしっかりとある。
その言葉を聞いて少し、ほっとした。
そして――
水谷のお父さんが帰ってくるまでしばらく俺たちは二人で水谷の家を堪能しようという話となった。
「へえ、あるんだ」
俺が目を付けたのは水谷の家に会ったゲーム機だ。
最新のゲーム機でそこまで持っている人もいない。
「誕生祝いでもらったんだ」
「そうなのか」
そう言えば、俺は水谷の誕生日を知らない。
このゲーム機の発売日は五ヵ月前という事。つまり水谷の誕生日は過ぎているのか。
そう考えると少しショックだ。
しかし、俺は俺で誕生日は二か月前に過ぎている。
そう考えると俺たちは同じ立場なのだろう。
「このゲームしようぜ」
俺がそう言うと、水谷は苦い顔をした。
「どうしたんだよ」
「僕がしたいのはそれじゃない」
俺が首をかしげると。
「ベットに行きたい」と言ってきた。
ベッドでじゃれたいという気持ちは分かる。
だけど、
「ここ、お前の家だぞ」
普段から親のいない俺の家と違い、しっかりと親がいるはずだ。
現に水谷のお母さんがいる。
リスクが高すぎる。
「まさか怯えているの?」
くそっ、可愛らしい顔をして言うな。
まず、今日ここに来た目的が、引っ越しをやめるように説得するためじゃなかったのか。
なんだか話がこじれている気がするが。
っくそ、
「分かったよ。やってやるよ」
「やったー。じゃあ、今度はゲームやろうね」
「あ、ああ」
なんだか俺はいつも水谷にペースを乱されっぱなしだ。
そしてベッドに寝転がらさせられ、そして、抱きしめられた。
水谷も上の服を脱ぎ、俺も脱ぐ。
その次の瞬間、水谷に抱きしめられる。
この光景、明らかに水谷の親が見たらびっくりするだろう。しかし、そのドキドキ感が快感になっていく。
水谷が教えてくれたんだ。
こういう特殊な恋愛を。
そして、水谷のお父さんが帰ってきた。
結局ベッドで絡み合ったのは最初だけで、あとは一緒にゲームをしていた。
特殊な恋愛から普通の物に代わったのだ。
ゲーム自体は一緒にやってて楽しかった。
だけど、忘れてはならない。
なぜ俺たちは今日ここにやってきたのか。
そう、今日は遊びに来たのではない。
今日は一緒に引越しを取り消す――つまり転勤を取りやめる説得をするために来たのだ。
俺は水谷と一緒に水谷の父親の元へと向かう。
「あの、すみません」
俺は頭を軽く下げる。
「転勤を取りやめてくれませんか」
俺は頭を地面に平伏させた。
「浅羽君」
「うん。僕もそうしたいと考えてはいるんだけどね」
水谷のお父さんの見た目は優しそうなおじさんだ。
水谷と同じく眼鏡をかけており、優男という印象がある。
それはもちろんいい意味でだ。
「水谷と俺は最近知り合っていつも遊んでいるんです。俺は水谷と離れたくない」
「やれやれ、僕も水谷だから調子が狂うなあ」
「亮とはずっと一緒に遊んでいたんです。だから、俺は亮ともっと一緒に遊びたい。だからお願いします。引越しの件を何とか出来ませんか?」
「……残念ながら断られたよ。僕以外にこの仕事を、この案件を頼めそうな人はもういないって」
その声は少し冷たいものだった。
だが、それは決して俺に対する憎悪とか嫌悪とかそう言うものではない。
ただ、現実を淡々と伝えているのだ。
だが、その会話で思う事がある。
やはり、この人も悔しいと思っているんだと。
この人も、できれば転勤したくないんだと。
「僕は仕事ができるんだ。だからかな、給料を上げるから転勤しろって命令口調で。まいっちゃうよ」
そう言って水谷のお父さんは頭をかいた。
「僕が直訴しても無駄なんだ」
だから諦めろって言っているのか?
「だから、それ以外の手を考えようと思う」
ん、考えてくれるのか?
「僕が思うに、他にも手があると思うんだ。実際に直訴してくれる友達もいるみたいだしね。さて、亮」
その視線は歩再び亮に向けられる。
「どんな方法が思い浮かぶ?」
まるで学校の教師みたいだ。
それに対し、亮は静かに言う。
「僕が思うのは、僕たちが一緒に暮らすことかな」
水谷、何を言っているんだ?
俺はそう思った。
一緒に暮らすとは同棲という事か?
それは流石に速すぎるんじゃないか?
色々と疑問が巡り巡る。
「僕が浅羽君の家に居候させてもらうという事です」
いつの間にそんなことを考えていたんだ。
俺は感心の声を漏らす。
「それは浅羽君には」
「伝えてないです」
それはまことなのか?
「はい。俺は知りません」
事実を告げた。するとなるほどなあ、と水谷のお父さんが漏らした。
「それはあまりにも非現実な気がするが」
この地に残りたいなら、案を出せと言ってそれかと思うが。
「僕は思うんだ。僕の問題は皆が出張に出ている間に僕がどこに泊まるか。そうなれば僕が浅羽君の家に泊まるのは合理的な考え叶って」
「それは違う」
急に冷たい言い方だ。
「それは甘えているだけだ。浅羽君のやさしさに。お前はそれでいいのか、何かを返せるのか?」
先程までの優しそうな雰囲気から一変、鬼の雰囲気だ。
「僕は許可されたとしても堅実なプランが無いやつをよそ様の家には到底遅れない」
「僕にできることはあるよ。料理に、裁縫に、掃除とか。だから僕が家事を代理でやったらいいよ。だって、浅羽君のお母様は仕事が忙しいんだから」
なんだかいつの間にか話は俺の関与しない部分に入って行っていると思う。
そんなことを考えているのなら最初から話してほしかった。
ちなみに俺は水谷のその考えには賛成だ。
父さんがほとんど帰ってこない中、家事を代理でやってくれる存在は、我が家で重宝されるべき存在だ。
「なるほど、道理にかなっている。ちゃんと考えているみたいで安心したよ」
そう言って水谷のお父さんは亮の頭を撫でた。
「だけど、もし厄介な存在だと浅羽家が認めたら、即座に僕のところに来てもらうよ。そのまえに、許可を取るところからかな」
「それは俺は大丈夫だと思います。俺が思うにですが」
父さんはほとんど家にいない。
泊まり込みの仕事などが多いのだ。
そんな中、一人家に増えても、別に困らないだろう。
いつも家を汚してしまう俺に代わってしてくれる存在が出来る。
それだけで、むしろプラスになるとさえ思っている。
だからうちの家には困ることはないのだ。
お金さえくれるのなら。
「僕もその線で考えてみるよ。でも」
「でも……」
「他の選択肢も踏まえて考えるからそこはよろしくね」
そう、俺に言う水谷の父親。
その言い方は子供をあやすみたいな感じだった。
「お父さん、浅羽君が嫌がってるよ」
確かに今俺は嫌だなと思っていた。理由は単純明快。
子ども扱いされるのが純粋に嫌なのだ。
「それはすまなかった。息子の友達にどう接したらいいのかがよくわからないんだよ」
「そう……ですか」
確かに、俺は今亮の友達の立場だ。
父親からしたらどきどきするようなものなのだろう。
まあ、俺は俺で実は友達じゃなく、恋人だったりするのだが。
「とりあえず今日はそんなところでいいかな」
「はい」
もうこれ以上論議することはないはずだ。
「でも、もう少しだけ亮と話したいです」
「かまわないよ」
そして俺は亮の部屋に行く。