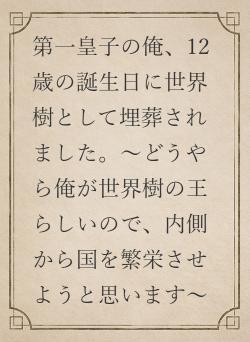懐かしい気持ちを胸に抱きながら、ダンジョンから宿に戻る帰り道。
日は大分傾き、優しい赤に包まれた森の中で俺はその花を見つけた。
「ピロテス……」
白く大きな花弁が垂れ、夕日に染っている。
「ん? ファレス、どうかしたか?」
急に立ち止まった俺を気にしてケイルが声をかけてきた。
「あ、ああ、いや……ピロテスが咲いているなと思って」
「……そういえばお前の宿もピロテスって名前だったな。なんか訳があるのか?」
そうか、そこの話は詳しく教えてなかったな。
「ああ、でも、それは今は良いんだ。それより、ちょっと寄り道してかないか?」
「寄り道? 俺は良いが……」
俺の提案を受け、ケイルが二人を振り返り確認する。
「俺も構わないですよ!」
「……どこへでも」
二人はすぐに頷き、同意を示してくれた。
「だってよ。じゃあ行こうぜ。その寄り道とやらに」
「ありがとう、悪いな。付き合わせて」
「水くせぇな……ほら、どこ行くんだよ?」
「すまん、こっちだ」
……あの日のことを考えるとどうもダメみたいだ。
だけど、この感傷も今日で乗り越えなくちゃならない。
日の沈んでいく西の空を見上げる。
いつまでも引きずってばかりじゃ、みんなにもあいつらにも合わせる顔がないよな。
気持ちを改めて、俺は目的地へ歩き出した。
◇◇◇
宿とは反対の方向に十数分ほど進んだその先。
その先が俺にとって最大のトラウマの場所だ。
「ここは……」
ケイルが一瞬息を飲むような声をだし、黙り込んだ。
「どうだ? いいところだろ?」
「……とても、綺麗ですね」
柔和に笑い、ネイロスはその景色に見とれている様だった。
森の中に突然、ぽっかりと空いた空間。
そこ一面に広がるのは美しいピロテスの花畑だ。
「ここが、ファレスさんの来たかった場所なんですか?」
景色に圧倒される二人を横目に見ていると、ダンカンがそう聞いてきた。
「ああ、十年前にも来たことがあるんだ」
「十年……そう言えばファレスさんは今おいくつなんですか?」
「今年で二十七になる年だよ。言葉にしてみると歳を取ったなって感じるな」
「そんなことないと思いますけど……というか二十七ってもしかして伝説の勇者と同じ学年ですか?」
……こいつ、何かに勘づいているのか?
もし、何かを察していたりするならばほんと……困るくらい優秀だな。
「ああ、そうだな。生きていれば、だけど」
勇者は戦死した。
俺が作りあげた存在しない記憶によりダンカンはそう思っているはず。
勘のいい彼に余計なことを言わないように、俺は自分からその話題に触れた。
「そうですね……。魔王を倒すくらい強かった勇者が戦死するって何が相手だったんですかね? それとも、魔王との戦いで手ひどい傷を負ったとか?」
「さぁ……どうだろうな。案外どこかで生き延びてるかもしれないぞ?」
「あはは! だったらいいですね」
冗談めかしてそんな風に言ってみた。
だが、ダンカンは存外本気でそれを願っている様子だ。
「? まあ、生きているに越したことはないが喜ぶほどか?」
「そりゃあ、そうですよ。だって、その方が人間味があるじゃないですか」
「人間味?」
「はい、確かに勇者はすごい人だと思いますし、尊敬もしますけど……その一方でどこか自分とは違うなって感じるところも多かったんです」
……語りだしたダンカンに俺は無言で続きを促す。
「だって、単身で魔族をどんどん討ち滅ぼして、終いには魔王まで討伐ですよ? まるで自分と同じ人間とは思えないというか……。だから、もし隠れて引退とかしててくれたら、ちょっと気持ちが分かるなって。……あはは、何真剣に語ってるんですかね俺」
……そうか。
そんな風に考える人もいるんだな。
これからも勇者であることを求め続けられることが耐えられそうになくて、引退をした。
だから、ダンカンのような考え方は俺にはとても新鮮に感じられた。
「いや、ありがとう。すごく嬉しいよ」
「え? なんでファレスさんが嬉しいんですか?」
「ははっ。なんでもないさ」
勇者も同じ人間だったら嬉しい……か。
立場を意識せず、無邪気にここで花を摘んでいた自分の姿が目に浮かび上がる。
確かにあの日は最悪だった。
でも、一人になる必要はなかったんだな。
ダンカンの何気ない言葉が、俺にそう思わせてくれた。
「おい、ファレス! 花冠作ったぞ!」
すると突然、花畑の中心でケイルが俺を呼んだ。
その手には第二近衛騎士隊副隊長が作ったとは思えないほど、出来のいい花冠が握られている。
「ははっ! 四十手前のおっさんが一人で花冠はきつすぎだろケイル!」
そう叫び返しながら、俺はケイルの方へ駆け出した。
ピロテスが象徴するのは永遠の愛。
だが、なにもその象徴する愛すべてが恋愛に関するものという訳ではない。
今日になってようやく、俺は自分のことを愛せるようになった気がした。
◇◇◇
「(なあ、ファレス)」
しばらく年甲斐もなくケイルとダンカンとはしゃぎまわり、疲れて休憩していたところにあの頭に声が響いてくる魔法でネイロスが話しかけて来た。
「(どうしたよ?)」
「(少しこっちへ来てくれ)」
「(ん? いいけど……)」
呼ばれた通り、二人から離れてネイロスのいるところまで歩いて行く。
「(それで、どうかしたのか?)」
「(ああ、お主にまた魔法を教えようと思ってな)」
「(魔法? また突然どうして?)」
「(まあ、そういう気分なのだ。少ししゃがんでみてくれ)」
花畑にしゃがみ、ピロテスに囲まれながらこちらを見上げるネイロス。
可憐ながらも美しく妖艶なその姿はさながら花の魔女とでも言えようか。
「(それで、どんな魔法なんだ?)」
隣にしゃがんで改めてそう聞く。
するとネイロスは足元のピロテスを数本摘んで手に乗せると魔法を発動した。
「(まあ、見ておれ。いくぞ〈光景の具象〉)」
ネイロスにしては珍しい、共用語での詠唱。その行為が意味するところは理解できなかったが、どことなく強い思いは伝わってきた。
ネイロスの手の中にある数本のピロテスに光が集まる。
その光は小さくなるもどんどん輝きを強めて収束し、形を成していく。
そして――
ネイロスの手のひらには、とても小さく精巧なピロテスの花飾りが付いた指輪が乗っていた。
「それは?」
魔法ではなく、声に出してそう聞く。
「この花畑があまりにも美しかったものでな。この景色を指輪に閉じ込めてみた。これをお主に送ろう」
するとネイロスも俺以外には聞こえない程度の声量で答えた。
「俺に? いいのか?」
ここの景色をよく気に入ってくれたことは伝わってくるが、こんなものを俺が貰ってしまっていいのだろうか。
そう思っていると、ネイロスが俺の空いている方の中指を指さした。
「前々から思っておったのだ。どうにも、その指輪が妾を牽制している、とな。だが、そんな妾の気分ひとつで外させる訳にもいかぬ。だから同じ土俵に立とうかと思ってな」
そういえば、初めて宿に来た日にもやたらに引っ掻いてきたっけ?
「……確かに猫の姿でうちに来た時からこの指輪に反応してたよな」
ミアから貰った指輪に触れる。
すると赤い宝石がミアの想いが込められているかのごとく煌々と輝いた。
「……やはりな。その指輪はお主と相手を強く繋いでおる。妾の方が近くにいるというのに。だから、お主は今日からその指輪を逆の中指に嵌めて過ごしてくれ」
繋いでいる?
魔法やその類には人一倍敏感な俺だが、この指輪からはそんな力は感じないのだが……。
まあ、害は無さそうだからなんでもいい。
「論理関係はよく分からないが……わかったよ。ありがとうネイロス」
そう言うとネイロスが一瞬、何かを期待するような顔でこちらを見た。
もちろん、それを見逃す俺でも、それの意味が分からない俺でもない。
周りから一際美しく咲きほこるピロテスを数本手折り、その魔法を発動した。
「〈光景の具象〉」
さっき見た魔法を完璧に模倣し、ネイロスが俺に作ってくれたものより、一回り胴が小さいピロテスの指輪を生み出した。
「これでいいか?」
「うむ! これでいつでもミアとやらに会えるわ!」
指輪を渡すと早速自分も右の中指に嵌めている。
「……喜んでくれたのなら良かったよ」
この指輪がそんな意味を持つのか、ネイロスが何を含んで言ったのかそれは俺には関係ない。ただ、ネイロスの願いが叶えられていたら良いとそう思った。
そんな二人を遠目に見る騎士が二人。
どこか寂しそうな顔でダンカンが呟く。
「あの、副隊長。俺に勝ち目って……」
「ねぇな。断言してやる」
可哀想な犬のような顔で話すダンカンをケイルはバッサリと切り捨てた。
「せめて慰めてくださいよぉ……」
「いいじゃねえか、ダンカン。男は失恋で強くなるもんだ」
「そういうもんですかね……」
「ああ、そうやってあいつも強くなったらしいぞ」
「? 誰のことですか?」
「ははっ、なんでもねえ」
「?」
ダンカンが疑問を含んだ視線をケイルに向ける中、そのケイルの視界にはあの日旅立って行った最強の青年が映っていた。
◇◇◇
「いや〜久しぶりに楽しかったな」
宿に帰ってきて四人で食卓を囲みながら、誰からともなくそんな声が漏れ出る。
「ほんと、お二人の戦闘力には驚かされましたけどね」
ダンカンはダンジョンでの戦闘に相当衝撃を受けたみたいだ。でも、その顔は圧倒的な実力を見て怖気付いてしまった訳ではなさそうだ。
むしろ――
「ダンカン、お前もまだまだ精進しろよ?」
「そうですね。正直今回の任務での一番の収穫はそれかもしれないです」
ケイルの冗談交じりの檄に真面目に答えるダンカン。
彼は間違いなく強くなるだろう。
そう確信できる表情だった。
「お二人の任務は調査では?」
「調査もしましたが、この辺りは支援の必要がないほど修繕されていますし、辺りに脅威となる魔物の存在も確認できませんでした。それにお強い二人がいるのなら余計な心配をする必要もありませんしね」
ネイロスのツッコミにもダンカンは丁寧に対応した。
しかし、その対応には少し前までのネイロスを意識したような感情は見えず、真面目に仕事に打ち込む騎士道だけが残っているように思われた。
どうやら本当に大きな収穫になったようだ。
この若さでこれほどの成長性、ケイルが気に入るのもよくわかる。
そんなことを考えながらケイルに話を振った。
「あと数日で戻るんだったか?」
「ああ、一瞬で時間が過ぎたな……」
「ここのベッドともついにお別れですか……。帰りの野営がキツそうです」
「弱音を吐くな、と言いたいところだが、さすがの俺も当分はキツそうだな」
「ふふっ、ではまた来ていただくほかありませんね!」
「そうだな。ケイルもダンカンもウチに来ればいつでもあの布団で寝られるぞ?」
「近衛騎士に無茶言うな……とは言え、また絶対来るからな」
「今度は彼女を連れてプライベートで来ますからね!」
会話はどんどん弾んでいく。
まるでこの名前の無い村が、探索者達で賑わっていたあの頃に戻ったかのように、仲間同士の友人同士の声は高く空にまで響いている。
きっとファレスが届けたい人達にもこの声は届いているのだろう。
日は大分傾き、優しい赤に包まれた森の中で俺はその花を見つけた。
「ピロテス……」
白く大きな花弁が垂れ、夕日に染っている。
「ん? ファレス、どうかしたか?」
急に立ち止まった俺を気にしてケイルが声をかけてきた。
「あ、ああ、いや……ピロテスが咲いているなと思って」
「……そういえばお前の宿もピロテスって名前だったな。なんか訳があるのか?」
そうか、そこの話は詳しく教えてなかったな。
「ああ、でも、それは今は良いんだ。それより、ちょっと寄り道してかないか?」
「寄り道? 俺は良いが……」
俺の提案を受け、ケイルが二人を振り返り確認する。
「俺も構わないですよ!」
「……どこへでも」
二人はすぐに頷き、同意を示してくれた。
「だってよ。じゃあ行こうぜ。その寄り道とやらに」
「ありがとう、悪いな。付き合わせて」
「水くせぇな……ほら、どこ行くんだよ?」
「すまん、こっちだ」
……あの日のことを考えるとどうもダメみたいだ。
だけど、この感傷も今日で乗り越えなくちゃならない。
日の沈んでいく西の空を見上げる。
いつまでも引きずってばかりじゃ、みんなにもあいつらにも合わせる顔がないよな。
気持ちを改めて、俺は目的地へ歩き出した。
◇◇◇
宿とは反対の方向に十数分ほど進んだその先。
その先が俺にとって最大のトラウマの場所だ。
「ここは……」
ケイルが一瞬息を飲むような声をだし、黙り込んだ。
「どうだ? いいところだろ?」
「……とても、綺麗ですね」
柔和に笑い、ネイロスはその景色に見とれている様だった。
森の中に突然、ぽっかりと空いた空間。
そこ一面に広がるのは美しいピロテスの花畑だ。
「ここが、ファレスさんの来たかった場所なんですか?」
景色に圧倒される二人を横目に見ていると、ダンカンがそう聞いてきた。
「ああ、十年前にも来たことがあるんだ」
「十年……そう言えばファレスさんは今おいくつなんですか?」
「今年で二十七になる年だよ。言葉にしてみると歳を取ったなって感じるな」
「そんなことないと思いますけど……というか二十七ってもしかして伝説の勇者と同じ学年ですか?」
……こいつ、何かに勘づいているのか?
もし、何かを察していたりするならばほんと……困るくらい優秀だな。
「ああ、そうだな。生きていれば、だけど」
勇者は戦死した。
俺が作りあげた存在しない記憶によりダンカンはそう思っているはず。
勘のいい彼に余計なことを言わないように、俺は自分からその話題に触れた。
「そうですね……。魔王を倒すくらい強かった勇者が戦死するって何が相手だったんですかね? それとも、魔王との戦いで手ひどい傷を負ったとか?」
「さぁ……どうだろうな。案外どこかで生き延びてるかもしれないぞ?」
「あはは! だったらいいですね」
冗談めかしてそんな風に言ってみた。
だが、ダンカンは存外本気でそれを願っている様子だ。
「? まあ、生きているに越したことはないが喜ぶほどか?」
「そりゃあ、そうですよ。だって、その方が人間味があるじゃないですか」
「人間味?」
「はい、確かに勇者はすごい人だと思いますし、尊敬もしますけど……その一方でどこか自分とは違うなって感じるところも多かったんです」
……語りだしたダンカンに俺は無言で続きを促す。
「だって、単身で魔族をどんどん討ち滅ぼして、終いには魔王まで討伐ですよ? まるで自分と同じ人間とは思えないというか……。だから、もし隠れて引退とかしててくれたら、ちょっと気持ちが分かるなって。……あはは、何真剣に語ってるんですかね俺」
……そうか。
そんな風に考える人もいるんだな。
これからも勇者であることを求め続けられることが耐えられそうになくて、引退をした。
だから、ダンカンのような考え方は俺にはとても新鮮に感じられた。
「いや、ありがとう。すごく嬉しいよ」
「え? なんでファレスさんが嬉しいんですか?」
「ははっ。なんでもないさ」
勇者も同じ人間だったら嬉しい……か。
立場を意識せず、無邪気にここで花を摘んでいた自分の姿が目に浮かび上がる。
確かにあの日は最悪だった。
でも、一人になる必要はなかったんだな。
ダンカンの何気ない言葉が、俺にそう思わせてくれた。
「おい、ファレス! 花冠作ったぞ!」
すると突然、花畑の中心でケイルが俺を呼んだ。
その手には第二近衛騎士隊副隊長が作ったとは思えないほど、出来のいい花冠が握られている。
「ははっ! 四十手前のおっさんが一人で花冠はきつすぎだろケイル!」
そう叫び返しながら、俺はケイルの方へ駆け出した。
ピロテスが象徴するのは永遠の愛。
だが、なにもその象徴する愛すべてが恋愛に関するものという訳ではない。
今日になってようやく、俺は自分のことを愛せるようになった気がした。
◇◇◇
「(なあ、ファレス)」
しばらく年甲斐もなくケイルとダンカンとはしゃぎまわり、疲れて休憩していたところにあの頭に声が響いてくる魔法でネイロスが話しかけて来た。
「(どうしたよ?)」
「(少しこっちへ来てくれ)」
「(ん? いいけど……)」
呼ばれた通り、二人から離れてネイロスのいるところまで歩いて行く。
「(それで、どうかしたのか?)」
「(ああ、お主にまた魔法を教えようと思ってな)」
「(魔法? また突然どうして?)」
「(まあ、そういう気分なのだ。少ししゃがんでみてくれ)」
花畑にしゃがみ、ピロテスに囲まれながらこちらを見上げるネイロス。
可憐ながらも美しく妖艶なその姿はさながら花の魔女とでも言えようか。
「(それで、どんな魔法なんだ?)」
隣にしゃがんで改めてそう聞く。
するとネイロスは足元のピロテスを数本摘んで手に乗せると魔法を発動した。
「(まあ、見ておれ。いくぞ〈光景の具象〉)」
ネイロスにしては珍しい、共用語での詠唱。その行為が意味するところは理解できなかったが、どことなく強い思いは伝わってきた。
ネイロスの手の中にある数本のピロテスに光が集まる。
その光は小さくなるもどんどん輝きを強めて収束し、形を成していく。
そして――
ネイロスの手のひらには、とても小さく精巧なピロテスの花飾りが付いた指輪が乗っていた。
「それは?」
魔法ではなく、声に出してそう聞く。
「この花畑があまりにも美しかったものでな。この景色を指輪に閉じ込めてみた。これをお主に送ろう」
するとネイロスも俺以外には聞こえない程度の声量で答えた。
「俺に? いいのか?」
ここの景色をよく気に入ってくれたことは伝わってくるが、こんなものを俺が貰ってしまっていいのだろうか。
そう思っていると、ネイロスが俺の空いている方の中指を指さした。
「前々から思っておったのだ。どうにも、その指輪が妾を牽制している、とな。だが、そんな妾の気分ひとつで外させる訳にもいかぬ。だから同じ土俵に立とうかと思ってな」
そういえば、初めて宿に来た日にもやたらに引っ掻いてきたっけ?
「……確かに猫の姿でうちに来た時からこの指輪に反応してたよな」
ミアから貰った指輪に触れる。
すると赤い宝石がミアの想いが込められているかのごとく煌々と輝いた。
「……やはりな。その指輪はお主と相手を強く繋いでおる。妾の方が近くにいるというのに。だから、お主は今日からその指輪を逆の中指に嵌めて過ごしてくれ」
繋いでいる?
魔法やその類には人一倍敏感な俺だが、この指輪からはそんな力は感じないのだが……。
まあ、害は無さそうだからなんでもいい。
「論理関係はよく分からないが……わかったよ。ありがとうネイロス」
そう言うとネイロスが一瞬、何かを期待するような顔でこちらを見た。
もちろん、それを見逃す俺でも、それの意味が分からない俺でもない。
周りから一際美しく咲きほこるピロテスを数本手折り、その魔法を発動した。
「〈光景の具象〉」
さっき見た魔法を完璧に模倣し、ネイロスが俺に作ってくれたものより、一回り胴が小さいピロテスの指輪を生み出した。
「これでいいか?」
「うむ! これでいつでもミアとやらに会えるわ!」
指輪を渡すと早速自分も右の中指に嵌めている。
「……喜んでくれたのなら良かったよ」
この指輪がそんな意味を持つのか、ネイロスが何を含んで言ったのかそれは俺には関係ない。ただ、ネイロスの願いが叶えられていたら良いとそう思った。
そんな二人を遠目に見る騎士が二人。
どこか寂しそうな顔でダンカンが呟く。
「あの、副隊長。俺に勝ち目って……」
「ねぇな。断言してやる」
可哀想な犬のような顔で話すダンカンをケイルはバッサリと切り捨てた。
「せめて慰めてくださいよぉ……」
「いいじゃねえか、ダンカン。男は失恋で強くなるもんだ」
「そういうもんですかね……」
「ああ、そうやってあいつも強くなったらしいぞ」
「? 誰のことですか?」
「ははっ、なんでもねえ」
「?」
ダンカンが疑問を含んだ視線をケイルに向ける中、そのケイルの視界にはあの日旅立って行った最強の青年が映っていた。
◇◇◇
「いや〜久しぶりに楽しかったな」
宿に帰ってきて四人で食卓を囲みながら、誰からともなくそんな声が漏れ出る。
「ほんと、お二人の戦闘力には驚かされましたけどね」
ダンカンはダンジョンでの戦闘に相当衝撃を受けたみたいだ。でも、その顔は圧倒的な実力を見て怖気付いてしまった訳ではなさそうだ。
むしろ――
「ダンカン、お前もまだまだ精進しろよ?」
「そうですね。正直今回の任務での一番の収穫はそれかもしれないです」
ケイルの冗談交じりの檄に真面目に答えるダンカン。
彼は間違いなく強くなるだろう。
そう確信できる表情だった。
「お二人の任務は調査では?」
「調査もしましたが、この辺りは支援の必要がないほど修繕されていますし、辺りに脅威となる魔物の存在も確認できませんでした。それにお強い二人がいるのなら余計な心配をする必要もありませんしね」
ネイロスのツッコミにもダンカンは丁寧に対応した。
しかし、その対応には少し前までのネイロスを意識したような感情は見えず、真面目に仕事に打ち込む騎士道だけが残っているように思われた。
どうやら本当に大きな収穫になったようだ。
この若さでこれほどの成長性、ケイルが気に入るのもよくわかる。
そんなことを考えながらケイルに話を振った。
「あと数日で戻るんだったか?」
「ああ、一瞬で時間が過ぎたな……」
「ここのベッドともついにお別れですか……。帰りの野営がキツそうです」
「弱音を吐くな、と言いたいところだが、さすがの俺も当分はキツそうだな」
「ふふっ、ではまた来ていただくほかありませんね!」
「そうだな。ケイルもダンカンもウチに来ればいつでもあの布団で寝られるぞ?」
「近衛騎士に無茶言うな……とは言え、また絶対来るからな」
「今度は彼女を連れてプライベートで来ますからね!」
会話はどんどん弾んでいく。
まるでこの名前の無い村が、探索者達で賑わっていたあの頃に戻ったかのように、仲間同士の友人同士の声は高く空にまで響いている。
きっとファレスが届けたい人達にもこの声は届いているのだろう。